
中城正堯(30回)
 細木志雄(2回) 細木大麓(27回) 岡林幹雄(27回)
鍋島高明(30回) 横山禎夫(30回) 西内一(30回)他
細木志雄(2回) 細木大麓(27回) 岡林幹雄(27回)
鍋島高明(30回) 横山禎夫(30回) 西内一(30回)他
●タイトルをクリックすると最新ページへジャンプします。
●画像にマウスポインターを置くと画像が拡大されます。全体像が見れない場合マウス中央のスクロールボタン(ホイール)か、マウスポインターを画像に載せたまま方向キー(←→↓↑)を使ってスクロールしてください。
| 2010.04.08 | 中城正堯(30回) | なんで今ごろ報恩感謝 |
| 2010.07.31 | 中城正堯(30回) | 学校再建と民主化への熱気伝える |
| 2010.10.17 | 中城正堯(30回) | 猫の皮事件とスト事件のなぞ |
| 2011.04.22 | 中城正堯(30回) | 海辺から龍馬の実像を発掘 |
| 2011.08.10 | 中城正堯(30回) | 展覧会と講座のご案内 |
| 2012.04.15 | 中城正堯(30回) | 龍馬「愚童伝説」から学びの原点をさぐる |
| 2014.05.31 | 中城正堯(30回) | 『江戸時代子ども遊び大事典』と中国版画展の反響 |
| 2014.12.01 | 中城正堯(30回) | 『高知城「御築城記」とその後の穴太衆』と『NHK番組紹介』 |
| 2015.05.21 | 中城正堯(30回) | 身辺整理に専念します |
| 2015.05.28 | 中城正堯(30回) | 龍馬最後の帰郷と種崎潜伏 |
| 2015.08.15 | 中城正堯(30回) | 校歌の謎1への回答 |
| 2016.02.28 | 中城正堯(30回) | 20世紀美術の先端を駆け抜けたアーティスト |
| 2016.04.16 | 中城正堯(30回) | 『新聞とネット、主役交代が鮮明に』への感想 |
| 2016.08.25 | 中城正堯(30回) | 浦戸城趾に"元親やぐら"を |
| 2016.09.23 | 中城正堯(30回) | 「公文禎子先生お別れ会」のご報告 |
| 2017.03.25 | 中城正堯(30回) | 三根圓次郎校長とチャイコフスキー |
| 2017.05.22 | 中城正堯(30回) | 生首を化粧した武士の娘 |
| 2017.07.10 | 中城正堯(30回) | 「土佐中初代校長の音楽愛」と、高知新聞が紹介 |
| 2017.08.20 | 中城正堯(30回) | 「“上方わらべ歌絵本”の研究」 |
| 2017.10.03 | 中城正堯(30回) | 「“上方わらべ歌絵本”の研究」 |
| 2017.10.10 | 中城正堯(30回) | 「浮世絵にみる子どもたちの文明開化」 |
| 2017.10.20 | 中城正堯(30回) | 『SAWAKOGODA合田佐和子光へ向かう旅』刊行 |
| 2018.01.02 | 中城正堯(30回) | 中国版画・中城コレクション |
| 2018.03.25 | 中城正堯(30回) | 母校出身“素顔のアーティスト” |
| 2018.04.25 | 中城正堯(30回) | 母校出身“素顔のアーティスト”に嬉しい反響 |
| 2018.05.03 | 中城正堯(30回) | 焼け跡で誕生した前衛アートの女神合田佐和子(34回) |
| 2018.05.27 | 中城正堯(30回) | 焼け跡で誕生した前衛アートの女神合田佐和子(34回) |
| 2018.06.07 | 中城正堯(30回) | 大地のエネルギーを絵筆で歌う田島征彦・征三兄弟(34回) |
| 2018.06.24 | 中城正堯(30回) | 大地のエネルギーを絵筆で歌う田島征彦・征三兄弟(34回) |
| 2018.06.28 | 中城正堯(30回) | 名編集長:大町“玄ちゃん”(30回)を偲んで |
| 2018.07.08 | 中城正堯(30回) | 凄絶なホラー作家にして酒豪、坂東眞砂子(51回) |
| 2018.07.22 | 中城正堯(30回) | 凄絶なホラー作家にして酒豪、坂東眞砂子(51回) |
| 2018.07.28 | 中城正堯(30回) | 合田や田島兄弟が新聞で話題に |
| 2018.08.11 | 中城正堯(30回) | 音楽・演劇から前衛美術まで個性派揃い |
| 2018.09.02 | 中城正堯(30回) | 回想浮世絵との出会いと子ども文化研究 |
| 2018.11.25 | 中城正堯(30回) | 土佐中での出会いから生まれた浮世絵コレクション |
| 2018.12.23 | 中城正堯(30回) | なぞの名所絵版画「播州石宝殿」と巨石文化 |
| 2018.12.25 | 中城正堯(30回) | 石の宝殿への反響---高砂市教育委員会より |
| 2019.01.10 | 中城正堯(30回) | 福を呼ぶ「金のなる木」や「七福神」 |
| 2019.01.20 | 中城正堯(30回) | 美しき養蚕神に秘められた少女たちの哀話 |
| 2019.02.17 | 中城正堯(30回) | 和製ポロ“打毬”を楽しんだ江戸の子ども |
| 2019.03.23 | 中城正堯(30回) | 布袋と美女のそっくり版画から“おんぶ文化”再考 |
| 2019.03.31 | 中城正堯(30回) | 「布袋と美女、おんぶ文化」について |
| 2019.07.02 | 中城正堯(30回) | 惜しまれるフレスコ画研究の中断 |
| 2019.07.15 | 中城正堯(30回) | 合田佐和子展 -友人とともに- |
| 2019.12.23 | 中城正堯(30回) | ジャーナリスト魂を貫き新聞協会賞 |
| 2020.03.07 | 中城正堯(30回) | 花だより |
| 2020.03.22 | 中城正堯(30回) | 「破天荒・感涙のサハラ!」と話題 |
| 2020.04.14 | 中城正堯(30回) | 庭のエビネが咲きました |
| 2020.04.29 | 中城正堯(30回) | 「リバプールと奴隷産業」を読んで--2 |
| 2020.07.16 | 中城正堯(30回) | 『綴る女』をめぐる変奏曲 |
| 2020.07.16 | 中城正堯(30回) | 「大江戸もののけ物語」の不思議な寺子屋 |
| 2020.08.14 | 中城正堯(30回) | 土佐藩御船頭の資料を展示 |
| 2020.08.27 | 中城正堯(30回) | 「ジョニ黒」ことはじめ |
| 2020.09.10 | 中城正堯(30回) | 高知でのコレラに関する歴史 |
| 2020.09.24 | 中城正堯(30回) | 「日曜美術館」 画家・田島征三さん |
| 2020.10.08 | 中城正堯(30回) | ハチ公とボビー、忠犬たちを仲介して |
| 2021.01.15 | 中城正堯(30回) | コロナ禍乗り越えベストセラーに |
| 2021.01.15 | 中城正堯(30回) | -親しめる『土佐中高100年の歩み』を創ろう- |
| 2021.03.15 | 中城正堯(30回) | 田島征彦展のお知らせ |
| 2021.05.10 | 中城正堯(30回) | 母校を熱愛した新聞部の“野球記者” |
| 2021.08.09 | 中城正堯(30回) | サンペイさん追憶!出会いと土佐の旅 |
| 2021.09.10 | 中城正堯(30回) | 江戸子ども文化論集への反響 |
| 2021.09.19 | 中城正堯(30回) | 香料列島モルッカ諸島 |
| 2021.10.15 | 中城正堯(30回) | ヒマラヤ南麓の愛しき稲作民 |
| 2021.10.23 | 中城正堯(30回) | 「ヨーロッパの木造建築」を楽しむ |
| 2021.11.04 | 中城正堯(30回) | ナポレオン3世皇妃と幕末狩野派 |
| 2021.11.26 | 中城正堯(30回) | 巨大な木造“王の家”そびえ立つニアス島 |
| 2021.12.15 | 中城正堯(30回) | ―“生意気な女”か“近代女性の先駆け”か― |
| 2022.02.22 | 中城正堯(30回) | ―写真と挿絵が語りかけるもの― |
| 2022.05.15 | 中城正堯(30回) | <同窓生アーティストの近況> |
| 2022.07.05 | 中城正堯(30回) | 「文明開化の子どもたち」展 |
| 2022.09.05 | 中城正堯(30回) | 「田島征三アートのぼうけん展」 「いのちのケハイ とわちゃんとシナイモツゴの物語」 「特別展アリス へんてこりん、へんてこりんな世界」 |
| 2022.09.30 | 中城正堯(30回) | 武市功君(30回生)逝去のお知らせ |
なんで今ごろ報恩感謝
昨年(2000年)6月に『土佐中・高創立80周年記念誌』に、在校当時の思い出やこれからの土佐のあり方に関して何か書くよう浅井伴泰君から電話があり、学校の編集委員会からも依頼状が届いた。そこで「世界へ人材送る学校に」という題で、建学の精神が人材育成から報恩感謝にすり変わっている問題を指摘するとともに、海外の大学へ進学できるコースの新設をよびかけた。ここでは、建学の精神にしぼって、設立当時の資料をもとに私見を述べておきたい。
建学の精神は何だったのか
2001年版の土佐中・高「学校案内」を見ると、相変わらず大きな文字で「報恩感謝の理念のもと社会に貢献する人材を育成することを建学の精神として創立されました」とある。また、80周年記念の高知新聞広告特集の「企画書」には「開校以来、報恩感謝の校是と文武両道の教育方員を掲げ」とある。幸い上村浩君が司会してくれたこの特集の座談会では「土佐中・高は学業もスポーツも、そして文化活動もという『文武両道』の校風のもと、個性豊かな人材を育て上げてきた」と述べてあり、報恩感謝など出てこない。文武両道は、校歌四番「それ右文と尚武こそ」に由来し、問題ない。
では、そもそも土佐中の創設の理念、建学の精神は、どう謳われてきただろう。いつから「報恩感謝」などという矮小化が始まったのだろう。
最も古い記録として、大正8年11月2日の『土陽新聞』記事がある。「土佐中学校創立目論見」の見出しで、「予科として小学五六年級を添附し七学級を置く」「一学年二十五人を限度とし俊秀者を集め無資力者は之に給費す」「学校全体を家庭的とし寄宿舎を設け成るべく全生徒を寄宿せしめ生徒をして田園生活に趣味を起さしむ」「職員以下小使に至る迄都て俊秀教育に趣味を有するものを選抜起用」とある。これは、初代校長三根円次郎着任以前だが、俊秀教育すなわち英才教育をめざし、その賛同者しか雇用しないと述べている。「生徒をして田園生活に趣味」というのも、時代を先取りしており、校舎・寄宿舎とも実際梅が辻の田圃のなかに建てられた。さらに、創立者である宇田友四郎、川崎幾三郎の伝記にも「国家有為の人材を養成することが其の目的」と明記してある。人材教育、英才教育という言葉も使われているが、報恩感謝は出てこない。『近代高知県教育史』にも、「英才教育を目的として大正九年二月に設立」とある。
初代三根校長の教育理念
では、初代校長三根円次郎の掲げた教育理念と教育方針をみてみよう。昭和五年の学校要覧には、設立趣意書が載せてあり「高等教育ヲ受クルニ十分ナル基礎教育二力ヲ致シ修業後ハ進デ上級学校二向ヒ他日国家ノ翅望スル人士ノ輩出ヲ期スルモノナリ」とある。やはり建学の目的は「国家有為の人材育成」であり、教育方針は「個人指導」「自発的修養」「自学自習」「自治」等となっている。生徒一人ひとりの個性と自律性を尊重しつつ入材の育成をめざす、画期的な教育であった。これは、当時東京府立一中校長川田正徴とともに、大正デモクラシー時代の全国中学教育をリードした三根校長ならではの方針だ。報恩感謝の言葉などはここにもない。わずかに、美文で知られた大町桂月が父兄の依頼で選文した「開校記念碑文」の中に、宇田・川崎二氏をたたえて「国家に尽すは二氏の恩に報ずる也」とあるにすぎない。
川田校長をちょっと紹介しておくと、高知県出身で府立一中校長として中等教育界に君臨し、宇田・川崎二氏への三根校長紹介者でもあった。大正二年四月から、一年二か月にわたって欧米の教育事情視察に出かけ、イギリスのイートン校、ハーロー校に感銘をうけ、府立一中を「生徒が自分の行動に責任を持ち、生活に責任をもち、しかも紳士的で、未来を背負う人材をつくる学校にしよう」(『日比谷高校百年史』)とした。一中から日比谷高へ続く自由闊達な校風を築いた名校長であった。
この川田校長の最良の同志が、帝国大学(東大)哲学科出身で「有志全国中学校長会」会長の任にあった山形中学校長三根円次郎であった。三根が会長として起案した「中学教育上(第一次)大戦後特に注意すべき事項」には、すでに「自学自習の気風を馴致すること」「個性教育に重きを置くこと」がうたってある(『山形東高等学校百年史』)。三根の教育者としての信念を示すエピソードは、大正七年に赴任した新潟中学でのスト事件である。赴任直後に新潟高校の新設が決まり、三根は進学準備の特別授業を始める。ところが反発した生徒が同盟休校をおこし、退学者が出る。その後、大正九年に人望を回復しないまま、土佐へ行く。ところが後になって、「実はこの退学生徒の転学先について、何日もかけて県内各地の中学を回り、熱心に奔走したのは三根校長自身だった」ことが判明する(『新潟高校百年史』)。土佐中時代も、失明しながらも卒業生の大学での学業、就職先から左翼運動とのかかわりまで案じ、さまざまな救いの手をそっとさし伸べている。生徒達に「報恩感謝」の念を強要するような姿勢は、微塵もない。
三根校長の先見性や、グローバルな感性は制服でも見られる。一回生の森岡清三郎先輩は、こう述べている。「制服が出来るということになり、東京府立一中の型、ネクタイ折襟のものを中沢に着せた。これはよいと喜んでいたが、きめられた制服はつめ襟で、皆がっかりした」(『創立五十周年記念誌』)。背広は値段が学生服の倍かかるため、やむをえず断念、霜降りの詰め襟学生服になった。日本の学校での制服は、明治12年に学習院が海軍士官型の制服を導入したのに始まり、軍国主義とともに広く普及した。襟の白線も軍の階級章をまねたものだ。土佐中では、二代青木勘校長が前任校の愛知一中にならい、他校との差別化のために導入した。挙手の礼など軍事教錬の強化に反対、配属将校との激論がもとで急逝したと伝えられる三根校長なら考えられないことだ。国際化時代のいま、黒い学生服に白線は全く陳腐だ。三根校長の当初の意図どおりの背広に、早急に変更すべきではないだろうか。
21世紀を迎え活発な議論を
話を戻すと、土佐中・高の歩みの中で「報恩感謝」を強調したのは、われわれが在籍した三代大嶋光次校長時代である。クラス名のHOKSも、報恩感謝に由来する。しかし、宇田・川崎両家や、父母の恩への感謝を説いても、建学の精神が報恩感謝とはいっていない。四代曽我部清澄、五代松浦勲両校長はともに母校出身だけに、きちんと建学の精神はおさえていた。曽我部校長は、創立五十周年の式典で「本校教育の基底をなす〈人材育成〉とい う根本理念は創立以来今も変わりございません」と述べている。もとより、建学の精神が時代に合わなくなれば、新しく校是や教育理念を制定するのは可能であり、非難すべきではない。しかし、建学の精神は勝手に変更できるものでないし、土佐中に関してはその必要もない。それに、今ごろ「報恩感謝」を持ち出すセンスが理解できない。この言葉にあこがれて生徒が応募するとは、とうてい考えられない。現在の校長は大嶋校長同様に母校出身ではないが、教頭以下母校出身の教職員は数多くいる。理事会や同窓会ともども、なぜ問題提起しないのか、不思議である。私学をめぐる経営環境が厳しさを増すなか、魅力ある教育理念を社会にきちんとアピールし、学内が一致してその実践に当たらねば生き残れないことは、いうまでもない。今一度、大正八年の「土佐中学校創立目録見」はじめ、設立当時の文献を全職員で読み返してほしい。また、報恩感謝がそんなに重要なら、学校が範を示し、学校案内や同窓会名簿などで、広く創立者・初代校長の人柄、教育理念を知らすべきだろう。御遺族との連絡も密にすべきだ。ところが名簿一つとっても、初代校長の御遺族すら空欄のままである。御次男は健在であり、80周年式典には当然御招待すべきであった。公文先生の御遺族も記載がない。恩師の御名前のミスも目立つ。これで報恩が校是などといえるだろうか。 最後に、建学の精神がきちんと伝わってない主要な原因に、創立八十周年を迎えながら、いまだに学校史が編纂されていないことがあげられる。これでは、母校への誇りを確かなものにすることも、大正自由教育における母校の素晴らしい実践例を教育史にとどめることもできない。学校当局が早急に対応するとともに、このような問題に関しての校内職員の積極的な議論を期待したい。
学校再建と民主化への熱気伝える
『新聞向陽』の名で学校新聞が創刊されたのは、戦後の新学制により昭和22年に新制土佐中、翌年に新制土佐高校がスタートして間もない24年3月であった。翌25年には早くも第6号を刊行、紙面も従来のタプロイド版から一般紙のサイズとなり、第9号から『向陽新聞』と改題する。当時、旧制土佐中は戦火で校舎を焼失、川崎・宇田ご両家からの多額の拠金も戦後インフレで価値をなくし、廃校の危機に立たされながら、三代校長・大嶋光次のもとで人材育成という建学の精神を日本再建に結びつけようと、懸命の努力を続けていた。この連載では、戦後の母校発展の跡を『向陽新聞』の紙面からさぐってみたい。(文中敬称省略)
創刊のいきさつと紙面
戦前は教育も国家統制のもとで皇民教育や軍事教練が強制されたが、戦後は米軍の占領下で教育の民主化がはかられた。六三制で中学までが義務教育になり、男女共学が打ち出された。大嶋校長は他の私学にさきがけてこの潮流を読み取り、中高一貫の男女共学に転換、定員も大増員に踏み切った。学園民主化の柱としては生徒会の設置と、生徒の自由参加によるクラブ活動(部活)の奨励があった。部活の中でも新聞部は、生徒の自主的な報道言論機関として学園民主化の重要な役割を担うこととなった。
敗戦時の土佐中生は県内各地で集団生活をしており、山崎和孝(26回)など1年生は高岡郡尾川村にいた。やがて高知市池の浦戸航空隊跡(現・高知女子大や高知医療センター)から兵舎の払い下げを受け、生徒一同も協力して運び、なんとか仮校舎を建てた。それと同時に部活が始まり、野球部・園芸部・文芸部・絵画部など続々誕生した。高1になった山崎が同級の西原道夫たちと新聞部創設を考えていた頃、中3の細木大麓・岩谷清水・岡林幹雄(27回)も同じ思いであることが分かり、一緒になって結成した。
創刊号のトップ記事は「創刊に際して 大嶋光次」である。校長は日本再建に教育の民主化が重要なことや、個人の自由・学徒の意志反映による学園の明朗化、自治会の強化に触れつつ、「新聞向陽の発行の議が起り全生徒から自由に責任ある投稿を募って一般に紹介…せんとする事は確かに学園民主化の一方法であると信じて疑わないが、新聞は社会の報道機関であるとともに其の属する社会の指導機関でもあるという責任を忘れてはならない」と述べている。隣に「救い難い敗戦気分」の記事があるのも時代の反映である。
論説は「学校生活に活気をもたせよ」で中3細木大麓、コラム「ひとりごと」は高1山崎で「高知女高(現丸の内高)と高知高(現追手前高)の自治会が二校合併を陳情」などの秘話が出ている。中2酒井芳美のエッセイ「小さきもの」には、早熟ぶりがうかがえる。高1山村泰造は「プロ野球展望」を堂々と論じている。「詩と俳句」から「笑話」まで掲載され、報道論説と文芸の総合紙であり、イリキ眼鏡店や哲学の店・田所文具店など、広告もしっかり集めてある。
昭和24年7月発行・第3号のトップは、「苦心の結晶われらの新校舎遂に落成」である。木造二階建新校舎落成式から、感銘深い挨拶として「時代の波にのれ そしておぼれるな」という、阿部孝旧制高知高校長の言葉を紹介している。落成式で表彰された町田義隆氏(工務店主)は「バラックを兵営跡から持ってくるのに走り回り、木材を手に入れるために大栃の営林署に校長と行った」と、さらっと語っている。後に掛水俊彦(24回)は、「大工の棟梁の姿で連日采配をふるった町田さんこそ隠れた功労者」と述べている。阿部の名言や隠れた功労者をきちんと取上げたのは、当時の編集者の見識であろう。また、国立大学設置法案反対の風潮に流されてストに突入した生徒会の「苦い経験」への反省記事もある。筆者も入学間もない頃、教室に先輩が来てアジ演説をした光景を覚えている。
学校ジャーナリズムの開花
昭和25年頃に新聞部で大活躍をしたのが岩谷清水であり、山崎は「彼はジャーナリズムのセンスに充ち、校内の事件を拾ってきてはジャーナリスティックに取り上げた。生徒会と学校が対立したときに大記事を書いてきたが、大議論の末に少し控えめに紙面を割付けた。これが高知新聞記者の目にとまり、<この小さい扱いは何事だ。学校新聞は学校の問題を掘り下げるのが使命だ>と厳しく指導をうけた」と、述懐している。この指摘は、次第に新聞部のバックボーンとして受け継がれていく。
創立者たちに続き、安部弥太郎(28回)や中山剛吉(29回)、さらに30回の多彩な部員が伝統を引き継ぐ。第8号からは林寛(28回・通称リンカーン)作の連載マンガ「向陽君」も始まる。安部が編集人の第11号トップは「伸びゆく本校女性徒たち」で、女子高生151名への新聞部調査から「受験先は薬学・医学が多数、将来結婚しない者26名、本校男子は不親切で利己的」など、女生徒のホンネを引き出している。「主張」(論説)も「女生徒の自覚と男生徒」と題して、5年目を迎えた男女共学を成功させる道をさぐり、さらに校外から婦人少年局高知職員室森沢女史の談話取材も行っている。二面トップの「上位を占める全面講和」は、社研部による講和問題への高校生の意識調査で、政治問題にも果敢にいどんでいる。愛称パン子ちゃんで親しまれた英語・池田起巳子先生のアメリカ招待留学決定も報じられ、やがて「アメリカだより」が登場する。
中山編集人の第12号トップは「座談会 生徒のための生徒会」だが、「生徒会活動は民主生活の第一歩」と論じ、別項の中学生徒会の活動では通称「オンカン道路」(梅ヶ辻から学校まで、中山駸馬先生の愛称)の交通整理に取り組むことなどが報告されている。美術部と新聞部共催の「校内展」開催と入賞者を東京に派遣する企画もあり、鎮西忠行先生の「東京へはだれがゆく?」を掲載している。県下を制覇した中学野球部の富田俊夫先生は「栄光への道をうち進まん」と檄文を執筆している。この頃、文化部・運動部とも大躍進をとげつつあった。堀詰座や高知中央公民館で開催された芸能発表会では、高塚準一郎の「俊寛」、西内総一郎(北村総一朗)の「煩悩無安(平維盛)」などが市民の間でも話題になった。北村が後に大活躍する素地は、この頃から培われていた。
大町玄編集人(30回)の第15号は、「新生日本の出発に当たって」がトップ記事で、昭和27年4月の講和条約発効に当たっての大嶋校長メッセージを掲載している。この号には、山崎・岩谷など新聞部先輩による東京支局開設が報じられ、早速「先輩訪問記」で東京同窓会の世話役を務めてきた同学社近藤久寿治社長の探訪記が載っており、独力で出版社を起こした経緯や後輩への期待が述べられている。千原宏編集人(30回)の同年11月第17号は、トップに「全校舎ついに完成 これから内容の充実だ」の文字が踊っている。開校33周年・本館落成に合わせて、「開校記念碑文」の再評価を呼びかける記事も出ている。
学校・新聞の躍進と課題
昭和20年代後半の新聞部にとっては、文化事業の展開も忘れることが出来ない。27年には応援歌を募集、河野伴香先生の詩が入選し平井康三郎(5回)の作曲で、後に甲子園にも響き渡る「青春、わかき、血潮はたぎる…」が誕生した。これに戦前からの校歌・向陽寮歌、創立三十周年記念歌を加えた「土佐中高 歌のアルバム」も29年の講堂落成記念に刊行した。同年「四国四県高等学校弁論大会」を開き、30年からは「先輩大学生に聞く会」を開始、31年には「小学館全国児童生徒図画作品展」を中央公民館で開催した。
昭和27年にはスポーツ新聞『向陽スポーツ』も刊行、28年には前年に続く春のセンバツ野球出場に取材記者を特派、夏には甲子園準優勝で湧く。翌29年には軟式テニスも全国優勝をとげた。向陽新聞も高い評価をいただき、29年7月には第4回高校新聞指導教官講習会で、「高二Sホーム 生徒会廃止案提出」「英語に化けたホームルーム」を扱った第22号が全国優秀五紙の一つに選ばれた。新聞部出身者と、新聞出版関係に従事する卒業生によって「向陽プレスクラブ」も結成された。33年の大嶋校長逝去の際には号外も発行された。
しかし校舎が完成し、進学での名声が定着、野球などクラブ活動が全盛を迎えるとともに、校内にはさまざまな「ゆるみ・ゆがみ」が生じ始めていた。やがて中学入試問題の漏洩と同盟休校という大事件が発生し、新聞部も真価が問われることになる。(以下次号)
<補記>創刊当時の事情については山崎和孝さんからメモをいただいたが、字数に限度があって十分には活用できなかった。いずれ、山崎・細木の両先輩から、このHPに寄稿いただきたい。また、占領下ならではの記事としては、第11号に「総司令部新聞出版課長インポデン中佐と安部新聞部長が懇談」とあるが、これも割愛した。昭和20年代の向陽新聞には、占領から独立への時代に揺れ動く戦後社会を反映した貴重な学園生活の記録が残されている。向陽プレスクラブの準備会によって向陽新聞バックナンバーの電子化が進んでいるので、ぜひこれらの記事を活用いただきたい。また、記事に出来ず胸の奥にしまい込んだままの事件も、いずれ紙面の背後から浮かび上がらせたい。(中城記) ―三根校長のエピソードを探る―
猫の皮事件とスト事件のなぞ
二十年ほど前、くもん出版にいた時だが宮地貫一先輩(21回生・現土佐中高理事長)から、『三根先生追悼誌』(昭和18年 土佐中学校同窓会発行)を復刻したいとのお話があり、出入りの印刷社でやってもらった。この本は、三根円次郎校長の人物や教育方針を知るにとどまらず、土佐中創立当時の学校の実態や師弟関係を如実に示す貴重な記録でもある。この復刻作業を進めるなかで不思議に思ったのが、細木志雄大先輩(2回生)の追悼文「三根先生の追憶」に出てくる以下の事件である。
「先生について私が最も嬉しくかつ力強く感じたのは山形中学校長時代の猫の皮事件、新潟中学校長時代のストライキ事件等に見られる先生の稜々たる気骨である。信ずる所に向って勇敢に突入される態度、威武を怖れず、権門に屈せず、かりそめにも阿諛迎合されない気概、さらに事に当たっていささかも動じない肚(はら)、そこに先生の偉大さを痛感した」
この二つの事件については、追悼誌の中の「三根先生を偲ぶ座談会」でも細木大先輩がさらに詳しく語っているが、伝聞であり事実かどうか確認がされてないと注記してある。そこで、山形・新潟双方の知人に調査を依頼した。その結果は28回生が編集発行した『くろしお 第四集』に概要のみ報告したが、補足を加えて再度明らかにしておきたい。なお、問題提起された細木志雄大先輩は、向陽新聞創刊メンバーのお一人である細木大麓さん(27回生)の父上で、東京大学農学部を卒業、戦後は高知県出納長などの要職に就き、土佐中高同窓会副会長でもあった。筆者が新聞部当時には、何度かインタビューに応じてくださった。向陽新聞10号・17号・21号に登場いただいている。
山形中学での猫の皮事件
まず、座談会(昭和16年に東京で開催)での細木大先輩の発言を、全文紹介しよう。
「あの添田敬一郎氏ね、あの人が山形県の知事時代に先生は山形の中学の校長だったのですネ。その中学へは添田さん以前の知事は卒業式には金ピカの服を着て出たそうです。ところが添田さんは背広で、しかもチョッキは毛皮だったのですネ。それで生徒達は学校を馬鹿にしているというので憤慨して、終了後知事が帰ろうとして玄関に出てみると白い模造紙に漫画を書いて、それに『添田猫の皮』という註が書いてあったそうです。(笑声)それを見て知事が憤慨して誰がこういうものを書いたのか調べて処分しろというのだそうです。ところが校長自身も生徒の気持ちがよく判かるし、無理がないという気持ちがしたのでしょう、処分も別にしなかったのですネ。知事は怒って校長をとうとう九州のたしか佐賀県の中学と思いますが、そこへ追い出してしまったということを聴いたことがあります」
「あの添田敬一郎…」とあるように、添田は当時著名な人物で、東大から内務省に進み、埼玉・山梨の知事を経て大正5年4月に山形県知事に就任、翌年12月に内務省地方局長に転じている。その後政治家となり、衆議院議員に当選7回、民政党政調会長を務め、第二次世界大戦の頃には産業報国運動や翼政会で活躍した。
猫の皮事件については、山形大教育学部の石島康男教授に調査を依頼した。程なく、山形中の後身校が刊行した『山形東高等学校百年史』などの資料が送られてきた。それによると、三根円次郎の第16代山形中学校長就任は大正2年1月、辞任は大正7年3月であり、その任期中の業績は「大正デモクラシーの中に」と題して記述してある。まず、経歴を述べてあり、明治30年に帝国大学文科大学哲学科を卒業した直後に修身・英語教師として山形中学に赴任、その後佐賀中学・徳島中学の校長を経て、39歳で再度山形中に今度は校長として着任とある。教育方針は「質実剛健の気風の中に自由闊達の精神を生徒に教え」、大正期における山中の気風が確立したとする。また、上級学校への進学を推奨し、山形の山中から日本の山中への脱皮を計ったともある。同時に学年別にコース(距離)を設定した全校マラソンを導入した。生徒は、校長の風貌を「眼光鋭く長髪をたくわえ、フロックコート姿の短身」「厳粛そのもの」と語っている。
ただ、猫の皮事件は公式の記録には見あたらない。勅任官待遇を受け、絶大な権力を持つ当時の知事への批判的事件を活字にする事ははばかられたのだろう。しかし状況は符合する。添田山形県知事は大正5年4月に着任しており、猫の皮事件は大正6年3月の卒業式での出来事だろう。同年12月には離任し、内務省地方局長に就任している。この翌年に、三根校長は九州ではなく新潟中学校長に転じている。知事の転任が先で、校長の転校も懲罰人事ではあるまい。ただ、表沙汰になる事はなかったものの、知事の教育軽視へ反発した生徒による風刺漫画が、知事の大人気ない態度と、三根校長の権威に屈しない姿勢を鮮明に対比させ、土佐中にまで語り伝えられたと思われる。
新潟中学ストライキ事件
細木大先輩は、同じ座談会でさらにこう述べている。
「新潟中学時代にストライキが起こって、それからしばらく校長が行方不明になったのですネ。どこへ行ったか判らんというので大騒ぎをしたのです。そうしたら新潟県の地方の中学を回ってストライキ騒ぎで処分した生徒の転校先について話をまとめてきたというのです。つまり校長はストライキを起こしたについて痛烈な訓辞をやって無期停学の処分をして置いてから、それから行方不明になったのだが、それはその処分された生徒の転校先について地方の中学へ交渉しに回っていたというのですネ。」
これを受けて都築宏明先輩(3回)は、「そういう点は土佐中学でも随分ありましたねェ。少し成績の悪い生徒に落第させないように他の学校への面倒を見たり…、他所へ行って優秀になったのが大分ありましたョ」
ストライキ事件については、新潟日報編集局の佐藤勝則氏の手をわずらわした。こちらは『新潟高校100年史』に、以下のようにきちんと記録されていた。大正7年4月に第11代校長として着任、「小柄で黒い髭をたくわえ、眼光鋭く、人を畏怖せしめる風貌を持ち、言辞も明晰で理路整然、修身の時間ともなれば、クラス全員緊張し、さすがの腕白どもも粛然として高遠な哲理を承った」とある。昼食には五年生を三名ずつ呼び、「一緒に弁当を食べつつ、生徒の身上・志望を聴取し、その志望に対しては適切な指導をするというきめ細かな一面を持っていた」が、近寄りがたい人物とも見られていた。それは、「眼病のためにほとんど失明寸前の状態にあったのだ。そのため、…生徒に挨拶されても気がつかず返礼を欠くことが多かった。だから生徒は、校長を<冷淡で傲慢な人物>と思い込んだのである」。眼病故の誤解が生じていたのだ。
この大正7年5月に新潟高校(旧制高校)の設置が決まると、新潟中学では入試準備の特別授業や模擬試験に忙殺されることになった。このような中で、6月18日に同盟休校が起こり、四、五年生の大部分が欠席した。理由書には「運動会の応援旗禁止」「処罰厳に過ぎる」などとあったが、実際は運動会後に生徒のみで慰労会を開いたことが発覚したので、その処分に対して生徒たちが先手を打ったとされる。さらに「強まる受験体制への不満、英才教育を掲げる三根校長への反発」もあったが、生徒側の根拠薄弱と100年史には述べてある。そして、中心生徒2名退学、2名無期停学などの処分が決まった。
三根校長は大正9年1月に新潟中を辞任し、土佐中学の初代校長に迎えられる。大正10年の新潟中学30周年には祝辞を寄せたが、100年史にはこう紹介してある。「<私は貴校歴代校長の中で最も不人望で生徒に嫌われ、ついに排斥のストライキを受けた>と語り、しかし<卒業生や県当局の斡旋によって多数の犠牲者を出さずに解決できた>として感謝の意を表している。実は退学生徒の転学先について、何日もかけて県内各地を回り、熱心に奔走したのは三根校長自身であった」。
三根校長の歩みと土佐中
細木大先輩が伝え聞いてきた三根校長をめぐるなぞの事件は、山形中学からの転任先が九州でなく新潟だった以外は、ほぼ正しかった。特に新潟中学では、正当な理由のないストライキの首謀者を厳しく処分しながらも、影では自らが転校先をさがして救済したのである。人材育成をめざして川崎・宇田両家が土佐中創立の際、校長の人選に尽力したのは土佐出身で元新潟県知事の北川信従と東京府立第一中学校長の川田正澂であった。『三根先生追悼誌』には、土佐中設立の趣旨は「機械的多数画一教育の弊を矯(た)め少数英才の個性長所発揮をはかり、将来邦家各方面の指導者たるべき基礎教育をなし、もって郷土ならびに国家に報ぜんとするにあり」とある。北川・川田ともに、この趣旨と三根校長の山形、新潟での校長としての手腕を充分見極めた上で、推挙したと思われる。また、三根校長も県立中学でのストライキ事件など苦い経験を生かしつつ、新設土佐中学の校風樹立に邁進したのである。
なお、三根校長は長崎県私立大村中学・第五高等中学校(旧制熊本高校)から帝国大学文科大学哲学科に進んでいる。卒業した明治30年には京都帝国大学が誕生し、従来の帝国大学は東京帝国大学となる。文科大学には、哲学・国文学・漢学・国史・史学があり、後の東京帝国大学文学部にあたる。当時の文科大学卒業生の進路について、『東京大学物語』(吉川弘文館 1999年刊)で中野実(東京大学・大学史史料室)は、「主な就職先は中等学校の教員にあった。その中から少しずつ文学者が登場してきていた」と述べている。筆者が研究室に訪ねた際には、「外山正一学長は、中学の教職に進んでも職人的教師ではなく、研究も続けて自ら生徒に範を示せと説いた。当時は、高等学校の数もまだ少なく、県立中学が各県の最高学府であり、国をあげてその充実をはかっていた。帝大卒の教員は尊敬される存在で、その待遇もよかった」と語ってくれた。
三根校長の哲学科同期は比較的多くて16名、一年先輩には桑木巌翼(哲学者・東大教授)がいる。国文科の一年先輩には高知出身の文人・大町芳衛(桂月)がおり、後に土佐中の開校記念碑文を書いて名文と讃えられる。国史科には三根と同じ長崎出身の黒板勝美(歴史学者・東大教授)や高知出身の中城直正がおり、中城は後に高知県立図書館の初代館長となって三根校長と再会する。
土佐中時代に三根校長はほとんど視力を失うが、全校生徒と親しく接し、敬愛を込めて「おとう」と呼ばれる。そして進学した大学での勉学ぶりから生活態度まで熟知され、気にかけて下さったと、多くの先輩が体験談を述べている。ご子息の三根徳一(歌手ディック・ミネ)、結城忠雄兄弟にもかつてお話をうかがったが、ご長男・徳一が語り、『筆山』にも執筆いただいた「貫いた教育方針」が忘れられない。そこには、「父は学校で<おはよう>と誰にも帽子をとって挨拶するのが常だった。死の前日のこと、軍部の将校がこれを敬礼にせよと迫ったが、父は教育方針は変えぬと、言い通した。腹をたてた将校は酒に酔って自宅に乗り込んできて、父と言い争った。この出来事が引き金になって、父は脳内出血を起こしたのであろう」とある。細木大先輩が述べたように、「権門に屈しない気骨」は、晩年になってもいささかも衰えてなかったのである。
なお、制服の袖に軍服をまねて白線を巻くようになったのは、二代校長青木勘の時代からである。三根校長は背広を望んでおられた。それにつけても、あと十年後に迫った開校100年には、ぜひ『土佐中高100年史』を刊行し、川崎・宇田ご両家から歴代校長・教職員・生徒・同窓会・振興会が一体となっての激動の時代の歩みをみんなでたどり、今後の母校発展に生かせるようにしたいものである。
海辺から龍馬の実像を発掘
ジャーナリストの大先輩
山田一郎さんのお名前は、出版社(学研)に入社した頃から種崎に帰郷するたびに父母から聞かされ、訪ねるように言われていた。父・中城惇一郎は若い頃は新聞記者志望であったが、祖父・中城直顕の養子となって大正14年に東京から帰郷、三里村長などについた。晩年になっても、村内出身の言論人である中島及・田中貢太郎のお二人に対しては、敬愛を込めて「きゅうさん」「田中のこうさん」と呼んでいた。この後に続く三里生まれのジャーナリストが、中島暁(10)・山田一郎・中山操の皆さんであった。
昭和30年代から40年代にかけて、山田さんは共同通信の文化部長・科学部長・常務理事などの要職を重ね、私も雑誌編集の仕事に追われ、ご挨拶をする機会を持てないままであった。昭和55年に退社した山田さんは、ジャーナリストとしてめざましい活躍を開始した。57年に『寺田寅彦覚書』で芸術選奨文部大臣賞新人賞を受賞、翌58年の正月からは高知新聞で「南風対談」を始めた。高知出身の「十二名家・巡礼の旅」の聞き手として、この対談で有光次郎・大原富枝に続き、三人目に公文式教育を考案した公文公(7)を選んでいただいた。当時私は、くもん出版から公文側の一員として取材に立ち会い、ようやく山田さんともご挨拶をすることができた。
山田さんと公文先生との出会いには前段がある。高知出身の近藤久寿治(6)が創業した出版社・同学社の新ビル落成記念パーティーで、昭和57年に山田さんは公文教育研究会役員の岩谷清水(27・高知市常盤町出身)と出会って公文先生の活躍ぶりを聞き、師弟の文通が始まっていたのだ。この経緯を山田さんは、高知新聞『南風帖』に書いておられる。さらに遡れば、公文先生が大阪帝大理学部数学科を卒業して最初に赴任した海南中学で教えた生徒の一人が、山田さんであった。「南風対談」では、この師弟がクラスの席順や同級生の消息、さらには当時の高知の教育事情まで克明に記憶しているのに驚かされた。実は私も公文先生の教え子で、戦時中には海軍予科練教授だった公文先生が帰郷、昭和24年に母校土佐中高の教諭になって初めてクラスを持った際の生徒であった。山田さんは、私にとって三里小学校の先輩であり、また公文先生の門下生でありながら数学の不得手な不肖の兄弟弟子でもあった。
平成7年7月に恩師公文公が永眠した際には、追悼文集に伝記執筆をお願いした。刊行まで限られた時間しかなかったが、公文禎子夫人などご遺族・関係者から丁寧な取材を重ね、心のこもった評伝を書き上げてくださった。公文式教育誕生の背景には、旧制土佐中で受けた、個人別・自学自習教育があることも指摘いただいた。
多士済々の東京「みさと会」
「南風対談」が契機で、海南時代の教え子である山本一男(デザイナー山本寛斎の父)も、革のジャンパーでオートバイに乗り、颯爽と千代田区市ヶ谷の公文東京本部にやってきた。「若い女性に追っかけられたが、赤信号で止った際に顔をのぞき込まれて老人であることがバレタ」などと、恩師に笑顔で話していた。三里組も、山田さんを囲む会をやろうということになり、平成初年に東京で「みさと会」を始めた。メンバーは竹村秀博(オリンパス)・小平〈中城〉久(家裁調停員)・池川富子(29・三枝商事)・平田喜信(30・中学で転校・横浜国大教授)・奴田原〈池〉訂(31・高知銀行)・秦洋一(34・朝日新聞)・小松勢津子(35・旺文社)・丸山〈早川〉智子(35・産経新聞)・中島朗(43・電通)など多士済々で、なぜかマスコミ関係者が圧倒的に多く、山田さんにも喜んでいただけた。会場は赤坂の「土佐」などであったが、下戸にもかかわれず最後まで若い酔っぱらいに付き合ってくださった。いかにも潮風にさらされて育ったような風貌と、ふるさとの人と風俗を回想しての鮮明な語り口に一同魅了された。郷土出身の作家・文化人の生い立ちや消息にも精通しておられ、驚かされた。
二回目の「みさと会」の案内状が手元にある。「今回は、高知県東京事務所次長として活躍中の池永昭文(36)さんが、高知新港や橋本県政など三里と高知の最新情報をお話くださいます」と記されている。同学社近藤社長夫人(旧姓・野町初甲)も、母の野町久喜が種崎の桟橋近くに住み、その妹が近くの釣り宿「橋本」のおかみであり、メンバーだった。平田君は私と小学の同級で、父上・平田信男は海上保安庁を経て東海大学教授を務めた航海工学の専門家であった。「みさと会」が縁で山田さんは信男をたずね、坂本龍馬「いろは丸事件」の詳細な資料を提供、現在の海難審判ではどちらに非があるのか審理を求め、真相に肉薄している。
平田君も先祖は土佐藩御船方だが、本人は王朝文学を専攻していた。「源氏物語」や「土佐日記」の研究で知られ、横浜国大の教授であった。国際交流基金からサンパウロ大の大学院生指導に派遣され、帰国すると副学長に就任、次いで図書館長としてその改築を指揮し、市民参加型の新しい大学図書館を開館するなど多忙を極めていた。定年1年前の平成12年に急逝、山田さんの要望を受けて晩年は高知で後身育成に当たると言ってくれていたが、かなわなかった。秦君も医療ジャーナリストとして注目されていたが、自分が病に倒れてしまった。小松さんは種崎にあった高芝医院の姻戚で、トフラー『第三の波』などの翻訳でも活躍した。丸山さんの父上は、市役所の種崎支所長であった。「みさと会」は、山田さんが横浜市から高知市に転居したこともあって、数年で活動を休止してしまったが、三里出身のジャーナリストにとって山田さんは生きたお手本であり、その綿密な取材ぶりと権威を恐れぬ執筆姿勢に、後輩は勇気を与えられてきた。
寅彦と龍馬の研究が双璧
山田さんが残された多くの功績の中で、寺田寅彦研究と坂本龍馬研究が双璧であり、粘り強い史料渉猟と関係者への根気強いアプローチで、次々と新事実を掘り起こしていった。
寅彦関連では、『寺田寅彦覚書』刊行後も寅彦の次女・関弥生など一族と交誼を重ねて信頼を得、さまざまな風評のあった三人の妻たちと寅彦との暖かい交情の実態を、前著の20年後に刊行した続刊『寺田寅彦 妻たちの歳月』で明らかにした。最初の妻・夏子の出生の秘密や、種崎・桂浜での療養生活、帰郷する寅彦の船を浜辺で迎える夏子の姿など、新資料を使って描写、山田さんならではの地を這うような粘り強い取材と人物への肉薄が感じられる好著であった。幕末土佐で起こった「井口刃傷事件」では、寅彦の父が果たした不幸な役割も初めて公にしている。
くもん出版で『父・寺田寅彦』(寺田東一他著・寺田寅彦記念賞受賞)を刊行したこともあって、この間の事情は山田さんからも寺田家・関家からもお聞きすることができた。平成5年に帰郷した際、寺田寅彦旧邸を御案内いただいたことも忘れられない。できればこの旧邸とは別途に寺田寅彦記念館を建て、原稿・絵画・著書・愛用の楽器など遺品や関係資料を展示したいと語っておられた。岩手県花巻市の宮沢賢治記念館が、文学者・科学者としての賢治を堪能できる見事な展示場になっているのを参考に、構想を描いていたようだ。寺田家が守ってきた貴重な遺品千数百点は山田さんに託されたが、寺田寅彦記念館は実現せず高知県立文学館に寄贈されることになった。
坂本龍馬に関しても、従来高知の史家が『汗血千里の駒』を「史実追及を堅実に行い」などと解説し、司馬遼太郎の小説『竜馬がゆく』が史実を離れていても国民文学としてもてはやされるのに対し、山田さんは新史料を発掘して昭和61年から高知新聞に新しい龍馬像の連載を開始した。これは翌年に、新潮社から『坂本龍馬―隠された肖像―』として刊行されたが、まさに隠されてきた龍馬像の出現であった。龍馬の父・八平の実家である山本家の系譜と沢辺琢磨波乱の生涯から、少年龍馬「案愚説」への反論まで、眼からウロコの連続であった。司馬がエッセイで「龍馬はなによりも海がすきであった」と述べたのに賛同しつつも、龍馬と海洋との関わりを少年時代の地縁から説き起こして実証的に解明したのはこの著書であった。なかでも三里関連の事項は、その風土と歴史を知り尽くした上で、関係者への取材を重ね、新事実を見事に掘り起こしている。
伊与・田鶴など三里人脈を発掘
特筆すべきは、龍馬の継母・伊与の素性を解明したことだ。北代家から川島家に嫁し、寡婦となって父・坂本八平の後妻に迎えられた女性の名前が、「伊与」であることを突き止めたのである。川島家は土佐藩御船倉の御用商人で当時は種崎に住み、御船方の中城家から四、五軒西にあった。当主の川島春麿(猪三郎)と中城直守は、歌人仲間で親しかった。川島家に継母とともに舟でやってきた龍馬が春麿の子どもたちと仲良くなり、特に次女・田鶴を可愛がったことを山田さんは聞き出している。中城直守の子・直楯や直顕とも当然出会っており、最後の帰郷での潜伏につながったとする。安政地震の津波で被害を受け、川島家は仁井田に移転したが、中城家は種崎から動かず直楯が当主となっていた。
慶応3年9月、龍馬最後の帰郷で震天丸にライフル銃一千挺を積んで浦戸湾に入港した際に、大政奉還への藩論が未だ定まっておらず、龍馬の一行はまず隠密裡に中城家にはいったのである。山田さんは、中城直守の筆録『年々随筆』と、中城直正(種崎小学校卒・初代高知県立図書館長)が父・直楯と母・早苗から聞き取った『随文随録』を史料として高く評価し、特に早苗が述べた龍馬の風貌描写を絶賛している。『随文随録』には、中城家で風呂に入り襖絵を眺めた後に、龍馬は「小島ヘ寄リ、舟ヘ帰ルトテ家ヲ出タリ」とある。
この小島家が龍馬を慕っていた川島家の次女・田鶴の嫁ぎ先であり、種崎川島家の跡地に家を建てて住んでいたことも、山田さんは調べ上げている。龍馬帰郷の際に小島家には、十市村の郷士で龍馬の剣道の師でもあった土居楠五郎が、孫の木岡一を連れてきており、木岡はギヤマンの鏡を龍馬に貰ったと『村のことども』(三里尋常高等学校 昭和7年刊)にある。この本では、「坂本龍馬の潜伏」と題して、まず郷土史家・松山秀美の中城家潜伏説を、次いで古老となった木岡の回想を紹介してある。これは、どちらかが真実ではなく、山田さんが解明したように龍馬は双方を順次訪問したのである。
田鶴への山田さんの思い入れはかなりのもので、仁井田浜の小島田鶴の墓前に立ち、「妙音観世音 梵音海潮音」と観音経をつぶやいたという。私の手元に残る色紙にも、これにちなんで「梵音海潮音 龍馬観世音 和平を願うて眠り居り申候 龍馬 山田一郎」と記されている。この小島家から城下浦戸町の今井家に嫁に入った直の子・今井純正が改名して長岡謙吉となり、海援隊に加わって「藩論」「船中八策」の起草者として活躍する。これも、山田さんの『海援隊遺文―坂本龍馬と長岡謙吉―』で、詳述されている。
龍馬と海を結びつけるきっかけとなった継母・伊与と川島家に関しては、再三川島文夫を訪問し、言い伝えを聞き取るとともに龍馬も見たとされる世界地図から古文書まで関連史料を調査されている。我が家では母・中城冨美とともに、信清悠久・美衛夫妻と昵懇であった。信清は戦前に反戦運動をした後、満州に渡って満映で脚本・監督を務め、戦後は映画のシナリオ作家として東京で活躍、帰高後はテレビ番組「はらたいらのおらんく風土記」の台本を執筆し、三里史談会の会員でもあった。山田さんとは、若い頃にともに満州で活躍し、また反骨精神旺盛な物書きとしても気があったようだ。満州時代になじんだのか、ともにコーヒー好きで、特に山田さんは東京・調布市の居室を訪ねても、まず自ら薫り高いコーヒーを入れてもてなしてくださった。
美衛は私の長姉で、若い時分には東京で婦人誌の記者をし、一時期は大原富枝の秘書をしていた。山田さんはこの大原富枝をはじめ、安岡章太郎・宮尾登美子・倉橋由美子(29)など錚々たる作家から信頼され、高知との折衝でも頼りにされていた。見識に裏付けされた率直な発言が好まれたからだ。しかし、歯に衣着せぬ言動は高知の文学関係者とは齟齬を来すこともあり、困惑の言葉を漏らすことがあった。自ら館長を務めた県立土佐山内家宝物資料館では学芸員の公募制を貫徹し、研究体制の充実にも取り組んで優秀な研究者を育成しておられた。山内家の信頼も厚く、国宝「古今和歌集高野切本」など山内家資料の、県への移管を実現した功績も大きい。
山田さんが龍馬研究に取り組んでいた頃、新人物往来社主催の龍馬研究会が東京であり、お誘いいただいて山田講師のお供をした。少人数の会だったが、坂本家一族の土居晴夫さんも来会、作家で後に直木賞を受賞した北原亞以子さんも出席しておられた。当時私は龍馬のことも中城家史料のこともほとんど知らず、恥ずかしい思いをしつつ少しは龍馬を調べようと思い立った。今にして思えばそれが山田さんのねらいでもあったようだ。おかげで後の「龍馬役者絵発見」に結びついた。
「中城文庫」の推進役
坂本龍馬が最後の帰郷で中城家に立ち寄ったことは、東京帝大国史科卒の歴史家・中城直正が、龍馬の接待に当たった父母からの鮮明な聞き書として記録している。これらを元に、郷土史家・松山秀美は『村のことども』で、歴史家・平尾道雄は『龍馬のすべて』で、きちんと触れている。しかし、大正14年に直正が東京で交通事故のため急逝してからは、聞き書『随文随録』の存在自体が次第に忘れ去られていった。
この記録が再び注目されるきっかけは、昭和55年の三里小学校開校百年記念誌『三里のことども』刊行である。中城家を調査された坂本一定、中山操の眼にとまり、山田一郎・宮地佐一郎のお二人にも龍馬に関する部分のコピーが渡された。この頃に私の義兄・信清悠久が龍馬生誕百五十年にちなんで『土佐史談』に「龍馬の足跡―種崎・中城家」と題して発表、龍馬が眺めた浮世絵貼り付けの襖が現存することも明らかにした。山田さんは昭和57年に、高知新聞連載「南風帳」で「種崎の龍馬」として紹介、宮地は『坂本龍馬全集』に採録してくださった。後者には、私の祖母・中城仲(旧姓千屋・海援隊士菅野覚兵衛の姪)が龍馬の妻・お龍さんに可愛がられ、ピストルで雀を撃って遊び、別れの記念に帯締めをもらった回想談(昭和16年の高知新聞記事)も納められている。
中城家の古文書などの史料が次第に注目され、高知市民図書館に寄託されるいきさつは、『大平山』第30号に「龍馬ゆかりの襖絵や宣長の短冊」として書かせていただいた。寄託が決まったのは、日本史、特に地方史研究の権威である林英夫立教大名誉教授の評価や、武市瑞山の子孫である武市盾夫(18)中央大教授の口添えもあったが、なにより高知での山田一郎・橋井昭六(元高知新聞社長)のお二人による当時の松尾徹人高知市長への推薦が決め手となった。
寄託が決まると、史料受け入れの担当となった市民図書館・安岡憲彦さんの大奮闘があり、6年目に立派な目録も出来て、平成20年2月1日には寄託から寄贈へ移行し、<「中城文庫」開設記念展・海から世界へ>も開催する運びとなった。ところが、その直前になって、展覧会はするが「中城文庫」は返還すると、図書館長からいってきた。ここでも面倒な仲介を、山田さんにお願いせざるを得なかった。そして岡﨑市長・吉川教育長と折衝いただき、とりあえず展覧会は開会、寄贈式はずれたものの2月13日に行われた。
私は寄贈式の日は、昭和大で肺血栓塞栓症の定期精密検診に当たっており、出席出来なかった。この病気は亡くなった山田さんのトミ夫人と同じ病気で、私も肺の動脈にアンブレラ・フィルターを入れており、この検診での胸部断層写真にもはっきりフィルターが映し出され、機能していることが確認出来た。山田夫人の主治医は後の宇宙飛行士・向井千秋さんである。その医療経過と山田さんの奥様への思いやりあふれる看病ぶりは著書『いのちなりけり』に詳しい。文中には患者が外出中に事故にあった場合に備えてのイエローカード(病名・薬・連絡先を記載)を紹介してあるが、私にもカードを用意するよう薦めてくださった。さっそく同様のカードを作り、いまも名刺入れに入れてある。
話を「中城文庫」にもどせば、問題は個人情報保護に即した利用規程の改定と、史料寄贈者への利用状況の告知を、中城家からお願いしたことにあった。寄贈後に高知県立歴史民俗資料館「絵葉書のなかの土佐」や、県立坂本龍馬記念館「坂本龍馬と戊辰戦争」などの企画展で「中城文庫」史料が活用されたが、市民図書館からは寄贈者に対し、まったく連絡がなかった。幸い歴民館からは図録を贈呈いただき、龍馬記念館からは出品リストを後日いただいた。山田さんも図書館の対応を残念がっておられたが、全国の公立博物館・文書館・美術館・図書館と比べ、利用者へのサービスも協力者への対応も遅れを取っているように思える。かつては高知市民図書館と言えば、文化人を館長に招聘し、出版活動から移動図書館・特設文庫・研究者への協力まで日本の最先端であったが、現在の高知市文化行政にその面影はない。県と高知市で新しく歴史資料館建設の構想があると聞くが、貴重な収蔵史料が多いだけに、その利用サービスでも全国の模範となっていただきたい。
生涯一ジャーナリスト
「中城文庫」とともに山田さんにご迷惑をかけたのは、中城家「離れ」の文化財指定調査である。高知市教育委員会から平成18年に、龍馬ゆかりの「離れ」につき、文化財指定を視野に入れて調査したいとの申し出があり、喜んで同意した。教育委員会の指定で建築物としての調査は伝統的建造物の修築で定評のある上田建築事務所が、歴史的位置付けは山田一郎・栗田健雄両氏が担当くださった。平成19年に『中城家「離れ」調査報告書』が出来上がり、高知市文化財保護審議会に諮問された。委員からは「川島家にしても中城家にしても資料が少ない」「市史跡として保存しなければならない程のものではない」との意見が出て、指定は見送りとなった。山田さんは長年の調査研究をふまえて、歴史的意義を説いてくださっただけに、私には「離れ」自体の文化財指定の可否はともかく、山田さんのこれまでの精密な研究成果が否定されたようで申し訳ない気持ちでいっぱいだった。
山田さんは、「審議内容にはいくらでも反論できるよ」とおっしゃり、委員の文化財についての研究姿勢や歴史認識を残念がっておられた。ただ評価できるのは、審議会の討議「要旨」を教育委員会が当家に示してくれたことである。ぜひ、このような情報開示の姿勢は継続していただきたい。
平成22年正月からNHK大河ドラマ「龍馬伝」が始まったこともあって、この「離れ」もいくらか注目されている。毎回ドラマ後にその舞台を紹介する「龍馬紀行」でも取上げたいとの連絡があり、三里史談会事務局の久保田昭賢(理科・久保田伸雄先生の令弟)さんに取材斑の案内をお願いした。6月末の撮影日はあいにくの大雨で、座敷に雨漏りがしており、撮影スタッフも驚いたようだ。久保田さんから現状を報告いただき、兄・中城達雄の即断で台風シーズンにそなえ、急ぎ屋根の修理を行った。地元業者には上田建築事務所とも打ち合せの上で、伝統的建造物にふさわしい修理をしていただいた。ただ、家屋は使用しないと痛みが早く、今後の活用法が課題である。山田さんは、いくつか腹案をもっておられたようだが、地元でなにかいい案があれば、当家としては山田さんへの感謝を込めて協力したいと考えている。なお、種崎の母屋には平成23年春から兄の孫・田副一家が住んでいる。
近年は、山田さんの調布市のお部屋を年に一度くらいはお訪ねしていた。満州時代の思い出話もうかがったが、終戦時に「ソ連機新京を爆撃」の大スクープを打電した話は口にせず、満州巡業に来ていて敗戦で帰国できなくなった落語家・古今亭志ん生との、糊口をしのぐための興行生活を楽しげに語ってくれた。最後の著書として
志ん生(本名・美濃部孝蔵)の一代記を書くべくその先祖を探り、「甲賀の忍者から徳川家康に取り立てられ、旗本となった美濃部家の末裔だった」とも言っていた。高知で倒れたのは、資料を漁り尽くし、敗戦後の大連での生活ぶりや、聞き取った秘話を元に執筆を始めたところであった。岩波書店での刊行も決まっていたが、原稿はご本人とともに泉下に運ばれてしまった。
平成21年の暮れには、上京する安岡憲彦さんと久しぶりに山田さんを訪問することになり、電話をかけたが本人も同じマンションの別室に住むご次男もご不在で、不安にかられた。高知で探っていただくと、入院中とのことであった。そして、年を越して訃報が届いた。3月4日に「生涯一ジャーナリスト」という山田さんにふさわしい名称で「偲ぶ会」が開かれると聞き、高知市城西館の会場に駆けつけ、遺影に最後のお別れをさせていただいた。そこには仁井田の浜に立つ老松のように、吹き寄せる時代の烈風に耐え、温顔のなかにも鋭い視線をたたえて真実を追い続けた希有な文人ジャーナリストの姿があった。合掌 展覧会と講座のご案内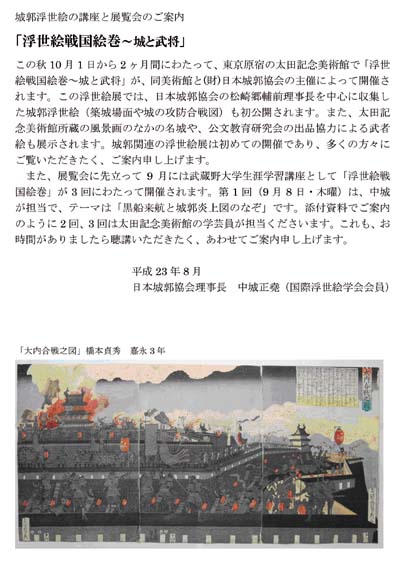
残暑お見舞い申上げます。
今回、城郭浮世絵に関する展覧会と講座を開くことに成りましたので、ご案内申上げます。
右の画像をクリックすると案内状と講座申込書(pdf文書)が出てきます。 龍馬「愚童伝説」から学びの原点をさぐる
平成二二年のNHK大河ドラマ『龍馬伝』終了から一年ほど経過し、放映中に出版されたおびただしい龍馬関連本もほぼ書店の店頭から消えた。この間、坂本龍馬に関する新史料の発掘や新しい観点からの評伝はほとんどなく、多くが既存の資料や伝説にもとづく再整理ないし焼き直しにすぎなかった。いまさらながら、山田一郎さんによる龍馬の継母・伊与の出自から、龍馬の父・八平の実家解明まで、丹念な資料の渉猟と歴史の舞台・関係者を訪ねての調査と論考に感心するばかりである。その著書『坂本龍馬―隠された肖像―』(昭和六二年 新潮社)、『海援隊遺文―坂本龍馬と長岡謙吉―』(平成三年 新潮社)を凌駕する作品に出会うことはなかった。
大河ドラマ『龍馬伝』自体は、放映一年前にNHKの関係者から、「福山雅治を龍馬にしたてた〈劇画〉で、岩崎弥太郎の眼から見る」と聞かされていたので、超かっこよい福山・龍馬と汚れ役香川・弥太郎の極端な対比にも驚かなかった。しかし、高知の城下と安芸の井ノ口村がすぐ隣町にされ、路上で出会った二人がよく行き来し、寺子屋の机が現在の学校と同じ並べ方で、龍馬の愚童ぶりに対して弥太郎には『論語集註』を読ませるなど、興ざめな場面も多かった。
放映でありがたかったのは、最終回の一つ前の「龍馬伝紀行」で我が家の種崎の「離れ」を、龍馬最後の帰郷で潜伏した家として取上げてくれたことだ。六月の撮影当日は帰郷できず、三里史談会の久保田昭賢さんに立ち会いをお願いした。あいにく大雨で、座敷は天井からの雨漏りで畳が濡れ、撮影場面の設定に苦労したとの電話をいただいた。関東在住の兄も私も、雨漏りしているとは思いもよらず、お陰ですぐ修理の手配をすることができた。以前、高知市教委が「文化財指定を視野」に上田建設に依頼して調査を行ってくれ、指定には該当しないとのことだったが、その調査を生かして三里の建築業者に幕末以来の屋根の保存修理をお願いした。NHKの撮影がなければ、雨漏りに気付かないところだった。
本稿では、テレビや伝記物語などで増幅される誤った龍馬伝説が真実と混同されないよう、龍馬ゆかりの旧三里村種崎で生まれ育った者として、龍馬少年の教育と人間形成に関していくつかの指摘をしておきたい。多くはすでに山田さんが論考済みであるが、いくらか別の視点も交えて重ねて呼びかけたい。
大器晩成の流行と愚童説
龍馬の最初の伝記小説は明治一六年に坂崎紫瀾が土陽新聞に連載した『汗血千里駒』であるが、大評判となり単行本としても数社から出版された。この復刻版は数種類あるが、高知では昭和五二年に土佐史談会から出た『汗血千里駒全』が版を重ね、平成五年には新しい「解題」をつけた新版が刊行された。平成二二年には岩波文庫で挿絵全六六点を収録した『汗血千里の駒 坂本龍馬君之伝』が出て、入手しやすくなった。
問題はこの伝記の位置付けである。坂崎は明治初期からの自由民権運動の激烈な活動家であり、その一環として政治小説を発表し、演説会を開催していた。しかし、明治一四年に高知警察署から政談演説禁止の処分を受ける。そこで、寄席芸人として鑑札をとり、馬鹿林鈍翁の芸名で講釈師となるが、たちまち逮捕される。この後で、龍馬の連載を始める。
岩波文庫の校注を担当した神戸大学教授で日本近代文学史専攻の林原純生氏は、「明治一六年という早い時点でかくも見事に坂本龍馬の自由人としての個性が表現されたことは、一つの驚きである」「史書や正史に対して、むしろ、自由党員として自由民権の最先端にいた坂崎紫瀾の歴史意識と、読者と共有しようとした政治理念が、坂本龍馬の個性的な行動や行動空間に強く反映されている」と述べ、自由民権運動のさなかに書かれたこの作品は、幕末や明治維新を素材にした大衆小説・歴史小説の先駆的作品であり、原点であると、高く評価している。
本来この作品は自由民権運動のための政治小説であり、冒頭には井口刃傷事件を持ってきて封建的身分制度のもとでの上士・下士の差別を見事に告発している。ついで、生い立ちに触れ、愚かにみえた少年が剣術や水練に励み、加持祈祷にかこつけて庶民の膏血を吸い取るニセ天狗を退治するまでに成長、十九歳で下士には許されなかった下駄を履いて江戸に出ると、千葉道場の娘・光子(佐那)とのロマンスが花咲く。興味尽きない場面展開の連続だが、政治的意図を持って書かれた小説であり、当然フィクションも多々含んでいる。確実な史料にのみ基づいた伝記や評伝ではない。特に坂崎は講釈師を演じていただけに、噂話を実話のように扱い、江戸の草双紙的な逸話を挿入、誇張した表現で場面を盛り上げている。まず、龍馬誕生にまつわるエピソードから検討してみよう。
龍馬誕生につき、「いにしえより英雄豪傑の世に降誕するやあるいは種々の奇瑞をしめせし」と述べ、龍馬の背の「いと怪しき産毛」の由来を母が懐胎中に愛猫を腹に載せたせいとし、龍馬と名づけたのは出生の前夜母の夢に「蛟龍(こうりゅう)昇天してその口中より吹き出した炎、胎内に入りしと見たり」と説く。蛟龍とは、龍が雲や雨を得て天に昇って龍になる前の姿で、英雄が真価を発揮する前の姿を指す。ここには、伝聞のままに記すと断ってある。続けて、「龍馬は十二、三歳の頃まではあまりにその行いの沈着にして小児の如く思えず。あたかも愚人に等しく、わけて夜溺(よばり)の癖さえあればその友に凌(しの)ぎ侮らるる事あれども、あえてさからう色とてなく…これぞ龍馬が大器晩成のしるしとやいわん」と書く。これが、龍馬愚童説・大器晩成説の発端である。
龍馬の背の産毛に関しては、後に妻のお龍や友人も触れており、生えていたのは事実であろうが、「母が常に猫を抱いていたから」はあり得ない。龍の炎が胎内に入って英雄豪傑が誕生するといった龍神伝説は、足柄山の山姥が夢で赤龍と交わって怪童金太郎が生まれたなど、江戸後期にはよく語られていた。英雄が少年期まで愚人であったが、やがて目覚めて大成するという大器晩成論も、うつけ者と呼ばれた織田信長、百姓の子で「手習い学問かつてなさず」と描かれた豊臣秀吉の事例など、幕末から明治まで枚挙にいとまがない。伝記物語の常套的な展開パターンであった。
著者の坂崎自身も、明治三二年博文館刊『少年読本 坂本龍馬』(図1)の緒言で、近年『汗血千里駒』が広く伝播したため、内容を踏襲した伝記が見られることを悔やみ、こう述べている。「世人の仮を認めて真と為すに至る。これ余のひそかに慚悔するところたり。爾来余は龍馬その人の為に大書特書すべきの新事実を発見したること一にして足らず。ここに於て更に実伝を著わし、もって許多(あまた)の誤謬を正し、あわせてその真面目を発揮せんと欲し…少しく余の旧過を償うべきのみ」。しかし、この新著でも薩長連合や大政奉還に関しての誤りは直してあるが、伝聞による生誕伝説・大器晩成説は前著と同じであった。
『汗血千里駒』以降の龍馬像
坂崎自身は、『汗血千里駒』の自序で「龍馬君の遺聞を得、すなわちもっぱら正史に考拠し」と記したが多々誤謬があり、伝聞によった部分もあることを自覚し、後のち訂正に努めていた。ところが、平成五年の土佐史談会版の解題で、岡林清水はこう論じた。「紫瀾はこの作品で、明治御一新を上士と下士・軽格との対立面から把握し、…軽格坂本龍馬を代表とする明治御一新へ向かっての大精神は、自由民権運動につながると考え、この自由党的思想性でもって、『汗血千里の駒』を支えようとした。だが、この作品は、単なる党派的理想宣伝の小説ではない。史実追及を堅実に行い、リアリティのあるものとなっている」。
坂崎の作品は龍馬伝の第一号であり、龍馬研究の基本資料であるが、正史・史実とは言えない内容を織り込んだ政治小説であった。本人もそれを自覚していたのに、平成を迎えての岡林の解題では、「史実追及」「リアリティあるもの」が強調されていた。現在の作家・漫画家・脚本家から龍馬ファンまで、広く実伝と誤解される要因になったようだ。
では、『汗血千里駒』以来、龍馬が実伝と小説の間でどう揺れ動き扱われてきたか、青少年期の描写を中心に筆者の管見から探ってみよう。
明治二九年七月には、坂本家の遠戚になる弘松宣枝が『坂本龍馬』(民友社)を出版、好評で年内だけで五版を重ね、第三版からは龍馬の肖像写真が口絵として掲載される。後に日露戦争でバルチック艦隊との決戦をひかえた一夜、昭憲皇太后の枕辺に現われ、「微臣坂本龍馬でござります。力及ばずといえども、皇国の海軍を守護いたしまする」と告げてかき消えた話が出る。宮内大臣だった田中光顕(元陸援隊士)が人物確認のため皇太后に献上した肖像写真は、この口絵のものとされる。お龍も同じ写真を持っていたと『千里駒後日譚』にある。この弘松の作品も、少年龍馬の描写は坂崎を踏襲している。
皇太后の夢に現われた龍馬の新伝説は、明治新政府で薩長に主導権を奪われた土佐派の閣僚・田中光顕が、挽回策に龍馬を担ぎ出したと言われる。この出来事は新聞が取り上げたため、世間に広まる。土佐出身の画家・公文菊僊は後に龍馬立像に「征露の年 皇后の玉夢に…」の漢詩を添えた画軸を制作、大当たりをとる。この話も、病で伏す唐の玄宗皇帝の夢に現われて小鬼を退治し、快癒させた鍾馗伝説と似ている。玄宗皇帝が夢で見た姿に似せて描かせた鍾馗像が魔除けとして好まれ、日本にも伝来、江戸時代には病魔除けとして版画が戸口に張り出され、軒先にも塑像が飾られた。
しかし、龍馬はまず自由民権運動家にかつがれたためか、武市半平太は故郷・高知市吹井に瑞山神社が建立されたのに、幸い神にされることはなく、いつまでも自由人でいられた。ニセ天狗の祈祷師を退治した逸話や、慶応二年のお龍との霧島山登山で天のさかほこに天狗の面が付けてあるのを笑い飛ばし、引き抜いてみるなど、少年期から合理的な思考で行動しており、神がかった戦争勝利予言は似合わない。
幼年時代の疑わしき伝聞
大正元年には『維新土佐勤王史』(冨山房)が瑞山会著述で刊行されるが、執筆を担当したのは坂崎紫瀾であった。平尾道雄はこの書を、坂崎特有の「文学的史書」と評している。ここでの龍馬少年の描写は、だいぶ平静を取りもどし、「彼の童時は物に臆して涕泣しやすく、故に群児の侮蔑を受くるも、あえてこれを怒らず」と述べ、後年兄・権平に出した手紙の「どうぞ昔の鼻垂れと御笑くだされまじく候」を紹介する。
母・幸は龍馬が十二歳の時に亡くなる。「当時龍馬は小高坂村の楠山某家に就き、習字と四書の素読を始めしに、たまたま学友と衝突して切りかけられ、ために退学したり。父母は再び過ちあらんことを恐れて、他に通学なさしめざりしより、ついに文学の素養を有する期を失いたり」と書く。四書とは、儒学の基本図書である大学・中庸・論語・孟子で、文学は学問といった意味である。続いて「すでに十四歳を過ぐるも、時に夜溺(夜尿)の癖を絶たず」で、父もその遅鈍を嘆いていたが、「さらに長じて剣道を日根野弁治に学ぶや、不思議にも気質とみに一変して別人の如く、その技もまた儕輩(せいはい)をしのぐに至れり」と記す。大雨の日に水練に向うのを日根野に怪しまれ、「水に入れば常に湿(うるお)う。なんぞ風雨を辞せんや」と答えたエピソードをあげ、龍馬が自らの行動に自信を持った証とする。(図2)
姉の乙女は龍馬の四歳(実は三歳)上で「女仁王」のあだなで呼ばれ、「短銃を好み、鷲尾山などの人なきところに上り…連発してその轟々たる反響にホホと打ち笑み」とか、「常に龍馬を励まして、これを奮励せしむる」と紹介してある。
これら『維新土佐勤王史』にある少年龍馬の逸話は、大正三年刊『坂本龍馬』(千頭清臣著 博文館)や、昭和二年刊『雋傑(しゅんけつ)坂本龍馬』(坂本中岡両先生銅像建設会 編集発行)でも、ほぼ同様だ。ただ千頭の本では二版増補で「疑わしき話」の項を設け、はな垂れと言われたことで龍馬を真の馬鹿というのは大きな間違いと記してある。千頭は高知出身の英文学者・貴族院議員として知られた存在だったが、実際の筆者は山内家史編修係・維新史家の田岡正枝であった。後者は、京都円山公園にある坂本・中岡像建設のための刊行で、銅像は昭和九年に完成したが第二次大戦で供出、昭和三七に再建された。
岩崎鏡川の史料収集と重松実男の見識
昭憲皇太后の夢に現われた龍馬は、日露戦争の勝利によって、自由民権の先駆者のみならず海軍の祖・皇国守護の英霊とされ、もてはやされるようになった。小説だけでなく、演劇や講談にも次々と取上げられた。これに対し、『汗血千里駒』以来の伝記と称する作品の内容を、「荒唐無稽の綺語でなければ、舌耕者流の延言」「正確な史料に憑拠(ひょうきょ)するものあるを見ない」と断じ、坂本龍馬の史料編纂に取り組だのが岩崎鏡川(英重)である。岩崎は山内家史編集係・維新史料編纂官を歴任、晩年は『坂本龍馬関係文書』編纂に心血をそそぎ、大正一五年五月に死亡したが、その一ヶ月後にまず私家版として刊行された。鏡川の次男が『オリンポスの果実』で知られる作家・田中英光である。
中城家の本家・中城直正(初代高知県立図書館長)は、大正期にこの岩崎と綿密に連絡をとって、維新の志士たちの史料収集と顕彰を中心に、県下の史料・史跡の収集保存や記念碑建立などに取り組んでいた。例えば大正三年一月から二月にかけて上京した際の日記には、維新史料編纂所の岩崎とともに土佐出身の田中光顕伯や土方久元伯、さらに東京帝大史料編纂所にいた帝大同期の歴史学者・黒板勝美などを訪問した記録が残っている。岩崎からの手紙もあり、内容は武市瑞山先生記念碑・同遺跡保存・堺事件殉難者合祀・紀貫之邸跡建碑、それに維新関連の贈位申請・文書購入などである。これらの手紙や日記は全て、高知市民図書館「中城文庫」に収まっている。
この『坂本龍馬関係文書』にも、龍馬の手紙の執筆年代などいくつかの誤りが後に指摘されたが、龍馬研究の画期的な史料集誕生であったことに間違いない。戯曲の傑作とされる真山青果『坂本龍馬』も、三里村出身の作家・田中貢太郎の『志士伝記』(改造社)も、この史料集刊行抜きには考えられないと、文芸評論家・尾崎秀樹氏は述べている。龍馬の史料発掘と編纂の仕事は岩崎亡き後も続き、郷土出身の研究者に受け継がれていく。その結実した刊行物が、平尾道雄著『海援隊始末記』『龍馬のすべて』・宮地佐一郎編『坂本龍馬全集』・山田一郎著『坂本龍馬―隠された肖像―』他・松岡司著『定本坂本龍馬伝』であり、坂本家ご一族の土居晴夫氏も綿密な考証によって『坂本龍馬の系譜』をまとめておられる。
これらの中で、少年龍馬の真実に最も迫っているのは、山田さんの著作である。そして、その先駆ともいうべき著述が、昭和一二年に重松実男編著で高知県教育会から刊行された『土佐を語る』の「坂本龍馬」であろう。あまり知られていない著述なので、少し長くなるが紹介しよう。
その出身 「坂本は天保六年に城下の本町筋一丁目の郷士の家に生まれた。幼少の頃遅鈍な劣等児であったように伝えられもするが、これは彼が後年兄権平への書翰に〈…どうぞ昔の鼻垂れとお笑い下されまじく候〉とある所などから誤り伝えられた話であろう。晩成の大器であったには相違ないが、遅鈍であったものとは思われぬ。…青年時代剣道の師日根野弁治が、大雨の中を水泳にでかける坂本に出会ってあやしむと、水へ入ったらどうせ濡れるから同じことだ。と答えた所も、一見間抜けたようで、その実中々才気煥発ではないか。」と書く。続けて十八、九歳で四万十川治水工事の監督を手伝い、精出す者に褒美を与えたことを、「すでに棟梁の器量をひらめかしておる」と評価する。さらに、「嘉永六年十九歳、剣道修業の志を立てて江戸へ上るとき、同行者の一行中坂本の姿が見えないので、見送り人が不審して集合所であった友人の宅へ立戻って見ると、彼は襖に貼った錦絵に見とれて〈たまるか義経の八艘跳じゃ〉などと太平楽をきめこんで、只今三百里外へ旅立つ者とも見えなかった」と紹介。当時の土佐から江戸は、今西洋へ旅するようなものなのに、坂本の「天衣無縫の大らかさがうかがわれる」と人柄にも触れている。
江戸への初めての旅立ちの際に、最初に立ち寄った家で襖(壁ともいう)に貼ってある浮世絵に見入った場面は、前出の弘松の本にも、仁井田出身の作家・田中貢太郎著『志士伝奇』の坂本龍馬にもある。慶応三年九月、最後の帰郷で種崎・中城家に潜伏した際に、やはり襖に貼られた浮世絵を眺めており、後に高知での芝居「汗血千里の駒」上演で、龍馬自身の浮世絵(役者絵)が制作されたことも含めて、不思議な縁を感じる。
その学問 「彼ははやくから剣道に専念したので、学問の素養の薄いのを悔い、帰国してからはよく読書した。海軍通の河田小龍という画家の啓発を受けて、将来の海上発展を夢みたのもその一、また折りにふれて和歌をも詠んだ。彼の詠草は、〈げにも世に 似つつもあるか 大井川 下す筏の はやき年月〉(他に二首掲載)などと、卒直武骨な個性の発露する中にも、自ら格調の整うた才気を見せている。漢籍では、老子を愛読したというから、なかなか世人が思ったように無学ではない」と述べている。さらに、読書法が変わっていて、『資治通鑑』を読ませると字音も句読も返り点もいい加減だが、「大意がわかればよいじゃないか」と笑っていたという。後年英語も学んだ。ある蘭学者によるオランダ政体論の講義中に、「それじゃ条理が立ちません」と指摘、蘭学者が誤りを詫びた話も紹介している。
航海術研究 「その後江戸へ下って勝海舟の門に入り、一心に航海術の研究を始めた。この動機は、彼と小千葉の倅の重太郎とが開国論者の海舟を斬るつもりで押しかけ、海舟に説得せられたことになっておるけれども、これは疑わしい。当時彼は海外の事情に盲目でもなく、海上雄飛の素志を抱いていた…」。ここでは、海舟を斬りに押しかけたとの伝説を否定し、神戸海軍塾での研鑽や、第二次長州戦争で「習得した海軍術を以て桜島丸を操縦し、幕鑑に砲火を浴びせかけてあやしまなかった」事例をあげ、高所の見識と評価する。
この重松の著書は、海援隊・薩長同盟・大政奉還・船中八策・遭難・逸話などの項目をたて、きちんと述べてある。学術書でないため、個々の出典を示してないのは残念だが、遅鈍ではなく、海舟を斬りに行った伝説は疑わしいと明記している。昭和初期の見識ある高知の知識人は、龍馬愚童説など信じていなかったのだ。
龍馬の手習いと寺子屋
龍馬は乙女姉さんへの親しみとユーモアあふれる手紙から、志士たちへの情報伝達、政治構想まで、さまざまな文書を書き残している。個性的な口語体の文章表現と、伸びやかな筆遣いでその想いが率直に伝わってくる。この筆力は、少年期に習得したものである。ここで、その学習歴を振り返ってみよう。主として高知県立坂本龍馬記念館の「龍馬略年表」による。〈 〉内は、筆者の追加事項である。
この年表で、まず注意いただきたいのは年齢で、江戸時代は数えであり生まれると一歳、龍馬は生後一月半で正月を迎えて二歳となる。現在の満年齢と二歳近くずれているのだ。母幸の亡くなったのは、今でいえば十歳ぐらいだ。この年に楠山塾に入門とあるが、『高知藩教育沿革取調』(明治二五年 冨山房刊)によれば、師匠は楠山荘助(庄助)、文政五年開業、安政四年廃業で、学科は読書習字、安政三年の生徒は男百人、女二十人となっている。龍馬が、すぐ退塾してもさほど問題なかったのは、入門前に家庭学習ですでにかなり読み書きを習得していたからだと思われる。
江戸後期には全国で寺子屋が普及し、庶民の子弟も数えの七歳くらいから読み書き算盤を習うようになるが、武士や庄屋、裕福な町人の多くは手習いの手ほどきを家庭で行うのが習わしであった。自叙伝『蜑(あま)の焼く藻の記』を残した幕府御家人・森山孝盛は、十歳までの教育は母任せだったという。初めは家庭学習で、途中から寺子屋に行く者もいた。いずれにしろ十二歳前後になり手習いを終えると、家塾・私塾・藩校、あるいは剣道場などに入門する。寺子屋の師匠が医師や武士・僧侶・庄屋などの兼業であったのに対し、藩公認の儒官による家塾も、民間の私塾も、漢学者や国学者が自宅で開いた塾であった。
坂本家の人々は代々和歌を楽しんだとされ、なかでも龍馬の祖母久は土佐では知られた歌人・井上好春の娘であり、その家風は龍馬の父八平・母幸にも受け継がれたようだ。山田さんが『海援隊遺文』で紹介したように、仁井田・川島家に残る『六百番歌合』には当時種崎にあった川島家で開かれた歌会の巻があり、そこには種崎の川島春麿・杉本清陰・中城直守などと並んで坂本直足(八平)の名が見られる。このような教養豊かな家庭では、手習いの手ほどきは父母が行い、親が読み書きの得意でない家庭では最初から寺子屋に通わせていた。
土佐での事例は、下級武士で国学者の楠瀬大枝(一七七六~一八三五)が残した日記『燧袋(ひうちぶくろ)』に記されている。この日記を分析した太田素子(和光大学教授)は『江戸の親子』(中公新書)で娘の教育について、「大枝は菊猪や笑の手習いをやはり自分で手がけている。…菊猪の記録では手習いの開始と初勘定を続けて記録しているが、手習いの開始は菊猪七歳」、「下級武士の息子たちが手習いはともかく、素読から講釈へ進む段階には私塾に通っていた」と述べている。
江戸の家庭教育の事例は、幕末に蘭医桂川家に生まれた今泉みねの『名ごりの夢』(平凡社東洋文庫)にある。「私の生まれた家では、…手習いでもしているのを見つかると、御じい様が桂川のうちに手習いや歌を習う馬鹿がどこにあるか…そんなことは習わなくてもできるもんだ」、「いきなり思ったことを歌によんで、それを書くのが手習いでした。いろはを習わせると言うよりも、それを最初から使わせて思うように書かせる。つまり、生活がそのまま教育ですね」と、語っている。
桂川家は極端な例だが、寺子屋でも家庭でも手習いは基本的に個人別自学自習であり、学びは学(まね)びから始った。多くが、まず「いろは」と数字を師匠・親が自ら書いた手本を真似て学び、次に往来物と呼ばれる木版摺りの教科書を使っての手習いへと進む。往来物の内容は、人名漢字、国名尽し、消息往来、さらに商売往来、風月往来などで、文字・単語・短文を習得し、日常生活の用語・知識・手紙文、そして職業知識や和歌風流へと続くカリキュラムがあった。
寺子屋の学習法と机の配置
学習法は、新しいお手本に進むたびに師匠から読み書きの指導を受けるが、あとはひたすら手習いの反復練習である。そして、一人ずつ師匠の前に出てチェックを受け、読み書きともきちんと出来れば新しい教材に進む。何十人生徒(寺子)がいても、学習内容は進度に応じて一人ひとり違っていた。往来物は七千種類以上あり、『土佐往来』といった地方版も出版されていた。和歌では『百人一首往来』『七夕和歌集』等があった。
家族で和歌を楽しんだ坂本家では、実母幸も継母伊与もそして三歳上の姉乙女も当然手習い指導の力を持っていた。中城直正の手稿『桃圃雑纂』にも「母幸ハ温厚貞節、ヨク八平ニ仕ヘ、子女ヲ教育セシガ」とある。龍馬には、病弱な母に代ってもっぱら乙女が指導、『古今和歌集』も教えたとされる。慶応元年九月の乙女・おやべに宛てた龍馬の手紙からは、『新葉和歌集』にも親しんでいたことがうかがえる。
このような手習いを終えると、十二歳くらいから私塾や家塾で、さらに四書五経・史記・唐詩選・資治通鑑などの漢籍とも取り組み、専門的知識を持った師匠の元で儒学や漢詩・国学を身につける。また、武士は武術にも励むことになる。
龍馬にとっては、寺子屋や私塾に行かずに、家庭で母幸や姉乙女からのびのびと自学自習で読み書き算盤、さらには歌の道を学んだことが、その後の人間形成にかえって役立ったように思われる。漢籍はさほど必要としなかったのだ。成人してからの手紙文や和歌から判断しても、読み書きの基礎学力はきちんと身につけていたし、砲術・航海術を学ぶために必要な数学力、例えば大砲の角度・火薬量から弾道と距離を計算する力も備えていた。英語にも挑戦している。
それにしても、近年の寺子屋描写はひどすぎる。NHK「龍馬伝」でも第一回に寺子屋と私塾(岡本寧浦)の場面が登場したが、どちらも今の学校同様に教師と生徒が向き合う形で机が並べられていた。寺子屋では一斉授業を行わないので、生徒たちは入門の際に持参した机を自由に並べて学習した。師匠に向って整然と並べることはあり得ない。このことは、金沢大学(日本教育史)の江森一郎教授が『「勉強」時代の幕あけ』(平凡社)で、江戸時代の寺子屋絵図を列挙して論じておられる。
ここでは、公文教育研究会所蔵の二点を紹介しよう。『孝経童子訓』所載の「書学之図」(図3)は行儀よい寺子屋で、右は男子席、左は女子席だ。師匠の前で個人指導を受ける生徒がいる。次の『絵本弄(もてあそび)』(図4)は、出かけていた師匠が帰ってみると、大騒ぎの場面である。龍馬もこんな騒動に巻き込まれたのだろうか。机はコの字型に並べてある。
ところが高知でも、六年ほど前に高知城の丸の内緑地で開かれていた江戸時代の城下町展示を見学に行くと、寺子屋のセットがあり、やはり全て前向きに机を並べてあった。本町の「龍馬の生まれたまち記念館」にも寄ったが、ここに置いてあった寺子屋場面の絵も同じだった。双方の係りには間違いを指摘しておいた。さすがに山形県立教育博物館の寺子屋展示は、江戸時代の天神机から落書きだらけの雨戸まで本物を揃えており、並べ方もコの字型できちんと考証がされていた。平成一三年に京都国際会議場で開かれた「ユネスコ世界寺子屋会議」の展示企画を担当し、浮世絵寺子屋図とともに山形の実物をお借りして展示したが、海外の参加者から大変好評であった。なお、寺子屋で使う質素な机を、学問の神様・菅原道真にちなんで天神机と呼んだ。
日本では明治五年の学制以降、ヨーロッパの小学校の一斉授業を取り入れたが、この授業法は十九世紀になってからイギリスの牧師が、植民地でのキリスト教普及のため考案したものである。二人の牧師の名前をとって、ベル・ランカスター・メソッドと呼ばれるが、少ない教師が効率よく大勢を指導するために助手を使い、同一教材で一斉授業を行った。
この教授方法を、産業革命と列強による戦乱の時代を迎え、労働者や兵士の手っ取り早い養成に迫られた欧米各国が、小学校に採用したのである。貴族たちは相変わらず家庭教師の個人指導を受けていた。平成一六年にドイツ城郭協会会長のザイン侯爵をその居城に訪ねたが、ハプスブルク家出身の城主夫人が述べた言葉「小学校には行かず家庭教師が来てくれました。両親からは家の誇りを忘れず、将来どこに住んでも土地の社会に貢献することを心がけるようにと教えられました」が、印象に残っている。夫人は城の隣で、自ら「チョウの生態博物館」を運営しておられた。
和歌と砲術が結ぶ三里と坂本家
さきに上げたように種崎の御船倉御用商人・川島春麿は楠瀬大枝に国学・和歌を学び、近所の杉本清陰や中城直守だけでなく、城下に住む龍馬の父坂本八平などとも歌人仲間であった。おそらく川島家と坂本家は廻漕業と商家として、業務上の繋がりも深かったと思われる。中城家も、大廻御船頭として土佐から江戸への藩船を操船、藩士やさまざまな物産を運んでいた。この三者は当然、仕事・和歌の双方で親しい仲だった。
三里にはこの時代の歌人に坂本春樹などもおり、和歌のサロンが出来ていたように思われる。そして、川島家の記録にあるように、坂本八平など城下の和歌仲間とも交流していた。『万葉集古義』で知られる国学者・鹿持雅澄も妻菊が仁井田郷吹井の出であり、仁井田・種崎をたびたび訪ねてこれら歌人と歌を贈りあっている。
中城直守は、この土佐の歌人仲間と江戸の歌人とを結ぶ役割もしていたようで、手稿『随筆』には国学者・齊藤彦麿を訪ねて教えを乞い歌を交わしたとある。藩船を運航して江戸に行っては歌人を訪ね、土佐への土産はもっぱら交換・購入した短冊と浮世絵だったと我が家には伝わっている。直守所蔵の短冊は三百人を越す歌人に及び、本居宣長・村田春海・野村望東尼から地元の谷真潮・中岡慎太郎に至る。
このような交流の中で、坂本八平は川島家をしばしば訪ねて早くから伊与を知っており、「思われびと」だったのではないかと山田さんは推測している。いずれにしろ、二人の結婚によって龍馬少年も乙女姉さんとともに川島家をよく訪問したと伝わっており、和歌にも浮世絵にも親しんだのではなかろうか。そして、城下本町の自宅から小舟をこいで鏡川を下り、浦戸湾を種崎に向かうなかで、行き交う藩船や荷船への興味と、海の彼方へのあこがれが芽生えたと思われる。川島家では、村人から「ヨーロッパ」と呼ばれるほど西洋事情に詳しかった春麿から万国地図なども見せられ、胸をときめかした事であろう。
和歌に続いて坂本家と三里を結ぶものに砲術がある。土佐藩では仁井田の浜を公設砲術稽古場としていたが、砲術指南に当たった一人が、徳弘孝蔵(董斎)で、『近世土佐の群像(4)鉄砲術の系譜』(渋谷雅之著)によると天保十二年(一八四一)に一三代藩主山内豊煕の命で下曽根金三郎に入門し、高島流砲術(西洋砲術)の免許皆伝を得ている。徳弘は下士で御持筒役に過ぎなかったが、上士の中には洋式砲術を嫌って藩命拒否の人物もいたなかで、いち早く西洋砲術を習得したのである。
龍馬の父八平は、和式砲術の時代から徳弘孝蔵に入門していたが、龍馬の兄・権平も安政三年(一八五六)に奥義を授けられた記録が残っている。いっぽう龍馬は、従来安政六年徳弘孝蔵に入門とされてきたが、山田さんは『海援隊遺文』で「龍馬、鉄砲修行」の項を立て、詳細な調査から「安政二年洋式砲術稽古、同三年正式入門」とし、安政六年は免許に近い奥許しと見ている。続けて龍馬の成長過程を「嘉永六年十二月一日、十九歳で江戸で佐久間象山に入門、砲術の初学を受け、安政元年六月、二十歳で帰国、河田小龍に航海通商策を説かれ、翌二年十一月、二十一歳、徳弘董斎のもとで砲術稽古…」と、述べている。これに対し、十九歳で高名な佐久間象山にいきなり入門は無理で、それ以前から土佐で砲術の初歩は学んでいたであろうとの説もある。
安政元年、河田小龍に会ったのは小龍が筒奉行池田歓蔵に随行して薩摩に赴き、大砲鋳造技術の視察から帰ったばかりであった。龍馬は江戸でペリーの黒船を見て帰国したところであり、大砲の威力も、外国の軍艦を迎えて攘夷の困難なことも、さらに外国船を購入しての旅客・物資の運輸とそのための人材育成の必要性も、よく理解できた。
龍馬は嘉永六年に江戸修行に出かける二年ほど前から、父や兄に連れられ、仁井田の砲術稽古を見学していたのではないだろうか。そしてその往復には小舟を使い、継母が住んでいた川島家にも寄り、江戸や長崎の新しい情報を聞き、更に川島家の幼い姉妹(喜久と田鶴)や中城直守の長男亀太郎少年(直楯)とも遊んだであろう。
坂本家は商家から郷士に転じただけに、古来の武士が剣術や槍術にこだわって銃砲術を蔑視したのに対し、早くから兵器としての威力を認め、その習得に取り組んできた。伝統的な和歌を好む反面、実利的合理的判断の出来る家庭で文明の利器にも敏感であった。この気質は、種崎・仁井田で古くから海運・造船に従事してきた人々とも共通するところが多かった。
このような風土から有名な龍馬のエピソード、「太刀→短刀→ピストル→万国公法」が生まれた。時代の変化に即応した所持品の更新であり、思考の更新である。実践でも龍馬は寺田屋でピストルを使って捕手の襲撃を防ぎ、第二次長州戦争では桜島丸に乗船して幕府軍への砲撃を指揮、慶応三年の帰郷では新鋭のエンフィールド銃千挺を土佐藩にもたらしている。
龍馬は、和歌で文章表現力とともに王朝人の雅や気概を、砲術で国内統一と欧米列強への軍事的対応策を、身に付けたのだ。
龍馬最後の帰郷と土佐のお龍
慶応三年の龍馬最後の帰郷と三里の人々、そして土佐に来たお龍の姿に簡単に触れておこう。九月二三日に蒸気船震天丸で浦戸湾に入った龍馬は、袙(あこめ)の袂石(たもといし)に停泊させ、小舟で種崎・中の桟橋に上陸すると、裏の竹やぶをくぐって中城家にはいった。当日は仁井田神社の神事(じんじ)で、人の出入りが多い表門は避けたのだ。中城家では、直守が御軍艦奉行による旧格切り替えに御船方仲間を糾合して反対したため、格禄を召し上げられ、長男直楯(亀太郎)に家を継がせたところであった。
城下の実家に直接入らなかったのは、土佐藩の政策が勤王か佐幕か明確になっておらず、持ち帰った最新式の銃千挺を土佐藩が倒幕に備えて受け入れるかどうか不安があったからだ。頼りの後藤象二郎は上京中であった。そこで、藩の方針が決まるまでは馴染みの多い種崎に潜伏した。川島家は、安政地震の津波で被害を受け、仁井田に転居していた。
中城家では直楯が龍馬一行を「離れ」に案内し、妻の早苗が世話をした。滞在中の様子は、直楯の長男直正が後に両親から聞き出し、覚書『随聞随録』に記載してある。これも山田さんはじめ多くの研究者が引用している。
龍馬はこの際に、川島家の屋敷跡にあった小島家も訪問している。小島家には少年時代に可愛がった川島家の妹娘・田鶴が嫁入っていたのだ。この家で、折良く来ていた土居楠五郎(日根野道場で指導を受けた師範代)とその孫・木岡一とも会っている。後に木岡が述べた回想が、『村のことども』(昭和七年 三里尋常高等小学校刊)にあり、土産にもらったギヤマンの図まで掲載してある。円形の鏡でPARISの文字を月桂樹の小枝が囲んでいる。このわずか二ヶ月足らず後に龍馬は不帰の人となっただけに、忘れ得ぬ思い出になったであろう。
龍馬の妻お龍も夫の亡き後、その遺言に従って妹起美を海援隊幹部・菅野覚兵衛(千屋寅之助)と長崎で結婚させ、明治元年春には土佐の坂本家にはいる。しかし、権平とうまくいかなかったのか、夏には和喰村(現芸西村和食)に帰っていた菅野夫妻の実家・千屋に身を寄せる。ここでお龍に可愛がってもらったのが十一歳ごろだった仲(覚兵衛の兄富之助の長女)で、中城直顕(直守の三男、私の祖父)の後妻に来てからその思い出を高知新聞記者に語っている。
そこには、龍馬遺愛の短銃でスズメを撃って遊び、人に見せたくないと龍馬からの手紙をすっかり焼き捨てたことから、お龍さんへの「あんな良い人はまたとない」という回想まである。日付は昭和一六年五月二五日で、記者は私の母冨美の弟岡林亀であった。この記事は、中城家から『坂本龍馬全集』にも提供した。菅野のアメリカ留学によって、明治二年お龍は土佐を去るが、別れに際し仲への記念に龍馬から贈られた帯留を譲っている。龍を刻んだ愛刀の目貫止めと下げ緒で作ってあり、中城家の娘の嫁ぎ先に代々受け継がれている。
最後に、『汗血千里駒』の冒頭で扱われた井口村刃傷事件と龍馬の関係に触れておこう。多くの研究者はこの事件に龍馬は参加していないとしてきた。山田さんは、寺田寅彦の父寺田利正が事件の当時者である下士・宇賀喜久馬(十九歳)の兄であり、寺田家には喜久馬切腹の介錯をしたのは利正で、上士二人を斬った池田虎之進と宇賀の切腹で収拾を図ったのは龍馬だったとの話が、密かに伝えられてきた事を明らかにしている。切腹は、武士としての面目が立つ自死であった。龍馬が関与したとの説は、元高知県立図書館長・川村源七がかつて唱えており、山田さんがそれを立証している。
坂崎が『汗血千里駒』を執筆した明治一六年には、城下を揺るがせたこの大事件の関係者も数多く生存しており、冒頭に持ってきたのは龍馬関与に自信があったからであろう。明治二○年高知座でのこの作品の上演でも、井口村刃傷事件が中心であり、大好評であった。坂崎の龍馬本の虚実と、政治小説としての正当な評価は今後も追及すべき課題である。
おわりに
坂本龍馬は、恵まれた家庭環境で家族の指導のもと、読み書き計算を自学自習で学び、そこから自ら学ぶ意欲と新しい課題にチャレンジする喜びを身に付け、成長していった。学びの場は、日常生活を過ごす家庭・地域から、城下の剣道道場や鏡川での水練、さらに仁井田の砲術稽古、そして江戸の千葉道場・佐久間象山の塾、神戸・長崎へと広がっていった。この間、和歌を学び歌も詠んだが、現実とは遊離しがちな漢学・漢籍には深入りしなかった。
代わりに川島春麿や河田小龍、江戸では佐久間象山や勝海舟など、当時の最新の情報と学識を持つ人々に接していった。また、種崎・仁井田の御船倉や砲術稽古の現場も訪ね、江戸では黒船警護の品川台場にも動員された。このような現場での見学や体験の積み重ねが、神戸での海軍操練所開設や長崎での亀山社中・海援隊結成で、花咲くことになる。
なかでも青少年時代に、御船倉の周辺で見た活発な船の行き来や種崎・仁井田の沖に広がる太平洋の大海原は、大きな影響を与えたと思われる。船は江戸・上方はもとより、長崎・下関・薩摩などから、様々な物産と情報をもたらしてきた。情報の一端は中城直守が文政から明治期まで記した『随筆』でも知ることができる。龍馬は、長崎とも取引をしていた川島春麿からの異国情報を、目を輝かせて聞いたのであろう。
寺子屋にはほとんど行かなくても、豊かな生活環境のなかで自学自習を行い、自ら学ぶ喜びに目覚めていったのである。後に愚童と呼ばれた「龍馬の学び」にこそ、教科書中心の一斉授業とテストに明け暮れる現代の教育病理を克服する鍵があるようだ。(註 引用文は現代用語に変えてある)
(本稿は『大平山』第三八号 平成二四年三月 三里史談会刊よりの転載である) 今こんなことをしています
『江戸時代子ども遊び大事典』と中国版画展の反響
新聞でも、中国版画展が5月13日の神奈川新聞、5月21日の朝日新聞で、大事典が5月24日の高知新聞で、紹介されましたので、記事を添付致します。中国版画展は神奈川新聞に記載のとおり私のコレクションで、今回が初公開です。6月29日まで開催しておりますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。
勉強志向の例としては海外留学を希望する傾向もあります。部活動を1年休部して留学し、留学終了後また部に戻ることもあります。この様な傾向は、企業活動の国際化と就職難という現在の学生を取り巻く環境と無縁でないと思います。我々の時代では1年のブランクを空けた後、部活動を継続することは考えられませんでした。この様な現役学生に対して、OBたちの評価も分かれます。「部に全力投球しない姿に物足りなさを感じる。」「学生の本分を全うした上で、部活動でもそれなりの成果を上げているのだから大したものだ。」どちらの意見ももっともですが、時代環境に関わらず全力を出し切っていれば評価したいと思います。
『高知城「御築城記」とその後の穴太衆』と『NHK番組紹介』
『城郭ニュース』125号に書いた高知城の原稿で、誌面のデータを別送しますので、
そのまま掲載頂けると有難いです。城郭協会には、転載の了解を得てあります。
もう一つはNHKの番組紹介で、このホームページがきっかけで、協力することになった番組 です。以下の文章をお願いします。放送までの短期間ですので、メンバーへのメールでも結 構です。
<お知らせ>
NHKに公文公先生の師弟関係が登場!
NHK総合テレビ12月19日夜10時放映の「ファミリーヒストリー山本寛斎」に、公文公先生(7回 生・公文式教育の創始者)と、山本寛斎氏の父・山本一男さんの師弟関係が紹介されます。 そのきっかけは向陽プレスクラブのホームページです。私が書いた「海辺から龍馬の実像を 発掘」の中で、海南中学で師弟関係にあったお二人の、東京での50年後の再会を紹介しまし た。山本さんは、公文先生が阪大を卒業した昭和11年、最初に赴任した海南での最初の教 え子の一人です。
これがNHK取材班の目にとまり、土佐高経由で筆者への取材依頼があり、協力致しました。 画面にはわずかしか出ないと思いますが、KPCホームページの情報発信力と、NHKの丹念 な情報収集に改めて驚かされました。山本家の家族関係も、驚きの連続です。
身辺整理に専念します
今朝8時過ぎにテレ朝を付けたら、堀内稔久弁護士(KPC会員・32回生)の顔が映っていてビックリしました。先月バイクに乗っていて事故死した萩原流行さんの死因に関し、警察対応に不信の念を抱いた奥様と、真相究明にあたっているそうです。
萩原さんは、昨年亡くなった竹邑類さん(35回生)が若き日に立ち上げた劇団ザ・スーパー・カムパ二イの看板俳優で、招待いただいてよく舞台を楽しみました。
竹邑さんは、ミュージカルなど舞台芸術の改革者でしたが、昨年『呵呵大将 我が友、三島由紀夫』を置き土産に、旅立ちました。才能あふれる芸術家であり、自由人でした。
堀内弁護士はじめ、みなさまの活躍を願っています。
先月の総会は、滋賀県立近代美術館での講演と重なり失礼しました。体力が衰え、浮世絵関連のおしゃべりも今月末の「東洋思想・・・」研究会での発表を最後に辞め、お迎えに備えての身辺整理に専念します。今日が七十代最後の誕生日です。 龍馬最後の帰郷と種崎潜伏
慶応三年(一八六七)九月、坂本龍馬が最後の帰郷をした際に高知市種崎に潜伏したことは、昭和七年三里尋常高等小学校刊の『村のことども』で紹介されているが、郷土の記録を綿密に掘り起こしたのは山田一郎であった。本稿ではその成果を活用しつつ、高知市民図書館「中城文庫」に収録された中城直守・直楯親子の原史料を極力提示し、龍馬の種崎での行動の意義とその時代的背景を明らかにしたい。ここに示した「龍馬役者絵」は、明治二○年に高知座で初めて上演された「坂本龍馬一代記」の役者絵である。なお、文中で古文書引用の際には、読み下し文に直してある。
車輪船沖遠く来たり
坂本龍馬の乗った芸州藩震天丸が慶応三年九月二三日、種崎沖に現われたのをいち早く発見したのは、中城直守(助蔵)であった。彼は文政十年(一八二七)以来、『随筆』と題する筆録を死の前年明治十年まで五十年にわたって書き続けてきた。その慶応三年の項に、「九月二十五日早朝、車輪船沖遠く来たり。而して碇を下ろす。午時(正午)に袙渡合に入る。而して碇泊。芸州船の由」とある。
直守は四年前の文久三年に、御軍艦奉行の旧格切り替えによる江戸雇いの車輪船乗員と旧来の御船手方のあまりの待遇格差に反発、種崎の松原に同志を糾合、先頭に立って連判状をつくり、反対運動を展開した。このために格禄を召上げられたが、慶応元年に長男・直楯による大廻御船頭継承が許された。隠居ながら、早朝には沖(太平洋)を見に家を出る習慣だったようで、舷側の車輪を回して走る蒸気船を発見したのだ。船が港外にいったん投錨後、浦戸湾に入って種崎の対岸にある御畳瀬の袙に碇泊するまでを見届けている。山田一郎は当日の月齢を調べ、港外で投錨したのは満潮を待つためであり、二五日としてある震天丸の来航は実は二三日であったと『坂本龍馬―隠された肖像―』で述べている。なお大廻御船頭とは、土佐から江戸へ直行する五百石ほどの帆走藩船の船長格であり、大坂までの小廻御船頭と区別していた。ともに下級武士・下士である。
直守の『随筆』には、震天丸発見当時の様子に続けて、「才谷梅次郎・中島作太郎・小沢庄次等三人、使者の趣をもって上陸、夜に入り梅次郎(空白)二人吸江の亭に行く、渡辺弥久馬と対談あるの由なるを、弥久馬故ありて来ず、金子平十郎来たれる由也、すこぶる皇国に関係するところの大儀なる趣のよし、梅次郎は実は坂本龍馬なり。今この人、皇国周旋の事件に付きすこぶる名誉ありて海内の英雄ととなう」とある。『随筆』には数日間の出来事をいちいち日を追わずに記載してあり、この部分も龍馬たちの入港当日の動きだけではない。文中人物の中島は海援隊士、小沢は三条実美の家臣・戸田雅楽、渡辺は土佐藩仕置役、金子は山内容堂側用役であった。
最も注目すべきは、「皇国周旋の事件」に触れていることだ。これは、慶応三年六月に「夕顔」船上で龍馬が後藤象二郎に説いてまとめ、長岡謙吉に執筆させた大政奉還の建議で、後に「船中八策」と呼ばれる。後藤はこれを山内容堂に示し、同意を得た上で九月一日から京に上っていた。「土佐藩政録」には、「九月、山内豊信(藩主)天下の形勢日にせまるを見て、後藤象二郎をして上京せしめ、書を幕府に上り、土地兵馬の大権を朝廷に奉還し、王政を復古し、ひろく衆議を採り、富国強兵の鴻基(天皇の大事業の基礎)を建て、万国と信義を以て交際を結ばんことを請う」とある。九月に入り、薩長は大政奉還を幕府が拒んだ場合にそなえて兵を上京させ、武力蜂起の準備をしていた。土佐藩にも建白書提出にとどまらず、武装強化・兵員上京という武力行使の準備を促すための帰国であった。
才谷は色黒、満面よみあざ
直守は全く触れていないが、龍馬が帰郷したこの日、中城家には龍馬から震天丸に迎えに来て欲しいとの知らせが届いたようで、直楯は小舟をこぎ寄せ、密かに龍馬一行を中城家に案内していた。その記録は、直楯の長男・中城直正(初代高知県立図書館長)が、残した『随聞随録』(明治四○年筆記)にある。母・早苗からの聞書である。
「坂本龍馬 才谷梅太郎。母二二の時、直正出生の前年来宅(母妊娠五ヶ月の時)、一絃琴を玩べり。坂本は権平の弟にして郷士御用人、本丁に住す。才谷は色黒、満面よみあざ(そばかす)あり。惣髪にて羽二重紋付羽織袴。[白き絽なる縞の小倉袴]梨地大小(打刀と脇差)、髪うすく、柔和の姿なり」。続いて小沢・中島などの姿・容貌にも触れ、「氏神神事の日(旧九月二三日)に来宅。旧浴室にて入浴。いずれも言語少なし」とある。
「当時坂本は小銃を芸州藩の船に積込み、佐々木(高行)に面会のために土佐へ来たれり。本船は(袙にある)袂石のところに着く。父上(直楯)、その朝召に応じて出で行かれしが、能勢作太郎(後・楠左衛門、平田為七の甥)と共に一行を案内して薮の方より宅に導きしなり」。
これが聞き書きの前半である。氏神とあるのは、仁井田神社(高知市仁井田)であり、神事とはその秋祭りの日であった。「その朝召に応じて」とあるが、だれから呼ばれたのかは記載がない。おそらく、才谷(坂本)からと記した依頼状が届いたのであろう。では、なぜ直楯が呼ばれ、またすぐ迎えに向かったのだろう。それは安政地震まで中城家の六、七軒東にあった御船倉御用商人・川島家と、坂本家との繋がりによると山田一郎は述べている。
この三家(坂本・川島・中城)の当主は和歌で結ばれており、川島に残る『六百番歌合』には、種崎の歌人として知られる杉本清陰・川島春麿(春満・通称猪三郎)、そして中城直守とともに、龍馬の父・坂本直足(郷士)の名が記されている。坂本家と川島家は歌で結ばれていただけでなく、妻を亡くした八平の後添いに、やはり川島家に嫁入りしたが未亡人になっていた北代伊与が迎えられた。龍馬十二歳の時である。「故に龍馬は幼時その姉(おとめ)とともに、たびたび川島家に遊びたり」と、『村のことども』で川島家の親戚・木岡一は語っている。直楯は龍馬より六歳下であるが、川島家の子どもたちとともに、龍馬に遊んでもらった仲と思われる。
今回の龍馬帰郷は、後藤象二郎の斡旋で二月に脱藩罪が許され、四月には土佐海援隊長に任命された後とはいえ、藩内には反勤王・反後藤の根強い勢力もあった。ライフル銃千挺を運んで、幕府が大政奉還に応じない場合は土佐藩に決起するよう奮起をうながすのは、危険な交渉であった。しかも同志・後藤は京におり、まずは城下から離れた種崎に潜伏、使いを出して打診せざるを得なかった。本来なら身を隠すには川島家に頼るところだが、安政元年の大地震で種崎は津波の被害を受け、川島家は安全な仁井田へ移転していた。そこで、幼なじみの直楯を頼ったのであろう。この時、直楯は二五歳、前年に村内の医師・浜田井作(収吾)の娘・早苗と結婚したばかりであった。井作は直守の実弟だが浜田に婿養子で迎えられた身で、直楯・早苗はいとこ同士の結婚であった。
土藩論を奮起せしめんと帰国
直楯は龍馬たちを乗せた小舟を種崎の〈中の桟橋〉に着けると、裏の竹やぶの方から中城家に案内した(地図参照)。中の桟橋は、仁井田から桂浜に向かって浦戸湾口に突き出た砂嘴・種崎の中ほど浦戸湾側にあり、安政地震まではすぐ側に川島家の屋敷があった。龍馬にとってはおなじみの土地だ。桟橋からの道はやがて大道りと交差、左折してしばらく行くと左側に中城家の表門がある。しかし、この日は仁井田神社の秋祭りで表通りは人の行き来が多いため、浦戸湾沿いの裏通りを進み、竹やぶの小道を抜けて中城家の離れに案内している。この竹やぶは、筆者の少年時代まであったが、藩政時代に仁井田浦の土佐藩御船倉と種崎の民家をさえぎるために植えられたと聞いていた。では、『随聞随録』にもどろう。
「父上先に入り、坂本、中島が、まだ湯は沸いておるかと云いしに、皆入浴せし後なりしが再び沸かせり。坂本は、(当時、時勢切迫の時期を気遣い)土藩論を奮起せしめんとて帰国せしなり。祖父(直守)に叔父(直顕)のブッサキ羽織を着せたり。 宴会の席にて御歩行・松原長次、しきりにしゃべりおりたり。一同茶の間にて食事、小沢は自ら井戸をくむ。中島は津野へ、坂本は小島へ寄り、舟へ帰るとて宅を出たり。小沢の宿は紺屋広次方なり。浜田祖父(医師・早苗の父)診察す。
二、三日間、母は湯の加減等をなせり。坂本氏より鏡をもらいしと云う。坂本は入浴後、裏の部屋に休息 [雑踏を避けしなるべし]、襖の張付けを見居りたり。母火鉢をもち行しに〈誠に図らずも御世話になります〉といえり」。
この聞書からは、当初言葉も少なかった一行が、入浴後の食事の席では、幾分くつろぐ様子がうかがえる。ただ饒舌な松原に対し、寡黙だった龍馬の姿には内に秘めた決意の重さが感じられる。山田一郎は、「早苗はこの年二二歳で、妊娠五ヶ月、直正をみごもっていたが、その記憶力はすばらしい。彼女は龍馬をはじめ全員の風貌、服装まで鮮やかに再現して語っている。特に龍馬の言葉やものごしまで、これほどリアルに伝えている文章を読んだことがない」と観察眼を評価している。早苗にとって、天下の国事に奔走する龍馬の姿には、強く惹かれるものが感じられたのであろう。 直楯は、神事(神祭)で来客の多い表座敷は避け、裏の離れに案内している。
この離れは今に残っている(写真参照)。龍馬が見た浮世絵を張付けた襖二枚も、昭和末まで使ってきたが高知市民図書館に寄贈、「中城文庫」に納まっている。浮世絵は、江戸後期の人気絵師であった国貞(豊国三代)や国芳の美しい源氏絵(三枚続)が中心であり、直守や直楯の江戸土産であった。龍馬が浮世絵好きであったことは、明治二九年刊『坂本龍馬』(弘松宣枝著)や昭和十二年刊『土佐を語る』(重松実男編著)でも述べられている。母・早苗がもらった鏡は失われたが、同じ鏡の図が『村のことども』にある。直経六㌢弱の円形で、裏面は月桂樹の小枝の中央にPARISの文字を刻んである。フランスからの輸入品であろう。
中城家では表座敷を避けただけでなく、かなり用心した様子が、直守にブッサキ羽織を着せたことで読み取れる。打裂羽織とは、帯刀に便利なように背縫いの下半分を縫い合わせていない武士の羽織である。「時勢切迫・土藩論を奮起」の文面には、大政奉還建議をひかえ、武装蜂起の決断がいまだ出来ない土佐藩への、龍馬の苛立ちが読み取れる。 聞書に「坂本は小島へ寄り、舟へ帰るとて宅を出たり」とある。当時、中の桟橋の川島家屋敷跡に住んでいた小島家の様子は『村のことども』にあり、九歳だった木岡一の談話として記されている。「外祖父・土居楠五郎氏(日根野氏門における龍馬の兄弟子)とともに、種崎神祭小島氏宅へ行きしに夕刻突然龍馬来たりしなり、・・・その夜土居氏との対面実に劇的シーンなりしも、少年一は偉丈夫なんぞ涙するや、と思いしという。・・・少年一がギヤマンの鏡を土産としてもらいしは、この夜なり」。
当時の小島家当主・亀次郎は山内容堂の秘書役をしており、妻の千蘇は川島家の出、嫡男・玄吉の妻・田鶴もまた川島家から迎えていた。田鶴は、幼い頃から龍馬を慕っていたとされるが、この時は結婚して二年目、まだ十九歳であった。二人の再会の様子は伝わっていない。また、亀次郎の妹・直は、医師・今井幸純と結婚、その子が龍馬の秘書役を務めた海援隊士・長岡謙吉(今井純正)であった。(小島家については、田鶴の曾孫・小島八千代さんから平成十四年にいただいた「小島家系図」による。)
湯かげんや小舟こぎで支えた夫妻
龍馬は種崎に潜伏し、土佐藩との交渉を進める。九月二四日に潜伏先から仕置役・渡辺弥久馬(後の斎藤利行)に出した手紙が残っている。「・・・手銃一千挺、芸州蒸汽船に積込み候て、浦戸の相廻し申し候。参りがけ下関に立ち寄り申し候所、京師の急報これあり候所、中々さしせまり候勢い、一変動これあり候も、今月末より来月初めのよう相聞こえ申し候、二十六日頃は薩州の兵は二大隊上京、その節長洲人数も上坂(是も三大隊ばかりとも存ぜられ候)との約定相成り申し候。小弟、下関に居の日、薩・大久保一蔵、長に使者に来たり、同国の蒸汽船を以て本国に帰り申し候。御国(土佐)の勢いはいかに御座候や、また後藤参政はいかが候や、(京師の周旋駆馳、下関にてうけたまわり、実に苦心に御座候)。乾氏(板垣退助)はいかがに候や、早々拝顔の上、万情申し述べたく一刻を争いて急報奉り候。謹言 坂本龍馬 渡辺先生」。(『坂本龍馬関係文書』)
こうして龍馬は種崎から小舟で使者を出し、土佐藩の首脳と交渉、数度にわたる会見の末、ついに二七日の土佐藩評定によって、大政奉還の確認と武力討伐に備えてのライフル銃千挺の買い上げが決定した。『随聞随録』に、「二、三日間、母は湯の加減等をなせり」とあり、中城家には二、三回来たようだ。土佐藩との交渉は初めは吸江(五台山)や松の鼻(常盤町)の茶店で隠密に行われたが、やがて城下の役宅に席を移す。この間、袙の震天丸・種崎の中城家・吸江や松の鼻、さらに高知城下の土佐藩役宅を結ぶのは、浦戸湾と江の口川・鏡川などの河川であり、御船頭の中城直楯とその配下が小舟をあやつり、上げ潮・引き潮の流れを読みながら、巧にこぎ渡ったと思われる。 龍馬は念願の交渉をまとめ、本町の坂本家にも帰って家族と再会したが、十月一日には慌ただしく震天丸で大坂をめざして浦戸を出港する。中城直守の『随筆』には、「朔日朝、右艦(震天丸)浦戸を出つ」とあり、種崎の浜では、中城直守たちが見送ったことであろう。荒天のなか室戸沖まで進んだが、荒れ狂う波浪に翻弄されて船体を破損、いったん須崎に避難、五日土佐藩差し回しの蒸汽船胡蝶で再度出港する。
龍馬は十月九日に京都に到着、その四日後の十三日に徳川慶喜が二条城で大政奉還を表明する。この日、建白書受諾の知らせが届く以前に龍馬が後藤象二郎に出した手紙には、「建白の儀、万一行われざれば、もとより必死の御覚悟ゆえ、(先生が二条城から)御下城無の時は、海援隊一手を以て、大樹(将軍が御所へ)参内の道路に待ち受け、社稷(国家)のため不(倶)載天の讐を報じ、事の正否に論なく先生に地下に御面会仕り候」とある。建白書が受諾されない場合は、「後藤は二条城で切腹するだろうから、自分は海援隊を率いて御所参内の将軍に報復、あの世で会おう」と、決死の覚悟を記したものだ。
ところが大政奉還受諾のこの日、朝廷は薩長に倒幕の密勅を下す。徳川慶喜の決断に感激したとされる龍馬は、密勅など知らぬまま十一月二日には福井に三岡八郎(由利公正)をたずね、国の財政策を授かる。新政府の実現に懸命に働くが、十五日に京都近江屋で中岡慎太郎と面談中、刺客に襲われ横死する。 中城直守には十一月末に知らせが届く。『随筆』に「坂本龍馬、先だって御国に来たり。密かに周旋の意趣あり候後、京師に登り旅宿に居るある夜、国元より書状来たれりとて旅宿をたたく者あり。この宿の召使いの者、出てすなわち書状を受取り来たり龍馬に渡す。龍馬何心もなく披見するところに、外より忽然として五、六人入り来たるや否や抜打ちに一同無二無三に切付ける。無刀にてあしらう内、深手処々に負いて死す。・・・この来る者は関東よりの業にして、さるべき壮勇の浪士を雇いてかく切害せしとも、いずれ確かならず。今、海内に名を轟かし、殊に御国のため力を尽くせし龍馬なる者を、ああ惜しむべし惜しむべし。なお詳しき事聞きたし」と記し、慨嘆している。 直楯の『随筆』には、吉村虎太郎たち天誅組の大和での壊滅、武市半平太の獄死などについては、無念の思いは秘めて淡々と記録してあるが、龍馬殺害の知らせにだけは、「ああ惜しむべし惜しむべし」と、心情を率直に吐露している。
大政奉還へ!龍馬奮戦の足跡
龍馬最後の帰郷は、大政奉還による近代日本誕生への最後の布石のためであった。幕府への土佐藩からの建白書提出には、拒否されないよう薩長とともに武装蜂起も辞さない軍事態勢の誇示も必要だった。これは単なる土佐藩びいきの提案ではなく、薩長のみでの倒幕への暴走を防ぎ、王政復古をとなえつつ、平和裏に近代国家建設を成し遂げるための妙案でもあった。
「日本を今一度せんたくいたし申し候・・・」(文久三年)と考えた龍馬が、その最後の施策として、土佐藩による大政奉還を迫った舞台が、少年時代から慣れ親しんだ浦戸湾であり、種崎であった。その現状を簡単に報告して稿を終えたい。
種崎の太平洋に面した海岸は、今に松林が広がり千松公園となっているが、黒船に備えて造られた台場(砲台)のあとは砂に埋もれて消えた。龍馬の乗った震天丸が通った湾口には、浦戸大橋がかかり、桂浜と結ばれている。種崎の先端は、昭和四一年からの航路拡張工事で切り取られ、御畳瀬の名勝・狭島も除去された。しかし、震天丸が碇泊した袙の海岸は幕末の風情を今にとどめており、袂石も健在である。
袂石から龍馬たちが小舟で渡って上陸した中の桟橋は、昭和三十年代からの自動車の発達によって役割を終え、地名のみ残った。龍馬が歩いた湾岸の景観も、中洲の埋め立て、竹やぶ・桃畑・空き地の宅地化などによって、すっかり変貌した。わずかに龍馬が潜伏した中城家の離れのみは、老朽化したが残っており、平成二二年のNHK大河ドラマ『龍馬伝』でも、「龍馬伝紀行」の中で紹介された。龍馬がその志の実現に向けて、決死の行動をとった土佐での最後の舞台であり、三里史談会有志の協力もいただいて保存に努めている。
龍馬潜伏にかかわった中城直楯は、その後陸軍築城掛となり、和歌を楽しみつつ東京・広島・新潟などで勤務し、明治二二年陸軍歩兵大尉で退任、明治二七年に種崎に帰郷する。長男直正に母・早苗が龍馬潜伏の状況を語ったのは同四○年、写真はその頃の夫妻である。
主要参考文献
『中城文庫 目録・索引編』『中城文庫 図版・解説編』高知市教育委員会 二○○二、二○○三年刊
『村のことども』三里尋常高等小学校編・発行 一九三二年刊
『坂本龍馬関係文書一、二』北泉社 一九九六年刊
『坂本龍馬―隠された肖像―』山田一郎著 新潮社 一九八七年刊 校歌の謎1への回答
よい質問をいただきました。猛暑の中でも、母校への思いを抱き続けているようで、なによりです。
謎1,の「向陽」の由来のみ、小生の理解するところをお知らせ致します。
「向陽」の出典は、中国古代の漢詩です。諸橋轍次『大漢和辞典』(大修館)に よると、<向陽 陽に向かう。日に向かう。潘岳(247~300 西晋の文学者)の 「閑居賦」、謝霊運(385~433 六朝時代 宋の詩人)の「山居賦」・・・>等の詩 に使われた用例をあげてあります。
土佐中では、校歌より先に「向陽会」(自治修養会)に使われており、これは三根 校長の命名かと思われます。三根校長が東京帝国大学哲学科在学中の哲学教 授は井上哲次郎でドイツ観念論哲学のみならず、漢学・東洋哲学にも精通していました。
また国文の物集高見教授も漢学に通じていました。江戸時代の公文書は漢文で
あり、三根の一年先輩で国史科だった中城直正(高知県立図書館初代館長)も、
漢文・漢詩に強く、桃圃と号して漢詩を詠んでいます。土佐に来た三根校長とも
交流しています。目下、『土佐史談』に依頼され、史談会創立100周年記念号に、
中城直正(遠い親戚)の略伝を執筆中です。
その他の謎についても調べたいところですが、土佐中関連の文献・資料はすべて 土佐校図書室と公文公教育研究所に寄贈し、手元にありません。これらに手掛か りがあるかどうかも不明です。是まで収集した資料は、順次寄贈先を選んで進呈 しています。満州版画は京大人文研が大変喜んでくれました。
公文さんの質問に対して、まず調査担当すべきは土佐校の同窓会担当者かと思 います。三浦先生の後任は、だれでしょうか。母校100年史編纂も進んでいること でもあり、母校の体制を確認下さい。
なお、「向陽高校」は和歌山・京都などいくつかあるようですが、いずれも戦後の 学校統合などで生まれた校名のようです。三根校長には、自治会にいい名称を 付けていただいたと思います。 <合田佐和子さんの思い出>
20世紀美術の先端を駆け抜けたアーティスト
2月23日の新聞で合田さん(34回)の訃報を目にした。19日に心不全で亡くなったとのこと。昨年の日本橋での個展にも本人は姿を見せず、療養中と聞いていたので心配していたが、残念でならない。彼女は絵画だけでなく、寺山修司「天井桟敷」・唐十郎「状況劇場」の舞台美術やポスター、超現実的な人形、ポラロイド写真にも取り組んできた。
土佐高新聞部の仲間として、また同時代の編集者として見てきた、20世紀美術界での彼女の先鋭的なアーティストとしての活躍ぶりが、脳裏に刻まれている。かつて書いた戯文に、本人および関係芸術家の文章なども引用し、しばし追憶に浸りたい。
<新聞部の仲間から> 美術界の異才、合田佐和子/中城正堯『一つの流れ』第8号 1985年刊
合田は新聞部だったので、中学時代からのつき合いになる。やせて眼のギョロッとした文学少女タイプだったが、芯は強い。ガラクタを集めたオブジェから始り、状況劇場や天上桟敷の舞台美術、怪奇幻想画、ポロライドカメラによる顔シリーズ、油彩のスーパーリアリズムと、とどまるところを知らない。
(彼女が武蔵野美術大卒業の際に作品を持って学研にきて以来、時折連絡を取っていた。)舞台で使うプラスチック人形の成型を教えてくれと、ひょっこり訪ねてきたりする。たえず新しいものにチャレンジし、美術界の話題を集めてきた。その才媛ぶりは、瀧口修造や東野芳明から高く評価されている。・・・昨年は、現代女流十人展の一人にも選ばれ、仕事は活発に続けている。
今年正月には銅版画集『銀幕』(美術出版社)を刊行した。手彩オリジナル版画入りの豪華本は、定価30万円である。その出版記念会には、根津甚八、四谷シモン、江波杏子、白石かずこなど、異色の東京ヤクザがかけつけていた。合田はエジプトが気に入り、安い家を買ったとかで、これからは日本と半々でくらすと、いたずらっぽい表情でいっていた。
(これは、土佐高30回Kホームのクラス誌に「東京ヤクザ交友録」として、同窓生の活躍ぶりをカタギとヤクザに分けて紹介した戯文で、芸術家は当然ヤクザとして扱った。)
<合田さんご本人の回想>
『パンドラ』序文/合田佐和子作品集 PARUKO出版 1983年
焼け跡 高校3年の夏休みに、四国山脈をかきわけて上京して以来、もう25年という年月が流れていったらしい。・・・美術界の西も東も分からなかった24才の6月に、はじめて開いた個展での作品は、今にして思えば、戦後の焼け跡の光景そのものだった。それも、近視眼的な子供の眼にうつった、災害のオブジェである。(夏休みに上京、以来東京の叔父の元で過ごし、卒業式だけ帰高出席したという。)
油彩 ニューヨークの裏通りで一枚の写真を拾った。二人の老婆と一人の老人が写っている小さな銀板写真だった。アレ、これはすでに二次元ではないか、これをそのままキャンバスに写しかえれば問題は、一方的に一時的に解決する。(立体オブジェにこだわり、立体を平面に写す油彩を躊躇していた合田は、拾った写真にインスピレーションを得て独創的なスター肖像画を生み出す。美大で商業デザイン科だった合田は、油絵の実技教育を受けておらず、独学で修得したと述べている。)
エジプト 1978年秋の個展作品を、肩から包帯をつるした腕で仕上げると、息もたえだえ子供二人を連れて半ばやけ気味でエジプトへ発った。(彼女はアスワンの村でくらし、「全部の病気を砂に返し、暖かいぬくもりだけを全身に吸い込んで東京に戻る」と、古代エジプトの守護神ホルスに惹かれたのか、目玉をモチーフに立体も平面も制作、『眼玉のハーレム』(PARUKO出版)を刊行する。後に中上健次の朝日新聞連載「軽蔑」では、毎回眼だけの挿絵を描いた。)
<仲間の賛辞>
恋のミイラ/唐十郎 合田佐和子個展カタログ 1975年
これらは、初めて仮面舞踏会につれてこられた少女の、ほのかなためらいと頬の紅潮を画布に移行させたものだろうか。・・・これらはドリームにドリームを塗りつぶした暗い恋のタブローである。こんな絵に囲まれながら、そこで、誰かと誰かの恋が結ばれたらどうしよう。
ぼくらのマドンナ/『銀幕』出版記念会案内状/四谷シモン 1985年
当代きっての才媛、ぼくらのマドンナ、佐和子が、突如、この夏の猛暑のさなか、銅版画の制作にのめりこみ、レンブラント、デューラーもものかは、銅と腐蝕液の異臭のなかから電光石火の早技で「月光写真」の如き「銀幕のスターたち」を誕生させました。・・・ぼくらのマドンナを囲み、歓談に花を咲かせたいと思います。
焼け跡に舞い降りた死の使者/坂東眞砂子(51回)『合田佐和子』高知県立美術館 2001年
八十年代に入り、合田佐和子は初期の焼け跡を連想させるオブジェと、人骨を組み合わせた作品を創りはじめる。ここにおいて、敗戦、焼け跡と、死が作品上で、明白に重ねあわされていく。・・・合田佐和子が描いてきた銀幕スターたちとは、戦後の日本に死をもたらした、死の使者たちだったのだ。彼らは大鎌の代わりに、セックス・アピールという武器を手にして、日本社会に乗りこんできた。その青ざめた皮膚の下にあるのは、骨。銀幕スターのきらめきの下に隠されているのは、骸骨であったのだ。
<わが追憶>
合田さんと思いがけず出会ったのは、1992年2月小松空港行きの機中であった。前の席に座った男女が楽しげにはしゃいでいる。ベルト着用のサインが消え、身を乗り出してみると、二人の若い男性助手を連れた合田さんだった。聞けば翌日から金沢のMROホールで公開制作をするという。仕事の合間をぬって会場に駆けつけると、詰めかけたファンに囲まれ、あざやかな筆さばきで大キャンバスに銀幕のスターを描いていた。
2001年の高知県立美術館「森村泰昌と合田佐和子」展、2003年の東京・渋谷区立松濤美術館「合田佐和子 影像」展でも、オープニングで元気な姿を見せていた。しかし、近年の鎌倉や日本橋の個展会場では、本人と会うことができなかった。5年ほど前に電話で近況を尋ねると、心臓の病をかかえ、思うように制作ができないといいながら、わたしの病気を気遣って、類似の病気を克服した友人・栗本慎一郎(経済人類学者)の治療法を薦めてくれた。
彼女は様々な病気を抱えながら、絶えず新しいテーマと技法にチャレンジし、現代アートの世界で先鋭的な作品を発表し続けてきた。その鋭利な感性に肉体がついて行けず、悲鳴を上げていたのであろう。高知県立美術館での合田展に寄稿をしてくれていた作家・坂東眞砂子さん(51回)に続いての合田さん訃報であり、土佐高で学んだ異能の女流芸術家が相次いで亡くなった。ご冥福をお祈りしたい。
<追記>いずれ「お別れの会」を開く予定で、「天井桟敷」関係者が準備中とのこと。
(作品自体は著作権者の了解が必要なので、印刷物からの画像引用の範囲にした) 『新聞とネット、主役交代が鮮明に』への感想
最近の「新聞報道」へのご意見、報道のあり方を真剣に考えているようで、感心しました。小生の感想をお伝えします。
まず、山尾志桜里議員の首相への質問、たまたまテレビ中継を見ていまし
た。さすが元公文の優秀児らしい、追及ぶりで感心しました。首相の答弁は
かなりおざなりでした。横浜のS先生の教室出身で、生徒の頃の勉強ぶりを
思い出しました。
翌日の新聞ではあまり取上げられていませんでしたが、ネットで火がついて、
新聞は後追いになっていました。
新聞報道のあり方、1.経営理念としての「公正な報道」、2.報道商品の品質 「報道の正確さ」・・・、これらよりも大切なことは、「真実の追及」ではないでしょ うか。「なにが公正か」は立場によって異なり、新聞報道は公正より「真実」を 大事にすべきです。真実の追及なら、反体制も反権力も関係ありません。また 新聞が、体制にどんな姿勢をとるか、各社に違いがあって当然です。
ただ、ミスリードのあった場合は率直に読者に謝る必要があります。かつて事実 に反し、民主党のひどい提灯持ちをした評論家が、今もテレビでしゃべっている のを見るとがっかりです。新聞社も記者も、そして政治家も「けじめ」が必要です。 山尾さんも、タクシーカードについて、真実を明らかにする必要があり、報道 機関には、保育問題の実態と共に、この追及も必要です。
マスコミは、新聞もテレビも花形職業になりすぎ、高学力か有力なコネがないと 入社できず、「真実の追及・報道」に命をかける人材が社内に少なくなりました。 今では活字の世界では週刊誌、それも外注のフリーランス記者の執念によって 特ダネが生まれている実情です。あとは、活字媒体でないネットの世界の活性化 がたよりです。
なお、公文の優秀児とは、在籍学年より先に進んで教材を解く力を付けた生徒で、 山尾さんは小学6年で高校程度に進み、トップグループにいました。同時に、中学 ではミュージカル「アニー」の主役も務め、東大法学部に進みました。
吉川さんはじめ、マスコミ関係者のご意見もお聞きしたいです。 2016年(平成28年)8月22日(月曜日)一高知新聞『所感雑感』
浦戸城趾に"元親やぐら"を
桂浜を訪ねる度に大変残念に思うのは、観光開発の陰で素晴らしい自然景観と史跡が損なわれていることだ。特に、史跡として重要な長宗我部元親の居城「浦戸城」の本丸(詰の段)周辺が、観光道路・国民宿舎・駐車場によって破壊されている。
かつて山内一豊の入国と高知城築城にともない、浦戸城の三重天守は三の丸の櫓となり、石垣はすべて運び出されたとされていた。しかし、山内家「御城築記」に「苦しからざる所はこわし取り」とあるとおり、本丸周辺の石垣はかなり残してあったことが、1991年からの浦戸城址発掘調査で判明した。当時の高知新聞には、「南北総延長約百mにわたる石垣群を発見」とある。石垣は裏込石を使った高石垣であり、瓦や鯱などの出土品もあつて、浦戸城が四国で最も早く「土の城」から脱皮し、天守と高石垣を備えた先駆的「石の城」であつたことを示していた。
ところが、地元民の保存運動にもかかわらず、石垣は調査後に埋め戻され、本丸跡はかえって見苦しい状況となった。しかし、太平洋に突き出た半島の地形を巧みに利用して縄張りされた浦戸城の各曲輪の跡や、堀切・竪堀などはまだ残っている。水軍の基地であった浦戸の漁港や、城下町に組み込まれていた
種崎を含め、浦戸城の遺構を保存しつつ、貴重な高石垣など城址の復元にむかっての長期的取り組みが望まれる。
そして、早急に着手して欲しいのは、本丸跡への"元親やぐら"の建造である。元親にとって浦戸城は、初陣で長浜城に続いて勝ち取った思い出深い城であり、周辺の地形も熟知していた。後に浦戸湾口を本拠地にしたのは、秀吉による朝鮮出兵だけでなく、国内交易にも、堺や薩摩にならっての南蛮貿易にも、造船・海運・水軍が不可欠と考えたからだ。この雄大な構想を育んだのは、城山からの360度の大眺望であろう。南には大空と大海原が果てしなく広がり、北には浦戸湾の彼方に四国山脈がそびえ立つ。
ここに建てた天守は単に湾口の監視塔ではなく、壮大な夢の発想基地であった。
桂浜の魅力は箱庭的海浜ではなく、城山に立って初めて味わえる自然と歴史が織りなす壮大な景観美だ。だが今に残る天守台は、樹林に覆われて展望がきかない。そこで、天守台の隣接地に、丸太組みで浦戸城三重天守と同じ高さの望楼"元親やぐら"を建てることを提案したい。中世から土佐の特産品であった材木を、伝統の技で組み上げ、元親と同じ目線で絶景を楽しみ、潮風や海鳴りを五感で味わって感性を呼び起こし、自らの生き方に思いを馳せる思索の場とするのだ。
<追記>
新聞に掲載後、早速地元の方々から電話をいただきました。その中で気になるのは、従来通りの観光開発がすでに二つも立案されていることです。それは、県立坂本龍馬記念館の新館増設と、高知市による「道の駅」新設で、ともに自然環境・史跡への保護がどれだけ配慮されているか疑問です。今回の原稿が、桂浜および浦戸湾口の自然と史跡の保護活用に役立つ事を願っています。 「公文禎子先生お別れ会」のご報告
土佐中6回生で、戦後土佐高教諭から、大阪に出て公文教育研究会を設立した公文公先生の奥様が逝去された。公文先生は、土佐中での個人別・能力別の自学自習を活かして公文式教育を考案、世界中に公文式教育を広めたが、二人三脚でこの教育法を育てたのが、禎子夫人であった。
禎子夫人の高知での新婚生活は、昭和20年からの1年と、22年からの5年間であったが、その間のエピソードを紹介し、加えて同級生(土佐高30回Oホーム)へのお別れ会報告文を添付する。
高知での公文禎子様
奈良で生まれ育った長井禎子様が、お見合いで公文先生と結婚されたのは、終戦間近の昭和20年3月で、先生は浦戸海軍航空隊教授であった。慣れない高知での新婚生活は、父と兄を亡くして一家の柱となっていた公文先生以外は女ばかりの家族との同居であった。しかも、先生は池(高知市)の航空隊に別居で、訪ねて行こうとしては道に迷って大変だったという。さらに7月には米軍の空襲にあい、たまたま帰省中だった先生と雨のように降りそそぐ焼夷弾の下を逃げまどい、衣笠(公文先生の母の実家・稲生)をめざした。住んでいた家は全焼であった。恐怖にさらされ、一首のうたもつくれなかったと述べている。
戦後、先生はいったん奈良の天理中に勤務、昭和22年に高知に戻り、高知商業を経て、24年に母校土佐中・高教諭となり、3年後に大阪に出る。この間、禎子夫人には高知で思いがけない人物との再会があった。樟蔭女子専門学校時代に、短歌を教わった安部忠三先生が、22年にNHK高知放送局長として着任されたのだ。高知歌人会にも入会、短歌を再開される。この安部局長の長男・弥太郎さんが土佐中28回生で、新聞部の中心となって我々30回生を指導してくださった。後に、京大からNHK記者となって活躍された。
公文夫妻が大阪に出た同年に、安部局長も奈良局長に転任、そのお薦めで前川佐美雄先生が主宰する日本歌人社に入会、うたに励まれ昭和44年には日本歌人賞を受賞する。以来、パリやシルクロードを訪ねてはうたを詠み、平成10年には歌集『パステルカラー』を出版された。
禎子夫人は、短歌以外に美術への造詣も深く、自ら油絵もお描きになった。また読書家で、我々は土佐中時代にご夫妻が所蔵されていた『岩波文庫』などによって、本の世界に導いていただいた。秀才として知られた公文俊平・竹内靖雄両先輩も「公文文庫」を大いに活用しておられた。
3Oホームの皆様へ
6月21日に96歳でお亡くなりになった公文禎子先生「お別れの会」が、9月21日に大阪の公文教育会館で行われ、土佐中1年B組の浅岡建三、武市功両君と共に参列してきたので、その様子をご報告する。
公文式の生徒は、現在世界各国428万人に及ぶが、禎子夫人は公文教育研究会の創始者・公文公先生のご夫人にとどまらず、公文式教室の最初の指導者であり、教材開発・教室運営にともにたずさわってこられた。昭和42年から10年間は公文教育研究会の前身である大阪数学研究会社長、さらに「のびてゆく幼稚園」開園、公文会長亡き後は50回を越える講座を全国で開催し、公文の教育理念を伝えきた。「公文禎子先生 お別れの会」は、公文教育研究会の関係者のみに限定されたが、全国から元指導者・社員、現役指導者・社員あわせて500人を越える方々が集い、献花をしてお別れを惜しんだ。
花祭壇の御遺影に向かって、元社員代表として武市功君(元副社長)が、弔辞を述べた。「禎子様に最初にお目にかかったのは今から67年前、高知市内の御自宅でした。土佐中学で教え子だった私は、数学を習うため御自宅にお邪魔していました。」という出会いから、会社を設立したものの十年余は赤字で、「主人と二人で荷車を引いて参りました。主人が引いて私が押して、やっと坂を上がって参りました」という禎子夫人の回想談をまじえ、追悼した。
最後に、ご親族を代表してお嬢様の新庄真帆子様のご挨拶があった。強く印象に残っているのは、初期のご苦労「父の教材がご近所でも評判になり、母が指導者になって教室を開いた。私たち幼い三人の子どもを育てながらであり、買い物や食事の準備もそこそこに、一人ひとりにちょうどの教材を用意するのは大変だった。なにしろ当時は教材も全て手書きだったから」、であった。
新庄真帆子様には、3O一同これまでの公文先生ご夫妻の御恩が忘れられないことをお伝えした。2000年の大阪同窓会の際に久武慶蔵君が公文公記念館で倒れたが、奥様の看病のお陰で大事に至らなかった事や、「うきぐも」発刊へのご協力に感謝していることを申上げた。また、今後一周忌の墓参など、教え子も参加出来る法事があれば、クラス代表が参列したいとの希望をお伝えした。真帆子様からは、高野(野口)さんか小生に連絡するとのお返事をいただいた。
帰りの新幹線で、公文先生亡き後に禎子夫人がはにかんだ表情で漏らされた、若きお二人のいわばデート時代の思い出話が甦った。「奈良での見合いで婚約が決まりました。私は阪大工学部の研究室に勤務していましたが、ときおり夕方に公文が訪ねて来て、私が出て来るのを、外でじっと待ってくれていました」。 ―平井康三郎、ディック・ミネ、ケーベル博士をめぐって―
三根圓次郎校長とチャイコフスキー
2020年には、土佐中学校創立100周年を迎える。大正9(1920)年の開校にあたっては、発案者の藤崎朋之高知市長や、出資者の川﨑幾三郎・宇田友四郎両氏とともに、「人材育成」という建学の精神に則した学校を創出し、見事な教育実践をおこなった初代・三根圓次郎校長を忘れるわけにはいかない。
三根校長は明治6年長崎県の生まれ、帝国大学文科大学(後の東京帝国大学文学部)の哲学科を出て教職に就き、若くしてすでに佐賀・徳島・山形・新潟の県立中学校長を歴任、東京府立一中(現日比谷高校)の川田正澂(まさずみ)校長(高知県出身)とともに、全国中等教育のリーダーとなっていた。土佐中校長に就任時は47歳であり、帝大で哲学を学んだ謹厳な教育者も、年輪を経て温和な慈父のまなざしを併せ持ち、やがて生徒たちから敬愛をこめて「おとう」と呼ばれる存在になった。
土佐中創立は、第一次世界大戦後の国際化と大正デモクラシーの時代を迎え、国家の期待する新しい「人材育成」を目指すものであった。教育方針には「個人指導」「自学自習」など、時代の先端をゆく斬新な理念が掲げられていた。この理念に基づくカリキュラムの編成や授業展開は、すでに『土佐中學を創った人々』で紹介したので、ここでは割愛する。ただ、創立100周年を迎えるに当たって強調したいのは、「人材育成」「自学自習」などの基本方針も、予科(小学5,6年生)からの英国人講師による英語教育も、時代を先取りしており、グローバル時代を迎えた1世紀後の今日でも、誇りを持って掲げることができる点だ。
今回は三根校長について、新しい観点「音楽を愛した教育哲学者」としての特色を、音楽をめぐる人物模様から紹介したい。土佐中に着任以来、先生は次第に視力を失い、「おとう」と親しまれた晩年には失明状態であった。しかし、この老校長の胸中には、少年の頃手にした横笛の音とともに、チャイコフスキーの音楽が絶えず鳴り響いていたように感じられる。あるときは、「くるみ割り人形」や「白鳥の湖」の軽やかな旋律が、あるときは交響曲第六番「悲愴」の荘厳な調べが、響き渡っていたのではないだろうか。
土佐中初期の卒業生による50周年の座談会で、こんなやりとりが紹介されている。<浜田麟一(6回生)「弁論会をやろうというと、校長はこの学校としては音楽をやろうといった。これはディック・ミネが音楽をやることになったので、自分も関心が音楽の方へ傾いて行ったのでしょうか」。伊野部重一郎(5回生)「校長はクラシックがかなり分かったので、息子が流行歌をやるのをなげいていたのでしょう」。鍋島友亀(3回生)「平井はハーモニカのバンドを作って、公会堂で土佐中公開演奏会をやった。配属将校(軍事教練のために配置された陸軍将校)がなぜ音楽をやるかと問うと、校長は生徒が将来政治家になった時、演説をするために声をきたえるのだと言ったという」>(『創立五十周年記念誌』)
伊野部の発言で、三根校長がクラシック音楽を好んでいたことがうかがえる。なかでもチャイコフスキーに惹かれていたように思われる。それはなぜか、三根校長の周辺に多い、素晴らしい音楽家の探訪からさぐりたい。まずは、平井康三郎(5回生)に代表される教え子たちであり、ついでご子息のディック・ミネである。それぞれ昭和期を代表する作曲家であり流行歌手であったが、今では知る人が少なくなった。この二人の音楽家としての歩みと三根校長の影響、そしてさかのぼって三根が帝大哲学科時代にケーベル教授から受けた哲学・美学の教えをさぐってみたい。この教授は、実はモスクワ音楽院でピアノを修得した名演奏家でもあった。
目 次
<第一章>“作曲家平井康三郎”生みの親
土佐中のピアノやマンドリンにびっくり
明治43年に高知県伊野町で生まれた平井康三郎(保喜・5回生)は、伊野小学校から大正12年に土佐中入学、昭和4年に東京音楽学校へ進学、ヴァイオリン科を終えた後に新設された研究科作曲部へ進んでプリングスハイム氏に師事、在学中の昭和11年には交声曲(カンタータ)「不盡山(ふじやま)をみて」が第5回音楽コンクールで1位に入賞する。代表作に「大いなる哉」「大仏開眼」があり、日本の歌曲「平城山(ひらやま)」「ゆりかご」「スキー(山は白銀)」でも親しまれた。校歌の作曲も多く、甲子園では毎年のように平井の曲が、勝利校を祝して流れた。作曲数は五千におよぶ。東京芸術大学や大阪音楽大学で教授を歴任、この間に文部省音楽教科書の編纂、『作曲指導』の執筆、『日本わらべ歌全集』の監修にもあたった。紫綬褒章など受章し、平成14年に逝去した。
長男丈一朗(たけいちろう)は巨匠カザルスに師事したチェリスト、次男丈二郎はピアニストであり、孫でニューヨーク祝祭管弦楽団音楽監督を務める指揮者の秀明、ロンドンを拠点とするピアニストの元喜ともども国際的に活躍している。康三郎が始めた「詩と音楽の会」も、丈一朗会長のもとで受け継がれている。平成27年には故郷「いの町」の新庁舎に平井康三郎記念ギャラリーがオープンし、寄贈されたグランドピアノなどゆかりの品々が展示され、「いのホール」で丈一朗や元喜による記念コンサートが開かれた。
平井の父は高知商業の国語教諭から実業界に転進したが、音楽好きで商業の壮大な校歌「鵬程万里はてもなく・・・」を作曲、家にはオルガンや蓄音機があった。音楽的に恵まれた家庭で育ち、ハーモニカが得意だった平井少年も、土佐中に入った驚きをこう語っている。
「グランドピアノはあるし、マンドリン・クラブはあるし、びっくりしました。レコードもベートーベンの第九をはじめ、名曲がたくさんある。蓄音機もビクターの最高級品です。ただ、残念ながらピアノを弾ける先生も、レコードを聴く生徒もいない。岡村弘(竹内・1回生)さんと私だけが弾いたり、聴いたりするだけだった」(『南風対談』)
教材・教具の整っていたのは楽器ばかりではない。青山学院を卒業と同時に英語教師として赴任した長谷川正夫は絵画も担当、「校長は画架、石膏像、額縁など私の要求するがままに買ってくれた。絵の時間には潮江山(筆山)に登ってスケッチさせたり、自然を眺めながら絵の講義をしたりして、全く自由にできた。・・・公会堂でマンドリン合奏会を開いたことがあったが、これが(高知での)この種の最初のコンサートであったとか聞いた。私と同期の常盤(正彦、音楽)先生がハーモニカの独奏会を開いたこともあった」(『創立五十周年記念誌』)。本格的な楽器・画材をそろえ、教室にとどまらずに野外授業や校外活動もおこなった。また、男子中学では厳禁だった女学校のバザーや運動会の見物に行くことも許されていた。
三根校長は、これから世界で活躍する人材には、文学や歴史だけでなく音楽や絵画の教養も大切だと考え、その素養がある新卒の長谷川・常盤両先生を採用、設備や教材も整えたのだ。イギリスのパブリックスクールにならって学校内に寄宿舎を用意し、運営は寄宿生の自治にゆだねた。そこでの平井少年の活躍を、五藤政美(4回生)は、昭和16年の「三根先生を偲ぶ座談会」でこう述べている。
「寄宿舎で茶話会をやる。そうすると皆一芸を出すわけで、平井君はハーモニカをやるわけだ、カルメンをやる。平井君はカルメンが巧いので、無論拍手喝采だ。校長先生は、大野(倉之助、数学)先生を顧みて、おれもカルメンなら知っているといっておりましたがねえ」。それを受け、片岡義信(1回生)が「平井君で思い出したが、ぼくらはマンドリンを買ってね、やったのだけれども上手になれなかった。・・・やはり校長も音楽を取り入れなければならんというのでね」と話す。都築宏明(3回生)は、三根校長のお宅(東京都大森)で奥さまに見せていただいた錦の袋に入れた横笛について、「若い時分に吹いたものだというのですね。それから推して考えて見ると、音楽の素養があったわけですね。趣味がないと思ったら多少あったのです」と、語っている。(『三根先生追悼誌』)
校長が父を説得、音楽学校へ
平井は得意のハーモニカで人気者になるとともに、三根校長の指示で1年生の時に早くも「向陽寮歌」の作曲をしている。作詞は岡村弘先輩であった。「向陽の空」で始まる校歌は、すでに越田三郎作詞・弘田龍太郎作曲でできていた。寄宿舎名・寮歌にも、「向陽」が用いられている。これは漢籍に通じていた三根校長が好んだ言葉と思われる。
普通の漢和辞典には登場しないが、諸橋轍次の『大漢和辞典』には「向陽 陽に向かう」とあり、潘岳や謝霊運の詩文を例示してある。「高い望みを抱く」といった意味だ。中学4年生になった平井は、ヴァイオリンをはじめる。自己流ながら腕を上げ、5年生になった昭和3年には、昭和天皇の即位を祝う御大礼奉祝音楽会に、学内の二人の弟子とともに出演している。その写真で分かるように、この時代の制服には白線などない。
平井は、高知県各地から集まった学友を相手に、方言調査もおこなう。音楽とともに言語学に興味を持っており、中学4年生の時には、二百あまりの方言を分類、語源の考証・活用例などを記した「土佐方言辞典」をまとめている。才気あふれる平井の方言研究からは、次のような漢詩の土佐弁による名訳も生まれる。
俺も思わくがあって都(かみ)へ出たきに (男子志を立てて郷関を出ず)
成功者(もの)に成らざったら死んだち帰(い)なんぜよ (学若し成らずんば死すとも帰らず)
ナンチャー どこで死んだち構(かま)んじゃないかよ (骨を埋む豈(あに)墳墓の地のみならんや)
どこへ行ったち おまん 墓地ゃ多いもんじゃ (人間到る処青山あり)
これを引用した山田一郎(評論家)は、「平井さんによると、この名訳に<詩吟のフシをつけて得意になって高唱し、三根圓次郎校長を呆然とさせたこともあった>」と書いている(『南風帖』)。平井は言語学でも早熟ぶりを発揮、作曲家になった後も、趣味は言語学・方言研究と述べ、全国の伝承わらべ歌を収録した大著『日本わらべ歌全集』全39冊にも監修者の一人として参画している。 言語学に興味を持った平井は英語も得意で、東京外国語学校に行くつもりで5年生に進んだ。当時の中学生は4年修了で旧制高校に進学できたため、土佐中5年生はほとんどいなかった。しかし、外国語学校や音楽学校・商船学校は5年卒業でないと受験できなかったため、平井は残っていたが、兄の薦めもあって東京音楽学校を目指したくなる。だが父親は医者か弁護士にしたくて大反対で、三根校長に「家の息子は音楽家にさせる心づもりはない」と怒鳴り込んだという。「三根先生を偲ぶ座談会」で、平井はこう述べている。
「(父は)先生から反対にしかられ、<それは以ての外の不心得であって、将来音楽がどういう役目をするか知らんか>といわれてね、<ただ政治家や役人になったらそれが偉いと思ったらあてが違うぞ>と大分しかられて、それから家に帰って来て大の音楽ファンに親父がなりましてね。<お前もその決心して行かにやぁいかんぞ>と。それまでは語学の方をやる心算であったので、校長もしみじみ生徒の行く先のことについて本当に親身になって考えてくれたと思います。<語学はありふれた学問だからぜひ音楽をやれ>、こう言ってくれました」(『三根先生追悼誌』)。平井は息子の丈一朗にも、「三根校長はクラシックが好きだった」と語っている。
音楽学校に進んだ後も手紙でよく激励を受けたが、なかでも印象的だったのは1年生の時の年賀状に記されていた「凡庸に堕するなかれ」であった。「この葉書は今でも持っており、時々出しては非常に発奮の資にした。これが、土佐中学の教育の真骨頂ではなかったかと思う」と、同じ座談会で語っている。日本情緒あふれる歌曲を生んだ昭和を代表する大作曲家・平井康三郎の誕生には、恩師・三根校長の存在が不可欠であった。(引用文献・図版の出典は最終章末尾に記載する)
<第二章>歌う社長や歌う文部次官も誕生
生伴奏で歌いまくった三菱の進藤
平井康三郎(5回生)は母校や同窓会への想いも強く、筆者が在学中の昭和28年に土佐高委員会(自治会)と新聞部で応援歌を創った際には、快く作曲してくださった。作詞は校内から公募だったが、入選作は中学主事・河野伴香の「青春若き・・・」であった。同窓会関東支部では、昭和63年の総会に講師として登壇いただいた。
「音楽と生活」をテーマに、ピアノ演奏をまじえての軽妙洒脱な音楽談義が忘れられない。平成4年には、土佐中柔道部の後輩・公文公(7回生)の依頼を快諾、公文教育研究会で特別講演会「音楽と人生」をおこなった。なお、著書『作曲指導』は、1年後輩の近藤久寿治が興した同学社から出版している。
初期の土佐中からは、平井のような音楽家だけでなく、数々の音楽愛好家が育っている。その筆頭が進藤(旧姓宮地)貞和(2回生)である。昭和45年に三菱電機社長になると、重電中心で殿様体質だった企業を見事に変身させ、大躍進を遂げた。特にクリーンヒーターなど家電のヒット商品開発と販売網整備には、目を見張らされるものがあった。その原動力は、飾らない豪快な人柄と、「歌う社長」と呼ばれた得意の歌声であり、技術者や販売店をたちまちやる気にさせた。筆者の『筆山』第3号でのインタビューで、「中学時代には、軟式テニスやハーモニカに熱中し、自己流でヴァイオリンもやった。
戦後は、オランダで「長崎物語」、ドイツで「野ばら」と歌いまくり、国際親善にも大いに役立てた」と語ってくれた。ギターやアコーデオンの生伴奏で歌い、ダークダックスとも共演した。その縁で平成7年には「ダークダックス阪神大震災救援チャリティーコンサート」が、進藤の協力を得て佐々木泰子(33回生)などによって開催された。
柔道部で平井から鍛えられたという公文公も、高知高校に進んでからレコード鑑賞に熱中した。堀詰・細井レコード店でのバッハ「ブランデンブルク協奏曲」観賞会にも行ったことを、友人の久武盛真が平成9年の『文化高知』に書いている。公文は、クラシックのレコードをかなり愛蔵していたが、昭和20年4月の高知大空襲で常盤町の実家が全焼、蔵に入れてあったレコードは溶けて黒い塊になっていたと、後日口惜しがっていた。平井の影響を受けたのか、公文式教育を始めてからは、音楽と言語の関連に注目、やがて乳幼児教育にわらべ歌を取り入れ、標語「生まれたら ただちに歌を 聞かせましょう」を唱え、母親に呼びかけていた。筆者は、平成5年にパリの国立小児病院を見学したが、新生児室で副院長から「心身の健全な発達には音楽が欠かせない。ここの医師は全員、取り上げた赤ん坊に母に代わってわらべ歌をうたってやる。入院中の子どものためには楽器をそろえてあり、演奏を楽しめる」と語ってくれた。音楽の意義に、改めて気付かされた。
宮地貫一(21回生)は三根校長亡き後の入学だが、「歌う文部事務次官」と称された。演歌の新曲が出ると即座に譜面を手に入れ、赤坂の「いしかわ」などでコップ酒を豪快に飲んでは、ピアノの生伴奏で歌っていた。二人の宮地先輩は、仕事も酒も歌も「こじゃんと」楽しんだ。なお、三根校長も酒は大好きで、飲むと「よさこい節」を歌うこともあったと聞く。
邦楽には長唄の佐藤、謡の近藤
三根校長の横笛とは関係ないが、邦楽の愛好家も多かった。佐藤秀樹(1回生)は、謡や長唄を修得、昭和58年には銀座ガスホールで長唄の大曲「船弁慶」を演じている。近藤久寿治(6回生)は、『新修ドイツ語辞典』で知られる教育出版社・同学社を興したが、多忙な中で同窓会の世話役をする一方、観世流の謡を五十数年にわたって修め、神楽坂の矢来能楽堂などでの発表を続けていた。大酒豪であったが、土佐中・三根校長への想いには並々ならぬものがあった。
余談になるが、昭和33年に三代・大嶋光次校長が逝去した際に、近藤は「次の校長は絶対に母校出身だ」との信念のもと、関東同窓会の先頭に立って曽我部清澄先輩(1回生・高知大学教授)を強力に推薦した。大学生だった筆者は、帰郷の際に親書を託されて高知の同窓会会長・米沢善左衛門(2回生)に届けた思い出がある。近藤たちが母校出身者にこだわったのは、戦時色の強くなった二代・青木勘校長(愛知県立第一中学校長から赴任)の時代に、
寄宿舎での上級生によるしごきや、制服に軍服同様の白い袖章(白線)採用などがあったからと思われる。青木校長は、東京帝国大学哲学科出身で三根の後輩であったが、時代のせいか三根校長時代にはあり得ない事態が発生、進学も奮わなくなり、校長の排斥運動が起こった。母校の教諭や高知高校在学中の同窓生を代表して、吉澤信一・曾和純一(16回生)が上京、排斥を近藤に相談したが、いさめられ実現しなかった(『筆山』第3号)。以来近藤は「三根精神の復興」を念じていた。『三根先生追悼誌』発行も、三根校長の「胸像レリーフ」校内設置も、その想いによる企画で、実務を裏で支えたのは近藤であった。
それにしても、三根校長はなぜ音楽や美術の教育にこれほど力を入れ、平井の才能を見抜いて音楽学校への進学を薦めたのだろう。進学校として、単に有名高校(旧制高校)・有名大学への進学率向上を目指すだけでなく、生徒一人ひとりの個性や才能を見抜いて進路指導にあたるとともに、芸術活動へのなみなみならぬ意欲が感じられる。これは、どこから来たのだろう。
<第三章>息子ディック・ミネはトップ歌手
立教大で相撲部からジャズ・バンドへ
三根校長の長男・徳一は、芸名ディック・ミネで知られる流行歌手で、第二次世界大戦前後の歌謡界で大活躍だった。モダンな歌とダンディーな容姿で実力・人気を併せ持ち、ジャズ・歌謡曲のトップ歌手となった。しかし、三根校長が健在のころは、息子が流行歌手というのははばかる雰囲気があったようで、戦時色の濃くなった昭和18年刊行の『三根先生追悼誌』には、息子のことはほとんど出てこない。近藤久寿治(6回生)は、大学在学中に平井康三郎(5回生)たちと東京で校長を囲んだ際に、平井のことを冗談交じりに「本郷の裏町で、はやり歌をうたっています」というと、校長は「そうか。実は、わしの息子もそのはやり歌をやっている」といわれた、とある。(『続続南風対談』)
ところが戦後になると立場が逆転、三根校長は世間から忘れられ、「ディック・ミネの父」として紹介されるようになった。ディック・ミネは平成3年に82歳で亡くなったが、朝日新聞は3段抜きの見出しでこう報じた。
<1934年、ビング・クロスビーが歌っていた「ダイナ」を自分で訳詩してデビューし、一躍人気歌手に。学生時代のアダ名からとった芸名「ディック・ミネ」は日本の洋風芸名のハシリとなった。タンゴ調の「黒い瞳」や、「上海帰りのリル」「二人は若い」・・・などの曲も次々とヒットして、折からのジャズブームに乗り、日本の男性ジャズ歌手の草分けとなった。古賀政男のすすめで歌謡曲にもレパートリーを広げ、「人生の並木道」「旅姿三人男」をはじめ、「夜霧のブルース」などでも成功した。・・・1979年から88年まで社団法人日本歌手協会会長。82年には「反核・日本の音楽家たち」結成の呼びかけ人にも名を連ねた。アムネスティ運動やフィリピンの子供たちへの学費援助などにも協力を惜しまなかった>
単なる流行歌手ではなく、社会性や反骨精神も持った「凡庸」ならざる親分肌のリーダーであった。では、その生い立ちからさぐってみよう。父が徳島中学校長だった明治41年に生まれ、徳一と命名された。父の転勤で、小学校は山形・新潟で過ごした。大正9年に土佐中に招かれた父は、母・敬(よし)が体調を崩したので家族を東京に残して単身赴任となった。徳一は日体大付属荏原中学に進んだが、相撲部で活躍したのが目立ち、立教大学に相撲部推薦で入学する。だが、「帝大だけが学校と思っていたおやじは怒った」という。学生時代におこなった不良相手の痛快な武勇伝の数々は、
著書『八方破れ言いたい放題』(政界往来社)に詳しい。体もなにもかもデカかったので、ディックと呼ばれるようになる。相撲から音楽への転向は、この本でこう述べてある。
「おやじは堅物一方の人だったけど、母親が話のわかる人でね。なにしろ日光東照宮宮司の娘だから、琴が抜群だった。西洋音楽にも理解があったし、音楽に親しませることが教育上もよろしいということを知っていた・・・電蓄が家にあり、シンフォニックジャズなんか、よく聞かされた」。
そのシンフォニーが大学で聞こえてきたことから立教大学交響楽団に入るが、さらにジャズ・バンドに転進する。自らリーダーとなった学生バンドは、母の紹介によって日光金谷ホテルでデビュー。卒業して逓信省の役人になるが、すぐ辞めてバンド活動に専念、さらにテイチクの専属歌手になる。平成元年の『筆山』に寄せたエッセイ「父」には、<「このごろ変な歌を歌っているディック・ミネというのはおまえか」と父に聞かれ、怒られるのを覚悟で「はい」というと、「世の中、どんな商売もある。やる以上は恥ずかしくないようにやれ、トップになれ」であった。父は息子に対しては自由放任であったが、自分の学校の生徒に対しては、実に細やかに、一人一人の個性を見抜いていた>と、書いている。
軍部にも動じなかった父を尊敬
昭和11年に三根校長が急逝した際には、母と高知に駆けつけたが、父の思い出を『筆山』第9号にこう記してある。
<自分の教育方針を頑として通した父は、文部省であれ軍人であれ、岩のごとく動じなかった。父は学校で「おはよう」と、だれにも帽子をとって挨拶するのが常だった。死の前日のこと、軍部の将校(土佐中への配属将校)がこれを敬礼にせよと迫ったが、父は教育方針は変えぬと言い通した。腹を立てた将校は酒に酔って自宅に乗り込んできて、父と言い争った。この出来事が引き金となって、脳内出血を起こしたのであろう。父の教育は今の時代にも立派に通用すると、私は父を誇りに思います>。三根校長に、秘書のように寄り添っていた芝純(7回生)は、『向陽』3号に「一夜、配属将校と激論せられ、翌日脳溢血で殉職された」と述べている。
やがて日本の大陸進出とともに、ディック・ミネたち歌手も上海から満州・樺太まで、軍の慰問演奏に動員される。昭和12年に日中戦争が始まり、翌年には国家総動員法が公布され、“敵性語排除”で芸名は三根耕一に変えられる。やがてジャズやダンスも禁止となる。しかし、ハルピンや上海には弾圧がおよばず、前線兵士の要望でディック・ミネを通すが、傷病兵の惨状には涙したという。東京大空襲が始まった頃は防空壕に入り、隠し持っていた短波受信機で米軍放送を聞き、大本営発表との違いをちゃんと知っていた。“立教”仕込みの英語は、戦後になってルイ・アームストロングが来たときにも重宝がられ、一週間つきっきりで案内している。永遠の「モダンボーイ」で、レコードの通算売り上げは4.000万枚以上におよぶ。著書には、豪快な女遊びもあけすけに述べてあるが、4人の奥さんを迎え、男女9人の子どもを育てている。昭和60年には9人の子ども一同の呼びかけで、喜寿を迎えた「父を祝う会」が、永田町のホテルで盛大に開かれた。
ディック・ミネは晩年になって、父について「熊本の旧制五高から帝大を出た偉い人で、五高の後輩に故・佐藤栄作元首相がいる。そんな関係で佐藤首相に可愛がってもらった」と、語っている。また、昭和54年に勲四等旭日小綬賞をもらった際には、「僕のおやじも、おじいさんももらった」と喜ぶとともに、「親孝行したいときには親はなし」と、嘆いている。親子はまったく別の分野で人生を歩みながらも、お互いに心を通わせていた。
こうして、徳一(ディック・ミネ)が流行歌手として大成した背景には、音楽好きの母・敬の影響が大きかったが、父・圓次郎も温かいまなざしを注ぎ続けていた。徳一も、三根が平井に与えた「凡庸に堕すなかれ」を実践したのだ。昭和60年の関東同窓会にゲストとして出席した際のスピーチでは、「オヤジは偉大だった」と述べていた。今は、父と並んで多摩霊園に眠っている。
三根校長には次男・結城忠雄がおり、筆者は父・圓次郎の思い出話をお聞きしたくて、昭和62年頃に杉並の御自宅を訪ねた。成人後に結城家に養子として迎えられ、会社を定年で退いた温厚な紳士で、こう語っていた。「子どもの頃、父は高知に単身赴任で、遊んでもらった覚えはあまりない。休みに大森の自宅に帰ってきても、東京の大学に進んだ教え子たちの勉強ぶりや就職が心配で、眼が悪いのもかまわずに東大などによく出かけていた。また、教え子も次々と家に訪ねてきた。昭和17年だったか、土佐中に父の胸像ができた除幕式に招待されて母と参加したが、父が皆さんに深く敬愛されていたことに、改めて気付かされた」
三根家では、ディック・ミネの三男・三根信宏が音楽の道に進み、「ギターの貴公子」と称されるギタリストになっている。
<第四章>哲学と音楽を育んだケーベル博士
哲学教授はチャイコフスキーの直弟子
偉大な教育者・三根圓次郎は、どのようにして誕生しただろうか。また、音楽など芸術の人生における意義についてどこで学び、クラシック音楽を好むようになったのであろうか。三根の実家は大村藩(長崎県)の大庄屋であり、大村中学から熊本の第五高等学校に進み、明治27年に帝国大学文科大学哲学科へ入学する。大学時代には、家庭教師などで自ら学資を稼いでいた。哲学は、前年にお雇い外国人として赴任したばかりのラファエル・フォン・ケーベル博士から教えを受ける。博士は異色の哲学者であり、素晴らしい教育者であった。
ケーベルは、1848年ロシアの生まれ。父はドイツ系ロシア人で国籍はロシアだったが、本人はドイツが祖国と言っていたという。幼少の頃からピアノを習い、19歳でモスクワ音楽院に入学、作曲家チャイコフスキーや名ピアニストのニコライ・ルービンシュタインに師事する。5年後に優秀な成績で卒業するものの、内気な性格から演奏家への道をあきらめ、哲学研究に転進する。ドイツのハイデルベルク大学で、ショーペンハウエルの研究によって学位を取る。ミュンヘンに移って哲学や宗教の歴史を学びつつ、音楽学校で音楽史や音楽美学の講義もおこなっていたところに、突然東京の大学からの招聘状が届く。恩師フォン・ハルトマンの推薦であり、チャイコフスキーからは反対されたが赴任を決断、明治26年6月に日本へ着任する。
当時の帝国大学文科大学は、多くを外国人教授に頼っており、ベルリン大学から招いた史学のルードヴィッヒ・リースのほか、独・英・仏の語学兼文学の教授は、いずれもそれぞれの国から招聘していた。哲学の日本人教授にはドイツ留学帰りの井上哲次郎もいたが、ドイツ観念哲学から東洋哲学、さらに国家主義へと進んだ人物だった。日本人によるアカデミックな哲学者の誕生は、哲学科で三根の少し先輩だった西田幾多郎が京大、桑木厳翼が東大の教授に就任する大正時代まで、待たねばならなかった。なお、外国人教授は、原則として英語で講義をおこなった。
哲学科でケーベルが担当した講義は、『帝国大学』(丸善 明治29年刊)によると1年で哲学概論・西洋哲学史、2年で西洋哲学史・論理学および知識論、3年で美学および美術史・哲学演習であった。一学年各科とも生徒は十数人で、講座によっては他の科の生徒とも合同であり、大変親しくなっていた。高知県出身では国文科に大町芳衛(桂月・作家)が、国史科に中城直正(初代高知県立図書館長)がいた。後に、大町によって土佐中開校記念碑文が記されるのは、三根と学友であったからだ。史学科には、幸田露伴の弟で日本経済史の開拓者となる幸田成友もいた。国史科の黒板勝美は東大教授となって日本の近代史学を牽引するが、昭和8年、東京での三根先生還暦祝賀会には駆けつけて「三根はまれに見る風格ある教育者」と称えた。三根が帝大を卒業した二年後に、寺田寅彦が五高から東京帝国大学理科大学物理学科に入学する。三根は、後に五高の後輩・寺田とも交流する。やがて、寺田もケーベルのもとに出入りするようになる。
日本人よ、偉大な芸術家・詩人に学べ
では、ケーベル博士が来日当時に、日本の音楽界に抱いた率直な感想を『ケーベル博士随筆集』から見てみよう。まず「音楽雑感」で、「日本へ来て、音楽らしい音楽というものを聴くことができないようになって以来、私は大音楽家の作品(楽譜)を読むことにしている。これによって私はこれらの作品の拙劣なる演奏から受けるよりも遙に大いなる楽を享けるのである」と述べている。こうして、最初は日本人の洋楽演奏に失望するが、明治31年から東京音楽学校(現東京芸術大学)のピアノ教師も務めるようになる。
音楽学校では、ボストン、ウィーンで6年間学んだ幸田延が、明治28年に帰国して母校の教授になっていた。延は、ケーベルからピアノを学ぶうちに腕前を認められピアノ科教授に就く。ケーベルも日本人の演奏をようやく評価、明治36年に日本初のオペラとして「オルフェイス」が音楽学校の奏楽堂で上演された際のピアノ伴奏をはじめ、度々ピアノを演奏している。この年には、幸田延の妹・幸もドイツ留学から帰り、音楽学校ヴァイオリン科教授となる。同年5月の第8回定期演奏会では、幸田姉妹・ケーベルがそれぞれピアノ・ヴァイオリンを披露して喝采を浴びている。幸もピアノや音楽史については、ケーベルから学ぶことが多かったと思われる。
こうして幸田延・幸の姉妹は、ケーベルから多々指導を受けることになるが、姉妹の間で生まれた幸田成友は、文科大学史学科でケーベルから西洋哲学史を学んで、経済史学者となる。幸田家では、三人揃ってケーベルの恩恵をうけていた。妹は結婚して安藤幸となるが、そのヴァイオリンの弟子に疋田友美子がいた。後の平井康三郎夫人である。
ケーベルは文科大学哲学科の教育について、大変手厳しい指摘をしている。「日本人の精神ならびに性格をはなはだしく醜くするところの傷所は、虚栄心と自己認識の欠乏と、および批判的能力のさらにそれ以上の欠如せることである。これらの悪性の精神的ならびに道義的欠点は、西洋の学術や芸術の杯から少しばかり啜ったような日本人においてとくに目立つ」「日本の学校当局者らは、・・・理知的ならびに倫理的教養には全然無価値なる、否、むしろ有害と言うべき・・・生徒の記憶を一杯に塞ぎ、疲労せしめ・・・試験のためにのみ学ばれるところの学課をもって、その生徒をいじめるのである」
卒業する哲学科の学生への挨拶では、こう述べている。「諸君は本日をもって諸君の自由――実生活ならびに学修における自由――の門出を祝さるる次第である。・・・およそ真に自由なる人とは法則に服従する人である、もっともその法則とは理性が正当として命ずるところのものである」「諸君に対して望むところは、諸君が偉大なる芸術家、詩人および文学者の作品をば、大思想家の著作と同様に、勤勉かつ厳密に研究せられんことである」(『ケーベル博士随筆集』)
三根たちは、これらの教えを「干天に慈雨」の思いで吸収していったと思われる。当時の帝大文科大学生は卒業すると、研究者の道に進むか当時の各県の最高学府である県立中学校の教諭になるかであった。「教師になっても、生徒に一方的に教え込む職人ではなく、生徒とともに学ぶ研究者でもあれ」が文科大学のモットーだったと、中野実(東京大学・大学史史料室)は語ってくれた。ケーベルの哲学や美学から、教師としてのバックボーンを得て、また音楽や美術の意義をよく理解し、三根たちは各地の学校に赴任していったのだ。
このケーベルのピアノに魅了された人物に、寺田寅彦がいる。五高時代にヴァイオリンを始めた寺田は、明治34年、東京帝国大学1年の時に夏子夫人が病気療養で高知に帰郷した孤独から逃れるため、東京音楽学校の慈善演奏会に行き、「橘(糸重)嬢のピアノ、幸田(延)嬢のヴァイオリン、ケーベル博士のピアノ・・・」を聴く。とくにケーベルの演奏に魅せられ、無性に会いたくなって自宅を訪問する。以来、夏目漱石を誘ってたびたびケーベルの出演するコンサートに出かけている。
寺田は、後にケーベルを悼んで随筆「二十四年前」を書いているが、そこには最初の演奏会での感動を「まっ黒なピアノに対して童顔金髪の色彩の感じも非常に上品であったが、しかしそれよりもこの人の内側から放射する何物かがひどく私を動かした」と記している。この随筆には、ケーベルを自宅に初訪問した様子も書き留めてある。寺田がヴァイオリンを独習していると話したときに、ヴァイオリンの値段を聞かれ、「9円」というと、「突然吹き出して大きな声でさもおもしろそうに笑った」とある。五高時代に、月額11円の仕送りから無理に工面して購入した安物であった。笑われても別に不愉快でなく、「私もわけもなく笑ってしまった」と、述べている。(『寺田寅彦随筆集第二巻』)。
明治38年1月3日の寺田の日記には、「阪井へ行き、琴三絃ヴァイオリンにて六段など合す」とある。阪井とは、夏子夫人の父・阪井重季(陸軍中将)であり、亡き妻の異母妹・美嘉子の琴などとの合奏に、ヴァイオリンで参加したのだ。肺病のため桂浜で、明治35年に亡くなった妻を偲んだのであろうか。夏子も美嘉子も、美人で評判だった。この頃から寺田は音響学を研究、明治41年には東京帝国大学理科大学から、理学博士の学位を授与される。主論文は「尺八の音響学的研究」であった。寅彦の孫・関直彦によると、一時ヴァイオリンを中断していたが、大正11年にアインシュタインが来日した際に、歓迎晩餐会で同氏が余興にヴァイオリンでベートーベンのクロイツェル・ソナタを弾いたのに触発され、高知出身の作曲家で土佐中校歌を作曲した弘田龍太郎からヴァイオリンの個人レッスンを受けることになったという。
寺田の五高以来の恩師・夏目漱石も、帝国大学文化大学の大学院で、来日したばかりのケーベルから美学の講義を受けている。漱石は寺田とともに、ケーベルの演奏会に何度か足を運び、自宅も訪問、随筆「ケーベル先生」を書いた。そこには、「文科大学へ行って、此処で一番人格の高い教授は誰だと聞いたら、百人の学生が九十人迄は、数ある日本の教授の名を口にする前に、まづフォン・ケーベルと答へるだろう」とある。文芸評論家の唐木順三は、「ケーベルと漱石」でケーベルの生活ぶりを、「読書と自分の耳にきかせるピアノと執筆の生活。自分の立場を〈哲学と詩との間〉において、詩と哲学を享受し観賞する生活。・・・生活即芸術であった」と書いている。(『現代日本文学大系 夏目漱石』)
ケーベル先生の遺産
土佐中校長に決まった三根は、大正9年3月、寺田を東京本郷に訪ね、寺田家が所有する高知市江ノ口の土地を学校用地に譲って欲しいと交渉している。五高の先輩、そしてケーベル先生の教え子からの依頼であったが、すでに先約があって成立しなかった。寺田は日記にこう記している。「三月四日 土佐中学校長三根圓次郎氏川田正澂氏の紹介で来た。中学敷地予定地に宅の地所ある故安く売ってくれといふ。先日来の江ノ口地所の買手は此れを知って買いだめに掛かったに相違ない」(『寺田寅彦全集 第二十一巻』)。土佐中の動きを察した業者が、手付け金を支払って、押さえてあったのだ。
同年に、県庁に提出した「土佐中学校設立認可願」の添付地図には、江ノ口小学校の北側に「新設校地」との記入がある。申し訳なく思ったからか、寺田寅彦は立派な柱時計を土佐中に寄贈、潮江村に完成した新校舎に飾ってあった。寺田が演奏を楽しみ、また音響学の研究材料にも使ったヴァイオリンやチェロは、自作の油彩画「蓄音機を聞く」とともに「高知県立文学館・寺田寅彦記念室」で見ることができる。ヴァイオリンは1814年にボヘミヤで製作された名器アマティのコピーで、孫の関直彦が譲り受けていたもの。
ケーベル博士は、独身のまま文科大学で21年間教えた後に引退し、ドイツに帰国しようとしたが、大正3年に横浜港で帰国船・香取丸に乗る直前に第一次世界大戦が勃発、帰国できなくなる。大正12年まで横浜のロシア領事館の一室で過ごして生涯を終え、東京雑司ヶ谷霊園に葬られた。夏目漱石や大町桂月も、ここに眠っている。
ケーベルたちによって音楽の才能を開花させた幸田姉妹は、旧幕臣の家に生まれたが、祖父や母が音曲好きで幼少期から箏曲や長唄の稽古を積んでいた。やがて東京女子師範学校付属小学校で西洋音楽に触れ、その音楽的才能を見いだされ、ピアノやヴァイオリンの道に進んだ。三根も横笛を手にしていたが、江戸時代には公家の世界では雅楽が、武家や町人では能楽や箏曲・長唄が好まれた。欧米の上流家庭で室内楽が好まれたのと同様に、日本の家庭にも邦楽を楽しむ伝統があり、西洋音楽の受容にもつながった。平井の「平城山」、山田耕筰の「からたちの花」、滝廉太郎の「荒城の月」などには、日本の風土色が色濃く漂い、日欧の融合から生まれた調べと言えよう。
昭和4年に東京音楽学校へ進んだ平井康三郎は、ケーベルに接することはかなわなかったが、疋田友美子と出会う。疋田は幸田延の妹・安藤幸教授の指導を受け、ヴァイオリン科を首席で卒業し、平井と結婚する。ケーベルから三根を挟んだ平井と、安藤幸を挟んだ友美子と、いわば孫弟子同士が結婚、そこから世界的なチェリスト・平井丈一朗が誕生した。ケーベルがチャイコフスキーから受け継いだ音楽の流れは、ロシアからドイツ経由で日本に到来、幸田姉妹そして三根や平井によって見事に根付き、さらに独自の音色を加えて世界へと流れていったのである。
三根校長たちは、ケーベル博士から哲学や美学の知識とともに、豊かな人生には音楽や美術を欠かすことができないという「生活即芸術」の教えを学んだ。さらに、内面から湧き出る教育者としての豊かな人間性を感じ取って巣立っていったのだ。三根校長にとどまらず、漱石や寅彦をも魅了した“ケーベルの教え”が、母校土佐中高の学園生活に受け継がれ、凡庸ならざる人材の育成に活かされることを願っている。
(本稿執筆に当たっては、三根圓次郎の孫・信宏氏、平井康三郎の長男・丈一朗氏、近藤久寿治の長男・孝夫氏、寺田寅彦の孫・関直彦氏、筆山会および向陽プレスクラブの皆様にご協力いただいた。感謝申し上げたい。なお、本文では敬称を省略させていただいた。)
<主要参考文献・図版出典>
『土佐中學を創った人々』向陽プレスクラブ 平成26年/『三根先生追悼誌』土佐中学校同窓会編集発行 昭和18年/『創立五十周年記念誌』創立五十周年記念誌編集委員会 昭和51年/『ミリオーネ全世界事典』5 学研 昭和55年/『南風対談』『続続南風対談』山田一郎 高知新聞社 昭和59・61年/『南風帖』山田一郎 高知新聞社 昭和58年/『八方破れ言いたい放題』ディック・ミネ 政界往来社 1985年/『筆山』土佐中・高同窓会 関東支部会報 各号/『ケーベル博士随筆集』久保勉訳編 岩波書店 1928年/『幸田姉妹』萩谷由喜子 ショパン 2003年/『東京芸術大学百年史演奏会篇第一巻』『東京芸術大学百年史東京音楽学校篇第一巻』音楽之友社 1990年・昭和62年/『寺田寅彦随筆集第二巻』小宮豊隆編 岩波書店 1947年/『寺田寅彦全集 第二十一巻(日記)』岩波書店 1998年/『現代日本文学大系 夏目漱石(一)(二)』筑摩書房 昭和43年・45年/『文化高知』(財)高知市文化振興財団 平成9年/『寺田寅彦画集』中央公論美術出版 寺田東一 昭和60年/『高知の文学』高知県立文学館 平成9年 生首を化粧した武士の娘
郷土誌『大平山』(高知市三里史談会発行)第43号に発表した、『おあん物語』の論考です。関ヶ原の合戦を逃れ、土佐に落ち延びた娘の体験記ですが、菊池寬は女性による「戦国時代のたった一つの自伝小説」と称賛しています。ここでは臨場感が出るように、戦国時代の合戦を描いた浮世絵や屏風から物語と類似の場面を選び、原本の挿絵に加えました。
子どもに語った戦国の実態
江戸初期の土佐の女性といえば、思い浮かぶのはだれであろう。まず、内助の功で知られる初代藩主・山内一豊(かつとよ)の妻がいるだろう。一豊亡き後、見性院(けんしょういん)の法号を受けるが、名前は「千代」とも「まつ」とも伝わり、明らかでない。へそくりで名馬を買った伝説はともかく、関ヶ原の直前に人質となっていた大坂から東国の一豊に送った「笠の緒の密書」は、徳川家康にも高く評価された実話だ。もう一人は、野中婉(えん)であろう。奉行職だった父野中兼山が失脚すると、44歳まで宿毛に幽閉された。その孤高の生涯は、大原富枝の名作『婉という女』に描かれている。
ここで紹介するのは、関ヶ原の大決戦のさなか、佐和山城で敵兵の生首に化粧を施すなど、悲惨な篭城を経験した「おあん」である。落城寸前に父山田去暦(きょれき)とともに城を抜け出し、土佐に落ち延びたおあんは雨森氏と結婚、夫亡き後は甥に養われ、八十余歳まで長生きしている。この老婆が「おあんさま」と呼ばれたのは、夫に先だたれて出家し、老尼の尊称「お庵様」が用いられたからであろうとされる。
『おあん物語』は、「子どもあつまりて、おあん様むかし物語なさりませといえば」から始まっており、近所の子どもたちにせがまれて、十数歳で体験した篭城戦の凄惨な光景を語った物語だ。さらに後半には、彦根城下での貧しい少女時代の生活体験が記されている。この話を、だれか分からないが筆記した者がおり、写本が流布した後、享保15(1730)年に土佐の谷垣守(かきもり)が本にまとめている。筆者は十年ほど前に神田の古書店で、朝川善庵が谷垣守本に挿絵を付けて天保8(1837)年に刊行した天保版を見付けて入手した。題簽(だいせん)に『おあんものがたり おきくものがたり』とあり、大坂夏の陣で大坂城から脱出した「お菊」の物語と合本にした大判(257×180ミリ)の和本だった。
こうして江戸時代から広く読み継がれてきた『おあん物語』であり、現代も国文学者や歴史学者から大いに注目されている。しかし、見性院や婉と違って高知では忘れ去られているようなので、この本の誕生のいきさつと内容、さらに各分野の研究者や文学者による論評と活用を紹介したい。なお、翻刻は、岩波文庫『雑兵物語 おあむ物語』(昭和18年)によったが、読みやすくするため現代文に直し、主人公「おあむ」は、「おあん」と表記した。文末の「おじゃった」などは活かしてある。では、本文(一部省略)に入ろう。
篭城し、生首にお歯黒を施す
「おあん」には、「おれが親父は、山田去暦といい、石田治部少輔(じぶしょう・三成)殿に奉公し、近江の国彦根に居られたが、その後、治部どの御謀反の時、美濃の国大垣の城へこもって、我々みなみな一所に、お城にいて、おじゃった」と、大垣城にこもったいきさつが出てくる。やがて、「家康様より、せめ衆、大勢城へむかわれて、戦が夜ひるおじゃったの。その寄せ手の大将は、田中兵部殿と申すでおじゃる」とある。攻め手の大将・田中吉政(兵部)は、豊臣秀次・秀吉に仕えたが、関ヶ原では東軍について石田三成を捕虜にする武勲をあげ、柳川藩主に取り立てられた人物だ。秀次に宿老(重臣)として仕えた際には、山内一豊も同じ宿老であった。ただ、石田は関ヶ原へ大垣城(岐阜県)から出陣しているが、田中が攻めたのは石田の本拠・佐和山城(滋賀県)である。したがって、『おあん物語』の舞台も実は佐和山城で、おあんの記憶違いで大垣城となったようだ。
戦が始まると、「石火矢(大砲)をうてば、櫓(やぐら)もゆるゆるうごき、地もさけるように、すさまじいので、気のよわい婦人なぞは、即時に目をまはして、難儀した」「はじめは、生きた心地もなく、ただ恐ろしや、こわやとばかり、われも人も思うたが、後々は、なんともおじゃる物じゃない」と変わる。恐ろしい砲撃を受けながらも、次第に慣れていく。
城中で女性は、どんな役割を担っていたか。「我々は母も、そのほか家中の内儀、娘たちも、みなみな天守に居て、鉄砲玉を鋳ました」女たちは、鉛を溶かして鋳型に流し込んでは、火縄銃の鉄砲玉を作った。
続けて、「取った首を天守へ集め、それぞれに札をつけて覚えおき、首にお歯黒を付ておじゃる。それはなぜなりや。昔は、お歯黒首はよき人とて賞翫した。それ故、白歯の首は、お歯黒を付て欲しいと、頼まれておじゃったが、首も怖いものでは、あらない。その首どもの血くさき中に、寝たことでおじゃった」とある。切り取った敵兵の生首に、お歯黒を施していたのだ。戦国時代の「賤ヶ岳(しずがたけ)合戦図屏風」などには、敵兵の首を持って凱旋する兵士の姿が描かれている。当時、首は戦場で手柄を上げた大事な証拠であり、それも白歯の雑兵よりもお歯黒をした身分の高い武将の首が評価され、恩賞につながったのだ。誰が捕った首か名札をつけ、お歯黒首への偽装工作までおこなっていた。挿絵①は、生首にお歯黒を施す場面で、右手前にはお歯黒の液(鉄漿(かね))を入れた角盥(つのだらい)がある。名札を付けた首も見える。左手前には火縄銃が置いてあり、背後の杭には首がずらりと掛けてある。
やがて、「寄せ手より鉄砲打掛け、もはや今日は城も落ちるだろうという」状態となる。そこへ「鉄砲玉が飛んで来て、われら弟、14歳になった者に当り、そのまま、ひりひりとして死んでおじゃった。さてさて、むごい事を見ておじゃったのう」と、歎いている。
たらいで脱出、土佐に来た「彦根ばば」
落城が迫ったある日、「わが親父(しんぷ)の持ち口(持場)へ、矢文が来て、<去暦は、家康様御手習いの御師匠であった。わけのある者なので、城から逃げたければ御助けできる。どこへなりとも、落ちなさい。旅費の心配もないよう、諸々に伝えておいた>との御事で、おじゃった」。家康様の師匠だったので、旅費も含め、脱出の手配をしたとの知らせだ。密かに天守へ行き、北の塀脇から梯子をかけて降り、たらいに乗って堀を渡った。人数は、両親とおあん、それに大人四人ばかりであった。挿絵②は、たらいで堀を渡る場面であり、右の藤文様の着物を着た娘がおあんで、16、7歳と思われる。
城をあとに落ち延びてゆくが、「五六町ほど、北へ行った時、母人(ははびと)、にわかに腹がいたみ、娘を産みなされた。大人はそのまま田の水で産湯をつかい、引上げて着物の裾でつつみ、母を父が肩へかけて、あお野が原へ落ちておじゃった。怖い事でおじゃったのう。むかしまっかう、南無阿弥陀、南無阿弥陀」。ここまでが、篭城から脱出までの経緯である。
さらに、土佐の子どもたちに、「彦根の話、なされよ」と言われ、こう語っている。「父親(山田去暦)は知行三百石取りであったが、戦が多く、何事も不自由であった。朝夕雑炊を食べておじゃった。おれが兄さまは、時々山へ鉄砲打ちに参られた。その時は朝菜飯(なめし)を炊き、我等も菜飯をもらえるので、うれしかった。衣類もなく、13の時、手織りの花染めの帷子(かたびら…ひとえの着物)一つよりなかった。その帷子を17の年まで着たので、すねが出て難儀であった。せめて、すねのかくれるほどの帷子ひとつ欲しやと思うた。このように、昔は物事が不自由な事であった。昼飯など食う事は、夢にもない事。夜に入り、夜食という事もなかった。今時の若い衆は、衣類の物好き、心をつくし、金を費やし、食物にいろいろ好みをいい、沙汰の限りなきこと(言語同断)である」。
こうして、彦根の時代を思い出しては、子どもをしかったので、後には「彦根ばば」のしこ名(綽名)をつけられたとある。さらに、今も老人が昔話を引用して、当世を戒(いまし)めることを「彦根」というが、この言葉は俗説では「おあん様」に始まったことで、土佐以外では通じないと、筆記者は付記してある。
谷垣守がまとめて出版、広く流布
土佐に来たことについては、「去暦、土佐の親類方へ下り、浪人。おあんは、雨森(あめのもり)儀右衛門(土佐藩士)と結婚。夫の亡き後は、甥の山田喜助(後に蛹也(ようや))に養育して貰う。寛文(1661~72)何年かに、八十余で死す」と、簡単に触れている。
聞書の筆者は、物語を終えた後に「おあんの物語」を残した経緯をこう述べている。「おあんの話を聞いたのは8、9歳の頃で、折々に聞き覚えた。誠に光陰矢の如し。正徳(1711~15)の頃、孫どもを集めてこの物語に、自分の昔のことも合わせて、世の中の苦しみを示すと、小賢しい孫どもが、『昔のおあんは彦根ばば、今のじい様は彦根じじ。今さら何をいうやら、世は変わった』と、鼻であしらうゆえ、腹を立てども後世おそるべし、どうなるだろう。今の孫たちも、また自分の孫たちに、このようにいわれるのだろうかと、勝手に想像、後はただ南無阿弥陀仏と繰り返すほかに、いうべき事はない」。
この本を編纂した谷垣守は、末尾に「真実の優れた記録である。誰が記録したのか分からないが、おそらく山田氏の覚書であろう。山田文左衛門所蔵のものを借りだして写した。享保15年3月」と記してある。
さらに、天保8年に『おあんものがたり おきくものがたり』として出版した江戸後期の儒学者・朝川善庵は、跋文(あとがき)で「狂言師・倉谷岱左衛門の門人某が安永年間に、大坂からこの本を持ってきた。御庵(おあん)とは、老尼の尊称である」と述べている。この本には、挿絵三枚が加えてある。朝川善庵は天明元年、江戸の生まれ、嘉永2年没である。挿絵には「武清」の落款(らっかん)があり、絵師は喜多武清だ。江戸後期の画家で、八丁堀に住み、谷文晁に師事した。渡辺崋山とも交流があり、崋山は「その臨写(写生)には、ほとんど真物に迫る貴重な物が多かった」と、語ったという。山東京伝『優曇華(うどんげ)物語』の挿絵も描いている。安政3(1856)年没。
『おあん物語』は、谷垣守本が原本であるとされ、写本が高知県立図書館にある。垣守(1698~1752)は谷秦山(じんざん)の息子で、儒学者・国学者。京や江戸にしばしば行き、諸家と交わり研鑽した。その子・真潮(ましお)ともども家学を深め、土佐を代表する学者となって、政治にも参与した。垣守がまとめた『おあん物語』は、天保8年版によって広く流布し、戦国時代の貴重な記録として、今に各地の図書館や大学に残っている。
では、明治から現代まで、識者や研究者によって、この物語がどのように受け止められてきたか、さぐってみよう。
岩崎鏡川による「おかあ武勇伝」
明治になると郷土史家・寺石正路が注目し、この物語を紹介するとともに、登場人物の墓地をさぐるなど考証にも取り組んだ。それらの成果を活かして、『おあん物語』に触れながら坂本龍馬の先祖を論じたのが、明治七年土佐山村生まれの維新史研究家・岩崎鏡川(きょうせん・英重)である。「坂本龍馬先祖美談」(『坂本龍馬関係文書一』大正15年)で、「土佐の国に昔、御案(おあん)物語といえる書あり、彼の帯屋町故山田平左衛門君の先祖・山田去暦の娘・御案といえる女丈夫の物語・・・江州佐和山籠城の時に血なまぐさき敵首を天守に運び・・・」と、まず「おあん」を紹介。続けて、坂本家本家の系図にあった「おかあ殿事績」から、こう述べている。「大和国吉野の須藤加賀守の娘・おかあ殿が、戦乱の中を落ちる際に敵六人に追いかけられて薄手(軽い傷)を負うが、敵に待てと言って小袖を引きちぎって鉢巻きにあてると、六人を切りとめ、土佐の豊永に落ち延びた。おかあ殿は小笠原佐兵に嫁ぎ、その妹が坂本家の先祖で才谷村に住む太良五良(ママ)の妻になった」。
龍馬の縁戚に当る土居晴夫は、「おか阿の武勇談」(『坂本龍馬の系譜』)でやはりこの話を紹介しているが、おか阿の妹は坂本家初代太郎五郎の妻ではなく、その子・彦三郎の妻とする。南国市三畠(さんぱく)には、小笠原佐兵・おか阿の墓と顕彰碑があるという。
岩崎鏡川は、おか阿は忘れられたのに「おあんの物語は、久しく世上に流伝し、今や歴史研究家としてその名を知らざるなし」と述べている。昭和にはいると歴史家だけでなく、多くの文学者がこの物語に注目し、さまざまな形で作品化する。まずは、岩崎鏡川の次男に生まれ、母・斉(ひとし)の実家・田中家にはいった作家・田中英光(ひでみつ)から取り上げよう。
田中英光の母方の祖父・田中福馬は種崎村の商家に生まれたが、宝永町に出て市場の仲買人として成功する。しかし自由民権運動で家産を傾け、東京に出た。英光は大正2年、東京赤坂で生まれたが、土佐人に囲まれて育ち、高知を故郷としていた。早大在学中の昭和7年には、ロサンゼルス・オリンピックにボート選手として参加。その後作家となり、『オリンパスの果実』などで知られる。昭和24年に太宰治の墓前で自殺する。この英光が昭和18、9年頃執筆したと推定される遺稿「土佐 2」(『田中英光全集8』芳賀書店)に、「おあん物語」がある。
虐げられた女性への追憶
この文章の最初に、「寺石正路氏の考証のついた、土佐協会誌第66号の付録があるので参考にさせて貰い、感想を述べながら意訳する」とある。おそらく父・鏡川の文章で「おあん物語」に注目し、寺石の文書も入手したのであろう。英光は、まず菊池寬の「わが愛読文章」から、次の部分を引用している。
「戦国時代に於ては、個人の私生活、ないし日常生活についての文献なぞは全然見当たらない。ことに女性の私生活については何も伝わっていない。その間にこのおあん物語だけが、一つの真珠のように光っている。これは戦国時代に於けるたった一つの自伝小説と云っても好いものだ」。このあと、現代文に意訳して物語を紹介、前半を終えたところで、こう感想を挟んである。「ここまでが、関ヶ原当時の思い出話だ。戦時中、女子供がどんなに惨めであったか、ただ虫のように生き、虫のように死んで行ったに過ぎない。ところが今度の戦争中におあん物語を時局に有意義な物語として取り上げ、昔でも女子供はこんなに苦しんだのだから、今の女子供は幸福だ。すべからく今の配給生活に感謝せよなぞ言っている人もいたが、これは反対で、三百年前の女子供の暗い生活と少しも変わらぬ、あるいはもっと酷い生活を強いられている現代の矛盾と欠陥をむしろ批判的に考えなければならないと思う」。
まことに的確な感想であり、言論統制の行われていた第二次世界大戦中には、絶対に発表できない内容である。昭和18年発行の岩波文庫版「おあむ物語」にも、並べて収められた「雑兵物語」の解説には、「戦闘に於ける果敢不屈の精神をうたって士気の高揚に資せんとしたもの」とある。当時の、新聞・出版は戦意高揚・耐乏生活一色であった。この昭和18年に高知市立三里国民学校に入学、空襲と空腹の中で小学生生活を過ごした筆者も、体験ずみのことであった。
英光は物語の後半を記した後、寺石の次のような考証を転記している。「山田去暦の墓は、高知城南潮江山字(あざ)高見にありと聞く。阿庵(おあん)の墓は同じ清水庵の傍らにあり。わが父は子供の頃、潮江村に住み、童遊の際、阿庵の墓に行き、木太刀を取り帰ったことがある。阿庵の墓は、なぜか知らないが木太刀の奉納がおびただしかった。昔から土佐では歯の痛む人は小溝に行き、お庵様といって祈願をして、平癒すればお歯黒を上げる習いがあった」。
英光は最後に、「この平凡な女性が、どうしてこのような俗信の対象となるまで、有名になったであろうか。同様な方言を生むまでに有名な荒武者・福富隼人と対照してみる時は面白い」と、問いかける。福富隼人は、長宗我部元親に仕えた伝説的な豪傑で、英光は隼人の孫で惨めな流浪の生涯を送った「福富半右衛門」を主人公に歴史小説を書いている。この二人を対比しつつ、こう記して「おあん物語」を終えている。
「隼人は生粋の土佐人であったが、その子孫は他国に流浪し、おあんは他国人であったが、その子孫は土佐に止まることになった。この点でもまた、対蹠(たいしょ)的であり、かつ私は土佐を限定した土佐と見る愚劣さを思う。そして軽々しく独断は出来ないが、こうして隼人が有名になった原因には、他国人の抑圧の下に苦しんだ土佐人が前代の自国人の英雄に対する敬愛の念を感じ、おあんが有名になった原因には、抑圧された民衆が、虐げられた女性の追憶にある真実さを、限りなく愛慕するの情を感じることができる」。
「おあん」に見る男女の生と性
「おあん物語」に関心を示した作家には、谷崎潤一郎、そして土佐出身の大原富枝がいる。二人の取上げ方を紹介しよう。
谷崎が「武州公秘話」を雑誌『新青年』に発表したのは、昭和6年である。後に谷崎全集に寄せた文章で、圓地文子は、「小説のはじめの方で城中の女達が首を化粧する前後の描写はこの作品中、白眉の部分」とし、「恐らく作者はこれらの場面を〈おあん物語〉や〈おきく物語〉などによって構想されたのでしょう」と述べている。
この物語の序で作者は、主人公・武州公を「一代の梟雄(きょうゆう…残忍で猛々しい人)、また被虐性的変態性欲者なり」と述べ、その由来となった事件に入っていく。13歳の秋、幼名・法師丸は、人質となっていた牡鹿(おじか)城が敵兵に囲まれ、篭城を余儀なくされる。ある夜半、五人の女たちが敵の生首に化粧を施す部屋に忍び込み、女たちの作業ぶりに恍惚感を抱く。なかでも、生首の髪を洗う16、7の若い女の、首に視入る時のほのかな微笑に陶酔を覚え、「殺されて首になって、醜い、苦しげな表情を浮かべて、そうして彼女の手に扱われたいのであった」と書く。伊藤整は、「武州公秘話」のモチーフは、「残虐性と美との観念の連絡と交錯」であり、古文書から得た物語に見事に生かされている。「作者一代の傑作」「世界諸国の文学の中にも類を求め得ない特異な作品」と、絶賛している。
戦後の作品では、大原富枝が昭和40年『中央公論』に発表した「おあんさま」がある。老いさらばえた「おあん」の回想から始まるが、城から落ち延びる際に、不破の山中で三人の落武者に襲われる場面を付け加えてある。土佐に落ち着き、結婚した新床でも、「夫のつめたい手が肌にふれたとき、・・・突然に、あの不破の山の三人の男たちを思い出した」とある。忌まわしい悪夢に悩まされながらも、いつしか仲の良い夫婦となっていた。
学問の世界では、昭和18年の岩波文庫版で、戦時教訓的なねらいを隠し、国語学者湯澤幸吉郎が「口語史上注意すべき事」として、語尾の「あらない」「おぢやる」などを指摘している。戦後は、民俗学者の柳田国男が、「民衆の生活」「口語資料」にかかわる「清新な教材」として、東京書籍の高校国語教科書に採用したことを、井出幸男が『宮本常一と土佐源氏の真実』で述べている。国語の古典教材に、庶民の生活誌が登場するのは画期的なことであったが、採択が広がらず、この教科書は消えていった。井出は、宮本の『土佐源氏』も「おあん物語」の語り口調の影響を受けており、また単に乞食から聞き取った民俗誌の資料ではなく、創作が入った文学作品だとする。筆者は、梅棹忠夫監修『民族探検の旅』(全8集・学研 昭和52年刊)に続き、宮本常一監修『日本文化の源流』をまとめるべく宮本を囲んで企画会議を開始していたが、昭和56年に逝去され、実現しなかった。「土佐源氏」(「土佐乞食のいろざんげ」)誕生のいきさつも聞き逃してしまった。宮本は柳田と親しく、田中英光には強い共感を寄せていた。
歴史家の受け止め方も述べておこう。磯田道史は、「女たちが見た関ヶ原の合戦」(『江戸の備忘録』文春文庫)で、「現在の長い平和は江戸時代以来のことだ。実は江戸の初めにも、日本人は今の平成時代と同じように〈戦争を知らない世代の到来〉を経験している。・・・江戸人が聞き耳を立てた〈戦争体験談〉」だとして、おあん物語を紹介している。小和田哲男は、『城と女と武将たち』(NHK出版)で、「おあん物語」から〈鉄砲玉の鋳造〉と〈敵の首へのお歯黒付け〉をあげ、篭城中の女たちの仕事であったことを実証している。
老人と子どもの新しい絆を!
こうして土佐の谷垣守が江戸初期にまとめた「おあん物語」は、その壮絶な戦争体験と、口語体の親しまれやすい文章から、広く読み継がれ、研究や創作の素材にもなってきた。まとめとして、これまで研究者に取り上げられなかった、「老人と子ども」という観点から、この物語の意義に触れておきたい。
「おあん物語」は、子どもが集まって「おあん」に昔話をせがむところから始まる。平和になった江戸時代の文献には、隠居の身となった老人たちが、子どもたちと過ごす様子が、よく現われてくる。越後の良寛は、「霞(かすみ)立つ永き春日(はるひ)を子供らと 手毬つきつゝこの日暮らしつ 子供らと手毬つきつゝ此のさとに 遊ぶ春日はくれずともよし」と歌を詠んでいる。江戸の山東京山は天保3年刊『五節供稚童講釈』で、「隠居とおぼしき剃髪の姿賤(いや)しからず、女小(ママ)供を集めて、五節供の講釈をするなり」と述べ、『菅江真澄全集』には仙台領徳岡の村上家で浄瑠璃を披露しようとした座頭(ざとう)に、子どもが「むかしむかし語れ」と催促した場面がある。これらは、いずれも江戸後期の事例だ。
テレビやスマホのない時代の子どもたちにとって、老人と遊び、昔話や体験談を聞くのは、なによりの楽しみであった。さらに、老人が地域の子どもの教育に積極的にかかわった記録もある。乙竹岩造が、『日本庶民教育史』で紹介した「あやまり役」である。寺子屋では、いたずらや怠慢で破門の罰を受けると、あやまり役の老人に知らせがあり、子どもを諭(さと)した上で、一緒に寺子屋の師匠におわびに行ってくれた。母親よりも、年の功で上手にとりなす老人が適任で、あやまり役は各地で見られた。
だが、老人の話も説教くさくなると、とたんに子どもに嫌われる。話を受け継いだおあんの孫も、やがて子どもたちに鼻であしらわれる。『女重宝記(ちょうほうき)』には、「上代の女はその心素直にして邪(よこしま)ならず。世の末、今の世におよびては、女の心日々に悪しくなり、人をそねみ妬(ねた)み、身を慢(まん)じ、色ふかく、偽りかざりて欲心多く、やさしき心なくして情けを知らず」とある。現代にも通用しそうだが、元禄5年(1692)に出た女子用教訓書の教えである。いつの世も、世代間ギャップは簡単には埋まらない。
だが、老人と子どもを上手に結びつけている例は現在もある。1999年にパリで出会った中学校の国語教師が、移民の子どもにとっている対応で、「正しいフランス語修得には古典的な詩文の暗誦が欠かせない。宿題に出すが、移民は親も教えることができない。そこで老人の家庭を訪問させ、教えてもらった。孤独な老人にも、話し相手ができたと喜ばれた」という。
現代の日本では、増大する高齢者は老人施設などに囲い込まれて別居、地域の子どもはおろか孫と接する機会も少ない。子どもも学校と塾に囲い込まれ、老人の体験談や昔話・わらべ歌を聞き、ともに遊ぶ機会は失われてしまった。おあんは土佐の子どもたちに囲まれ、昔話をせがまれつつ幸せな晩年を過ごした。その生涯を記録した、谷垣守のような人物にも恵まれた。老人と子どもが直(じか)に触れ合い、遊び、語り合う、新しい絆の構築が望まれる。 「三根圓次郎校長とチャイコフスキー」その後の反響
「土佐中初代校長の音楽愛」と、高知新聞が紹介
向陽プレスクラブで発行した表記の小冊子につき、公文敏雄会長から報告いただいた発行直後の反響に続き、筆者の手元にもさまざまな感想が届いたので、お知らせしたい。
まずマスコミ関係では、高知新聞の7月7日朝刊学芸欄に、「土佐中初代校長の音楽愛」との見出しで、片岡編集委員による添付の紹介記事が掲載された。ディック・ミネが大好きという同新聞社元会長のH様からは「三根校長はもっと知られねばと思っていた。この冊子は素晴らしい役割。隠れた話がたくさんです」と、便りが届いた。
「もり・かけ問題」で超多忙の朝日新聞東京本社編集委員(教育担当)U氏は「ひと・教育・そして時代が見えてきます。教育斑の仲間とも共有したい」とのことだった。ヴェトナムの枯葉剤障害児のその後を追っている写真家O氏の手紙には、「土佐中がいかにおもしろい人材を輩出しているか、知りませんでした。三根校長の息子がディック・ミネで、お母さんが日光東照宮の宮司の娘にも、びっくり」とあった。U・O氏とも高知とは無関係な友人だ。
高知出身で元集英社編集担当役員のI氏は、「和辻哲郎の本でケーベルには関心を持っていたが、三根校長が教え子で、寺田寅彦や平井康三郎など高知の人物につながるとは、思いがけないことだった」と、喜んでくれた。高知在住の編集者Yさんは、「すばらしい人物を輩出した土佐中高は、やはり素晴らしい理念を持った教育者によって創られたのですね」といい、高知の大学講師(福祉問題専攻)Y氏は「ケーベル博士は、明治31年に音楽学校で開かれた慈善音楽会の収益金を貧困家庭の子女のための二葉幼稚園に寄付している」と、博士の知られざる慈善行為を教えてくれた。
同窓生では、森健(23回)・門脇稔(25回生)・公文俊平(28回)などの先輩から、「面白くて一気に読んだ。知らなかった話ばかりで、よく取材してある」などの連絡をいただいた。母校には、教職員及び学校・振興会・同窓会の役員用に、向陽プレスクラブから60部謹呈してある。小村彰校長からの礼状をいただいたが、これらの人々がどう受け止め、今後の教育方針や学校100年史に生かしていただけるか、見守りたい。なお、ありがたい反響は、向陽プレスクラブが発行元を引き受けてくれたお陰であり、皆様に感謝したい。
『浮世絵芸術』174号に発表
「“上方わらべ歌絵本”の研究」
8年前に上方の子ども遊びを描いた多色摺の絵本を、いかにもやんちゃな子どもたちの遊ぶ姿に魅せられて入手した。しかし、題名も絵師も不明で、文章ならびに描かれた遊びの内容も、簡単には解読できなかった。近年やや暇になったので再チャレンジして調査すると、安永・天明期(1772~88)の合羽摺(かっぱずり)「上方わらべ歌絵本」であることが分かり、国際浮世絵学会の研究誌にこのほど発表した。合羽摺とは、型紙の切り抜いた部分に、刷毛で色を塗る技法であり、上方で発達した。
この絵本は、テーマが「わらべ歌遊び」、印刷技法が「全ページ合羽摺」であり、この両面から類書のない貴重な子ども本であることが判明した。約250年前の上方いたずらっ子たちを、無事現代に甦らせることができ、ほっとしている。
6場面からなるこの絵本は、いずれも画面いっぱいに子どもたちの遊び戯れる姿が描かれ、上部にわらべ歌が添えてある。では、2場面を紹介しよう。
1.お万どこ行った
歌は、「お万どこ行った、油買いに」で始まり、雨降ってすべって、油一升こぼして、犬がねぶって・・・、と続く。絵は、奉公人のお万が転んだ瞬間と、嬉し気に駆け寄る子どもや犬を巧に捉えている。のれんの影に、三井紋の樽が見えている。
2.子買を子買を
「子買を子買を」「どの子が欲しいぞ」と、買い手と売り手が交互に歌い、対価にくれる御馳走はなにか、問答を楽しむ演劇的遊戯だ。絵は左が売り手で、右側のお膳・蒲鉾・饅頭を持つ子たちが買い手。
*なお、全文閲覧をご希望の方はお知らせください。抜刷を進呈致します。 高知新聞で紹介
「“上方わらべ歌絵本”の研究」
皆様へ
高知新聞9月26日付の学芸欄に、拙論「〈上方わらべ歌絵本〉の研究」の紹介記事が掲載されましたので、添付致します。
この論文は、国際浮世絵学会の研究誌「浮世絵芸術」第174号に発表したものです。 浮世絵展のお知らせ……町田市立国際版画美術館で開催中、11月23日まで
「浮世絵にみる子どもたちの文明開化」
来年が明治維新から150年目に当たるのを記念しての、浮世絵展です。明治の浮世絵には、文明開化の時代を迎え、陸蒸気や学校・英語・洋服に戸惑いながらも、元気いっぱいに遊び学ぶ子どもたちの姿が、しっかり捉えられています。これら明治の子ども関連浮世絵を、初めて総集したものがこの展覧会で、教材錦絵やおもちゃ絵も豊富です。明治を代表する絵師の一人、南国市後免生まれの山本昇雲も、見事な作品を残しています。
本展は中城(国際浮世絵学会理事)が監修、図録に「文明開化と学校で激変した“子どもの天国”」を執筆しています。同美術館は、小田急・JR横浜線「町田」より徒歩15分、℡042-724-5656です。
合田佐和子さん関連のお知らせ
『SAWAKOGODA合田佐和子光へ向かう旅』刊行
また、お嬢様の合田ノブヨさんも、新作コラージュの作品集「箱庭の娘たち」を出版、その出版記念展が、東京・恵比寿の「Galerie LIBRAIRIE6」(地下鉄・JR恵比寿駅西口より徒歩2分、℡03-6452-3345)で、11月4日~26日まで開催される。
町田市立国際版画美術館:新収蔵展
中国版画・中城コレクション
町田市立国際版画美術館では、2018年1月5日から2月18日まで2017年度新収蔵作品展「Present for you」が開催される。今回は葛飾北斎などの浮世絵作品34点とともに、中城正堯旧蔵の中国民間版画16点が展示の中心となっている。
町田市に寄贈した中城コレクションは、中国清朝中期から中華民国にいたる木版彩色の吉祥画・歴史画・神仙画など99点におよぶ。主な製作地は、天津楊柳青と蘇州。これらの作品は、2014年に横浜ユーラシア文化館主催「福を呼ぶ中国版画の世界―富貴・長寿への日中夢くらべ―」に出品され、2011年に中国国家プロジェクトとして編纂刊行された『中国木版年画集成 日本蔵品巻』(中華書局)にも30点ほど収録されている。
ここに掲載した「李文忠掃北」(蘇州・清朝中期)は明王朝建国の歴史合戦画。「宋王観景楊八姐遊春」(天津楊柳青・中華民国)は、北宋の皇帝仁宋が柳八姐に出会って魅せられる戯曲の名場面。
町田市立国際版画美術館:町田市原町田4-28-1(小田急・JR横浜線町田駅より徒歩15分)℡042-726-2771
-倉橋由美子、合田佐和子、田島征彦・征三兄弟、坂東眞砂子-
母校出身“素顔のアーティスト”
土佐高出身の関東在住者有志による筆山会(会長佐々木ひろこ33回)3月例会で、表題の卓話を仰せつかった。母校出身の文芸家・芸術家は、まだまだ多士済々であるが、時間の制約もあり、筆者と直接交流のあったこの5人に絞って報告をおこなった。“素顔の”と題したように、作家論や芸術論ではなく、あくまで筆者がふれた個性豊かなこれらアーティストの思い出話にすぎなかった。当日、23~83回生まで14名の出席者があったものの、これら同窓生の作品を愛読ないし鑑賞した経験のあるメンバーはごくわずかであった。
ここでは、筆山会での発表内容に出席者の反響も加えて順次ご報告したい。拙文が、現代日本を代表する各分野のアーティストとして輝くこれら同窓生の作品を、あらためて愛読・鑑賞する機会になるとともに、皆様が知る別の素顔を回想してお知らせいただけると、大変幸いである。残念ながら女性3人はすべて鬼籍に入ってしまったが、作品は多くのファンに愛され続けている。では、倉橋由美子さんから始めよう。(本文では、敬称を省略させていただく)
母校出身“素顔のアーティスト” (Ⅰ)
『パルタイ』で文壇に衝撃のデビュー 倉橋由美子(29回)
お茶の水での再会、帰郷・結婚・留学
昭和33年頃の春、中大生だった筆者は、東京お茶の水駅の近くで連れだって歩く竹内靖雄と倉橋由美子両先輩(29回)にぱったり出会った。竹内は28回の公文俊平と並んで当時の土佐中高きっての秀才として知られ、新聞部員として交流もあったのですぐ分かった。倉橋は園芸部員で、学校の花壇の世話をする姿を見かけ、また各部責任者が出席してクラブ活動の予算を検討する予算会議で顔を合わせ、見覚えがあった。
相手は二人連れであり、とっさに黙礼を交わしただけですれ違った。東大の竹内は三年になって本郷に来ていたし、倉橋は日本女子衛生短大を経て明治大学に入ったので、同級生として久しぶりに再会したのだろうと単純に思っていた。ところが、夏休みになって帰郷、高知市街に出て喫茶店プリンスに入ると、ここでもお二人に出会った。ようやくその親密さに気付き、今度は「またお会いしましたね」と声をかけた。
それから2年後、筆者が学研で編集者のスタートをきって間もない昭和35年に、明大4年生の倉橋は、『パルタイ』で文壇へ衝撃的な登場をとげた。明治大学新聞に発表直後から話題となって文芸誌に転載、さらに同年末には文藝春秋社から単行本として刊行された。この本の帯に推薦文を遠藤周作とともに寄せた倉橋の恩師で評論家・平野謙は、「革命運動の根ぶかい純粋性と観念性を一学生に具現した作品」であり、「大江健三郎の処女作をみつけたときに似た興奮をおぼえる」と、斬新なこの作品に出会った感激を吐露していた。
筆者も一読し、抽象的・寓話的な独自の作風とされながらも、当時の革新政党による学生を巻き込んでの労働者へのオルグ活動の世界が鮮やかに捉えられているのに驚嘆した。知識だけで描ける文章ではなく、実態を把握したうえでの創作と読み取れた。竹内の協力も相まって倉橋の才能が開花したであろうと推測した。竹内は東大経済学部大学院を終えると成蹊大学教授となり、経済思想史・経済倫理学で業績を挙げるとともに、経済エッセイでも数々の名文を残したが、平成23年に逝去した。
後に聞くと、倉橋は土佐中高時代には受験勉強そっちのけで文学全集の作品を破読、「“くまてん”(吉本泰喜先生)のお陰で漢文・漢詩が好きになり、母親の反対を押し切って文学部に入学、仏文を専攻してカフカ、カミュ、サルトルに親しんだという。大学では欧米の新しい文学の潮流と、学生運動の先端に触れ、鮮烈な倉橋文学が誕生、純文学の新鋭として出版各社から追いかけられることとなる。
『パルタイ』は35年度上期芥川賞候補になったが、最終審査で北杜夫の『夜と霧の隅で』と競い、二作同時選定の意見も出たが結局北のみが選ばれる。倉橋の作品は、テーマも文体もあまりにも斬新だっただけに拒否反応を示す評論家もいたのだろう。翌年度も『暗い旅』が候補に挙がるが選にもれる。この時の受賞者は、後に夕刊紙・週刊誌でポルノ小説を乱作する宇能鴻一郎であった。時を経て池袋の場末の居酒屋で、ひと仕事を終え、黙々と杯を傾ける宇能を何度か見かけたが、受賞時の面影はなかった。選考委員の先見性が疑われる選考だった。『パルタイ』は、36年に第12回女流文学賞を受賞する。
昭和37年、明大大学院に進んでいた倉橋は歯科医だった父の急逝で退学し、土佐山田町の自宅に帰る。この際に、同年婦人公論女流新人賞を受賞したものの次作の執筆に苦慮していた宮尾登美子や、高知支局にいたNHKの熊谷冨裕、朝日新聞の米倉守(後に美術記者として活躍)と出会う。旧知の西岡瑠璃子先輩(28回)とも再会する。そして39年には、宮尾の仲人で急遽熊谷と結婚する。後に関東同窓会の『筆山』4号での筆者のインタビューに応え、結婚のいきさつをこう語ってくれた。「宮尾さんの紹介で、熊谷と生まれて初めてのお見合いをしたのです。『ものを書くなら結婚した方がいい。食べさせてやる』という言葉に、あまりの感激で、ただ『はい』と、いってしまいました」。 見合いの直後に伊藤整などの推薦で、フルブライト委員会からアメリカ留学の話が来たため、急遽三翠園で挙式をしている。「結婚のいきさつは秘密の約束だったのに、宮尾さんが書いた」とも、語っていた。結婚後に二人はアイオワ州立大で1年間の留学生活を過ごす。熊谷はNHKを退職して独立、映像プロデューサーとなる。
旺盛な執筆活動、旧友とも交流
アメリカから帰国後、旺盛な執筆活動を再開するが、二人のお嬢さんにも恵まれ、主婦としての役割も楽しむ。昭和47年末から半年ほどは、一家でポルトガルへ渡って暮らしている。昭和50年には、早くも『倉橋由美子全作品集』(全8巻)が新潮社から出る。
ここに載せた写真は、昭和62年に市ヶ谷にあった公文教育研究会に公文公先生(7回)を訪ねた倉橋であり、同席した浅井伴泰(30回)である。師弟再会のキッカケは、倉橋がお嬢さんの入学した玉川学園の雑誌に「ソフィスト繁昌」と題したエッセイを書き、公文が当代の代表的なソフィスト、すなわちプロに徹した教師であると称えたからだ。倉橋は、教師の原型は知識を与えるソフィストであり、労働者でも聖職者でもないと説いている。同窓会幹事長として長く接した浅井は、「われわれには高名な純文学作家とは感じさせない気さくな主婦そのもので、同窓会にもよく協力してくれた」と語る。
インタビューを掲載した『筆山』が届いたと電話をくださったとき、印象に残っているのは、「あれは書かなかったねえ」である。「あれ」とは、学生時代のお茶の水・高知での出会いだ。続けて、「彼の奥さんも高知の人なので気にするといけないので・・・」と、気配りをみせていた。竹内は、昭和52年に『イソップ経済学』、その後『世界名作の経済倫理学』で、古典物語を素材に登場人物の思想と行動を分析、軽妙なエッセイを残している。つい、倉橋が昭和59年に発表した『大人のための残酷童話』や、続く『老人のための残酷童話』を連想する。竹内は、ギリシャ悲劇からカミュ『異邦人』まで取上げているが、各名作の末尾には「教訓」を添えてあり、これは倉橋の『残酷童話』でも同様である。
竹内もまた、「公文先生の蔵書」というエッセイで、公文の思い出を「それこそハレー彗星級の知的巨人だった」「私は物に憑かれたように“公文図書館”の本を読んだ」と記している。手にした本は、数学者デデキントの『連続数と無理数』から、自然科学、歴史、文学におんでおり、イソップ物語も土佐中時代にこの図書館で見付けたようだ。
奇想天外な創作と忍び寄る病魔
倉橋は著名になっても文壇で群を作ることはなかったが、芥川賞で競った北杜夫、そして重鎮・中村真一郎とは仲がよかったようだ。筆者も中村にはお世話になり、いつだったか熱海の別荘に銅版画家・木原康行とまねかれ、中村夫人(詩人・佐岐えりぬ)ともども飲み明かした。その際に倉橋の話になって、「素晴らしい作家だが、男女の愛情描写やエロスがまだ不足。もっと遊ぶように言ってくれ」と、告げられた。後日、倉橋に話すと、「私も“小説に艶がない、もっと遊べ”と直接言われた」とのことだった。神宮前の中村宅では、たまたま親友・加藤周一、堀田善衛との座に同席した。二人は中村をからかうように「彼は昔から我々が政治談義に熱中すると居眠りを始めるが、女の話になるとむっくり起きてくる」と打ち明けてくれた。小説家にとって、エロスは不可欠のようだった。
後に、坂東眞砂子(51回)が『山妣(やまはは)』で直木賞をとった勢いからか「いまの日本の小説は面白くない。倉橋さんも・・・」と広言していた。倉橋と会った際に、このことにも話が及んだが、「元気があっていいねえ」と受け流していた。すでに昭和59年に発表した『大人のための残酷童話』の「あとがき」で、「近頃の小説は面白くないという説があります」と書き、その原因を解明しつつ、「大人に喜ばれる残酷で超現実の世界やエロチックに傾く大人の童話に手を付けた」と述べている。
大人の童話だけでなく、後期の長編小説では奇想天外な創作世界が展開、男女の恋愛にはエロチックな場面が織り込んであり、思わず引き込まれる。その代表が、未来の女権国家を描いた『アマノン国往還記』(泉鏡花文学賞受賞)である。ここでは、アマノン国(土佐方言「あまのん」に由来)へ潜入した宣教師が、女たちの失ったセックス復活に大活躍をする。もう一つが桂子さんシリーズで、『シンポシオン』では核戦争を前に、教養豊かな人物が源氏物語からギリシャ悲劇・漢詩まで飛び交う大人の会話と恋愛を繰り広げる。サティのピアノ曲が流れ、シェリーやワインが注がれる優雅なシンポシオン(酒宴)で、なぜか思いがけず沈下橋・皿鉢料理・いたどりなど郷土色に遭遇、頬がゆるむのも後輩読者の特権である。くまてん仕込みの漢詩の古典も巧に配してある。
平成7年には、同学年の福島清三から「月刊『文芸春秋』の「同級生交歓」に、泉谷良彦・中山剛吉・大脇順和・倉橋などと出たい。交渉をたのむ」と話があった。同社の知人に相談すると、「編集部は倉橋さんから申し込んで欲しいといっている」との返事。早速本人にお願いしたが、「私から頼むと編集部に借りを作る」と、最初は躊躇していた。出版界では、借りを作ると書きたくない仕事も断われなくなるのだ。しかし、クラスメートの願いを聞き入れて、話をまとめてくださった。大脇にとっては「中学時代の懐かしい少女」、福島にとっては「在学中から主婦型」だった倉橋との久しぶりの再会だった。
やがて平成10年頃になると、電話で体調不良をこぼすようになり、「耳鳴りがひどく、仕事にならない。あちこち耳鼻科の名医を訪ねたが原因不明なの」とのことだった。そして、「耳でなく心臓に問題があると、やっと分かった。しかし治療は困難みたい。気晴らしに体調の良いときに四国遍路を始めた」と伝えてきた。参考までに「高群逸枝の『お遍路』が面白い」と伝えると、「読む読む」といっていた。 病とともに、倉橋が珍しく愚痴をこぼしたのは、夫君の熊谷がかつて沖縄海洋博の仕事で赤字を背負った話だった。プロポーズの言葉と違ってフリーの映像作家はさまざまな不安要素を抱え込んでおり、夫の仕事ぶりは心配のタネだったようだ。晩年の長編『アマノン国往還記』の付録には、「もし女性(私)が育児と男性から解放される時代がきたら、という“仮定”に立って書いてみた(笑)」とある。ぜひ倉橋の切なる願望を、この作品からさぐって欲しい。
平成17年3月に筆者は肺血栓塞栓症で突然倒れた。一月半の入院で命拾いをして自宅療養中だった6月、「倉橋由美子、拡張型心筋症で永眠、享年69歳」の知らせが届いた。
望まれる作品誕生の背景研究
逝去の翌年6月に、明治大学中央図書館で同大学特別功労賞受賞記念「倉橋由美子展」が開催され、なんとか見学にかけつけた。この展示で認識を新たにしたのは、倉橋文学の国際性である。イギリスに飛んで作品の舞台を探訪したうえで翻訳した『嵐が丘』の続編『嵐が丘にかえる』はじめ、最新の『新訳 星の王子様』まで22点が展示してあった。『パルタイ』『アマノン国往還記』など著書の翻訳出版も、英語・仏語・独語・ポルトガル語・中国語など27点におよぶ。さらに、カルフォルニア大バークレー校などの大学院生による「倉橋文学」を取り上げた博士論文5点がならべてあった。
当時、近代文学を専攻した大学生の論文テーマとして、倉橋人気の高いことは聞いていたが、海外でもこれほど評価が高いとは気付かなかった。この倉橋文学誕生には、明治大学でのフランス文学専攻とともに、土佐中高での読書や学び、そして学友・教師との交流 が欠かせない要素であった。西岡瑠璃子たちの協力で、高知県文学館に倉橋コーナーができていると聞くが、母校でもさらなる資料収集と、倉橋文学誕生の背景研究が望まれる。 母校出身“素顔のアーティスト”に嬉しい反響
3月にこのホームページにアップされた「母校出身“素顔のアーティスト”(Ⅰ)倉橋由美子(29回)」に、多くの嬉しい反響があったので、感謝してお知らせしたい。
まず、最初の読者であった藤宗俊一編集長からで、<倉橋さんの記事を読んでいて、『山田に帰った』という言葉で、「たしか、当時の部長だった宮地さん(40回生)ら女性陣が山田のご自宅に取材に伺ったはずだけど……。」調べてみると60号に掲載されていましたのでpdfで添付します。当時、私は中学3年生で KURAHASHI Who???の世界にいました。それが、半年後には編集長に上り詰めるとは、新聞部も人材が不足していたのですね。>とのこと。
さすがに名編集長で、病後の体でありながら、昔々の関連記事をきちんと思い出して送ってくれた。どうか、宮地(島崎)敦子記者のインタビュー記事「すぽっと ストーリーのない小説 倉橋由美子さん」をお読みいただきたい。
ついで、倉橋さんと同期の大脇順和(29回)さんが、拙文で触れた『文芸春秋』平成7年2月号の「同級生交歓」の誌面コピーに、6人の動静(倉橋・泉谷が他界、福島・岡本が闘病中、元気なのは中山・大脇)を添えて届けてくださった。ここに、その紙面を紹介する。なお、このなかの中山剛吉さんが新聞部、また大脇さんの弟・大脇恵二(31回)さんも新聞部だった。
倉橋さんをよく知る先輩、28回生の公文俊平さんから「知らないことが少なくなく、興味深かった」、西岡瑠璃子さんからは「懐かしいことばっかり」との連絡をいただいた。
久武慶蔵(30回)君は、「倉橋文学は実存主義文学の模倣にすぎないとの批判に対して、彼女は文学は本質的には模倣だと答え、ハチキンの気概を感じ、“土佐人の原点”をみました」とのメールを寄せてくれた。
この記事をKPCのHPにアップしたことは、会員以外にもメールで知らせ、閲覧を呼びかけた。反響は、どうしても倉橋さんと近い世代に限られたが、向陽プレスクラブの存在告知にいくらかはつながったようだ、前田憲一(37回)さんのように、初めてこのHPを開き、多彩な情報にビックリした後輩もいた。 母校出身“素顔のアーティスト”(Ⅱ)-1(前編)
焼け跡で誕生した前衛アートの女神合田佐和子(34回)
熱烈なファンのいた合田佐和子だが、残念ながら同窓生では同学年かよほどの美術好きでないと、その作品に触れたことがなく、名前も記憶に残ってないだろう。闘病の末に平成28年2月に亡くなると、4月には嵐山光三郎、巌谷國士、唐十郎などを発起人に、「お見送りする会」が品川プリンスホテルで開催され、交遊のあった前衛文化人や現代アートの女神とあがめたファンが多数つどい、マルチアーティストとしての合田の多彩な足跡を偲んだ。翌年1月には、遺稿集とも言うべき『90度のまなざし』(港の人)、8月には作品集『合田佐和子 光へ向かう旅』(平凡社)と、相次いで刊行されたのもその人気故である。追悼展も、日本橋「みうらじろうギャラリー」などで次々と開かれた。
では、『90度のまなざし』の著者紹介から、略歴を見てみよう。「1940年、高知市生まれ。武蔵野美術学校本科在学中より、廃物を使ったオブジェ制作を開始。1965年に瀧口修造の後押しにより初個展、以後、定期的に個展開催。70年代より油彩作品を制作、唐十郎の劇団状況劇場と寺山修司の演劇実験室天井桟敷の舞台美術や宣伝美術も多く手がける。映画スターたちのポートレイト、目玉、エジプト、バラや鉱物などをモチーフに多数の作品を発表、超現実へと誘う幻想的な世界を作りあげた」とある。
略歴では触れられていないが戦争中は広島県呉市で過ごし、5歳で終戦を迎え、高知市へもどって焼け跡で遊んで育つ。後にこの頃を回想し「焼け跡の中で、色ガラスが溶けて土や石と合体した塊を発見、半狂乱になって集めたりした。後年、この原体験は、ガラス箱のオブジェなどとなって、くり返し現われてくる」(「現れては消えるあのシーン、あの俳優」『キネマ旬報』1995年4月下旬号)と記している。小学校ではプロマイド集めに熱中、嵐寬寿郎の鞍馬天狗などを町はずれまでかけずり回って探し集めたという。
父は広島で繊維メーカーの技術者として働いた経験を生かし、戦後の高知では衛生材料製造業を興して成功を収めていた。比較的裕福なインテリ一家で、高知市が始めた中央の文化人を招いての夏期市民大学を家族で受講するなど、文学や芸術にも関心が高かった。
土佐中への入学は、昭和28年(1953)である。高校時代はもっぱら新聞部員として活躍していた。その様子は、「向陽プレスクラブ」ホームページ2016年3月12日付「新聞部同期の合田佐和子さんを偲ぶ」で、印刷所での大組に立ち会って、美しい紙面の割付けに力量を発揮したことなど、吉川順三(34回)が心のこもった追憶をしている。
彼女の略歴紹介で目をひくのは、画家では納まらない多彩な美術ジャンルでの活躍である。オブジェから油彩画、写真、舞台美術など自由自在に異種領域間をワープ、どの分野でも合田カラーで人々を魅了してきた。まずは、合田が制作中の写真と、母校の創立75周年記念『会員名簿』の表紙を飾った「クリスタルブルーなデートリヒ1」から、人と作品を思い起こしていただきたい。そして、彼女の土佐高新聞部時代から中央の美術界での活躍まで、ほぼ60年間の交流で接した素顔をつづり、手向けとしたい。
新聞部の毒舌記者、オンカンが補導
合田は4年後輩であり、出会ったのは筆者が大学時代(昭和30~34)に帰郷、新聞部の活動に参加した際であった。この時期はいわば新聞部の黄金時代で、合田の同期には吉川順三(毎日新聞)、秦洋一(朝日新聞)、国見昭郎(NHK)など、のちにマスコミで大活躍する人材が揃っていた。さらに、浜田晋介や山崎(久永)洋子も編集長として活躍していた。「向陽新聞」も彼らが編集制作の中心であった昭和31年度には、5回も発行している。筆者も夏休みの恒例事業になっていた「先輩大学生に聞く会」や、大嶋校長を囲む座談会などに、よく狩り出された。
新聞制作以外の活動で、最も印象に残っているのは夏休みのキャンプと、新年会である。31年夏には種崎千松公園に、翌年は大田口の吉野川河原にテントを張った。新年会は、岡林敏眞(32回)の実家料亭などで毎年開いた。これら、お遊び会に必ず付き合ってくれたのが合田である。新聞部の部室では、毒舌で仲間をやり込め「恐ろしかった」という部員すらいるが、学校外では嬉々として活動、特に海水浴は好きなようだった。水着姿の彼女はすらりとした体形に日焼けした肌、なにより鋭いまなざしが強く印象に残っている。
彼女は種崎の海水浴場で、「突然の大波をかぶって溺れそうになったとき、先輩に助けられた」と後に語っていたが、これは幻影かも知れない。荒波に立ち向かうのは中学時代から好きだったようで、台風の直後に祖父のスクーターで桂浜に駆けつけ、被害を受けた水族館をのぞいたあと、「決死のゲーム」に挑戦したという。それは、海に突き出た岬の先端に祀られた祠・竜宮への石段を、大波が引きあげて次に打ち寄せる40秒ばかりの間に全力で駆け上ることだった。岬のてっぺんに立って、絶壁にぶつかって落ちる波の「とろけるような奇怪なオブジェの大乱舞」をながめ、はしゃぐためだったと述べている。
高校時代には映画館で補導を受け、強い印象を受ける。「学校帰りに映画館へ入り、“青い麦”を見て、出口で補導された。怒った時はライオンの如く、やさしい時はカンガルーの如し、と自らを“オンカン”と命名した中山(駿馬)先生が、ライオンになって待ちかまえていて、説教された」。
すばらしい映画のどこがいけないのか、やっとの思いで聞くと「すばらしい映画だからこそ、見てはいけないのだ!」と言われ、「甘い、背徳的な、せつない気分は、今でも心に灼きついていて、今ごろになって、やはりオンカン先生は正しかったんだ、と思えるのである」(「現れては消えるあのシーン、あの俳優」前出)と回想している。
土佐高でアーティスト合田誕生に結びつく大きな出来事は、髙1になった新学期から、美術教師に高崎元尚(16回)が赴任したことである。前任の鎮西忠行も画家だったが、静物や風景を写実的に描く正統派であった。新任の高崎は、東京美術学校(現東京芸大)を出てモダンアート協会や具体美術協会に属し、戦後日本の前衛美術界をリードしてきた人物であった。「生涯現役」を掲げて創作に挑み続け、高く評価されたが、昨年6月高知県立美術館で「高崎元尚新作展-破壊 COLLAPSE-」開催中、94歳で亡くなられた。
高崎の赴任によって、再び絵画への興味を甦らせ、新聞部だけでなく美術部にも出入りするようになった。14歳で描いた自画像が、愛知県の「おかざき世界子ども美術博物館」に収蔵されている。
太いタッチで少女の真っ直ぐな内面まで表現している。高3になると、美術へと進路を定め、夏休みに上京して御茶の水美術学院へ通う。美術大学へ進学するためにはデッサンなど実技が必要で、二学期になっても東京にとどまり続け、年末にやっと帰高している。この時の新年会の写真には、すっかり垢抜けした合田の姿が見られる。前列の女性は右から旧姓で、34回の山崎洋子・合田佐和子、35回の大野令子・浜口正子・早川智子、31回の森下睦美(後の新聞部顧問)である。大学は、武蔵野美術学校本科(現武蔵野美術大学)商業デザイン科に入学する。
焼け跡で誕生した前衛アートの女神合田佐和子(34回)
大学を出て学研の学習雑誌編集部にいた筆者に、彼女から突然訪問したいと電話があったのは、たしか昭和37年(1962)であった。彼女は土佐高の同級生で多摩美術学校(現多摩美術大学)の田島征三を連れ、作品を抱えて現れた。二人は大学がちがっても同じ美術専攻で、上京してから意気投合、就職はせずに美術で食っていこうと思い立ち、見本の作品を持って出版社回りを始めたのだという。
田島とは初対面だったが、すでに全国観光ポスター展で、土佐沖のかつお釣りを描いた躍動感あふれる作品が金賞を得ており、自信満々だった。力強いタッチの人物や生き物は小学生を読者対象とする学習雑誌にも向いており、興味を示す編集者がいて早速仕事に結びついた。合田はカットやオブジェの写真を見せてくれたが、ちょっと子ども向きではなかった。むろん出版社によっては、合田も歓迎されたようだ。
昭和37年の夏休みには、母校の国語教師・新聞部顧問となった森下睦美が、全国高校新聞大会に出席のため、3人の女子部員をともなって上京した。その際の写真には、前列の4人の上京組を迎え、後列には左から岩谷清水(27回)・合田・横山禎夫(30回)・筆者が並んでいる。
この頃合田はガラクタオブジェの制作に熱中、瀧口修造などから認められ、40年(1965)には銀座で初の個展を開く。土佐のやせた少女は、さなぎからチョウへと美しく変身し、個展の前年には同郷の画家・志賀健蔵と結婚、披露宴は高知のホテルで盛大におこなわれた。オブジェは次第に注目を浴び、澁澤龍彦、イサム・ノグチ、白石かずこ、池田満寿夫などからも評価されるようになった。41年1月に長女を出産するが、6月には離婚する。友人には、「経済的にも頼ろうとするばかりで、稼ごうとしない男に愛想を尽かした」と、漏らしている。当時、合田からもらった名刺が残っている。A3の用紙いっぱいに一つ目の妖怪やろくろ首の女などが乱舞しており、氏名・住所・電話は申し訳のように小さく添えてある。目玉への執着もうかがえる。
やがて四谷シモン、唐十郎と知り合い、昭和44年(1967)には唐が主宰する状況劇場「少女都市」で透明な仮面など小道具を制作する。空き地や神社の境内に、怪しげな紅テントを張って演じられる不思議な演劇空間にはまり、舞台美術や宣伝美術もまかされるようになる。この頃、突然電話をかけてきて、「プラスチックで仮面や手足を制作したい。どこかいい業者を知らないか」とのこと。当時、学習雑誌の付録としてプラスチック製の教具制作も手がけており、すぐに出入りの金型屋や成型加工業者を紹介した。
こうして多忙となったなかで、46年1月には彫刻家三木冨雄と結婚、ロックフェラー財団の招聘を受けた三木とともにニューヨークに渡り、8月まで滞在する。ここでアンダーグラウンドの映像作家ジャックと出会い、夜ごと夫婦で廃墟のようなロフトに訪ねたという。
ニューヨークで世界の先鋭美術に触れるとともに、古ぼけた写真を拾ったことが、アーティスト合田の大きな転機となる。油彩画に拒絶反応を示し、立体物のみを制作していた合田は、こう述べている。「N・Yの裏通りで一枚の写真を拾った。二人の老婆と一人の老人が写っている、小さな銀板写真だった。手に取って眺めているうち、ハタと気付いた。アレ、これはすでに二次元ではないか」(「INTRODUCTION」『合田佐和子作品集 パンドラ』PARCO出版)。8月東京に帰ると、経済生活を維持するためにも油彩に取り組む覚悟を決め、渋谷の画材店で店員に油絵の描き方をたずね、絵の具5本と百号のキャンバスを買う。高校時代に見た「甘く、背徳的な」女優たちのプロマイドも収集、こうして、後に代表作となるスター・シリーズが誕生する。
唐十郎に続き寺山修司の演劇に参入
昭和55年(1980)3月には渋谷の西武百貨店美術画廊で「夢の回廊 合田佐和子[ポートレート]展」を開催、作品集「ポートレート」を刊行する。手元に残るこの作品集には、ローマ字のサインとともに1980.3.13と記されている。70年安保後の気怠い街角に、往年の退廃的スターが、エロスと妖気と死の影をまとって再登場、衝撃を与える。以来、生身の人間を描くことはなく、写真を素材に自己流の油彩で描き続ける。
この間、米国から帰国後47年に三木と離婚するが、同年末に次女が誕生する。舞台美術の仕事も広がり、「状況劇場が好きだから、ダメ」と言い続けてきた唐のライバル・寺山修司の天井桟敷にも参画する。演劇「中国の不思議な役人」から、香港ロケによる映画「上海異人娼館」など、寺山作品に欠かせない存在となる。だが、最初に「演劇の世界は地獄だよ」とからかわれたとおり、その仕事は過酷だった。台本が遅れに遅れ、「青ひげ公の城」では、一週間で14景の舞台下絵を描かねばならず、「さび付いた頭をフル回転させ、狂ったように取り組んだ」と語っている。心身ともに消耗の激しい作業だったが、寺山のイメージに見事に応え、喜ばれる。唐組の仕事も終生継続する。
さらに合田は、写真の撮影から現像・コラージュの技法も習得する。米国から上陸したポラロイド写真にいちはやく挑戦、昭和56年には「合田佐和子ポラロイド写真展」を六本木アートセンターで開催する。59年には銅版画による豪華詩画集『銀幕』を刊行、その出版記念会案内状で四谷シモンは「当代きっての才媛、ぼくらのマドンナ、佐和子が・・・電光石火の早技で〈月光写真〉の如き〈銀幕のスターたち〉を誕生させました」と、讃えている。油彩・演劇・写真・銅版と、合田のとどまるところを知らない快進撃は、若者の支持を得て現代アートの女神かのような存在となっていく。
昭和60年(1985)になり、娘二人とエジプト・アスワンに移住すると知らせがあったときは、筆者も訪ねた土地であり、あの砂漠と青空だけが広がる世界への脱出は理解できた。いっぽう、灼熱の村での暮らしに危惧も感じた。一家はヌビア人の村に住み込み、泥の家に居住する。合田は「サバコ、サバコ」と親しまれるが、頻繁に停電が発生、冷房もままならない生活に長女(当時19歳)は早々に帰国、次女(12歳)には「映画もTVもネオンも恋しいヨー!」と嘆かれ、1年足らずで滞在を打ち切る。
滞在中、エジプト村日記を『朝日ジャーナル』に連載、後に『ナイルのほとりで』と題して朝日新聞社から刊行される。この頃、筆者は「船の目玉―海の魔除けの不思議な系譜」を執筆中で、ホルスの目に魅了された合田から、ナイル川の帆船ファルーカの目玉情報の提供を受けた(拙著『アジア魔除け曼荼羅』NTT出版に収録)。朝日新聞では、平成3年(1991)の連載小説「軽蔑」(中上健次)の挿絵を担当、目をテーマに描き続ける。
独自の目で幻想的世界を開拓
帰国後は、世田谷区から神奈川県葉山町、さらに鎌倉へと転居し、旺盛な制作活動を再開する。平成4年2月には、石川県小松行きの飛行機で偶然彼女と乗り合わせた。若い男性助手を連れており、金沢市で4日間にわたる公開制作をするとのことだった。仕事の日程をやりくりして会場に駆けつけ、二百号の大作に挑む現場に立ち会えたのは幸運だった。
かつては、小さな個人画廊での個展が中心で異端の画家という存在だったが、次第に時代の先端を行くアーティストとして美術界からも注目されるようになり、民間・公営双方の著名美術館からも声がかかるようになった。特に平成13年(2001)の高知県立美術館<「森村泰昌と合田佐和子」展>と、15年の渋谷区松濤美術館<「合田佐和子 影像 絵画・オブジェ・写真」展>は、彼女の代表作を総集した展覧会で、異分野への果敢な挑戦と斬新な表現を求め続け、戦後の日本美術界に刻印した鮮やかな足跡が読み取れた。
残念ながら平成20年代になると体調を崩すことが多くなり、鎌倉や日本橋の個展に足を運んでも本人の姿はなかった。本人の声を聞くことができたのは22年4月で、土佐高関東同窓会会報への寄稿を、新聞部出身の永森裕子(44回)から頼まれて電話した。元気な声で快諾してくれ、筆者の病状(肺血栓)を心配し、『脳梗塞糖尿病を救うミミズの酵素』をぜひ読むように薦めてくれた。親しい間柄の栗本慎一郎(経済人類学者)が、脳梗塞の治療回復の体験から綴った本で、合田の病にも効果があったという。しかし、個展の作品制作に追われて体調が悪化、結局原稿は書けず、堀内稔久(32回)が代わってくれた。
かつて寺山修司は、「合田佐和子の怪奇幻想のだまし絵は、絵の具に毒薬を溶かして描くかと思われるほど、悪意と哄笑にあふれるものである。・・・だが、そうした絵を描く合田佐和子自身は、支那服の似合う絶世の美女である」(「密蝋画」)と賛辞を惜しまなかった。
その合田の才気あふれる頭脳も、過酷な要求に応えての舞台美術制作から、油彩での意表をつく幻想的で奇怪なスターの描出、「目玉」への偏愛と創造に追われ、次第に機能障害をきたしたようだった。訃報は新聞で知った。焼け跡のガラクタから美に目覚め、マルチアーティストとして現代美術の先端を走り続けた75年の生涯であった。昨年11月には次女合田ノブヨの「箱庭の娘たち」作品集出版記念展が、渋谷区恵比寿の画廊であった。母親から受け継いだかのようなコラージュ作品が並び、熱心な若者ファンが会場を埋めていた。いずれ高知県立美術館で、合田佐和子回顧展ないし合田母子作品展の開催が望まれる。
母校出身“素顔のアーティスト”(Ⅲ)-1(前編)
大地のエネルギーを絵筆で歌う田島征彦・征三兄弟(34回)
今年(2018年)の正月4日、朝日新聞を開いて驚いた。一頁丸ごと使ったカラー広告があり、両手を広げたハダカの子どもを頭上高く掲げた父が、大地を踏ん張って立っている。泥絵具の荒々しいタッチは、まぎれもなく“あの田島征三”の作品だ。「働く人みな、ずーっと健康」(伊藤忠)とある。まっとうな労働に誇りを持つ商社のイメージ広告で、小さくSeizoのサインがある。しかし、日本を代表する商社の“征三”起用に、不思議な想いにかられた。それは20年前、彼が住んでいた東京都日の出村(現日の出町)での広域ごみ処分場建設反対運動に立ち上がったものの、工事が強行される中で胃がんを発病、手術後に見舞った際のやつれた姿が、いまだ目に焼き付いていたからである。
今は伊東市に住む本人から、電話で経緯を聞いた。伊藤忠商事とは昨年(2017年)からの付き合いで、6月を皮切りに3回にわたって日本経済新聞で、見開き二面を使っての大広告に起用され、それが同年度の日経広告大賞に輝き、今年の正月広告につながったという。広告代理店があげたいくつかの候補イラストから、田島征三の絵本に見覚えのあった伊藤忠・岡藤正広社長(現会長)が即決したのだ。昨年は、「懸命に〈稼ぐ〉」、「無駄を〈削る〉」、「損を〈防ぐ〉」がテーマだった。〈稼ぐ〉では、荷車に満載した魚や野菜を全力で運ぶ夫妻が描かれている。骨太の経営理念を見事に表現したとして、大賞受賞となった。
筆者のとまどいを察したのか、「日の出村のごみ闘争では、豊かな自然をぶちこわす行政と戦ったが、別に何でも反対じゃない。いま、廃校を丸ごと作品にした〈絵本と木の実の美術館〉のある新潟県十日町市では、市長をはじめ行政とも仲ようやりゆう」とのこと。なお、伊藤忠では元厚生労働省事務次官の村木厚子(49回)が社外取締役を務めている。
こうして昨年、田島征三は大学時代の高知県観光ポスターでの金賞以来、再度広告の世界で脚光を浴びた。それにとどまらずに新作絵本でも、大がかりな野外展示(インスタレーション)でも、新たな挑戦を始めている。
いっぽう田島征彦にとっても、昨年は絵本作家としての新境地を確立する記念すべき年であった。2015年に障害者と健常者がともに生きる姿を描いて日本絵本大賞を受賞した『ふしぎなともだち』(くもん出版)に続き、2年の取材と推考を経て生まれた『のら犬ボン』(くもん出版)が、人と動物の関係を問いかける創作絵本として社会的反響を呼んだのだ。この絵本は、移住した淡路島で出会った三匹の野良犬から発想を得て、動物愛護センターなど関係者の取材を重ねてかき上げたもの。刊行直後から「ペット思う心 絵本で訴える、島の捨て犬問題取材し創作」(神戸新聞)、「捨てられる側の悲しみ」(高知新聞)など、各紙が社会面で大きく取り上げた。この絵本は、従来の型染絵ではなく、太い絵筆を使った大胆なタッチの描画ながら、人や犬の表情を巧みに表現している。
なお、征三は「たしませいぞう」、征彦は「たじまゆきひこ」と、姓の読み方を変えている。混同を避けるためだが、若い頃はしばしば同一視や取り違えがあった。
兄弟で日本・世界の絵本賞を総なめ
この一卵性双生児と筆者との出会いは、合田佐和子(34回)の項で書いたように1962年(昭和37)で、まず弟征三であった。当時、征三は多摩美術学校(現多摩美術大学)図案科在学中で、学習誌にいくらかカットを描いてもらった。やがて京都市立美術大学(現京都市立芸術大学)染織図案科を出た兄・征彦も紹介された。ただ、1970年頃から筆者は大人ものの編集部に異動したので、二人から個展などの案内状をもらっても、仕事での付き合いは途絶えていた。征三が個展で「作品の大小にかかわらず一点一万円、“早い者勝ち”としたら、大きい方からどんどん売れた」などの話は洩れ聞いた。
田島征三は、1965年(昭和40)に彼の作品のファンだった喜代恵と結婚、2年後に『ちからたろう』(今江祥智・文、ポプラ社)がブラティスヴァ世界絵本原画展(スロバキア)で金のりんご賞を受賞、4年後にはこの絵本賞の審査員に招かれる。1969年に東京都西多摩の日の出村に移住し、農耕と創作活動に取り組む。1973年には『ふきまんぶく』(偕成社)が、講談社出版文化賞を受賞、絵本が内外で高く評価されるとともに、『やぎのしずか』シリーズが幼児の人気絵本となる。また、米軍機墜落事故の犠牲者・館野正盛の裁判闘争を支援する会に加わり、社会福祉法人しがらき会信楽青年寮(知的障がい者生活寮・作業所)の手すき和紙や陶板を活用、協力して作品を制作するなど、社会的視野も持ち続けた。
田島征彦は、入学当初は染織になじめず教授にも反発したが、次第になじみ、専攻科(大学院)を経て、大阪芸術大学や成安女子短期大学の講師となる。染織を教えつつ、シルクスクリーンによる作品制作も始める。1971年には教え子の英子と結婚する。やはり教え子だった高畑正が、筋萎縮症と戦いながら懸命に制作する生き様に衝撃を受け、講師を辞職、1975年に丹波の八木町へ妻・英子と移住し、農作業をしながら作品制作に取り組む。同年、京都府洋画版画新人賞を受け、賞金でソ連・ヨーロッパ研修旅行に出かける。途中から征三も加わる。帰国した翌年、3年前から取り組んできた初めての絵本『祇園祭』(童心社)が完成、いきなりブラティスヴァ世界絵本原画展で金牌賞を受賞する。1979年には『じごくのそうべえ』(童心社)が絵本にっぽん賞に輝く。吉村敬子との共同制作『あつおのぼうけん』は、障害者と本音でぶつかりあい、行動をともにすることから生まれ、感動的な絵本に仕上がった。1980年には、NHK「新日本紀行」が、兄弟それぞれの農耕と創作の日々を追いかけて紹介する。
こうして画家・絵本作家として注目される存在になった二人は、1990年刊『現代日本 朝日人物事典』(朝日新聞社)に揃って登場、児童文学者の今江祥智がその作風をこう紹介している。「征三:卒業制作が絵本『しばてん』で、泥絵具をいかした極めて土俗的で大胆な画風のもの。・・・絵本『ふるやのもり』、『ふきまんぶく』から最新作の『とべバッタ』まで、従来のお子さま絵本とは対極的な、力動感あふれる個性的な絵本を相ついで発表してきた」。「征彦:型染絵を学び、その手法で最初の絵本『祇園祭』を制作。簡潔で力強く美しいこの祭りの絵本で注目を集めた。以来『じごくのそうべえ』から・・・同じ手法でユニークな絵本をつくりつづけている」。今江は、エッセイストとしての二人も高く評価している。
征彦『中岡はどこぜよ』がボローニャで絵本賞
1981年(昭和56)に筆者は公文公(7回)のお誘いで公文教育研究会出版部に転職、1988年には児童書・教育書を出版する「くもん出版」を設立してその責任者となった。絵本も重要分野で、田島兄弟とも仕事が再開された。まず、くもん出版の季刊PR誌『本の海』に征三による幼い頃の回想記『絵の中のぼくの村』を連載してもらった。1940年に大阪で生まれた二人は、敗戦の年に父の故郷・高知県芳原村(現高知市春野町)に移住。ともに病弱だったが、勉強そっちのけで豊かな自然に浸り、川魚や野鳥を追いかけ、いたずらやけんかをくり返しながら成長していく。その姿が絵入りで赤裸々につづられ、大好評だった。
この頃、征三の住む日の出町の山野が、都下三多摩地区の廃棄物を処分する巨大ごみ処分場の候補となる。田島たち住民は「日の出の自然を守る会」を結成、田島夫人・喜代恵が代表になる。彼らは「地域毎の安全でコンパクトなごみ処分場」という代案を掲げて運動を展開する。征三たちの呼びかけで、音楽家・小室等、映画監督・高畠勲など著名文化人も応援に駆けつける。筆者も「日の出の森・支える会」に入会した。しかし、征三たちの体を張っての抵抗も、行政に強制排除されて工事は着工となる。
そんななかで1990年、京都の征彦から「たっての願い」として、刊行早々に出版社が倒産して絶版になった『中岡はどこぜよ』を出して欲しいとの依頼があった。絵本担当の編集者が気に入り、喜んで引き受けた。坂本龍馬がテレビの中から大阪に現れ、「中岡はどこぜよ」と、自転車で走りまわるナンセンス絵本である。征彦による土佐弁の文に、京都美大の後輩・関屋敏隆のとぼけた切り絵が見事にマッチしている。これが“たまるか”翌年のボローニャ国際児童図書展で絵本賞を受賞した。作者・版元揃ってイタリア、ボローニャに来いとのこと。急な話で征彦はスケジュール調整がつかず、関屋と筆者が参加、帰国後に京都丹波の田島家に報告に行った。そのときの写真には、征彦夫妻と関屋、お土産に持参した古代エトルリア出土の人体彫像(レプリカ)が写っている。合鴨を飼育しての無農薬栽培で実った自家米ご飯や、採れたての野菜を使った鴨鍋をご馳走になった。
征彦からは、続いて「たっての願い」として、土佐のミミズを主人公にした『みみずのかんたろう』を出して欲しいと言ってきた。子どもが喜ぶ絵本とは思えず躊躇したが、作者・編集者の熱意とボローニャでのタナボタの絵本賞もあって引き受けた。高知で話題になり、高知新聞(1992年4月)のインタビューを受けた征彦は、「出版社にも〈ミミズが主人公では・・・〉と、断わられ続けたが、土佐高の先輩が経営する東京の出版社が快く引き受けてくれた」と述べている。幼年時代に出会ったかんたろうミミズを求めて再三帰郷し、巨大なミミズの恋を型絵染で色彩豊かに染め上げ、彼の代表作の一つとなった。土のぬくもりを出すために、原画は水上勉が越前若狭ですいた竹紙に染めてある。
母校出身“素顔のアーティスト”(Ⅲ)-2(後編)
大地のエネルギーを絵筆で歌う田島征彦・征三兄弟(34回)
田島征彦のミミズ絵本ができ上がった1992年(平成4)には、連載を終えた『絵の中のぼくの村』も出版した。これが映画監督東陽一の目にとまり、高知出身・中島丈博との共同脚本で、シグロによる映画化が決定した。1995年の夏、仁淀川上流のロケ地・吾北村を訪ねた。オーディションで選ばれた双子の子役が、のびのびとやんちゃな兄弟を演じていた。完成試写会では見事な出来映えに感動、母親役の原田美枝子、父親役の長塚京三にもお会いした。
翌年、突然朗報が届いた。「第46回ベルリン国際映画祭、銀熊賞受賞!」の知らせだ。この映画は、その後もベルギー、フランスなどの国際映画祭でグランプリを受賞、国内でも日本映画批評家大賞の作品賞・主演女優賞となり、さらに子役二人が特別賞を授与された。東監督は、文部省芸術選奨文部大臣賞を得た。これらも、もとはといえば田島兄弟の郷里での幼年期への郷愁を込めた自伝的エッセイであった。題名のとおり、かつての「ぼくの村」は住宅地に変貌、消えていた。
征彦は、『みみずのかんたろう』出版の翌年、文化庁在外研修生に選ばれ、パリのアトリエ・コントルポアンで一版多色刷の銅版画を学ぶことになる。現地からの手紙に、こう記してあった。「アトリエでの銅版画が思いのほかぼくの作品に合っていて、銅版の上にビニールシートを貼り、型を刻っています。銅版画の型染めをやっているわけです。アトリエのみんながびっくりしています。欲がでて、朝から晩まで頑張っています」。「木原さんの個展が帰国予定日で残念」ともある。このアトリエは、英国人版画家ウィリアム・ヘイターが始めたもので、筆者の友人木原康行もここで学び、パリに終生居住、生命と宇宙を象徴するような抽象精密画をビュランで銅版に刻み続けていた。フランス画家版画家協会に正会員として迎えられたのは、長谷川潔に続き日本人二人目であった。ぜひ対面させたかったがかなわず、木原は2011年に死去した。日本での木口木版の開拓者・日和崎尊夫(高知出身)も、木原を訪ねて痛飲したと聞いている。
帰国した征彦に、パリ研修のいきさつを聞くと、京都美大時代の恩師・木村重信の推薦だと聞き、これにもビックリ。筆者も、学研で『民族探検の旅』を編集した際に、梅棹忠夫から紹介されて以来のお付き合いで、木村が創設した民族芸術学会の会員となり、くもん出版では著書『美の源流 先史時代の岩面画』出版や、児童用『名画カード(日本編・海外編)』の監修などでお世話になった。
木村は、美術史・民族美術が専門で、大阪大学教授・国立国際美術館館長などを歴任、美術学界のリーダ-であったが、弟子の面倒をよく見た。征彦の『祇園祭』についても、サンケイ新聞で取り上げ、「この絵本は、手で描かれずに、型染作品であることに特色がある。山鉾を飾る染織品が染色画によってあらわされるという、二重の面白さが見どころ」などと丁寧に紹介している。もう一人、木村の世話になった土佐高卒業生に柳原睦夫(29回)がいる。鷲田清一が朝日新聞「折々のことば」784に、こう記している。「おい、ヒマやろ・・・ヒマなはずや。・・・若き日の陶芸家、柳原睦夫は、ある講演の仕事を(木村教授から)回された。当日なんと教授が会場にいる。その後、家に連れて行かれ、たらふくご馳走になる。そして今晩も泊まれと。強引な教授、実は若い作家の暮らし向きを案じ、世に必死で売り込もうとしたのかも」。昨年開かれた「木村を偲ぶ会」で、世話役を務めた柳原の回想から取ったものだ。偲ぶ会は、体調不良で残念ながら失礼した。
土佐高での高﨑先生との出会いが転機
1996年(平成8)には、初めての兄弟共作絵本『ふたりはふたご』をくもん出版から刊行した。ところが、創作活動とごみ闘争で激務が続くなか、1998年58歳を迎えた征三は胃がんであることが判明、大学病院で胃の三分の二を切除、川越市の病院で療養にはいった。そして、30年過ごした日の出町に帰ることなく伊豆に転居、現在は伊東市に住んでいる。征彦も60歳になった2000年に、住み慣れた京都を離れて淡路島に移転する。では、ここで二人の美術活動の出発点となった、土佐中高時代を振り返ってみよう。
幼い頃から絵が好きで、地面に棒きれで絵を描きなぐって遊んだ兄弟は、小学に入ると村人が開いていた絵画教室に通う。教師だった父母にすすめられるまま、1953年に土佐中へ入る。左はその頃の写真で、前列右から父・姉・征彦・母、後ろは征三である。中学の美術教師は洋画家・鎮西忠行だったが、高校になるとモダンアートの高﨑元尚(16回)となり、より強く影響を受ける。洋画家・中村博の画塾にもふたり揃って通う。
この間、征三は夏期市民大学での岡本太郎の講演「芸術は、積み上げではない。いきなりドカンだ!」に感銘を受け、またピカソのデッサン集を入手、宝物のように愛でる。岡本もピカソも、古代文化や民族美術からインスピレーションを得て、新しい芸術への突破口にしていた。後になり、彼の絵本にキュービズムや抽象表現主義の傾向が現れるのも、「木の実のアート」を始めるのも、源流はこの高校時代だ。
いっぽう征彦は、戸籍上は兄ながら引っ込み思案な性格で、絵に自信満々の弟が酒も飲んで青春を謳歌する姿に、劣等感を感じていた。土佐高の校内言論大会で、征三が再軍備問題を堂々と論じるのに惹かれ、自ら自由民権思想の研究会を立ち上げたが打ち込めない。進学は美大と決めていた征三と違い、高3になっても進路がさだまらず、絶望的になっていた。そんなとき、高﨑先生から福沢一郎展を教えられ、観賞して興奮、帰ってからその残像をスケッチブックに描きまくった。先生に見せると「福沢作品にちっとも似てないところが面白い。君にしか描けない絵がある」と励まされる。この一言で絵に回帰、「君の学力で入れる美大は、京都美術大の染織図案科しかない」と教えられ、受験準備を始める。
征三や同級の合田佐和子は、東京御茶の水美術院ですでに夏期講習を受けていた。征彦は征三・合田とともに三学期の授業を免除してもらって、この美術院で受験直前の講習を受け、ようやく京都美大に合格、征三は多摩美図案科に入学する。それにしても、田島兄弟・合田の三人が、三学期欠席でも卒業させる許可を、高﨑先生は曽我部清澄校長(1回)によく取り付けたものだ。
大学へ進学してからも、兄弟の高知との縁は切れない。二人で高知県観光課吉本課長に観光ポスター制作を持ちかけ、征三が泥絵具で描いたエネルギッシュな「鰹の一本づり」が採用される。さらに、当時のM知事が汚い絵と評価し、課長がやっと説得したこの作品が、全国既製観光ポスター展でデザイン界の大御所を差し置いて、金賞・特別賞を受賞する。征彦は高知県展にも次々と出品、特選もとる。そして、土佐の絵金(絵師・金蔵)の凄惨な芝居絵に魅せられ、型染絵に本気で取り組む。
征彦は若き日を回顧して、「樹木希林さんが、文学座で大先輩の杉村春子さんや芥川比呂志さんに平気でぶつかり、喧嘩し、叱られながら育ったと言っていた。ぼくも高﨑先生はじめ多くの人にぶつかり、助けられ、なんとかやって来た」と語る。土佐の山野であふれる生命力を吸い取って育った野生児の兄弟は、青年期になってほとばしる美術への情熱を、大らかに受け止めてくれる大人に恵まれ、次第にその才能を開花させたのである。
海辺の新天地へ移住、限りなきチャレンジ
こうして、征彦は京都の祭りや上方落語など伝統文化に題材を求め、民衆のあふれるバイタリティーを、繊細な感覚で型染絵に染め上げ、征三はふきのとうやバッタなど、自然界のダイナミックな生命力を、泥絵具を使って荒々しいタッチで表現してきた。その絵本は、現実逃避のあまく可愛いいおとぎの世界ではなく、生命力の根元をさぐる骨太の作品であり、子どもも大人も楽しめた。それらは、若くして農村に移住し、家畜を飼い農作物を育てながらのいわば「半農半画」の生活から生まれた。「半農半画」は貧乏画家の生きる手立てでもあったが、そこから題材も得た。このような生活は、夫人の協力があって初めて成り立った。征彦の英子夫人は、生活設計が不得手な夫にかわってローンを組み、丹波に二千坪もの家と田畑を購入、生活の安定を図った。征三の喜代恵夫人は、協調性に乏しい夫にかわって「日の出の自然を守る会」代表となり、長期の運動をまとめた。
60歳を迎える頃、征三は伊豆半島、征彦は淡路島と、ともに土佐と風土の似た海辺の村に移転、心機一転して最初に紹介したような新しい仕事にチャレンジしている。2006年には、高知県立美術館で、『激しく創った!! 田島征彦と田島征三の半世紀』展が開かれた。
最近の征彦の手紙には「あたたかさと海の見える生活に感動、新しい作品の方向がうまれた」とある。『ふしぎなともだち』『のら犬ボン』など新作の大きな反響に支えられて、新しい絵本の方向性に自信を深め、次作の取材・構想に取り組んでいる。それは、どこでもだれでも抱える身近な大問題の提起であり、人間性の根幹を問いかける絵本だ。彼は、絵本を主軸にその主題と表現手法の深化を、がんこに追及している。
かたや征三は、2012年「日・中・韓 平和絵本」に加わり、『ぼくのこえがきこえますか』を刊行した。戦死した若き兵士の魂が、「なんのためにしぬの?」と悲痛な叫びをあげる心象風景が表現されていて心を打つ。2009年には十日町市の里山に、廃校を利用した「絵本と木の実の美術館」を開設、学校を丸ごと使った「空間絵本」を創りあげ、予想を倍する来場者を集めた。地域活性化のモデルケースとして注目されているが、なにより地元住民が次々と来場し、面白がってくれたのが嬉しかったようだ。
さらにこの地で三年ごとに開催し、国際的に知られる「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」(総合ディレクター・北川フラム)では、本年のメイン展示として長さ65メートルの巨大オブジェ「マムシトンネル」を山裾に建造中である。米人芸術家アーサー・ビナードはじめ、そびえ立つ樹林を順次伐採して建築空間を整える空師(そらし)や、宮大工・土建業者などと共同の大仕事だ。胎生で一度に十匹もの子を産む母マムシをイメージ、子どもたちが胎内にもぐって遊び、その生命力を実感して欲しいという。マムシ絵本『わたしの森に』も、くもん出版から刊行するとのことだ。彼の仕事は絵画・絵本にとどまらず、木の実のオブジェ、空間絵本、立体巨大マムシと発展、岡本太郎張りの大爆発を続けている。その完成が楽しみであるが、心身を消耗する大プロジェクトだけに、健康だけが心配だ。
級友から「6月9日、大町玄君逝去」の知らせをうけ、晴子夫人に次の弔電を差し上げた。
「突然のご逝去の知らせを受け悲しみに堪えません
昭和二四年 土佐中学・公文公先生のクラスで同級になって以来
中高六年間 同じクラス 同じ新聞部でした
以来 玄ちゃんは我々の永遠の級長さんでした
心からご冥福をお祈り申しあげます」
中学入学当初から“玄ちゃん”は勉学・遊び、そして統率力とも抜きん出た存在で、だれもが認めるクラスのリーダーであった。その才能を磨くため、公文先生に呼ばれた数人が、自宅で数学・英語の指導を受けるようになり、筆者も玄ちゃんから声が掛かり、後からなんとか加えてもらった。そして、新聞部にもさそわれ、中2から入部、企画・取材から、記事の書き方、紙面の割付まで見習った。彼は、放送部にも席を置いていた。
2015年、高知での卒業60周年の学年同窓会のあと、ひろめ市場の二次会で昔話になり、「中学2年の後期だったか、おんしに応援演説をされて中学生徒会長選挙に出た。番狂わせになり、3年の福島さんを破って当選。中3でもやった」と、話しかけてきた。確かに新聞部だけでなく、生徒会でも、そして遊びでもリーダーだった。中学生徒会では、大町会長・中城議長のこともあった。
遊びの中心は草野球。ビー玉にゴムひもや毛糸を巻き付けて布で縫った手作りボールで、昼休みなどに夢中で遊んだ。次第に軟式ボール、バット、グローブが普及すると、大町キャプテン以下、潮江や三里に出かけて他流試合も行った。いい加減な審判をすると、相手から「メヒカリ食ってこい!」などと、ヤジられたものだ。
高校進学は、公文先生の提案で4クラスの担任を事前に発表、生徒が自由に選択できた。大町・浅井・千原など新聞部一同は多くが公文先生を慕ってそのクラスを希望した。ところが、一大事が発生した。公文先生が突如大阪に転勤することになったのだ。後任は英語の織谷馨先生だったが、まだ若くて包容力が未熟だったために、たちまち生徒とぶつかった。以来、授業内容でもクラス運営でも、衝突の連続だった。
そのような中で、高1になると大町は向陽新聞編集長となり、1952年5月発行第15号には、格調高く「新生日本の出発に当って」と題する大嶋校長のメッセージをトップに掲げた。ようやく日本独立がかなったのだ。この紙面には「人文科学部生る」の記事もあり、部長は公文俊平(28回)、指導教師は社会思想史・町田守正、日本史・古谷俊夫などとある。当時、社会も学内も活気にあふれており、生徒会と新聞部による「応援歌募集」や、「先輩大学生に聞く会」「四国高校弁論大会」などが次々と企画、開催された。
だが、わがクラスの混乱は続き、卒業後も浪人の大学受験内申書が間に合わないなど、問題が続発、学校にも訴えたが打開できなかった。人望の厚かった英語のH先生に相談すると、「私の教え子であり、公にするのはひかえて欲しい。収める」とのことだったが、効果はなかった。当時の大町からの憤懣やるかたない速達が、2通手元に残されている。
部活にもどすと、従来通り高1で大町たち多くの新聞部員は退部、受験勉強に軸足を移したが、筆者と横山禎夫は高3まで部活を続けた。特に筆者は、部活やクラスの混乱をいいことに、勉強そっちのけで過ごした。向陽新聞は全国優秀五紙にも選ばれたが、受験勉強には全く身がはいらず、私大に進んだ。
わがクラスからは、結局7名が東大に進み、ちょうど70名クラスの1割を占めたが、担任との軋轢もあって現役入学ばかりでなかったのはやむを得ない。それよりも、東大経済を出た大町が、新聞部や大学での演劇活動をふまえてマスコミをめざし、NHKの内定を得ていたのに、あるこだわりから最後に製造業に転じたのは残念だった。放送界には適材であり、経営管理部門でも、番組制作部門でも、リーダーとなる人物だった。
富士電機の要職を降りてからは、級友とのお遊びにもよく付き合ってくれた。日本城郭協会主催の、2003年イタリア城郭視察旅行にも加わり、旧知の後輩・藤宗俊一(42回、フィレンツェ大建築学部)の名解説を楽しんでいた。同年秋の沖縄城跡巡りにもご夫婦で参加し、向陽プレスクラブ総会も健康の許す限り参加してくれていた。
老いても級長さんの役割は途切れず、20号まで出たクラス誌「うきぐも」発行や、クラス会開催の主役であった。また、草野球以来の虎キチで、神宮球場の阪神×ヤクルト戦はよく級友と観戦していた。肺がんと分かってもタバコを手放さず、悠々囲碁を楽しんでいた。今年の年賀状には、達筆で「告知された余命期限を過ぎて三ヶ月経ちました。期限切れの余命を楽しむが如く、慈しむが如く、ゆっくりと面白がって生きております」とあった。達観した心境のようだった。
告別式の行われた6月13日は、あいにく日本城郭協会総会に当り、筆者の体力では浦安市斎場との掛け持ちは無理だったが、浅井・西内・松﨑などの同級生、さらに向陽プレスクラブの公文敏雄会長が参列し、お別れを告げてくれた。城郭協会総会の開かれた神田・学士会館は、奇しくも50年前の晴子夫人との婚礼の場であり、5月には高知からの親族も含めてここに集い、元気な玄ちゃんを囲んで、盛大に金婚式を祝ったばかりだという。50年前、筆者は悪友にそそのかされてクラス代表の拙い祝辞を述べた思い出が蘇ってきた。 合掌。 母校出身“素顔のアーティスト”(Ⅳ)-1(前編)
凄絶なホラー作家にして酒豪、坂東眞砂子(51回)
1996年に『山妣(やまはは)』(新潮社)で直木賞をとった坂東眞砂子と、初めて会ったのは1993年であった。紹介してくれたのは、坂東と土佐高の同級生で、ゴリラの画家としてすでに知られていた阿部(旧姓浜口)知暁(ちさと)であるが、月日や場所は定かでない。すでに坂東は、童話作家として『クリーニング屋のお月様』(理論社 1987年)はじめ数冊を刊行、注目されており、当時教育出版社にいた筆者も、有望な新人と聞いていた。
会ってみると、三十半ばとは思えない若々しいおかっぱの童顔で、奈良女子大住居学科を出てイタリアのミラノ工科大などに留学、帰国後にフリーライターとして雑誌の記事を書きつつ、童話に取り組んできたと話してくれた。すでに毎日童話新人賞なども受賞しているが、「これからは、大人の小説を書きます。土佐を舞台にした第一作が、もうすぐ出来上がります」とのことであった。
やがてマガジンハウス社から、「乞御高評」の付箋付きで著書『死国』が贈られてきた。帯には「新鋭書き下ろし伝奇ロマン 四国を舞台に繰り広げられる不可思議な現象と事件!」とあり、作家・小池真理子の惹句「丹念な描写が怖さを紡ぎ出す」と続く。死国とは四国であり、四国遍路を舞台に使ったこの一作で、一躍女流ホラー作家として脚光を浴びる。童話とは全く異質の作品に、驚きつつ礼状を出すと、折り返しハガキで「年内にはまた新刊を出す予定です。そのうちに社(くもん出版)に伺います」とあった。
秋には次作『狗神(いぬがみ)』(角川書店)が届いた。狗神(犬神)とは土佐の憑(つ)きもの神で、これに憑かれると半狂乱になるなど異常行動をとる。犬神の憑く家は代々決まっているとされ、犬神筋と呼ばれた。犬神が憑くと、太夫(たゆう)という神職者に頼んで御祓いをして落としてもらった。
主人公の美希は、痛ましい少女時代の過去を忘れ、山村で紙を漉いてつましく暮らしていた。若き中学教師の赴任とともに、奇怪な現象に巻き込まれ、狗神筋の家として忌み嫌われ差別される。やがて、近親相姦が明らかになり、一族は村人に襲われ、惨劇で幕を閉じる。後に、天海祐希の主演で映画化された。執筆に当たっては、「土佐憑物資料」などを渉猟している。筆者は物部村でいざなぎ流神事を見学したばかりだったので、読後感に、土佐の民俗・信仰を題材にするなら高知県立歴史民俗資料館の吉村淑甫館長を訪ね、また民間信仰研究者でいざなぎ流にも詳しい小松和彦(当時阪大教授)の著書も読むよう書き添えて送った。翌年1月に手紙が届き、「小松教授の御本は、以前より興味深く拝見しています。今回も参考にさせていただきました。吉村館長にも教えを受けたい・・・」とあった。
この年に筆者は、寝袋をかついでタイ北部の山岳少数民族探訪にでかけ、日本人女性が子どものために開いた寄宿舎学校に立ち寄った。一人で運営するNさんが、「二日酔いみたい」といって、現れたので事情を聞くと、「前日に村の呪術師から“憑きものが出始めたから、御祓いをする”といわれ、祠の前で厄払いを受け、強い焼酎を無理にのまされた。村のしきたりには従わないと、生活できないから」とのこと。帰国後に、坂東にこれを伝え、伝奇小説も土佐ばかりでなく、東南アジアも含めて海外まで舞台を広げてはと提案した。やがて、手紙が来て、「タイの面白い話」への礼と、吉村館長の子息で角川書店編集部の吉村千穎(現風日社)に会ったこと、現在、土佐清水を舞台にした長編に取り組んでいることが述べてあった。
土佐清水を舞台とする長編は、『桃色浄土』(講談社)であり、1994年10月に刊行された。この頃には、出版界期待の新鋭伝奇ロマン作家として、各社から追いかけられる存在となり、筆者との連絡も直木賞受賞の頃には途絶えた。従ってここからの“素顔”は、主として各社の担当編集者からの伝聞と、本人の随筆による。
文才豊かな酒豪、綿密な現地取材
イタリアから帰国後に、東京でフリーライターとして雑誌に紀行文や取材ルポを書いていた坂東は、応募した童話が新人賞になり、その審査員だった童話作家・寺村輝夫が開いていた文学講座に通う。作品の添削・講評を受けながら文学修業に励んだことが出版につながり、1986年に『ミラノの風とシニョリーナ イタリア紀行』(あかね書房)が刊行される。担当編集者は筆者と学研で同僚だった後路好章で、そのいきさつと人物をこう語る。
「寺村先生から、“坂東は抜きんでて文章力がある。ぜひ、起用しなさい”と強い推薦があり、高学年児童向けの海外紀行シリーズで、イタリアを書いてもらった。期待どおりの出来映えだった。打ち合せの合間に、イタリアで男性から迫られたことを赤裸々に、楽しげに話してくれた。後に電車で偶然会ったが酒臭い状態で、寺村先生から“二人きりで飲まないよう、ぶっ倒れるまで飲むことがある”と聞かされていたのを思い出した。とにかく、文才に恵まれ、また酒豪であった」
創作児童文学を数冊出版したのちに、『死国』を皮切りに大人ものの伝奇小説に転じ、『蟲』(角川書店)で日本ホラー小説大賞佳作、『桜雨』(集英社)で島清恋愛文学賞など、次々と受賞する。そして1996年刊の『山妣』によって38歳の若さで直木賞に輝く。受賞の知らせは、翌年の1月に滞在中のイタリアで聞く。高知新聞の取材に、「村社会が私のテーマ。日本民族の根源的な思い出として書ければいい・・・」と、語っている。授賞式には、選考委員・渡辺淳一、直木賞作家・宮尾登美子とともに母・美代子の姿もあった。高校卒業と同時に家を離れ、奈良、ミラノで学び、東京では定職に就かず、母には心配を掛けてばかりだっただけに、母子ともども喜びはひとしおだったと思われる。
『山妣』の帯には、「業深き男と女に荒れ狂う魔物。山妣伝説の扉が開かれた――明治末期、越後の豪雪地帯を舞台に、旅芸人、遊女、又鬼(またぎ)、瞽女(ごぜ)、山師らが織りなす凄絶な愛憎劇。未曾有の大作!」とある。坂東は、すでに二度直木賞候補になっており、今回は作者、版元とも受賞への期待を込めた渾身の力作であった。この作品の担当編集者であった木村達哉は、当時をこう回想してくれた。
「現地取材を実に丹念にする作家だった。『山妣』の舞台は、全く土地勘のない新潟だけに、2年以上取材に時間をかけ、季節をかえて何度も足を運んだ。芝居の場面を書くために檜枝岐(ひのえまた 福島県)へ農村歌舞伎の開演時期に行き、秘境といわれる秋山郷も、数日かけて歩きまわった。民俗学に興味を持ち、関連文献をよく読み込んでから現地取材に向かった。特に、宮本常一、宮田登、それに歴史家・網野善彦の本を読んでいた。仕事に手厳しい作家で、安易な妥協を許さず、著書の装丁一つ取っても、納得いくまで注文を付けてきた。ただ、仕事を終えての酒席では陽気で、近況から作品の構想、高知の思い出など楽しげに話してくれた。土佐の女性らしい酒豪で、日本酒を冷やですいすい飲む姿と、“木村さんは弱いんだから”と笑われたことが印象に残っている」
なお、木村の新潮社同期には『奇跡の歌』などで知られるノンフィクション作家の門田隆将(門脇護53回)がおり、SF評論家の大森望(54回)も元同僚だったという。
タヒチで「生」と「性」を謳歌したハチキン
直木賞受賞後、人気作家として一段と多忙になるなか、2001年刊『曼荼羅道』(文芸春秋)が、柴田錬三郎賞を受ける。戦時下のマレイ半島で、日本人の現地妻となった部族の娘の数奇な生涯をたどる長編だ。講評で黒岩重吾は、「この受賞作には、読んだあとの気迫だとか衝撃、あるいは感動、それから余韻が必要・・・今回は衝撃を受けた」と語っている。
柴田錬三郎は、その生前筆者がかなり付き合い、文学への厳しい見方を実感していた作家だけに、嬉しかった。1975年には柴練原作のNHK人形劇『真田十勇士』の漫画化権をとり、石森章太郎に作画を依頼、1年間高輪プリンスホテルの仕事場に通った。あるとき、ホテルに文藝春秋社から直木賞の候補作が届き、リストを見せていただいた。知り合いの時代小説作家の名前があり、評価をうかがうと、「Tは資料に頼りすぎでまだダメだ。作家は創作力が命」と明快だった。田中角栄の私生活をめぐる『プレイボーイ』誌裏面での猛烈なバトルと、その幕引きの真相に、作家としての気概を感じた。『週刊新潮』の人気連載小説『眠狂四郎』シリーズに登場した、西洋占星術の内輪話も打ち明けられた。
坂東に話をもどすと、2001年に高知県立美術館で開催の合田佐和子(34回)展図録には、アトリエを訪問した上で合田論「焼け跡に舞い降りた死の使者」を寄稿している。2003年には高知新聞など地方紙で、自由民権運動に題材を取った『梟首(きょうしゅ)の島』の連載が始まる。私生活ではすでに1998年からタヒチに移住し、フランス人建築家兼彫刻家をパートナーとして暮らしていた。子どもの頃から南の島にあこがれていたというが、それだけではない。彼女は、「わたしは自分が憎い。鏡で顔を見るのも嫌い・・・」(『わたし』)と語っており、特に高校から大学にかけては、容姿にも才能にも自信喪失気味であった。それが、22歳で行ったイタリアでは、「なんといっても楽しかったのは、町で男によく声をかけられたことだった。・・・“チャオ、ベッラ(別嬪さん)”と声をかけてくる。・・・男たちがウインクしてくる」(『愛を笑いとばす女たち』(新潮社)のだ。
彼女のような丸いぼっちゃりタイプは、欧米人には東洋美人の典型と写る。さらに、おしとやかな態度より、はっきり自己主張する人間が好まれる。坂東はイタリア男性の熱い性的エネルギーを浴び続け、自信を回復したのだ。仏領タヒチへの移住は、南太平洋の楽園とされるその自然だけでなく、そこに住む開放的な西洋人にも惹かれたのだ。
取材で島の自宅を訪問した木村は、「タヒチと言っても観光地でなく、淋しい土地に住み、野菜や果物を栽培、鶏を飼育、魚を獲って自給自足をめざすたくましい生活ぶりに驚いた」という。作家として、都会の喧噪を離れ、自然のなかで人間本来の生き方をさぐりたかったのだろう。奈良女子大の後輩でもある新潮社の中瀬ゆかりは、飲みっぷりをこう語る。
「日本酒でも何でも飲んでいましたが、一番お好きだったのはやはりワイン。ひとりでボトル2本くらいは軽くあけていました。タヒチでは、夕方、自宅の農作業が一段落したらテラスに椅子を出して、冷えたシャンパンを開け、“あー、この一杯のために今日も働いたわ”みたいな言葉が出るくらい好きでした。酔うほどに議論になり、いつも論客のマサコにやり込められました。話題は下ネタから天下国家まで、といっても私とは恋愛とか男性論が中心で、深夜まで飲んだくれていました。料理の腕もプロ級で、ハチキンを絵に描いたような豪傑。まさに「生」と「性」を謳歌。知的で自由な発言、よく笑い、欲望にも忠実な生き様は、私たちの憧れでした」
凄絶なホラー作家にして酒豪、坂東眞砂子(51回)
タヒチで暮らしつつ、2002年に自伝小説『わたし』(角川書店)が刊行される。帯には「衝撃の自伝小説」「心の深淵には、人に対する激しい憎しみと恐怖を抱えた“わたし”が住んでいる」とある。祖母はじめ家族、そしてタヒチでのパートナーなどに関する赤裸々な記述はともかく、高校の学友に対しても「疑似友人」と述べ、憎しみに満ちた記述を連ねている。自伝「小説」とうたい、仮名になっているとは言え、級友にとっては誰を指すか明白であり、身に覚えのない記述に嫌悪感を抱かずにはいられなかったであろう。
高知県佐川町斗賀野で生まれた坂東は、中学まで地元の学校に通い、高校から土佐高に入学、1時間半かけて汽車で通学した。「最後まで“名門校”の雰囲気に馴染むことなく、高校を卒業した」(『身辺雑記』朝日新聞社)とも述べている。
両親が教師と保母という家庭で育ち、小学校では図書室が大好きで『長靴下のピッピ』や『ツバメ号とアマゾン号』、そして漫画に夢中になった。中学ではカミュの『異邦人』に惹かれ、文芸部でも活動、成績も良く仲間のリーダーだった。高校で2年、3年と同級だった八木勝二は、「彼女の印象は、横山大観の『無我』の少女のように茫洋とした容姿で、男子の友人はおらず、女子の友人も浜口や竹崎(現YASUKO HACKIN)に限られていた。『わたし』に書いてあることは、創作が多い。いつの間にか流行作家になり、直木賞をもらった。級友と“すごいねえ。そんな才能があったがか”と、話したことだった」という。
担任だった濱田俊充(理科35回)も、「友だちは少なかったが、浜口知暁とは仲が良く、よく一緒にいた。直木賞作家になるとは想像出来なかった」と語る。その浜口は、かつて筆者に坂東を紹介してくれた画家・阿部だが、「もう彼女のことは話したくない」と語るのみだ。合田佐和子や田島兄弟は、高校時代に美術教師によって才能を見出されたが、坂東の才能は埋もれたままであった。
「猫殺し」に見る坂東の“偽悪”
2006年8月、坂東は日本経済新聞夕刊の連載エッセイに「子猫殺し」を書く。「こんなことを書いたら、・・・世の動物愛護家には、鬼畜のように罵倒されるだろう。そんなことを承知で打ち明けるが、私は生まれたばかりの子猫を殺している。家の隣の崖の下がちょうど空き地になっているので、生まれ落ちるや、そこに放り投げるのである」
掲載直後から、まずネットで坂東バッシングがはじまり、新聞雑誌でも文化人の論評をまじえての集中砲火を浴びる。本人が覚悟した以上の糾弾だった。坂東には『死国』発表以来付けられた「ホラー作家」に加え、「猫殺し」のレッテルが加えられる。かねて坂東は、「私はホラーという横文字の恐怖を書いているのではない、日本人が持っている自然や神に対する畏怖(いふ)感を書いている」と反発してきた。「猫殺し」の真実はなんだったのか。友人で作家の東野圭吾の問いかけに、坂東はこう答えている。「崖というと、断崖絶壁を想像する人が多いけど、実際は二メートル程度の段差。下は草むらやから、落としたぐらいで死なへん。つまり正確にいうと、子猫を裏の草むらに捨てた、ということやね」(「レンザブロー」)。坂東は、人間と動物、特に家畜や愛玩動物との関係を、根元から問いかけるために、「捨て猫」でなく、インパクトのある「子猫殺し」にしたのだ。
ここでも、『わたし』での「疑似友人」への容赦ない表現同様に、「わたし」を“偽悪化”して、「子猫殺し」に自らを仕立て上げている。エッセイでは、あえて自身を悪者にした上で、他者(友人や愛玩動物)への攻撃姿勢を強調、読者に問題提起をしている。
彼女は作家としての年輪を重ね、文壇での評価が定まるとともに、高校卒業と同時に離れた高知の人々を思い出すこともあったようだ。『わたし』が出版されて3年くらいたったある夜、東京にいた高校の同級生・八木のもとに、大学時代の親友から突然電話があり、「銀座の寿司屋で飲んでいる。珍しい人と替わる」とのこと。そして出たのが坂東で、「高知新聞連載の『梟首の島』が本になる。あした新聞社で対談があり、終わったら電話する。会おう」だった。卒業式以来の声だったが、酔ったせいか意外にさばけた印象だったという。だが、翌日待てど暮らせど電話はなかった。取次いだ親友に事情を聞くと、「たまたま寿司屋で土佐弁が聞こえたので、声をかけると坂東さんだった。高知に八木という友人がおるといったら、“同級生じゃ、電話しょう”となった」とのこと。
坂東は2008年には50歳となり、長編『鬼神の狂乱』(幻冬舎)を上梓する。江戸後期に土佐豊永郷で起こった狗神憑きの事件から題材を得て、鎮圧に参加した下級武士と村娘の恋を織り込んである。民間信仰だけでなく当時の社会的背景も織り込んで、完成度の高い楽しめる作品に仕上がっている。いつもながら、本の末尾には郷土史家・公文豪など取材協力者の氏名を、詳細にあげてあった。この年の年末には、タヒチのパートナーとも別れて帰国する。翌年には、高知に帰郷し、鏡川上流の高知市鏡に、イタリアンカフェをオープン。オーストラリアの北東に浮かぶバヌアツにも家を建て、若い夫ケビンとくらす。
高知とバヌアツを往き来しながら、旺盛な執筆活動を続け、2011年には『くちぬい』(集英社)を出版する。高知へ帰郷後に実感した非合理な土地慣行や高齢者による新参者へのいじめ、共同体のために口を閉ざす”口縫い”をテーマに、田舎への愛憎を作品化している。
郷里への想いと「チームマサコ」
2013年、体調不良を訴え、検診の結果舌癌と判明する。高知で治療を続けながら連載を抱え、執筆活動を続ける。やがて、肺にも転移し、末期ガンとの診断が下る。東京での治療を希望し、同年末には、友人・久保京子の車で、東京の病院に移動する。
東京では、新潮社や集英社をはじめ仲良しの編集者・新聞記者・作家たちが女性だけで「チームマサコ」を結成、入院生活を支援した。その様子を、中瀬はこう述べている。
「高知にもどるまで約1ヶ月間のサポートシステムです。病室に付き添い、水分補給にシャーペットを溶かしてスポンジに含ませては舌にのせてやり、買い物やお金の管理も行い、時には泊まり込みました。“死”への想いが渦巻き、たまには爆発したようですが、私には最後までユーモアたっぷりなマサコ節でした。病室は男子禁制で、仲良しの男性編集者にも面会拒否を通していました。やつれたすがたは、見せたくなかったのでしょう」
母やケビンも駆けつけたが、「自分のルーツである高知に帰りたい」との希望で、2014年1月23日に空路高知に搬送された。だが、27日には家族に見守られて、帰らぬ人となった。享年55歳。多くの知人にも、闘病中とは気付かれない間の訃報で、八木は同級生を誘って「坂東の店へ行こう」と、話していた矢先であり、残念だったという。
こうして坂東は、土俗的な信仰と習俗の村社会にみられる人間の業を描いて、直木賞作家としての地位を築いた。さらに、古代王朝や自由民権運動を舞台にした歴史ロマン、明治以降の日本のアジア・太平洋進出を庶民の立場から捉えた社会派小説など、新ジャンルに挑戦、時代・舞台を重層的に交錯させ、劇的な結末に導き、読者を魅了し続けた。豊富な海外生活をもとに、あっけらかんとした性描写や、愛を笑い飛ばす性への賛歌は、カトリック・儒教そして近代市民社会のモラルへの挑戦でもあった。差別・戦争・原爆・原発事故にも、強い関心を寄せていた。
1993年の『死国』から、2013年絶筆となった『眠る魚』(集英社)まで、わずか20年ばかりの間に40冊余の多彩な小説を送り出している。早すぎる死に対し、ひところ女流ホラー作家として併称された篠田節子は、近作の『隠された刻』(新潮社)、『朱鳥の陵(あかみどりのみささぎ)』(集英社)、『くちぬい』(集英社)をあげ、「内容の充実に加え高い緊張感とダイナミズムは失われていない・・・老成、円熟には無縁の熱量に圧倒される」(朝日新聞2014.4.13)と、最期まで衰えなかった創作力を追憶している。
未完の絶筆長編『眠る魚』の編集担当だった今野加寿子は、坂東が書き残した「故郷の土地は、私の最後の砦」「原発事故のもたらした最大の精神的被害は、日本人の土地に対する信頼の消失」を紹介。「2014年1月。余命宣告を受け、最期を迎える場所として向かったのは、土地と家屋を所有する他ならぬ高知だった。自力で歩くこともままならない状態で、看護師同行のもと飛行機に乗る」と述べている。(『眠る魚』解題)
坂東の作品に関しては、既刊以上に望むことはない。ただ一つ、円熟期を迎え再度執筆して欲しかったのは『わたし2』である。余命を知ってからの郷里土佐への想いが伝わるだけに、土地だけでなく級友はじめ土佐の人々への想いも、改めて聞きたくなった。
元防衛大臣・中谷元から防衛問題を取材
本稿執筆後に、<2014年に東京で開かれた「坂東眞砂子さんを偲ぶ会」に、土佐高同級生の中谷元代議士(元防衛大臣)が出席し、心のこもった挨拶をしていた>との情報が、知人の編集者から寄せられた。同級の男子とは交流がなかったと聞いていただけに意外で、叔父の浅井伴泰(30回)に問い合わせると、国会開期末で多忙な7月17日に、中谷元ご本人から電話をいただいた。以下が、その概要である。
「坂東さんは、2008年4月から11月まで高知新聞に『やっちゃれ、やっちゃれ!―-独立・土佐黒潮共和国』(後に文藝春秋刊)を連載した。その中で防衛問題も扱うので、きちんと勉強したいとの申し出だった。執筆に先だち、二、三度お会いして率直な意見交換をおこなった。卒業以来の再会で、国家防衛への考え方には相異もあったが、熱心な取材ぶりが印象に残っている。人気作家となってもよく資料を収集、異論もふまえ、独自の小説世界を創作している姿に接しただけに、急逝が残念でならなかった」
合田や田島兄弟が新聞で話題に
“素顔のアーティスト”で紹介した人たちが、「新聞に出ちょった」との情報が西内一(30回)などから、次々と寄せられたのでお伝えしたい。
まず、7月3日の日本経済新聞文化欄で、美術評論家・勅使河原純は、連載「マドンナ&アーティスト十選」の一人に、合田佐和子「ベロニカ・レイク」選んでいる。勅使河原によれば、「美女狩り」で有名な合田が選んだ妖艶なマドンナが、1940~50年代のアメリカで、男を惑わす宿命の女のレッテルを貼られたベロニカで、「合田にとっては一分のスキもない悪女こそ、もっとも心許せる女神だった」と述べている。
7月5日の朝日新聞夕刊「古都ものがたり・京都」には「田島征彦が絵本にした祇園祭」の記事が大きく掲載された。40年以上前、絵本『祇園祭』に着手したころの田島はまだ無名で、取材は難航したが、3年間かよって仕上げる。「きらびやかだけでない、祈りや鎮魂、情熱といった人間の根源を揺り動かすものがいっぱいあった。それを染めた」と、語っている。この絵本は、ブラティスバラ世界絵本原画展で金牌を受賞、ロングセラーになっている。
この翌日には、全国紙の全面を使った「越後妻有・アートの夏」「大地の芸術祭」開催告知が出た。メイン会場の一つが「鉢&田島征三 絵本と木の実の美術館」で、廃校を舞台にオブジェで構成した“空間絵本”の写真が掲載してあった。やがて本人から、山裾に出来つつある巨大オブジェ「マムシトンネル」の写真が送られてきた。7月29日からは、いよいよ「越後妻有アートトリエンナーレ2018」が始まる。夏休みの旅行に、ぜひ子ども連れで訪ねたい芸術際である。それに合わせて、マムシ絵本『わたしの森』(くもん出版)も刊行されるので、内容をちょっぴり先行公開しよう。
なお、最初に紹介した倉橋由美子(29回)につき、今ベストセラーを連発中の下重曉子との出会いを書き漏らしたので、『うきぐも』14号(30年卒Oホームクラス誌1990年刊)から再録する。下重は筆者と同年の旅仲間で、高知に案内したほか海外も含めてよく旅に出かけ、自宅にも往き来した。連れ合いは、元テレビ朝日の温厚な記者である。
「1989年6月23日、先輩の倉橋由美子さんに、旅仲間の下重曉子さんを、神楽坂でお引き合わせする。ともにファンで、紙上でたがいの作品にラブコールを贈っていたが、会うチャンスがなかったとのこと。会った瞬間から意気投合、肝胆相照らす仲となる。特にお二人とも、結婚談義がケッサクだったが、オフレコである。この日たまたま上京中の福島清三先輩(29回)から電話があり、途中から合流する」(「平成元年出版ヤクザ行状記」) 母校出身“素顔のアーティスト”(Ⅴ)まだまだおるぜよ編
音楽・演劇から前衛美術まで個性派揃い
作曲家・平井康三郎や「踊る大捜査線」の北村総一朗
卒業生で初めて芸術の道に進み、東京音楽学校(現東京芸術大学)を卒業、作曲家として大活躍をしたのが、平井康三郎(5回、1910~2002)である。「不盡山(ふじやま)をみて」「大仏開眼」「平城山」「ゆりかご」から、「スキー(山は白銀・・・)」など五千曲を作曲、東京芸術大学の作曲科教授として後身を育成、故郷いの町には、平井康三郎記念ギャラリーができている。平井の音楽家としての才能をいち早く認め、父親を説得して音楽大へ進学させたのは三根圓次郎校長である。その経緯は拙著『三根圓次郎校長とチャイコフスキー』((向陽プレスクラブ刊)に述べてある。本年4月には、NHKラジオ「うたのふるさと散歩 平井康三郎記念ギャラリー」に、長男でチェリストの平井丈一朗が登場、生い立ちや土佐中での三根校長・ヴァイオリンとの出会いを語っていた。
その後、日本を代表するような音楽家は生まれていないようだが、現在東京芸大大学院オペラ専攻に上久保沙耶(89回)がおり、今後に期待したい。
俳優では、1997年にフジテレビ「踊る大捜査線」の神田総一朗署長役で大人気となった北村総一朗(29回、1935~)がいる。このドラマが東宝で映画化されたのに続き、テレビドラマ「京都迷宮案内」では文学座で同期だった橋爪功と共演、北野武監督『アウトレイジ』で巨大組織会長を演じるなど、コミカルな役からコワモテまで自在に演じ、今も引っ張りだこだ。バラエティ番組やCMでもよく見かける。
舞台でのキャリヤは長く、筆者が初めてその演技を見て魅了させられたのは、高校時代である。1952年に高知市中央公民館で行われた「土佐中高校舎落成記念 芸能発表会」での『俊寛』で、悲壮感漂う主役を演じていた西内総一郎が、若き日の北村であった。この発表会では、新聞部もプログラムの編集に協力したので、よく覚えている。高知大農学部に進むが演劇に打ち込み、1961年には上京して念願の文学座研究生となる。同期には、橋爪のほか樹木希林などがいる。その後、劇団雲を経て劇団昴に所属、テレビにも「竜馬がゆく」「太陽にほえろ」などよく出演し、貴重な存在であったが名脇役に留まっていた。それが、「踊る大捜査線」で一挙に人気爆発、スターとなった。この間、高校時代以来の夢である新劇の舞台から離れることはなく、本年8月の劇団昴『無頼の女房』公演では、演出家として若い団員を率いて、坂口安吾夫妻の葛藤を上演している。新劇界の最長老の一人である。名前は、西内から北村総一郎になり、さらに「踊る大捜査線」の神田総一朗にちなんで今は総一朗だ。
ミュージカルや演劇の世界では、演出・振付けの分野で顕著な業績をあげてきた人物に、竹邑類(35回、1944~2013)と北村文典(39回、1946~)がいる。
竹邑は土佐中時代からモダンダンスを習い、明治大学仏文科に進む。ダンスのグループを結成し、愛称ピーターで親しまれる。大学を中退してダンサーとなり、ミュージカル「屋根の上のヴァイオリン弾き」に、初代ヴァイオリン弾きの役で出演する。1970年に自らミュージカル劇団「ザ・スーパー・カンパニー」を結成、銀座・博品館劇場の公演には、土佐高同期の小松勢津子などに誘われて筆者も駆けつけ、ミュージカルを初めて楽しんだ思い出がある。ミュージカルの開拓者・挑戦者も、この頃には演出家・振付家の第一人者となり、宝塚歌劇・NHKの歌謡バラエティ・映画『陽暉楼』等で大活躍、坂東玉三郎・平幹二朗・水谷八重子などの名優から信頼され、その舞台の演出・振付けを任されていた。2013年にガンで逝去。著書に、若い頃に新宿で出会って以来の三島由紀夫との交流を綴った『呵呵大将 我が友、三島由紀夫』(新潮社)がある。
彼の劇団で育った俳優に萩原流行(ながれ)がいたが、2015年にオートバイで走行中に警視庁護送車と接触事故を起し、転倒死亡した。事故の原因に不信を抱いた夫人の依頼で訴訟を担当した弁護士が堀内稔久(32回)で、護送車の運転不注意であることを裁判で明らかにした。
もう一人の北村は東宝の演劇部に所属し、主演・森光子のでんぐり返りが話題を呼んだ「放浪記」などの演出で知られる。大学は関西学院大学社会学部だが、在学中からフランス・ナンシーの「国際大学演劇祭」に日本代表で参加するなど、演劇に取り組んだ。東宝では、菊田一夫や北条秀司の演出助手を経て、主に時代劇・喜劇の演出にあたってきた。東宝演劇をささえる重鎮である。
世界の先端をめざした前衛芸術家・高﨑元尚、柳原睦夫
美術界で特筆すべきは高﨑元尚(16回、1923~2017)の活躍で、高知で世界の前衛美術の最前線に立ち、生涯新作への挑戦を続けると同時に、教育者として人材育成にあたった。90歳を超えても創作意欲を持続し、2017年6月高知県立美術館で「高﨑元尚新作展-破壊COLLAPSE-」が始まって間もなく逝去した。1956~88年まで土佐高で美術教師を務めたが、「面白いことをやれ、人のやることをやるな」と呼びかけ、「ぼくが見て面白いと思うもの、変わったもの、見たことのないものを見せた」(日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ)と述べている。この教えを受け、すでに紹介した合田佐和子や田島征三・征彦が巣立っていった。合田の両親には、美大への進学を自ら説得している。
高﨑は香美町の生まれ。土佐中時代には数学、特に幾何が得意で、早稲田大学専門部建築科に入学、ロシア・アバンギャルドなどに触れ、翌年には東京美術学校(現東京芸術大学)彫刻家に転じる。ところが戦争激化で、彫刻制作にも大和魂を強要され、同級の岩田健とともに反抗、やがて学徒出陣となる。この岩田は、温厚な人格者で後に母子像彫刻の第一人者となり、筆者は大阪の公文教育会館ロビーに飾るブロンズ像「本を読む母と子」を依頼、1989年に完成したが、高﨑と親友だったとは、全く気付かなかった。
戦後、高﨑は美大に復学して卒業、中学教師の職につき、モダンアート協会に入る。やがて帰郷、1953年の県展に出品するが、なんと落選している。翌年、東京でのモダンアート展で新人賞を受賞し、ようやく認められたようだ。高知モダンアート研究会を結成、1956年から土佐中高教師となる。浜口富治たちと「前衛土佐派」をつくって活発な制作・発表を続け、中央の美術界からも注目される。1965年の京都国立近代美術館への出品作が内外の美術関係者から評価され、抽象美術の先駆者が集まる具体美術協会にも参加、翌年ニューヨークで開催された「第1回ジャパン・アート・フェスティバル」に出品、渡米する。
高﨑は関西・東京からは距離を置き、高知にいたほうが美術界の動向がよく見えると述べている。また、前衛美術の中心地アメリカは絶えず意識し、晩年になってもいつでも対応出来るよう英語力の持続に努めていたと聞く。想いがかない、2013年にニューヨークのグッゲンハイム美術館から出品依頼があり、90歳になっていたが会場へ出向いた。高﨑の作品については、このHPに山本嘉博(51回)が「高﨑元尚先生逝く」(2017.10.12)、「追伸」(11.02)を掲載しているので、ご覧いただきたい。美術教師であるとともに、生涯自ら新作に挑み、芸術家としての生き様を最期まで見せ続けた希有なアーティストであった。
前衛美術の世界で、もう一人の先駆者が現代陶芸の代表的作家で、大阪芸術大学名誉教授の柳原睦夫(28回、1934~)である。戦争直後、高知市内の旧家で育った柳原は伝統文化とアメリカ文明のはざまで成長、土佐中に入学する。絵を学ぶ進路をさぐるため、知人の紹介で京都市立美術学校長の長崎太郎を訪ねたことから、同校へ進学する。工芸科で近代陶芸の大家・富本憲吉に学ぶが、前衛美術に魅了され、モダンアート展に出品、彫刻的な造形や抽象表現主義的な作品に取り組む。さらには金や銀のラスター釉を使った装飾性豊かな陶器を経て、縄文式・弥生形壺と称する新作まで、独自の挑戦を続けている。
この間、1966年にワシントン大学に招かれて講師を務めたのを皮切りに、再三アメリカの大学で陶芸指導を行うなど、国際的な活動を展開する。日本では、大阪芸術大学教授となる。高知のモダンアート研究会とも交流、1961年の「柳原睦夫・高﨑元尚二人展」はじめ個展も高知大丸などで開催、2003年には高知県立美術館で「柳原睦夫と現代陶芸」展が開催された。近作について、壺の「中の力が形をつくる。空っぽの意味をどうとらえるか」と、語っており、東洋の禅への回帰ともとれる。田島征彦同様に、若い頃から関西美術界の重鎮・木村重信に眼を掛けられた一人だ。
絵本・漫画・陶芸・ゴリラ画家からフィギュアまで
美術の分野には、まだまだ個性豊かな異色のアーティストがいる。絵本の西村繁男(40回、1947~)、漫画家の黒鉄ヒロシ(竹村弘 41回、1945~)、陶芸の武吉廣和(43回、1950~)、画家の阿部知暁(旧姓:浜口 51回、1957~)などである。
西村は、中央大学商学部に進むが大学紛争で学校は閉鎖、セツ・モードセミナーで学ぶうちに、田島征三先輩を訪ねたことがキッカケで、イラストレーターから絵本作家に進む。田島に誘われて、「ベトナムの子どもを支援する会」の野外展に参加、憧れていた長新太・和田誠などに混じって出品する。『絵で見る日本の歴史』で絵本にっぽん賞大賞、『がたごと がたごと』で日本絵本賞を受賞、日本を代表する絵本作家の一人となった。高知の日曜市を描いた『にちよういち』(童心社)はじめ、『やこうれっしゃ』『おふろやさん』(福音館)など、現場で取材・スケッチを重ね、すみずみまで精密に描写・構成してある。画面からは登場人物一人ひとりへの作者の暖かいまなざしが感じられ、子どもたちからも親しまれている。人気児童文学者・那須正幹と組んだ『絵で読む広島の原爆』や、『ぼくらの地図旅行』(福音館)の、鳥瞰図も見飽きない。本人と会ったことはないが、田島や那須から聞き、書店や図書館で折に触れては手に取って、楽しんできた。
黒鉄は、近年は漫画家というより、ユニークな発想のコメンテーターとして知られる。武蔵野美術大学商業デザイン科を中退して漫画に取り組み、『漫画サンデー』に連載の「ひみこ~っ」のモダンな絵柄・意外な発想で人気を得る。幕末維新を題材にした『新撰組』で文藝春秋漫画賞、『坂本龍馬』で文化庁メディア芸術祭マンガ部門大賞、さらに『赤兵衛』で小学館漫画賞審査委員特別賞を受賞。『千思万考』『もののふ日本論』(幻冬社)など、著書も多い。同窓会・県人会には顔を見せず、筆者もある漫画家の叙勲記念会で見かけて挨拶しただけだ。本人も紫綬褒章を受けている。本名は竹村弘で、酒蔵「司牡丹」の一族、黒鉄はその屋号に由来する。
武吉は、土佐の山中に穴窯(あながま)を築き、孤軍奮闘している陶芸家だ。1984年に東京池袋の西武百貨店で個展を開催した際に、島崎(森下)睦美(31回)から土佐高教師時代の教え子との知らせを受け、会場を訪ねた。茶器・花器などさまざまな作品の中でも、特に目をひいたのは自然釉のたっぷりかかった大きな壺であった。聞くと、早稲田大学の建築科に進んだが陶芸にはまり中退、全国の窯場を探訪した後に、四万十川の奥地に鎌倉時代からの古式穴窯を築いたという。土をこね、自ら伐採した赤松を昼夜10日間焚き続け、焼きあげるのだ。知人の陶芸評論家も高く評価、雑誌でも取り上げてくれた。最近は音信が途絶えているが、HPを開くと穴窯での作陶を続けているようだ。柳原の現代陶器と対極をなす、いわば自然(土と炎)との合作で生まれる人智を超えた名品だ。
阿部は、大阪芸術大学を1982年に卒業、ゴリラ一筋の画家で自ら「ゴリラ画家」を名乗る。父は、高﨑元尚(16回)と「前衛土佐派」を作った浜口富治である。小学時代に動物園でゴリラを見て以来のゴリラ好きで、先輩画家から「好きなものを描きなさい」と言われ、ゴリラ探訪が始まったという。世界の動物園はもとより、アフリカの森に野生のゴリラを訪ね、観察・交流を続けている。著書には、『ゴリラを訪ねて三千里』(理論社)、『ゴリラを描きたくて』(ポプラ社)などがある。ゴリラ研究の世界的権威・山極寿一(現京都大学総長)は、2010年の高知大丸での個展に寄せた文章で、「ぜひ阿部さんの画を通してゴリラの心、遠い人間の先祖の心を知って欲しい」と述べている。山極によると、個人主義化の強いサル類と異なり、ヒト科のゴリラは家族集団で助け合って暮らしている。だが、近年人間はサル化(個人主義化)が見られるという。ゴリラの実態を熟知した阿部には、ゴリラの人間味あふれる家族生活を描いた新作絵本を期待したい。
最後に、千頭裕(58回)から紹介されたデハラユキノリ(出原幸典 68回 1974~)に触れておきたい。大阪芸術大学デザイン学科を卒業後、フィギュアイラストレーターとして活躍、海外も含め毎年新作を発表し続けている。お菓子「きのこ山」が、代表作の一つである。
芸術的教養を重視した三根校長の先駆的“人材教育”
母校卒業生からは、これら以外にノンフィクション文学で大活躍の塩田潮(塩田満彦 40回)や門田隆将(門脇護 53回)、文藝評論家の高山宏(42回)・加賀野井秀一(44回)・大森望(英保未来 54回)などがおり、アーティスト・文化人の輩出がいわば伝統になっている。では、その原点はどこにあるだろう。やはり平井康三郎を見いだした初代校長・三根圓次郎である。平井と同じ5回生の伊野部重一郎(昭和4年卒)は、当時の学校生活を「我が土佐中には音楽があり、音楽会が時々あって先生方も演奏された。また校外から小さい音楽団を招いて演奏したこともある」(『三根先生追悼誌』)と述べている。開校時に英語教師として赴任した長谷川正夫(青山学院卒)は絵画も担当、「校長は画架、石膏像、額縁など私の要求するままに買ってくれた。絵の時間には潮江山(筆山)に登ってスケッチをさせたり、自然を眺めながら絵の講義をしたりして、全く自由にできた」(『創立五十周年記念誌』)という。これは、大正時代に興った『赤い鳥』に代表される芸術教育運動も後押ししたが、なにより三根校長の芸術重視の教育理念にもとづくものだ。
土佐中学開校当時の文部省「中学校則」の教科には、図画および唱歌もあったが、唱歌は「当分欠クコトヲ得」とあり、必修ではなかった。音楽として必修になるのは、昭和6年の中学令改正からである。それなのに、上級学校への進学・人材育成をめざす土佐中は、なぜ芸術教科に注力、当初から授業に取り入れたのか。それは、三根校長が文科大学(現東京大学文学部)で学んだ哲学科主任教授ケーベル博士の教えに感銘を受けたからであろう。ドイツで哲学を学んだ博士は、ロシアでチャイコフスキーから直接学んだピアニストでもあった。ケーベルは、学生にこう呼びかけている。「私の諸君に対して望むところは、諸君が偉大なる芸術家、詩人および文学者の作品をば、大思想家の著作と同様に、勤勉かつ厳密に研究せられんことである」(『ケーベル博士随筆集』岩波書店)。
三根校長は、人間の成長にとって芸術的教養がいかに大切かを実感しており、土佐中で実践するとともに、一高・東大進学の力がある平井には、優れた音楽的才能があることを見抜き、あえて東京音楽学校を薦めたのである。第二次大戦中、戦時体制が強化されるなか東京美術学校に進んだ高﨑元尚も、卒業後母校の教師として多くの芸術家や芸術愛好者を育てた。現代の情報化社会では、商品デザインやCMソング選定にとどまらず、世界に飛躍する各界のトップには、文学・音楽・美術の素養が不可欠になってきている。
第二次大戦後には、大嶋光次校長が新制中学・高校として再出発するに当り、男女共学を導入するとともに学園の民主化を図った。そして、運動部・文化部の設立と活性化を行い、多くのアスリート、アーティストが誕生した。こうした伝統が、100周年を迎えてさらに深化し、時代を切り開く教養豊かな人材が育つことを強く願っている。(完)
≪お詫び≫筆者の校正ミスで、お名前に誤記があり、大変失礼致しました。黒鉄ヒロシ様、西村繁男様、ならびに読者の皆様にお詫び申し上げます。……中城正堯 回想浮世絵との出会いと子ども文化研究
冨田さんから、「なぜ浮世絵に関心を持ったのか?」とのお尋ねがあったので、「浮世絵による江戸子ども文化研究」の経緯と成果を、簡単に説明したい。
直接のキッカケは、公文教育研究会による1986年(昭和61年)のくもん子ども研究所設立である。その理事に就任し、研究テーマの提案を求められた。そこで「子どもに関する浮世絵の収集と、その解読による江戸子ども文化研究」を提案、当時の公文毅社長が「だれもやってないテーマならやろう」と決断、多額の予算を任されてスタートした。では、なぜこのテーマだったのか、当時話題になっていたフランスの歴史学者フィリップ・アリエス著『<子供>の誕生』(みすず書房)でもちいられた、絵画を史料とし活用する子ども史研究手法に共感を覚えたからである。
ただ、美人画や役者絵・名所絵・春画で知られる浮世絵が、はたして子ども文化研究に役立つ絵画史料としての質と量を持っているのか、周囲からは危惧された。しかし、幼い頃から実家の襖に貼ってあった浮世絵(坂本龍馬も眺めたと伝わる)に親しみ、土佐中の図工で横田富之助先生から浮世絵版画の制作指導を受け、さらに編集者としてアン・ヘリング先生(児童文学・おもちゃ絵研究者)など浮世絵愛好者と接し、自信を深めた。1986年に東京都庭園美術館で開催された「日本の子どもの本歴史展」でも、浮世絵版画の技法による多色刷の子ども本やおもちゃ絵(紙工作や双六など)が展示されており、子どもの遊びや学びを描いた子ども絵(風俗画)も、子ども向けの昔話や武者絵(物語絵)などもあるだろうと確信した。
こうして約20年間、前半はくもん出版の業務と兼務しつつ浮世絵収集と研究に取り組み、約3.000点の子ども浮世絵(子ども絵・おもちゃ絵・子ども物語絵)を国内・海外から収集した。この間、精神分析学の北山修先生(九州大学名誉教授、ザ・フォーク・クルセダーズ)による江戸の母子関係分析、日本史の黒田日出男先生(東京大学史料編纂所元所長)による江戸子ども風俗と中国唐子との関連研究など、学術研究に多々寄与できた。
ヴァティカンのローマ教皇ヨハネ・パウロⅡ世にも招かれ、ご説明にうかがった。この間、パリではアリエスの門弟が国立中央図書館で開催した「L’enfance au Moyen Age」展があり、豪華研究図録を取り寄せて楽しんだ。
また、国際交流基金が日本を代表する美術コレクションとして、1998年から翌年にかけてヨーロッパ巡回展(モスクワ・パリ・エディンバラ・ケルン)を開催。ケルンでは、ドイツに於ける日本年で秋篠宮両殿下に展示のご説明を仰せつかり、記念講演「浮世絵の子どもたち」も同時通訳付で行った。
子ども浮世絵展は国内では、東京・大阪・高知など全国30ヶ所ほどで開催、各地で講演やギャラリートークを行ってきた。出版活動の主要な作品は、冨田さんの紹介の通りである。
国際浮世絵学会では、「子ども浮世絵に見る魔除け」「もう一つの美人画“母子絵”」などを発表、学会誌『浮世絵芸術』に「<上方わらべ歌絵本>の研究」などを執筆した。今は、國學院大学を中心とする大学院生の子ども浮世絵研究会に、時折顔を出している。
なお、子ども浮世絵で世界に知られる存在となった公文教育研究会の収蔵品は、ウェブサイト『くもん子ども浮世絵ミュージアム』として公開されている。 <版画万華鏡・1>
土佐中での出会いから生まれた浮世絵コレクション
中城正堯(30回) 2010.04.08
 |
|---|
建学の精神は何だったのか
2001年版の土佐中・高「学校案内」を見ると、相変わらず大きな文字で「報恩感謝の理念のもと社会に貢献する人材を育成することを建学の精神として創立されました」とある。また、80周年記念の高知新聞広告特集の「企画書」には「開校以来、報恩感謝の校是と文武両道の教育方員を掲げ」とある。幸い上村浩君が司会してくれたこの特集の座談会では「土佐中・高は学業もスポーツも、そして文化活動もという『文武両道』の校風のもと、個性豊かな人材を育て上げてきた」と述べてあり、報恩感謝など出てこない。文武両道は、校歌四番「それ右文と尚武こそ」に由来し、問題ない。
では、そもそも土佐中の創設の理念、建学の精神は、どう謳われてきただろう。いつから「報恩感謝」などという矮小化が始まったのだろう。
最も古い記録として、大正8年11月2日の『土陽新聞』記事がある。「土佐中学校創立目論見」の見出しで、「予科として小学五六年級を添附し七学級を置く」「一学年二十五人を限度とし俊秀者を集め無資力者は之に給費す」「学校全体を家庭的とし寄宿舎を設け成るべく全生徒を寄宿せしめ生徒をして田園生活に趣味を起さしむ」「職員以下小使に至る迄都て俊秀教育に趣味を有するものを選抜起用」とある。これは、初代校長三根円次郎着任以前だが、俊秀教育すなわち英才教育をめざし、その賛同者しか雇用しないと述べている。「生徒をして田園生活に趣味」というのも、時代を先取りしており、校舎・寄宿舎とも実際梅が辻の田圃のなかに建てられた。さらに、創立者である宇田友四郎、川崎幾三郎の伝記にも「国家有為の人材を養成することが其の目的」と明記してある。人材教育、英才教育という言葉も使われているが、報恩感謝は出てこない。『近代高知県教育史』にも、「英才教育を目的として大正九年二月に設立」とある。
初代三根校長の教育理念
では、初代校長三根円次郎の掲げた教育理念と教育方針をみてみよう。昭和五年の学校要覧には、設立趣意書が載せてあり「高等教育ヲ受クルニ十分ナル基礎教育二力ヲ致シ修業後ハ進デ上級学校二向ヒ他日国家ノ翅望スル人士ノ輩出ヲ期スルモノナリ」とある。やはり建学の目的は「国家有為の人材育成」であり、教育方針は「個人指導」「自発的修養」「自学自習」「自治」等となっている。生徒一人ひとりの個性と自律性を尊重しつつ入材の育成をめざす、画期的な教育であった。これは、当時東京府立一中校長川田正徴とともに、大正デモクラシー時代の全国中学教育をリードした三根校長ならではの方針だ。報恩感謝の言葉などはここにもない。わずかに、美文で知られた大町桂月が父兄の依頼で選文した「開校記念碑文」の中に、宇田・川崎二氏をたたえて「国家に尽すは二氏の恩に報ずる也」とあるにすぎない。
川田校長をちょっと紹介しておくと、高知県出身で府立一中校長として中等教育界に君臨し、宇田・川崎二氏への三根校長紹介者でもあった。大正二年四月から、一年二か月にわたって欧米の教育事情視察に出かけ、イギリスのイートン校、ハーロー校に感銘をうけ、府立一中を「生徒が自分の行動に責任を持ち、生活に責任をもち、しかも紳士的で、未来を背負う人材をつくる学校にしよう」(『日比谷高校百年史』)とした。一中から日比谷高へ続く自由闊達な校風を築いた名校長であった。
この川田校長の最良の同志が、帝国大学(東大)哲学科出身で「有志全国中学校長会」会長の任にあった山形中学校長三根円次郎であった。三根が会長として起案した「中学教育上(第一次)大戦後特に注意すべき事項」には、すでに「自学自習の気風を馴致すること」「個性教育に重きを置くこと」がうたってある(『山形東高等学校百年史』)。三根の教育者としての信念を示すエピソードは、大正七年に赴任した新潟中学でのスト事件である。赴任直後に新潟高校の新設が決まり、三根は進学準備の特別授業を始める。ところが反発した生徒が同盟休校をおこし、退学者が出る。その後、大正九年に人望を回復しないまま、土佐へ行く。ところが後になって、「実はこの退学生徒の転学先について、何日もかけて県内各地の中学を回り、熱心に奔走したのは三根校長自身だった」ことが判明する(『新潟高校百年史』)。土佐中時代も、失明しながらも卒業生の大学での学業、就職先から左翼運動とのかかわりまで案じ、さまざまな救いの手をそっとさし伸べている。生徒達に「報恩感謝」の念を強要するような姿勢は、微塵もない。
三根校長の先見性や、グローバルな感性は制服でも見られる。一回生の森岡清三郎先輩は、こう述べている。「制服が出来るということになり、東京府立一中の型、ネクタイ折襟のものを中沢に着せた。これはよいと喜んでいたが、きめられた制服はつめ襟で、皆がっかりした」(『創立五十周年記念誌』)。背広は値段が学生服の倍かかるため、やむをえず断念、霜降りの詰め襟学生服になった。日本の学校での制服は、明治12年に学習院が海軍士官型の制服を導入したのに始まり、軍国主義とともに広く普及した。襟の白線も軍の階級章をまねたものだ。土佐中では、二代青木勘校長が前任校の愛知一中にならい、他校との差別化のために導入した。挙手の礼など軍事教錬の強化に反対、配属将校との激論がもとで急逝したと伝えられる三根校長なら考えられないことだ。国際化時代のいま、黒い学生服に白線は全く陳腐だ。三根校長の当初の意図どおりの背広に、早急に変更すべきではないだろうか。
21世紀を迎え活発な議論を
話を戻すと、土佐中・高の歩みの中で「報恩感謝」を強調したのは、われわれが在籍した三代大嶋光次校長時代である。クラス名のHOKSも、報恩感謝に由来する。しかし、宇田・川崎両家や、父母の恩への感謝を説いても、建学の精神が報恩感謝とはいっていない。四代曽我部清澄、五代松浦勲両校長はともに母校出身だけに、きちんと建学の精神はおさえていた。曽我部校長は、創立五十周年の式典で「本校教育の基底をなす〈人材育成〉とい う根本理念は創立以来今も変わりございません」と述べている。もとより、建学の精神が時代に合わなくなれば、新しく校是や教育理念を制定するのは可能であり、非難すべきではない。しかし、建学の精神は勝手に変更できるものでないし、土佐中に関してはその必要もない。それに、今ごろ「報恩感謝」を持ち出すセンスが理解できない。この言葉にあこがれて生徒が応募するとは、とうてい考えられない。現在の校長は大嶋校長同様に母校出身ではないが、教頭以下母校出身の教職員は数多くいる。理事会や同窓会ともども、なぜ問題提起しないのか、不思議である。私学をめぐる経営環境が厳しさを増すなか、魅力ある教育理念を社会にきちんとアピールし、学内が一致してその実践に当たらねば生き残れないことは、いうまでもない。今一度、大正八年の「土佐中学校創立目録見」はじめ、設立当時の文献を全職員で読み返してほしい。また、報恩感謝がそんなに重要なら、学校が範を示し、学校案内や同窓会名簿などで、広く創立者・初代校長の人柄、教育理念を知らすべきだろう。御遺族との連絡も密にすべきだ。ところが名簿一つとっても、初代校長の御遺族すら空欄のままである。御次男は健在であり、80周年式典には当然御招待すべきであった。公文先生の御遺族も記載がない。恩師の御名前のミスも目立つ。これで報恩が校是などといえるだろうか。 最後に、建学の精神がきちんと伝わってない主要な原因に、創立八十周年を迎えながら、いまだに学校史が編纂されていないことがあげられる。これでは、母校への誇りを確かなものにすることも、大正自由教育における母校の素晴らしい実践例を教育史にとどめることもできない。学校当局が早急に対応するとともに、このような問題に関しての校内職員の積極的な議論を期待したい。
2001年6月1日発行『うきぐも』18号(30回生Oホームクラス誌)より
向陽新聞に見る土佐中高の歩み①学校再建と民主化への熱気伝える
中城正堯(30回) 2010.07.31
 筆者近影 |
|---|
創刊のいきさつと紙面
戦前は教育も国家統制のもとで皇民教育や軍事教練が強制されたが、戦後は米軍の占領下で教育の民主化がはかられた。六三制で中学までが義務教育になり、男女共学が打ち出された。大嶋校長は他の私学にさきがけてこの潮流を読み取り、中高一貫の男女共学に転換、定員も大増員に踏み切った。学園民主化の柱としては生徒会の設置と、生徒の自由参加によるクラブ活動(部活)の奨励があった。部活の中でも新聞部は、生徒の自主的な報道言論機関として学園民主化の重要な役割を担うこととなった。
敗戦時の土佐中生は県内各地で集団生活をしており、山崎和孝(26回)など1年生は高岡郡尾川村にいた。やがて高知市池の浦戸航空隊跡(現・高知女子大や高知医療センター)から兵舎の払い下げを受け、生徒一同も協力して運び、なんとか仮校舎を建てた。それと同時に部活が始まり、野球部・園芸部・文芸部・絵画部など続々誕生した。高1になった山崎が同級の西原道夫たちと新聞部創設を考えていた頃、中3の細木大麓・岩谷清水・岡林幹雄(27回)も同じ思いであることが分かり、一緒になって結成した。
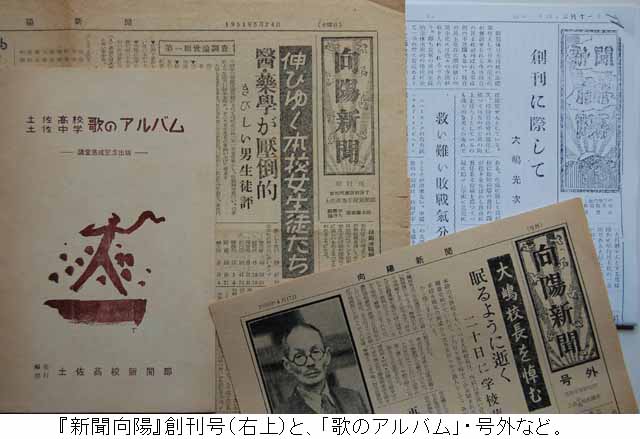 |
|---|
論説は「学校生活に活気をもたせよ」で中3細木大麓、コラム「ひとりごと」は高1山崎で「高知女高(現丸の内高)と高知高(現追手前高)の自治会が二校合併を陳情」などの秘話が出ている。中2酒井芳美のエッセイ「小さきもの」には、早熟ぶりがうかがえる。高1山村泰造は「プロ野球展望」を堂々と論じている。「詩と俳句」から「笑話」まで掲載され、報道論説と文芸の総合紙であり、イリキ眼鏡店や哲学の店・田所文具店など、広告もしっかり集めてある。
昭和24年7月発行・第3号のトップは、「苦心の結晶われらの新校舎遂に落成」である。木造二階建新校舎落成式から、感銘深い挨拶として「時代の波にのれ そしておぼれるな」という、阿部孝旧制高知高校長の言葉を紹介している。落成式で表彰された町田義隆氏(工務店主)は「バラックを兵営跡から持ってくるのに走り回り、木材を手に入れるために大栃の営林署に校長と行った」と、さらっと語っている。後に掛水俊彦(24回)は、「大工の棟梁の姿で連日采配をふるった町田さんこそ隠れた功労者」と述べている。阿部の名言や隠れた功労者をきちんと取上げたのは、当時の編集者の見識であろう。また、国立大学設置法案反対の風潮に流されてストに突入した生徒会の「苦い経験」への反省記事もある。筆者も入学間もない頃、教室に先輩が来てアジ演説をした光景を覚えている。
学校ジャーナリズムの開花
昭和25年頃に新聞部で大活躍をしたのが岩谷清水であり、山崎は「彼はジャーナリズムのセンスに充ち、校内の事件を拾ってきてはジャーナリスティックに取り上げた。生徒会と学校が対立したときに大記事を書いてきたが、大議論の末に少し控えめに紙面を割付けた。これが高知新聞記者の目にとまり、<この小さい扱いは何事だ。学校新聞は学校の問題を掘り下げるのが使命だ>と厳しく指導をうけた」と、述懐している。この指摘は、次第に新聞部のバックボーンとして受け継がれていく。
 |
|---|
中山編集人の第12号トップは「座談会 生徒のための生徒会」だが、「生徒会活動は民主生活の第一歩」と論じ、別項の中学生徒会の活動では通称「オンカン道路」(梅ヶ辻から学校まで、中山駸馬先生の愛称)の交通整理に取り組むことなどが報告されている。美術部と新聞部共催の「校内展」開催と入賞者を東京に派遣する企画もあり、鎮西忠行先生の「東京へはだれがゆく?」を掲載している。県下を制覇した中学野球部の富田俊夫先生は「栄光への道をうち進まん」と檄文を執筆している。この頃、文化部・運動部とも大躍進をとげつつあった。堀詰座や高知中央公民館で開催された芸能発表会では、高塚準一郎の「俊寛」、西内総一郎(北村総一朗)の「煩悩無安(平維盛)」などが市民の間でも話題になった。北村が後に大活躍する素地は、この頃から培われていた。
大町玄編集人(30回)の第15号は、「新生日本の出発に当たって」がトップ記事で、昭和27年4月の講和条約発効に当たっての大嶋校長メッセージを掲載している。この号には、山崎・岩谷など新聞部先輩による東京支局開設が報じられ、早速「先輩訪問記」で東京同窓会の世話役を務めてきた同学社近藤久寿治社長の探訪記が載っており、独力で出版社を起こした経緯や後輩への期待が述べられている。千原宏編集人(30回)の同年11月第17号は、トップに「全校舎ついに完成 これから内容の充実だ」の文字が踊っている。開校33周年・本館落成に合わせて、「開校記念碑文」の再評価を呼びかける記事も出ている。
学校・新聞の躍進と課題
昭和20年代後半の新聞部にとっては、文化事業の展開も忘れることが出来ない。27年には応援歌を募集、河野伴香先生の詩が入選し平井康三郎(5回)の作曲で、後に甲子園にも響き渡る「青春、わかき、血潮はたぎる…」が誕生した。これに戦前からの校歌・向陽寮歌、創立三十周年記念歌を加えた「土佐中高 歌のアルバム」も29年の講堂落成記念に刊行した。同年「四国四県高等学校弁論大会」を開き、30年からは「先輩大学生に聞く会」を開始、31年には「小学館全国児童生徒図画作品展」を中央公民館で開催した。
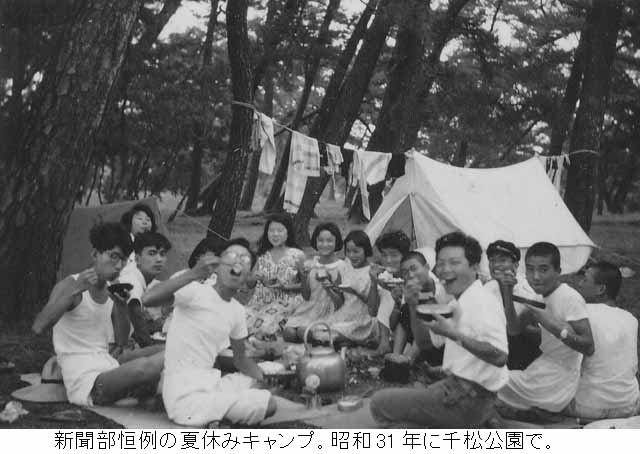 |
|---|
しかし校舎が完成し、進学での名声が定着、野球などクラブ活動が全盛を迎えるとともに、校内にはさまざまな「ゆるみ・ゆがみ」が生じ始めていた。やがて中学入試問題の漏洩と同盟休校という大事件が発生し、新聞部も真価が問われることになる。(以下次号)
<補記>創刊当時の事情については山崎和孝さんからメモをいただいたが、字数に限度があって十分には活用できなかった。いずれ、山崎・細木の両先輩から、このHPに寄稿いただきたい。また、占領下ならではの記事としては、第11号に「総司令部新聞出版課長インポデン中佐と安部新聞部長が懇談」とあるが、これも割愛した。昭和20年代の向陽新聞には、占領から独立への時代に揺れ動く戦後社会を反映した貴重な学園生活の記録が残されている。向陽プレスクラブの準備会によって向陽新聞バックナンバーの電子化が進んでいるので、ぜひこれらの記事を活用いただきたい。また、記事に出来ず胸の奥にしまい込んだままの事件も、いずれ紙面の背後から浮かび上がらせたい。(中城記) ―三根校長のエピソードを探る―
猫の皮事件とスト事件のなぞ
中城正堯(30回) 2010.10.17
細木志雄大先輩の校長追憶
 筆者近影 |
|---|
「先生について私が最も嬉しくかつ力強く感じたのは山形中学校長時代の猫の皮事件、新潟中学校長時代のストライキ事件等に見られる先生の稜々たる気骨である。信ずる所に向って勇敢に突入される態度、威武を怖れず、権門に屈せず、かりそめにも阿諛迎合されない気概、さらに事に当たっていささかも動じない肚(はら)、そこに先生の偉大さを痛感した」
この二つの事件については、追悼誌の中の「三根先生を偲ぶ座談会」でも細木大先輩がさらに詳しく語っているが、伝聞であり事実かどうか確認がされてないと注記してある。そこで、山形・新潟双方の知人に調査を依頼した。その結果は28回生が編集発行した『くろしお 第四集』に概要のみ報告したが、補足を加えて再度明らかにしておきたい。なお、問題提起された細木志雄大先輩は、向陽新聞創刊メンバーのお一人である細木大麓さん(27回生)の父上で、東京大学農学部を卒業、戦後は高知県出納長などの要職に就き、土佐中高同窓会副会長でもあった。筆者が新聞部当時には、何度かインタビューに応じてくださった。向陽新聞10号・17号・21号に登場いただいている。
山形中学での猫の皮事件
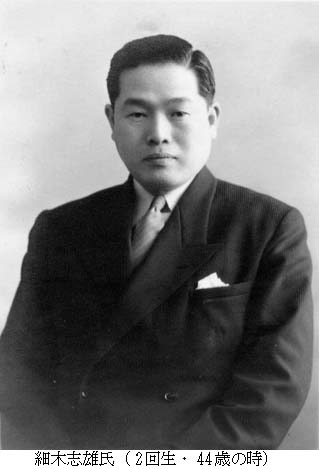 |
|---|
「あの添田敬一郎氏ね、あの人が山形県の知事時代に先生は山形の中学の校長だったのですネ。その中学へは添田さん以前の知事は卒業式には金ピカの服を着て出たそうです。ところが添田さんは背広で、しかもチョッキは毛皮だったのですネ。それで生徒達は学校を馬鹿にしているというので憤慨して、終了後知事が帰ろうとして玄関に出てみると白い模造紙に漫画を書いて、それに『添田猫の皮』という註が書いてあったそうです。(笑声)それを見て知事が憤慨して誰がこういうものを書いたのか調べて処分しろというのだそうです。ところが校長自身も生徒の気持ちがよく判かるし、無理がないという気持ちがしたのでしょう、処分も別にしなかったのですネ。知事は怒って校長をとうとう九州のたしか佐賀県の中学と思いますが、そこへ追い出してしまったということを聴いたことがあります」
「あの添田敬一郎…」とあるように、添田は当時著名な人物で、東大から内務省に進み、埼玉・山梨の知事を経て大正5年4月に山形県知事に就任、翌年12月に内務省地方局長に転じている。その後政治家となり、衆議院議員に当選7回、民政党政調会長を務め、第二次世界大戦の頃には産業報国運動や翼政会で活躍した。
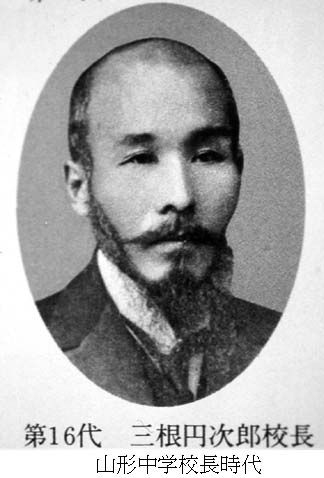 |
|---|
ただ、猫の皮事件は公式の記録には見あたらない。勅任官待遇を受け、絶大な権力を持つ当時の知事への批判的事件を活字にする事ははばかられたのだろう。しかし状況は符合する。添田山形県知事は大正5年4月に着任しており、猫の皮事件は大正6年3月の卒業式での出来事だろう。同年12月には離任し、内務省地方局長に就任している。この翌年に、三根校長は九州ではなく新潟中学校長に転じている。知事の転任が先で、校長の転校も懲罰人事ではあるまい。ただ、表沙汰になる事はなかったものの、知事の教育軽視へ反発した生徒による風刺漫画が、知事の大人気ない態度と、三根校長の権威に屈しない姿勢を鮮明に対比させ、土佐中にまで語り伝えられたと思われる。
新潟中学ストライキ事件
細木大先輩は、同じ座談会でさらにこう述べている。
「新潟中学時代にストライキが起こって、それからしばらく校長が行方不明になったのですネ。どこへ行ったか判らんというので大騒ぎをしたのです。そうしたら新潟県の地方の中学を回ってストライキ騒ぎで処分した生徒の転校先について話をまとめてきたというのです。つまり校長はストライキを起こしたについて痛烈な訓辞をやって無期停学の処分をして置いてから、それから行方不明になったのだが、それはその処分された生徒の転校先について地方の中学へ交渉しに回っていたというのですネ。」
これを受けて都築宏明先輩(3回)は、「そういう点は土佐中学でも随分ありましたねェ。少し成績の悪い生徒に落第させないように他の学校への面倒を見たり…、他所へ行って優秀になったのが大分ありましたョ」
ストライキ事件については、新潟日報編集局の佐藤勝則氏の手をわずらわした。こちらは『新潟高校100年史』に、以下のようにきちんと記録されていた。大正7年4月に第11代校長として着任、「小柄で黒い髭をたくわえ、眼光鋭く、人を畏怖せしめる風貌を持ち、言辞も明晰で理路整然、修身の時間ともなれば、クラス全員緊張し、さすがの腕白どもも粛然として高遠な哲理を承った」とある。昼食には五年生を三名ずつ呼び、「一緒に弁当を食べつつ、生徒の身上・志望を聴取し、その志望に対しては適切な指導をするというきめ細かな一面を持っていた」が、近寄りがたい人物とも見られていた。それは、「眼病のためにほとんど失明寸前の状態にあったのだ。そのため、…生徒に挨拶されても気がつかず返礼を欠くことが多かった。だから生徒は、校長を<冷淡で傲慢な人物>と思い込んだのである」。眼病故の誤解が生じていたのだ。
この大正7年5月に新潟高校(旧制高校)の設置が決まると、新潟中学では入試準備の特別授業や模擬試験に忙殺されることになった。このような中で、6月18日に同盟休校が起こり、四、五年生の大部分が欠席した。理由書には「運動会の応援旗禁止」「処罰厳に過ぎる」などとあったが、実際は運動会後に生徒のみで慰労会を開いたことが発覚したので、その処分に対して生徒たちが先手を打ったとされる。さらに「強まる受験体制への不満、英才教育を掲げる三根校長への反発」もあったが、生徒側の根拠薄弱と100年史には述べてある。そして、中心生徒2名退学、2名無期停学などの処分が決まった。
三根校長は大正9年1月に新潟中を辞任し、土佐中学の初代校長に迎えられる。大正10年の新潟中学30周年には祝辞を寄せたが、100年史にはこう紹介してある。「<私は貴校歴代校長の中で最も不人望で生徒に嫌われ、ついに排斥のストライキを受けた>と語り、しかし<卒業生や県当局の斡旋によって多数の犠牲者を出さずに解決できた>として感謝の意を表している。実は退学生徒の転学先について、何日もかけて県内各地を回り、熱心に奔走したのは三根校長自身であった」。
三根校長の歩みと土佐中
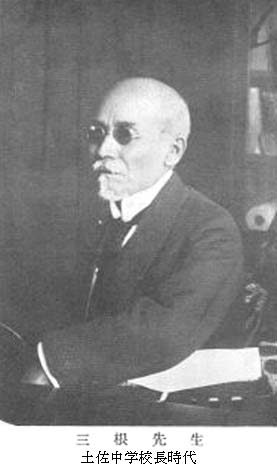 |
|---|
なお、三根校長は長崎県私立大村中学・第五高等中学校(旧制熊本高校)から帝国大学文科大学哲学科に進んでいる。卒業した明治30年には京都帝国大学が誕生し、従来の帝国大学は東京帝国大学となる。文科大学には、哲学・国文学・漢学・国史・史学があり、後の東京帝国大学文学部にあたる。当時の文科大学卒業生の進路について、『東京大学物語』(吉川弘文館 1999年刊)で中野実(東京大学・大学史史料室)は、「主な就職先は中等学校の教員にあった。その中から少しずつ文学者が登場してきていた」と述べている。筆者が研究室に訪ねた際には、「外山正一学長は、中学の教職に進んでも職人的教師ではなく、研究も続けて自ら生徒に範を示せと説いた。当時は、高等学校の数もまだ少なく、県立中学が各県の最高学府であり、国をあげてその充実をはかっていた。帝大卒の教員は尊敬される存在で、その待遇もよかった」と語ってくれた。
三根校長の哲学科同期は比較的多くて16名、一年先輩には桑木巌翼(哲学者・東大教授)がいる。国文科の一年先輩には高知出身の文人・大町芳衛(桂月)がおり、後に土佐中の開校記念碑文を書いて名文と讃えられる。国史科には三根と同じ長崎出身の黒板勝美(歴史学者・東大教授)や高知出身の中城直正がおり、中城は後に高知県立図書館の初代館長となって三根校長と再会する。
 |
|---|
なお、制服の袖に軍服をまねて白線を巻くようになったのは、二代校長青木勘の時代からである。三根校長は背広を望んでおられた。それにつけても、あと十年後に迫った開校100年には、ぜひ『土佐中高100年史』を刊行し、川崎・宇田ご両家から歴代校長・教職員・生徒・同窓会・振興会が一体となっての激動の時代の歩みをみんなでたどり、今後の母校発展に生かせるようにしたいものである。
(引用文は現代表記に改めた)
<山田一郎先生追悼文>海辺から龍馬の実像を発掘
中城正堯(30回) 2011.04.22
山田先生は高知出身のジャーナリスト・評論家で、昭和から平成にかけて活躍、寺田寅彦や坂本龍馬の研究で知られます。高知市三里で昭和7年に生まれ、平成22年1月に90歳で亡くなられました。三里史談会発行の『大平山』37号に追悼文を寄稿いたしましたが、生前には土佐高出身者とも交流が深く、そのことにも触れましたのでここに転載させていただきます。文中の土佐高出身者は太字で表記し、カッコに卒業回を付記いたしました。
ジャーナリストの大先輩
 |
|---|
昭和30年代から40年代にかけて、山田さんは共同通信の文化部長・科学部長・常務理事などの要職を重ね、私も雑誌編集の仕事に追われ、ご挨拶をする機会を持てないままであった。昭和55年に退社した山田さんは、ジャーナリストとしてめざましい活躍を開始した。57年に『寺田寅彦覚書』で芸術選奨文部大臣賞新人賞を受賞、翌58年の正月からは高知新聞で「南風対談」を始めた。高知出身の「十二名家・巡礼の旅」の聞き手として、この対談で有光次郎・大原富枝に続き、三人目に公文式教育を考案した公文公(7)を選んでいただいた。当時私は、くもん出版から公文側の一員として取材に立ち会い、ようやく山田さんともご挨拶をすることができた。
山田さんと公文先生との出会いには前段がある。高知出身の近藤久寿治(6)が創業した出版社・同学社の新ビル落成記念パーティーで、昭和57年に山田さんは公文教育研究会役員の岩谷清水(27・高知市常盤町出身)と出会って公文先生の活躍ぶりを聞き、師弟の文通が始まっていたのだ。この経緯を山田さんは、高知新聞『南風帖』に書いておられる。さらに遡れば、公文先生が大阪帝大理学部数学科を卒業して最初に赴任した海南中学で教えた生徒の一人が、山田さんであった。「南風対談」では、この師弟がクラスの席順や同級生の消息、さらには当時の高知の教育事情まで克明に記憶しているのに驚かされた。実は私も公文先生の教え子で、戦時中には海軍予科練教授だった公文先生が帰郷、昭和24年に母校土佐中高の教諭になって初めてクラスを持った際の生徒であった。山田さんは、私にとって三里小学校の先輩であり、また公文先生の門下生でありながら数学の不得手な不肖の兄弟弟子でもあった。
平成7年7月に恩師公文公が永眠した際には、追悼文集に伝記執筆をお願いした。刊行まで限られた時間しかなかったが、公文禎子夫人などご遺族・関係者から丁寧な取材を重ね、心のこもった評伝を書き上げてくださった。公文式教育誕生の背景には、旧制土佐中で受けた、個人別・自学自習教育があることも指摘いただいた。
多士済々の東京「みさと会」
「南風対談」が契機で、海南時代の教え子である山本一男(デザイナー山本寛斎の父)も、革のジャンパーでオートバイに乗り、颯爽と千代田区市ヶ谷の公文東京本部にやってきた。「若い女性に追っかけられたが、赤信号で止った際に顔をのぞき込まれて老人であることがバレタ」などと、恩師に笑顔で話していた。三里組も、山田さんを囲む会をやろうということになり、平成初年に東京で「みさと会」を始めた。メンバーは竹村秀博(オリンパス)・小平〈中城〉久(家裁調停員)・池川富子(29・三枝商事)・平田喜信(30・中学で転校・横浜国大教授)・奴田原〈池〉訂(31・高知銀行)・秦洋一(34・朝日新聞)・小松勢津子(35・旺文社)・丸山〈早川〉智子(35・産経新聞)・中島朗(43・電通)など多士済々で、なぜかマスコミ関係者が圧倒的に多く、山田さんにも喜んでいただけた。会場は赤坂の「土佐」などであったが、下戸にもかかわれず最後まで若い酔っぱらいに付き合ってくださった。いかにも潮風にさらされて育ったような風貌と、ふるさとの人と風俗を回想しての鮮明な語り口に一同魅了された。郷土出身の作家・文化人の生い立ちや消息にも精通しておられ、驚かされた。
二回目の「みさと会」の案内状が手元にある。「今回は、高知県東京事務所次長として活躍中の池永昭文(36)さんが、高知新港や橋本県政など三里と高知の最新情報をお話くださいます」と記されている。同学社近藤社長夫人(旧姓・野町初甲)も、母の野町久喜が種崎の桟橋近くに住み、その妹が近くの釣り宿「橋本」のおかみであり、メンバーだった。平田君は私と小学の同級で、父上・平田信男は海上保安庁を経て東海大学教授を務めた航海工学の専門家であった。「みさと会」が縁で山田さんは信男をたずね、坂本龍馬「いろは丸事件」の詳細な資料を提供、現在の海難審判ではどちらに非があるのか審理を求め、真相に肉薄している。
平田君も先祖は土佐藩御船方だが、本人は王朝文学を専攻していた。「源氏物語」や「土佐日記」の研究で知られ、横浜国大の教授であった。国際交流基金からサンパウロ大の大学院生指導に派遣され、帰国すると副学長に就任、次いで図書館長としてその改築を指揮し、市民参加型の新しい大学図書館を開館するなど多忙を極めていた。定年1年前の平成12年に急逝、山田さんの要望を受けて晩年は高知で後身育成に当たると言ってくれていたが、かなわなかった。秦君も医療ジャーナリストとして注目されていたが、自分が病に倒れてしまった。小松さんは種崎にあった高芝医院の姻戚で、トフラー『第三の波』などの翻訳でも活躍した。丸山さんの父上は、市役所の種崎支所長であった。「みさと会」は、山田さんが横浜市から高知市に転居したこともあって、数年で活動を休止してしまったが、三里出身のジャーナリストにとって山田さんは生きたお手本であり、その綿密な取材ぶりと権威を恐れぬ執筆姿勢に、後輩は勇気を与えられてきた。
寅彦と龍馬の研究が双璧
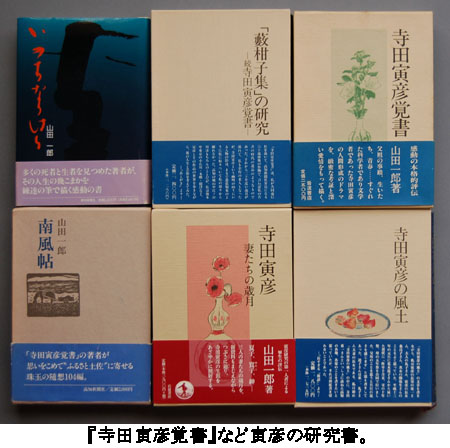 |
|---|
寅彦関連では、『寺田寅彦覚書』刊行後も寅彦の次女・関弥生など一族と交誼を重ねて信頼を得、さまざまな風評のあった三人の妻たちと寅彦との暖かい交情の実態を、前著の20年後に刊行した続刊『寺田寅彦 妻たちの歳月』で明らかにした。最初の妻・夏子の出生の秘密や、種崎・桂浜での療養生活、帰郷する寅彦の船を浜辺で迎える夏子の姿など、新資料を使って描写、山田さんならではの地を這うような粘り強い取材と人物への肉薄が感じられる好著であった。幕末土佐で起こった「井口刃傷事件」では、寅彦の父が果たした不幸な役割も初めて公にしている。
くもん出版で『父・寺田寅彦』(寺田東一他著・寺田寅彦記念賞受賞)を刊行したこともあって、この間の事情は山田さんからも寺田家・関家からもお聞きすることができた。平成5年に帰郷した際、寺田寅彦旧邸を御案内いただいたことも忘れられない。できればこの旧邸とは別途に寺田寅彦記念館を建て、原稿・絵画・著書・愛用の楽器など遺品や関係資料を展示したいと語っておられた。岩手県花巻市の宮沢賢治記念館が、文学者・科学者としての賢治を堪能できる見事な展示場になっているのを参考に、構想を描いていたようだ。寺田家が守ってきた貴重な遺品千数百点は山田さんに託されたが、寺田寅彦記念館は実現せず高知県立文学館に寄贈されることになった。
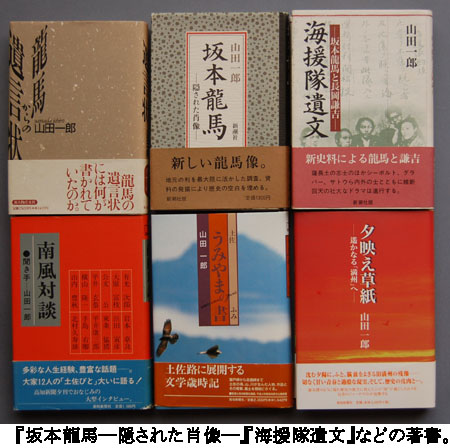 |
|---|
伊与・田鶴など三里人脈を発掘
特筆すべきは、龍馬の継母・伊与の素性を解明したことだ。北代家から川島家に嫁し、寡婦となって父・坂本八平の後妻に迎えられた女性の名前が、「伊与」であることを突き止めたのである。川島家は土佐藩御船倉の御用商人で当時は種崎に住み、御船方の中城家から四、五軒西にあった。当主の川島春麿(猪三郎)と中城直守は、歌人仲間で親しかった。川島家に継母とともに舟でやってきた龍馬が春麿の子どもたちと仲良くなり、特に次女・田鶴を可愛がったことを山田さんは聞き出している。中城直守の子・直楯や直顕とも当然出会っており、最後の帰郷での潜伏につながったとする。安政地震の津波で被害を受け、川島家は仁井田に移転したが、中城家は種崎から動かず直楯が当主となっていた。
慶応3年9月、龍馬最後の帰郷で震天丸にライフル銃一千挺を積んで浦戸湾に入港した際に、大政奉還への藩論が未だ定まっておらず、龍馬の一行はまず隠密裡に中城家にはいったのである。山田さんは、中城直守の筆録『年々随筆』と、中城直正(種崎小学校卒・初代高知県立図書館長)が父・直楯と母・早苗から聞き取った『随文随録』を史料として高く評価し、特に早苗が述べた龍馬の風貌描写を絶賛している。『随文随録』には、中城家で風呂に入り襖絵を眺めた後に、龍馬は「小島ヘ寄リ、舟ヘ帰ルトテ家ヲ出タリ」とある。
この小島家が龍馬を慕っていた川島家の次女・田鶴の嫁ぎ先であり、種崎川島家の跡地に家を建てて住んでいたことも、山田さんは調べ上げている。龍馬帰郷の際に小島家には、十市村の郷士で龍馬の剣道の師でもあった土居楠五郎が、孫の木岡一を連れてきており、木岡はギヤマンの鏡を龍馬に貰ったと『村のことども』(三里尋常高等学校 昭和7年刊)にある。この本では、「坂本龍馬の潜伏」と題して、まず郷土史家・松山秀美の中城家潜伏説を、次いで古老となった木岡の回想を紹介してある。これは、どちらかが真実ではなく、山田さんが解明したように龍馬は双方を順次訪問したのである。
田鶴への山田さんの思い入れはかなりのもので、仁井田浜の小島田鶴の墓前に立ち、「妙音観世音 梵音海潮音」と観音経をつぶやいたという。私の手元に残る色紙にも、これにちなんで「梵音海潮音 龍馬観世音 和平を願うて眠り居り申候 龍馬 山田一郎」と記されている。この小島家から城下浦戸町の今井家に嫁に入った直の子・今井純正が改名して長岡謙吉となり、海援隊に加わって「藩論」「船中八策」の起草者として活躍する。これも、山田さんの『海援隊遺文―坂本龍馬と長岡謙吉―』で、詳述されている。
龍馬と海を結びつけるきっかけとなった継母・伊与と川島家に関しては、再三川島文夫を訪問し、言い伝えを聞き取るとともに龍馬も見たとされる世界地図から古文書まで関連史料を調査されている。我が家では母・中城冨美とともに、信清悠久・美衛夫妻と昵懇であった。信清は戦前に反戦運動をした後、満州に渡って満映で脚本・監督を務め、戦後は映画のシナリオ作家として東京で活躍、帰高後はテレビ番組「はらたいらのおらんく風土記」の台本を執筆し、三里史談会の会員でもあった。山田さんとは、若い頃にともに満州で活躍し、また反骨精神旺盛な物書きとしても気があったようだ。満州時代になじんだのか、ともにコーヒー好きで、特に山田さんは東京・調布市の居室を訪ねても、まず自ら薫り高いコーヒーを入れてもてなしてくださった。
 |
|---|
山田さんが龍馬研究に取り組んでいた頃、新人物往来社主催の龍馬研究会が東京であり、お誘いいただいて山田講師のお供をした。少人数の会だったが、坂本家一族の土居晴夫さんも来会、作家で後に直木賞を受賞した北原亞以子さんも出席しておられた。当時私は龍馬のことも中城家史料のこともほとんど知らず、恥ずかしい思いをしつつ少しは龍馬を調べようと思い立った。今にして思えばそれが山田さんのねらいでもあったようだ。おかげで後の「龍馬役者絵発見」に結びついた。
「中城文庫」の推進役
坂本龍馬が最後の帰郷で中城家に立ち寄ったことは、東京帝大国史科卒の歴史家・中城直正が、龍馬の接待に当たった父母からの鮮明な聞き書として記録している。これらを元に、郷土史家・松山秀美は『村のことども』で、歴史家・平尾道雄は『龍馬のすべて』で、きちんと触れている。しかし、大正14年に直正が東京で交通事故のため急逝してからは、聞き書『随文随録』の存在自体が次第に忘れ去られていった。
この記録が再び注目されるきっかけは、昭和55年の三里小学校開校百年記念誌『三里のことども』刊行である。中城家を調査された坂本一定、中山操の眼にとまり、山田一郎・宮地佐一郎のお二人にも龍馬に関する部分のコピーが渡された。この頃に私の義兄・信清悠久が龍馬生誕百五十年にちなんで『土佐史談』に「龍馬の足跡―種崎・中城家」と題して発表、龍馬が眺めた浮世絵貼り付けの襖が現存することも明らかにした。山田さんは昭和57年に、高知新聞連載「南風帳」で「種崎の龍馬」として紹介、宮地は『坂本龍馬全集』に採録してくださった。後者には、私の祖母・中城仲(旧姓千屋・海援隊士菅野覚兵衛の姪)が龍馬の妻・お龍さんに可愛がられ、ピストルで雀を撃って遊び、別れの記念に帯締めをもらった回想談(昭和16年の高知新聞記事)も納められている。
中城家の古文書などの史料が次第に注目され、高知市民図書館に寄託されるいきさつは、『大平山』第30号に「龍馬ゆかりの襖絵や宣長の短冊」として書かせていただいた。寄託が決まったのは、日本史、特に地方史研究の権威である林英夫立教大名誉教授の評価や、武市瑞山の子孫である武市盾夫(18)中央大教授の口添えもあったが、なにより高知での山田一郎・橋井昭六(元高知新聞社長)のお二人による当時の松尾徹人高知市長への推薦が決め手となった。
寄託が決まると、史料受け入れの担当となった市民図書館・安岡憲彦さんの大奮闘があり、6年目に立派な目録も出来て、平成20年2月1日には寄託から寄贈へ移行し、<「中城文庫」開設記念展・海から世界へ>も開催する運びとなった。ところが、その直前になって、展覧会はするが「中城文庫」は返還すると、図書館長からいってきた。ここでも面倒な仲介を、山田さんにお願いせざるを得なかった。そして岡﨑市長・吉川教育長と折衝いただき、とりあえず展覧会は開会、寄贈式はずれたものの2月13日に行われた。
 |
|---|
話を「中城文庫」にもどせば、問題は個人情報保護に即した利用規程の改定と、史料寄贈者への利用状況の告知を、中城家からお願いしたことにあった。寄贈後に高知県立歴史民俗資料館「絵葉書のなかの土佐」や、県立坂本龍馬記念館「坂本龍馬と戊辰戦争」などの企画展で「中城文庫」史料が活用されたが、市民図書館からは寄贈者に対し、まったく連絡がなかった。幸い歴民館からは図録を贈呈いただき、龍馬記念館からは出品リストを後日いただいた。山田さんも図書館の対応を残念がっておられたが、全国の公立博物館・文書館・美術館・図書館と比べ、利用者へのサービスも協力者への対応も遅れを取っているように思える。かつては高知市民図書館と言えば、文化人を館長に招聘し、出版活動から移動図書館・特設文庫・研究者への協力まで日本の最先端であったが、現在の高知市文化行政にその面影はない。県と高知市で新しく歴史資料館建設の構想があると聞くが、貴重な収蔵史料が多いだけに、その利用サービスでも全国の模範となっていただきたい。
生涯一ジャーナリスト
「中城文庫」とともに山田さんにご迷惑をかけたのは、中城家「離れ」の文化財指定調査である。高知市教育委員会から平成18年に、龍馬ゆかりの「離れ」につき、文化財指定を視野に入れて調査したいとの申し出があり、喜んで同意した。教育委員会の指定で建築物としての調査は伝統的建造物の修築で定評のある上田建築事務所が、歴史的位置付けは山田一郎・栗田健雄両氏が担当くださった。平成19年に『中城家「離れ」調査報告書』が出来上がり、高知市文化財保護審議会に諮問された。委員からは「川島家にしても中城家にしても資料が少ない」「市史跡として保存しなければならない程のものではない」との意見が出て、指定は見送りとなった。山田さんは長年の調査研究をふまえて、歴史的意義を説いてくださっただけに、私には「離れ」自体の文化財指定の可否はともかく、山田さんのこれまでの精密な研究成果が否定されたようで申し訳ない気持ちでいっぱいだった。
山田さんは、「審議内容にはいくらでも反論できるよ」とおっしゃり、委員の文化財についての研究姿勢や歴史認識を残念がっておられた。ただ評価できるのは、審議会の討議「要旨」を教育委員会が当家に示してくれたことである。ぜひ、このような情報開示の姿勢は継続していただきたい。
平成22年正月からNHK大河ドラマ「龍馬伝」が始まったこともあって、この「離れ」もいくらか注目されている。毎回ドラマ後にその舞台を紹介する「龍馬紀行」でも取上げたいとの連絡があり、三里史談会事務局の久保田昭賢(理科・久保田伸雄先生の令弟)さんに取材斑の案内をお願いした。6月末の撮影日はあいにくの大雨で、座敷に雨漏りがしており、撮影スタッフも驚いたようだ。久保田さんから現状を報告いただき、兄・中城達雄の即断で台風シーズンにそなえ、急ぎ屋根の修理を行った。地元業者には上田建築事務所とも打ち合せの上で、伝統的建造物にふさわしい修理をしていただいた。ただ、家屋は使用しないと痛みが早く、今後の活用法が課題である。山田さんは、いくつか腹案をもっておられたようだが、地元でなにかいい案があれば、当家としては山田さんへの感謝を込めて協力したいと考えている。なお、種崎の母屋には平成23年春から兄の孫・田副一家が住んでいる。
近年は、山田さんの調布市のお部屋を年に一度くらいはお訪ねしていた。満州時代の思い出話もうかがったが、終戦時に「ソ連機新京を爆撃」の大スクープを打電した話は口にせず、満州巡業に来ていて敗戦で帰国できなくなった落語家・古今亭志ん生との、糊口をしのぐための興行生活を楽しげに語ってくれた。最後の著書として
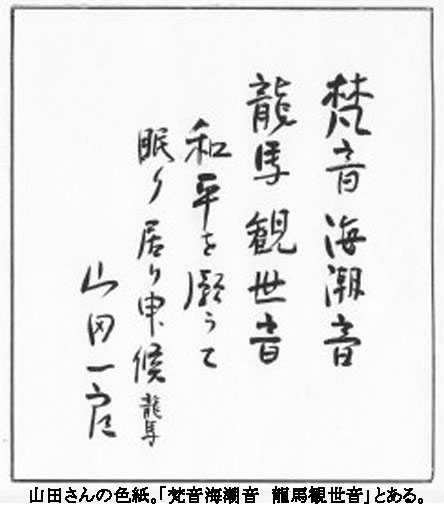 |
|---|
平成21年の暮れには、上京する安岡憲彦さんと久しぶりに山田さんを訪問することになり、電話をかけたが本人も同じマンションの別室に住むご次男もご不在で、不安にかられた。高知で探っていただくと、入院中とのことであった。そして、年を越して訃報が届いた。3月4日に「生涯一ジャーナリスト」という山田さんにふさわしい名称で「偲ぶ会」が開かれると聞き、高知市城西館の会場に駆けつけ、遺影に最後のお別れをさせていただいた。そこには仁井田の浜に立つ老松のように、吹き寄せる時代の烈風に耐え、温顔のなかにも鋭い視線をたたえて真実を追い続けた希有な文人ジャーナリストの姿があった。合掌 展覧会と講座のご案内
中城正堯(30回) 2011.08.10
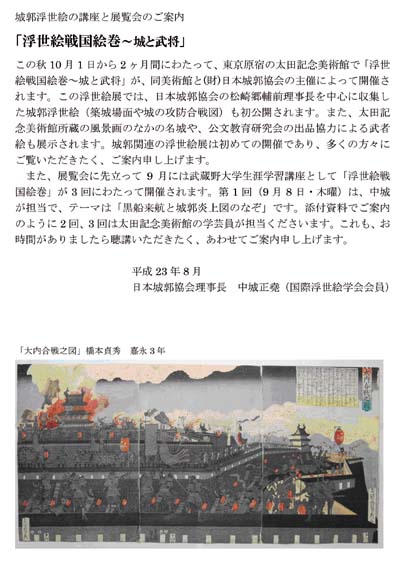
残暑お見舞い申上げます。
今回、城郭浮世絵に関する展覧会と講座を開くことに成りましたので、ご案内申上げます。
右の画像をクリックすると案内状と講座申込書(pdf文書)が出てきます。 龍馬「愚童伝説」から学びの原点をさぐる
中城正堯(30回) 2012.04.15
はじめに
 筆者近影 |
|---|
大河ドラマ『龍馬伝』自体は、放映一年前にNHKの関係者から、「福山雅治を龍馬にしたてた〈劇画〉で、岩崎弥太郎の眼から見る」と聞かされていたので、超かっこよい福山・龍馬と汚れ役香川・弥太郎の極端な対比にも驚かなかった。しかし、高知の城下と安芸の井ノ口村がすぐ隣町にされ、路上で出会った二人がよく行き来し、寺子屋の机が現在の学校と同じ並べ方で、龍馬の愚童ぶりに対して弥太郎には『論語集註』を読ませるなど、興ざめな場面も多かった。
放映でありがたかったのは、最終回の一つ前の「龍馬伝紀行」で我が家の種崎の「離れ」を、龍馬最後の帰郷で潜伏した家として取上げてくれたことだ。六月の撮影当日は帰郷できず、三里史談会の久保田昭賢さんに立ち会いをお願いした。あいにく大雨で、座敷は天井からの雨漏りで畳が濡れ、撮影場面の設定に苦労したとの電話をいただいた。関東在住の兄も私も、雨漏りしているとは思いもよらず、お陰ですぐ修理の手配をすることができた。以前、高知市教委が「文化財指定を視野」に上田建設に依頼して調査を行ってくれ、指定には該当しないとのことだったが、その調査を生かして三里の建築業者に幕末以来の屋根の保存修理をお願いした。NHKの撮影がなければ、雨漏りに気付かないところだった。
本稿では、テレビや伝記物語などで増幅される誤った龍馬伝説が真実と混同されないよう、龍馬ゆかりの旧三里村種崎で生まれ育った者として、龍馬少年の教育と人間形成に関していくつかの指摘をしておきたい。多くはすでに山田さんが論考済みであるが、いくらか別の視点も交えて重ねて呼びかけたい。
大器晩成の流行と愚童説
龍馬の最初の伝記小説は明治一六年に坂崎紫瀾が土陽新聞に連載した『汗血千里駒』であるが、大評判となり単行本としても数社から出版された。この復刻版は数種類あるが、高知では昭和五二年に土佐史談会から出た『汗血千里駒全』が版を重ね、平成五年には新しい「解題」をつけた新版が刊行された。平成二二年には岩波文庫で挿絵全六六点を収録した『汗血千里の駒 坂本龍馬君之伝』が出て、入手しやすくなった。
問題はこの伝記の位置付けである。坂崎は明治初期からの自由民権運動の激烈な活動家であり、その一環として政治小説を発表し、演説会を開催していた。しかし、明治一四年に高知警察署から政談演説禁止の処分を受ける。そこで、寄席芸人として鑑札をとり、馬鹿林鈍翁の芸名で講釈師となるが、たちまち逮捕される。この後で、龍馬の連載を始める。
岩波文庫の校注を担当した神戸大学教授で日本近代文学史専攻の林原純生氏は、「明治一六年という早い時点でかくも見事に坂本龍馬の自由人としての個性が表現されたことは、一つの驚きである」「史書や正史に対して、むしろ、自由党員として自由民権の最先端にいた坂崎紫瀾の歴史意識と、読者と共有しようとした政治理念が、坂本龍馬の個性的な行動や行動空間に強く反映されている」と述べ、自由民権運動のさなかに書かれたこの作品は、幕末や明治維新を素材にした大衆小説・歴史小説の先駆的作品であり、原点であると、高く評価している。
本来この作品は自由民権運動のための政治小説であり、冒頭には井口刃傷事件を持ってきて封建的身分制度のもとでの上士・下士の差別を見事に告発している。ついで、生い立ちに触れ、愚かにみえた少年が剣術や水練に励み、加持祈祷にかこつけて庶民の膏血を吸い取るニセ天狗を退治するまでに成長、十九歳で下士には許されなかった下駄を履いて江戸に出ると、千葉道場の娘・光子(佐那)とのロマンスが花咲く。興味尽きない場面展開の連続だが、政治的意図を持って書かれた小説であり、当然フィクションも多々含んでいる。確実な史料にのみ基づいた伝記や評伝ではない。特に坂崎は講釈師を演じていただけに、噂話を実話のように扱い、江戸の草双紙的な逸話を挿入、誇張した表現で場面を盛り上げている。まず、龍馬誕生にまつわるエピソードから検討してみよう。
 |
|---|
龍馬の背の産毛に関しては、後に妻のお龍や友人も触れており、生えていたのは事実であろうが、「母が常に猫を抱いていたから」はあり得ない。龍の炎が胎内に入って英雄豪傑が誕生するといった龍神伝説は、足柄山の山姥が夢で赤龍と交わって怪童金太郎が生まれたなど、江戸後期にはよく語られていた。英雄が少年期まで愚人であったが、やがて目覚めて大成するという大器晩成論も、うつけ者と呼ばれた織田信長、百姓の子で「手習い学問かつてなさず」と描かれた豊臣秀吉の事例など、幕末から明治まで枚挙にいとまがない。伝記物語の常套的な展開パターンであった。
著者の坂崎自身も、明治三二年博文館刊『少年読本 坂本龍馬』(図1)の緒言で、近年『汗血千里駒』が広く伝播したため、内容を踏襲した伝記が見られることを悔やみ、こう述べている。「世人の仮を認めて真と為すに至る。これ余のひそかに慚悔するところたり。爾来余は龍馬その人の為に大書特書すべきの新事実を発見したること一にして足らず。ここに於て更に実伝を著わし、もって許多(あまた)の誤謬を正し、あわせてその真面目を発揮せんと欲し…少しく余の旧過を償うべきのみ」。しかし、この新著でも薩長連合や大政奉還に関しての誤りは直してあるが、伝聞による生誕伝説・大器晩成説は前著と同じであった。
『汗血千里駒』以降の龍馬像
坂崎自身は、『汗血千里駒』の自序で「龍馬君の遺聞を得、すなわちもっぱら正史に考拠し」と記したが多々誤謬があり、伝聞によった部分もあることを自覚し、後のち訂正に努めていた。ところが、平成五年の土佐史談会版の解題で、岡林清水はこう論じた。「紫瀾はこの作品で、明治御一新を上士と下士・軽格との対立面から把握し、…軽格坂本龍馬を代表とする明治御一新へ向かっての大精神は、自由民権運動につながると考え、この自由党的思想性でもって、『汗血千里の駒』を支えようとした。だが、この作品は、単なる党派的理想宣伝の小説ではない。史実追及を堅実に行い、リアリティのあるものとなっている」。
坂崎の作品は龍馬伝の第一号であり、龍馬研究の基本資料であるが、正史・史実とは言えない内容を織り込んだ政治小説であった。本人もそれを自覚していたのに、平成を迎えての岡林の解題では、「史実追及」「リアリティあるもの」が強調されていた。現在の作家・漫画家・脚本家から龍馬ファンまで、広く実伝と誤解される要因になったようだ。
では、『汗血千里駒』以来、龍馬が実伝と小説の間でどう揺れ動き扱われてきたか、青少年期の描写を中心に筆者の管見から探ってみよう。
明治二九年七月には、坂本家の遠戚になる弘松宣枝が『坂本龍馬』(民友社)を出版、好評で年内だけで五版を重ね、第三版からは龍馬の肖像写真が口絵として掲載される。後に日露戦争でバルチック艦隊との決戦をひかえた一夜、昭憲皇太后の枕辺に現われ、「微臣坂本龍馬でござります。力及ばずといえども、皇国の海軍を守護いたしまする」と告げてかき消えた話が出る。宮内大臣だった田中光顕(元陸援隊士)が人物確認のため皇太后に献上した肖像写真は、この口絵のものとされる。お龍も同じ写真を持っていたと『千里駒後日譚』にある。この弘松の作品も、少年龍馬の描写は坂崎を踏襲している。
皇太后の夢に現われた龍馬の新伝説は、明治新政府で薩長に主導権を奪われた土佐派の閣僚・田中光顕が、挽回策に龍馬を担ぎ出したと言われる。この出来事は新聞が取り上げたため、世間に広まる。土佐出身の画家・公文菊僊は後に龍馬立像に「征露の年 皇后の玉夢に…」の漢詩を添えた画軸を制作、大当たりをとる。この話も、病で伏す唐の玄宗皇帝の夢に現われて小鬼を退治し、快癒させた鍾馗伝説と似ている。玄宗皇帝が夢で見た姿に似せて描かせた鍾馗像が魔除けとして好まれ、日本にも伝来、江戸時代には病魔除けとして版画が戸口に張り出され、軒先にも塑像が飾られた。
しかし、龍馬はまず自由民権運動家にかつがれたためか、武市半平太は故郷・高知市吹井に瑞山神社が建立されたのに、幸い神にされることはなく、いつまでも自由人でいられた。ニセ天狗の祈祷師を退治した逸話や、慶応二年のお龍との霧島山登山で天のさかほこに天狗の面が付けてあるのを笑い飛ばし、引き抜いてみるなど、少年期から合理的な思考で行動しており、神がかった戦争勝利予言は似合わない。
幼年時代の疑わしき伝聞
大正元年には『維新土佐勤王史』(冨山房)が瑞山会著述で刊行されるが、執筆を担当したのは坂崎紫瀾であった。平尾道雄はこの書を、坂崎特有の「文学的史書」と評している。ここでの龍馬少年の描写は、だいぶ平静を取りもどし、「彼の童時は物に臆して涕泣しやすく、故に群児の侮蔑を受くるも、あえてこれを怒らず」と述べ、後年兄・権平に出した手紙の「どうぞ昔の鼻垂れと御笑くだされまじく候」を紹介する。
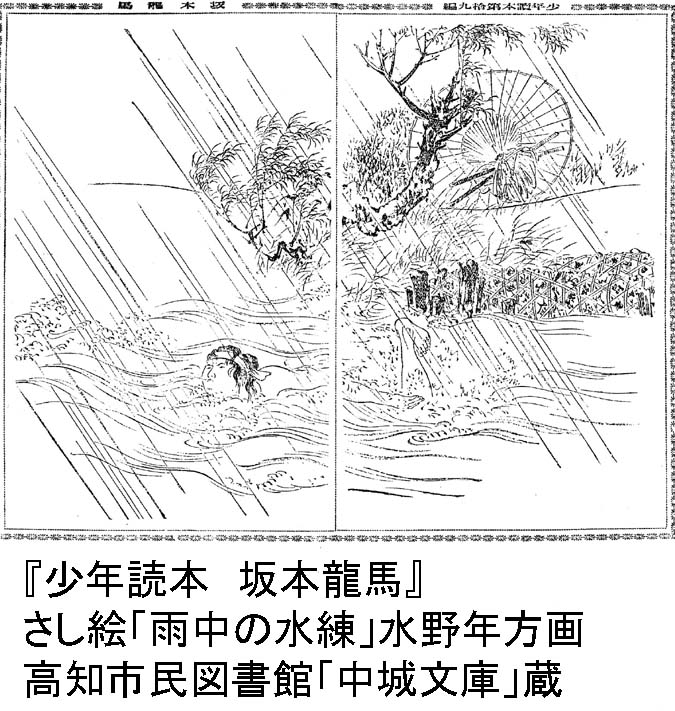 |
|---|
姉の乙女は龍馬の四歳(実は三歳)上で「女仁王」のあだなで呼ばれ、「短銃を好み、鷲尾山などの人なきところに上り…連発してその轟々たる反響にホホと打ち笑み」とか、「常に龍馬を励まして、これを奮励せしむる」と紹介してある。
これら『維新土佐勤王史』にある少年龍馬の逸話は、大正三年刊『坂本龍馬』(千頭清臣著 博文館)や、昭和二年刊『雋傑(しゅんけつ)坂本龍馬』(坂本中岡両先生銅像建設会 編集発行)でも、ほぼ同様だ。ただ千頭の本では二版増補で「疑わしき話」の項を設け、はな垂れと言われたことで龍馬を真の馬鹿というのは大きな間違いと記してある。千頭は高知出身の英文学者・貴族院議員として知られた存在だったが、実際の筆者は山内家史編修係・維新史家の田岡正枝であった。後者は、京都円山公園にある坂本・中岡像建設のための刊行で、銅像は昭和九年に完成したが第二次大戦で供出、昭和三七に再建された。
岩崎鏡川の史料収集と重松実男の見識
昭憲皇太后の夢に現われた龍馬は、日露戦争の勝利によって、自由民権の先駆者のみならず海軍の祖・皇国守護の英霊とされ、もてはやされるようになった。小説だけでなく、演劇や講談にも次々と取上げられた。これに対し、『汗血千里駒』以来の伝記と称する作品の内容を、「荒唐無稽の綺語でなければ、舌耕者流の延言」「正確な史料に憑拠(ひょうきょ)するものあるを見ない」と断じ、坂本龍馬の史料編纂に取り組だのが岩崎鏡川(英重)である。岩崎は山内家史編集係・維新史料編纂官を歴任、晩年は『坂本龍馬関係文書』編纂に心血をそそぎ、大正一五年五月に死亡したが、その一ヶ月後にまず私家版として刊行された。鏡川の次男が『オリンポスの果実』で知られる作家・田中英光である。
中城家の本家・中城直正(初代高知県立図書館長)は、大正期にこの岩崎と綿密に連絡をとって、維新の志士たちの史料収集と顕彰を中心に、県下の史料・史跡の収集保存や記念碑建立などに取り組んでいた。例えば大正三年一月から二月にかけて上京した際の日記には、維新史料編纂所の岩崎とともに土佐出身の田中光顕伯や土方久元伯、さらに東京帝大史料編纂所にいた帝大同期の歴史学者・黒板勝美などを訪問した記録が残っている。岩崎からの手紙もあり、内容は武市瑞山先生記念碑・同遺跡保存・堺事件殉難者合祀・紀貫之邸跡建碑、それに維新関連の贈位申請・文書購入などである。これらの手紙や日記は全て、高知市民図書館「中城文庫」に収まっている。
この『坂本龍馬関係文書』にも、龍馬の手紙の執筆年代などいくつかの誤りが後に指摘されたが、龍馬研究の画期的な史料集誕生であったことに間違いない。戯曲の傑作とされる真山青果『坂本龍馬』も、三里村出身の作家・田中貢太郎の『志士伝記』(改造社)も、この史料集刊行抜きには考えられないと、文芸評論家・尾崎秀樹氏は述べている。龍馬の史料発掘と編纂の仕事は岩崎亡き後も続き、郷土出身の研究者に受け継がれていく。その結実した刊行物が、平尾道雄著『海援隊始末記』『龍馬のすべて』・宮地佐一郎編『坂本龍馬全集』・山田一郎著『坂本龍馬―隠された肖像―』他・松岡司著『定本坂本龍馬伝』であり、坂本家ご一族の土居晴夫氏も綿密な考証によって『坂本龍馬の系譜』をまとめておられる。
これらの中で、少年龍馬の真実に最も迫っているのは、山田さんの著作である。そして、その先駆ともいうべき著述が、昭和一二年に重松実男編著で高知県教育会から刊行された『土佐を語る』の「坂本龍馬」であろう。あまり知られていない著述なので、少し長くなるが紹介しよう。
その出身 「坂本は天保六年に城下の本町筋一丁目の郷士の家に生まれた。幼少の頃遅鈍な劣等児であったように伝えられもするが、これは彼が後年兄権平への書翰に〈…どうぞ昔の鼻垂れとお笑い下されまじく候〉とある所などから誤り伝えられた話であろう。晩成の大器であったには相違ないが、遅鈍であったものとは思われぬ。…青年時代剣道の師日根野弁治が、大雨の中を水泳にでかける坂本に出会ってあやしむと、水へ入ったらどうせ濡れるから同じことだ。と答えた所も、一見間抜けたようで、その実中々才気煥発ではないか。」と書く。続けて十八、九歳で四万十川治水工事の監督を手伝い、精出す者に褒美を与えたことを、「すでに棟梁の器量をひらめかしておる」と評価する。さらに、「嘉永六年十九歳、剣道修業の志を立てて江戸へ上るとき、同行者の一行中坂本の姿が見えないので、見送り人が不審して集合所であった友人の宅へ立戻って見ると、彼は襖に貼った錦絵に見とれて〈たまるか義経の八艘跳じゃ〉などと太平楽をきめこんで、只今三百里外へ旅立つ者とも見えなかった」と紹介。当時の土佐から江戸は、今西洋へ旅するようなものなのに、坂本の「天衣無縫の大らかさがうかがわれる」と人柄にも触れている。
江戸への初めての旅立ちの際に、最初に立ち寄った家で襖(壁ともいう)に貼ってある浮世絵に見入った場面は、前出の弘松の本にも、仁井田出身の作家・田中貢太郎著『志士伝奇』の坂本龍馬にもある。慶応三年九月、最後の帰郷で種崎・中城家に潜伏した際に、やはり襖に貼られた浮世絵を眺めており、後に高知での芝居「汗血千里の駒」上演で、龍馬自身の浮世絵(役者絵)が制作されたことも含めて、不思議な縁を感じる。
その学問 「彼ははやくから剣道に専念したので、学問の素養の薄いのを悔い、帰国してからはよく読書した。海軍通の河田小龍という画家の啓発を受けて、将来の海上発展を夢みたのもその一、また折りにふれて和歌をも詠んだ。彼の詠草は、〈げにも世に 似つつもあるか 大井川 下す筏の はやき年月〉(他に二首掲載)などと、卒直武骨な個性の発露する中にも、自ら格調の整うた才気を見せている。漢籍では、老子を愛読したというから、なかなか世人が思ったように無学ではない」と述べている。さらに、読書法が変わっていて、『資治通鑑』を読ませると字音も句読も返り点もいい加減だが、「大意がわかればよいじゃないか」と笑っていたという。後年英語も学んだ。ある蘭学者によるオランダ政体論の講義中に、「それじゃ条理が立ちません」と指摘、蘭学者が誤りを詫びた話も紹介している。
航海術研究 「その後江戸へ下って勝海舟の門に入り、一心に航海術の研究を始めた。この動機は、彼と小千葉の倅の重太郎とが開国論者の海舟を斬るつもりで押しかけ、海舟に説得せられたことになっておるけれども、これは疑わしい。当時彼は海外の事情に盲目でもなく、海上雄飛の素志を抱いていた…」。ここでは、海舟を斬りに押しかけたとの伝説を否定し、神戸海軍塾での研鑽や、第二次長州戦争で「習得した海軍術を以て桜島丸を操縦し、幕鑑に砲火を浴びせかけてあやしまなかった」事例をあげ、高所の見識と評価する。
この重松の著書は、海援隊・薩長同盟・大政奉還・船中八策・遭難・逸話などの項目をたて、きちんと述べてある。学術書でないため、個々の出典を示してないのは残念だが、遅鈍ではなく、海舟を斬りに行った伝説は疑わしいと明記している。昭和初期の見識ある高知の知識人は、龍馬愚童説など信じていなかったのだ。
龍馬の手習いと寺子屋
龍馬は乙女姉さんへの親しみとユーモアあふれる手紙から、志士たちへの情報伝達、政治構想まで、さまざまな文書を書き残している。個性的な口語体の文章表現と、伸びやかな筆遣いでその想いが率直に伝わってくる。この筆力は、少年期に習得したものである。ここで、その学習歴を振り返ってみよう。主として高知県立坂本龍馬記念館の「龍馬略年表」による。〈 〉内は、筆者の追加事項である。
| 一八三五 | (天保六) | 一歳 十一月十五日、郷士・坂本長兵衛(八平)の次男として誕生 |
| 一八四六 | (弘化三) | 十二歳 六月母幸没。この年小高坂の楠山塾に入門、間もなく退塾 |
| 一八四七 | (弘化四) | 十三歳 〈この頃父八平が種崎川島家から伊与を後妻に迎える〉 |
| 一八四八 | (嘉永一) | 十四歳 城下築屋敷の日根野弁治道場に入門し剣術を学ぶ |
| 一八五三 | (嘉永六) | 十九歳 三月「小栗流和兵法事目録」を受ける。剣術修業のため江戸へ赴き、千葉定吉道場に入門。〈佐久間象山に入門、砲術の初学を学ぶ〉ペリー浦賀に来航。土佐藩臨時雇として品川海岸警護につく |
| 一八五四 | (嘉永七) | 二〇歳 六月江戸より帰国。この頃河田小龍に会い、将来を啓発される |
| (安政一) | ||
| 一八五五 | (安政二) | 二一歳 父八平没。〈九月十一月 徳弘孝蔵のもとで洋式砲術稽古〉 |
| 一八五六 | (安政三) | 二二歳 八月再び剣術砲術修業のため江戸へ向かう |
| 一八五八 | (安政五) | 二四歳 千葉定吉より「北辰一刀流長刀兵法目録」を受ける。九月帰国 |
| 一八五九 | (安政六) | 二五歳 砲術家徳弘孝蔵に入門し西洋砲術を学ぶ |
| 一八六一 | (文久一) | 二七歳 〈井口村で上士・下士の刃傷事件起こる〉土佐勤王党に加盟 |
| 一八六二 | (文久二) | 二八歳 萩の久坂玄瑞を訪ねる。三月脱藩し勝海舟の門下生となる |
江戸後期には全国で寺子屋が普及し、庶民の子弟も数えの七歳くらいから読み書き算盤を習うようになるが、武士や庄屋、裕福な町人の多くは手習いの手ほどきを家庭で行うのが習わしであった。自叙伝『蜑(あま)の焼く藻の記』を残した幕府御家人・森山孝盛は、十歳までの教育は母任せだったという。初めは家庭学習で、途中から寺子屋に行く者もいた。いずれにしろ十二歳前後になり手習いを終えると、家塾・私塾・藩校、あるいは剣道場などに入門する。寺子屋の師匠が医師や武士・僧侶・庄屋などの兼業であったのに対し、藩公認の儒官による家塾も、民間の私塾も、漢学者や国学者が自宅で開いた塾であった。
坂本家の人々は代々和歌を楽しんだとされ、なかでも龍馬の祖母久は土佐では知られた歌人・井上好春の娘であり、その家風は龍馬の父八平・母幸にも受け継がれたようだ。山田さんが『海援隊遺文』で紹介したように、仁井田・川島家に残る『六百番歌合』には当時種崎にあった川島家で開かれた歌会の巻があり、そこには種崎の川島春麿・杉本清陰・中城直守などと並んで坂本直足(八平)の名が見られる。このような教養豊かな家庭では、手習いの手ほどきは父母が行い、親が読み書きの得意でない家庭では最初から寺子屋に通わせていた。
土佐での事例は、下級武士で国学者の楠瀬大枝(一七七六~一八三五)が残した日記『燧袋(ひうちぶくろ)』に記されている。この日記を分析した太田素子(和光大学教授)は『江戸の親子』(中公新書)で娘の教育について、「大枝は菊猪や笑の手習いをやはり自分で手がけている。…菊猪の記録では手習いの開始と初勘定を続けて記録しているが、手習いの開始は菊猪七歳」、「下級武士の息子たちが手習いはともかく、素読から講釈へ進む段階には私塾に通っていた」と述べている。
江戸の家庭教育の事例は、幕末に蘭医桂川家に生まれた今泉みねの『名ごりの夢』(平凡社東洋文庫)にある。「私の生まれた家では、…手習いでもしているのを見つかると、御じい様が桂川のうちに手習いや歌を習う馬鹿がどこにあるか…そんなことは習わなくてもできるもんだ」、「いきなり思ったことを歌によんで、それを書くのが手習いでした。いろはを習わせると言うよりも、それを最初から使わせて思うように書かせる。つまり、生活がそのまま教育ですね」と、語っている。
桂川家は極端な例だが、寺子屋でも家庭でも手習いは基本的に個人別自学自習であり、学びは学(まね)びから始った。多くが、まず「いろは」と数字を師匠・親が自ら書いた手本を真似て学び、次に往来物と呼ばれる木版摺りの教科書を使っての手習いへと進む。往来物の内容は、人名漢字、国名尽し、消息往来、さらに商売往来、風月往来などで、文字・単語・短文を習得し、日常生活の用語・知識・手紙文、そして職業知識や和歌風流へと続くカリキュラムがあった。
寺子屋の学習法と机の配置
学習法は、新しいお手本に進むたびに師匠から読み書きの指導を受けるが、あとはひたすら手習いの反復練習である。そして、一人ずつ師匠の前に出てチェックを受け、読み書きともきちんと出来れば新しい教材に進む。何十人生徒(寺子)がいても、学習内容は進度に応じて一人ひとり違っていた。往来物は七千種類以上あり、『土佐往来』といった地方版も出版されていた。和歌では『百人一首往来』『七夕和歌集』等があった。
家族で和歌を楽しんだ坂本家では、実母幸も継母伊与もそして三歳上の姉乙女も当然手習い指導の力を持っていた。中城直正の手稿『桃圃雑纂』にも「母幸ハ温厚貞節、ヨク八平ニ仕ヘ、子女ヲ教育セシガ」とある。龍馬には、病弱な母に代ってもっぱら乙女が指導、『古今和歌集』も教えたとされる。慶応元年九月の乙女・おやべに宛てた龍馬の手紙からは、『新葉和歌集』にも親しんでいたことがうかがえる。
このような手習いを終えると、十二歳くらいから私塾や家塾で、さらに四書五経・史記・唐詩選・資治通鑑などの漢籍とも取り組み、専門的知識を持った師匠の元で儒学や漢詩・国学を身につける。また、武士は武術にも励むことになる。
龍馬にとっては、寺子屋や私塾に行かずに、家庭で母幸や姉乙女からのびのびと自学自習で読み書き算盤、さらには歌の道を学んだことが、その後の人間形成にかえって役立ったように思われる。漢籍はさほど必要としなかったのだ。成人してからの手紙文や和歌から判断しても、読み書きの基礎学力はきちんと身につけていたし、砲術・航海術を学ぶために必要な数学力、例えば大砲の角度・火薬量から弾道と距離を計算する力も備えていた。英語にも挑戦している。
それにしても、近年の寺子屋描写はひどすぎる。NHK「龍馬伝」でも第一回に寺子屋と私塾(岡本寧浦)の場面が登場したが、どちらも今の学校同様に教師と生徒が向き合う形で机が並べられていた。寺子屋では一斉授業を行わないので、生徒たちは入門の際に持参した机を自由に並べて学習した。師匠に向って整然と並べることはあり得ない。このことは、金沢大学(日本教育史)の江森一郎教授が『「勉強」時代の幕あけ』(平凡社)で、江戸時代の寺子屋絵図を列挙して論じておられる。
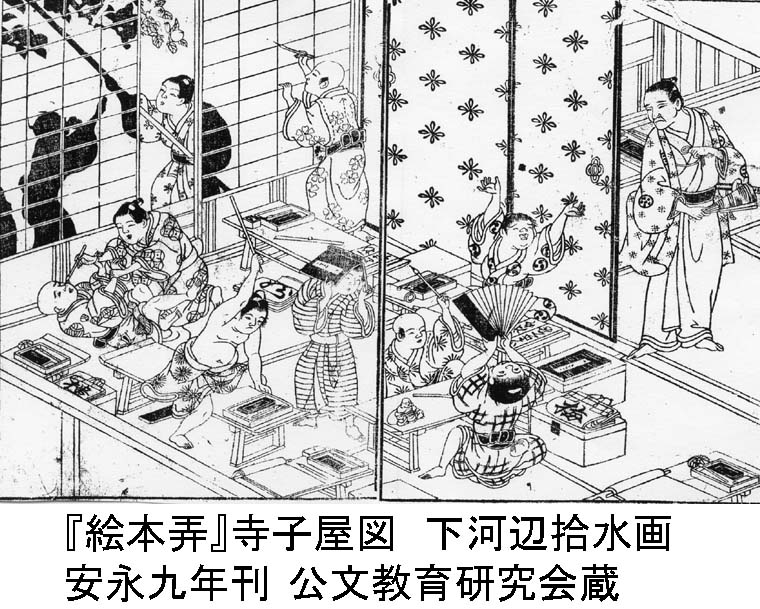 |
 |
|---|
ところが高知でも、六年ほど前に高知城の丸の内緑地で開かれていた江戸時代の城下町展示を見学に行くと、寺子屋のセットがあり、やはり全て前向きに机を並べてあった。本町の「龍馬の生まれたまち記念館」にも寄ったが、ここに置いてあった寺子屋場面の絵も同じだった。双方の係りには間違いを指摘しておいた。さすがに山形県立教育博物館の寺子屋展示は、江戸時代の天神机から落書きだらけの雨戸まで本物を揃えており、並べ方もコの字型できちんと考証がされていた。平成一三年に京都国際会議場で開かれた「ユネスコ世界寺子屋会議」の展示企画を担当し、浮世絵寺子屋図とともに山形の実物をお借りして展示したが、海外の参加者から大変好評であった。なお、寺子屋で使う質素な机を、学問の神様・菅原道真にちなんで天神机と呼んだ。
日本では明治五年の学制以降、ヨーロッパの小学校の一斉授業を取り入れたが、この授業法は十九世紀になってからイギリスの牧師が、植民地でのキリスト教普及のため考案したものである。二人の牧師の名前をとって、ベル・ランカスター・メソッドと呼ばれるが、少ない教師が効率よく大勢を指導するために助手を使い、同一教材で一斉授業を行った。
この教授方法を、産業革命と列強による戦乱の時代を迎え、労働者や兵士の手っ取り早い養成に迫られた欧米各国が、小学校に採用したのである。貴族たちは相変わらず家庭教師の個人指導を受けていた。平成一六年にドイツ城郭協会会長のザイン侯爵をその居城に訪ねたが、ハプスブルク家出身の城主夫人が述べた言葉「小学校には行かず家庭教師が来てくれました。両親からは家の誇りを忘れず、将来どこに住んでも土地の社会に貢献することを心がけるようにと教えられました」が、印象に残っている。夫人は城の隣で、自ら「チョウの生態博物館」を運営しておられた。
和歌と砲術が結ぶ三里と坂本家
さきに上げたように種崎の御船倉御用商人・川島春麿は楠瀬大枝に国学・和歌を学び、近所の杉本清陰や中城直守だけでなく、城下に住む龍馬の父坂本八平などとも歌人仲間であった。おそらく川島家と坂本家は廻漕業と商家として、業務上の繋がりも深かったと思われる。中城家も、大廻御船頭として土佐から江戸への藩船を操船、藩士やさまざまな物産を運んでいた。この三者は当然、仕事・和歌の双方で親しい仲だった。
三里にはこの時代の歌人に坂本春樹などもおり、和歌のサロンが出来ていたように思われる。そして、川島家の記録にあるように、坂本八平など城下の和歌仲間とも交流していた。『万葉集古義』で知られる国学者・鹿持雅澄も妻菊が仁井田郷吹井の出であり、仁井田・種崎をたびたび訪ねてこれら歌人と歌を贈りあっている。
中城直守は、この土佐の歌人仲間と江戸の歌人とを結ぶ役割もしていたようで、手稿『随筆』には国学者・齊藤彦麿を訪ねて教えを乞い歌を交わしたとある。藩船を運航して江戸に行っては歌人を訪ね、土佐への土産はもっぱら交換・購入した短冊と浮世絵だったと我が家には伝わっている。直守所蔵の短冊は三百人を越す歌人に及び、本居宣長・村田春海・野村望東尼から地元の谷真潮・中岡慎太郎に至る。
このような交流の中で、坂本八平は川島家をしばしば訪ねて早くから伊与を知っており、「思われびと」だったのではないかと山田さんは推測している。いずれにしろ、二人の結婚によって龍馬少年も乙女姉さんとともに川島家をよく訪問したと伝わっており、和歌にも浮世絵にも親しんだのではなかろうか。そして、城下本町の自宅から小舟をこいで鏡川を下り、浦戸湾を種崎に向かうなかで、行き交う藩船や荷船への興味と、海の彼方へのあこがれが芽生えたと思われる。川島家では、村人から「ヨーロッパ」と呼ばれるほど西洋事情に詳しかった春麿から万国地図なども見せられ、胸をときめかした事であろう。
和歌に続いて坂本家と三里を結ぶものに砲術がある。土佐藩では仁井田の浜を公設砲術稽古場としていたが、砲術指南に当たった一人が、徳弘孝蔵(董斎)で、『近世土佐の群像(4)鉄砲術の系譜』(渋谷雅之著)によると天保十二年(一八四一)に一三代藩主山内豊煕の命で下曽根金三郎に入門し、高島流砲術(西洋砲術)の免許皆伝を得ている。徳弘は下士で御持筒役に過ぎなかったが、上士の中には洋式砲術を嫌って藩命拒否の人物もいたなかで、いち早く西洋砲術を習得したのである。
龍馬の父八平は、和式砲術の時代から徳弘孝蔵に入門していたが、龍馬の兄・権平も安政三年(一八五六)に奥義を授けられた記録が残っている。いっぽう龍馬は、従来安政六年徳弘孝蔵に入門とされてきたが、山田さんは『海援隊遺文』で「龍馬、鉄砲修行」の項を立て、詳細な調査から「安政二年洋式砲術稽古、同三年正式入門」とし、安政六年は免許に近い奥許しと見ている。続けて龍馬の成長過程を「嘉永六年十二月一日、十九歳で江戸で佐久間象山に入門、砲術の初学を受け、安政元年六月、二十歳で帰国、河田小龍に航海通商策を説かれ、翌二年十一月、二十一歳、徳弘董斎のもとで砲術稽古…」と、述べている。これに対し、十九歳で高名な佐久間象山にいきなり入門は無理で、それ以前から土佐で砲術の初歩は学んでいたであろうとの説もある。
安政元年、河田小龍に会ったのは小龍が筒奉行池田歓蔵に随行して薩摩に赴き、大砲鋳造技術の視察から帰ったばかりであった。龍馬は江戸でペリーの黒船を見て帰国したところであり、大砲の威力も、外国の軍艦を迎えて攘夷の困難なことも、さらに外国船を購入しての旅客・物資の運輸とそのための人材育成の必要性も、よく理解できた。
龍馬は嘉永六年に江戸修行に出かける二年ほど前から、父や兄に連れられ、仁井田の砲術稽古を見学していたのではないだろうか。そしてその往復には小舟を使い、継母が住んでいた川島家にも寄り、江戸や長崎の新しい情報を聞き、更に川島家の幼い姉妹(喜久と田鶴)や中城直守の長男亀太郎少年(直楯)とも遊んだであろう。
坂本家は商家から郷士に転じただけに、古来の武士が剣術や槍術にこだわって銃砲術を蔑視したのに対し、早くから兵器としての威力を認め、その習得に取り組んできた。伝統的な和歌を好む反面、実利的合理的判断の出来る家庭で文明の利器にも敏感であった。この気質は、種崎・仁井田で古くから海運・造船に従事してきた人々とも共通するところが多かった。
このような風土から有名な龍馬のエピソード、「太刀→短刀→ピストル→万国公法」が生まれた。時代の変化に即応した所持品の更新であり、思考の更新である。実践でも龍馬は寺田屋でピストルを使って捕手の襲撃を防ぎ、第二次長州戦争では桜島丸に乗船して幕府軍への砲撃を指揮、慶応三年の帰郷では新鋭のエンフィールド銃千挺を土佐藩にもたらしている。
龍馬は、和歌で文章表現力とともに王朝人の雅や気概を、砲術で国内統一と欧米列強への軍事的対応策を、身に付けたのだ。
龍馬最後の帰郷と土佐のお龍
慶応三年の龍馬最後の帰郷と三里の人々、そして土佐に来たお龍の姿に簡単に触れておこう。九月二三日に蒸気船震天丸で浦戸湾に入った龍馬は、袙(あこめ)の袂石(たもといし)に停泊させ、小舟で種崎・中の桟橋に上陸すると、裏の竹やぶをくぐって中城家にはいった。当日は仁井田神社の神事(じんじ)で、人の出入りが多い表門は避けたのだ。中城家では、直守が御軍艦奉行による旧格切り替えに御船方仲間を糾合して反対したため、格禄を召し上げられ、長男直楯(亀太郎)に家を継がせたところであった。
城下の実家に直接入らなかったのは、土佐藩の政策が勤王か佐幕か明確になっておらず、持ち帰った最新式の銃千挺を土佐藩が倒幕に備えて受け入れるかどうか不安があったからだ。頼りの後藤象二郎は上京中であった。そこで、藩の方針が決まるまでは馴染みの多い種崎に潜伏した。川島家は、安政地震の津波で被害を受け、仁井田に転居していた。
中城家では直楯が龍馬一行を「離れ」に案内し、妻の早苗が世話をした。滞在中の様子は、直楯の長男直正が後に両親から聞き出し、覚書『随聞随録』に記載してある。これも山田さんはじめ多くの研究者が引用している。
龍馬はこの際に、川島家の屋敷跡にあった小島家も訪問している。小島家には少年時代に可愛がった川島家の妹娘・田鶴が嫁入っていたのだ。この家で、折良く来ていた土居楠五郎(日根野道場で指導を受けた師範代)とその孫・木岡一とも会っている。後に木岡が述べた回想が、『村のことども』(昭和七年 三里尋常高等小学校刊)にあり、土産にもらったギヤマンの図まで掲載してある。円形の鏡でPARISの文字を月桂樹の小枝が囲んでいる。このわずか二ヶ月足らず後に龍馬は不帰の人となっただけに、忘れ得ぬ思い出になったであろう。
龍馬の妻お龍も夫の亡き後、その遺言に従って妹起美を海援隊幹部・菅野覚兵衛(千屋寅之助)と長崎で結婚させ、明治元年春には土佐の坂本家にはいる。しかし、権平とうまくいかなかったのか、夏には和喰村(現芸西村和食)に帰っていた菅野夫妻の実家・千屋に身を寄せる。ここでお龍に可愛がってもらったのが十一歳ごろだった仲(覚兵衛の兄富之助の長女)で、中城直顕(直守の三男、私の祖父)の後妻に来てからその思い出を高知新聞記者に語っている。
そこには、龍馬遺愛の短銃でスズメを撃って遊び、人に見せたくないと龍馬からの手紙をすっかり焼き捨てたことから、お龍さんへの「あんな良い人はまたとない」という回想まである。日付は昭和一六年五月二五日で、記者は私の母冨美の弟岡林亀であった。この記事は、中城家から『坂本龍馬全集』にも提供した。菅野のアメリカ留学によって、明治二年お龍は土佐を去るが、別れに際し仲への記念に龍馬から贈られた帯留を譲っている。龍を刻んだ愛刀の目貫止めと下げ緒で作ってあり、中城家の娘の嫁ぎ先に代々受け継がれている。
最後に、『汗血千里駒』の冒頭で扱われた井口村刃傷事件と龍馬の関係に触れておこう。多くの研究者はこの事件に龍馬は参加していないとしてきた。山田さんは、寺田寅彦の父寺田利正が事件の当時者である下士・宇賀喜久馬(十九歳)の兄であり、寺田家には喜久馬切腹の介錯をしたのは利正で、上士二人を斬った池田虎之進と宇賀の切腹で収拾を図ったのは龍馬だったとの話が、密かに伝えられてきた事を明らかにしている。切腹は、武士としての面目が立つ自死であった。龍馬が関与したとの説は、元高知県立図書館長・川村源七がかつて唱えており、山田さんがそれを立証している。
坂崎が『汗血千里駒』を執筆した明治一六年には、城下を揺るがせたこの大事件の関係者も数多く生存しており、冒頭に持ってきたのは龍馬関与に自信があったからであろう。明治二○年高知座でのこの作品の上演でも、井口村刃傷事件が中心であり、大好評であった。坂崎の龍馬本の虚実と、政治小説としての正当な評価は今後も追及すべき課題である。
おわりに
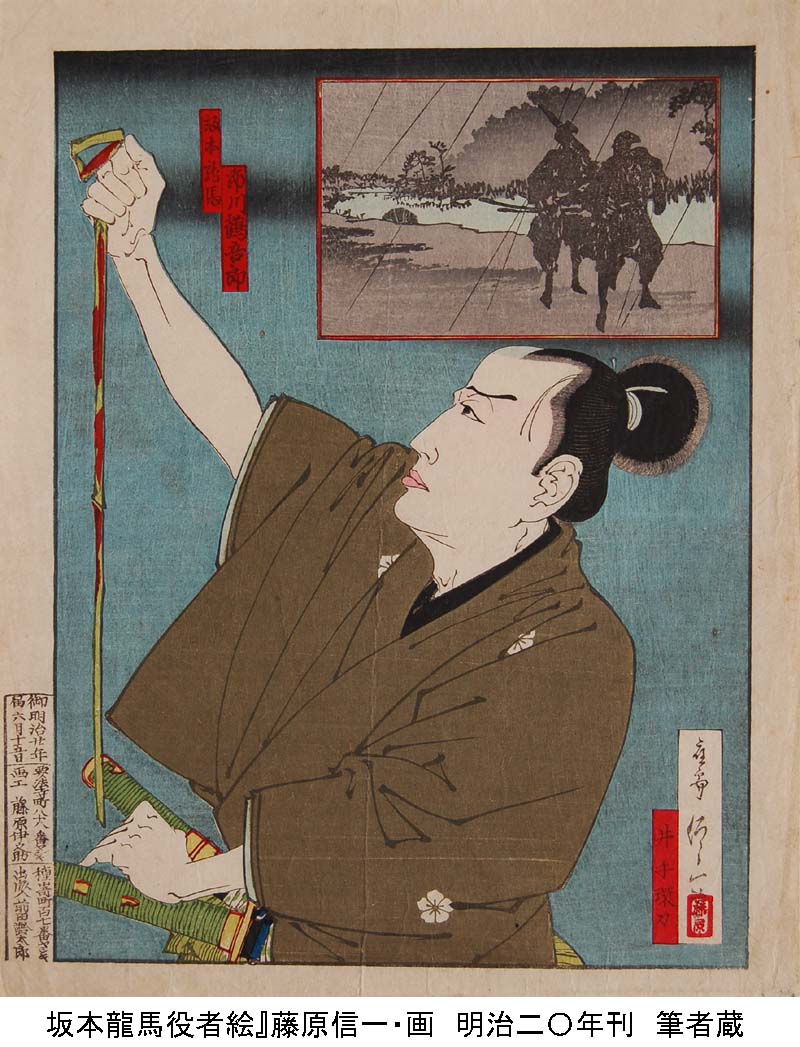 |
|---|
代わりに川島春麿や河田小龍、江戸では佐久間象山や勝海舟など、当時の最新の情報と学識を持つ人々に接していった。また、種崎・仁井田の御船倉や砲術稽古の現場も訪ね、江戸では黒船警護の品川台場にも動員された。このような現場での見学や体験の積み重ねが、神戸での海軍操練所開設や長崎での亀山社中・海援隊結成で、花咲くことになる。
なかでも青少年時代に、御船倉の周辺で見た活発な船の行き来や種崎・仁井田の沖に広がる太平洋の大海原は、大きな影響を与えたと思われる。船は江戸・上方はもとより、長崎・下関・薩摩などから、様々な物産と情報をもたらしてきた。情報の一端は中城直守が文政から明治期まで記した『随筆』でも知ることができる。龍馬は、長崎とも取引をしていた川島春麿からの異国情報を、目を輝かせて聞いたのであろう。
寺子屋にはほとんど行かなくても、豊かな生活環境のなかで自学自習を行い、自ら学ぶ喜びに目覚めていったのである。後に愚童と呼ばれた「龍馬の学び」にこそ、教科書中心の一斉授業とテストに明け暮れる現代の教育病理を克服する鍵があるようだ。(註 引用文は現代用語に変えてある)
(本稿は『大平山』第三八号 平成二四年三月 三里史談会刊よりの転載である) 今こんなことをしています
『江戸時代子ども遊び大事典』と中国版画展の反響
中城正堯(30回) 2014.05.31
 筆者近影 |
|---|
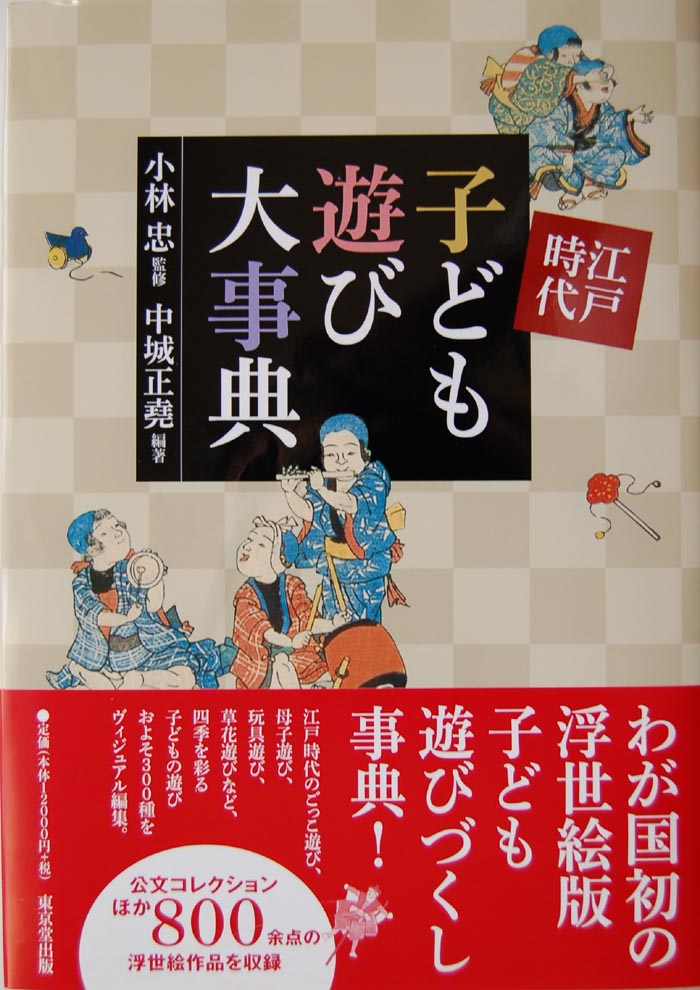 子ども遊び大事典 |
|---|
 神奈川新聞5月13日 |
 高知新聞5月24日 |
|---|
中城正堯(30回) 2014.12.01
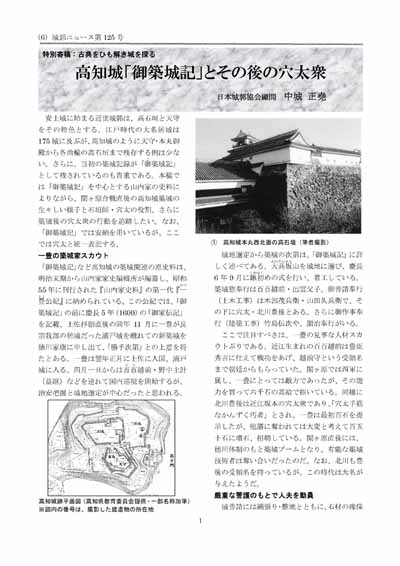 この画像をクリックすると PDFファイル(紙面)が開きます |
|---|
もう一つはNHKの番組紹介で、このホームページがきっかけで、協力することになった番組 です。以下の文章をお願いします。放送までの短期間ですので、メンバーへのメールでも結 構です。
<お知らせ>
NHKに公文公先生の師弟関係が登場!
NHK総合テレビ12月19日夜10時放映の「ファミリーヒストリー山本寛斎」に、公文公先生(7回 生・公文式教育の創始者)と、山本寛斎氏の父・山本一男さんの師弟関係が紹介されます。 そのきっかけは向陽プレスクラブのホームページです。私が書いた「海辺から龍馬の実像を 発掘」の中で、海南中学で師弟関係にあったお二人の、東京での50年後の再会を紹介しまし た。山本さんは、公文先生が阪大を卒業した昭和11年、最初に赴任した海南での最初の教 え子の一人です。
これがNHK取材班の目にとまり、土佐高経由で筆者への取材依頼があり、協力致しました。 画面にはわずかしか出ないと思いますが、KPCホームページの情報発信力と、NHKの丹念 な情報収集に改めて驚かされました。山本家の家族関係も、驚きの連続です。
 番組案内はがき 提供:NHK |
|---|
中城正堯(30回) 2015.05.21
皆様へ
 筆者近影 |
|---|
萩原さんは、昨年亡くなった竹邑類さん(35回生)が若き日に立ち上げた劇団ザ・スーパー・カムパ二イの看板俳優で、招待いただいてよく舞台を楽しみました。
竹邑さんは、ミュージカルなど舞台芸術の改革者でしたが、昨年『呵呵大将 我が友、三島由紀夫』を置き土産に、旅立ちました。才能あふれる芸術家であり、自由人でした。
堀内弁護士はじめ、みなさまの活躍を願っています。
先月の総会は、滋賀県立近代美術館での講演と重なり失礼しました。体力が衰え、浮世絵関連のおしゃべりも今月末の「東洋思想・・・」研究会での発表を最後に辞め、お迎えに備えての身辺整理に専念します。今日が七十代最後の誕生日です。 龍馬最後の帰郷と種崎潜伏
中城正堯(30回) 2015.05.28
 筆者近影 |
|---|
車輪船沖遠く来たり
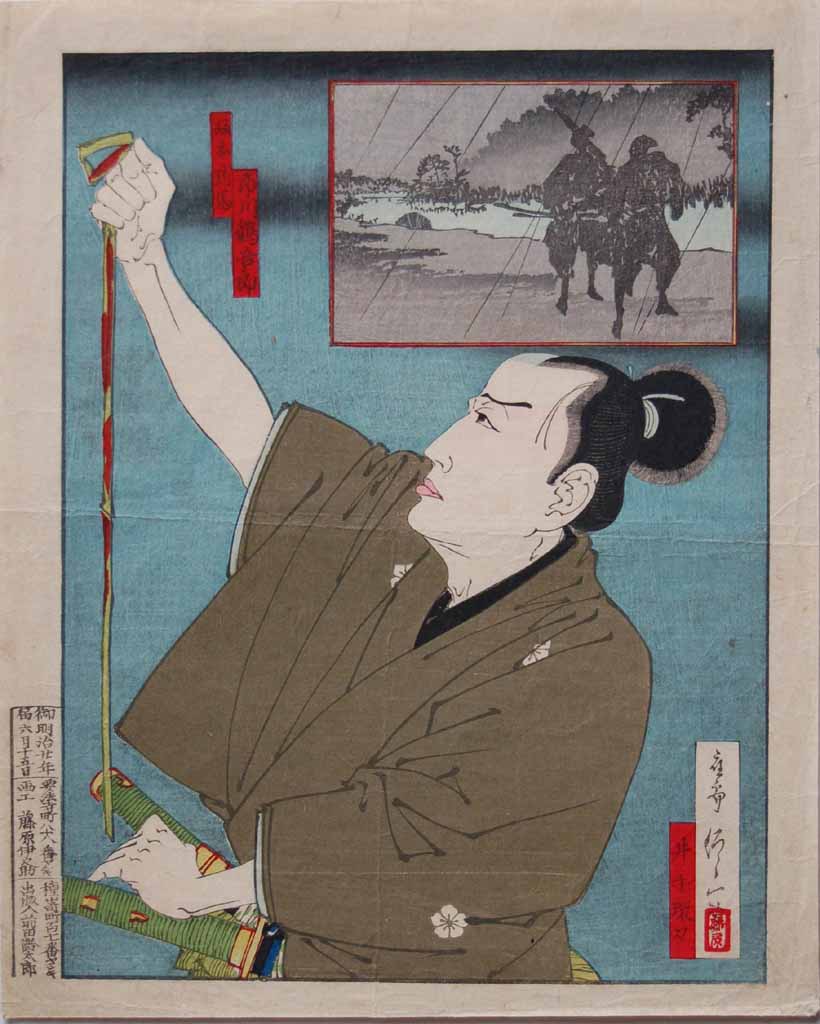 「龍馬役者絵」藤原信一画 明治二○年 |
|---|
直守は四年前の文久三年に、御軍艦奉行の旧格切り替えによる江戸雇いの車輪船乗員と旧来の御船手方のあまりの待遇格差に反発、種崎の松原に同志を糾合、先頭に立って連判状をつくり、反対運動を展開した。このために格禄を召上げられたが、慶応元年に長男・直楯による大廻御船頭継承が許された。隠居ながら、早朝には沖(太平洋)を見に家を出る習慣だったようで、舷側の車輪を回して走る蒸気船を発見したのだ。船が港外にいったん投錨後、浦戸湾に入って種崎の対岸にある御畳瀬の袙に碇泊するまでを見届けている。山田一郎は当日の月齢を調べ、港外で投錨したのは満潮を待つためであり、二五日としてある震天丸の来航は実は二三日であったと『坂本龍馬―隠された肖像―』で述べている。なお大廻御船頭とは、土佐から江戸へ直行する五百石ほどの帆走藩船の船長格であり、大坂までの小廻御船頭と区別していた。ともに下級武士・下士である。
直守の『随筆』には、震天丸発見当時の様子に続けて、「才谷梅次郎・中島作太郎・小沢庄次等三人、使者の趣をもって上陸、夜に入り梅次郎(空白)二人吸江の亭に行く、渡辺弥久馬と対談あるの由なるを、弥久馬故ありて来ず、金子平十郎来たれる由也、すこぶる皇国に関係するところの大儀なる趣のよし、梅次郎は実は坂本龍馬なり。今この人、皇国周旋の事件に付きすこぶる名誉ありて海内の英雄ととなう」とある。『随筆』には数日間の出来事をいちいち日を追わずに記載してあり、この部分も龍馬たちの入港当日の動きだけではない。文中人物の中島は海援隊士、小沢は三条実美の家臣・戸田雅楽、渡辺は土佐藩仕置役、金子は山内容堂側用役であった。
最も注目すべきは、「皇国周旋の事件」に触れていることだ。これは、慶応三年六月に「夕顔」船上で龍馬が後藤象二郎に説いてまとめ、長岡謙吉に執筆させた大政奉還の建議で、後に「船中八策」と呼ばれる。後藤はこれを山内容堂に示し、同意を得た上で九月一日から京に上っていた。「土佐藩政録」には、「九月、山内豊信(藩主)天下の形勢日にせまるを見て、後藤象二郎をして上京せしめ、書を幕府に上り、土地兵馬の大権を朝廷に奉還し、王政を復古し、ひろく衆議を採り、富国強兵の鴻基(天皇の大事業の基礎)を建て、万国と信義を以て交際を結ばんことを請う」とある。九月に入り、薩長は大政奉還を幕府が拒んだ場合にそなえて兵を上京させ、武力蜂起の準備をしていた。土佐藩にも建白書提出にとどまらず、武装強化・兵員上京という武力行使の準備を促すための帰国であった。
才谷は色黒、満面よみあざ
直守は全く触れていないが、龍馬が帰郷したこの日、中城家には龍馬から震天丸に迎えに来て欲しいとの知らせが届いたようで、直楯は小舟をこぎ寄せ、密かに龍馬一行を中城家に案内していた。その記録は、直楯の長男・中城直正(初代高知県立図書館長)が、残した『随聞随録』(明治四○年筆記)にある。母・早苗からの聞書である。
「坂本龍馬 才谷梅太郎。母二二の時、直正出生の前年来宅(母妊娠五ヶ月の時)、一絃琴を玩べり。坂本は権平の弟にして郷士御用人、本丁に住す。才谷は色黒、満面よみあざ(そばかす)あり。惣髪にて羽二重紋付羽織袴。[白き絽なる縞の小倉袴]梨地大小(打刀と脇差)、髪うすく、柔和の姿なり」。続いて小沢・中島などの姿・容貌にも触れ、「氏神神事の日(旧九月二三日)に来宅。旧浴室にて入浴。いずれも言語少なし」とある。
「当時坂本は小銃を芸州藩の船に積込み、佐々木(高行)に面会のために土佐へ来たれり。本船は(袙にある)袂石のところに着く。父上(直楯)、その朝召に応じて出で行かれしが、能勢作太郎(後・楠左衛門、平田為七の甥)と共に一行を案内して薮の方より宅に導きしなり」。
これが聞き書きの前半である。氏神とあるのは、仁井田神社(高知市仁井田)であり、神事とはその秋祭りの日であった。「その朝召に応じて」とあるが、だれから呼ばれたのかは記載がない。おそらく、才谷(坂本)からと記した依頼状が届いたのであろう。では、なぜ直楯が呼ばれ、またすぐ迎えに向かったのだろう。それは安政地震まで中城家の六、七軒東にあった御船倉御用商人・川島家と、坂本家との繋がりによると山田一郎は述べている。
この三家(坂本・川島・中城)の当主は和歌で結ばれており、川島に残る『六百番歌合』には、種崎の歌人として知られる杉本清陰・川島春麿(春満・通称猪三郎)、そして中城直守とともに、龍馬の父・坂本直足(郷士)の名が記されている。坂本家と川島家は歌で結ばれていただけでなく、妻を亡くした八平の後添いに、やはり川島家に嫁入りしたが未亡人になっていた北代伊与が迎えられた。龍馬十二歳の時である。「故に龍馬は幼時その姉(おとめ)とともに、たびたび川島家に遊びたり」と、『村のことども』で川島家の親戚・木岡一は語っている。直楯は龍馬より六歳下であるが、川島家の子どもたちとともに、龍馬に遊んでもらった仲と思われる。
今回の龍馬帰郷は、後藤象二郎の斡旋で二月に脱藩罪が許され、四月には土佐海援隊長に任命された後とはいえ、藩内には反勤王・反後藤の根強い勢力もあった。ライフル銃千挺を運んで、幕府が大政奉還に応じない場合は土佐藩に決起するよう奮起をうながすのは、危険な交渉であった。しかも同志・後藤は京におり、まずは城下から離れた種崎に潜伏、使いを出して打診せざるを得なかった。本来なら身を隠すには川島家に頼るところだが、安政元年の大地震で種崎は津波の被害を受け、川島家は安全な仁井田へ移転していた。そこで、幼なじみの直楯を頼ったのであろう。この時、直楯は二五歳、前年に村内の医師・浜田井作(収吾)の娘・早苗と結婚したばかりであった。井作は直守の実弟だが浜田に婿養子で迎えられた身で、直楯・早苗はいとこ同士の結婚であった。
土藩論を奮起せしめんと帰国
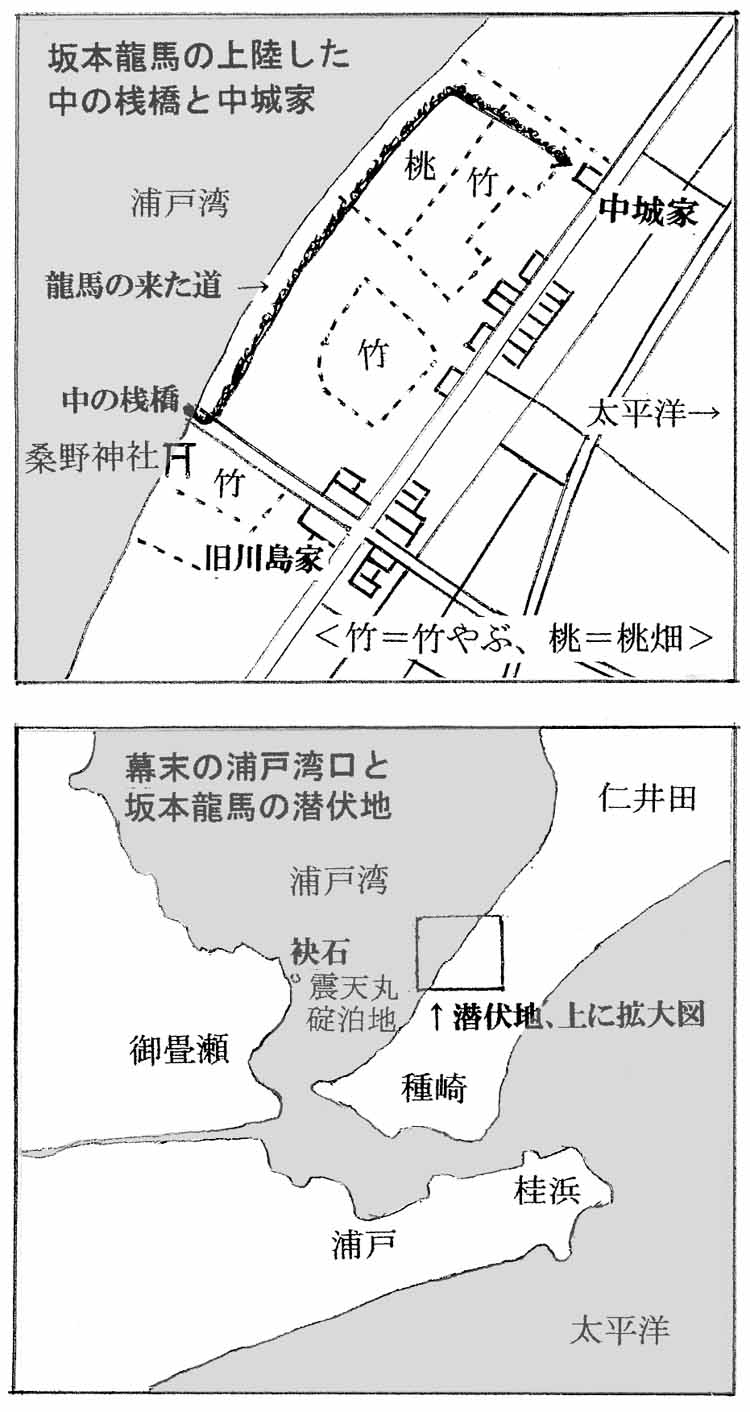 |
|---|
「父上先に入り、坂本、中島が、まだ湯は沸いておるかと云いしに、皆入浴せし後なりしが再び沸かせり。坂本は、(当時、時勢切迫の時期を気遣い)土藩論を奮起せしめんとて帰国せしなり。祖父(直守)に叔父(直顕)のブッサキ羽織を着せたり。 宴会の席にて御歩行・松原長次、しきりにしゃべりおりたり。一同茶の間にて食事、小沢は自ら井戸をくむ。中島は津野へ、坂本は小島へ寄り、舟へ帰るとて宅を出たり。小沢の宿は紺屋広次方なり。浜田祖父(医師・早苗の父)診察す。
二、三日間、母は湯の加減等をなせり。坂本氏より鏡をもらいしと云う。坂本は入浴後、裏の部屋に休息 [雑踏を避けしなるべし]、襖の張付けを見居りたり。母火鉢をもち行しに〈誠に図らずも御世話になります〉といえり」。
この聞書からは、当初言葉も少なかった一行が、入浴後の食事の席では、幾分くつろぐ様子がうかがえる。ただ饒舌な松原に対し、寡黙だった龍馬の姿には内に秘めた決意の重さが感じられる。山田一郎は、「早苗はこの年二二歳で、妊娠五ヶ月、直正をみごもっていたが、その記憶力はすばらしい。彼女は龍馬をはじめ全員の風貌、服装まで鮮やかに再現して語っている。特に龍馬の言葉やものごしまで、これほどリアルに伝えている文章を読んだことがない」と観察眼を評価している。早苗にとって、天下の国事に奔走する龍馬の姿には、強く惹かれるものが感じられたのであろう。 直楯は、神事(神祭)で来客の多い表座敷は避け、裏の離れに案内している。
 龍馬が潜伏した中城家離れの座敷 筆者撮影 |
|---|
中城家では表座敷を避けただけでなく、かなり用心した様子が、直守にブッサキ羽織を着せたことで読み取れる。打裂羽織とは、帯刀に便利なように背縫いの下半分を縫い合わせていない武士の羽織である。「時勢切迫・土藩論を奮起」の文面には、大政奉還建議をひかえ、武装蜂起の決断がいまだ出来ない土佐藩への、龍馬の苛立ちが読み取れる。 聞書に「坂本は小島へ寄り、舟へ帰るとて宅を出たり」とある。当時、中の桟橋の川島家屋敷跡に住んでいた小島家の様子は『村のことども』にあり、九歳だった木岡一の談話として記されている。「外祖父・土居楠五郎氏(日根野氏門における龍馬の兄弟子)とともに、種崎神祭小島氏宅へ行きしに夕刻突然龍馬来たりしなり、・・・その夜土居氏との対面実に劇的シーンなりしも、少年一は偉丈夫なんぞ涙するや、と思いしという。・・・少年一がギヤマンの鏡を土産としてもらいしは、この夜なり」。
当時の小島家当主・亀次郎は山内容堂の秘書役をしており、妻の千蘇は川島家の出、嫡男・玄吉の妻・田鶴もまた川島家から迎えていた。田鶴は、幼い頃から龍馬を慕っていたとされるが、この時は結婚して二年目、まだ十九歳であった。二人の再会の様子は伝わっていない。また、亀次郎の妹・直は、医師・今井幸純と結婚、その子が龍馬の秘書役を務めた海援隊士・長岡謙吉(今井純正)であった。(小島家については、田鶴の曾孫・小島八千代さんから平成十四年にいただいた「小島家系図」による。)
湯かげんや小舟こぎで支えた夫妻
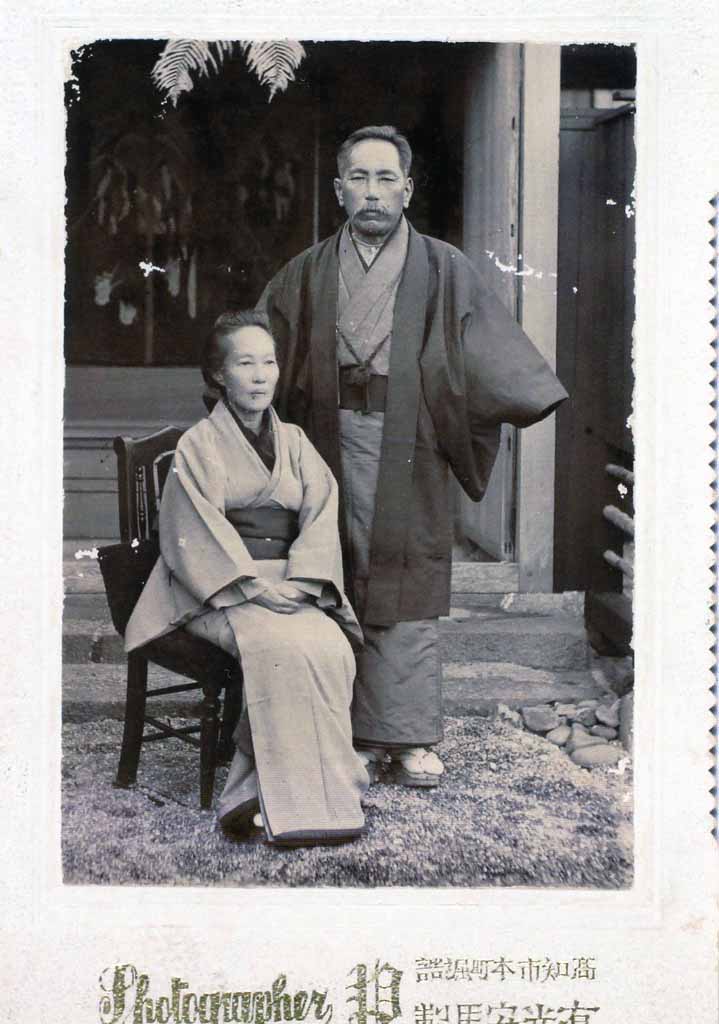 龍馬潜伏を助けた中城直楯・早苗夫妻 |
|---|
こうして龍馬は種崎から小舟で使者を出し、土佐藩の首脳と交渉、数度にわたる会見の末、ついに二七日の土佐藩評定によって、大政奉還の確認と武力討伐に備えてのライフル銃千挺の買い上げが決定した。『随聞随録』に、「二、三日間、母は湯の加減等をなせり」とあり、中城家には二、三回来たようだ。土佐藩との交渉は初めは吸江(五台山)や松の鼻(常盤町)の茶店で隠密に行われたが、やがて城下の役宅に席を移す。この間、袙の震天丸・種崎の中城家・吸江や松の鼻、さらに高知城下の土佐藩役宅を結ぶのは、浦戸湾と江の口川・鏡川などの河川であり、御船頭の中城直楯とその配下が小舟をあやつり、上げ潮・引き潮の流れを読みながら、巧にこぎ渡ったと思われる。 龍馬は念願の交渉をまとめ、本町の坂本家にも帰って家族と再会したが、十月一日には慌ただしく震天丸で大坂をめざして浦戸を出港する。中城直守の『随筆』には、「朔日朝、右艦(震天丸)浦戸を出つ」とあり、種崎の浜では、中城直守たちが見送ったことであろう。荒天のなか室戸沖まで進んだが、荒れ狂う波浪に翻弄されて船体を破損、いったん須崎に避難、五日土佐藩差し回しの蒸汽船胡蝶で再度出港する。
龍馬は十月九日に京都に到着、その四日後の十三日に徳川慶喜が二条城で大政奉還を表明する。この日、建白書受諾の知らせが届く以前に龍馬が後藤象二郎に出した手紙には、「建白の儀、万一行われざれば、もとより必死の御覚悟ゆえ、(先生が二条城から)御下城無の時は、海援隊一手を以て、大樹(将軍が御所へ)参内の道路に待ち受け、社稷(国家)のため不(倶)載天の讐を報じ、事の正否に論なく先生に地下に御面会仕り候」とある。建白書が受諾されない場合は、「後藤は二条城で切腹するだろうから、自分は海援隊を率いて御所参内の将軍に報復、あの世で会おう」と、決死の覚悟を記したものだ。
ところが大政奉還受諾のこの日、朝廷は薩長に倒幕の密勅を下す。徳川慶喜の決断に感激したとされる龍馬は、密勅など知らぬまま十一月二日には福井に三岡八郎(由利公正)をたずね、国の財政策を授かる。新政府の実現に懸命に働くが、十五日に京都近江屋で中岡慎太郎と面談中、刺客に襲われ横死する。 中城直守には十一月末に知らせが届く。『随筆』に「坂本龍馬、先だって御国に来たり。密かに周旋の意趣あり候後、京師に登り旅宿に居るある夜、国元より書状来たれりとて旅宿をたたく者あり。この宿の召使いの者、出てすなわち書状を受取り来たり龍馬に渡す。龍馬何心もなく披見するところに、外より忽然として五、六人入り来たるや否や抜打ちに一同無二無三に切付ける。無刀にてあしらう内、深手処々に負いて死す。・・・この来る者は関東よりの業にして、さるべき壮勇の浪士を雇いてかく切害せしとも、いずれ確かならず。今、海内に名を轟かし、殊に御国のため力を尽くせし龍馬なる者を、ああ惜しむべし惜しむべし。なお詳しき事聞きたし」と記し、慨嘆している。 直楯の『随筆』には、吉村虎太郎たち天誅組の大和での壊滅、武市半平太の獄死などについては、無念の思いは秘めて淡々と記録してあるが、龍馬殺害の知らせにだけは、「ああ惜しむべし惜しむべし」と、心情を率直に吐露している。
大政奉還へ!龍馬奮戦の足跡
龍馬最後の帰郷は、大政奉還による近代日本誕生への最後の布石のためであった。幕府への土佐藩からの建白書提出には、拒否されないよう薩長とともに武装蜂起も辞さない軍事態勢の誇示も必要だった。これは単なる土佐藩びいきの提案ではなく、薩長のみでの倒幕への暴走を防ぎ、王政復古をとなえつつ、平和裏に近代国家建設を成し遂げるための妙案でもあった。
「日本を今一度せんたくいたし申し候・・・」(文久三年)と考えた龍馬が、その最後の施策として、土佐藩による大政奉還を迫った舞台が、少年時代から慣れ親しんだ浦戸湾であり、種崎であった。その現状を簡単に報告して稿を終えたい。
種崎の太平洋に面した海岸は、今に松林が広がり千松公園となっているが、黒船に備えて造られた台場(砲台)のあとは砂に埋もれて消えた。龍馬の乗った震天丸が通った湾口には、浦戸大橋がかかり、桂浜と結ばれている。種崎の先端は、昭和四一年からの航路拡張工事で切り取られ、御畳瀬の名勝・狭島も除去された。しかし、震天丸が碇泊した袙の海岸は幕末の風情を今にとどめており、袂石も健在である。
袂石から龍馬たちが小舟で渡って上陸した中の桟橋は、昭和三十年代からの自動車の発達によって役割を終え、地名のみ残った。龍馬が歩いた湾岸の景観も、中洲の埋め立て、竹やぶ・桃畑・空き地の宅地化などによって、すっかり変貌した。わずかに龍馬が潜伏した中城家の離れのみは、老朽化したが残っており、平成二二年のNHK大河ドラマ『龍馬伝』でも、「龍馬伝紀行」の中で紹介された。龍馬がその志の実現に向けて、決死の行動をとった土佐での最後の舞台であり、三里史談会有志の協力もいただいて保存に努めている。
龍馬潜伏にかかわった中城直楯は、その後陸軍築城掛となり、和歌を楽しみつつ東京・広島・新潟などで勤務し、明治二二年陸軍歩兵大尉で退任、明治二七年に種崎に帰郷する。長男直正に母・早苗が龍馬潜伏の状況を語ったのは同四○年、写真はその頃の夫妻である。
主要参考文献
『中城文庫 目録・索引編』『中城文庫 図版・解説編』高知市教育委員会 二○○二、二○○三年刊
『村のことども』三里尋常高等小学校編・発行 一九三二年刊
『坂本龍馬関係文書一、二』北泉社 一九九六年刊
『坂本龍馬―隠された肖像―』山田一郎著 新潮社 一九八七年刊 校歌の謎1への回答
中城正堯(30回) 2015.08.15
公文敏雄様、皆様
 筆者近影 |
|---|
謎1,の「向陽」の由来のみ、小生の理解するところをお知らせ致します。
「向陽」の出典は、中国古代の漢詩です。諸橋轍次『大漢和辞典』(大修館)に よると、<向陽 陽に向かう。日に向かう。潘岳(247~300 西晋の文学者)の 「閑居賦」、謝霊運(385~433 六朝時代 宋の詩人)の「山居賦」・・・>等の詩 に使われた用例をあげてあります。
土佐中では、校歌より先に「向陽会」(自治修養会)に使われており、これは三根 校長の命名かと思われます。三根校長が東京帝国大学哲学科在学中の哲学教 授は井上哲次郎でドイツ観念論哲学のみならず、漢学・東洋哲学にも精通していました。
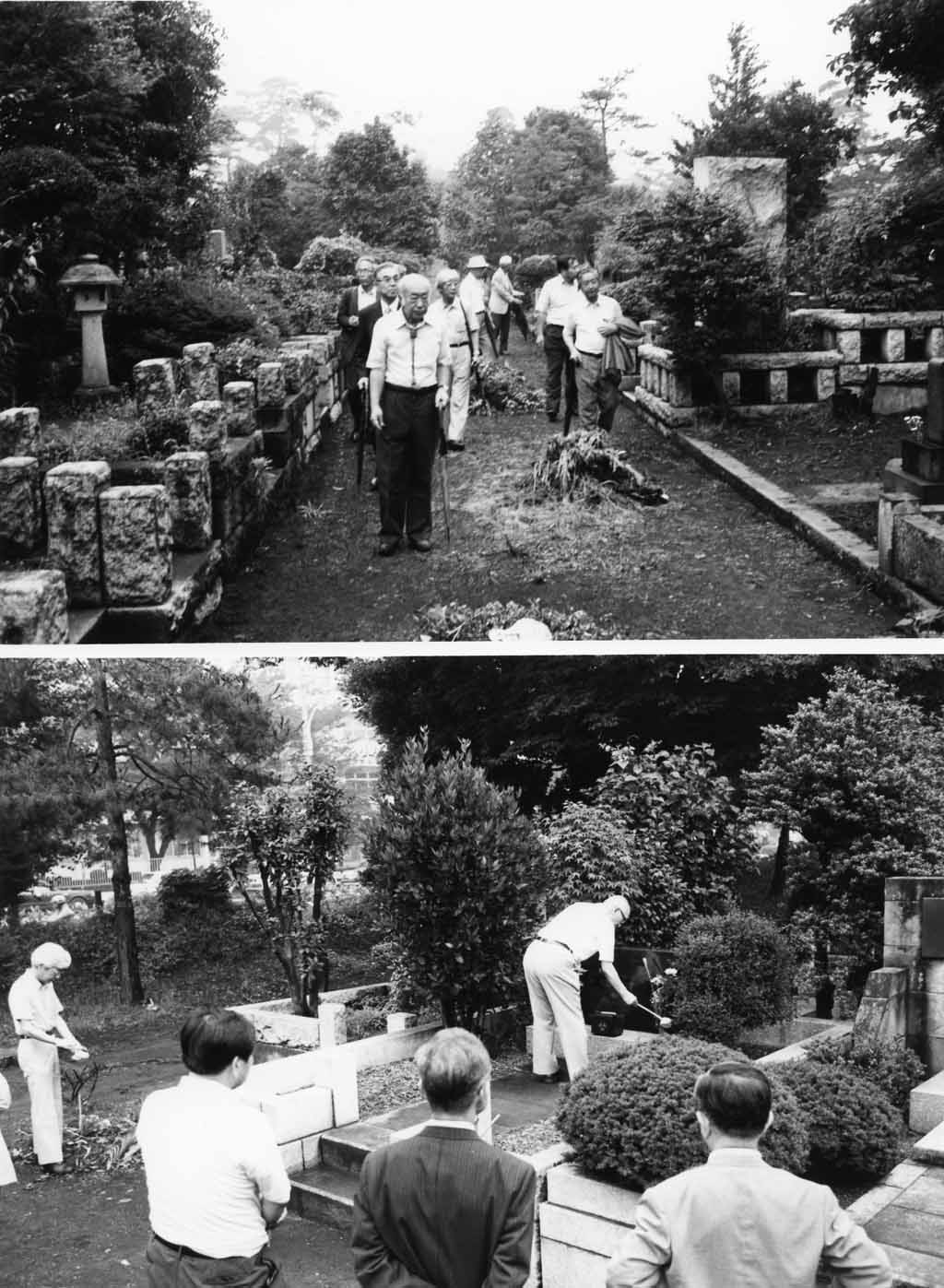 1990年頃の筆山会による「三根校長墓参会」 |
|---|
その他の謎についても調べたいところですが、土佐中関連の文献・資料はすべて 土佐校図書室と公文公教育研究所に寄贈し、手元にありません。これらに手掛か りがあるかどうかも不明です。是まで収集した資料は、順次寄贈先を選んで進呈 しています。満州版画は京大人文研が大変喜んでくれました。
公文さんの質問に対して、まず調査担当すべきは土佐校の同窓会担当者かと思 います。三浦先生の後任は、だれでしょうか。母校100年史編纂も進んでいること でもあり、母校の体制を確認下さい。
なお、「向陽高校」は和歌山・京都などいくつかあるようですが、いずれも戦後の 学校統合などで生まれた校名のようです。三根校長には、自治会にいい名称を 付けていただいたと思います。 <合田佐和子さんの思い出>
20世紀美術の先端を駆け抜けたアーティスト
中城正堯(30回) 2016.02.28
 筆者近影 |
|---|
土佐高新聞部の仲間として、また同時代の編集者として見てきた、20世紀美術界での彼女の先鋭的なアーティストとしての活躍ぶりが、脳裏に刻まれている。かつて書いた戯文に、本人および関係芸術家の文章なども引用し、しばし追憶に浸りたい。
<新聞部の仲間から> 美術界の異才、合田佐和子/中城正堯『一つの流れ』第8号 1985年刊
 新聞部の千松公園キャンプ、前列左端が合田さん。1956年 |
|---|
今年正月には銅版画集『銀幕』(美術出版社)を刊行した。手彩オリジナル版画入りの豪華本は、定価30万円である。その出版記念会には、根津甚八、四谷シモン、江波杏子、白石かずこなど、異色の東京ヤクザがかけつけていた。合田はエジプトが気に入り、安い家を買ったとかで、これからは日本と半々でくらすと、いたずらっぽい表情でいっていた。
(これは、土佐高30回Kホームのクラス誌に「東京ヤクザ交友録」として、同窓生の活躍ぶりをカタギとヤクザに分けて紹介した戯文で、芸術家は当然ヤクザとして扱った。)
<合田さんご本人の回想>
『パンドラ』序文/合田佐和子作品集 PARUKO出版 1983年
 「合田佐和子 影像」掲載ポートレート(松濤美術館) |
|---|
油彩 ニューヨークの裏通りで一枚の写真を拾った。二人の老婆と一人の老人が写っている小さな銀板写真だった。アレ、これはすでに二次元ではないか、これをそのままキャンバスに写しかえれば問題は、一方的に一時的に解決する。(立体オブジェにこだわり、立体を平面に写す油彩を躊躇していた合田は、拾った写真にインスピレーションを得て独創的なスター肖像画を生み出す。美大で商業デザイン科だった合田は、油絵の実技教育を受けておらず、独学で修得したと述べている。)
エジプト 1978年秋の個展作品を、肩から包帯をつるした腕で仕上げると、息もたえだえ子供二人を連れて半ばやけ気味でエジプトへ発った。(彼女はアスワンの村でくらし、「全部の病気を砂に返し、暖かいぬくもりだけを全身に吸い込んで東京に戻る」と、古代エジプトの守護神ホルスに惹かれたのか、目玉をモチーフに立体も平面も制作、『眼玉のハーレム』(PARUKO出版)を刊行する。後に中上健次の朝日新聞連載「軽蔑」では、毎回眼だけの挿絵を描いた。)
<仲間の賛辞>
恋のミイラ/唐十郎 合田佐和子個展カタログ 1975年
これらは、初めて仮面舞踏会につれてこられた少女の、ほのかなためらいと頬の紅潮を画布に移行させたものだろうか。・・・これらはドリームにドリームを塗りつぶした暗い恋のタブローである。こんな絵に囲まれながら、そこで、誰かと誰かの恋が結ばれたらどうしよう。
ぼくらのマドンナ/『銀幕』出版記念会案内状/四谷シモン 1985年
当代きっての才媛、ぼくらのマドンナ、佐和子が、突如、この夏の猛暑のさなか、銅版画の制作にのめりこみ、レンブラント、デューラーもものかは、銅と腐蝕液の異臭のなかから電光石火の早技で「月光写真」の如き「銀幕のスターたち」を誕生させました。・・・ぼくらのマドンナを囲み、歓談に花を咲かせたいと思います。
焼け跡に舞い降りた死の使者/坂東眞砂子(51回)『合田佐和子』高知県立美術館 2001年
八十年代に入り、合田佐和子は初期の焼け跡を連想させるオブジェと、人骨を組み合わせた作品を創りはじめる。ここにおいて、敗戦、焼け跡と、死が作品上で、明白に重ねあわされていく。・・・合田佐和子が描いてきた銀幕スターたちとは、戦後の日本に死をもたらした、死の使者たちだったのだ。彼らは大鎌の代わりに、セックス・アピールという武器を手にして、日本社会に乗りこんできた。その青ざめた皮膚の下にあるのは、骨。銀幕スターのきらめきの下に隠されているのは、骸骨であったのだ。
 作品集・展覧会図録・著書など |
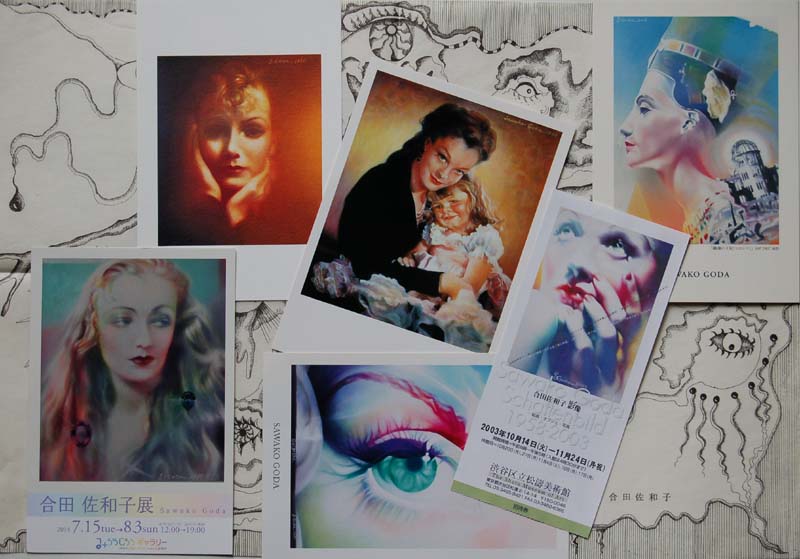 絵はがきなど |
|---|
合田さんと思いがけず出会ったのは、1992年2月小松空港行きの機中であった。前の席に座った男女が楽しげにはしゃいでいる。ベルト着用のサインが消え、身を乗り出してみると、二人の若い男性助手を連れた合田さんだった。聞けば翌日から金沢のMROホールで公開制作をするという。仕事の合間をぬって会場に駆けつけると、詰めかけたファンに囲まれ、あざやかな筆さばきで大キャンバスに銀幕のスターを描いていた。
2001年の高知県立美術館「森村泰昌と合田佐和子」展、2003年の東京・渋谷区立松濤美術館「合田佐和子 影像」展でも、オープニングで元気な姿を見せていた。しかし、近年の鎌倉や日本橋の個展会場では、本人と会うことができなかった。5年ほど前に電話で近況を尋ねると、心臓の病をかかえ、思うように制作ができないといいながら、わたしの病気を気遣って、類似の病気を克服した友人・栗本慎一郎(経済人類学者)の治療法を薦めてくれた。
彼女は様々な病気を抱えながら、絶えず新しいテーマと技法にチャレンジし、現代アートの世界で先鋭的な作品を発表し続けてきた。その鋭利な感性に肉体がついて行けず、悲鳴を上げていたのであろう。高知県立美術館での合田展に寄稿をしてくれていた作家・坂東眞砂子さん(51回)に続いての合田さん訃報であり、土佐高で学んだ異能の女流芸術家が相次いで亡くなった。ご冥福をお祈りしたい。
<追記>いずれ「お別れの会」を開く予定で、「天井桟敷」関係者が準備中とのこと。
(作品自体は著作権者の了解が必要なので、印刷物からの画像引用の範囲にした) 『新聞とネット、主役交代が鮮明に』への感想
中城正堯(30回) 2016.04.16
公文敏雄様
最近の「新聞報道」へのご意見、報道のあり方を真剣に考えているようで、感心しました。小生の感想をお伝えします。
 筆者近影 |
|---|
新聞報道のあり方、1.経営理念としての「公正な報道」、2.報道商品の品質 「報道の正確さ」・・・、これらよりも大切なことは、「真実の追及」ではないでしょ うか。「なにが公正か」は立場によって異なり、新聞報道は公正より「真実」を 大事にすべきです。真実の追及なら、反体制も反権力も関係ありません。また 新聞が、体制にどんな姿勢をとるか、各社に違いがあって当然です。
ただ、ミスリードのあった場合は率直に読者に謝る必要があります。かつて事実 に反し、民主党のひどい提灯持ちをした評論家が、今もテレビでしゃべっている のを見るとがっかりです。新聞社も記者も、そして政治家も「けじめ」が必要です。 山尾さんも、タクシーカードについて、真実を明らかにする必要があり、報道 機関には、保育問題の実態と共に、この追及も必要です。
マスコミは、新聞もテレビも花形職業になりすぎ、高学力か有力なコネがないと 入社できず、「真実の追及・報道」に命をかける人材が社内に少なくなりました。 今では活字の世界では週刊誌、それも外注のフリーランス記者の執念によって 特ダネが生まれている実情です。あとは、活字媒体でないネットの世界の活性化 がたよりです。
なお、公文の優秀児とは、在籍学年より先に進んで教材を解く力を付けた生徒で、 山尾さんは小学6年で高校程度に進み、トップグループにいました。同時に、中学 ではミュージカル「アニー」の主役も務め、東大法学部に進みました。
吉川さんはじめ、マスコミ関係者のご意見もお聞きしたいです。 2016年(平成28年)8月22日(月曜日)一高知新聞『所感雑感』
浦戸城趾に"元親やぐら"を
中城正堯(30回) 2016.08.25
 筆者近影 |
|---|
かつて山内一豊の入国と高知城築城にともない、浦戸城の三重天守は三の丸の櫓となり、石垣はすべて運び出されたとされていた。しかし、山内家「御城築記」に「苦しからざる所はこわし取り」とあるとおり、本丸周辺の石垣はかなり残してあったことが、1991年からの浦戸城址発掘調査で判明した。当時の高知新聞には、「南北総延長約百mにわたる石垣群を発見」とある。石垣は裏込石を使った高石垣であり、瓦や鯱などの出土品もあつて、浦戸城が四国で最も早く「土の城」から脱皮し、天守と高石垣を備えた先駆的「石の城」であつたことを示していた。
 浦戸城本丸址からの眺望 |
|---|
そして、早急に着手して欲しいのは、本丸跡への"元親やぐら"の建造である。元親にとって浦戸城は、初陣で長浜城に続いて勝ち取った思い出深い城であり、周辺の地形も熟知していた。後に浦戸湾口を本拠地にしたのは、秀吉による朝鮮出兵だけでなく、国内交易にも、堺や薩摩にならっての南蛮貿易にも、造船・海運・水軍が不可欠と考えたからだ。この雄大な構想を育んだのは、城山からの360度の大眺望であろう。南には大空と大海原が果てしなく広がり、北には浦戸湾の彼方に四国山脈がそびえ立つ。
 樹林におおわれた天守台址 |
|---|
桂浜の魅力は箱庭的海浜ではなく、城山に立って初めて味わえる自然と歴史が織りなす壮大な景観美だ。だが今に残る天守台は、樹林に覆われて展望がきかない。そこで、天守台の隣接地に、丸太組みで浦戸城三重天守と同じ高さの望楼"元親やぐら"を建てることを提案したい。中世から土佐の特産品であった材木を、伝統の技で組み上げ、元親と同じ目線で絶景を楽しみ、潮風や海鳴りを五感で味わって感性を呼び起こし、自らの生き方に思いを馳せる思索の場とするのだ。
(財団法人日本城郭協会顧問)
 高知新聞『所感雑感』 |
|---|
新聞に掲載後、早速地元の方々から電話をいただきました。その中で気になるのは、従来通りの観光開発がすでに二つも立案されていることです。それは、県立坂本龍馬記念館の新館増設と、高知市による「道の駅」新設で、ともに自然環境・史跡への保護がどれだけ配慮されているか疑問です。今回の原稿が、桂浜および浦戸湾口の自然と史跡の保護活用に役立つ事を願っています。 「公文禎子先生お別れ会」のご報告
中城正堯(30回) 2016.09.23
 弔辞を述べる武市功君 |
|---|
禎子夫人の高知での新婚生活は、昭和20年からの1年と、22年からの5年間であったが、その間のエピソードを紹介し、加えて同級生(土佐高30回Oホーム)へのお別れ会報告文を添付する。
高知での公文禎子様
奈良で生まれ育った長井禎子様が、お見合いで公文先生と結婚されたのは、終戦間近の昭和20年3月で、先生は浦戸海軍航空隊教授であった。慣れない高知での新婚生活は、父と兄を亡くして一家の柱となっていた公文先生以外は女ばかりの家族との同居であった。しかも、先生は池(高知市)の航空隊に別居で、訪ねて行こうとしては道に迷って大変だったという。さらに7月には米軍の空襲にあい、たまたま帰省中だった先生と雨のように降りそそぐ焼夷弾の下を逃げまどい、衣笠(公文先生の母の実家・稲生)をめざした。住んでいた家は全焼であった。恐怖にさらされ、一首のうたもつくれなかったと述べている。
 沖縄竹富島でのご夫妻(1990年11月) |
|---|
公文夫妻が大阪に出た同年に、安部局長も奈良局長に転任、そのお薦めで前川佐美雄先生が主宰する日本歌人社に入会、うたに励まれ昭和44年には日本歌人賞を受賞する。以来、パリやシルクロードを訪ねてはうたを詠み、平成10年には歌集『パステルカラー』を出版された。
禎子夫人は、短歌以外に美術への造詣も深く、自ら油絵もお描きになった。また読書家で、我々は土佐中時代にご夫妻が所蔵されていた『岩波文庫』などによって、本の世界に導いていただいた。秀才として知られた公文俊平・竹内靖雄両先輩も「公文文庫」を大いに活用しておられた。
3Oホームの皆様へ
 ご挨拶される新庄真帆子様 |
|---|
公文式の生徒は、現在世界各国428万人に及ぶが、禎子夫人は公文教育研究会の創始者・公文公先生のご夫人にとどまらず、公文式教室の最初の指導者であり、教材開発・教室運営にともにたずさわってこられた。昭和42年から10年間は公文教育研究会の前身である大阪数学研究会社長、さらに「のびてゆく幼稚園」開園、公文会長亡き後は50回を越える講座を全国で開催し、公文の教育理念を伝えきた。「公文禎子先生 お別れの会」は、公文教育研究会の関係者のみに限定されたが、全国から元指導者・社員、現役指導者・社員あわせて500人を越える方々が集い、献花をしてお別れを惜しんだ。
花祭壇の御遺影に向かって、元社員代表として武市功君(元副社長)が、弔辞を述べた。「禎子様に最初にお目にかかったのは今から67年前、高知市内の御自宅でした。土佐中学で教え子だった私は、数学を習うため御自宅にお邪魔していました。」という出会いから、会社を設立したものの十年余は赤字で、「主人と二人で荷車を引いて参りました。主人が引いて私が押して、やっと坂を上がって参りました」という禎子夫人の回想談をまじえ、追悼した。
最後に、ご親族を代表してお嬢様の新庄真帆子様のご挨拶があった。強く印象に残っているのは、初期のご苦労「父の教材がご近所でも評判になり、母が指導者になって教室を開いた。私たち幼い三人の子どもを育てながらであり、買い物や食事の準備もそこそこに、一人ひとりにちょうどの教材を用意するのは大変だった。なにしろ当時は教材も全て手書きだったから」、であった。
新庄真帆子様には、3O一同これまでの公文先生ご夫妻の御恩が忘れられないことをお伝えした。2000年の大阪同窓会の際に久武慶蔵君が公文公記念館で倒れたが、奥様の看病のお陰で大事に至らなかった事や、「うきぐも」発刊へのご協力に感謝していることを申上げた。また、今後一周忌の墓参など、教え子も参加出来る法事があれば、クラス代表が参列したいとの希望をお伝えした。真帆子様からは、高野(野口)さんか小生に連絡するとのお返事をいただいた。
帰りの新幹線で、公文先生亡き後に禎子夫人がはにかんだ表情で漏らされた、若きお二人のいわばデート時代の思い出話が甦った。「奈良での見合いで婚約が決まりました。私は阪大工学部の研究室に勤務していましたが、ときおり夕方に公文が訪ねて来て、私が出て来るのを、外でじっと待ってくれていました」。 ―平井康三郎、ディック・ミネ、ケーベル博士をめぐって―
三根圓次郎校長とチャイコフスキー
中城正堯(30回) 2017.03.25
はじめに:クラシックを愛した教育者・三根
 筆者近影 |
|---|
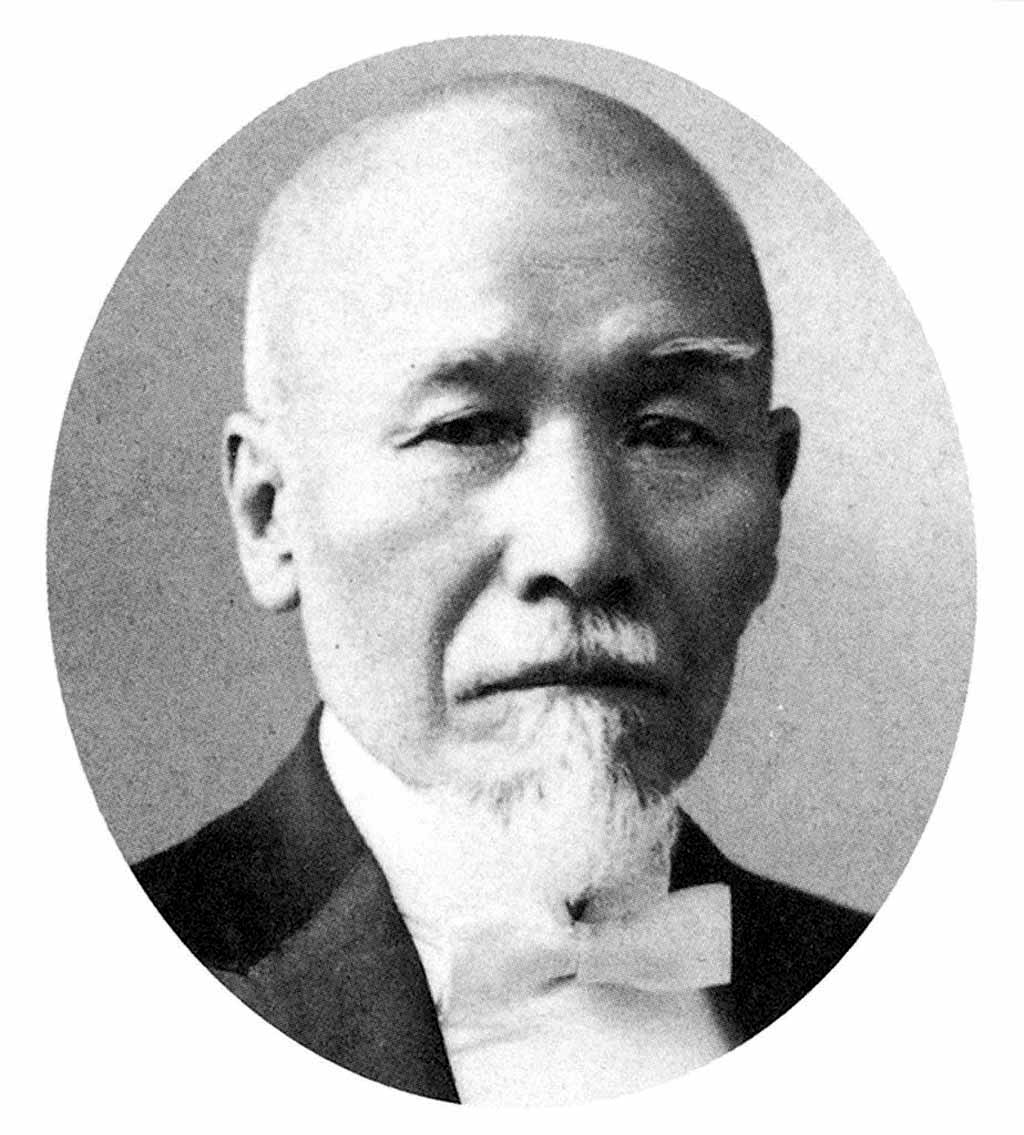 三根圓次郎(土佐中高校提供) |
|---|
土佐中創立は、第一次世界大戦後の国際化と大正デモクラシーの時代を迎え、国家の期待する新しい「人材育成」を目指すものであった。教育方針には「個人指導」「自学自習」など、時代の先端をゆく斬新な理念が掲げられていた。この理念に基づくカリキュラムの編成や授業展開は、すでに『土佐中學を創った人々』で紹介したので、ここでは割愛する。ただ、創立100周年を迎えるに当たって強調したいのは、「人材育成」「自学自習」などの基本方針も、予科(小学5,6年生)からの英国人講師による英語教育も、時代を先取りしており、グローバル時代を迎えた1世紀後の今日でも、誇りを持って掲げることができる点だ。
 チャイコフスキー (『ミリオーネ全世界事典』) |
|---|
土佐中初期の卒業生による50周年の座談会で、こんなやりとりが紹介されている。<浜田麟一(6回生)「弁論会をやろうというと、校長はこの学校としては音楽をやろうといった。これはディック・ミネが音楽をやることになったので、自分も関心が音楽の方へ傾いて行ったのでしょうか」。伊野部重一郎(5回生)「校長はクラシックがかなり分かったので、息子が流行歌をやるのをなげいていたのでしょう」。鍋島友亀(3回生)「平井はハーモニカのバンドを作って、公会堂で土佐中公開演奏会をやった。配属将校(軍事教練のために配置された陸軍将校)がなぜ音楽をやるかと問うと、校長は生徒が将来政治家になった時、演説をするために声をきたえるのだと言ったという」>(『創立五十周年記念誌』)
伊野部の発言で、三根校長がクラシック音楽を好んでいたことがうかがえる。なかでもチャイコフスキーに惹かれていたように思われる。それはなぜか、三根校長の周辺に多い、素晴らしい音楽家の探訪からさぐりたい。まずは、平井康三郎(5回生)に代表される教え子たちであり、ついでご子息のディック・ミネである。それぞれ昭和期を代表する作曲家であり流行歌手であったが、今では知る人が少なくなった。この二人の音楽家としての歩みと三根校長の影響、そしてさかのぼって三根が帝大哲学科時代にケーベル教授から受けた哲学・美学の教えをさぐってみたい。この教授は、実はモスクワ音楽院でピアノを修得した名演奏家でもあった。
目 次
mok1<第一章>“作曲家平井康三郎”生みの親
mok2<第二章>歌う社長や歌う文部次官も誕生
mok3<第三章>息子ディック・ミネはトップ歌手
mok4<第四章>哲学と音楽を育んだケーベル博士
<第一章>“作曲家平井康三郎”生みの親
土佐中のピアノやマンドリンにびっくり
 平井康三郎 (平井家提供) |
|---|
 いの町庁舎・平井康三郎記念ギャラリー(森木光司撮影) |
|---|
「グランドピアノはあるし、マンドリン・クラブはあるし、びっくりしました。レコードもベートーベンの第九をはじめ、名曲がたくさんある。蓄音機もビクターの最高級品です。ただ、残念ながらピアノを弾ける先生も、レコードを聴く生徒もいない。岡村弘(竹内・1回生)さんと私だけが弾いたり、聴いたりするだけだった」(『南風対談』)
教材・教具の整っていたのは楽器ばかりではない。青山学院を卒業と同時に英語教師として赴任した長谷川正夫は絵画も担当、「校長は画架、石膏像、額縁など私の要求するがままに買ってくれた。絵の時間には潮江山(筆山)に登ってスケッチさせたり、自然を眺めながら絵の講義をしたりして、全く自由にできた。・・・公会堂でマンドリン合奏会を開いたことがあったが、これが(高知での)この種の最初のコンサートであったとか聞いた。私と同期の常盤(正彦、音楽)先生がハーモニカの独奏会を開いたこともあった」(『創立五十周年記念誌』)。本格的な楽器・画材をそろえ、教室にとどまらずに野外授業や校外活動もおこなった。また、男子中学では厳禁だった女学校のバザーや運動会の見物に行くことも許されていた。
三根校長は、これから世界で活躍する人材には、文学や歴史だけでなく音楽や絵画の教養も大切だと考え、その素養がある新卒の長谷川・常盤両先生を採用、設備や教材も整えたのだ。イギリスのパブリックスクールにならって学校内に寄宿舎を用意し、運営は寄宿生の自治にゆだねた。そこでの平井少年の活躍を、五藤政美(4回生)は、昭和16年の「三根先生を偲ぶ座談会」でこう述べている。
「寄宿舎で茶話会をやる。そうすると皆一芸を出すわけで、平井君はハーモニカをやるわけだ、カルメンをやる。平井君はカルメンが巧いので、無論拍手喝采だ。校長先生は、大野(倉之助、数学)先生を顧みて、おれもカルメンなら知っているといっておりましたがねえ」。それを受け、片岡義信(1回生)が「平井君で思い出したが、ぼくらはマンドリンを買ってね、やったのだけれども上手になれなかった。・・・やはり校長も音楽を取り入れなければならんというのでね」と話す。都築宏明(3回生)は、三根校長のお宅(東京都大森)で奥さまに見せていただいた錦の袋に入れた横笛について、「若い時分に吹いたものだというのですね。それから推して考えて見ると、音楽の素養があったわけですね。趣味がないと思ったら多少あったのです」と、語っている。(『三根先生追悼誌』)
校長が父を説得、音楽学校へ
平井は得意のハーモニカで人気者になるとともに、三根校長の指示で1年生の時に早くも「向陽寮歌」の作曲をしている。作詞は岡村弘先輩であった。「向陽の空」で始まる校歌は、すでに越田三郎作詞・弘田龍太郎作曲でできていた。寄宿舎名・寮歌にも、「向陽」が用いられている。これは漢籍に通じていた三根校長が好んだ言葉と思われる。
 土佐中時代の平井(左)と 二人の弟子(平井家提供) |
|---|
俺も思わくがあって都(かみ)へ出たきに (男子志を立てて郷関を出ず)
成功者(もの)に成らざったら死んだち帰(い)なんぜよ (学若し成らずんば死すとも帰らず)
ナンチャー どこで死んだち構(かま)んじゃないかよ (骨を埋む豈(あに)墳墓の地のみならんや)
どこへ行ったち おまん 墓地ゃ多いもんじゃ (人間到る処青山あり)
これを引用した山田一郎(評論家)は、「平井さんによると、この名訳に<詩吟のフシをつけて得意になって高唱し、三根圓次郎校長を呆然とさせたこともあった>」と書いている(『南風帖』)。平井は言語学でも早熟ぶりを発揮、作曲家になった後も、趣味は言語学・方言研究と述べ、全国の伝承わらべ歌を収録した大著『日本わらべ歌全集』全39冊にも監修者の一人として参画している。 言語学に興味を持った平井は英語も得意で、東京外国語学校に行くつもりで5年生に進んだ。当時の中学生は4年修了で旧制高校に進学できたため、土佐中5年生はほとんどいなかった。しかし、外国語学校や音楽学校・商船学校は5年卒業でないと受験できなかったため、平井は残っていたが、兄の薦めもあって東京音楽学校を目指したくなる。だが父親は医者か弁護士にしたくて大反対で、三根校長に「家の息子は音楽家にさせる心づもりはない」と怒鳴り込んだという。「三根先生を偲ぶ座談会」で、平井はこう述べている。
 平井康三郎(平井家提供) |
|---|
音楽学校に進んだ後も手紙でよく激励を受けたが、なかでも印象的だったのは1年生の時の年賀状に記されていた「凡庸に堕するなかれ」であった。「この葉書は今でも持っており、時々出しては非常に発奮の資にした。これが、土佐中学の教育の真骨頂ではなかったかと思う」と、同じ座談会で語っている。日本情緒あふれる歌曲を生んだ昭和を代表する大作曲家・平井康三郎の誕生には、恩師・三根校長の存在が不可欠であった。(引用文献・図版の出典は最終章末尾に記載する)
<第二章>歌う社長や歌う文部次官も誕生
生伴奏で歌いまくった三菱の進藤
平井康三郎(5回生)は母校や同窓会への想いも強く、筆者が在学中の昭和28年に土佐高委員会(自治会)と新聞部で応援歌を創った際には、快く作曲してくださった。作詞は校内から公募だったが、入選作は中学主事・河野伴香の「青春若き・・・」であった。同窓会関東支部では、昭和63年の総会に講師として登壇いただいた。
 平井の土佐校応援歌が流れる甲子園 2016年春(藤宗俊一撮影) |
|---|
初期の土佐中からは、平井のような音楽家だけでなく、数々の音楽愛好家が育っている。その筆頭が進藤(旧姓宮地)貞和(2回生)である。昭和45年に三菱電機社長になると、重電中心で殿様体質だった企業を見事に変身させ、大躍進を遂げた。特にクリーンヒーターなど家電のヒット商品開発と販売網整備には、目を見張らされるものがあった。その原動力は、飾らない豪快な人柄と、「歌う社長」と呼ばれた得意の歌声であり、技術者や販売店をたちまちやる気にさせた。筆者の『筆山』第3号でのインタビューで、「中学時代には、軟式テニスやハーモニカに熱中し、自己流でヴァイオリンもやった。
 ダークダックスと歌う進藤(土佐中高提供) |
|---|
柔道部で平井から鍛えられたという公文公も、高知高校に進んでからレコード鑑賞に熱中した。堀詰・細井レコード店でのバッハ「ブランデンブルク協奏曲」観賞会にも行ったことを、友人の久武盛真が平成9年の『文化高知』に書いている。公文は、クラシックのレコードをかなり愛蔵していたが、昭和20年4月の高知大空襲で常盤町の実家が全焼、蔵に入れてあったレコードは溶けて黒い塊になっていたと、後日口惜しがっていた。平井の影響を受けたのか、公文式教育を始めてからは、音楽と言語の関連に注目、やがて乳幼児教育にわらべ歌を取り入れ、標語「生まれたら ただちに歌を 聞かせましょう」を唱え、母親に呼びかけていた。筆者は、平成5年にパリの国立小児病院を見学したが、新生児室で副院長から「心身の健全な発達には音楽が欠かせない。ここの医師は全員、取り上げた赤ん坊に母に代わってわらべ歌をうたってやる。入院中の子どものためには楽器をそろえてあり、演奏を楽しめる」と語ってくれた。音楽の意義に、改めて気付かされた。
宮地貫一(21回生)は三根校長亡き後の入学だが、「歌う文部事務次官」と称された。演歌の新曲が出ると即座に譜面を手に入れ、赤坂の「いしかわ」などでコップ酒を豪快に飲んでは、ピアノの生伴奏で歌っていた。二人の宮地先輩は、仕事も酒も歌も「こじゃんと」楽しんだ。なお、三根校長も酒は大好きで、飲むと「よさこい節」を歌うこともあったと聞く。
邦楽には長唄の佐藤、謡の近藤
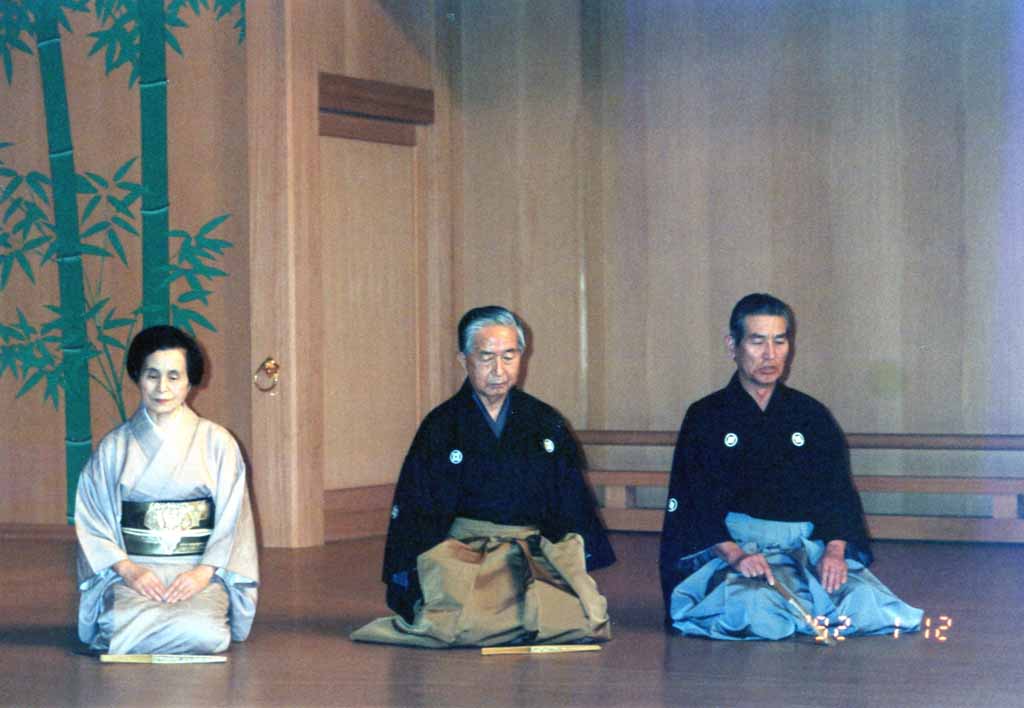 謡に励んだ近藤久寿治…中央(近藤家提供) |
|---|
余談になるが、昭和33年に三代・大嶋光次校長が逝去した際に、近藤は「次の校長は絶対に母校出身だ」との信念のもと、関東同窓会の先頭に立って曽我部清澄先輩(1回生・高知大学教授)を強力に推薦した。大学生だった筆者は、帰郷の際に親書を託されて高知の同窓会会長・米沢善左衛門(2回生)に届けた思い出がある。近藤たちが母校出身者にこだわったのは、戦時色の強くなった二代・青木勘校長(愛知県立第一中学校長から赴任)の時代に、
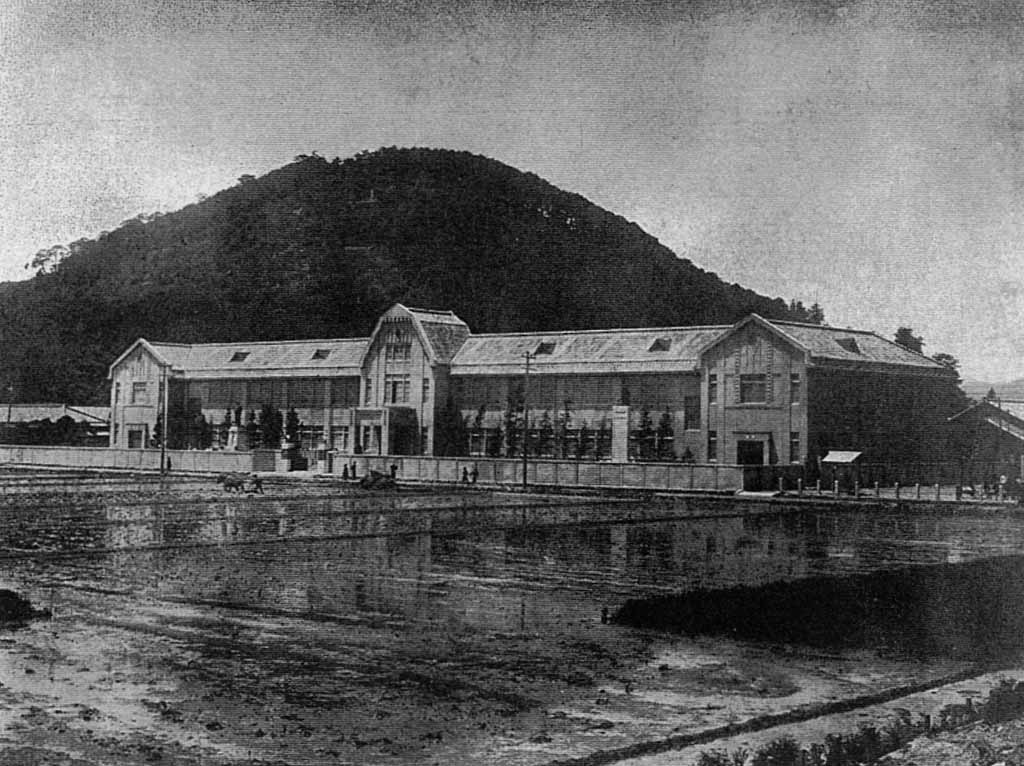 三根校長時代の旧校舎(『三根校長追悼誌』) |
|---|
それにしても、三根校長はなぜ音楽や美術の教育にこれほど力を入れ、平井の才能を見抜いて音楽学校への進学を薦めたのだろう。進学校として、単に有名高校(旧制高校)・有名大学への進学率向上を目指すだけでなく、生徒一人ひとりの個性や才能を見抜いて進路指導にあたるとともに、芸術活動へのなみなみならぬ意欲が感じられる。これは、どこから来たのだろう。
<第三章>息子ディック・ミネはトップ歌手
立教大で相撲部からジャズ・バンドへ
三根校長の長男・徳一は、芸名ディック・ミネで知られる流行歌手で、第二次世界大戦前後の歌謡界で大活躍だった。モダンな歌とダンディーな容姿で実力・人気を併せ持ち、ジャズ・歌謡曲のトップ歌手となった。しかし、三根校長が健在のころは、息子が流行歌手というのははばかる雰囲気があったようで、戦時色の濃くなった昭和18年刊行の『三根先生追悼誌』には、息子のことはほとんど出てこない。近藤久寿治(6回生)は、大学在学中に平井康三郎(5回生)たちと東京で校長を囲んだ際に、平井のことを冗談交じりに「本郷の裏町で、はやり歌をうたっています」というと、校長は「そうか。実は、わしの息子もそのはやり歌をやっている」といわれた、とある。(『続続南風対談』)
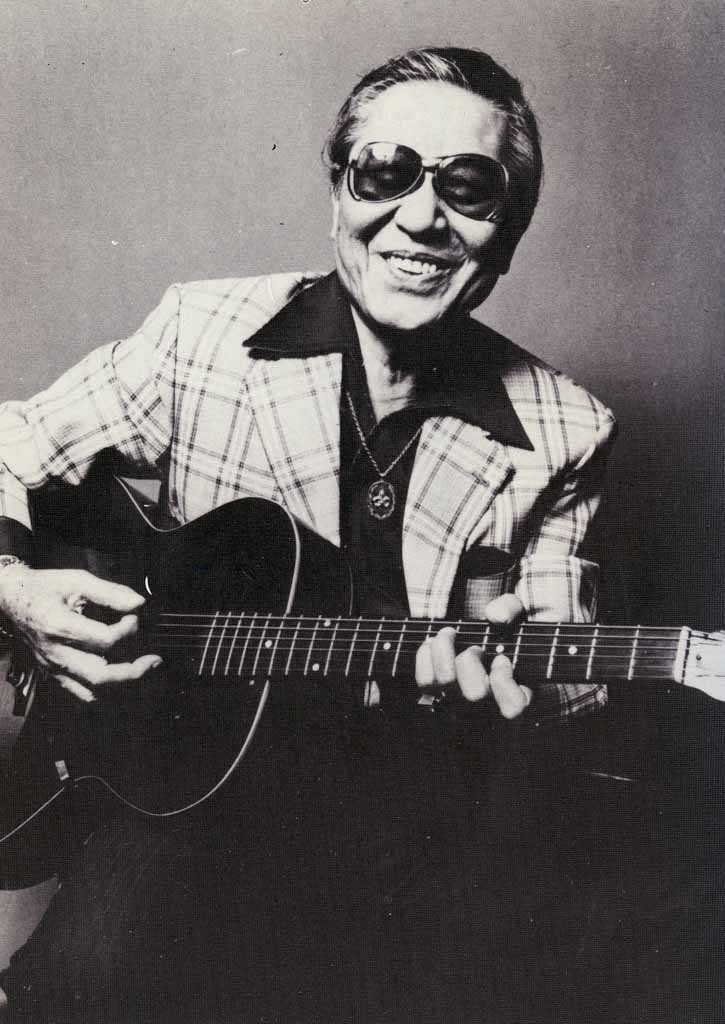 歌うディック・ミネ(三根家提供) |
|---|
<1934年、ビング・クロスビーが歌っていた「ダイナ」を自分で訳詩してデビューし、一躍人気歌手に。学生時代のアダ名からとった芸名「ディック・ミネ」は日本の洋風芸名のハシリとなった。タンゴ調の「黒い瞳」や、「上海帰りのリル」「二人は若い」・・・などの曲も次々とヒットして、折からのジャズブームに乗り、日本の男性ジャズ歌手の草分けとなった。古賀政男のすすめで歌謡曲にもレパートリーを広げ、「人生の並木道」「旅姿三人男」をはじめ、「夜霧のブルース」などでも成功した。・・・1979年から88年まで社団法人日本歌手協会会長。82年には「反核・日本の音楽家たち」結成の呼びかけ人にも名を連ねた。アムネスティ運動やフィリピンの子供たちへの学費援助などにも協力を惜しまなかった>
単なる流行歌手ではなく、社会性や反骨精神も持った「凡庸」ならざる親分肌のリーダーであった。では、その生い立ちからさぐってみよう。父が徳島中学校長だった明治41年に生まれ、徳一と命名された。父の転勤で、小学校は山形・新潟で過ごした。大正9年に土佐中に招かれた父は、母・敬(よし)が体調を崩したので家族を東京に残して単身赴任となった。徳一は日体大付属荏原中学に進んだが、相撲部で活躍したのが目立ち、立教大学に相撲部推薦で入学する。だが、「帝大だけが学校と思っていたおやじは怒った」という。学生時代におこなった不良相手の痛快な武勇伝の数々は、
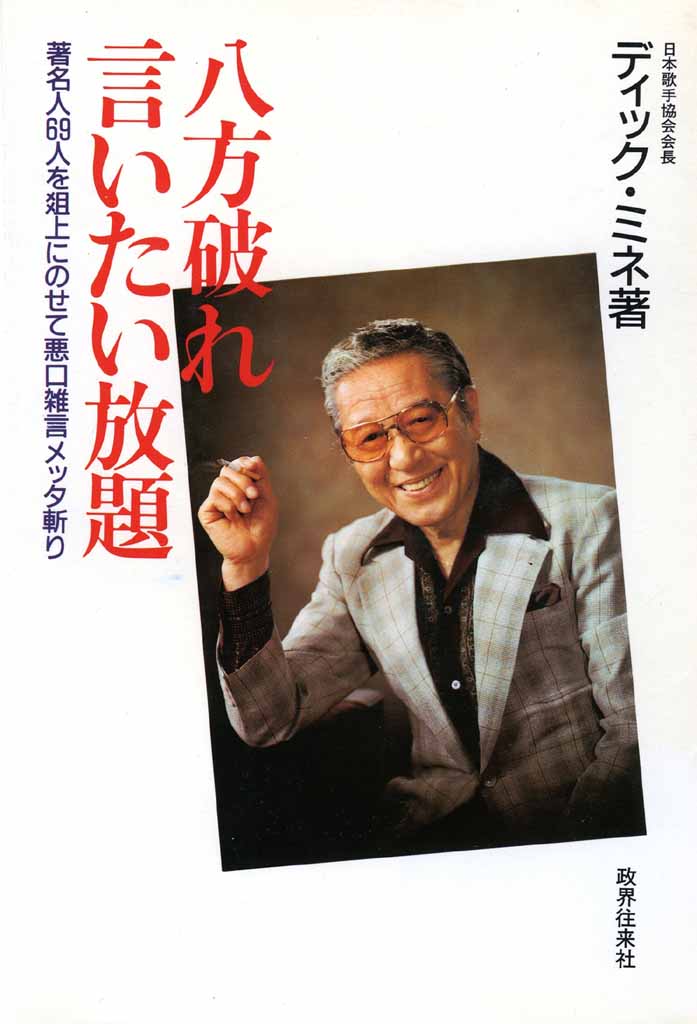 『八方破れ言いたい放題』表紙 写真はディック・ミネ |
|---|
「おやじは堅物一方の人だったけど、母親が話のわかる人でね。なにしろ日光東照宮宮司の娘だから、琴が抜群だった。西洋音楽にも理解があったし、音楽に親しませることが教育上もよろしいということを知っていた・・・電蓄が家にあり、シンフォニックジャズなんか、よく聞かされた」。
そのシンフォニーが大学で聞こえてきたことから立教大学交響楽団に入るが、さらにジャズ・バンドに転進する。自らリーダーとなった学生バンドは、母の紹介によって日光金谷ホテルでデビュー。卒業して逓信省の役人になるが、すぐ辞めてバンド活動に専念、さらにテイチクの専属歌手になる。平成元年の『筆山』に寄せたエッセイ「父」には、<「このごろ変な歌を歌っているディック・ミネというのはおまえか」と父に聞かれ、怒られるのを覚悟で「はい」というと、「世の中、どんな商売もある。やる以上は恥ずかしくないようにやれ、トップになれ」であった。父は息子に対しては自由放任であったが、自分の学校の生徒に対しては、実に細やかに、一人一人の個性を見抜いていた>と、書いている。
軍部にも動じなかった父を尊敬
昭和11年に三根校長が急逝した際には、母と高知に駆けつけたが、父の思い出を『筆山』第9号にこう記してある。
<自分の教育方針を頑として通した父は、文部省であれ軍人であれ、岩のごとく動じなかった。父は学校で「おはよう」と、だれにも帽子をとって挨拶するのが常だった。死の前日のこと、軍部の将校(土佐中への配属将校)がこれを敬礼にせよと迫ったが、父は教育方針は変えぬと言い通した。腹を立てた将校は酒に酔って自宅に乗り込んできて、父と言い争った。この出来事が引き金となって、脳内出血を起こしたのであろう。父の教育は今の時代にも立派に通用すると、私は父を誇りに思います>。三根校長に、秘書のように寄り添っていた芝純(7回生)は、『向陽』3号に「一夜、配属将校と激論せられ、翌日脳溢血で殉職された」と述べている。
 三根家の人々 中央の次男忠雄を挟んで校長ご夫妻 前列左端が徳一(三根家提供) |
|---|
ディック・ミネは晩年になって、父について「熊本の旧制五高から帝大を出た偉い人で、五高の後輩に故・佐藤栄作元首相がいる。そんな関係で佐藤首相に可愛がってもらった」と、語っている。また、昭和54年に勲四等旭日小綬賞をもらった際には、「僕のおやじも、おじいさんももらった」と喜ぶとともに、「親孝行したいときには親はなし」と、嘆いている。親子はまったく別の分野で人生を歩みながらも、お互いに心を通わせていた。
こうして、徳一(ディック・ミネ)が流行歌手として大成した背景には、音楽好きの母・敬の影響が大きかったが、父・圓次郎も温かいまなざしを注ぎ続けていた。徳一も、三根が平井に与えた「凡庸に堕すなかれ」を実践したのだ。昭和60年の関東同窓会にゲストとして出席した際のスピーチでは、「オヤジは偉大だった」と述べていた。今は、父と並んで多摩霊園に眠っている。
 多摩霊園に眠る三根校長と徳一 (中平公美子撮影) |
 三根校長の胸像 本山白雲作(筆者撮影) |
|---|
<第四章>哲学と音楽を育んだケーベル博士
哲学教授はチャイコフスキーの直弟子
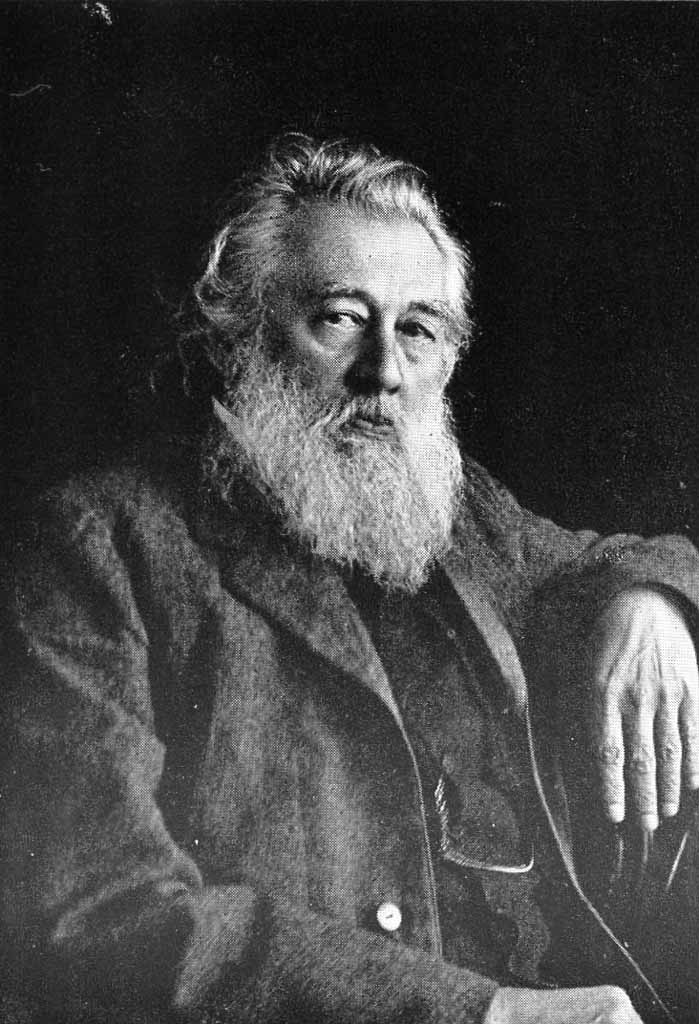 ケーベル(『ケーベル博士随筆集』) |
|---|
ケーベルは、1848年ロシアの生まれ。父はドイツ系ロシア人で国籍はロシアだったが、本人はドイツが祖国と言っていたという。幼少の頃からピアノを習い、19歳でモスクワ音楽院に入学、作曲家チャイコフスキーや名ピアニストのニコライ・ルービンシュタインに師事する。5年後に優秀な成績で卒業するものの、内気な性格から演奏家への道をあきらめ、哲学研究に転進する。ドイツのハイデルベルク大学で、ショーペンハウエルの研究によって学位を取る。ミュンヘンに移って哲学や宗教の歴史を学びつつ、音楽学校で音楽史や音楽美学の講義もおこなっていたところに、突然東京の大学からの招聘状が届く。恩師フォン・ハルトマンの推薦であり、チャイコフスキーからは反対されたが赴任を決断、明治26年6月に日本へ着任する。
当時の帝国大学文科大学は、多くを外国人教授に頼っており、ベルリン大学から招いた史学のルードヴィッヒ・リースのほか、独・英・仏の語学兼文学の教授は、いずれもそれぞれの国から招聘していた。哲学の日本人教授にはドイツ留学帰りの井上哲次郎もいたが、ドイツ観念哲学から東洋哲学、さらに国家主義へと進んだ人物だった。日本人によるアカデミックな哲学者の誕生は、哲学科で三根の少し先輩だった西田幾多郎が京大、桑木厳翼が東大の教授に就任する大正時代まで、待たねばならなかった。なお、外国人教授は、原則として英語で講義をおこなった。
 ケーベルや三根がくぐった東大赤門(藤宗俊一撮影) |
|---|
 ケーベルがチャイコフスキーからピアノを学んだモスクワ モスクワ川とクレムリン(筆者撮影) |
 ケーベルが哲学を学んだハイデルベルク ネッカー川と古城(筆者撮影) |
|---|
では、ケーベル博士が来日当時に、日本の音楽界に抱いた率直な感想を『ケーベル博士随筆集』から見てみよう。まず「音楽雑感」で、「日本へ来て、音楽らしい音楽というものを聴くことができないようになって以来、私は大音楽家の作品(楽譜)を読むことにしている。これによって私はこれらの作品の拙劣なる演奏から受けるよりも遙に大いなる楽を享けるのである」と述べている。こうして、最初は日本人の洋楽演奏に失望するが、明治31年から東京音楽学校(現東京芸術大学)のピアノ教師も務めるようになる。
音楽学校では、ボストン、ウィーンで6年間学んだ幸田延が、明治28年に帰国して母校の教授になっていた。延は、ケーベルからピアノを学ぶうちに腕前を認められピアノ科教授に就く。ケーベルも日本人の演奏をようやく評価、明治36年に日本初のオペラとして「オルフェイス」が音楽学校の奏楽堂で上演された際のピアノ伴奏をはじめ、度々ピアノを演奏している。この年には、幸田延の妹・幸もドイツ留学から帰り、音楽学校ヴァイオリン科教授となる。同年5月の第8回定期演奏会では、幸田姉妹・ケーベルがそれぞれピアノ・ヴァイオリンを披露して喝采を浴びている。幸もピアノや音楽史については、ケーベルから学ぶことが多かったと思われる。
 平井康三郎・丈一朗夫妻(平井家提供) |
|---|
ケーベルは文科大学哲学科の教育について、大変手厳しい指摘をしている。「日本人の精神ならびに性格をはなはだしく醜くするところの傷所は、虚栄心と自己認識の欠乏と、および批判的能力のさらにそれ以上の欠如せることである。これらの悪性の精神的ならびに道義的欠点は、西洋の学術や芸術の杯から少しばかり啜ったような日本人においてとくに目立つ」「日本の学校当局者らは、・・・理知的ならびに倫理的教養には全然無価値なる、否、むしろ有害と言うべき・・・生徒の記憶を一杯に塞ぎ、疲労せしめ・・・試験のためにのみ学ばれるところの学課をもって、その生徒をいじめるのである」
 ケーベル(手前右)と東京音楽学校管弦楽団、左は幸田姉妹 (『東京芸術大学百年史東京音楽学校篇第一巻』) |
|---|
三根たちは、これらの教えを「干天に慈雨」の思いで吸収していったと思われる。当時の帝大文科大学生は卒業すると、研究者の道に進むか当時の各県の最高学府である県立中学校の教諭になるかであった。「教師になっても、生徒に一方的に教え込む職人ではなく、生徒とともに学ぶ研究者でもあれ」が文科大学のモットーだったと、中野実(東京大学・大学史史料室)は語ってくれた。ケーベルの哲学や美学から、教師としてのバックボーンを得て、また音楽や美術の意義をよく理解し、三根たちは各地の学校に赴任していったのだ。
このケーベルのピアノに魅了された人物に、寺田寅彦がいる。五高時代にヴァイオリンを始めた寺田は、明治34年、東京帝国大学1年の時に夏子夫人が病気療養で高知に帰郷した孤独から逃れるため、東京音楽学校の慈善演奏会に行き、「橘(糸重)嬢のピアノ、幸田(延)嬢のヴァイオリン、ケーベル博士のピアノ・・・」を聴く。とくにケーベルの演奏に魅せられ、無性に会いたくなって自宅を訪問する。以来、夏目漱石を誘ってたびたびケーベルの出演するコンサートに出かけている。
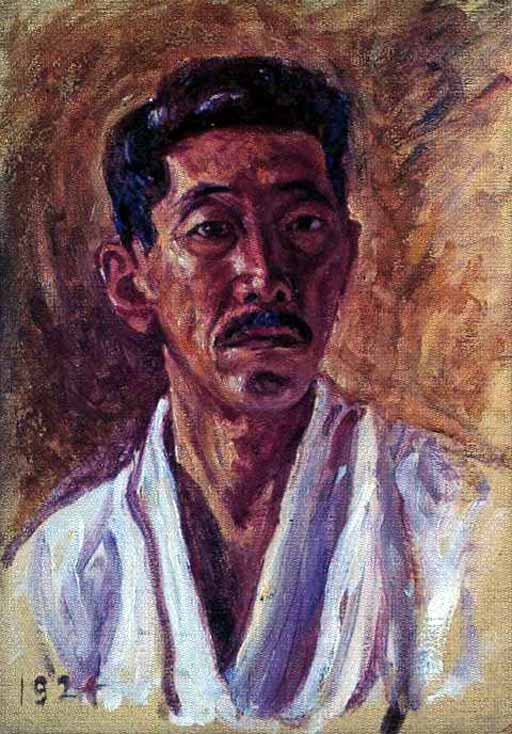 寺田寅彦「自画像A」 (『高知の文学』高知県立文学館) |
|---|
明治38年1月3日の寺田の日記には、「阪井へ行き、琴三絃ヴァイオリンにて六段など合す」とある。阪井とは、夏子夫人の父・阪井重季(陸軍中将)であり、亡き妻の異母妹・美嘉子の琴などとの合奏に、ヴァイオリンで参加したのだ。肺病のため桂浜で、明治35年に亡くなった妻を偲んだのであろうか。夏子も美嘉子も、美人で評判だった。この頃から寺田は音響学を研究、明治41年には東京帝国大学理科大学から、理学博士の学位を授与される。主論文は「尺八の音響学的研究」であった。寅彦の孫・関直彦によると、一時ヴァイオリンを中断していたが、大正11年にアインシュタインが来日した際に、歓迎晩餐会で同氏が余興にヴァイオリンでベートーベンのクロイツェル・ソナタを弾いたのに触発され、高知出身の作曲家で土佐中校歌を作曲した弘田龍太郎からヴァイオリンの個人レッスンを受けることになったという。
寺田の五高以来の恩師・夏目漱石も、帝国大学文化大学の大学院で、来日したばかりのケーベルから美学の講義を受けている。漱石は寺田とともに、ケーベルの演奏会に何度か足を運び、自宅も訪問、随筆「ケーベル先生」を書いた。そこには、「文科大学へ行って、此処で一番人格の高い教授は誰だと聞いたら、百人の学生が九十人迄は、数ある日本の教授の名を口にする前に、まづフォン・ケーベルと答へるだろう」とある。文芸評論家の唐木順三は、「ケーベルと漱石」でケーベルの生活ぶりを、「読書と自分の耳にきかせるピアノと執筆の生活。自分の立場を〈哲学と詩との間〉において、詩と哲学を享受し観賞する生活。・・・生活即芸術であった」と書いている。(『現代日本文学大系 夏目漱石』)
ケーベル先生の遺産
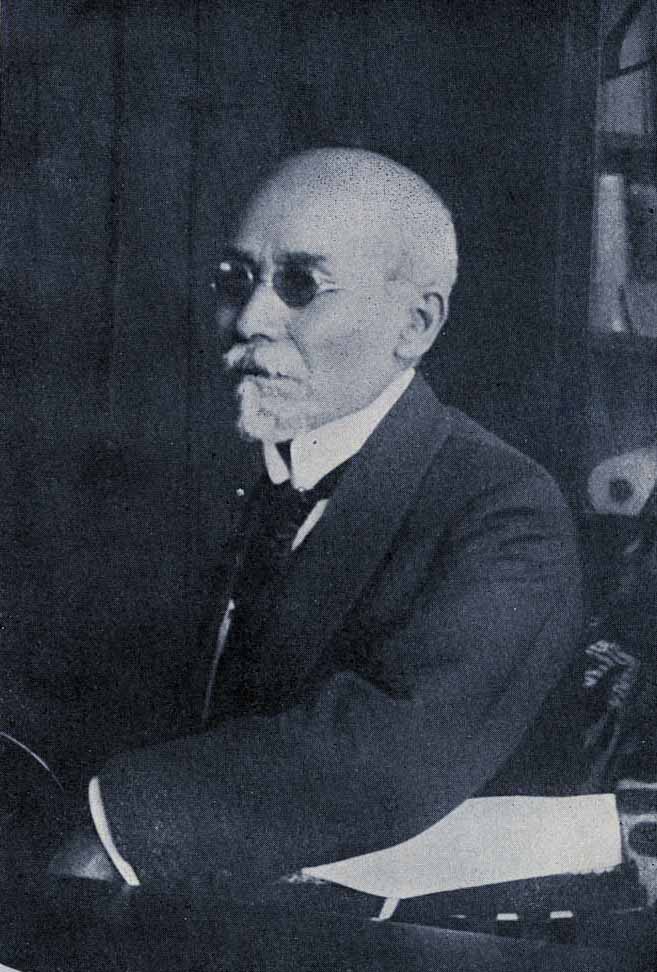 三根圓次郎(『三根先生追悼誌』) |
|---|
同年に、県庁に提出した「土佐中学校設立認可願」の添付地図には、江ノ口小学校の北側に「新設校地」との記入がある。申し訳なく思ったからか、寺田寅彦は立派な柱時計を土佐中に寄贈、潮江村に完成した新校舎に飾ってあった。寺田が演奏を楽しみ、また音響学の研究材料にも使ったヴァイオリンやチェロは、自作の油彩画「蓄音機を聞く」とともに「高知県立文学館・寺田寅彦記念室」で見ることができる。ヴァイオリンは1814年にボヘミヤで製作された名器アマティのコピーで、孫の関直彦が譲り受けていたもの。
 「蓄音機を聞く」(『寺田寅彦画集』より) |
|---|
ケーベルたちによって音楽の才能を開花させた幸田姉妹は、旧幕臣の家に生まれたが、祖父や母が音曲好きで幼少期から箏曲や長唄の稽古を積んでいた。やがて東京女子師範学校付属小学校で西洋音楽に触れ、その音楽的才能を見いだされ、ピアノやヴァイオリンの道に進んだ。三根も横笛を手にしていたが、江戸時代には公家の世界では雅楽が、武家や町人では能楽や箏曲・長唄が好まれた。欧米の上流家庭で室内楽が好まれたのと同様に、日本の家庭にも邦楽を楽しむ伝統があり、西洋音楽の受容にもつながった。平井の「平城山」、山田耕筰の「からたちの花」、滝廉太郎の「荒城の月」などには、日本の風土色が色濃く漂い、日欧の融合から生まれた調べと言えよう。
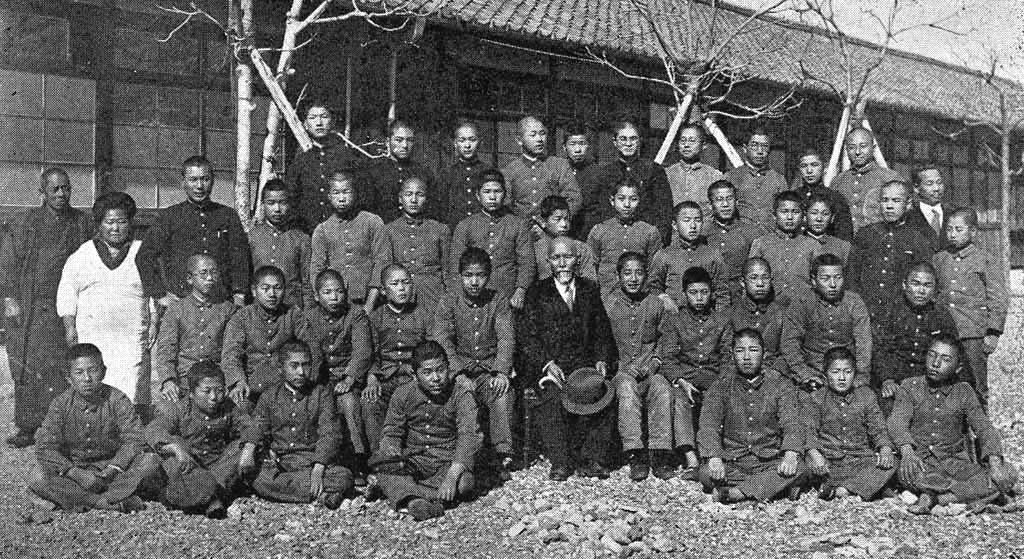 寄宿舎生に囲まれた三根校長 昭和10年(『三根先生追悼誌』) |
|---|
三根校長たちは、ケーベル博士から哲学や美学の知識とともに、豊かな人生には音楽や美術を欠かすことができないという「生活即芸術」の教えを学んだ。さらに、内面から湧き出る教育者としての豊かな人間性を感じ取って巣立っていったのだ。三根校長にとどまらず、漱石や寅彦をも魅了した“ケーベルの教え”が、母校土佐中高の学園生活に受け継がれ、凡庸ならざる人材の育成に活かされることを願っている。
(本稿執筆に当たっては、三根圓次郎の孫・信宏氏、平井康三郎の長男・丈一朗氏、近藤久寿治の長男・孝夫氏、寺田寅彦の孫・関直彦氏、筆山会および向陽プレスクラブの皆様にご協力いただいた。感謝申し上げたい。なお、本文では敬称を省略させていただいた。)
三根圓次郎(『三根先生追悼誌』)
 熊本第五高等学校時代 (明治28年) |
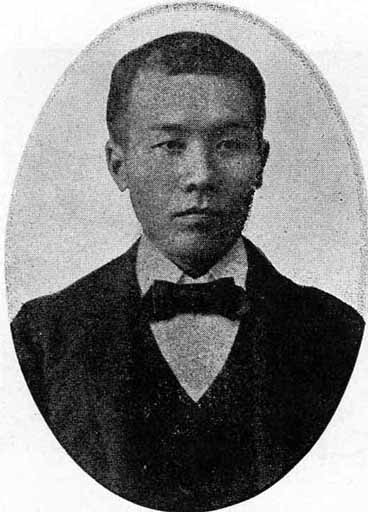 東京帝大文科大学哲学科 卒業の翌年(明治31年) |
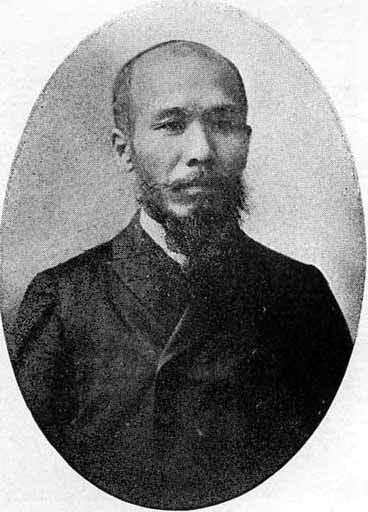 県立徳島中学校長時代 (明治42年) |
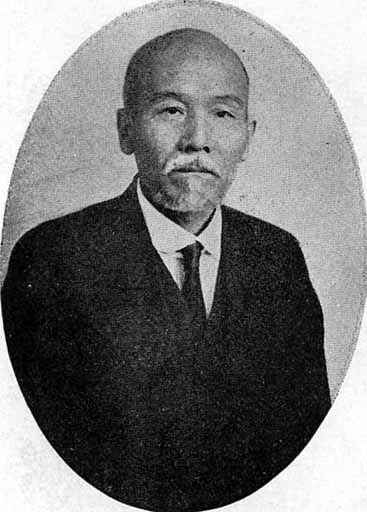 土佐中学校長就任4年後 (大正13年) |
|---|
『土佐中學を創った人々』向陽プレスクラブ 平成26年/『三根先生追悼誌』土佐中学校同窓会編集発行 昭和18年/『創立五十周年記念誌』創立五十周年記念誌編集委員会 昭和51年/『ミリオーネ全世界事典』5 学研 昭和55年/『南風対談』『続続南風対談』山田一郎 高知新聞社 昭和59・61年/『南風帖』山田一郎 高知新聞社 昭和58年/『八方破れ言いたい放題』ディック・ミネ 政界往来社 1985年/『筆山』土佐中・高同窓会 関東支部会報 各号/『ケーベル博士随筆集』久保勉訳編 岩波書店 1928年/『幸田姉妹』萩谷由喜子 ショパン 2003年/『東京芸術大学百年史演奏会篇第一巻』『東京芸術大学百年史東京音楽学校篇第一巻』音楽之友社 1990年・昭和62年/『寺田寅彦随筆集第二巻』小宮豊隆編 岩波書店 1947年/『寺田寅彦全集 第二十一巻(日記)』岩波書店 1998年/『現代日本文学大系 夏目漱石(一)(二)』筑摩書房 昭和43年・45年/『文化高知』(財)高知市文化振興財団 平成9年/『寺田寅彦画集』中央公論美術出版 寺田東一 昭和60年/『高知の文学』高知県立文学館 平成9年 生首を化粧した武士の娘
中城正堯(30回) 2017.05.22
―戦乱を逃れ、土佐に来た「おあん」その後―
 筆者近影 |
|---|
子どもに語った戦国の実態
江戸初期の土佐の女性といえば、思い浮かぶのはだれであろう。まず、内助の功で知られる初代藩主・山内一豊(かつとよ)の妻がいるだろう。一豊亡き後、見性院(けんしょういん)の法号を受けるが、名前は「千代」とも「まつ」とも伝わり、明らかでない。へそくりで名馬を買った伝説はともかく、関ヶ原の直前に人質となっていた大坂から東国の一豊に送った「笠の緒の密書」は、徳川家康にも高く評価された実話だ。もう一人は、野中婉(えん)であろう。奉行職だった父野中兼山が失脚すると、44歳まで宿毛に幽閉された。その孤高の生涯は、大原富枝の名作『婉という女』に描かれている。
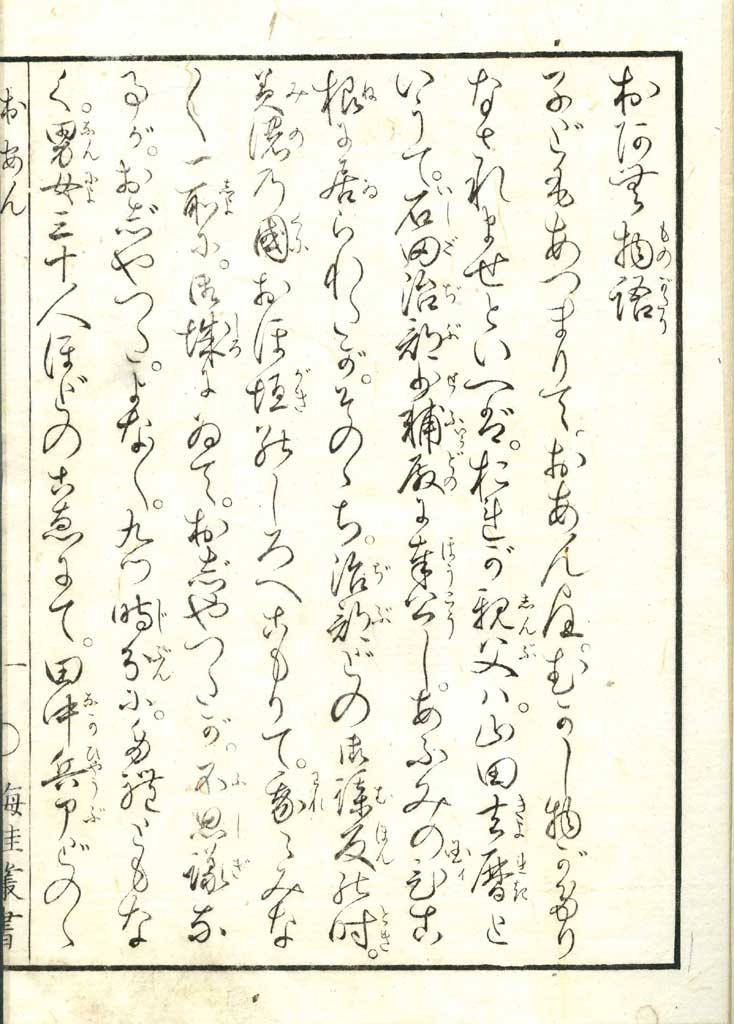 『おあん物語』 (天保版 喜多武清画 筆者蔵) |
|---|
『おあん物語』は、「子どもあつまりて、おあん様むかし物語なさりませといえば」から始まっており、近所の子どもたちにせがまれて、十数歳で体験した篭城戦の凄惨な光景を語った物語だ。さらに後半には、彦根城下での貧しい少女時代の生活体験が記されている。この話を、だれか分からないが筆記した者がおり、写本が流布した後、享保15(1730)年に土佐の谷垣守(かきもり)が本にまとめている。筆者は十年ほど前に神田の古書店で、朝川善庵が谷垣守本に挿絵を付けて天保8(1837)年に刊行した天保版を見付けて入手した。題簽(だいせん)に『おあんものがたり おきくものがたり』とあり、大坂夏の陣で大坂城から脱出した「お菊」の物語と合本にした大判(257×180ミリ)の和本だった。
こうして江戸時代から広く読み継がれてきた『おあん物語』であり、現代も国文学者や歴史学者から大いに注目されている。しかし、見性院や婉と違って高知では忘れ去られているようなので、この本の誕生のいきさつと内容、さらに各分野の研究者や文学者による論評と活用を紹介したい。なお、翻刻は、岩波文庫『雑兵物語 おあむ物語』(昭和18年)によったが、読みやすくするため現代文に直し、主人公「おあむ」は、「おあん」と表記した。文末の「おじゃった」などは活かしてある。では、本文(一部省略)に入ろう。
篭城し、生首にお歯黒を施す
「おあん」には、「おれが親父は、山田去暦といい、石田治部少輔(じぶしょう・三成)殿に奉公し、近江の国彦根に居られたが、その後、治部どの御謀反の時、美濃の国大垣の城へこもって、我々みなみな一所に、お城にいて、おじゃった」と、大垣城にこもったいきさつが出てくる。やがて、「家康様より、せめ衆、大勢城へむかわれて、戦が夜ひるおじゃったの。その寄せ手の大将は、田中兵部殿と申すでおじゃる」とある。攻め手の大将・田中吉政(兵部)は、豊臣秀次・秀吉に仕えたが、関ヶ原では東軍について石田三成を捕虜にする武勲をあげ、柳川藩主に取り立てられた人物だ。秀次に宿老(重臣)として仕えた際には、山内一豊も同じ宿老であった。ただ、石田は関ヶ原へ大垣城(岐阜県)から出陣しているが、田中が攻めたのは石田の本拠・佐和山城(滋賀県)である。したがって、『おあん物語』の舞台も実は佐和山城で、おあんの記憶違いで大垣城となったようだ。
戦が始まると、「石火矢(大砲)をうてば、櫓(やぐら)もゆるゆるうごき、地もさけるように、すさまじいので、気のよわい婦人なぞは、即時に目をまはして、難儀した」「はじめは、生きた心地もなく、ただ恐ろしや、こわやとばかり、われも人も思うたが、後々は、なんともおじゃる物じゃない」と変わる。恐ろしい砲撃を受けながらも、次第に慣れていく。
城中で女性は、どんな役割を担っていたか。「我々は母も、そのほか家中の内儀、娘たちも、みなみな天守に居て、鉄砲玉を鋳ました」女たちは、鉛を溶かして鋳型に流し込んでは、火縄銃の鉄砲玉を作った。
 挿絵① 生首にお歯黒を施す女性 |
|---|
やがて、「寄せ手より鉄砲打掛け、もはや今日は城も落ちるだろうという」状態となる。そこへ「鉄砲玉が飛んで来て、われら弟、14歳になった者に当り、そのまま、ひりひりとして死んでおじゃった。さてさて、むごい事を見ておじゃったのう」と、歎いている。
たらいで脱出、土佐に来た「彦根ばば」
挿絵② たらいで堀を渡って脱出 |
|---|
挿絵③ 道ばたで出産した母子をかついで逃避行 |
|---|
さらに、土佐の子どもたちに、「彦根の話、なされよ」と言われ、こう語っている。「父親(山田去暦)は知行三百石取りであったが、戦が多く、何事も不自由であった。朝夕雑炊を食べておじゃった。おれが兄さまは、時々山へ鉄砲打ちに参られた。その時は朝菜飯(なめし)を炊き、我等も菜飯をもらえるので、うれしかった。衣類もなく、13の時、手織りの花染めの帷子(かたびら…ひとえの着物)一つよりなかった。その帷子を17の年まで着たので、すねが出て難儀であった。せめて、すねのかくれるほどの帷子ひとつ欲しやと思うた。このように、昔は物事が不自由な事であった。昼飯など食う事は、夢にもない事。夜に入り、夜食という事もなかった。今時の若い衆は、衣類の物好き、心をつくし、金を費やし、食物にいろいろ好みをいい、沙汰の限りなきこと(言語同断)である」。
こうして、彦根の時代を思い出しては、子どもをしかったので、後には「彦根ばば」のしこ名(綽名)をつけられたとある。さらに、今も老人が昔話を引用して、当世を戒(いまし)めることを「彦根」というが、この言葉は俗説では「おあん様」に始まったことで、土佐以外では通じないと、筆記者は付記してある。
谷垣守がまとめて出版、広く流布
土佐に来たことについては、「去暦、土佐の親類方へ下り、浪人。おあんは、雨森(あめのもり)儀右衛門(土佐藩士)と結婚。夫の亡き後は、甥の山田喜助(後に蛹也(ようや))に養育して貰う。寛文(1661~72)何年かに、八十余で死す」と、簡単に触れている。
聞書の筆者は、物語を終えた後に「おあんの物語」を残した経緯をこう述べている。「おあんの話を聞いたのは8、9歳の頃で、折々に聞き覚えた。誠に光陰矢の如し。正徳(1711~15)の頃、孫どもを集めてこの物語に、自分の昔のことも合わせて、世の中の苦しみを示すと、小賢しい孫どもが、『昔のおあんは彦根ばば、今のじい様は彦根じじ。今さら何をいうやら、世は変わった』と、鼻であしらうゆえ、腹を立てども後世おそるべし、どうなるだろう。今の孫たちも、また自分の孫たちに、このようにいわれるのだろうかと、勝手に想像、後はただ南無阿弥陀仏と繰り返すほかに、いうべき事はない」。
 生首をかかげての凱旋(成瀬家蔵「小牧長久手合戦図屏風」より 『戦国合戦絵屏風集成 第二巻』中央公論社) |
|---|
さらに、天保8年に『おあんものがたり おきくものがたり』として出版した江戸後期の儒学者・朝川善庵は、跋文(あとがき)で「狂言師・倉谷岱左衛門の門人某が安永年間に、大坂からこの本を持ってきた。御庵(おあん)とは、老尼の尊称である」と述べている。この本には、挿絵三枚が加えてある。朝川善庵は天明元年、江戸の生まれ、嘉永2年没である。挿絵には「武清」の落款(らっかん)があり、絵師は喜多武清だ。江戸後期の画家で、八丁堀に住み、谷文晁に師事した。渡辺崋山とも交流があり、崋山は「その臨写(写生)には、ほとんど真物に迫る貴重な物が多かった」と、語ったという。山東京伝『優曇華(うどんげ)物語』の挿絵も描いている。安政3(1856)年没。
『おあん物語』は、谷垣守本が原本であるとされ、写本が高知県立図書館にある。垣守(1698~1752)は谷秦山(じんざん)の息子で、儒学者・国学者。京や江戸にしばしば行き、諸家と交わり研鑽した。その子・真潮(ましお)ともども家学を深め、土佐を代表する学者となって、政治にも参与した。垣守がまとめた『おあん物語』は、天保8年版によって広く流布し、戦国時代の貴重な記録として、今に各地の図書館や大学に残っている。
では、明治から現代まで、識者や研究者によって、この物語がどのように受け止められてきたか、さぐってみよう。
岩崎鏡川による「おかあ武勇伝」
 生首を持ち帰る兵(「賤ヶ岳合戦図屏風」より 『戦国合戦絵屏風集成 第二巻』中央公論社) |
|---|
龍馬の縁戚に当る土居晴夫は、「おか阿の武勇談」(『坂本龍馬の系譜』)でやはりこの話を紹介しているが、おか阿の妹は坂本家初代太郎五郎の妻ではなく、その子・彦三郎の妻とする。南国市三畠(さんぱく)には、小笠原佐兵・おか阿の墓と顕彰碑があるという。
岩崎鏡川は、おか阿は忘れられたのに「おあんの物語は、久しく世上に流伝し、今や歴史研究家としてその名を知らざるなし」と述べている。昭和にはいると歴史家だけでなく、多くの文学者がこの物語に注目し、さまざまな形で作品化する。まずは、岩崎鏡川の次男に生まれ、母・斉(ひとし)の実家・田中家にはいった作家・田中英光(ひでみつ)から取り上げよう。
田中英光の母方の祖父・田中福馬は種崎村の商家に生まれたが、宝永町に出て市場の仲買人として成功する。しかし自由民権運動で家産を傾け、東京に出た。英光は大正2年、東京赤坂で生まれたが、土佐人に囲まれて育ち、高知を故郷としていた。早大在学中の昭和7年には、ロサンゼルス・オリンピックにボート選手として参加。その後作家となり、『オリンパスの果実』などで知られる。昭和24年に太宰治の墓前で自殺する。この英光が昭和18、9年頃執筆したと推定される遺稿「土佐 2」(『田中英光全集8』芳賀書店)に、「おあん物語」がある。
虐げられた女性への追憶
この文章の最初に、「寺石正路氏の考証のついた、土佐協会誌第66号の付録があるので参考にさせて貰い、感想を述べながら意訳する」とある。おそらく父・鏡川の文章で「おあん物語」に注目し、寺石の文書も入手したのであろう。英光は、まず菊池寬の「わが愛読文章」から、次の部分を引用している。
「戦国時代に於ては、個人の私生活、ないし日常生活についての文献なぞは全然見当たらない。ことに女性の私生活については何も伝わっていない。その間にこのおあん物語だけが、一つの真珠のように光っている。これは戦国時代に於けるたった一つの自伝小説と云っても好いものだ」。このあと、現代文に意訳して物語を紹介、前半を終えたところで、こう感想を挟んである。「ここまでが、関ヶ原当時の思い出話だ。戦時中、女子供がどんなに惨めであったか、ただ虫のように生き、虫のように死んで行ったに過ぎない。ところが今度の戦争中におあん物語を時局に有意義な物語として取り上げ、昔でも女子供はこんなに苦しんだのだから、今の女子供は幸福だ。すべからく今の配給生活に感謝せよなぞ言っている人もいたが、これは反対で、三百年前の女子供の暗い生活と少しも変わらぬ、あるいはもっと酷い生活を強いられている現代の矛盾と欠陥をむしろ批判的に考えなければならないと思う」。
 落城して炎上する城(「大内合戦之図」橋本貞秀 松﨑郷輔所蔵) |
|---|
英光は物語の後半を記した後、寺石の次のような考証を転記している。「山田去暦の墓は、高知城南潮江山字(あざ)高見にありと聞く。阿庵(おあん)の墓は同じ清水庵の傍らにあり。わが父は子供の頃、潮江村に住み、童遊の際、阿庵の墓に行き、木太刀を取り帰ったことがある。阿庵の墓は、なぜか知らないが木太刀の奉納がおびただしかった。昔から土佐では歯の痛む人は小溝に行き、お庵様といって祈願をして、平癒すればお歯黒を上げる習いがあった」。
英光は最後に、「この平凡な女性が、どうしてこのような俗信の対象となるまで、有名になったであろうか。同様な方言を生むまでに有名な荒武者・福富隼人と対照してみる時は面白い」と、問いかける。福富隼人は、長宗我部元親に仕えた伝説的な豪傑で、英光は隼人の孫で惨めな流浪の生涯を送った「福富半右衛門」を主人公に歴史小説を書いている。この二人を対比しつつ、こう記して「おあん物語」を終えている。
「隼人は生粋の土佐人であったが、その子孫は他国に流浪し、おあんは他国人であったが、その子孫は土佐に止まることになった。この点でもまた、対蹠(たいしょ)的であり、かつ私は土佐を限定した土佐と見る愚劣さを思う。そして軽々しく独断は出来ないが、こうして隼人が有名になった原因には、他国人の抑圧の下に苦しんだ土佐人が前代の自国人の英雄に対する敬愛の念を感じ、おあんが有名になった原因には、抑圧された民衆が、虐げられた女性の追憶にある真実さを、限りなく愛慕するの情を感じることができる」。
「おあん」に見る男女の生と性
「おあん物語」に関心を示した作家には、谷崎潤一郎、そして土佐出身の大原富枝がいる。二人の取上げ方を紹介しよう。
谷崎が「武州公秘話」を雑誌『新青年』に発表したのは、昭和6年である。後に谷崎全集に寄せた文章で、圓地文子は、「小説のはじめの方で城中の女達が首を化粧する前後の描写はこの作品中、白眉の部分」とし、「恐らく作者はこれらの場面を〈おあん物語〉や〈おきく物語〉などによって構想されたのでしょう」と述べている。
この物語の序で作者は、主人公・武州公を「一代の梟雄(きょうゆう…残忍で猛々しい人)、また被虐性的変態性欲者なり」と述べ、その由来となった事件に入っていく。13歳の秋、幼名・法師丸は、人質となっていた牡鹿(おじか)城が敵兵に囲まれ、篭城を余儀なくされる。ある夜半、五人の女たちが敵の生首に化粧を施す部屋に忍び込み、女たちの作業ぶりに恍惚感を抱く。なかでも、生首の髪を洗う16、7の若い女の、首に視入る時のほのかな微笑に陶酔を覚え、「殺されて首になって、醜い、苦しげな表情を浮かべて、そうして彼女の手に扱われたいのであった」と書く。伊藤整は、「武州公秘話」のモチーフは、「残虐性と美との観念の連絡と交錯」であり、古文書から得た物語に見事に生かされている。「作者一代の傑作」「世界諸国の文学の中にも類を求め得ない特異な作品」と、絶賛している。
 落城で逃げまどう民衆(「大坂夏の陣図屏風」より、大阪城天守閣蔵) |
|---|
学問の世界では、昭和18年の岩波文庫版で、戦時教訓的なねらいを隠し、国語学者湯澤幸吉郎が「口語史上注意すべき事」として、語尾の「あらない」「おぢやる」などを指摘している。戦後は、民俗学者の柳田国男が、「民衆の生活」「口語資料」にかかわる「清新な教材」として、東京書籍の高校国語教科書に採用したことを、井出幸男が『宮本常一と土佐源氏の真実』で述べている。国語の古典教材に、庶民の生活誌が登場するのは画期的なことであったが、採択が広がらず、この教科書は消えていった。井出は、宮本の『土佐源氏』も「おあん物語」の語り口調の影響を受けており、また単に乞食から聞き取った民俗誌の資料ではなく、創作が入った文学作品だとする。筆者は、梅棹忠夫監修『民族探検の旅』(全8集・学研 昭和52年刊)に続き、宮本常一監修『日本文化の源流』をまとめるべく宮本を囲んで企画会議を開始していたが、昭和56年に逝去され、実現しなかった。「土佐源氏」(「土佐乞食のいろざんげ」)誕生のいきさつも聞き逃してしまった。宮本は柳田と親しく、田中英光には強い共感を寄せていた。
歴史家の受け止め方も述べておこう。磯田道史は、「女たちが見た関ヶ原の合戦」(『江戸の備忘録』文春文庫)で、「現在の長い平和は江戸時代以来のことだ。実は江戸の初めにも、日本人は今の平成時代と同じように〈戦争を知らない世代の到来〉を経験している。・・・江戸人が聞き耳を立てた〈戦争体験談〉」だとして、おあん物語を紹介している。小和田哲男は、『城と女と武将たち』(NHK出版)で、「おあん物語」から〈鉄砲玉の鋳造〉と〈敵の首へのお歯黒付け〉をあげ、篭城中の女たちの仕事であったことを実証している。
老人と子どもの新しい絆を!
 高知城、おあんはこの城下で穏やかな 晩年を過ごした。(筆者撮影) |
|---|
「おあん物語」は、子どもが集まって「おあん」に昔話をせがむところから始まる。平和になった江戸時代の文献には、隠居の身となった老人たちが、子どもたちと過ごす様子が、よく現われてくる。越後の良寛は、「霞(かすみ)立つ永き春日(はるひ)を子供らと 手毬つきつゝこの日暮らしつ 子供らと手毬つきつゝ此のさとに 遊ぶ春日はくれずともよし」と歌を詠んでいる。江戸の山東京山は天保3年刊『五節供稚童講釈』で、「隠居とおぼしき剃髪の姿賤(いや)しからず、女小(ママ)供を集めて、五節供の講釈をするなり」と述べ、『菅江真澄全集』には仙台領徳岡の村上家で浄瑠璃を披露しようとした座頭(ざとう)に、子どもが「むかしむかし語れ」と催促した場面がある。これらは、いずれも江戸後期の事例だ。
テレビやスマホのない時代の子どもたちにとって、老人と遊び、昔話や体験談を聞くのは、なによりの楽しみであった。さらに、老人が地域の子どもの教育に積極的にかかわった記録もある。乙竹岩造が、『日本庶民教育史』で紹介した「あやまり役」である。寺子屋では、いたずらや怠慢で破門の罰を受けると、あやまり役の老人に知らせがあり、子どもを諭(さと)した上で、一緒に寺子屋の師匠におわびに行ってくれた。母親よりも、年の功で上手にとりなす老人が適任で、あやまり役は各地で見られた。
だが、老人の話も説教くさくなると、とたんに子どもに嫌われる。話を受け継いだおあんの孫も、やがて子どもたちに鼻であしらわれる。『女重宝記(ちょうほうき)』には、「上代の女はその心素直にして邪(よこしま)ならず。世の末、今の世におよびては、女の心日々に悪しくなり、人をそねみ妬(ねた)み、身を慢(まん)じ、色ふかく、偽りかざりて欲心多く、やさしき心なくして情けを知らず」とある。現代にも通用しそうだが、元禄5年(1692)に出た女子用教訓書の教えである。いつの世も、世代間ギャップは簡単には埋まらない。
だが、老人と子どもを上手に結びつけている例は現在もある。1999年にパリで出会った中学校の国語教師が、移民の子どもにとっている対応で、「正しいフランス語修得には古典的な詩文の暗誦が欠かせない。宿題に出すが、移民は親も教えることができない。そこで老人の家庭を訪問させ、教えてもらった。孤独な老人にも、話し相手ができたと喜ばれた」という。
現代の日本では、増大する高齢者は老人施設などに囲い込まれて別居、地域の子どもはおろか孫と接する機会も少ない。子どもも学校と塾に囲い込まれ、老人の体験談や昔話・わらべ歌を聞き、ともに遊ぶ機会は失われてしまった。おあんは土佐の子どもたちに囲まれ、昔話をせがまれつつ幸せな晩年を過ごした。その生涯を記録した、谷垣守のような人物にも恵まれた。老人と子どもが直(じか)に触れ合い、遊び、語り合う、新しい絆の構築が望まれる。 「三根圓次郎校長とチャイコフスキー」その後の反響
「土佐中初代校長の音楽愛」と、高知新聞が紹介
中城正堯(30回) 2017.07.10
 筆者近影 |
|---|
まずマスコミ関係では、高知新聞の7月7日朝刊学芸欄に、「土佐中初代校長の音楽愛」との見出しで、片岡編集委員による添付の紹介記事が掲載された。ディック・ミネが大好きという同新聞社元会長のH様からは「三根校長はもっと知られねばと思っていた。この冊子は素晴らしい役割。隠れた話がたくさんです」と、便りが届いた。
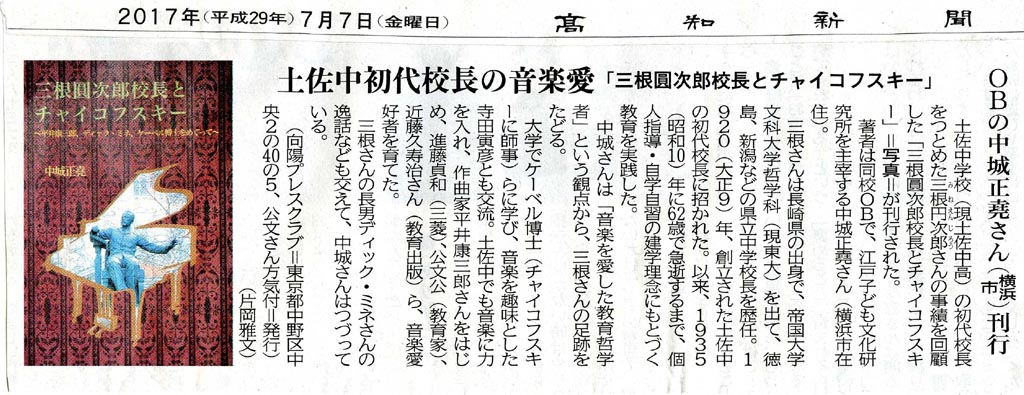 高知新聞学芸欄での紹介記事 2017/07/07 |
|---|
高知出身で元集英社編集担当役員のI氏は、「和辻哲郎の本でケーベルには関心を持っていたが、三根校長が教え子で、寺田寅彦や平井康三郎など高知の人物につながるとは、思いがけないことだった」と、喜んでくれた。高知在住の編集者Yさんは、「すばらしい人物を輩出した土佐中高は、やはり素晴らしい理念を持った教育者によって創られたのですね」といい、高知の大学講師(福祉問題専攻)Y氏は「ケーベル博士は、明治31年に音楽学校で開かれた慈善音楽会の収益金を貧困家庭の子女のための二葉幼稚園に寄付している」と、博士の知られざる慈善行為を教えてくれた。
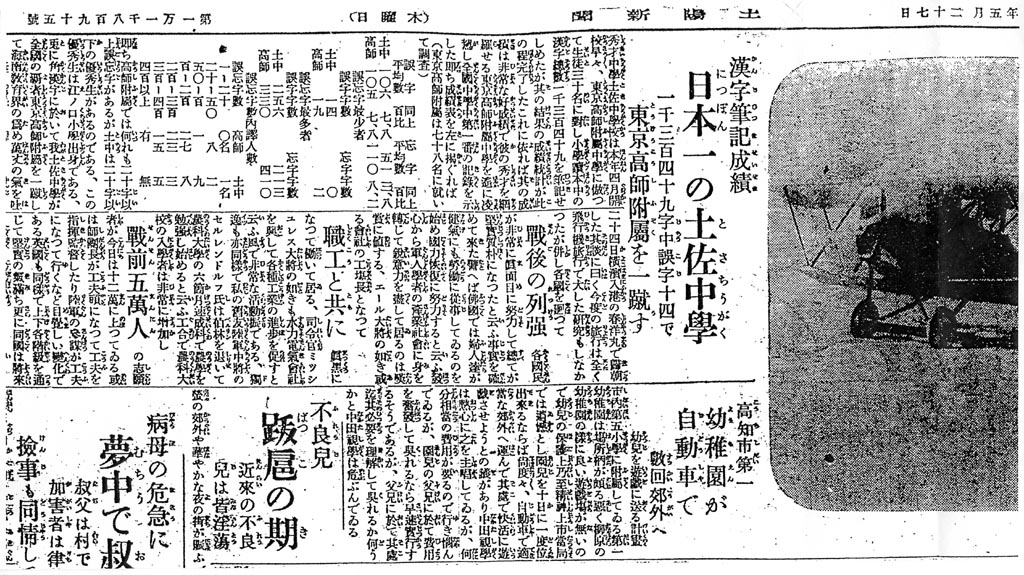 「開校したばかりの土佐中が漢字筆記で日本一の記録を示した」とある。 土陽新聞大正9年5月27日。右の飛行機が時代を示している。 |
|---|
「“上方わらべ歌絵本”の研究」
中城正堯(30回) 2017.08.20
 筆者近影 |
|---|
この絵本は、テーマが「わらべ歌遊び」、印刷技法が「全ページ合羽摺」であり、この両面から類書のない貴重な子ども本であることが判明した。約250年前の上方いたずらっ子たちを、無事現代に甦らせることができ、ほっとしている。
6場面からなるこの絵本は、いずれも画面いっぱいに子どもたちの遊び戯れる姿が描かれ、上部にわらべ歌が添えてある。では、2場面を紹介しよう。
1.お万どこ行った
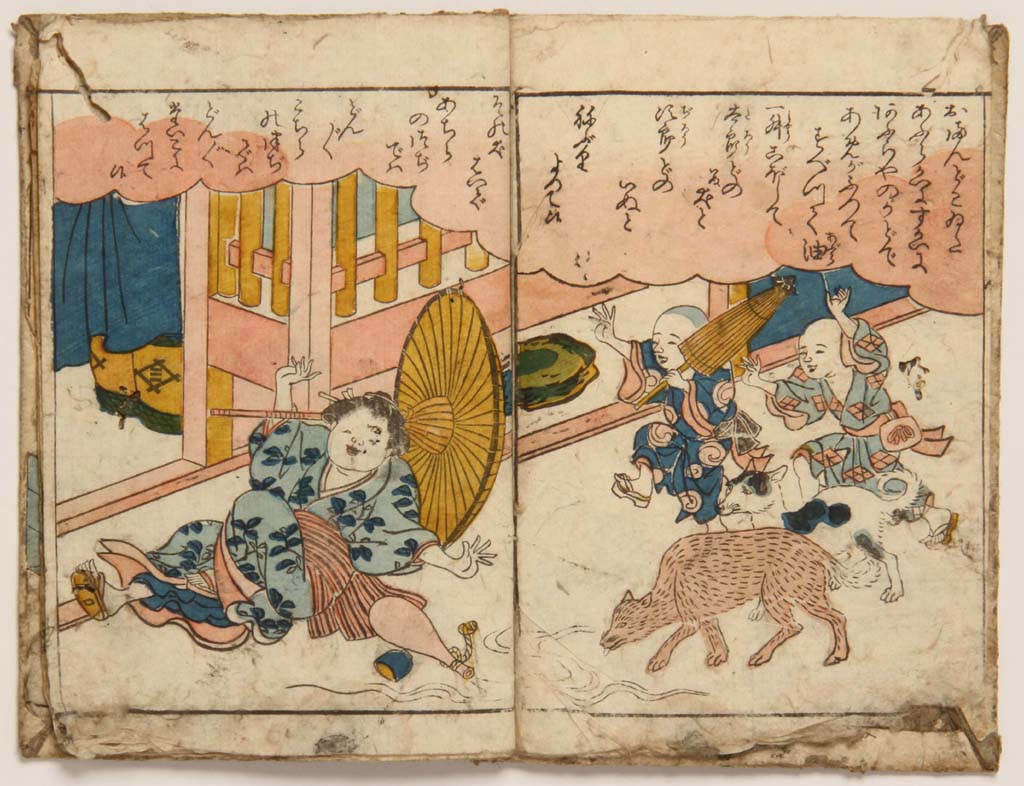 |
|---|
2.子買を子買を
 |
|---|
*なお、全文閲覧をご希望の方はお知らせください。抜刷を進呈致します。 高知新聞で紹介
「“上方わらべ歌絵本”の研究」
中城正堯(30回) 2017.10.03
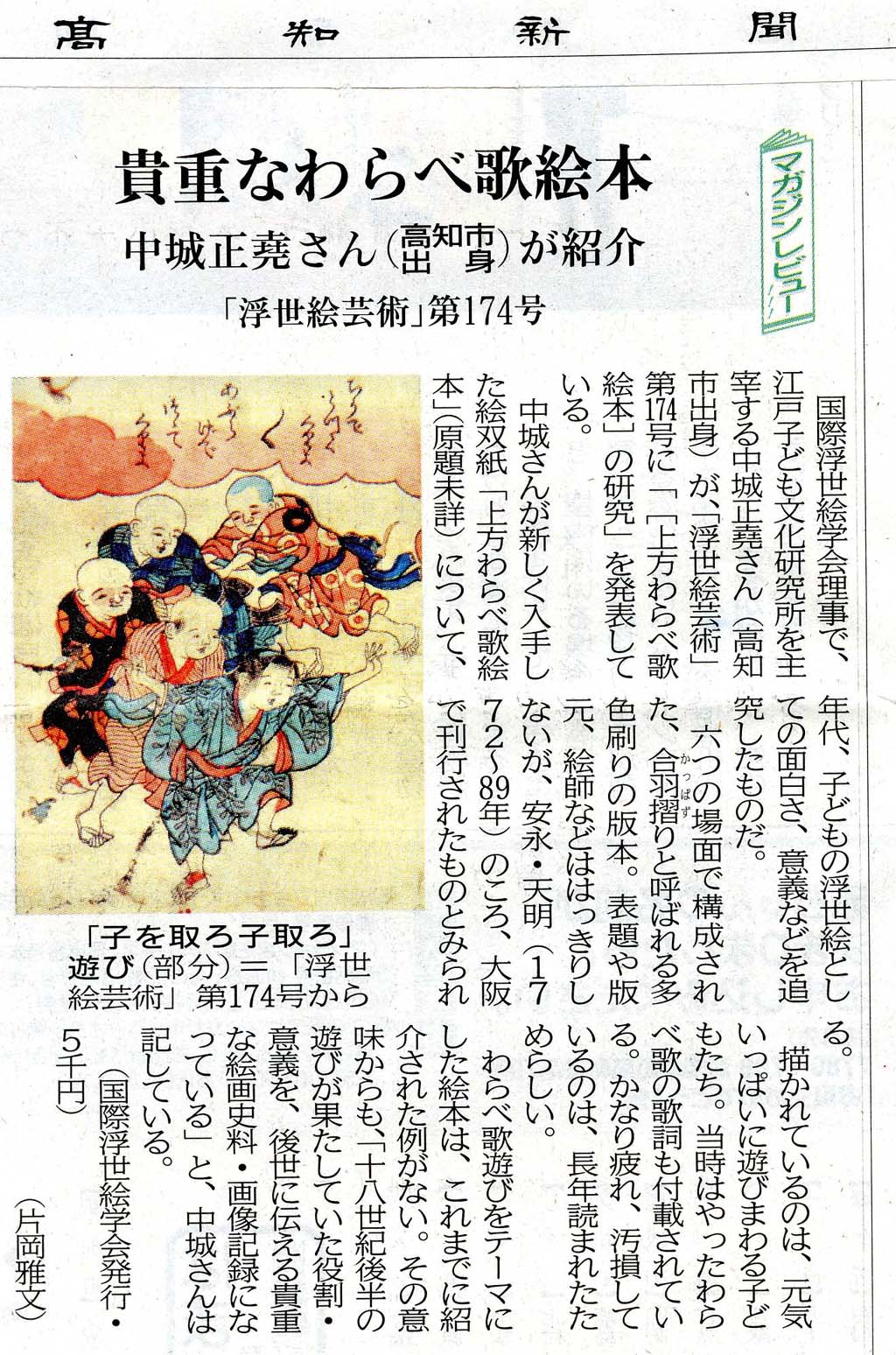 |
|---|
高知新聞9月26日付の学芸欄に、拙論「〈上方わらべ歌絵本〉の研究」の紹介記事が掲載されましたので、添付致します。
この論文は、国際浮世絵学会の研究誌「浮世絵芸術」第174号に発表したものです。 浮世絵展のお知らせ……町田市立国際版画美術館で開催中、11月23日まで
「浮世絵にみる子どもたちの文明開化」
中城正堯(30回) 2017.10.10
 筆者近影 |
|---|
本展は中城(国際浮世絵学会理事)が監修、図録に「文明開化と学校で激変した“子どもの天国”」を執筆しています。同美術館は、小田急・JR横浜線「町田」より徒歩15分、℡042-724-5656です。
 山本昇雲 「いま姿 おすずみ」 |
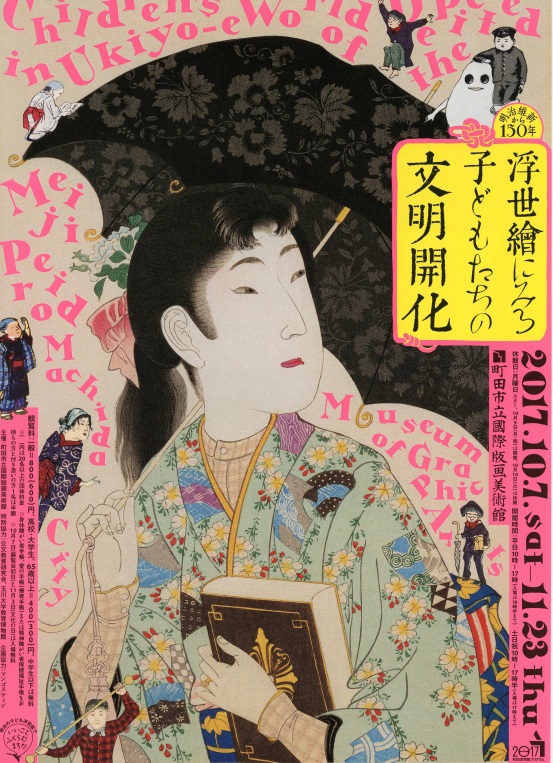 同展覧会チラシ 画は楊洲周延 |
|---|
『SAWAKOGODA合田佐和子光へ向かう旅』刊行
中城正堯(30回) 2017.10.20
昨年2月に亡くなった合田佐和子さん(34回)は、現代アートの旗手として、画家の枠を超えたさまざまな分野で活動をしてきただけに、逝去を惜しむ声が多く、唐十郎氏などを発起人とする「お見送りする会」はじめ、数多くの追悼展や出版記念展が開かれてきた。
このほど、平凡社コロナ・ブックスとして『SAWAKO GODA 合田佐和子 光へ向かう旅』が刊行されたので、ご紹介する。帯に「少女の夢を、呼び醒ます―。没後初の作品集」とあり、油彩・オブジェ・写真など多彩な作品と、親交のあった巌谷國士・吉本ばなな等の各氏がエッセイを寄せている。(定価:本体2,000円)
また、お嬢様の合田ノブヨさんも、新作コラージュの作品集「箱庭の娘たち」を出版、その出版記念展が、東京・恵比寿の「Galerie LIBRAIRIE6」(地下鉄・JR恵比寿駅西口より徒歩2分、℡03-6452-3345)で、11月4日~26日まで開催される。
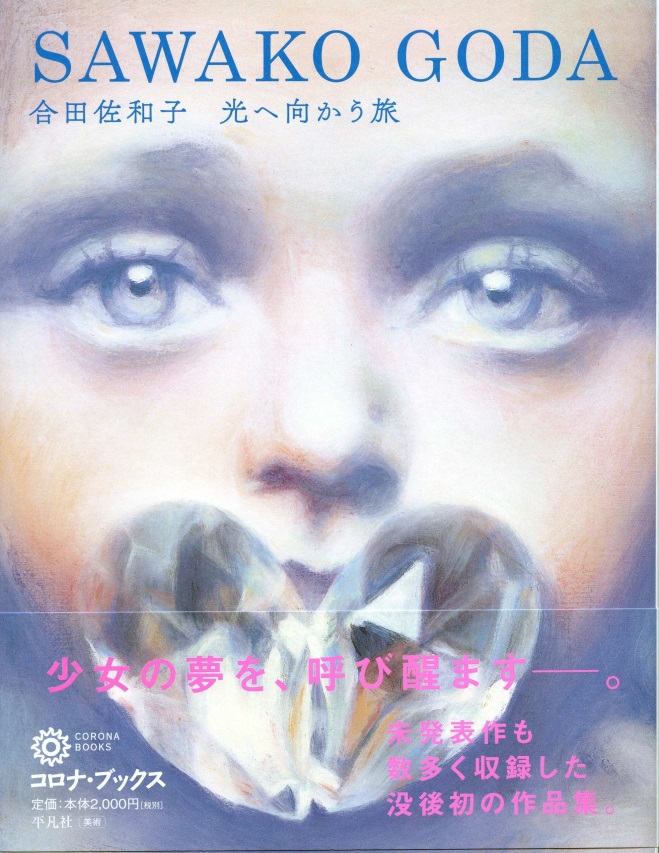 『SAWAKO GODA 合田佐和子 光へ向かう旅』の表紙 |
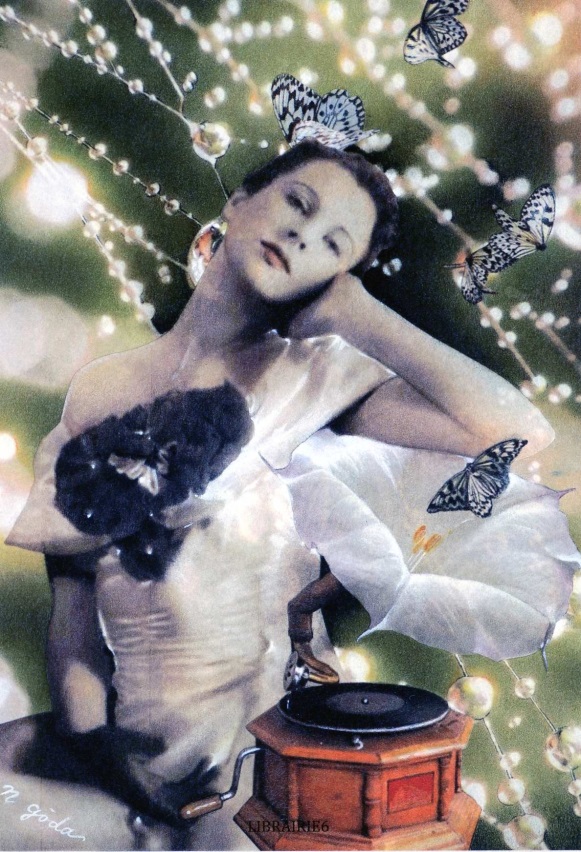 合田ノブヨ「箱庭の娘たち」出版記念展の案内状より |
|---|
中国版画・中城コレクション
中城正堯(30回) 2018.01.02
 筆者近影 |
|---|
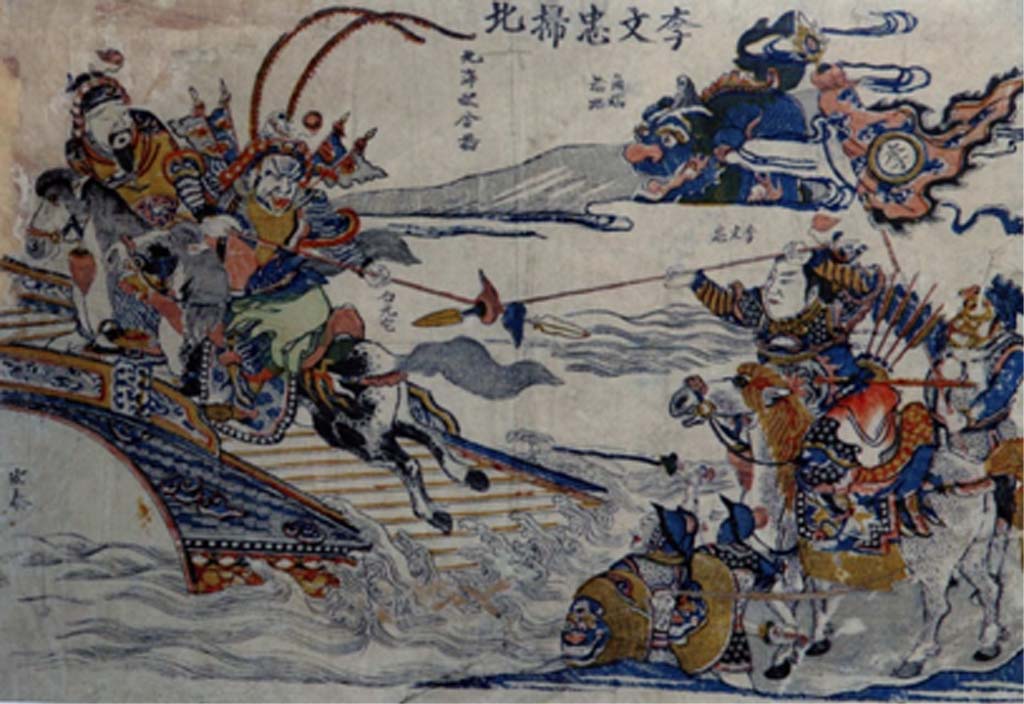 「李文忠掃北」(蘇州・清朝中期) |
|---|
 「宋王観景楊八姐遊春」(天津楊柳青・中華民国) |
|---|
町田市立国際版画美術館:町田市原町田4-28-1(小田急・JR横浜線町田駅より徒歩15分)℡042-726-2771
-倉橋由美子、合田佐和子、田島征彦・征三兄弟、坂東眞砂子-
母校出身“素顔のアーティスト”
中城正堯(30回) 2018.03.25
 著者近影………背景は拙宅の桃で、 43年前に「こばえ」から育てたもの。 |
|---|
ここでは、筆山会での発表内容に出席者の反響も加えて順次ご報告したい。拙文が、現代日本を代表する各分野のアーティストとして輝くこれら同窓生の作品を、あらためて愛読・鑑賞する機会になるとともに、皆様が知る別の素顔を回想してお知らせいただけると、大変幸いである。残念ながら女性3人はすべて鬼籍に入ってしまったが、作品は多くのファンに愛され続けている。では、倉橋由美子さんから始めよう。(本文では、敬称を省略させていただく)
母校出身“素顔のアーティスト” (Ⅰ)
『パルタイ』で文壇に衝撃のデビュー 倉橋由美子(29回)
お茶の水での再会、帰郷・結婚・留学
 倉橋由美子 (明治大学「倉橋由美子展」目録より) |
|---|
相手は二人連れであり、とっさに黙礼を交わしただけですれ違った。東大の竹内は三年になって本郷に来ていたし、倉橋は日本女子衛生短大を経て明治大学に入ったので、同級生として久しぶりに再会したのだろうと単純に思っていた。ところが、夏休みになって帰郷、高知市街に出て喫茶店プリンスに入ると、ここでもお二人に出会った。ようやくその親密さに気付き、今度は「またお会いしましたね」と声をかけた。
それから2年後、筆者が学研で編集者のスタートをきって間もない昭和35年に、明大4年生の倉橋は、『パルタイ』で文壇へ衝撃的な登場をとげた。明治大学新聞に発表直後から話題となって文芸誌に転載、さらに同年末には文藝春秋社から単行本として刊行された。この本の帯に推薦文を遠藤周作とともに寄せた倉橋の恩師で評論家・平野謙は、「革命運動の根ぶかい純粋性と観念性を一学生に具現した作品」であり、「大江健三郎の処女作をみつけたときに似た興奮をおぼえる」と、斬新なこの作品に出会った感激を吐露していた。
筆者も一読し、抽象的・寓話的な独自の作風とされながらも、当時の革新政党による学生を巻き込んでの労働者へのオルグ活動の世界が鮮やかに捉えられているのに驚嘆した。知識だけで描ける文章ではなく、実態を把握したうえでの創作と読み取れた。竹内の協力も相まって倉橋の才能が開花したであろうと推測した。竹内は東大経済学部大学院を終えると成蹊大学教授となり、経済思想史・経済倫理学で業績を挙げるとともに、経済エッセイでも数々の名文を残したが、平成23年に逝去した。
後に聞くと、倉橋は土佐中高時代には受験勉強そっちのけで文学全集の作品を破読、「“くまてん”(吉本泰喜先生)のお陰で漢文・漢詩が好きになり、母親の反対を押し切って文学部に入学、仏文を専攻してカフカ、カミュ、サルトルに親しんだという。大学では欧米の新しい文学の潮流と、学生運動の先端に触れ、鮮烈な倉橋文学が誕生、純文学の新鋭として出版各社から追いかけられることとなる。
『パルタイ』は35年度上期芥川賞候補になったが、最終審査で北杜夫の『夜と霧の隅で』と競い、二作同時選定の意見も出たが結局北のみが選ばれる。倉橋の作品は、テーマも文体もあまりにも斬新だっただけに拒否反応を示す評論家もいたのだろう。翌年度も『暗い旅』が候補に挙がるが選にもれる。この時の受賞者は、後に夕刊紙・週刊誌でポルノ小説を乱作する宇能鴻一郎であった。時を経て池袋の場末の居酒屋で、ひと仕事を終え、黙々と杯を傾ける宇能を何度か見かけたが、受賞時の面影はなかった。選考委員の先見性が疑われる選考だった。『パルタイ』は、36年に第12回女流文学賞を受賞する。
昭和37年、明大大学院に進んでいた倉橋は歯科医だった父の急逝で退学し、土佐山田町の自宅に帰る。この際に、同年婦人公論女流新人賞を受賞したものの次作の執筆に苦慮していた宮尾登美子や、高知支局にいたNHKの熊谷冨裕、朝日新聞の米倉守(後に美術記者として活躍)と出会う。旧知の西岡瑠璃子先輩(28回)とも再会する。そして39年には、宮尾の仲人で急遽熊谷と結婚する。後に関東同窓会の『筆山』4号での筆者のインタビューに応え、結婚のいきさつをこう語ってくれた。「宮尾さんの紹介で、熊谷と生まれて初めてのお見合いをしたのです。『ものを書くなら結婚した方がいい。食べさせてやる』という言葉に、あまりの感激で、ただ『はい』と、いってしまいました」。 見合いの直後に伊藤整などの推薦で、フルブライト委員会からアメリカ留学の話が来たため、急遽三翠園で挙式をしている。「結婚のいきさつは秘密の約束だったのに、宮尾さんが書いた」とも、語っていた。結婚後に二人はアイオワ州立大で1年間の留学生活を過ごす。熊谷はNHKを退職して独立、映像プロデューサーとなる。
旺盛な執筆活動、旧友とも交流
アメリカから帰国後、旺盛な執筆活動を再開するが、二人のお嬢さんにも恵まれ、主婦としての役割も楽しむ。昭和47年末から半年ほどは、一家でポルトガルへ渡って暮らしている。昭和50年には、早くも『倉橋由美子全作品集』(全8巻)が新潮社から出る。
 右から倉橋、公文公、浅井伴泰(筆者撮影) |
|---|
インタビューを掲載した『筆山』が届いたと電話をくださったとき、印象に残っているのは、「あれは書かなかったねえ」である。「あれ」とは、学生時代のお茶の水・高知での出会いだ。続けて、「彼の奥さんも高知の人なので気にするといけないので・・・」と、気配りをみせていた。竹内は、昭和52年に『イソップ経済学』、その後『世界名作の経済倫理学』で、古典物語を素材に登場人物の思想と行動を分析、軽妙なエッセイを残している。つい、倉橋が昭和59年に発表した『大人のための残酷童話』や、続く『老人のための残酷童話』を連想する。竹内は、ギリシャ悲劇からカミュ『異邦人』まで取上げているが、各名作の末尾には「教訓」を添えてあり、これは倉橋の『残酷童話』でも同様である。
竹内もまた、「公文先生の蔵書」というエッセイで、公文の思い出を「それこそハレー彗星級の知的巨人だった」「私は物に憑かれたように“公文図書館”の本を読んだ」と記している。手にした本は、数学者デデキントの『連続数と無理数』から、自然科学、歴史、文学におんでおり、イソップ物語も土佐中時代にこの図書館で見付けたようだ。
奇想天外な創作と忍び寄る病魔
倉橋は著名になっても文壇で群を作ることはなかったが、芥川賞で競った北杜夫、そして重鎮・中村真一郎とは仲がよかったようだ。筆者も中村にはお世話になり、いつだったか熱海の別荘に銅版画家・木原康行とまねかれ、中村夫人(詩人・佐岐えりぬ)ともども飲み明かした。その際に倉橋の話になって、「素晴らしい作家だが、男女の愛情描写やエロスがまだ不足。もっと遊ぶように言ってくれ」と、告げられた。後日、倉橋に話すと、「私も“小説に艶がない、もっと遊べ”と直接言われた」とのことだった。神宮前の中村宅では、たまたま親友・加藤周一、堀田善衛との座に同席した。二人は中村をからかうように「彼は昔から我々が政治談義に熱中すると居眠りを始めるが、女の話になるとむっくり起きてくる」と打ち明けてくれた。小説家にとって、エロスは不可欠のようだった。
後に、坂東眞砂子(51回)が『山妣(やまはは)』で直木賞をとった勢いからか「いまの日本の小説は面白くない。倉橋さんも・・・」と広言していた。倉橋と会った際に、このことにも話が及んだが、「元気があっていいねえ」と受け流していた。すでに昭和59年に発表した『大人のための残酷童話』の「あとがき」で、「近頃の小説は面白くないという説があります」と書き、その原因を解明しつつ、「大人に喜ばれる残酷で超現実の世界やエロチックに傾く大人の童話に手を付けた」と述べている。
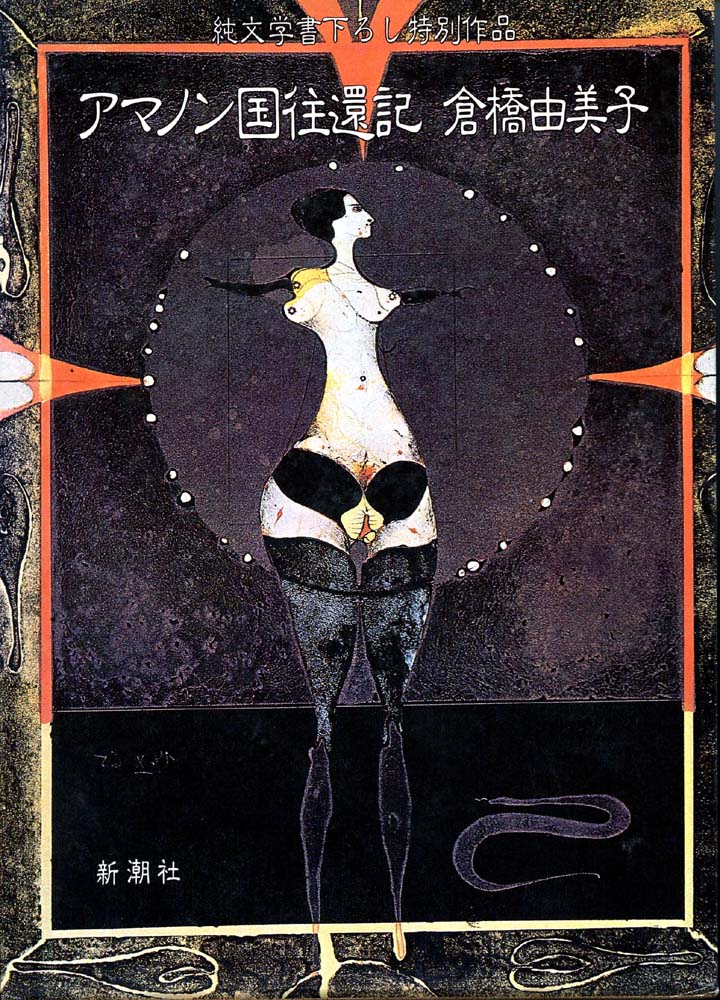 『アマノン国往還記』(新潮社)表紙 |
|---|
平成7年には、同学年の福島清三から「月刊『文芸春秋』の「同級生交歓」に、泉谷良彦・中山剛吉・大脇順和・倉橋などと出たい。交渉をたのむ」と話があった。同社の知人に相談すると、「編集部は倉橋さんから申し込んで欲しいといっている」との返事。早速本人にお願いしたが、「私から頼むと編集部に借りを作る」と、最初は躊躇していた。出版界では、借りを作ると書きたくない仕事も断われなくなるのだ。しかし、クラスメートの願いを聞き入れて、話をまとめてくださった。大脇にとっては「中学時代の懐かしい少女」、福島にとっては「在学中から主婦型」だった倉橋との久しぶりの再会だった。
やがて平成10年頃になると、電話で体調不良をこぼすようになり、「耳鳴りがひどく、仕事にならない。あちこち耳鼻科の名医を訪ねたが原因不明なの」とのことだった。そして、「耳でなく心臓に問題があると、やっと分かった。しかし治療は困難みたい。気晴らしに体調の良いときに四国遍路を始めた」と伝えてきた。参考までに「高群逸枝の『お遍路』が面白い」と伝えると、「読む読む」といっていた。 病とともに、倉橋が珍しく愚痴をこぼしたのは、夫君の熊谷がかつて沖縄海洋博の仕事で赤字を背負った話だった。プロポーズの言葉と違ってフリーの映像作家はさまざまな不安要素を抱え込んでおり、夫の仕事ぶりは心配のタネだったようだ。晩年の長編『アマノン国往還記』の付録には、「もし女性(私)が育児と男性から解放される時代がきたら、という“仮定”に立って書いてみた(笑)」とある。ぜひ倉橋の切なる願望を、この作品からさぐって欲しい。
平成17年3月に筆者は肺血栓塞栓症で突然倒れた。一月半の入院で命拾いをして自宅療養中だった6月、「倉橋由美子、拡張型心筋症で永眠、享年69歳」の知らせが届いた。
望まれる作品誕生の背景研究
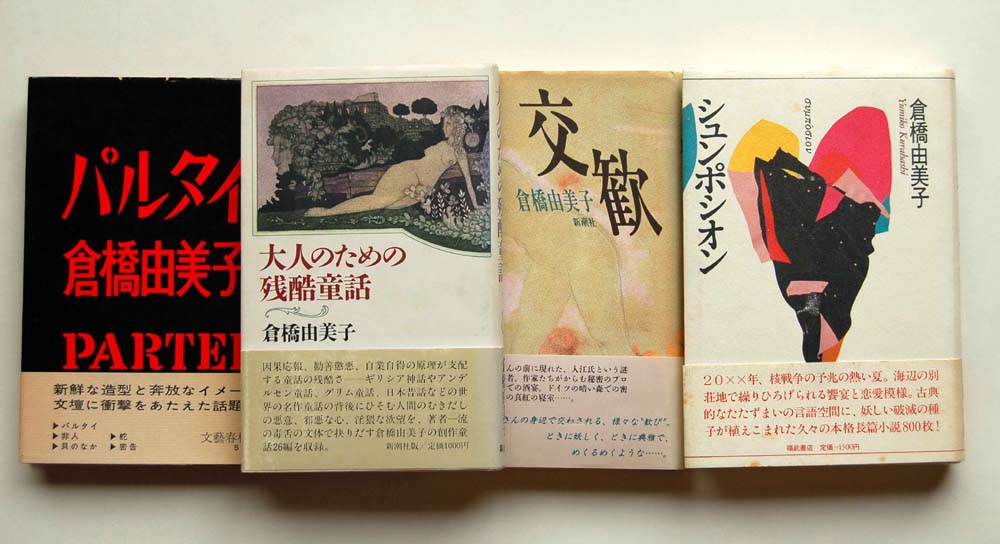 『パルタイ』(文藝春秋)をはじめ著書の数々 |
|---|
当時、近代文学を専攻した大学生の論文テーマとして、倉橋人気の高いことは聞いていたが、海外でもこれほど評価が高いとは気付かなかった。この倉橋文学誕生には、明治大学でのフランス文学専攻とともに、土佐中高での読書や学び、そして学友・教師との交流 が欠かせない要素であった。西岡瑠璃子たちの協力で、高知県文学館に倉橋コーナーができていると聞くが、母校でもさらなる資料収集と、倉橋文学誕生の背景研究が望まれる。 母校出身“素顔のアーティスト”に嬉しい反響
中城正堯(30回) 2018.04.25
 筆者近影 |
|---|
まず、最初の読者であった藤宗俊一編集長からで、<倉橋さんの記事を読んでいて、『山田に帰った』という言葉で、「たしか、当時の部長だった宮地さん(40回生)ら女性陣が山田のご自宅に取材に伺ったはずだけど……。」調べてみると60号に掲載されていましたのでpdfで添付します。当時、私は中学3年生で KURAHASHI Who???の世界にいました。それが、半年後には編集長に上り詰めるとは、新聞部も人材が不足していたのですね。>とのこと。
さすがに名編集長で、病後の体でありながら、昔々の関連記事をきちんと思い出して送ってくれた。どうか、宮地(島崎)敦子記者のインタビュー記事「すぽっと ストーリーのない小説 倉橋由美子さん」をお読みいただきたい。
 「すぽっと ストーリーのない小説 倉橋由美子さん」 |
|---|
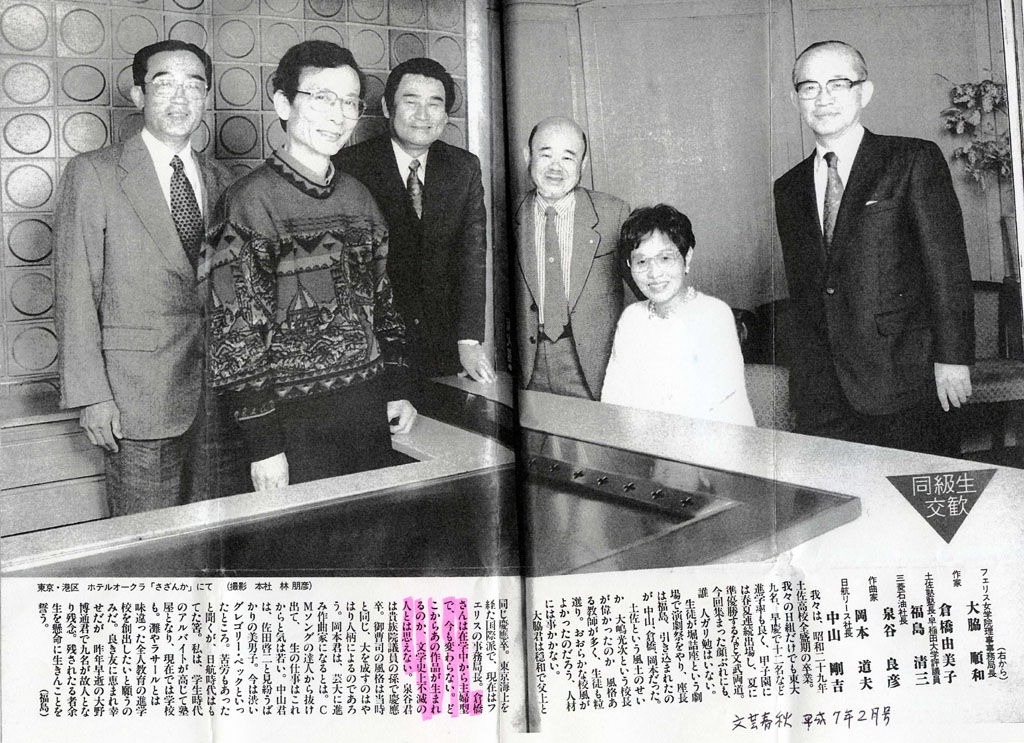 『文芸春秋』平成7年2月号の「同級生交歓」の誌面コピー |
|---|
久武慶蔵(30回)君は、「倉橋文学は実存主義文学の模倣にすぎないとの批判に対して、彼女は文学は本質的には模倣だと答え、ハチキンの気概を感じ、“土佐人の原点”をみました」とのメールを寄せてくれた。
この記事をKPCのHPにアップしたことは、会員以外にもメールで知らせ、閲覧を呼びかけた。反響は、どうしても倉橋さんと近い世代に限られたが、向陽プレスクラブの存在告知にいくらかはつながったようだ、前田憲一(37回)さんのように、初めてこのHPを開き、多彩な情報にビックリした後輩もいた。 母校出身“素顔のアーティスト”(Ⅱ)-1(前編)
焼け跡で誕生した前衛アートの女神合田佐和子(34回)
中城正堯(30回) 2018.05.03
型破りのオブジェからスタート
熱烈なファンのいた合田佐和子だが、残念ながら同窓生では同学年かよほどの美術好きでないと、その作品に触れたことがなく、名前も記憶に残ってないだろう。闘病の末に平成28年2月に亡くなると、4月には嵐山光三郎、巌谷國士、唐十郎などを発起人に、「お見送りする会」が品川プリンスホテルで開催され、交遊のあった前衛文化人や現代アートの女神とあがめたファンが多数つどい、マルチアーティストとしての合田の多彩な足跡を偲んだ。翌年1月には、遺稿集とも言うべき『90度のまなざし』(港の人)、8月には作品集『合田佐和子 光へ向かう旅』(平凡社)と、相次いで刊行されたのもその人気故である。追悼展も、日本橋「みうらじろうギャラリー」などで次々と開かれた。
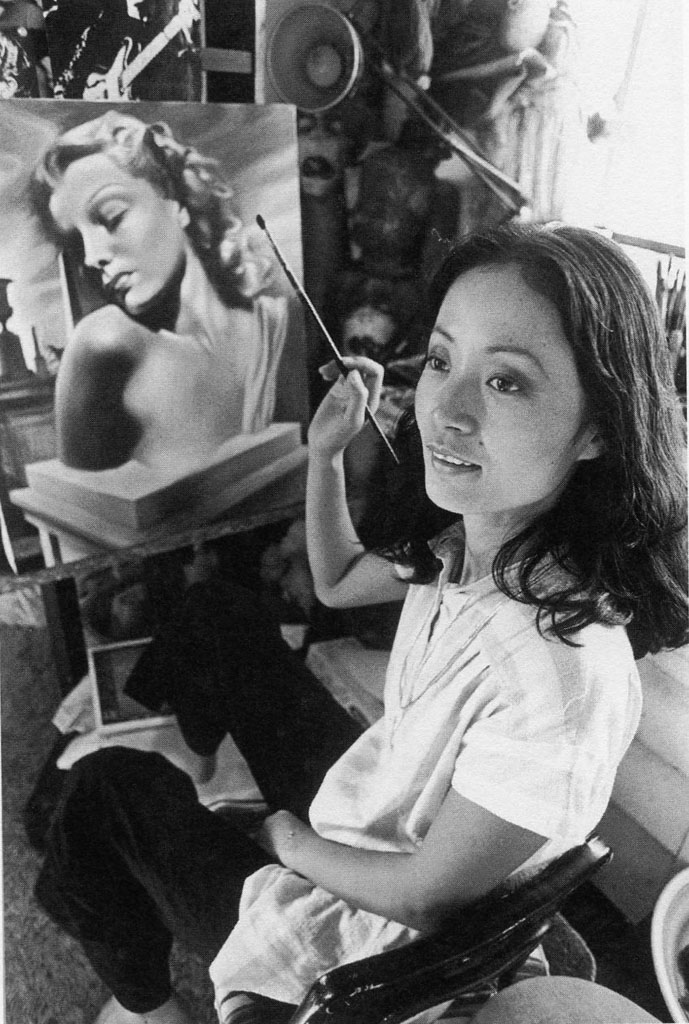 絵筆を持つ合田佐和子(『90度のまなざし』より) |
|---|
略歴では触れられていないが戦争中は広島県呉市で過ごし、5歳で終戦を迎え、高知市へもどって焼け跡で遊んで育つ。後にこの頃を回想し「焼け跡の中で、色ガラスが溶けて土や石と合体した塊を発見、半狂乱になって集めたりした。後年、この原体験は、ガラス箱のオブジェなどとなって、くり返し現われてくる」(「現れては消えるあのシーン、あの俳優」『キネマ旬報』1995年4月下旬号)と記している。小学校ではプロマイド集めに熱中、嵐寬寿郎の鞍馬天狗などを町はずれまでかけずり回って探し集めたという。
父は広島で繊維メーカーの技術者として働いた経験を生かし、戦後の高知では衛生材料製造業を興して成功を収めていた。比較的裕福なインテリ一家で、高知市が始めた中央の文化人を招いての夏期市民大学を家族で受講するなど、文学や芸術にも関心が高かった。
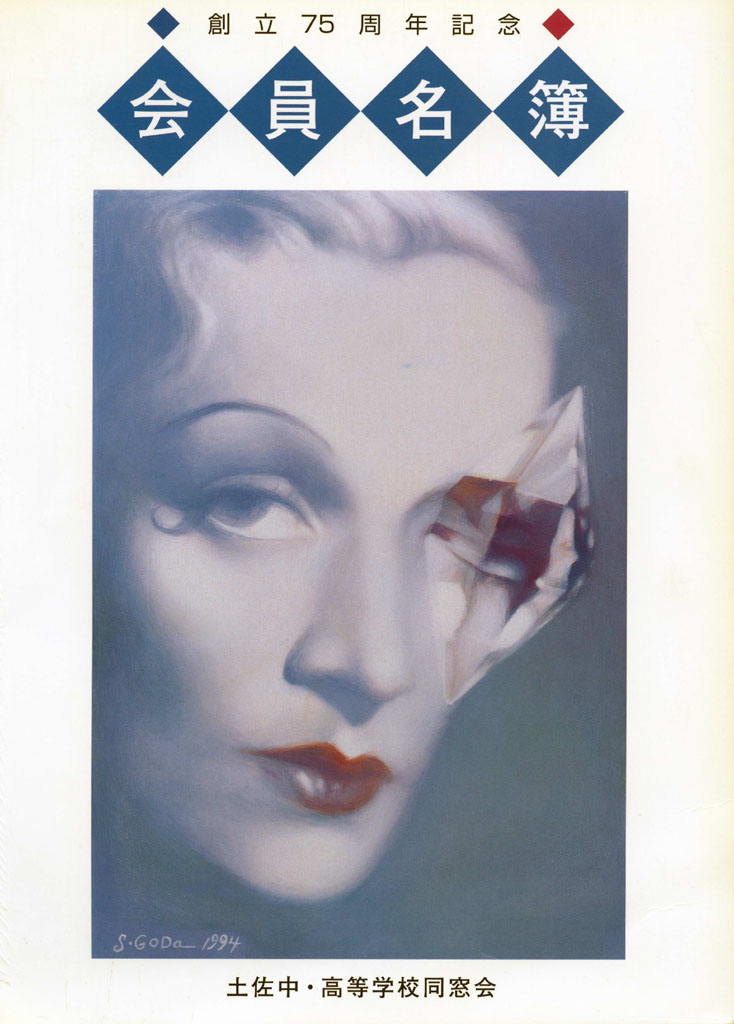 土佐中高『会員名簿』2015年表紙 「クリスタルブルーなデートリヒ1」 |
|---|
彼女の略歴紹介で目をひくのは、画家では納まらない多彩な美術ジャンルでの活躍である。オブジェから油彩画、写真、舞台美術など自由自在に異種領域間をワープ、どの分野でも合田カラーで人々を魅了してきた。まずは、合田が制作中の写真と、母校の創立75周年記念『会員名簿』の表紙を飾った「クリスタルブルーなデートリヒ1」から、人と作品を思い起こしていただきたい。そして、彼女の土佐高新聞部時代から中央の美術界での活躍まで、ほぼ60年間の交流で接した素顔をつづり、手向けとしたい。
新聞部の毒舌記者、オンカンが補導
合田は4年後輩であり、出会ったのは筆者が大学時代(昭和30~34)に帰郷、新聞部の活動に参加した際であった。この時期はいわば新聞部の黄金時代で、合田の同期には吉川順三(毎日新聞)、秦洋一(朝日新聞)、国見昭郎(NHK)など、のちにマスコミで大活躍する人材が揃っていた。さらに、浜田晋介や山崎(久永)洋子も編集長として活躍していた。「向陽新聞」も彼らが編集制作の中心であった昭和31年度には、5回も発行している。筆者も夏休みの恒例事業になっていた「先輩大学生に聞く会」や、大嶋校長を囲む座談会などに、よく狩り出された。
 種崎海水浴場での新聞部キャンプ。 前列左が合田、後列は横山・吉川。 |
|---|
彼女は種崎の海水浴場で、「突然の大波をかぶって溺れそうになったとき、先輩に助けられた」と後に語っていたが、これは幻影かも知れない。荒波に立ち向かうのは中学時代から好きだったようで、台風の直後に祖父のスクーターで桂浜に駆けつけ、被害を受けた水族館をのぞいたあと、「決死のゲーム」に挑戦したという。それは、海に突き出た岬の先端に祀られた祠・竜宮への石段を、大波が引きあげて次に打ち寄せる40秒ばかりの間に全力で駆け上ることだった。岬のてっぺんに立って、絶壁にぶつかって落ちる波の「とろけるような奇怪なオブジェの大乱舞」をながめ、はしゃぐためだったと述べている。
高校時代には映画館で補導を受け、強い印象を受ける。「学校帰りに映画館へ入り、“青い麦”を見て、出口で補導された。怒った時はライオンの如く、やさしい時はカンガルーの如し、と自らを“オンカン”と命名した中山(駿馬)先生が、ライオンになって待ちかまえていて、説教された」。
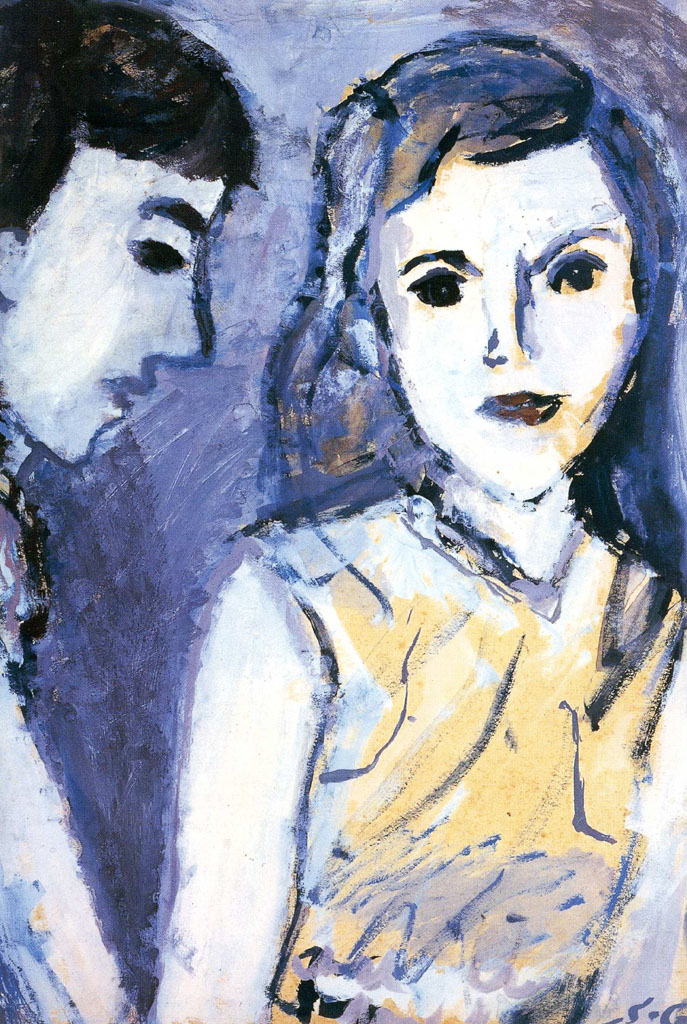 合田14歳の自画像。 (おかざき世界子ども美術博物館蔵) |
|---|
土佐高でアーティスト合田誕生に結びつく大きな出来事は、髙1になった新学期から、美術教師に高崎元尚(16回)が赴任したことである。前任の鎮西忠行も画家だったが、静物や風景を写実的に描く正統派であった。新任の高崎は、東京美術学校(現東京芸大)を出てモダンアート協会や具体美術協会に属し、戦後日本の前衛美術界をリードしてきた人物であった。「生涯現役」を掲げて創作に挑み続け、高く評価されたが、昨年6月高知県立美術館で「高崎元尚新作展-破壊 COLLAPSE-」開催中、94歳で亡くなられた。
高崎の赴任によって、再び絵画への興味を甦らせ、新聞部だけでなく美術部にも出入りするようになった。14歳で描いた自画像が、愛知県の「おかざき世界子ども美術博物館」に収蔵されている。
 高3の新年会に、東京から帰郷して出席。 中列左より2人目が筆者 |
|---|
(後編に続く)
母校出身“素顔のアーティスト”(Ⅱ)-2(後編)焼け跡で誕生した前衛アートの女神合田佐和子(34回)
中城正堯(30回) 2018.05.27
東京での再会と奇怪な大判名刺
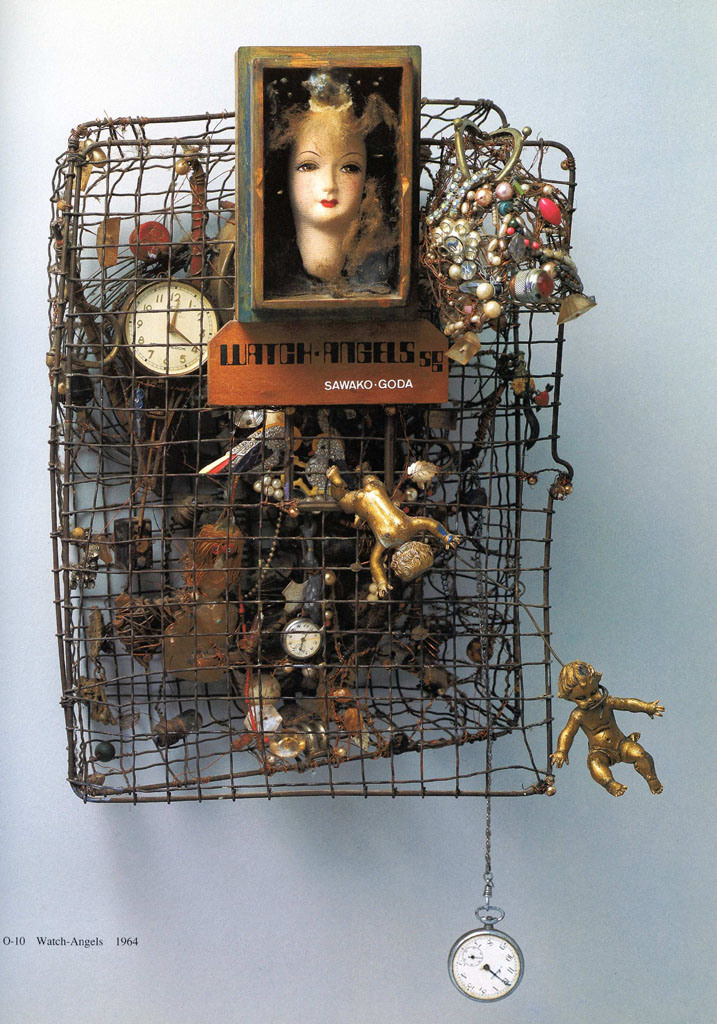 合田のオブジェ「Watch-Angels」。 1964年(『合田佐和子 影像』 渋谷区立松濤美術館より) |
|---|
田島とは初対面だったが、すでに全国観光ポスター展で、土佐沖のかつお釣りを描いた躍動感あふれる作品が金賞を得ており、自信満々だった。力強いタッチの人物や生き物は小学生を読者対象とする学習雑誌にも向いており、興味を示す編集者がいて早速仕事に結びついた。合田はカットやオブジェの写真を見せてくれたが、ちょっと子ども向きではなかった。むろん出版社によっては、合田も歓迎されたようだ。
 上京した新聞部員を迎えた合田たち。 前列左より宮地敦子、江沢憲子、竹内たみ(40回)、森下睦美(31回) |
|---|
この頃合田はガラクタオブジェの制作に熱中、瀧口修造などから認められ、40年(1965)には銀座で初の個展を開く。土佐のやせた少女は、さなぎからチョウへと美しく変身し、個展の前年には同郷の画家・志賀健蔵と結婚、披露宴は高知のホテルで盛大におこなわれた。オブジェは次第に注目を浴び、澁澤龍彦、イサム・ノグチ、白石かずこ、池田満寿夫などからも評価されるようになった。41年1月に長女を出産するが、6月には離婚する。友人には、「経済的にも頼ろうとするばかりで、稼ごうとしない男に愛想を尽かした」と、漏らしている。当時、合田からもらった名刺が残っている。A3の用紙いっぱいに一つ目の妖怪やろくろ首の女などが乱舞しており、氏名・住所・電話は申し訳のように小さく添えてある。目玉への執着もうかがえる。
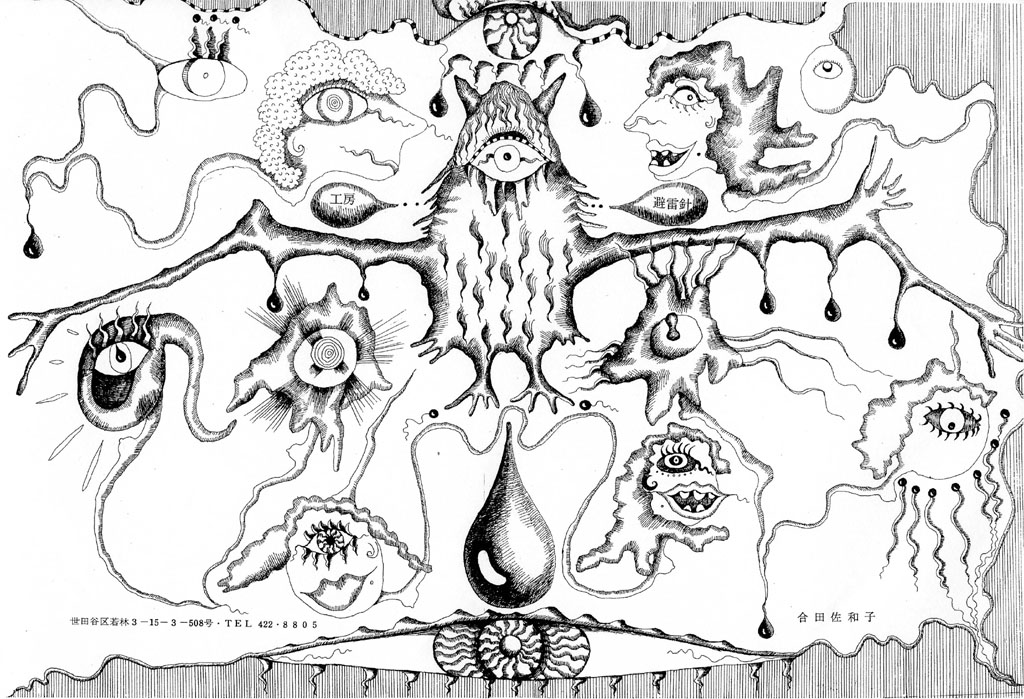 工夫をこらした新人画家合田のイラスト名刺。(筆者蔵) |
|---|
こうして多忙となったなかで、46年1月には彫刻家三木冨雄と結婚、ロックフェラー財団の招聘を受けた三木とともにニューヨークに渡り、8月まで滞在する。ここでアンダーグラウンドの映像作家ジャックと出会い、夜ごと夫婦で廃墟のようなロフトに訪ねたという。
ニューヨークで世界の先鋭美術に触れるとともに、古ぼけた写真を拾ったことが、アーティスト合田の大きな転機となる。油彩画に拒絶反応を示し、立体物のみを制作していた合田は、こう述べている。「N・Yの裏通りで一枚の写真を拾った。二人の老婆と一人の老人が写っている、小さな銀板写真だった。手に取って眺めているうち、ハタと気付いた。アレ、これはすでに二次元ではないか」(「INTRODUCTION」『合田佐和子作品集 パンドラ』PARCO出版)。8月東京に帰ると、経済生活を維持するためにも油彩に取り組む覚悟を決め、渋谷の画材店で店員に油絵の描き方をたずね、絵の具5本と百号のキャンバスを買う。高校時代に見た「甘く、背徳的な」女優たちのプロマイドも収集、こうして、後に代表作となるスター・シリーズが誕生する。
唐十郎に続き寺山修司の演劇に参入
昭和55年(1980)3月には渋谷の西武百貨店美術画廊で「夢の回廊 合田佐和子[ポートレート]展」を開催、作品集「ポートレート」を刊行する。手元に残るこの作品集には、ローマ字のサインとともに1980.3.13と記されている。70年安保後の気怠い街角に、往年の退廃的スターが、エロスと妖気と死の影をまとって再登場、衝撃を与える。以来、生身の人間を描くことはなく、写真を素材に自己流の油彩で描き続ける。
この間、米国から帰国後47年に三木と離婚するが、同年末に次女が誕生する。舞台美術の仕事も広がり、「状況劇場が好きだから、ダメ」と言い続けてきた唐のライバル・寺山修司の天井桟敷にも参画する。演劇「中国の不思議な役人」から、香港ロケによる映画「上海異人娼館」など、寺山作品に欠かせない存在となる。だが、最初に「演劇の世界は地獄だよ」とからかわれたとおり、その仕事は過酷だった。台本が遅れに遅れ、「青ひげ公の城」では、一週間で14景の舞台下絵を描かねばならず、「さび付いた頭をフル回転させ、狂ったように取り組んだ」と語っている。心身ともに消耗の激しい作業だったが、寺山のイメージに見事に応え、喜ばれる。唐組の仕事も終生継続する。
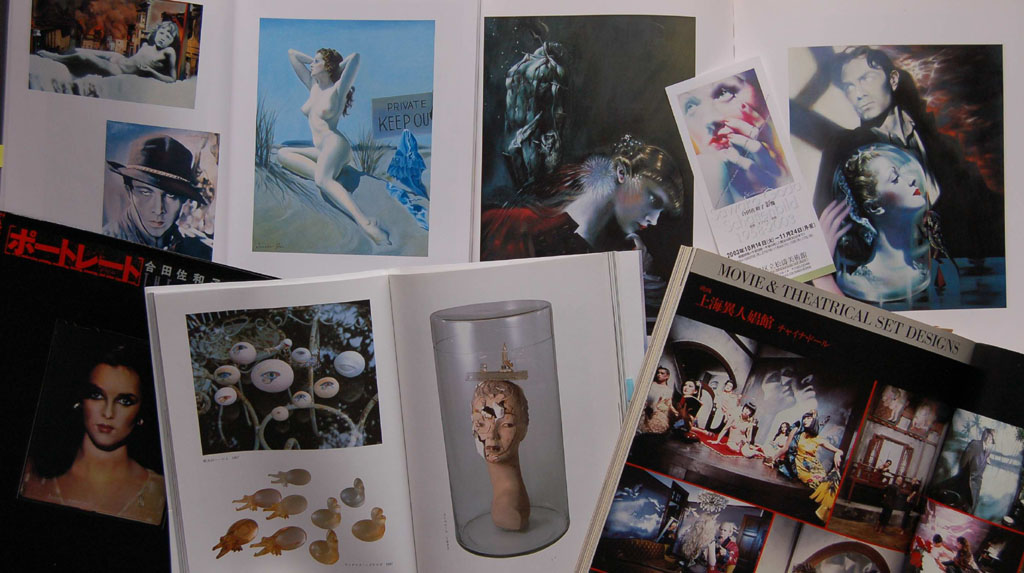 合田の絵画作品、作品集から。 |
|---|
昭和60年(1985)になり、娘二人とエジプト・アスワンに移住すると知らせがあったときは、筆者も訪ねた土地であり、あの砂漠と青空だけが広がる世界への脱出は理解できた。いっぽう、灼熱の村での暮らしに危惧も感じた。一家はヌビア人の村に住み込み、泥の家に居住する。合田は「サバコ、サバコ」と親しまれるが、頻繁に停電が発生、冷房もままならない生活に長女(当時19歳)は早々に帰国、次女(12歳)には「映画もTVもネオンも恋しいヨー!」と嘆かれ、1年足らずで滞在を打ち切る。
滞在中、エジプト村日記を『朝日ジャーナル』に連載、後に『ナイルのほとりで』と題して朝日新聞社から刊行される。この頃、筆者は「船の目玉―海の魔除けの不思議な系譜」を執筆中で、ホルスの目に魅了された合田から、ナイル川の帆船ファルーカの目玉情報の提供を受けた(拙著『アジア魔除け曼荼羅』NTT出版に収録)。朝日新聞では、平成3年(1991)の連載小説「軽蔑」(中上健次)の挿絵を担当、目をテーマに描き続ける。
独自の目で幻想的世界を開拓
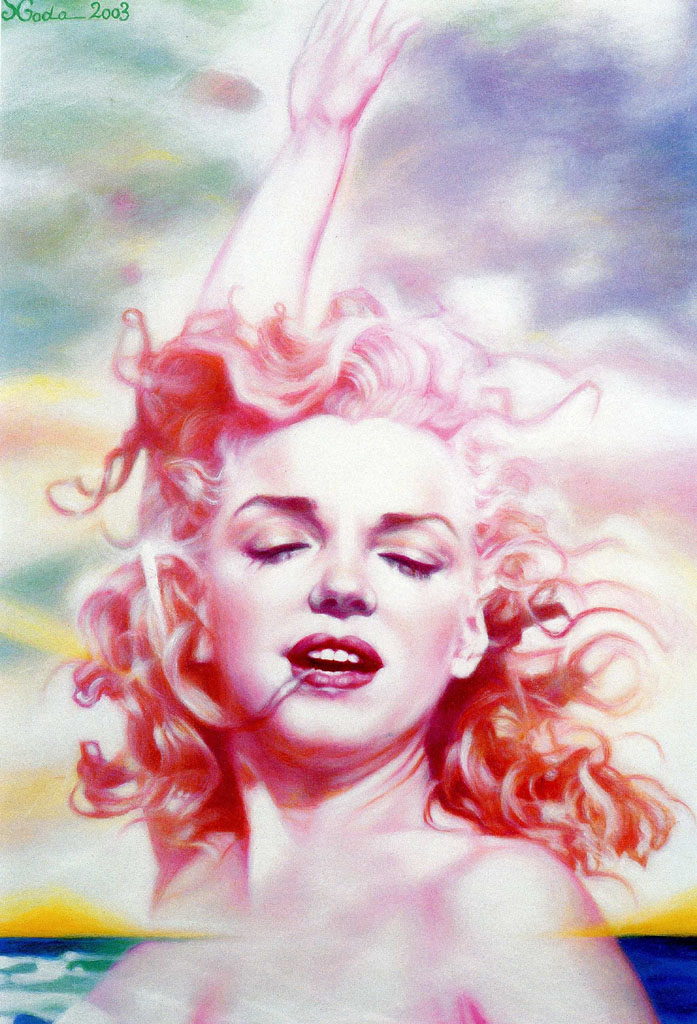 合田佐和子「マリリンの海」 2003年(『合田佐和子 影像』より) |
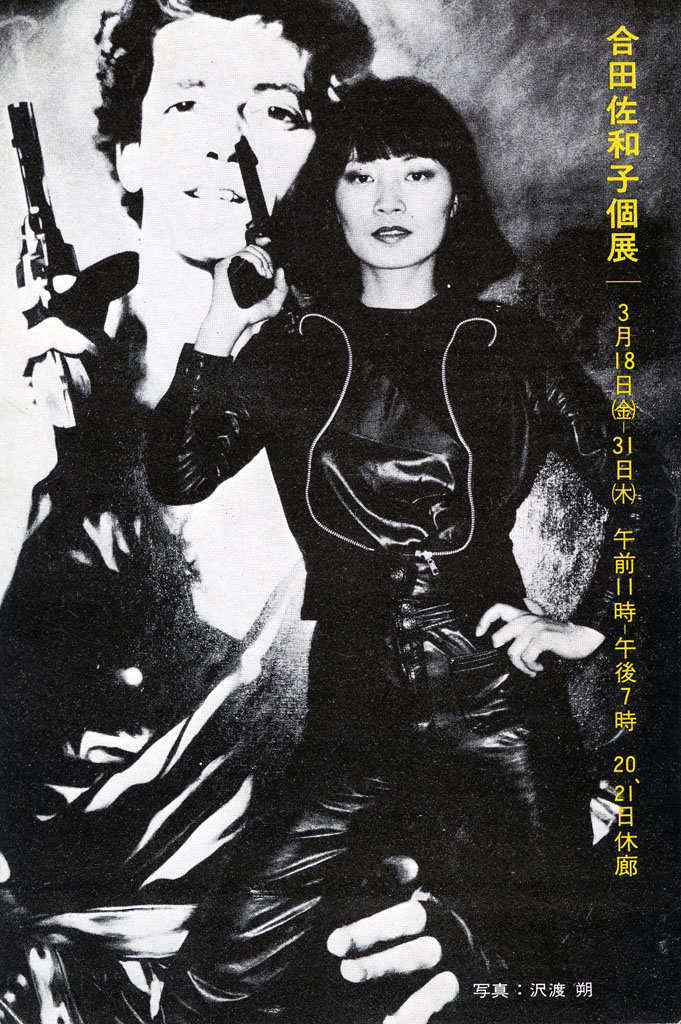 若き日の「合田佐和子個展」 案内状(写真:沢渡朔) 1977年 |
|---|
かつては、小さな個人画廊での個展が中心で異端の画家という存在だったが、次第に時代の先端を行くアーティストとして美術界からも注目されるようになり、民間・公営双方の著名美術館からも声がかかるようになった。特に平成13年(2001)の高知県立美術館<「森村泰昌と合田佐和子」展>と、15年の渋谷区松濤美術館<「合田佐和子 影像 絵画・オブジェ・写真」展>は、彼女の代表作を総集した展覧会で、異分野への果敢な挑戦と斬新な表現を求め続け、戦後の日本美術界に刻印した鮮やかな足跡が読み取れた。
残念ながら平成20年代になると体調を崩すことが多くなり、鎌倉や日本橋の個展に足を運んでも本人の姿はなかった。本人の声を聞くことができたのは22年4月で、土佐高関東同窓会会報への寄稿を、新聞部出身の永森裕子(44回)から頼まれて電話した。元気な声で快諾してくれ、筆者の病状(肺血栓)を心配し、『脳梗塞糖尿病を救うミミズの酵素』をぜひ読むように薦めてくれた。親しい間柄の栗本慎一郎(経済人類学者)が、脳梗塞の治療回復の体験から綴った本で、合田の病にも効果があったという。しかし、個展の作品制作に追われて体調が悪化、結局原稿は書けず、堀内稔久(32回)が代わってくれた。
かつて寺山修司は、「合田佐和子の怪奇幻想のだまし絵は、絵の具に毒薬を溶かして描くかと思われるほど、悪意と哄笑にあふれるものである。・・・だが、そうした絵を描く合田佐和子自身は、支那服の似合う絶世の美女である」(「密蝋画」)と賛辞を惜しまなかった。
 合田佐和子展の各種案内状。 |
|---|
大地のエネルギーを絵筆で歌う田島征彦・征三兄弟(34回)
中城正堯(30回) 2018.06.07
「働く人」と「のら犬」へのまなざし
 田島征三の近影(本人提供) |
|---|
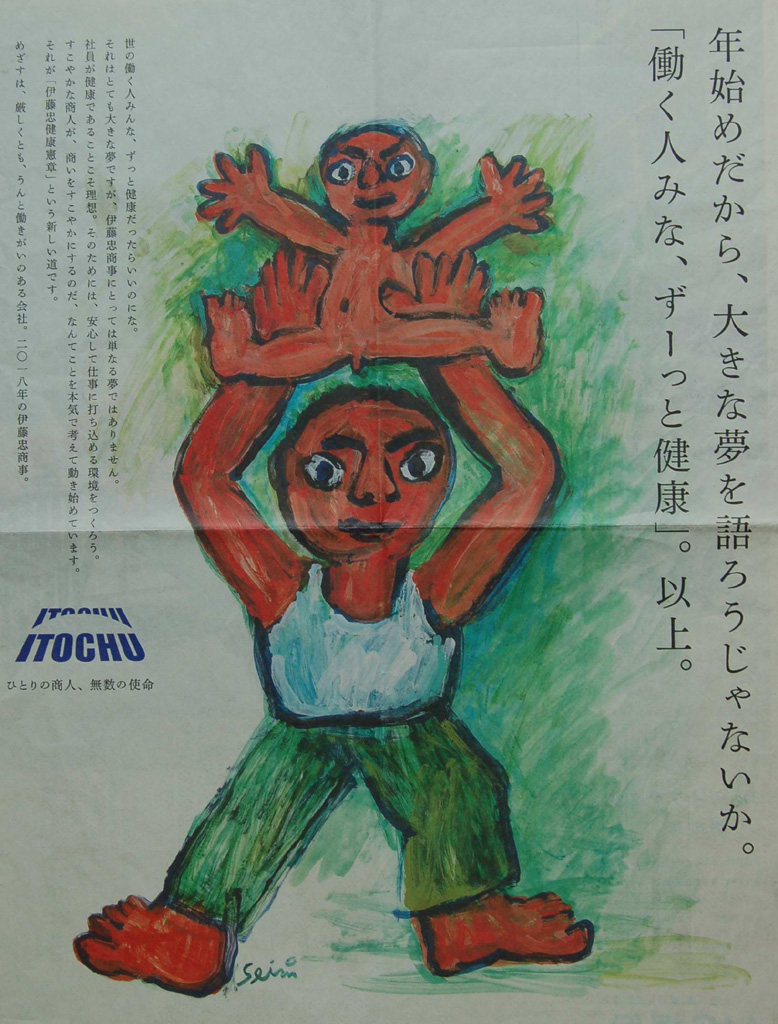 今年正月の伊藤忠商事広告、絵・田島征三。 |
|---|
筆者のとまどいを察したのか、「日の出村のごみ闘争では、豊かな自然をぶちこわす行政と戦ったが、別に何でも反対じゃない。いま、廃校を丸ごと作品にした〈絵本と木の実の美術館〉のある新潟県十日町市では、市長をはじめ行政とも仲ようやりゆう」とのこと。なお、伊藤忠では元厚生労働省事務次官の村木厚子(49回)が社外取締役を務めている。
こうして昨年、田島征三は大学時代の高知県観光ポスターでの金賞以来、再度広告の世界で脚光を浴びた。それにとどまらずに新作絵本でも、大がかりな野外展示(インスタレーション)でも、新たな挑戦を始めている。
 アトリエの田島征彦(くもん出版提供) 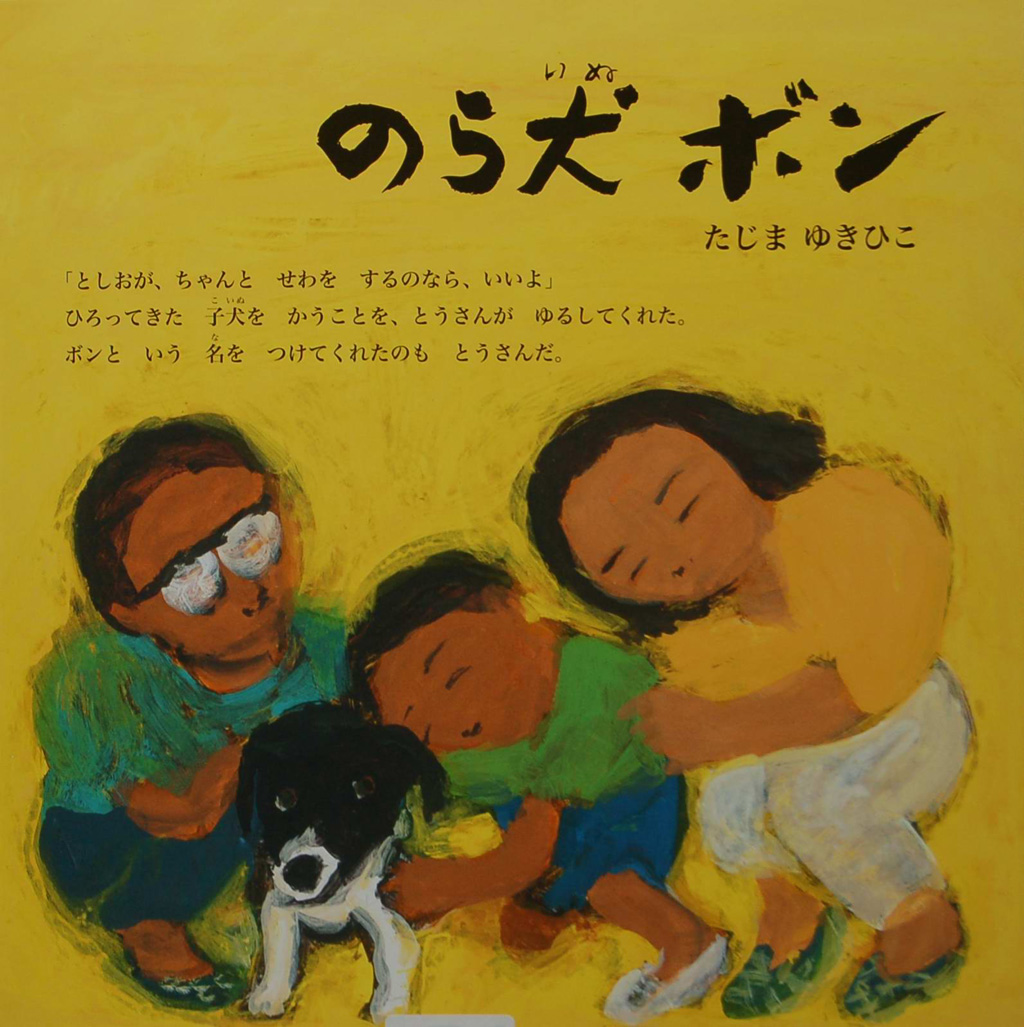 『のら犬ボン』扉絵、田島征彦。 |
|---|
なお、征三は「たしませいぞう」、征彦は「たじまゆきひこ」と、姓の読み方を変えている。混同を避けるためだが、若い頃はしばしば同一視や取り違えがあった。
兄弟で日本・世界の絵本賞を総なめ
この一卵性双生児と筆者との出会いは、合田佐和子(34回)の項で書いたように1962年(昭和37)で、まず弟征三であった。当時、征三は多摩美術学校(現多摩美術大学)図案科在学中で、学習誌にいくらかカットを描いてもらった。やがて京都市立美術大学(現京都市立芸術大学)染織図案科を出た兄・征彦も紹介された。ただ、1970年頃から筆者は大人ものの編集部に異動したので、二人から個展などの案内状をもらっても、仕事での付き合いは途絶えていた。征三が個展で「作品の大小にかかわらず一点一万円、“早い者勝ち”としたら、大きい方からどんどん売れた」などの話は洩れ聞いた。
田島征三は、1965年(昭和40)に彼の作品のファンだった喜代恵と結婚、2年後に『ちからたろう』(今江祥智・文、ポプラ社)がブラティスヴァ世界絵本原画展(スロバキア)で金のりんご賞を受賞、4年後にはこの絵本賞の審査員に招かれる。1969年に東京都西多摩の日の出村に移住し、農耕と創作活動に取り組む。1973年には『ふきまんぶく』(偕成社)が、講談社出版文化賞を受賞、絵本が内外で高く評価されるとともに、『やぎのしずか』シリーズが幼児の人気絵本となる。また、米軍機墜落事故の犠牲者・館野正盛の裁判闘争を支援する会に加わり、社会福祉法人しがらき会信楽青年寮(知的障がい者生活寮・作業所)の手すき和紙や陶板を活用、協力して作品を制作するなど、社会的視野も持ち続けた。
 征三の絵本。上『しばてん』『とべバッタ』の表紙、 下『ふきまんぶく』の本文。 |
|---|
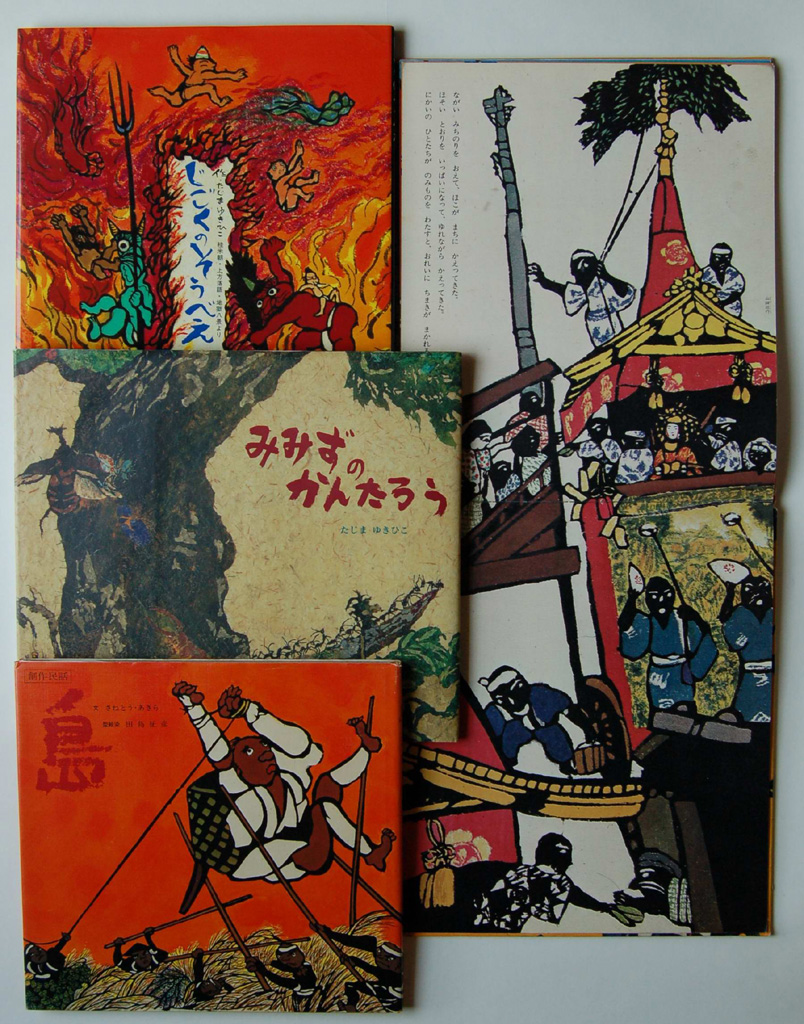 征彦の絵本。左『じごくのそうべえ』 『みみずのかんたろう』『島』の表紙、 右『祇園祭』の本文。 |
|---|
征彦『中岡はどこぜよ』がボローニャで絵本賞
1981年(昭和56)に筆者は公文公(7回)のお誘いで公文教育研究会出版部に転職、1988年には児童書・教育書を出版する「くもん出版」を設立してその責任者となった。絵本も重要分野で、田島兄弟とも仕事が再開された。まず、くもん出版の季刊PR誌『本の海』に征三による幼い頃の回想記『絵の中のぼくの村』を連載してもらった。1940年に大阪で生まれた二人は、敗戦の年に父の故郷・高知県芳原村(現高知市春野町)に移住。ともに病弱だったが、勉強そっちのけで豊かな自然に浸り、川魚や野鳥を追いかけ、いたずらやけんかをくり返しながら成長していく。その姿が絵入りで赤裸々につづられ、大好評だった。
この頃、征三の住む日の出町の山野が、都下三多摩地区の廃棄物を処分する巨大ごみ処分場の候補となる。田島たち住民は「日の出の自然を守る会」を結成、田島夫人・喜代恵が代表になる。彼らは「地域毎の安全でコンパクトなごみ処分場」という代案を掲げて運動を展開する。征三たちの呼びかけで、音楽家・小室等、映画監督・高畠勲など著名文化人も応援に駆けつける。筆者も「日の出の森・支える会」に入会した。しかし、征三たちの体を張っての抵抗も、行政に強制排除されて工事は着工となる。
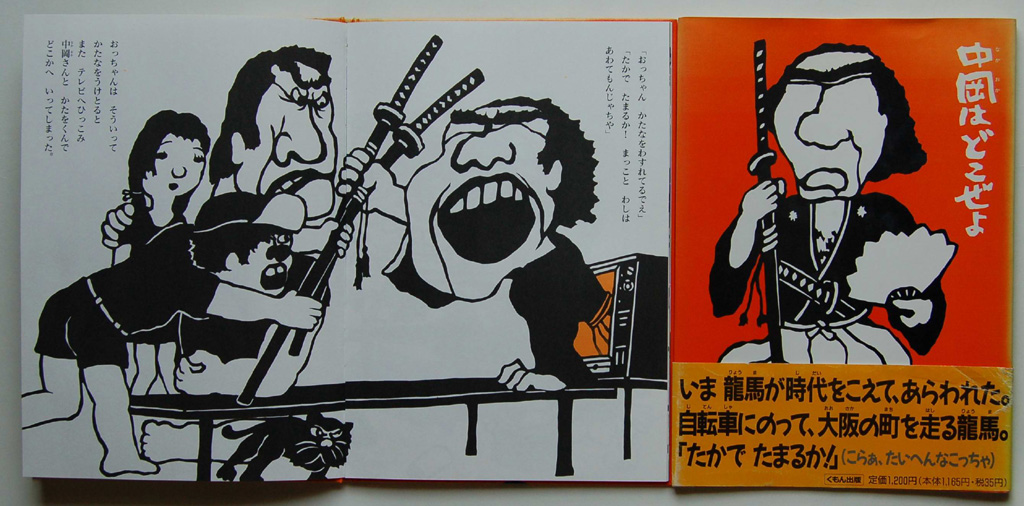 征彦文・関屋敏隆絵『中岡はどこぜよ』の表紙と本文。 |
|---|
 右から田島征彦・英子夫妻と関屋(筆者撮影)。 |
|---|
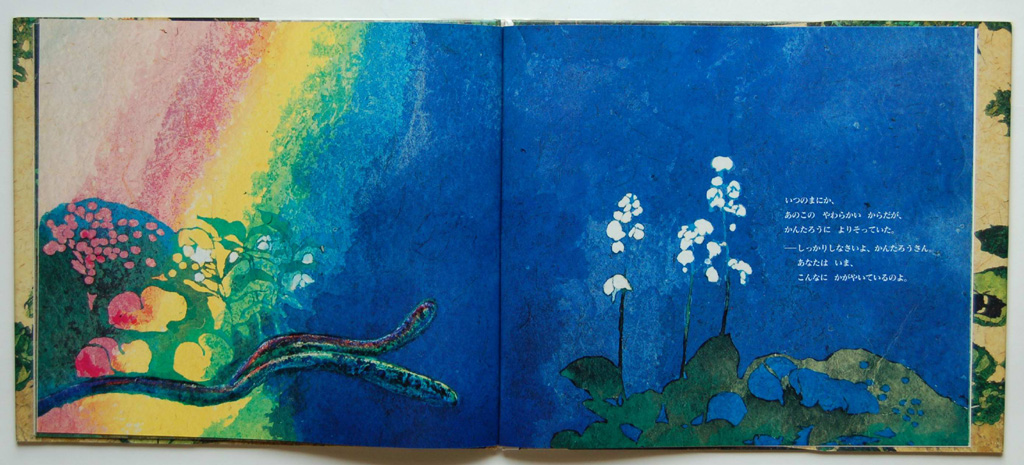 色鮮やかに染められた『みみずのかんたろう』本文。 |
|---|
大地のエネルギーを絵筆で歌う田島征彦・征三兄弟(34回)
中城正堯(30回) 2018.06.24
征三『絵の中のぼくの村』がベルリンで銀熊賞
田島征彦のミミズ絵本ができ上がった1992年(平成4)には、連載を終えた『絵の中のぼくの村』も出版した。これが映画監督東陽一の目にとまり、高知出身・中島丈博との共同脚本で、シグロによる映画化が決定した。1995年の夏、仁淀川上流のロケ地・吾北村を訪ねた。オーディションで選ばれた双子の子役が、のびのびとやんちゃな兄弟を演じていた。完成試写会では見事な出来映えに感動、母親役の原田美枝子、父親役の長塚京三にもお会いした。
翌年、突然朗報が届いた。「第46回ベルリン国際映画祭、銀熊賞受賞!」の知らせだ。この映画は、その後もベルギー、フランスなどの国際映画祭でグランプリを受賞、国内でも日本映画批評家大賞の作品賞・主演女優賞となり、さらに子役二人が特別賞を授与された。東監督は、文部省芸術選奨文部大臣賞を得た。これらも、もとはといえば田島兄弟の郷里での幼年期への郷愁を込めた自伝的エッセイであった。題名のとおり、かつての「ぼくの村」は住宅地に変貌、消えていた。
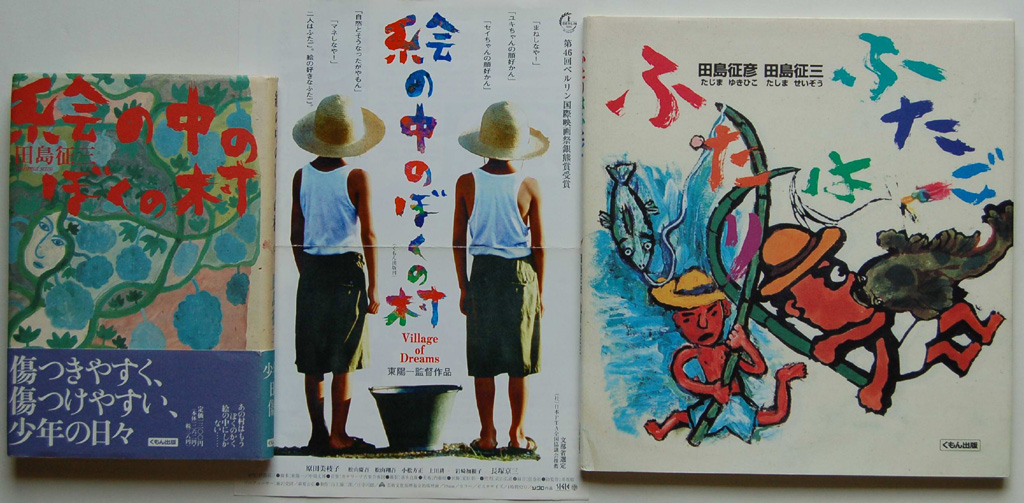 左から田島征三『絵の中のぼくの村』表紙と映画のチラシ、共作絵本『ふたりはふたご』表紙。 |
|---|
帰国した征彦に、パリ研修のいきさつを聞くと、京都美大時代の恩師・木村重信の推薦だと聞き、これにもビックリ。筆者も、学研で『民族探検の旅』を編集した際に、梅棹忠夫から紹介されて以来のお付き合いで、木村が創設した民族芸術学会の会員となり、くもん出版では著書『美の源流 先史時代の岩面画』出版や、児童用『名画カード(日本編・海外編)』の監修などでお世話になった。
木村は、美術史・民族美術が専門で、大阪大学教授・国立国際美術館館長などを歴任、美術学界のリーダ-であったが、弟子の面倒をよく見た。征彦の『祇園祭』についても、サンケイ新聞で取り上げ、「この絵本は、手で描かれずに、型染作品であることに特色がある。山鉾を飾る染織品が染色画によってあらわされるという、二重の面白さが見どころ」などと丁寧に紹介している。もう一人、木村の世話になった土佐高卒業生に柳原睦夫(29回)がいる。鷲田清一が朝日新聞「折々のことば」784に、こう記している。「おい、ヒマやろ・・・ヒマなはずや。・・・若き日の陶芸家、柳原睦夫は、ある講演の仕事を(木村教授から)回された。当日なんと教授が会場にいる。その後、家に連れて行かれ、たらふくご馳走になる。そして今晩も泊まれと。強引な教授、実は若い作家の暮らし向きを案じ、世に必死で売り込もうとしたのかも」。昨年開かれた「木村を偲ぶ会」で、世話役を務めた柳原の回想から取ったものだ。偲ぶ会は、体調不良で残念ながら失礼した。
土佐高での高﨑先生との出会いが転機
 兄弟が中学生時代の一家。 前列右から、父・姉・征彦・母、後列は征三。 |
|---|
幼い頃から絵が好きで、地面に棒きれで絵を描きなぐって遊んだ兄弟は、小学に入ると村人が開いていた絵画教室に通う。教師だった父母にすすめられるまま、1953年に土佐中へ入る。左はその頃の写真で、前列右から父・姉・征彦・母、後ろは征三である。中学の美術教師は洋画家・鎮西忠行だったが、高校になるとモダンアートの高﨑元尚(16回)となり、より強く影響を受ける。洋画家・中村博の画塾にもふたり揃って通う。
この間、征三は夏期市民大学での岡本太郎の講演「芸術は、積み上げではない。いきなりドカンだ!」に感銘を受け、またピカソのデッサン集を入手、宝物のように愛でる。岡本もピカソも、古代文化や民族美術からインスピレーションを得て、新しい芸術への突破口にしていた。後になり、彼の絵本にキュービズムや抽象表現主義の傾向が現れるのも、「木の実のアート」を始めるのも、源流はこの高校時代だ。
いっぽう征彦は、戸籍上は兄ながら引っ込み思案な性格で、絵に自信満々の弟が酒も飲んで青春を謳歌する姿に、劣等感を感じていた。土佐高の校内言論大会で、征三が再軍備問題を堂々と論じるのに惹かれ、自ら自由民権思想の研究会を立ち上げたが打ち込めない。進学は美大と決めていた征三と違い、高3になっても進路がさだまらず、絶望的になっていた。そんなとき、高﨑先生から福沢一郎展を教えられ、観賞して興奮、帰ってからその残像をスケッチブックに描きまくった。先生に見せると「福沢作品にちっとも似てないところが面白い。君にしか描けない絵がある」と励まされる。この一言で絵に回帰、「君の学力で入れる美大は、京都美術大の染織図案科しかない」と教えられ、受験準備を始める。
 高﨑元尚先生。退職後に土佐高美術室で。 (土佐高校提供) |
|---|
大学へ進学してからも、兄弟の高知との縁は切れない。二人で高知県観光課吉本課長に観光ポスター制作を持ちかけ、征三が泥絵具で描いたエネルギッシュな「鰹の一本づり」が採用される。さらに、当時のM知事が汚い絵と評価し、課長がやっと説得したこの作品が、全国既製観光ポスター展でデザイン界の大御所を差し置いて、金賞・特別賞を受賞する。征彦は高知県展にも次々と出品、特選もとる。そして、土佐の絵金(絵師・金蔵)の凄惨な芝居絵に魅せられ、型染絵に本気で取り組む。
征彦は若き日を回顧して、「樹木希林さんが、文学座で大先輩の杉村春子さんや芥川比呂志さんに平気でぶつかり、喧嘩し、叱られながら育ったと言っていた。ぼくも高﨑先生はじめ多くの人にぶつかり、助けられ、なんとかやって来た」と語る。土佐の山野であふれる生命力を吸い取って育った野生児の兄弟は、青年期になってほとばしる美術への情熱を、大らかに受け止めてくれる大人に恵まれ、次第にその才能を開花させたのである。
海辺の新天地へ移住、限りなきチャレンジ
こうして、征彦は京都の祭りや上方落語など伝統文化に題材を求め、民衆のあふれるバイタリティーを、繊細な感覚で型染絵に染め上げ、征三はふきのとうやバッタなど、自然界のダイナミックな生命力を、泥絵具を使って荒々しいタッチで表現してきた。その絵本は、現実逃避のあまく可愛いいおとぎの世界ではなく、生命力の根元をさぐる骨太の作品であり、子どもも大人も楽しめた。それらは、若くして農村に移住し、家畜を飼い農作物を育てながらのいわば「半農半画」の生活から生まれた。「半農半画」は貧乏画家の生きる手立てでもあったが、そこから題材も得た。このような生活は、夫人の協力があって初めて成り立った。征彦の英子夫人は、生活設計が不得手な夫にかわってローンを組み、丹波に二千坪もの家と田畑を購入、生活の安定を図った。征三の喜代恵夫人は、協調性に乏しい夫にかわって「日の出の自然を守る会」代表となり、長期の運動をまとめた。
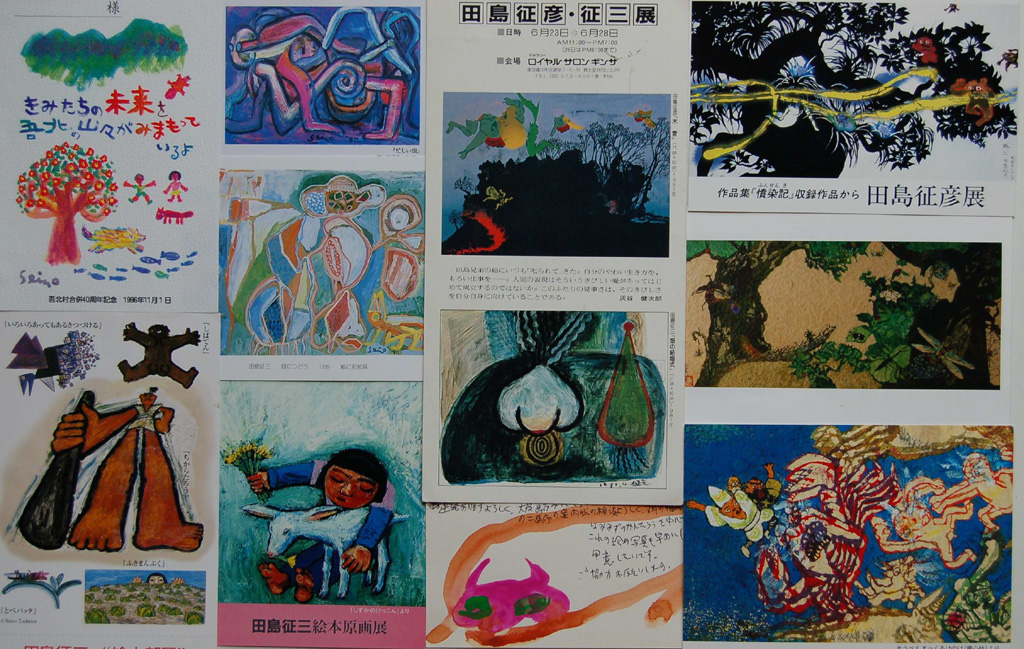 兄弟から届いた個展の案内状。 |
|---|
最近の征彦の手紙には「あたたかさと海の見える生活に感動、新しい作品の方向がうまれた」とある。『ふしぎなともだち』『のら犬ボン』など新作の大きな反響に支えられて、新しい絵本の方向性に自信を深め、次作の取材・構想に取り組んでいる。それは、どこでもだれでも抱える身近な大問題の提起であり、人間性の根幹を問いかける絵本だ。彼は、絵本を主軸にその主題と表現手法の深化を、がんこに追及している。
かたや征三は、2012年「日・中・韓 平和絵本」に加わり、『ぼくのこえがきこえますか』を刊行した。戦死した若き兵士の魂が、「なんのためにしぬの?」と悲痛な叫びをあげる心象風景が表現されていて心を打つ。2009年には十日町市の里山に、廃校を利用した「絵本と木の実の美術館」を開設、学校を丸ごと使った「空間絵本」を創りあげ、予想を倍する来場者を集めた。地域活性化のモデルケースとして注目されているが、なにより地元住民が次々と来場し、面白がってくれたのが嬉しかったようだ。
 2006年、東京での兄弟。左征彦、右征三。 (『激しく創った!!』童心社より) |
|---|
<主要参考文献>田島征彦『憤染記』(染織と生活社)『新編くちたんばのんのんき』(飛鳥)、田島征三『絵の中のぼくの村』(くもん出版)『人生のお汁』(偕成社)、共著『激しく創った!!』(童心社)
中城正堯(30回) 2018.06.28
 2003年 サン・レオ城で故人と筆者 |
|---|
「突然のご逝去の知らせを受け悲しみに堪えません
昭和二四年 土佐中学・公文公先生のクラスで同級になって以来
中高六年間 同じクラス 同じ新聞部でした
以来 玄ちゃんは我々の永遠の級長さんでした
心からご冥福をお祈り申しあげます」
 1955年2月、新聞部送別会。前列右から、 横山、大町、西野顧問、中城、千原。 |
|---|
2015年、高知での卒業60周年の学年同窓会のあと、ひろめ市場の二次会で昔話になり、「中学2年の後期だったか、おんしに応援演説をされて中学生徒会長選挙に出た。番狂わせになり、3年の福島さんを破って当選。中3でもやった」と、話しかけてきた。確かに新聞部だけでなく、生徒会でも、そして遊びでもリーダーだった。中学生徒会では、大町会長・中城議長のこともあった。
遊びの中心は草野球。ビー玉にゴムひもや毛糸を巻き付けて布で縫った手作りボールで、昼休みなどに夢中で遊んだ。次第に軟式ボール、バット、グローブが普及すると、大町キャプテン以下、潮江や三里に出かけて他流試合も行った。いい加減な審判をすると、相手から「メヒカリ食ってこい!」などと、ヤジられたものだ。
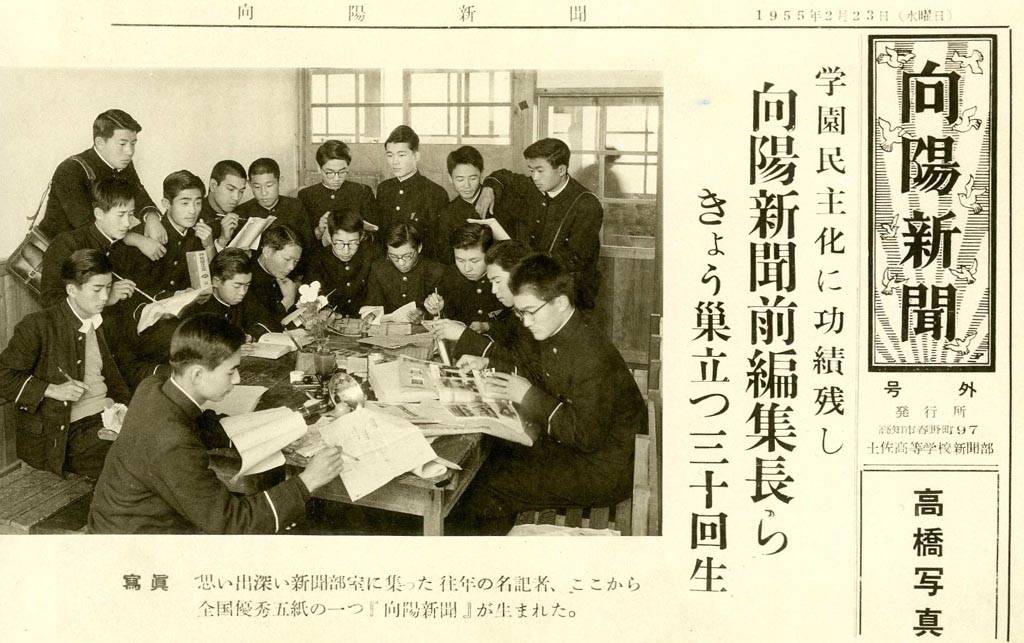 30回生の「卒業記念アルバム」より、 新聞部の写真。(左端に坐る大町) |
|---|
そのような中で、高1になると大町は向陽新聞編集長となり、1952年5月発行第15号には、格調高く「新生日本の出発に当って」と題する大嶋校長のメッセージをトップに掲げた。ようやく日本独立がかなったのだ。この紙面には「人文科学部生る」の記事もあり、部長は公文俊平(28回)、指導教師は社会思想史・町田守正、日本史・古谷俊夫などとある。当時、社会も学内も活気にあふれており、生徒会と新聞部による「応援歌募集」や、「先輩大学生に聞く会」「四国高校弁論大会」などが次々と企画、開催された。
 1960年の関東同窓会記念写真。 後列左から、大町、山岸先生、西内、 前列左から、横山、田所、中城。先生以外は30回生。 |
|---|
部活にもどすと、従来通り高1で大町たち多くの新聞部員は退部、受験勉強に軸足を移したが、筆者と横山禎夫は高3まで部活を続けた。特に筆者は、部活やクラスの混乱をいいことに、勉強そっちのけで過ごした。向陽新聞は全国優秀五紙にも選ばれたが、受験勉強には全く身がはいらず、私大に進んだ。
わがクラスからは、結局7名が東大に進み、ちょうど70名クラスの1割を占めたが、担任との軋轢もあって現役入学ばかりでなかったのはやむを得ない。それよりも、東大経済を出た大町が、新聞部や大学での演劇活動をふまえてマスコミをめざし、NHKの内定を得ていたのに、あるこだわりから最後に製造業に転じたのは残念だった。放送界には適材であり、経営管理部門でも、番組制作部門でも、リーダーとなる人物だった。
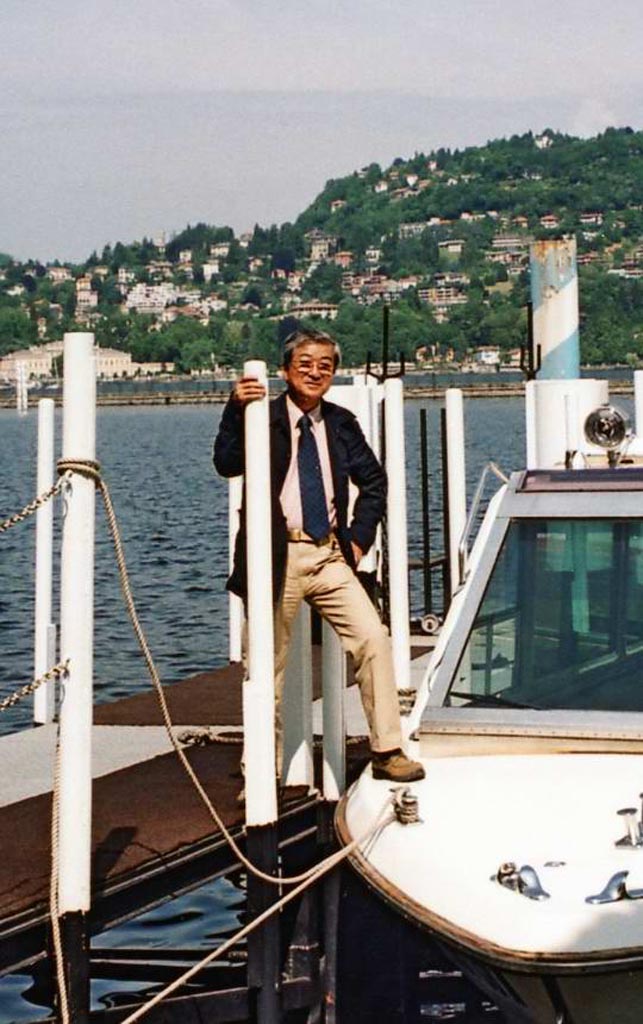 2003年、イタリア城郭視察旅行で コモ湖に遊ぶ。 |
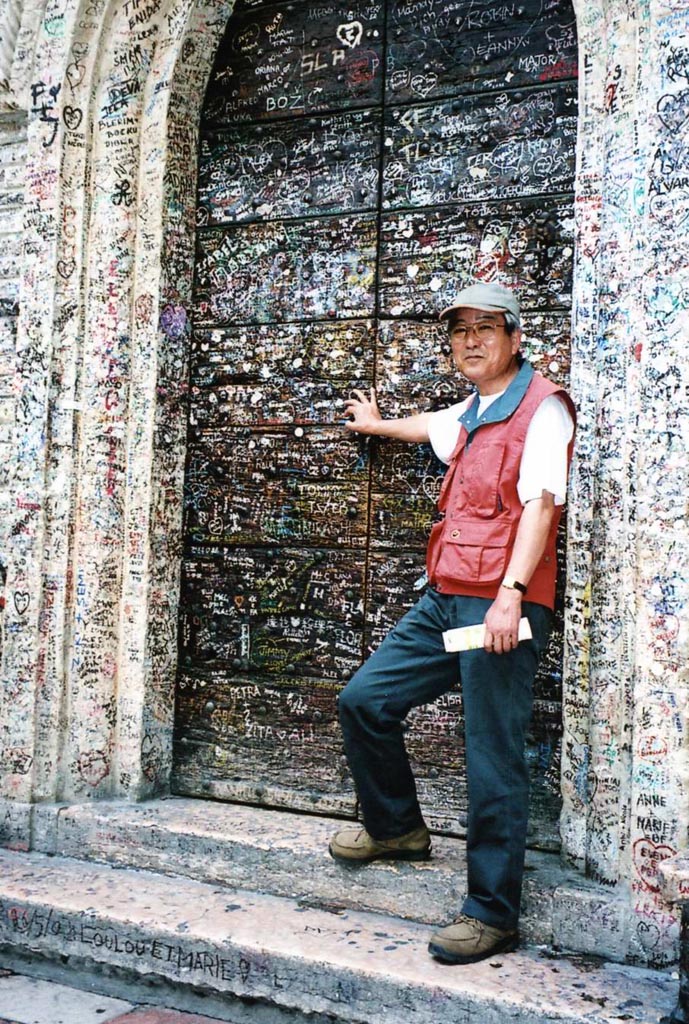 ヴェローナ、ロミオとジュリエットの 舞台で演劇活動を回想。 |
|---|
老いても級長さんの役割は途切れず、20号まで出たクラス誌「うきぐも」発行や、クラス会開催の主役であった。また、草野球以来の虎キチで、神宮球場の阪神×ヤクルト戦はよく級友と観戦していた。肺がんと分かってもタバコを手放さず、悠々囲碁を楽しんでいた。今年の年賀状には、達筆で「告知された余命期限を過ぎて三ヶ月経ちました。期限切れの余命を楽しむが如く、慈しむが如く、ゆっくりと面白がって生きております」とあった。達観した心境のようだった。
告別式の行われた6月13日は、あいにく日本城郭協会総会に当り、筆者の体力では浦安市斎場との掛け持ちは無理だったが、浅井・西内・松﨑などの同級生、さらに向陽プレスクラブの公文敏雄会長が参列し、お別れを告げてくれた。城郭協会総会の開かれた神田・学士会館は、奇しくも50年前の晴子夫人との婚礼の場であり、5月には高知からの親族も含めてここに集い、元気な玄ちゃんを囲んで、盛大に金婚式を祝ったばかりだという。50年前、筆者は悪友にそそのかされてクラス代表の拙い祝辞を述べた思い出が蘇ってきた。 合掌。 母校出身“素顔のアーティスト”(Ⅳ)-1(前編)
凄絶なホラー作家にして酒豪、坂東眞砂子(51回)
中城正堯(30回) 2018.07.08
イタリア帰りの童話作家から転進
 坂東眞砂子(高知県立文学館提供) |
|---|
会ってみると、三十半ばとは思えない若々しいおかっぱの童顔で、奈良女子大住居学科を出てイタリアのミラノ工科大などに留学、帰国後にフリーライターとして雑誌の記事を書きつつ、童話に取り組んできたと話してくれた。すでに毎日童話新人賞なども受賞しているが、「これからは、大人の小説を書きます。土佐を舞台にした第一作が、もうすぐ出来上がります」とのことであった。
やがてマガジンハウス社から、「乞御高評」の付箋付きで著書『死国』が贈られてきた。帯には「新鋭書き下ろし伝奇ロマン 四国を舞台に繰り広げられる不可思議な現象と事件!」とあり、作家・小池真理子の惹句「丹念な描写が怖さを紡ぎ出す」と続く。死国とは四国であり、四国遍路を舞台に使ったこの一作で、一躍女流ホラー作家として脚光を浴びる。童話とは全く異質の作品に、驚きつつ礼状を出すと、折り返しハガキで「年内にはまた新刊を出す予定です。そのうちに社(くもん出版)に伺います」とあった。
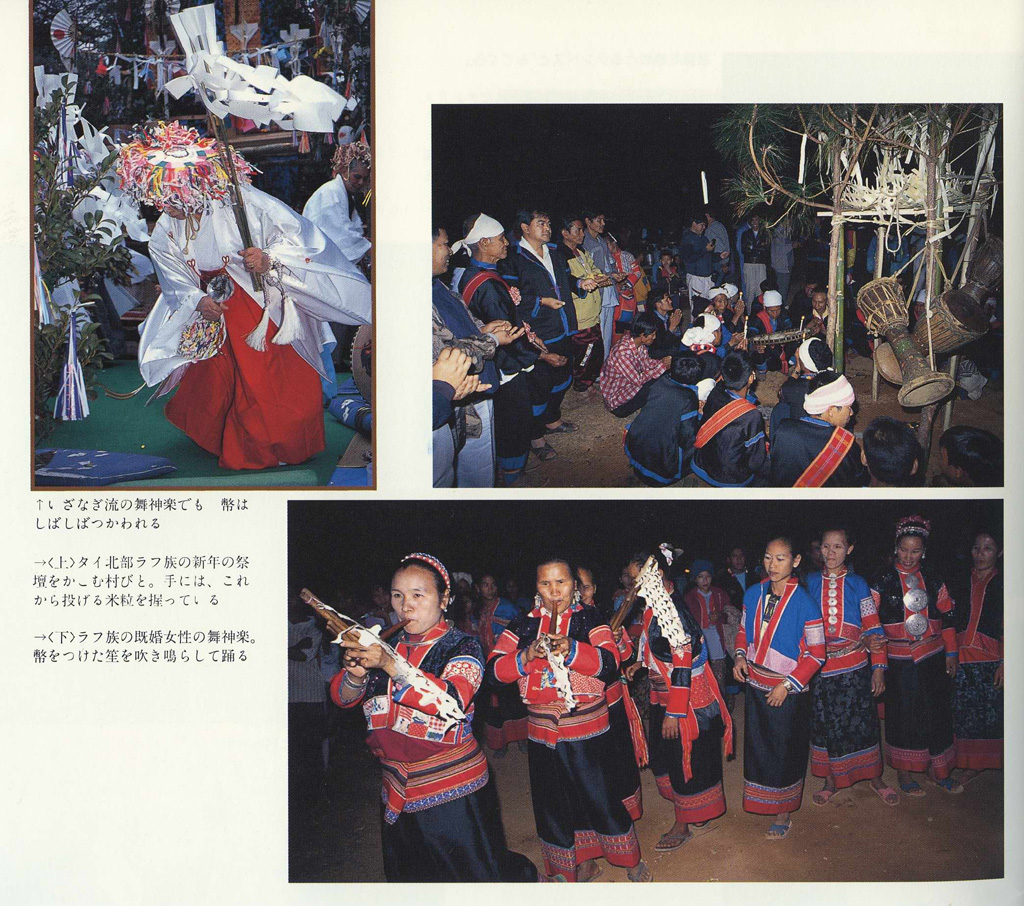 土佐のいざなぎ流(上左)とタイ北部山岳民族の祭礼。 (『季刊民族学』91号、筆者撮影) |
|---|
主人公の美希は、痛ましい少女時代の過去を忘れ、山村で紙を漉いてつましく暮らしていた。若き中学教師の赴任とともに、奇怪な現象に巻き込まれ、狗神筋の家として忌み嫌われ差別される。やがて、近親相姦が明らかになり、一族は村人に襲われ、惨劇で幕を閉じる。後に、天海祐希の主演で映画化された。執筆に当たっては、「土佐憑物資料」などを渉猟している。筆者は物部村でいざなぎ流神事を見学したばかりだったので、読後感に、土佐の民俗・信仰を題材にするなら高知県立歴史民俗資料館の吉村淑甫館長を訪ね、また民間信仰研究者でいざなぎ流にも詳しい小松和彦(当時阪大教授)の著書も読むよう書き添えて送った。翌年1月に手紙が届き、「小松教授の御本は、以前より興味深く拝見しています。今回も参考にさせていただきました。吉村館長にも教えを受けたい・・・」とあった。
 日本人が運営するタイ山岳民族子弟 の寄宿舎学校。(筆者撮影) |
|---|
土佐清水を舞台とする長編は、『桃色浄土』(講談社)であり、1994年10月に刊行された。この頃には、出版界期待の新鋭伝奇ロマン作家として、各社から追いかけられる存在となり、筆者との連絡も直木賞受賞の頃には途絶えた。従ってここからの“素顔”は、主として各社の担当編集者からの伝聞と、本人の随筆による。
文才豊かな酒豪、綿密な現地取材
イタリアから帰国後に、東京でフリーライターとして雑誌に紀行文や取材ルポを書いていた坂東は、応募した童話が新人賞になり、その審査員だった童話作家・寺村輝夫が開いていた文学講座に通う。作品の添削・講評を受けながら文学修業に励んだことが出版につながり、1986年に『ミラノの風とシニョリーナ イタリア紀行』(あかね書房)が刊行される。担当編集者は筆者と学研で同僚だった後路好章で、そのいきさつと人物をこう語る。
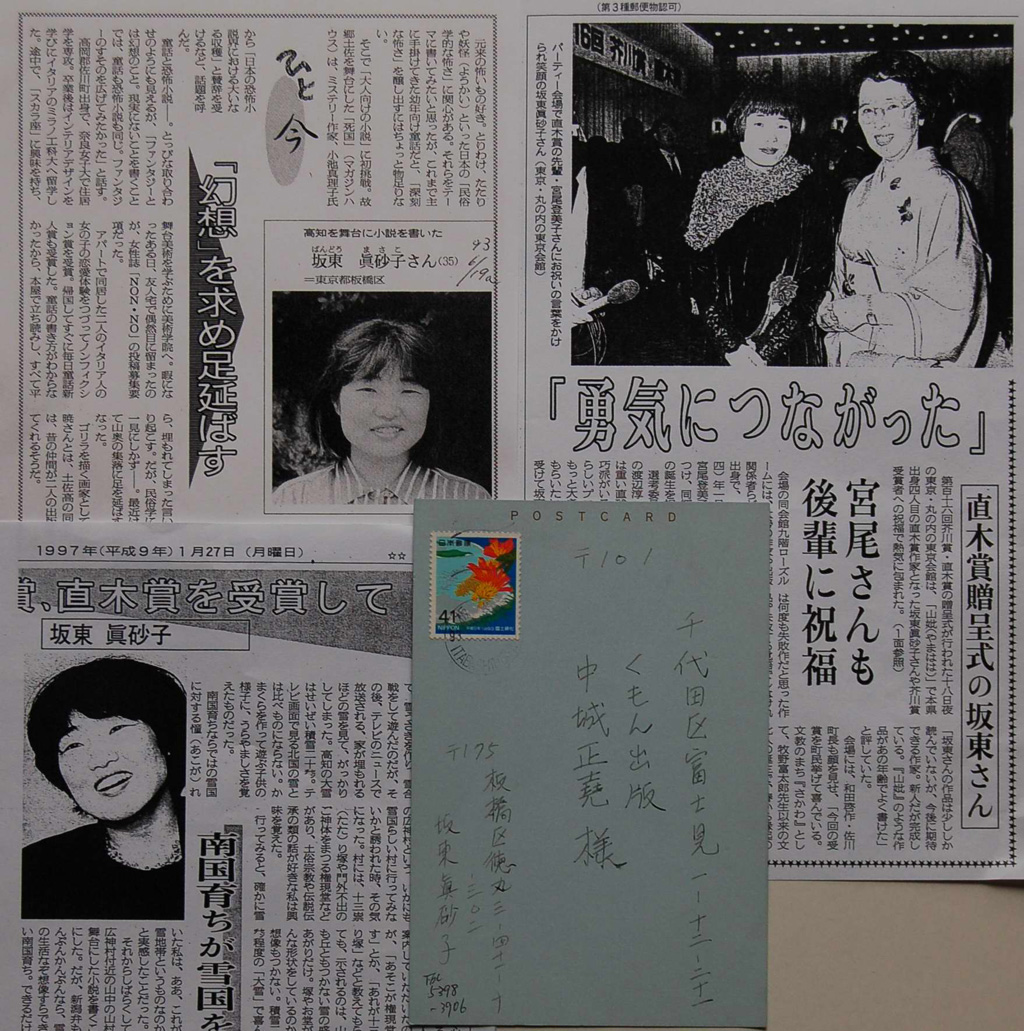 『死国』出版や『山妣』直木賞受賞を 知らせる高知新聞と、筆者へのハガキ。 |
|---|
創作児童文学を数冊出版したのちに、『死国』を皮切りに大人ものの伝奇小説に転じ、『蟲』(角川書店)で日本ホラー小説大賞佳作、『桜雨』(集英社)で島清恋愛文学賞など、次々と受賞する。そして1996年刊の『山妣』によって38歳の若さで直木賞に輝く。受賞の知らせは、翌年の1月に滞在中のイタリアで聞く。高知新聞の取材に、「村社会が私のテーマ。日本民族の根源的な思い出として書ければいい・・・」と、語っている。授賞式には、選考委員・渡辺淳一、直木賞作家・宮尾登美子とともに母・美代子の姿もあった。高校卒業と同時に家を離れ、奈良、ミラノで学び、東京では定職に就かず、母には心配を掛けてばかりだっただけに、母子ともども喜びはひとしおだったと思われる。
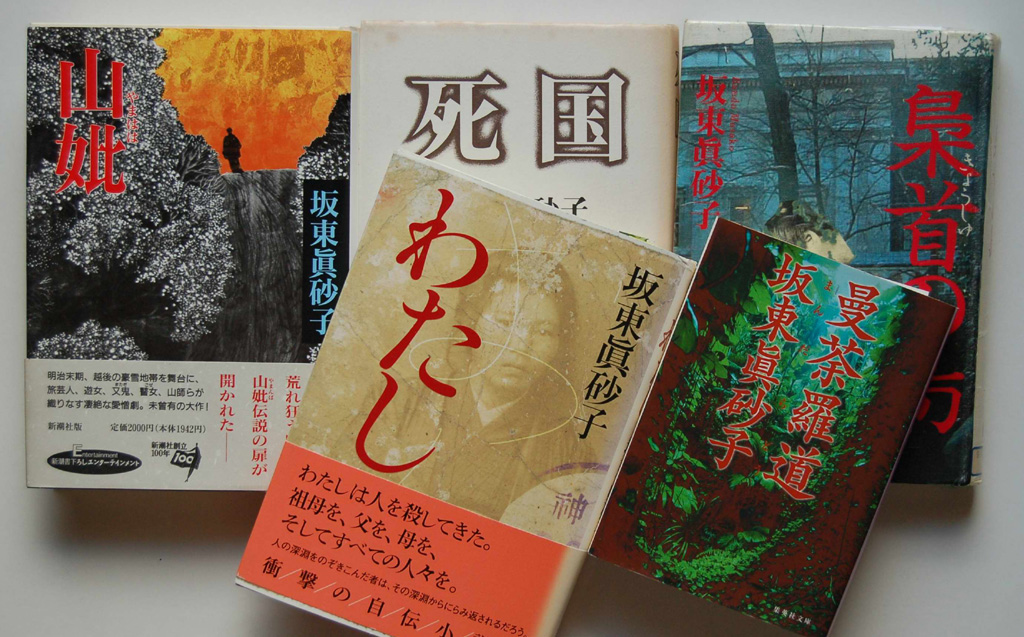 『山妣』『梟首の島』『わたし』など代表作。 |
|---|
「現地取材を実に丹念にする作家だった。『山妣』の舞台は、全く土地勘のない新潟だけに、2年以上取材に時間をかけ、季節をかえて何度も足を運んだ。芝居の場面を書くために檜枝岐(ひのえまた 福島県)へ農村歌舞伎の開演時期に行き、秘境といわれる秋山郷も、数日かけて歩きまわった。民俗学に興味を持ち、関連文献をよく読み込んでから現地取材に向かった。特に、宮本常一、宮田登、それに歴史家・網野善彦の本を読んでいた。仕事に手厳しい作家で、安易な妥協を許さず、著書の装丁一つ取っても、納得いくまで注文を付けてきた。ただ、仕事を終えての酒席では陽気で、近況から作品の構想、高知の思い出など楽しげに話してくれた。土佐の女性らしい酒豪で、日本酒を冷やですいすい飲む姿と、“木村さんは弱いんだから”と笑われたことが印象に残っている」
なお、木村の新潮社同期には『奇跡の歌』などで知られるノンフィクション作家の門田隆将(門脇護53回)がおり、SF評論家の大森望(54回)も元同僚だったという。
タヒチで「生」と「性」を謳歌したハチキン
直木賞受賞後、人気作家として一段と多忙になるなか、2001年刊『曼荼羅道』(文芸春秋)が、柴田錬三郎賞を受ける。戦時下のマレイ半島で、日本人の現地妻となった部族の娘の数奇な生涯をたどる長編だ。講評で黒岩重吾は、「この受賞作には、読んだあとの気迫だとか衝撃、あるいは感動、それから余韻が必要・・・今回は衝撃を受けた」と語っている。
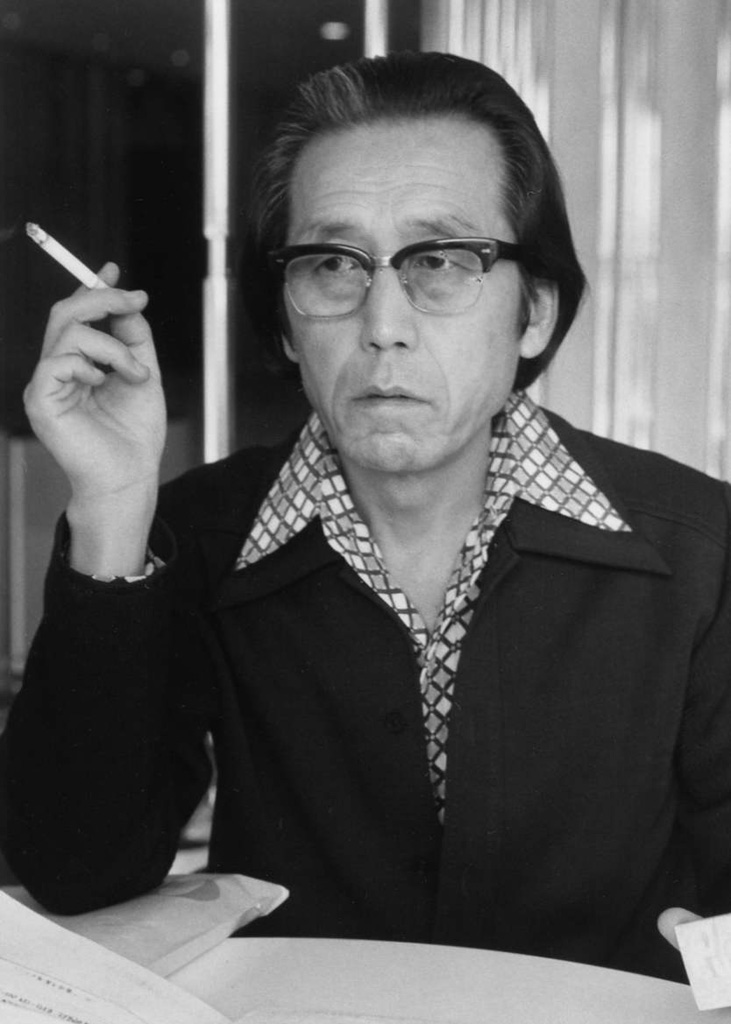 柴田錬三郎。(筆者蔵) |
|---|
 イタリアの陽気な恋人。 1991年ボローニャで。(筆者撮影) |
|---|
彼女のような丸いぼっちゃりタイプは、欧米人には東洋美人の典型と写る。さらに、おしとやかな態度より、はっきり自己主張する人間が好まれる。坂東はイタリア男性の熱い性的エネルギーを浴び続け、自信を回復したのだ。仏領タヒチへの移住は、南太平洋の楽園とされるその自然だけでなく、そこに住む開放的な西洋人にも惹かれたのだ。
 タヒチなど南洋を題材にした随筆や小説。右下は坂東。 |
|---|
「日本酒でも何でも飲んでいましたが、一番お好きだったのはやはりワイン。ひとりでボトル2本くらいは軽くあけていました。タヒチでは、夕方、自宅の農作業が一段落したらテラスに椅子を出して、冷えたシャンパンを開け、“あー、この一杯のために今日も働いたわ”みたいな言葉が出るくらい好きでした。酔うほどに議論になり、いつも論客のマサコにやり込められました。話題は下ネタから天下国家まで、といっても私とは恋愛とか男性論が中心で、深夜まで飲んだくれていました。料理の腕もプロ級で、ハチキンを絵に描いたような豪傑。まさに「生」と「性」を謳歌。知的で自由な発言、よく笑い、欲望にも忠実な生き様は、私たちの憧れでした」
(後編に続く)
母校出身“素顔のアーティスト”(Ⅳ)-2(後編)凄絶なホラー作家にして酒豪、坂東眞砂子(51回)
中城正堯(30回) 2018.07.22
高校時代の『わたし』と疑似友人
タヒチで暮らしつつ、2002年に自伝小説『わたし』(角川書店)が刊行される。帯には「衝撃の自伝小説」「心の深淵には、人に対する激しい憎しみと恐怖を抱えた“わたし”が住んでいる」とある。祖母はじめ家族、そしてタヒチでのパートナーなどに関する赤裸々な記述はともかく、高校の学友に対しても「疑似友人」と述べ、憎しみに満ちた記述を連ねている。自伝「小説」とうたい、仮名になっているとは言え、級友にとっては誰を指すか明白であり、身に覚えのない記述に嫌悪感を抱かずにはいられなかったであろう。
 坂東が在籍した頃の土佐高校舎、 高知市塩屋崎町。(筆者撮影) |
|---|
両親が教師と保母という家庭で育ち、小学校では図書室が大好きで『長靴下のピッピ』や『ツバメ号とアマゾン号』、そして漫画に夢中になった。中学ではカミュの『異邦人』に惹かれ、文芸部でも活動、成績も良く仲間のリーダーだった。高校で2年、3年と同級だった八木勝二は、「彼女の印象は、横山大観の『無我』の少女のように茫洋とした容姿で、男子の友人はおらず、女子の友人も浜口や竹崎(現YASUKO HACKIN)に限られていた。『わたし』に書いてあることは、創作が多い。いつの間にか流行作家になり、直木賞をもらった。級友と“すごいねえ。そんな才能があったがか”と、話したことだった」という。
担任だった濱田俊充(理科35回)も、「友だちは少なかったが、浜口知暁とは仲が良く、よく一緒にいた。直木賞作家になるとは想像出来なかった」と語る。その浜口は、かつて筆者に坂東を紹介してくれた画家・阿部だが、「もう彼女のことは話したくない」と語るのみだ。合田佐和子や田島兄弟は、高校時代に美術教師によって才能を見出されたが、坂東の才能は埋もれたままであった。
「猫殺し」に見る坂東の“偽悪”
2006年8月、坂東は日本経済新聞夕刊の連載エッセイに「子猫殺し」を書く。「こんなことを書いたら、・・・世の動物愛護家には、鬼畜のように罵倒されるだろう。そんなことを承知で打ち明けるが、私は生まれたばかりの子猫を殺している。家の隣の崖の下がちょうど空き地になっているので、生まれ落ちるや、そこに放り投げるのである」
掲載直後から、まずネットで坂東バッシングがはじまり、新聞雑誌でも文化人の論評をまじえての集中砲火を浴びる。本人が覚悟した以上の糾弾だった。坂東には『死国』発表以来付けられた「ホラー作家」に加え、「猫殺し」のレッテルが加えられる。かねて坂東は、「私はホラーという横文字の恐怖を書いているのではない、日本人が持っている自然や神に対する畏怖(いふ)感を書いている」と反発してきた。「猫殺し」の真実はなんだったのか。友人で作家の東野圭吾の問いかけに、坂東はこう答えている。「崖というと、断崖絶壁を想像する人が多いけど、実際は二メートル程度の段差。下は草むらやから、落としたぐらいで死なへん。つまり正確にいうと、子猫を裏の草むらに捨てた、ということやね」(「レンザブロー」)。坂東は、人間と動物、特に家畜や愛玩動物との関係を、根元から問いかけるために、「捨て猫」でなく、インパクトのある「子猫殺し」にしたのだ。
ここでも、『わたし』での「疑似友人」への容赦ない表現同様に、「わたし」を“偽悪化”して、「子猫殺し」に自らを仕立て上げている。エッセイでは、あえて自身を悪者にした上で、他者(友人や愛玩動物)への攻撃姿勢を強調、読者に問題提起をしている。
 タヒチの美しい景観。(筆者撮影) |
|---|
坂東は2008年には50歳となり、長編『鬼神の狂乱』(幻冬舎)を上梓する。江戸後期に土佐豊永郷で起こった狗神憑きの事件から題材を得て、鎮圧に参加した下級武士と村娘の恋を織り込んである。民間信仰だけでなく当時の社会的背景も織り込んで、完成度の高い楽しめる作品に仕上がっている。いつもながら、本の末尾には郷土史家・公文豪など取材協力者の氏名を、詳細にあげてあった。この年の年末には、タヒチのパートナーとも別れて帰国する。翌年には、高知に帰郷し、鏡川上流の高知市鏡に、イタリアンカフェをオープン。オーストラリアの北東に浮かぶバヌアツにも家を建て、若い夫ケビンとくらす。
高知とバヌアツを往き来しながら、旺盛な執筆活動を続け、2011年には『くちぬい』(集英社)を出版する。高知へ帰郷後に実感した非合理な土地慣行や高齢者による新参者へのいじめ、共同体のために口を閉ざす”口縫い”をテーマに、田舎への愛憎を作品化している。
郷里への想いと「チームマサコ」
2013年、体調不良を訴え、検診の結果舌癌と判明する。高知で治療を続けながら連載を抱え、執筆活動を続ける。やがて、肺にも転移し、末期ガンとの診断が下る。東京での治療を希望し、同年末には、友人・久保京子の車で、東京の病院に移動する。
東京では、新潮社や集英社をはじめ仲良しの編集者・新聞記者・作家たちが女性だけで「チームマサコ」を結成、入院生活を支援した。その様子を、中瀬はこう述べている。
「高知にもどるまで約1ヶ月間のサポートシステムです。病室に付き添い、水分補給にシャーペットを溶かしてスポンジに含ませては舌にのせてやり、買い物やお金の管理も行い、時には泊まり込みました。“死”への想いが渦巻き、たまには爆発したようですが、私には最後までユーモアたっぷりなマサコ節でした。病室は男子禁制で、仲良しの男性編集者にも面会拒否を通していました。やつれたすがたは、見せたくなかったのでしょう」
 坂東の愛した土佐の青い空と海、 緑の山々。桂浜で。(筆者撮影) |
|---|
こうして坂東は、土俗的な信仰と習俗の村社会にみられる人間の業を描いて、直木賞作家としての地位を築いた。さらに、古代王朝や自由民権運動を舞台にした歴史ロマン、明治以降の日本のアジア・太平洋進出を庶民の立場から捉えた社会派小説など、新ジャンルに挑戦、時代・舞台を重層的に交錯させ、劇的な結末に導き、読者を魅了し続けた。豊富な海外生活をもとに、あっけらかんとした性描写や、愛を笑い飛ばす性への賛歌は、カトリック・儒教そして近代市民社会のモラルへの挑戦でもあった。差別・戦争・原爆・原発事故にも、強い関心を寄せていた。
1993年の『死国』から、2013年絶筆となった『眠る魚』(集英社)まで、わずか20年ばかりの間に40冊余の多彩な小説を送り出している。早すぎる死に対し、ひところ女流ホラー作家として併称された篠田節子は、近作の『隠された刻』(新潮社)、『朱鳥の陵(あかみどりのみささぎ)』(集英社)、『くちぬい』(集英社)をあげ、「内容の充実に加え高い緊張感とダイナミズムは失われていない・・・老成、円熟には無縁の熱量に圧倒される」(朝日新聞2014.4.13)と、最期まで衰えなかった創作力を追憶している。
 病床でもイタリアの青春を回想しただろう。 フィレンツェのサイケな若者。 アルノ川の橋脚で、1991年。(筆者撮影)) |
|---|
坂東の作品に関しては、既刊以上に望むことはない。ただ一つ、円熟期を迎え再度執筆して欲しかったのは『わたし2』である。余命を知ってからの郷里土佐への想いが伝わるだけに、土地だけでなく級友はじめ土佐の人々への想いも、改めて聞きたくなった。
元防衛大臣・中谷元から防衛問題を取材
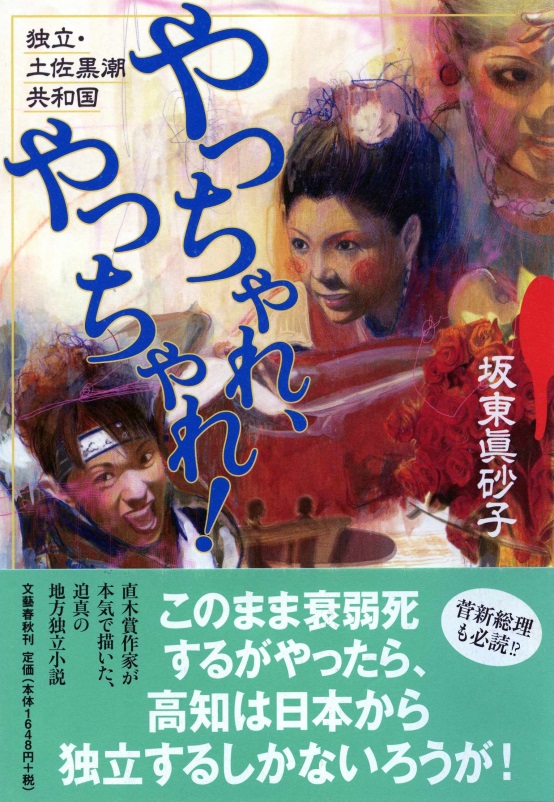 高知独立をテーマにした『やっちゃれ、 やっちゃれ!―独立・土佐黒潮共和国』 (文藝春秋) |
|---|
「坂東さんは、2008年4月から11月まで高知新聞に『やっちゃれ、やっちゃれ!―-独立・土佐黒潮共和国』(後に文藝春秋刊)を連載した。その中で防衛問題も扱うので、きちんと勉強したいとの申し出だった。執筆に先だち、二、三度お会いして率直な意見交換をおこなった。卒業以来の再会で、国家防衛への考え方には相異もあったが、熱心な取材ぶりが印象に残っている。人気作家となってもよく資料を収集、異論もふまえ、独自の小説世界を創作している姿に接しただけに、急逝が残念でならなかった」
*本文執筆に当り、文中に記載以外に高知県立文学館津田加須子、高知新聞片岡雅文、集英社村田登志江、土佐高同級山本嘉博の皆様にご協力いただいた。感謝したい。
<訂正>坂東眞砂子さんの記事(前編)で、「イタリア帰りの童話作家から転進」の項の末尾、「角川書店編集部の吉村千彰(現朝日新聞)」を、「角川書店編集部の吉村千穎(現風日社)」に訂正します。吉村千彰氏と吉村千穎氏を混同し、失礼いたしました。
合田や田島兄弟が新聞で話題に
中城正堯(30回) 2018.07.28
 合田佐和子「ベロニカ・レイク」日本経済新聞。 |
|---|
まず、7月3日の日本経済新聞文化欄で、美術評論家・勅使河原純は、連載「マドンナ&アーティスト十選」の一人に、合田佐和子「ベロニカ・レイク」選んでいる。勅使河原によれば、「美女狩り」で有名な合田が選んだ妖艶なマドンナが、1940~50年代のアメリカで、男を惑わす宿命の女のレッテルを貼られたベロニカで、「合田にとっては一分のスキもない悪女こそ、もっとも心許せる女神だった」と述べている。
7月5日の朝日新聞夕刊「古都ものがたり・京都」には「田島征彦が絵本にした祇園祭」の記事が大きく掲載された。40年以上前、絵本『祇園祭』に着手したころの田島はまだ無名で、取材は難航したが、3年間かよって仕上げる。「きらびやかだけでない、祈りや鎮魂、情熱といった人間の根源を揺り動かすものがいっぱいあった。それを染めた」と、語っている。この絵本は、ブラティスバラ世界絵本原画展で金牌を受賞、ロングセラーになっている。
 「田島征彦が絵本にした祇園祭」朝日新聞。 |
|---|
 山裾に巨大な姿を見せるマムシトンネル。(大地の芸術際) |
|---|
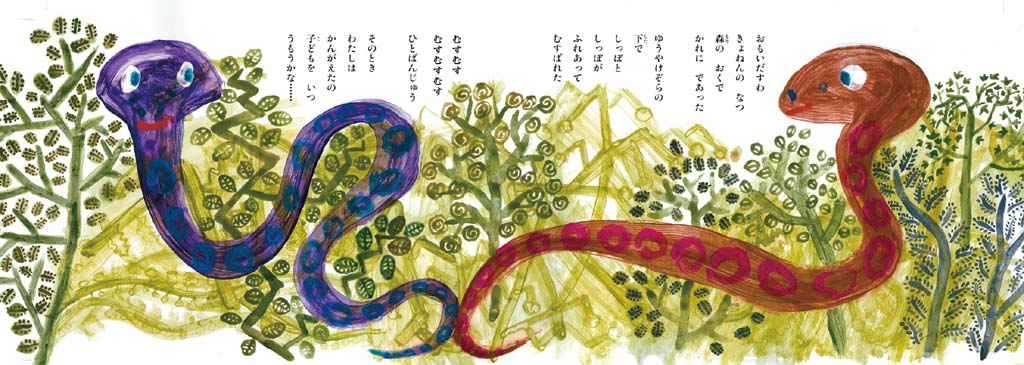 絵本『わたしの森』、若いマムシの恋。(くもん出版) |
|---|
なお、最初に紹介した倉橋由美子(29回)につき、今ベストセラーを連発中の下重曉子との出会いを書き漏らしたので、『うきぐも』14号(30年卒Oホームクラス誌1990年刊)から再録する。下重は筆者と同年の旅仲間で、高知に案内したほか海外も含めてよく旅に出かけ、自宅にも往き来した。連れ合いは、元テレビ朝日の温厚な記者である。
「1989年6月23日、先輩の倉橋由美子さんに、旅仲間の下重曉子さんを、神楽坂でお引き合わせする。ともにファンで、紙上でたがいの作品にラブコールを贈っていたが、会うチャンスがなかったとのこと。会った瞬間から意気投合、肝胆相照らす仲となる。特にお二人とも、結婚談義がケッサクだったが、オフレコである。この日たまたま上京中の福島清三先輩(29回)から電話があり、途中から合流する」(「平成元年出版ヤクザ行状記」) 母校出身“素顔のアーティスト”(Ⅴ)まだまだおるぜよ編
音楽・演劇から前衛美術まで個性派揃い
中城正堯(30回) 2018.08.11
これまで取り上げた5人のアーティストは、文芸・美術の世界で現代日本を代表する実績を積み、また筆者とも面識のある人物であった。しかし、母校出身者には、「まだまだすごい芸術家がおるぜよ」との声が寄せられた。そこで、筆者の独断と偏見で、ぜひ作品に接していただきたいアーティストを紹介する。末尾では、このような人物を輩出した、土佐中教育の原点も考察したい。( )は、卒業回と生没年。敬称省略。
作曲家・平井康三郎や「踊る大捜査線」の北村総一朗
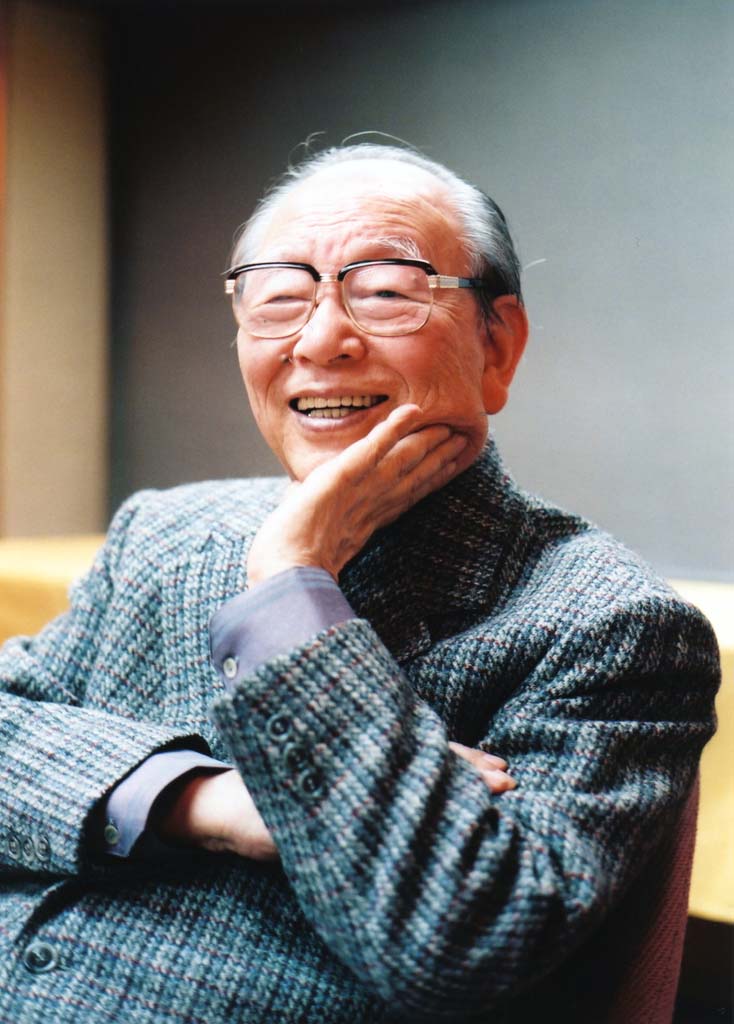 晩年の平井康三郎(平井家提供) |
|---|
 中学時代の平井(左)と学友(平井家提供) |
|---|
俳優では、1997年にフジテレビ「踊る大捜査線」の神田総一朗署長役で大人気となった北村総一朗(29回、1935~)がいる。このドラマが東宝で映画化されたのに続き、テレビドラマ「京都迷宮案内」では文学座で同期だった橋爪功と共演、北野武監督『アウトレイジ』で巨大組織会長を演じるなど、コミカルな役からコワモテまで自在に演じ、今も引っ張りだこだ。バラエティ番組やCMでもよく見かける。
 北村総一朗(同氏HPより) |
|---|
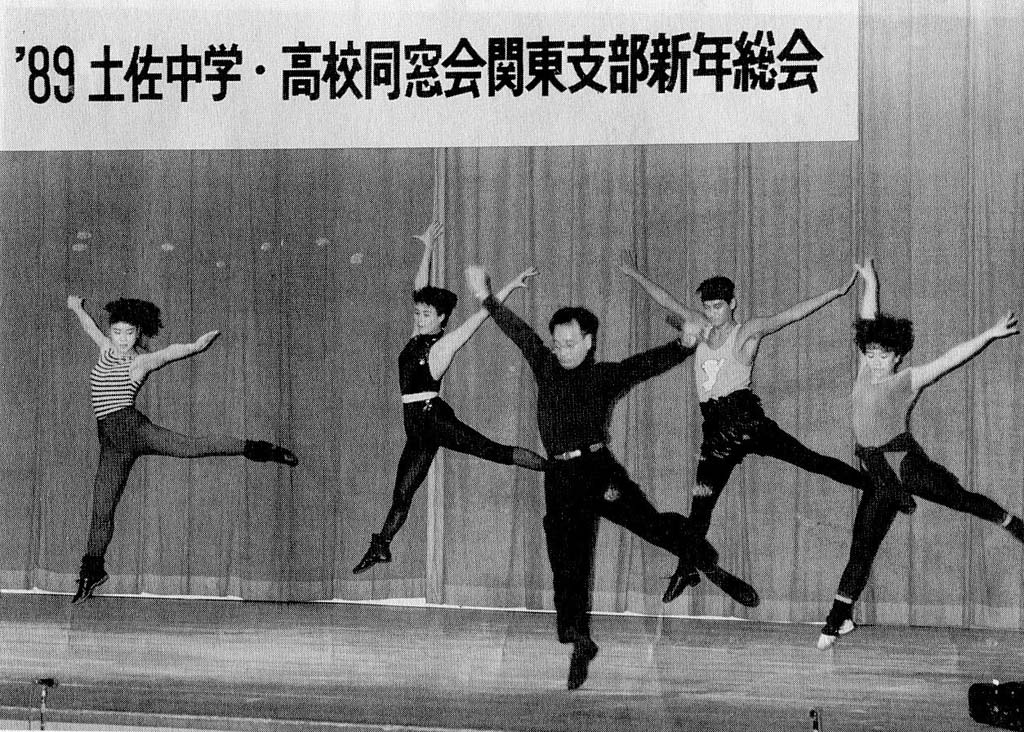 竹邑類、’89同窓会関東支部総会での実演。(『筆山』第8号より) |
|---|
竹邑は土佐中時代からモダンダンスを習い、明治大学仏文科に進む。ダンスのグループを結成し、愛称ピーターで親しまれる。大学を中退してダンサーとなり、ミュージカル「屋根の上のヴァイオリン弾き」に、初代ヴァイオリン弾きの役で出演する。1970年に自らミュージカル劇団「ザ・スーパー・カンパニー」を結成、銀座・博品館劇場の公演には、土佐高同期の小松勢津子などに誘われて筆者も駆けつけ、ミュージカルを初めて楽しんだ思い出がある。ミュージカルの開拓者・挑戦者も、この頃には演出家・振付家の第一人者となり、宝塚歌劇・NHKの歌謡バラエティ・映画『陽暉楼』等で大活躍、坂東玉三郎・平幹二朗・水谷八重子などの名優から信頼され、その舞台の演出・振付けを任されていた。2013年にガンで逝去。著書に、若い頃に新宿で出会って以来の三島由紀夫との交流を綴った『呵呵大将 我が友、三島由紀夫』(新潮社)がある。
彼の劇団で育った俳優に萩原流行(ながれ)がいたが、2015年にオートバイで走行中に警視庁護送車と接触事故を起し、転倒死亡した。事故の原因に不信を抱いた夫人の依頼で訴訟を担当した弁護士が堀内稔久(32回)で、護送車の運転不注意であることを裁判で明らかにした。
もう一人の北村は東宝の演劇部に所属し、主演・森光子のでんぐり返りが話題を呼んだ「放浪記」などの演出で知られる。大学は関西学院大学社会学部だが、在学中からフランス・ナンシーの「国際大学演劇祭」に日本代表で参加するなど、演劇に取り組んだ。東宝では、菊田一夫や北条秀司の演出助手を経て、主に時代劇・喜劇の演出にあたってきた。東宝演劇をささえる重鎮である。
世界の先端をめざした前衛芸術家・高﨑元尚、柳原睦夫
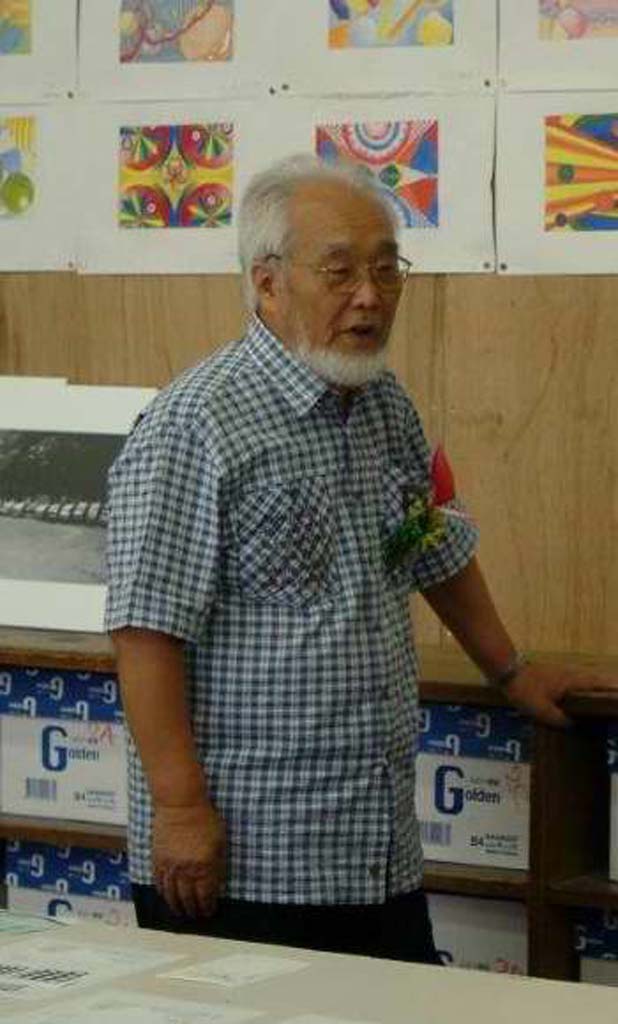 高﨑元尚、退職後に母校の美術室で (土佐中高提供) |
|---|
高﨑は香美町の生まれ。土佐中時代には数学、特に幾何が得意で、早稲田大学専門部建築科に入学、ロシア・アバンギャルドなどに触れ、翌年には東京美術学校(現東京芸術大学)彫刻家に転じる。ところが戦争激化で、彫刻制作にも大和魂を強要され、同級の岩田健とともに反抗、やがて学徒出陣となる。この岩田は、温厚な人格者で後に母子像彫刻の第一人者となり、筆者は大阪の公文教育会館ロビーに飾るブロンズ像「本を読む母と子」を依頼、1989年に完成したが、高﨑と親友だったとは、全く気付かなかった。
 高﨑元尚「LANDSCAPE」 (『高﨑元尚新作展』図録、高知県立美術館より) |
|---|
高﨑は関西・東京からは距離を置き、高知にいたほうが美術界の動向がよく見えると述べている。また、前衛美術の中心地アメリカは絶えず意識し、晩年になってもいつでも対応出来るよう英語力の持続に努めていたと聞く。想いがかない、2013年にニューヨークのグッゲンハイム美術館から出品依頼があり、90歳になっていたが会場へ出向いた。高﨑の作品については、このHPに山本嘉博(51回)が「高﨑元尚先生逝く」(2017.10.12)、「追伸」(11.02)を掲載しているので、ご覧いただきたい。美術教師であるとともに、生涯自ら新作に挑み、芸術家としての生き様を最期まで見せ続けた希有なアーティストであった。
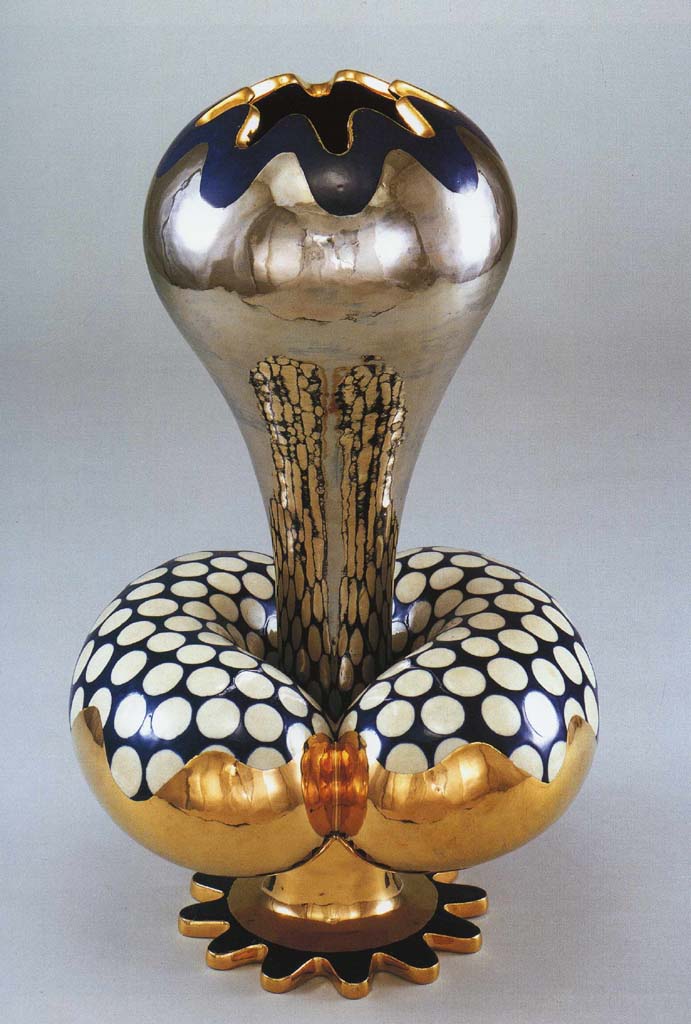 柳原睦夫「紺釉金銀彩花瓶」 (『柳原睦夫と現代陶芸』図録、高知県立美術館より) |
|---|
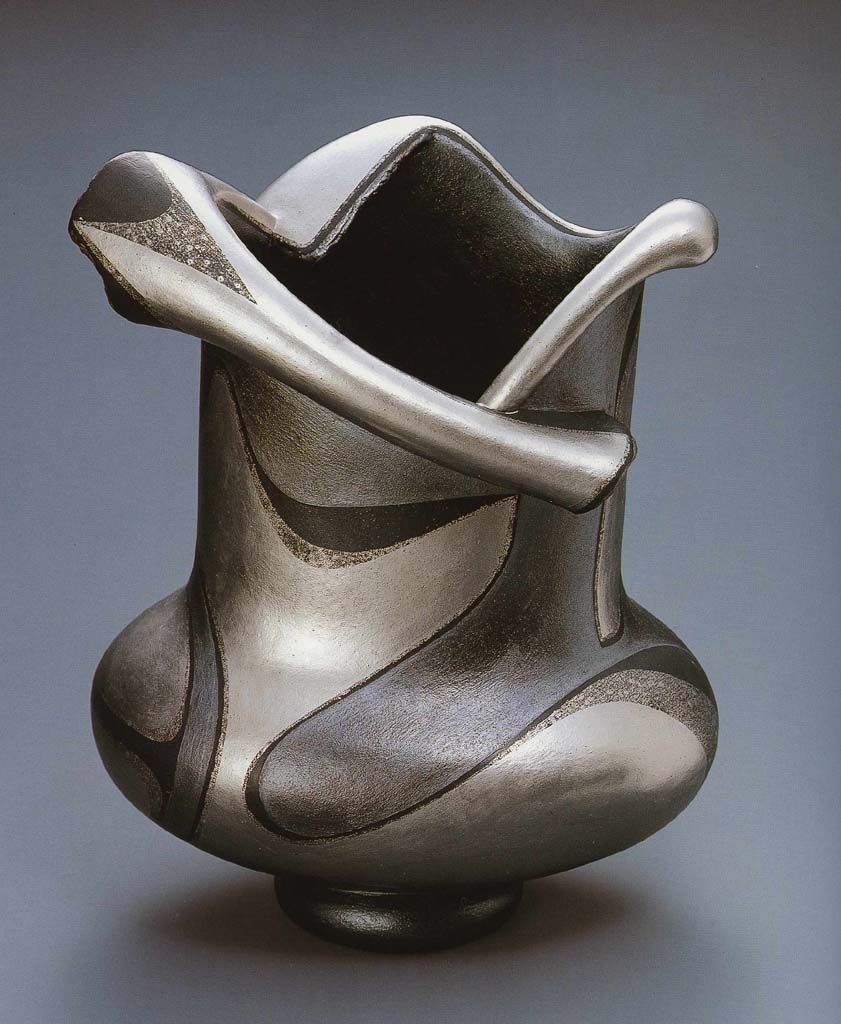 柳原睦夫「縄文式・弥生形壺」(同上) |
|---|
絵本・漫画・陶芸・ゴリラ画家からフィギュアまで
美術の分野には、まだまだ個性豊かな異色のアーティストがいる。絵本の西村繁男(40回、1947~)、漫画家の黒鉄ヒロシ(竹村弘 41回、1945~)、陶芸の武吉廣和(43回、1950~)、画家の阿部知暁(旧姓:浜口 51回、1957~)などである。
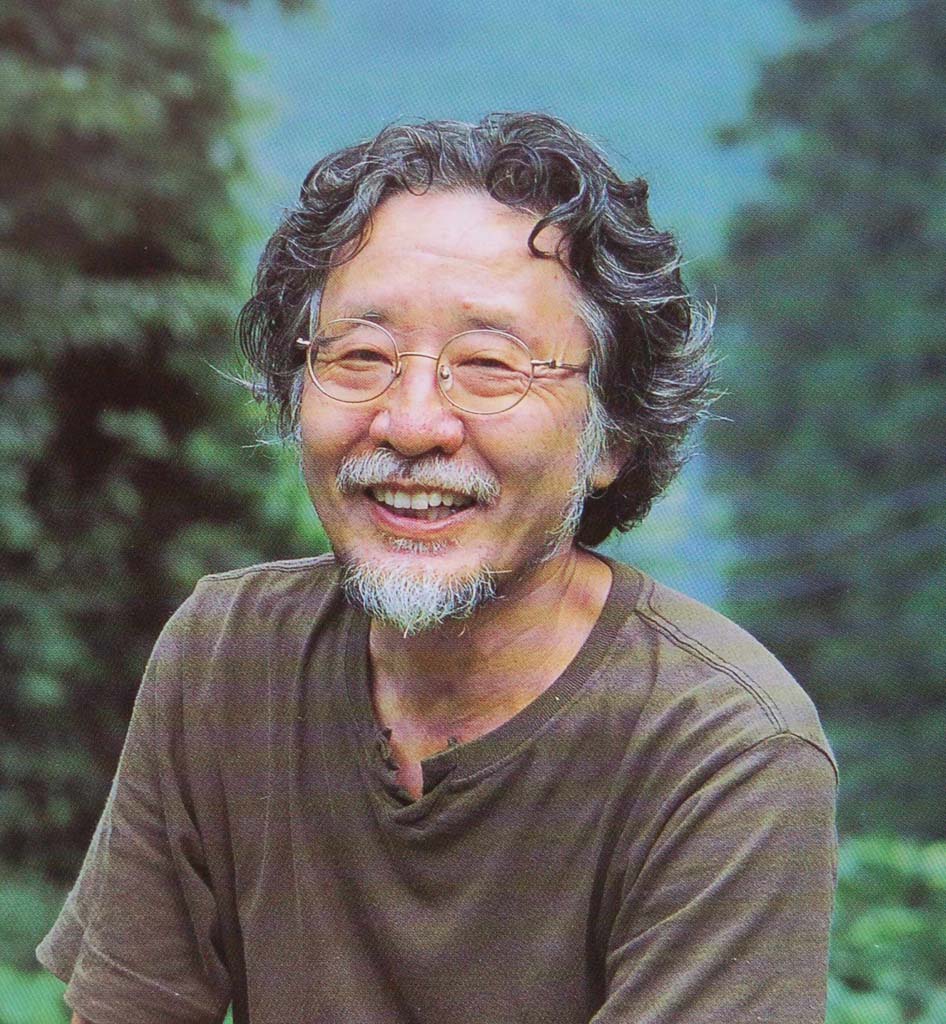 西村繁男 (別冊太陽『絵本の作家たちⅣ』より) |
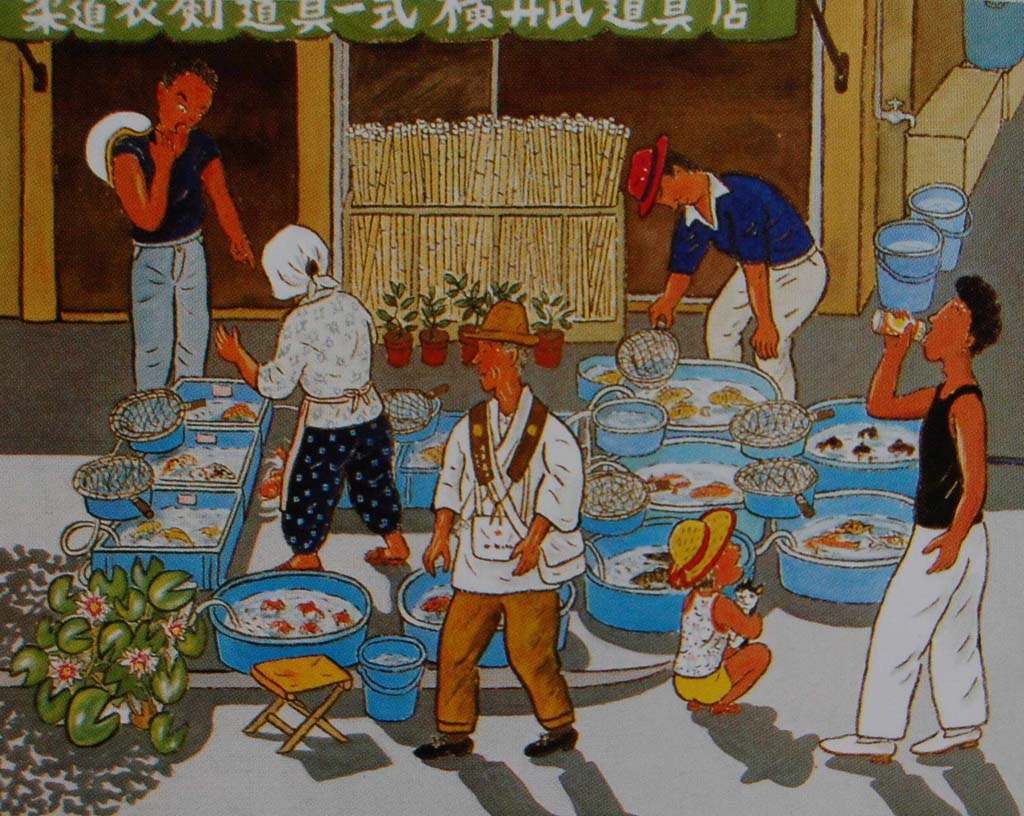 西村繁男『にちよういち』(福音館より) |
|---|
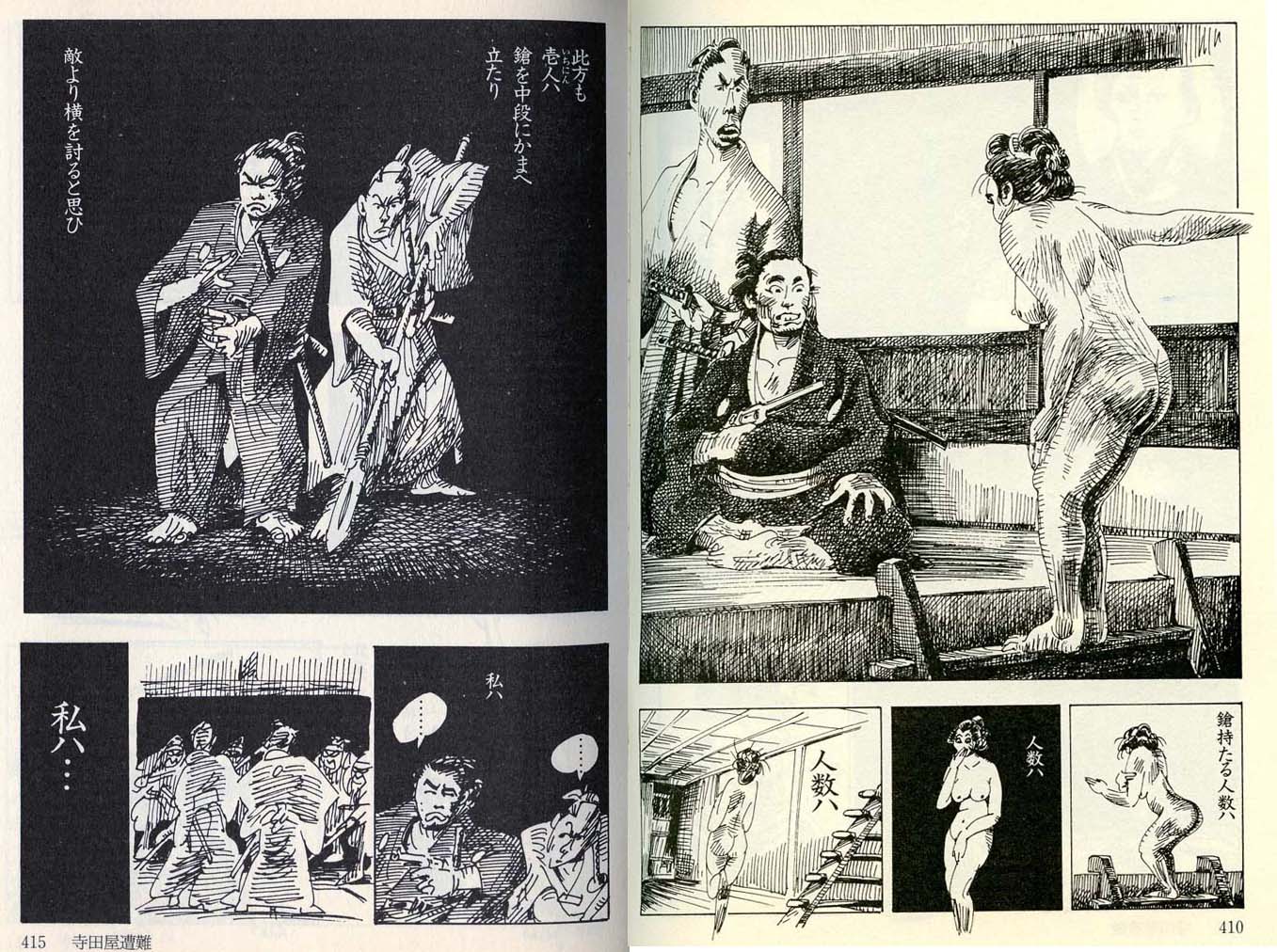 黒鉄ヒロシ『坂本龍馬』寺田屋遭難(PHP研究所より) |
|---|
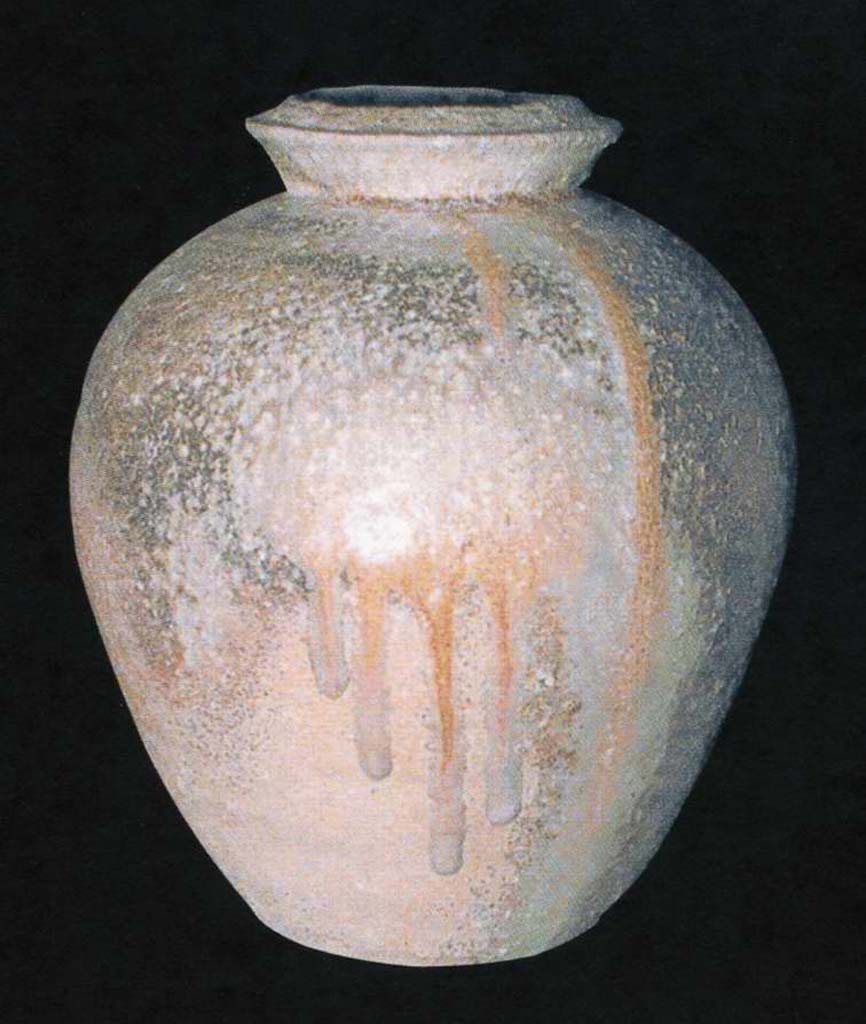 武吉廣和「自然釉壺」(個展案内状より) |
|---|
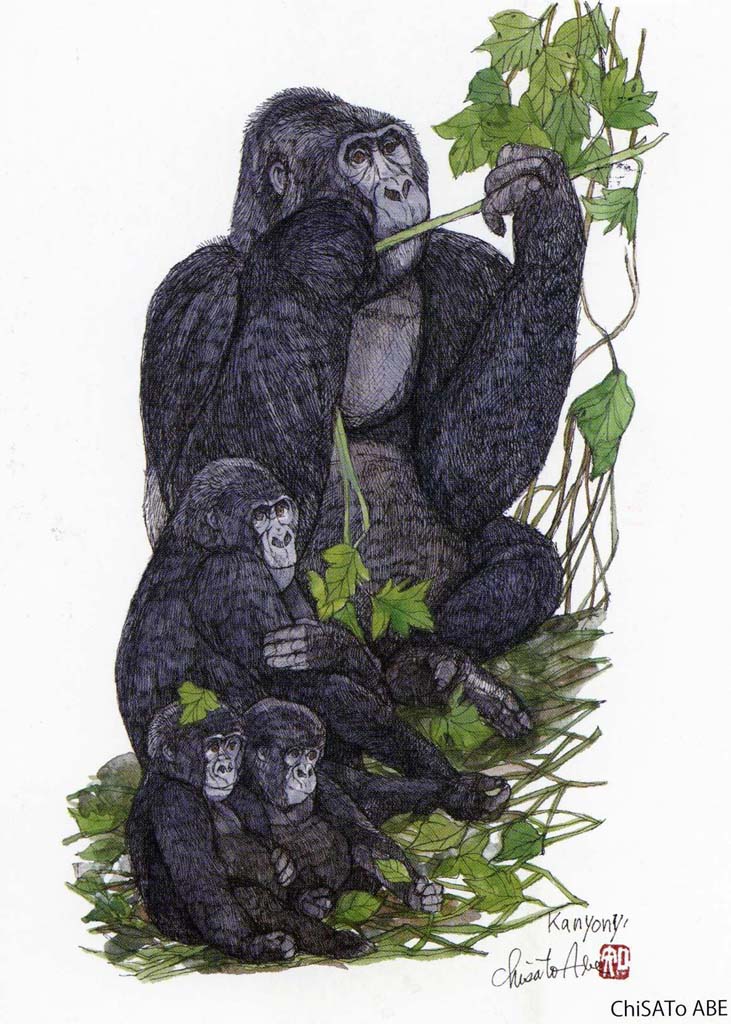 阿部知暁「ゴリラの親子」(年賀状より) |
|---|
 デハラユキノリの名刺(千頭裕提供) |
|---|
芸術的教養を重視した三根校長の先駆的“人材教育”
母校卒業生からは、これら以外にノンフィクション文学で大活躍の塩田潮(塩田満彦 40回)や門田隆将(門脇護 53回)、文藝評論家の高山宏(42回)・加賀野井秀一(44回)・大森望(英保未来 54回)などがおり、アーティスト・文化人の輩出がいわば伝統になっている。では、その原点はどこにあるだろう。やはり平井康三郎を見いだした初代校長・三根圓次郎である。平井と同じ5回生の伊野部重一郎(昭和4年卒)は、当時の学校生活を「我が土佐中には音楽があり、音楽会が時々あって先生方も演奏された。また校外から小さい音楽団を招いて演奏したこともある」(『三根先生追悼誌』)と述べている。開校時に英語教師として赴任した長谷川正夫(青山学院卒)は絵画も担当、「校長は画架、石膏像、額縁など私の要求するままに買ってくれた。絵の時間には潮江山(筆山)に登ってスケッチをさせたり、自然を眺めながら絵の講義をしたりして、全く自由にできた」(『創立五十周年記念誌』)という。これは、大正時代に興った『赤い鳥』に代表される芸術教育運動も後押ししたが、なにより三根校長の芸術重視の教育理念にもとづくものだ。
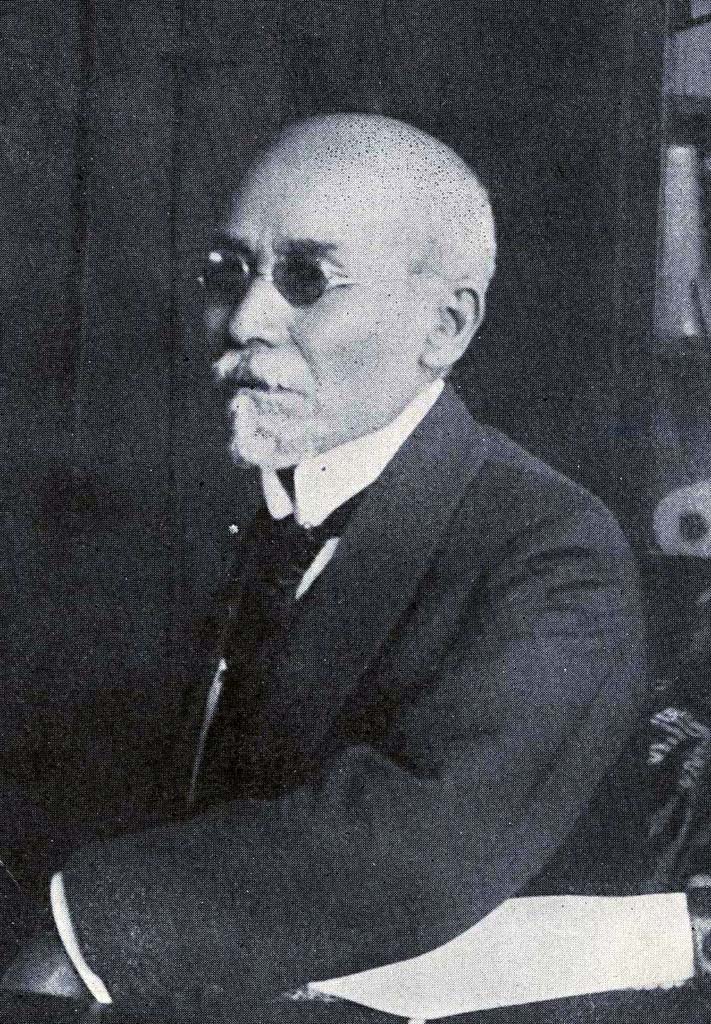 三根圓次郎(『三根校長追悼誌』より) |
|---|
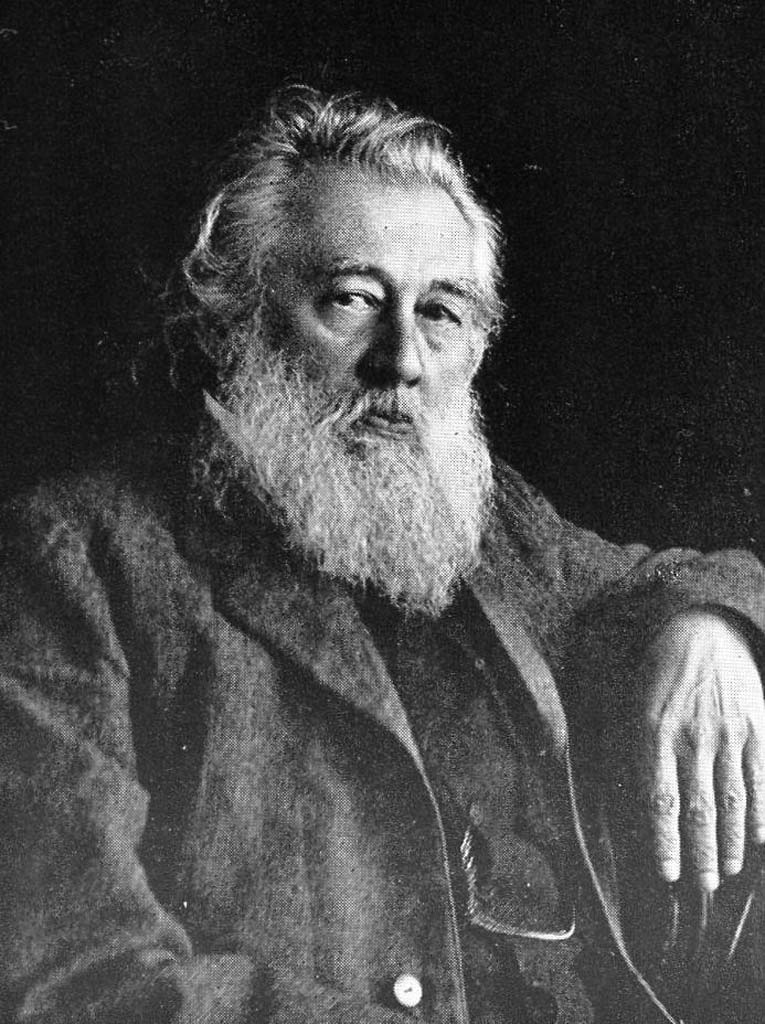 三根の恩師・ケーベル博士 (『ケーベル博士随想録』より) |
|---|
 三根圓次郎校長(土佐中高提供) |
|---|
≪お詫び≫筆者の校正ミスで、お名前に誤記があり、大変失礼致しました。黒鉄ヒロシ様、西村繁男様、ならびに読者の皆様にお詫び申し上げます。……中城正堯 回想浮世絵との出会いと子ども文化研究
中城正堯(30回) 2018.09.02
 筆者近影 |
|---|
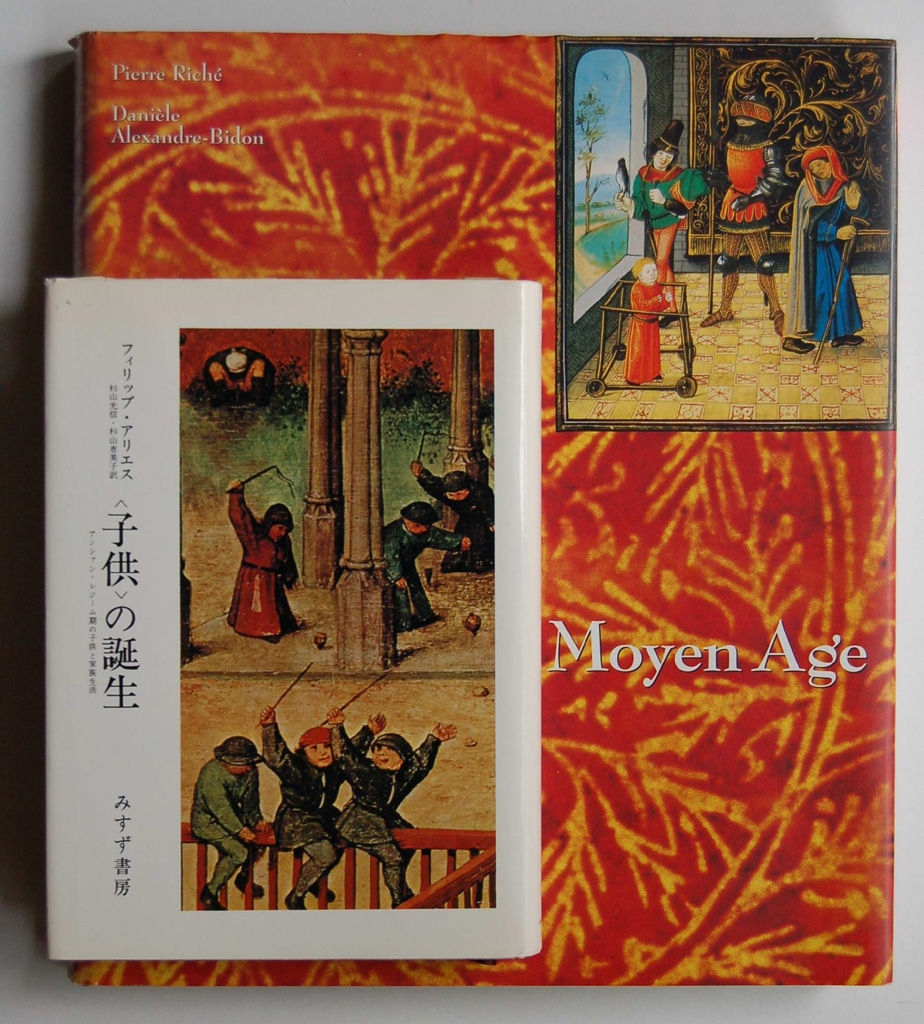 アリエス著『<子供>の誕生』と、 門弟による『L’enfance au Moyen Age』。 |
|---|
ただ、美人画や役者絵・名所絵・春画で知られる浮世絵が、はたして子ども文化研究に役立つ絵画史料としての質と量を持っているのか、周囲からは危惧された。しかし、幼い頃から実家の襖に貼ってあった浮世絵(坂本龍馬も眺めたと伝わる)に親しみ、土佐中の図工で横田富之助先生から浮世絵版画の制作指導を受け、さらに編集者としてアン・ヘリング先生(児童文学・おもちゃ絵研究者)など浮世絵愛好者と接し、自信を深めた。1986年に東京都庭園美術館で開催された「日本の子どもの本歴史展」でも、浮世絵版画の技法による多色刷の子ども本やおもちゃ絵(紙工作や双六など)が展示されており、子どもの遊びや学びを描いた子ども絵(風俗画)も、子ども向けの昔話や武者絵(物語絵)などもあるだろうと確信した。
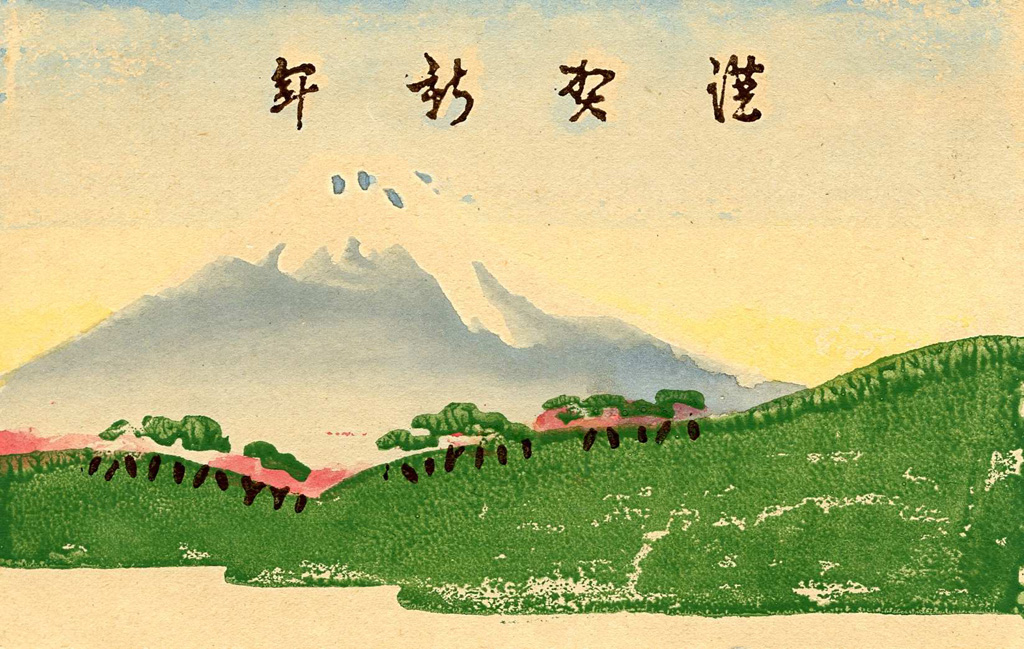 筆者土佐中時代の浮世絵「年賀状」。 |
|---|
また、国際交流基金が日本を代表する美術コレクションとして、1998年から翌年にかけてヨーロッパ巡回展(モスクワ・パリ・エディンバラ・ケルン)を開催。ケルンでは、ドイツに於ける日本年で秋篠宮両殿下に展示のご説明を仰せつかり、記念講演「浮世絵の子どもたち」も同時通訳付で行った。
 ヴァティカンでローマ教皇ヨハネ・パウロⅡ世と。 |
|---|
国際浮世絵学会では、「子ども浮世絵に見る魔除け」「もう一つの美人画“母子絵”」などを発表、学会誌『浮世絵芸術』に「<上方わらべ歌絵本>の研究」などを執筆した。今は、國學院大学を中心とする大学院生の子ども浮世絵研究会に、時折顔を出している。
なお、子ども浮世絵で世界に知られる存在となった公文教育研究会の収蔵品は、ウェブサイト『くもん子ども浮世絵ミュージアム』として公開されている。 <版画万華鏡・1>
土佐中での出会いから生まれた浮世絵コレクション
中城正堯(30回) 2018.11.25
巡航船で通ったバラック校舎で戦後民主教育
 筆者近影 |
敗戦から間もない昭和24年(1949年)に、土佐中学に入学した。ここでの3年間が、その後の人生を決めたと言っても過言ではない。編集・出版の世界に進んだのも、浮世絵の収集研究を始めたのも、この3年間があったからである。
|---|
 昭和27年2月に、校舎玄関前に勢ぞろいした新聞部員。 |
|---|
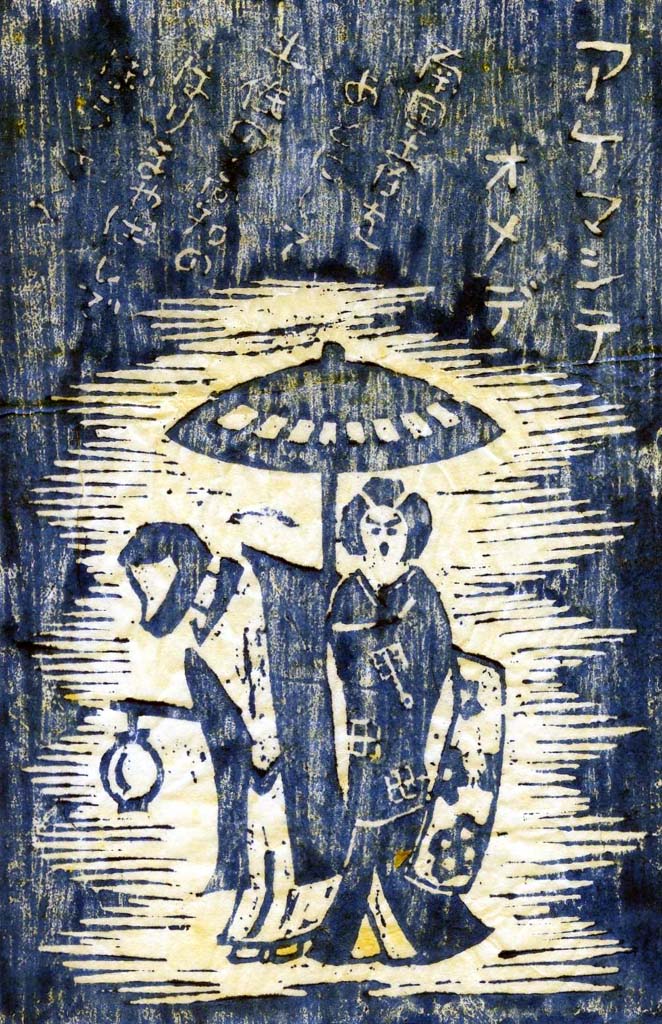 版画で制作した年賀状 「坊さんかんざし人形」 |
|---|
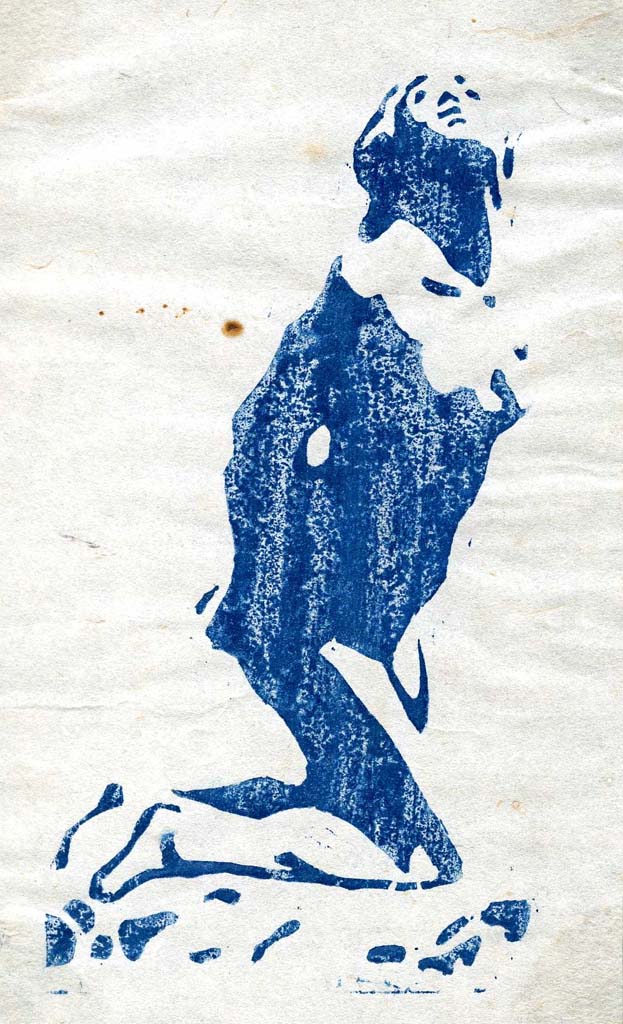 中高時代の自作版画。「女性像」 |
|---|
肝心の授業など学校生活はどうだったか、とにかく素晴らしい先生が揃っていた。海辺の田舎(種崎)育ちで、焼玉エンジンの巡航船で30分かけて高知桟橋に着き、さらに土電で梅ヶ辻へ出て通学した。校舎はオンボロながら、先生方は数学の公文公、生物の中山俊馬、漢文の吉本泰喜など碩学揃いで、充実したユニークな授業に引き込まれた。オンカンこと中山先生は、来高した天皇陛下に高知産貝類のご説明役を仰せつかるかと思えば、試験問題は高知新聞連載の時代小説から貧乏浪人の長屋暮らしを引用、「この小説に出て来る動物を分類せよ」であった。その動物とは、ムカデ、ゲジゲジ、ナメクジ・ゴキブリ・ノミなどだ。
他にも、各教科に山下芳雄(理科)、伊賀千人(社会)など後に大学教授になる研究心旺盛な先生や、タコ、カマスなどの愛称で呼ばれ、独自の授業展開で生徒を魅了するベテラン教師など、多彩であった。
公文先生・版画・新聞部、中学3年間で3つの出会い
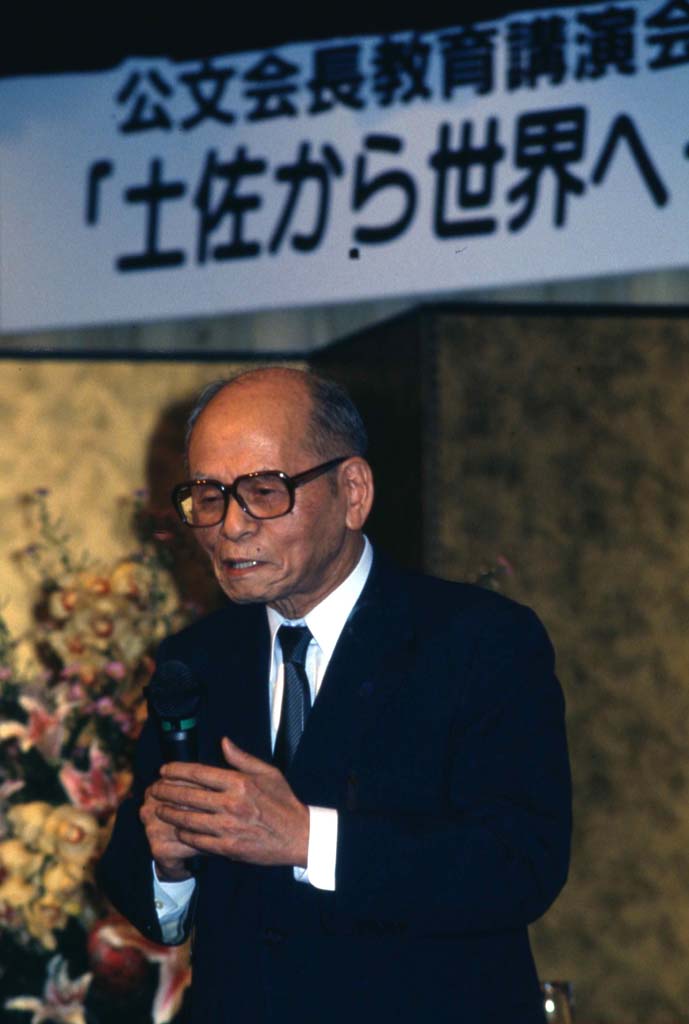 平成5年、高知で講演する公文公先生 演題は「土佐から世界へ」。 |
|---|
公文先生は、戦後の文部省カリキュラムに添った教科書による一斉授業だけでは、生徒の学力を十分伸ばすことはできないと考え、知寄町の自宅での指導も開始した。後に、「生徒のために旧制土佐中のように学年より先へ進める授業をしたかったが、学校に理解してもらえなかった。そこで、家へ生徒を呼び、代数の問題集と英文講読を始めた。個人別自学自習でどんどん先へ進んでもらった」と、語っている。当時の教室では、公文俊平・川村克彦両先輩(28回生)が、助手をしてくれていた。今や世界中で428万人が学ぶKUMON式の源流は、旧制土佐中教育と公文先生の高知での私塾であった。
筆者にとって楽しかった授業は美術で、洋画家の鎮西忠行先生が水彩画を、彫刻家の横田富之助先生が彫刻や版画を指導してくださった。特に高知女子大から教えに来ていた横田先生の、木版画制作に魅せられた。参考資料にあった北斎や広重の版画を真似て、「富士山」の多色摺年賀状(2018年7月、このHPに掲載ずみ)を制作、その後もロダンの彫像や「坊さんかんざし人形」などを版木に刻み、刷り上げた。坂本龍馬も見たという我が家の襖の絵「田原藤太百足退治」が、江戸後期の木版浮世絵であることにも気付かされた。
 実家にあった浮世絵 「田原藤太百足退治」(歌川国麿、弘化・嘉永頃) |
|---|
土佐中で出会ったこの公文先生、版画、そして新聞部が40年後に結びつき、「子ども浮世絵」の収集・研究が後半生の大仕事になるとは、思いがけないことであった。
子ども浮世絵研究とヨーロッパ巡回展
 子ども絵「風流をさなあそび」 (歌川広重、天保初期,公文教育研究会蔵)。 |
|---|
しかし、会社創設初期には教材開発、指導者養成以外に、資金調達、労働争議、教材の流出・模倣といった難題が次々に降りかかった。禎子夫人をはじめ、その実弟長井淳三、公文先生の長男公文毅、甥国澤建紀(36回生)など親族が事業に参画、さらに土佐中B組だった武市功(30回生、後副社長)、浅岡建三(中卒で転校、顧問弁護士・鑑査役)も経営中枢を支え、次第に体制が整った。昭和49年(1974年)には、海外最初の教室がニューヨークに開設され、見城徹(現幻冬舎社長)が企画した公文公著『公文式算数の秘密』(廣済堂出版)がベストセラーとなり、一挙に全国で生徒が急増した。
 ヨーロッパ巡回展モスクワ会場 左はロシアの文化大臣、右奥筆者。 |
|---|
この頃、公文教育研究会では経営も軌道に乗り、出版活動にも着手、武市功君から「公文公会長、公文毅社長が、出版担当で来て欲しいといっている。ぜひ来い。」との呼びかけがあった。こうして、昭和56年に公文に移籍、出版部(後にくもん出版として独立)の責任者に就任。その5年後に、くもん子ども研究所が設立され、兼務として理事になった。研究テーマを求められ、前例のない「浮世絵を絵画史料として活用した江戸子ども文化研究」を提案、自ら子どもに関する浮世絵など絵画史料の収集と研究に着手した。
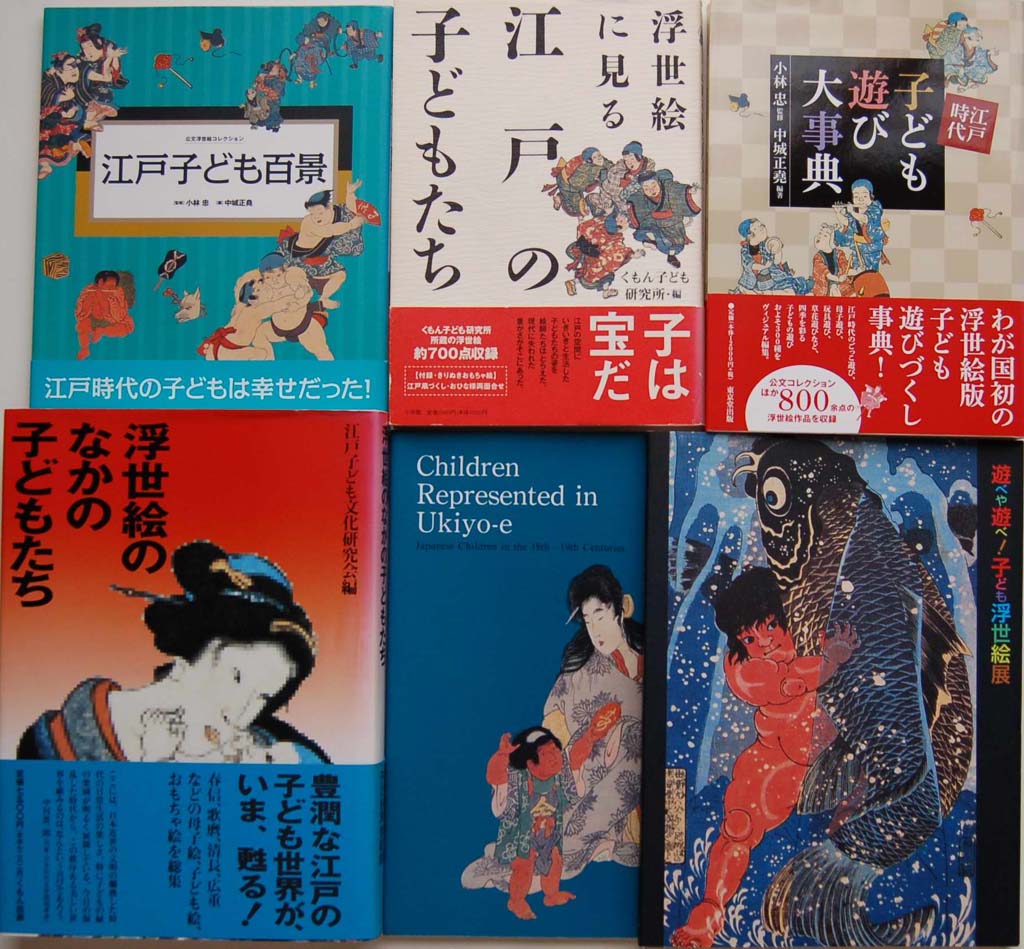 浮世絵に関する筆者の編著書 |
|---|
<版画万華鏡>と題したこの随想では、既刊の編著書からこぼれ落ちている版画に関するさまざまな思い出や、調査研究の断片を拾い集めて順次映し出したい。次回は兵庫県高砂市にあるなぞの巨石神殿「石宝殿(いしのほうでん)」の、護符版画を紹介しよう。 <版画万華鏡・2>
なぞの名所絵版画「播州石宝殿」と巨石文化
中城正堯(30回) 2018.12.23
水に浮かぶ巨石がご神体
昭和61年(1986年)から、くもん子ども研究所の「子ども浮世絵による江戸子ども文化研究」の担当となり、早速浮世絵収集を始めた。主な収集対象は、遊びや学びなど子どもの生活風俗を描いた子ども絵、そして母子絵、さらに子どもが紙工作や豆本・豆図鑑として楽しんだおもちゃ絵である。収集先は、神田の古書店、そして古書会館で毎週末に開かれる業界の即売会、またデパートの催事場で当時はよく開催されていた「古本市」などであった。むろん、大阪出張の際には梅田阪急の古書店街や京都の老舗古書店・浮世絵店にも立ち寄った。
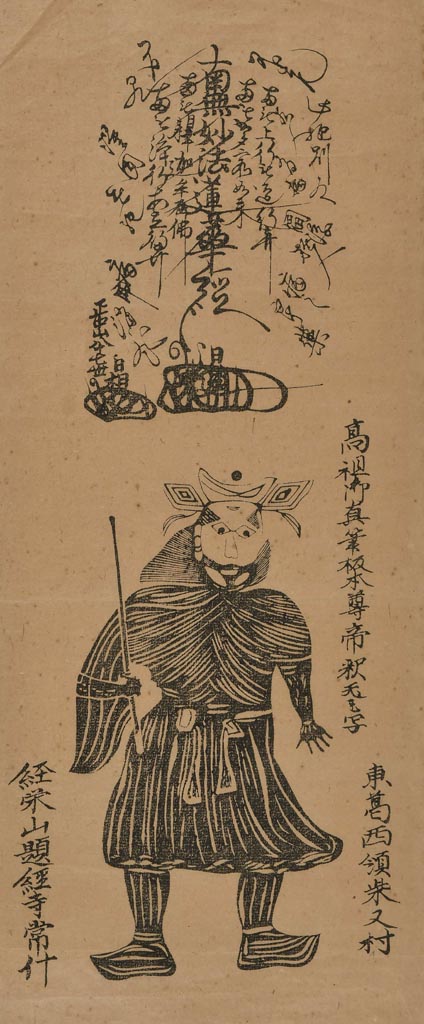 図1.「帝釈天像」町田市立 国際版画美術館「中城コレクション」 |
|---|
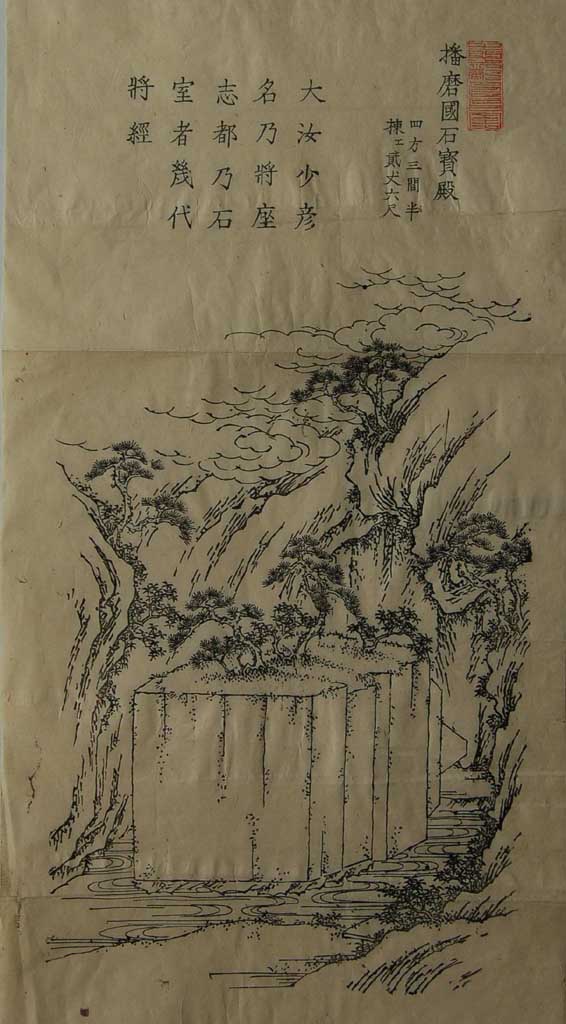 図3.「播州石宝殿図」筆者蔵 |
|---|
続いて「播州国石宝殿」(図3)の題で、水辺に浮かぶような巨石を描いた縦長の版画を見付けた。画幅に仕立てるための版画で、やはり万葉集の歌が添えてある。制作年代は、幕末か明治初年だろう。もう一点は、「播州石宝殿」の朱印を押し、「はりま いしのはうでん」と題した袋入りで、絵図二枚と神社縁起一枚がはいっていた。絵の一つが「播磨国石宝殿真景」(図4)で、明治中期の石版刷りだ。神社縁起には、「神代の昔に大穴牟遅(おおあなむち)と少毘古那(すくなひこな)の二神が天津神の命を受けて一夜で石の宮殿造営を始めたが、賊神鎮圧のために宮殿を正面に起こす前に夜明けを迎え、未完成となった。だが、二神の霊はこの岩に永劫に籠り、国土を鎮めると仰せになった。よって、石の宝殿、鎭の石室と称する」などとある。
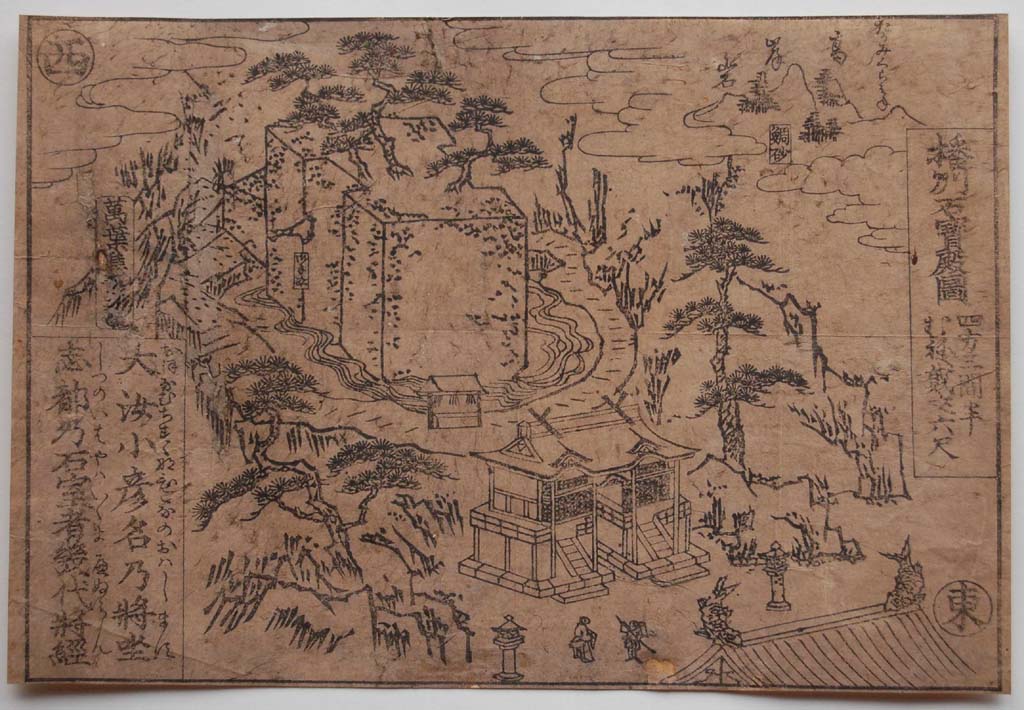 図2.「播州国石宝殿」筆者蔵 |
 図4.「播州国石宝殿真景」筆者蔵 |
|---|
シーボルトも見学した「日本三奇」の一つ
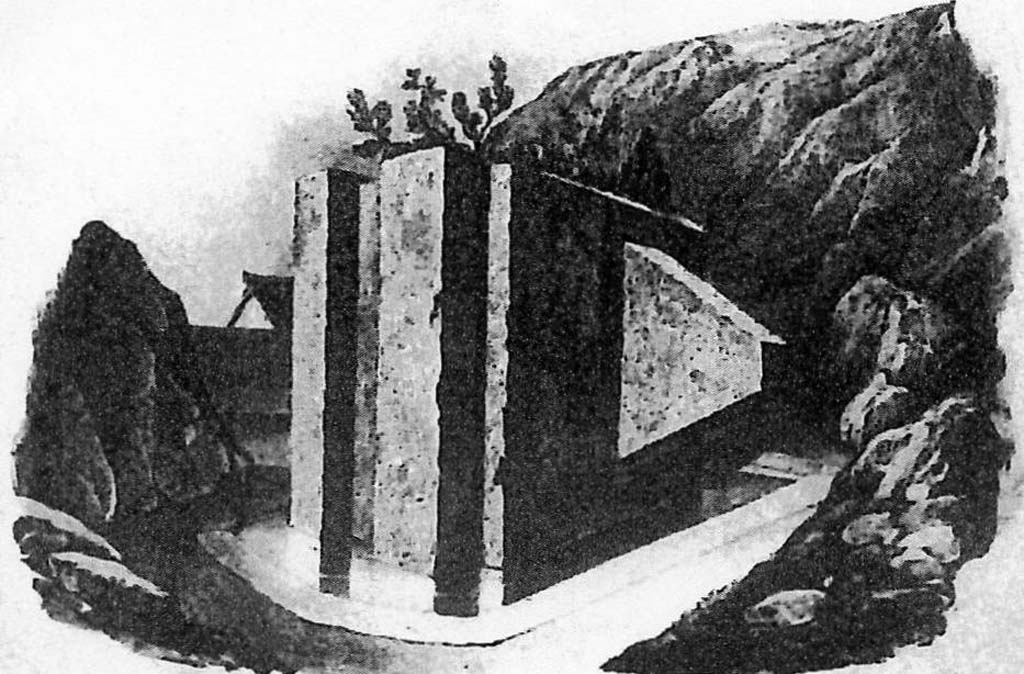 図5.シーボルトの見た石の宝殿 『Nippon』より |
|---|
 写真① 石の宝殿、左側面 筆者撮影 |
 写真② 上から見た左側面 筆者撮影 |
|---|
平成11年(1999年)、姫路城からの帰途に、ようやく石の宝殿を探訪することができた。山陽本線姫路駅から各停で三駅、神戸方向にもどると「宝殿駅」がある。タクシーで生石神社門前まで行き、高い石段を登ると立派な社殿が現われる。これが拝殿で、中央を抜けると御神体の巨石が鎮座している。岩山をくり抜き、奥の突起を屋根として、家を横倒しにした形状だが、周りの岩壁との間隔が狭く、標準レンズでは納まりきらない。ワイドレンズを待たずに来たのを悔やみつつ撮った写真が①~③である。
 写真③ 右後部からの石の宝殿と景観 筆者撮影 |
|---|
巨石を宮殿形に加工した古代石工の技術に驚き、江戸の人々が神わざと感じて「日本三奇」にあげたのも理解できた。社殿に「算額」を掲げてあったのも、幕末のこの神社の人気ぶりを示している。算額は和算の難題に挑んだ数学者が、解答を額にして名のある神社に奉納したもので、この算額は三角関数を駆使して解いた幾何の難問であった。宮司からお話を伺い、「生石神社略記」などをいただいて、神社を後にした。
巨石信仰の系譜を追って高知、エジプトへ
 写真④ 姫路城備前門の 左右石垣に使われた石棺 筆者撮影 |
|---|
 写真⑤ 明日香村の「益田の岩船」筆者撮影 |
|---|
巨石文化は国内各地に残り、高知県では足摺岬の唐人駄馬遺跡が知られる。この巨石群は一部岩面に線刻が見られる程度で、自然石である。ただ、巨石周辺から縄文・弥生の石器や土器が出土しており、巨石信仰の祭事空間であったと推定される。海外では、オーストラリア原住民の聖なる岩山ウルル(エアーズロック、写真⑥)が、同様の位置付けだ。
巨石に加工を施した巨石記念物も世界各地に残っている。筆者が訪ねたのは、アブシンベルとギザ、チリのイースター島、インドネシアの二アス島とスマトラ島だが、エジプトでは製作を中断したオベリスク(写真⑦)も訪ねた。さらに、国際的写真家・野町和嘉氏からいただいたエチオピア写真集『ETHIOPIA 伝説の聖櫃』を開き、ラリベラの岩窟教会(写真⑧ 世界遺産)を見て驚いた。巨大な岩盤を十字の形を残して掘り下げ、教会を造ってあるのだ。古代からの洞窟信仰とキリスト教が習合、6~13世紀に造られたとある。播磨での石の宝殿誕生とも時期が重なり、篤き信仰心が生んだ偉大な石造技術に驚嘆した。
 写真⑥ ウルルでの筆者 1965年 矢島康次撮影 |
 写真⑦ 製作を中断した エジプトのオベリスク 筆者撮影 |
 写真⑧ エチオピアの岩窟教会 野町和嘉『ETHIOPIA 伝説の聖櫃』より |
|---|
中城正堯(30回) 2018.12.25
「石の宝殿」面倒をかけましたが、冨田さんに続いて、高砂市からも下記の反響がありましたので、お知らせします。
では、よいお正月を!
************************************
中城 様
ご連絡いただき、有難うございます。ホームページ拝見させていただきました。図の画質が良く拡大もでき、とても見やすかったです。現地の写真も豊富で、石の宝殿を含め、実際の遺跡に行ってみたくなる印象を受けました。
この度は、石の宝殿を取り上げていただき、有難うございました。また今後とも、高砂市の文化財行政にご協力の程、よろしくお願いします。
-------------------- ∴ ------------------
高砂市教育委員会 生涯学習課 文化財係 奥山 貴
〒676-0823 兵庫県高砂市阿弥陀町生石61-1
Tel 079-448-8255 FAX 079-490-5975
E-Mail : tact7610@city.takasago.lg.jp
-------------------- ∵ ------------------ <町田市立美術館へのご案内>
福を呼ぶ「金のなる木」や「七福神」
中城正堯(30回) 2019.01.10
町田市立国際版画美術館で「中城コレクション」など展示
 筆者近影 |
|---|
同美術館の案内状には、「本コレクションの特徴は、吉祥画題を描いた版画が多数含まれていることです。なかでも中城氏は、豊作や商売繁盛、勤倹貯蓄を表す「金のなる木」の図像が、多数の浮世絵、引札、民間版画に見出せることに注目し、収集しています。もとは中国版画にみられる「揺樹銭」のモチーフから発展したもので・・・」等とある。写真は寄贈コレクションより二点。
・交通 JR横浜線・小田急「町田駅」下車徒歩15分****入場無料
・電話042―726―2771
 「金之成木」渓斎英泉 天保弘化頃 |
 「七福神宝船」作者未詳 天保頃 回文 |
|---|
美しき養蚕神に秘められた少女たちの哀話
中城正堯(30回) 2019.01.20
天竺から流れ着いた美少女“金色姫”
 図1.「衣襲明神」浮世絵 歌川芳員 嘉永安政頃 筆者蔵 |
|---|
立像の女神は、吉祥天のような衣服を着て、頭に鳳凰の冠と絹の反物を載せ、沓(くつ)をはいている。右手には蚕の種紙を、左手には桑の小枝を持つ。衣装の胸には、なぜかうずくまった馬の図がある。画面下部に落款「一寿齊芳員画」と版元印「藤慶」があり、幕末の歌川派絵師・芳員が、江戸通油町・藤岡慶次郞の店から版行したとわかる。女神の周りを埋める賛には、およそこんなことが書いてある。
<かけまくもおそれおおくも、これは養蚕の祖神、常陸国日向川(ひなたがわ)村、蚕霊山(さんれいざん)聖福寺の衣襲明神である。この神を祭れば、養蚕をする家は蚕がよく育ち、蚕屋のネズミを防ぎ、蚕はすべて繭となり、万倍の利益を得る。一般の男女がこの神を信心すれば、衣食住とも恵まれること疑いなし>
江戸後期の養蚕ブームで、常陸国日向川村(現茨城県神栖市日川)聖福寺の養蚕護符「衣襲明神」が評判になり、数多く作られた。この錦絵護符は、嘉永安政(1848~60)頃に出た一枚だ。当時、この衣襲明神は聖福寺境内に祀られていた。由来は、こう語られている。
<孝霊天皇(紀元前285年)の春3月。豊浦浜(日川)の漁師権太夫が、沖に漂う小舟を引き上げてみると、世にも稀な美女が倒れていた。少女は天竺(インド)霖夷国の金色姫で、国一番の美女だったが継母に憎まれ、桑の木で造ったうつぼ舟に乗せられ海に流された。豊浦浜に漂着、権太夫に愛育されるが病死して蚕となり、養蚕をこの地に伝えた。金色姫と権太夫に感謝して、村人は蚕霊神社を造営した>
江戸のコピーライター馬琴が生んだ衣襲明神
 図2.「衣襲明神之像」富山版画 明治時代 筆者蔵 |
|---|
江戸後期から明治にかけての養蚕ブームを反映して、『養蚕機織図』には30種類を超える養蚕の神仏護符が掲載されていた。その最古の作品が、文政10年(1827)に鶴屋喜右衛門版行の「衣襲明神」であり、絵師名の落款はないが撰文は「曲亭陳人」とある。『南総里見八犬伝』で知られる曲亭こと滝沢馬琴が、八犬伝を執筆中に書いたものだ。彼の日記には、「文政10年1月20日に鶴屋から依頼あり、鹿島の千手院聖福寺などで調査させる。3月19日に稿を終える」などと、経緯がきちんと記されている。
筆者所蔵の芳員作品の賛は、ごく一部の表現を変えただけで馬琴の撰文をいわば流用している。この流用は、明治時代の各種「衣襲明神」まで続く。養蚕農家にとって、蚕の種紙を購入したあと、無事に繭に育て上げるまでには、桑の栽培やネズミの害防止などさまざまな課題があり、神頼みをせざるを得なかったようだ。その心理を巧に汲み取り、さらに一般民衆に対しても、この護符の御利益を説いてある。
養蚕の祖神「衣襲明神」の名称も馬琴の創作であり、古事記や日本書紀、さらには現在の神名辞典にも登場しない。「衣笠・絹傘」をもじっての造語であろう。神道の古典的な養蚕守護神・稚産霊神(わかむすびのかみ)などに代わって、民間信仰として興った衣襲明神が農民の信頼を得たのだ。馬琴は江戸を代表する戯作者だけに、コピーライターとしても見事な筆力で、平賀源内がうなぎ屋におくった「土用うしの日」と並ぶ名作だ。ただ画像は、女神の容姿・表情・色調とも芳員の浮世絵が最も優れている。明治時代の女神は、化学染料によるどぎつい彩色が多い。胸の馬も馬琴にちなむともいうが、根拠不明だ。
ではここで、同じ衣襲明神ながら女神立像でなく、騎馬像のタイプを見てみよう。「衣襲明神之像」(図2)と神名が大書してあり、「富山市袋町高見喜平版」とある。薄墨の馬にまたがった女神の装束は立像とほぼ同様だが、宝冠をかぶり、帯状の天衣をひらめかせ、右手に種紙を左手に手綱を持ち、馬の足元にはまっ白の繭が散らばる。
オシラサマが伝える馬と少女の悲恋
 図3.「オシラサマ」左が馬頭 北上市博物館 筆者撮影 |
|---|
富山版画の衣襲明神にも、馬琴の撰文を簡略化して付けたものがあり、女神の姿・所持品も類似しているが、なぜか女神が馬に寄り添った像や、騎馬像が現れる。『売薬版画』は、三種類の「衣襲明神」を載せ、「関東・東北地方の養蚕地帯へ持っていき、配ったもの」と述べ、さらに岩手県遠野の伝説が生んだ信仰の中に「オシラサマ」(図3)という悲話があるとして、柳田国男の『遠野物語』から、こう紹介してある。
<昔あるところに貧しき百姓あり。妻はなくて美しき娘あり。また一匹の馬を養う。娘この馬を愛して夜になれば厩舎(うまや)に行きて寝(い)ね、ついに馬と夫婦になれり。或る夜父はこの事を知りて、その次の日に娘には知らせず、馬を連れ出して桑の木につり下げて殺したり。その夜娘は馬のおらぬより父に尋ねてこの事を知り、驚き悲しみて桑の木の下に行き、死したる馬の首に縋りて泣きいたりしを、父はこれを悪(にく)みて斧をもって後より馬の首を切り落とせしに、たちまち娘はその首に乗りたるまま天に昇り去れり。オシラサマというはこの時より成りたる神なり>
二つの養蚕神の習合拡散、そして退場
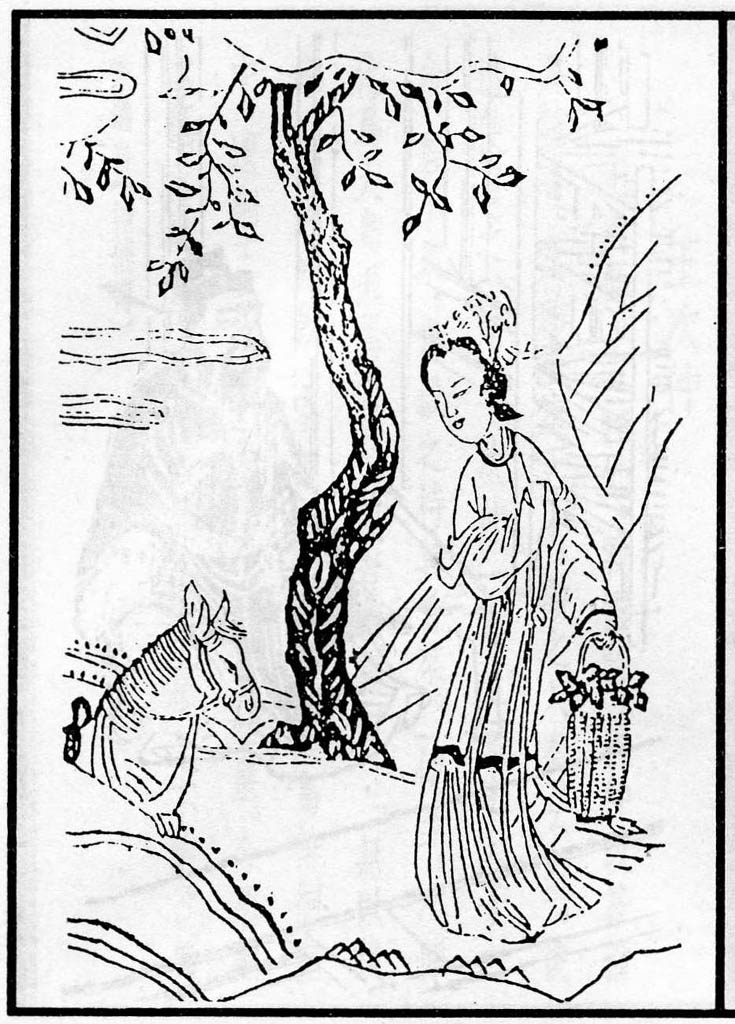 図4.「蠶女」『中国神仙画像集』 (上海古籍出版社)より |
|---|
 図5.「馬と娘」絵馬 遠野市 現代 筆者撮影 |
|---|
 図6.「多賀大社像」画幅(部分) 木版手彩色 筆者蔵 |
|---|
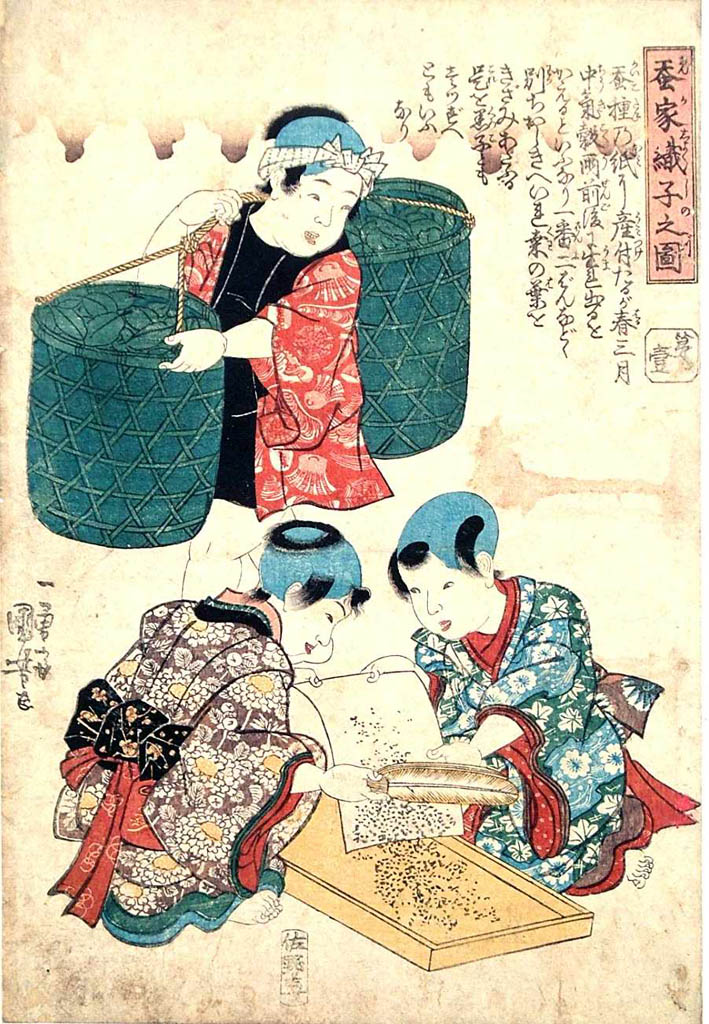 図7.「蚕家織子之図 第壹」浮世絵 歌川国芳 天保頃 公文教育研究会蔵 |
|---|
明治になると神仏分離が強行され、常陸聖福寺では衣襲明神を祀る蚕霊神社が独立、寺は馬鳴菩薩を祀る。養蚕業の大ブームもあって、衣襲明神・金色姫・馬鳴菩薩など、さまざまな養蚕神仏像がもてはやされた。だが、養蚕産業の衰退とともに、養蚕神は急速に退場、艶やかな絹糸の輝きの背後にあった守護神・金色姫たちも姿を消す。だが、残された浮世絵の養蚕護符や子どもの養蚕絵からは、当時の養蚕への人々の熱い想いが伝わってくる。次回は、戦前高知でも見られたが、今や全国的にも消滅寸前の打毬(和製ポロ)の画像をお見せしたい。 <版画万華鏡・4>
和製ポロ“打毬”を楽しんだ江戸の子ども
中城正堯(30回) 2019.02.17
将軍吉宗が復活させた騎馬打毬
 (図1)「子供あそび〈打毬〉」歌川貞房 天保頃(公文教育研究会蔵) |
東京の古書店で、馬に乗った二人の少年が網竿を手に紅白の球をすくい合う場面を目にして驚いたのは、平成3年(1991年)の春であった。子どもを描いた浮世絵の収集を始めて5年ほどたっていたが、これまで目にした作品には町人の子どもしか見当たらなかった。この絵の子どもは腰に刀を差し、立派な鞍を付けた馬にまたがっており、どう見ても武家の少年である。(図1)
|---|
 (図2)「風流見立狂言 しどう方角」勝川春朗 (葛飾北斎)寛政頃(公文教育研究会蔵) |
|---|
これが珍品であるのは、まず作者・春朗が若き日の葛飾北斎であることだ。彼は北斎以前に春朗や宗理などと名乗った時代があり、その頃は子ども絵も手がけている。しかし北斎になってからはほとんどなく、『北斎漫画』にも、子どもの姿はわずかしか描いてない。
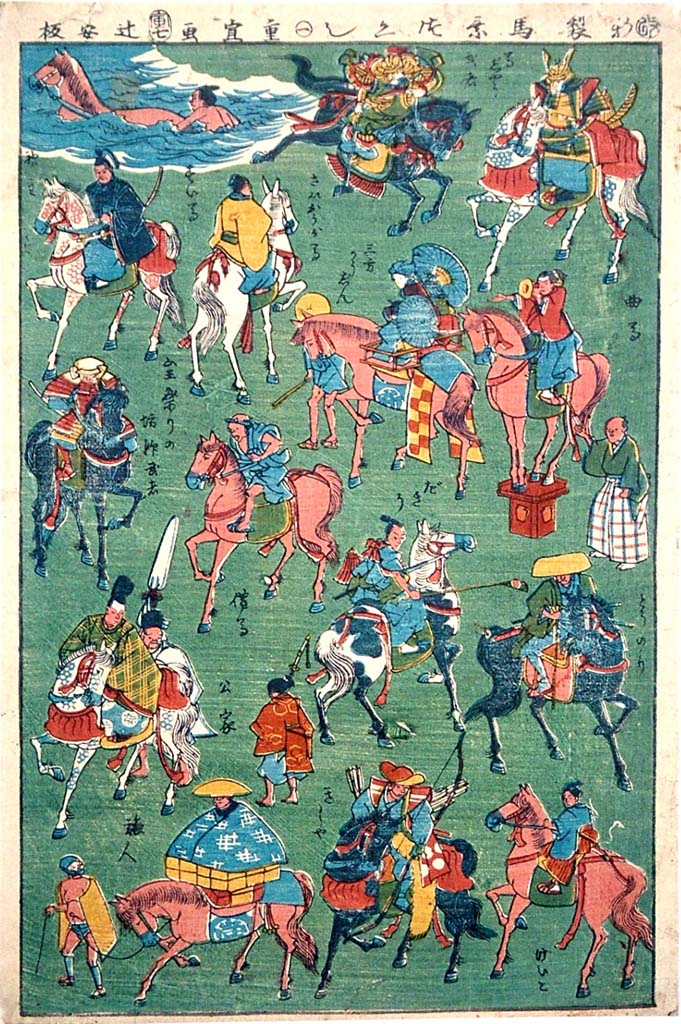 (図3)「新製馬乗づくし」中央に打毬 歌川重宣 安政元年(公文教育研究会蔵) |
|---|
春駒を使った子どもの馬遊びの浮世絵には、春朗の少し前に北尾重政の「やつし八景 勢田夕照」もあり、春駒にまたがった子どもが大名気分で近江・瀬田の大橋を渡っている。江戸後期の嘉永・安政になると、子どもが遊びに使った“おもちゃ絵”に馬が多くなる。一つは「源平打毬合戦双六」(歌川国郷)などの双六で、紅白の駒を毬門(ゴール)まで競って進めた。もう一つは、馬の用途・毛色による種類や歴史的名馬を図示した「馬づくし」の豆図館で、「新製馬乗づくし」(図3・歌川重宣)など各種あった。これらの流行は、江戸の子どもにとって歴史的名馬や騎士の姿が、あこがれの的であったことを示している。
インパールで続くポロと消えた土佐の打毬
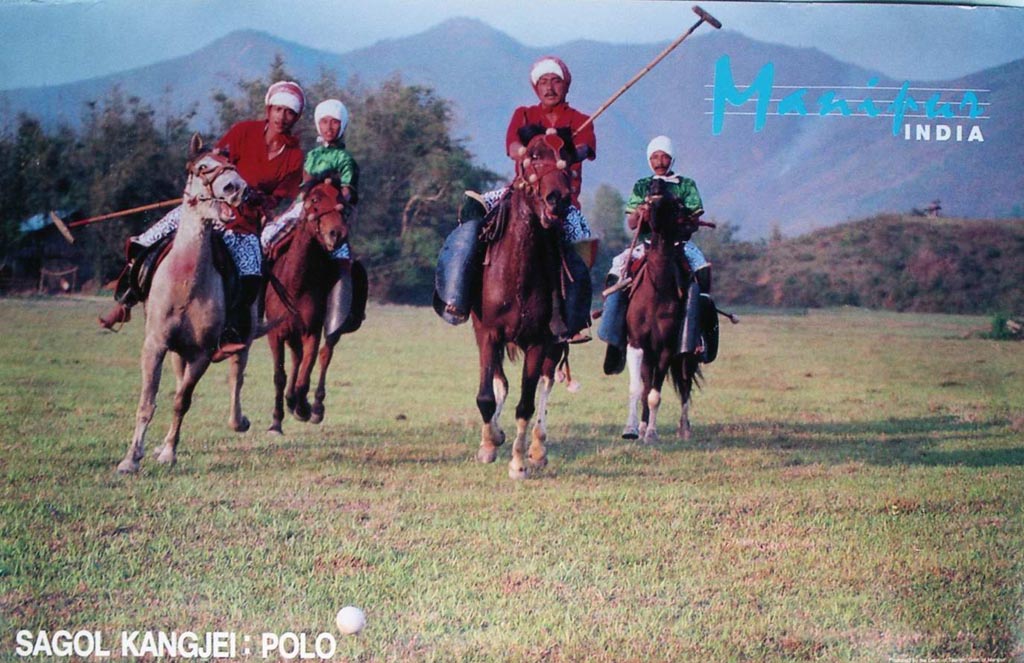 (図4)インド、マニプルのポロ試合ポスター(筆者撮影) |
|---|
江戸の打毬は狭い馬場で、網の付いた毬杖で毬をすくって毬門に投げ込むが、ここは広いグランドでの競技であり、硬い木の球をマレットで相手のゴールに打ち込んで勝敗を競う。ゴールはグランドの両端に設けてあり、馬場の片側にゴール(毬門)を設ける打毬とは異なる。馬は小型馬ポロポニーだが、江戸時代の日本馬よりはだいぶ大きいようだ。
帰国して調べると、ポロは古代ペルシャの遊牧民世界で始まり、やがてチベット経由で中国へも伝わって唐の王朝で盛んになり、この中国式打毬が奈良王朝にもたらされる。いっぽう、ペルシャからインドへも伝わり、マニプルでは藩王たちに楽しまれてきた。1850年代にイギリスで紅茶ブームが起こり、アッサム紅茶を求めてこの地にイギリス人が押し寄せ、英国軍も駐屯した。やがて騎馬隊をはじめ軍人たちがポロに夢中になり、本国にも持ち帰って競技を楽しみ、ヨーロッパに広がる。さらにイギリスの世界進出にともなって、米国・濠州・南米へと広がったのである。こうして、ペルシャで生まれたこの競技は、中国・日本型の打毬と、インド・イギリス型のポロに分かれていった。
 (図5)「千代田之御表 打毬上覧」楊洲周延 明治28年頃(筆者蔵) |
|---|
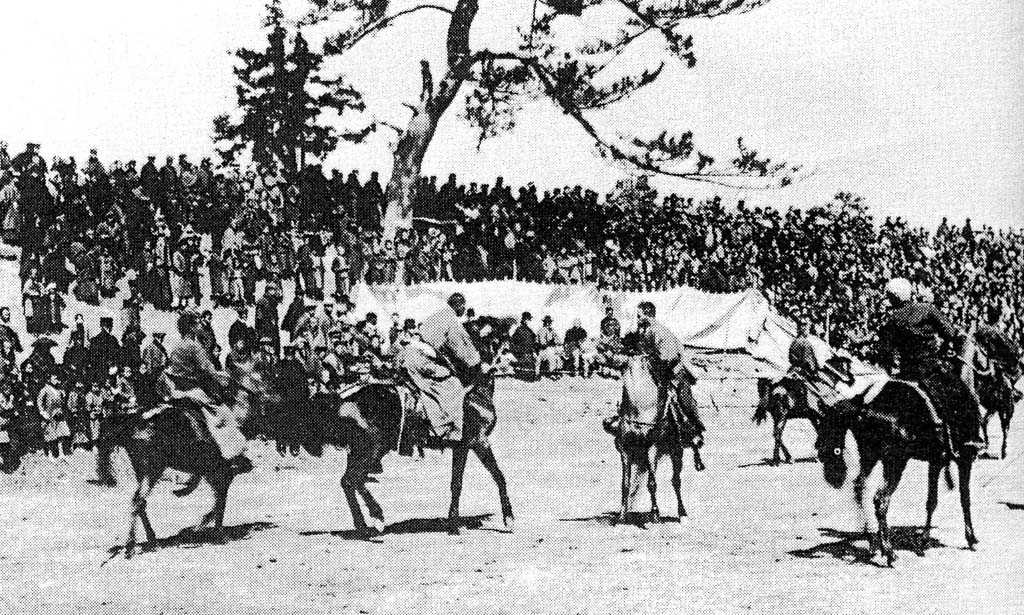 (図6)「土佐独特の打毬」絵はがき 昭和初期(『絵葉書 明治・大正・昭和』より) |
|---|
 (図7)「金太良三人兄弟」鴨をさばく次男 喜多川歌麿 寛政末(公文教育研究会蔵) |
|---|
八戸に生きていた江戸の騎馬打毬
平成7年9月「愛馬の日」に、東京世田谷の馬事公苑で記念事業として、宮内庁主馬班による打毬試合(図8)があると聞き、生きた打毬を初観戦した。
 (図8)馬事公苑での打毬試合 平成7年(筆者撮影) |
|---|
 (図9)加賀美流騎馬打毬で毬を奪い合う騎士 平成9年(筆者撮影) |
|---|
ここでも、相手の妨害を防ぎつつ毬を毬杖ですくっては毬門に近づき、投げる。左手で手綱を握り、右手で長い毬杖をふるって毬を投げ込む技が見所だ。主審の見定(みさだめ)奉行がゴールの判定をしており、毬門からはずれた毬は投げ返される。
 (図10)力一杯毬を投げた騎士、右後方が 上覧席 平成14年(筆者撮影) |
|---|
この周辺は、古くから南部駒で知られた馬産地であり、馬を飼育する農家や愛好家が中心になって八戸騎馬打毬会を結成、伝統の馬術を守り続けている。平成14年にも再訪した。騎手の中に中学生がいたのは頼もしい限りだった。現在打毬は、この加賀美流と宮内庁流の二種が受け継がれ、山形市豊烈神社でも宮内庁流の打毬がおこなわれている。
海外のポロは英・米そしてアルゼンチンが三大帝国だと『ポロ その歴史と精神』(森美香 朝日新聞社)にあるが、持病で海外渡航ができなくなり、見学はかなわなかった。今はポロに由来するポロシャツを着て、広いグランドを駿馬で激しく駆け回るスポーツとしてのポロを夢想するのみだ。
打毬では礼節が尊ばれ、かつて初ゴールは上級武将に譲る慣例もあったと聞く。軍人・貴族・富裕層のスポーツとなったポロの試合では、貴族相手でも遠慮なく、激しく馬体をぶつけ合って球を撃ち、怪我も恐れず勝敗を競う。古代ペルシャ以来の壮大な馬術文化の潮流は、東西で違った様相を見せている。
浮世絵「子供あそび〈打毬〉」の発掘は、江戸文化のなごりを求めて各地をめぐる楽しさを与えてくれ、今に生きる〈打毬〉にも出会えた。同一文化が伝播しても、受容地によって大きく変化する面白さも体験できた。次回は、「浮世絵そっくりさん」を紹介しよう。 <版画万華鏡・5>
布袋と美女のそっくり版画から“おんぶ文化”再考
中城正堯(30回) 2019.03.23
ネパールの布袋が背負うは女神か遊女か
 図1.ネパール版画 「布袋と美女の川渡り」筆者蔵 |
 図2.ネパール版画 「ヒンドゥー教の女神」部分 筆者蔵 |
|---|
ネパールで布袋様と出会ったのは、1990年であった。首都カトマンズの古い街並みを散策し、版画店でヒンドゥー教のシヴァ神、カーリー女神、さらには象頭神ガネーシャ、日本で弁才天となったサラスヴァティーなどの楽しい版画を購入した。浮世絵と同じ木版画だが多くは墨摺で、彩り豊かな作品は手彩色を加えたもの、いずれも安価だ。
そこでなんと「布袋と美女の川渡り」(図1)を見付けたのだ。美女を背に川を渡るのは、髭面で太鼓腹の紛れもない布袋様だ。仏陀(釈迦牟尼)はネパールでもよく見かけるが、布袋とは珍しい。背中の美女が異様で、まげを結い、波千鳥文の着物に大きな帯を結び、一見江戸時代の遊女風だが、上半身裸で乳房を見せており、彫りが深い目鼻立ちはヒンドゥー教の女神(図2)を連想させられる。布袋の川渡り自体は、浮世絵画集で見た記憶があり、何はともあれ購入した。
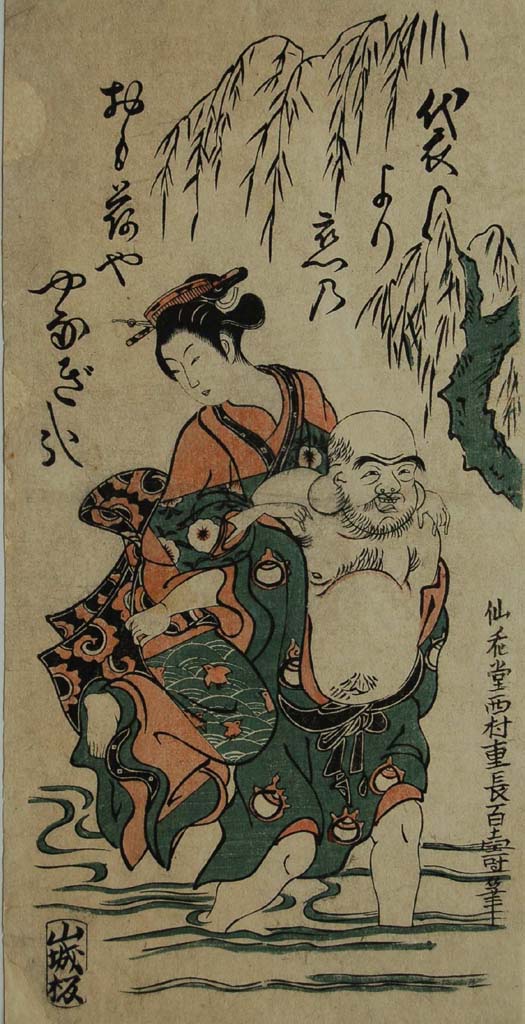 図3.西村重長 「布袋と美女の川渡り」筆者蔵 |
|---|
 図4.室町期狩野派 「布袋図」ボストン美術館蔵 |
|---|
 図5.コッヘム城壁画 「キリストを背負う聖人」筆者撮影 |
|---|
印象派の女性画家が歌麿母子絵に感動
聖人が重荷を背負って川を渡る姿もよいが、おんぶといえばやはり母の背の我が子であろう。その最高傑作とされる絵画が、喜多川歌麿の母子絵である。フランスの作家ゴンクールは『歌麿』(1891年パリ刊、2005年平凡社刊)で、「遊郭の女を描くこの画家の興味深い一面は、母性のテーマ」と述べ、授乳・行水・おしっこなど、幼児を優しく世話する母親の表現を絶賛、こう記している。
「母子群像の内で最も幸福な場面の一つが、子供を背負った母親と母の肩から身を乗り出した子供が、手水鉢に入れた水を二人してのぞき込んでいる図である。溜水は自然の鏡となって、くっつき一体化し、抱き合っているような母子の姿を映し出している」
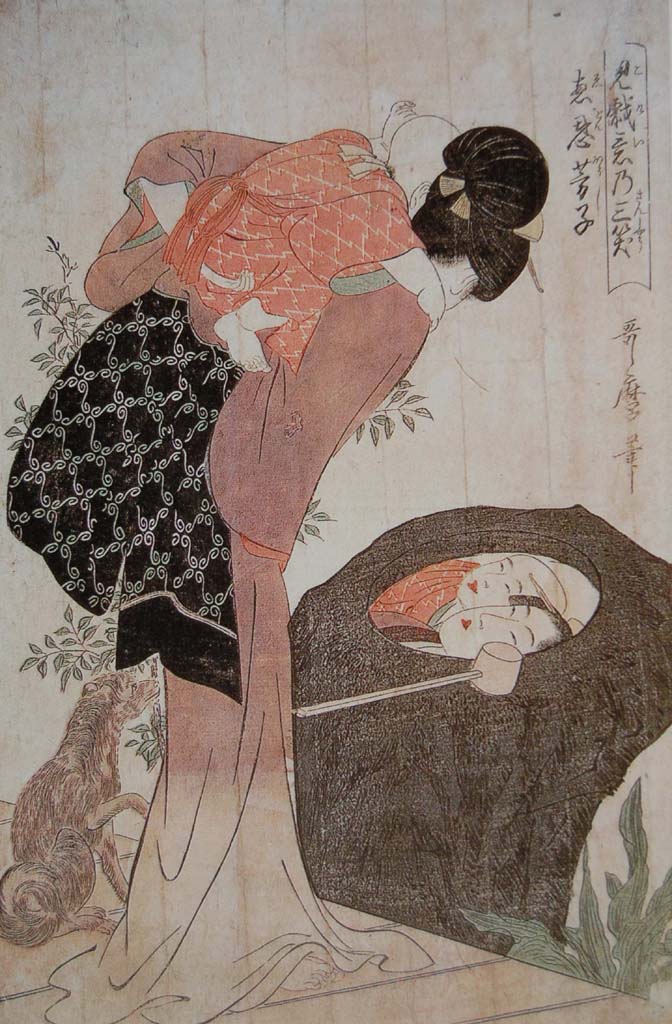 図6.喜多川歌麿「児戯意之三笑」 大英博物館蔵 |
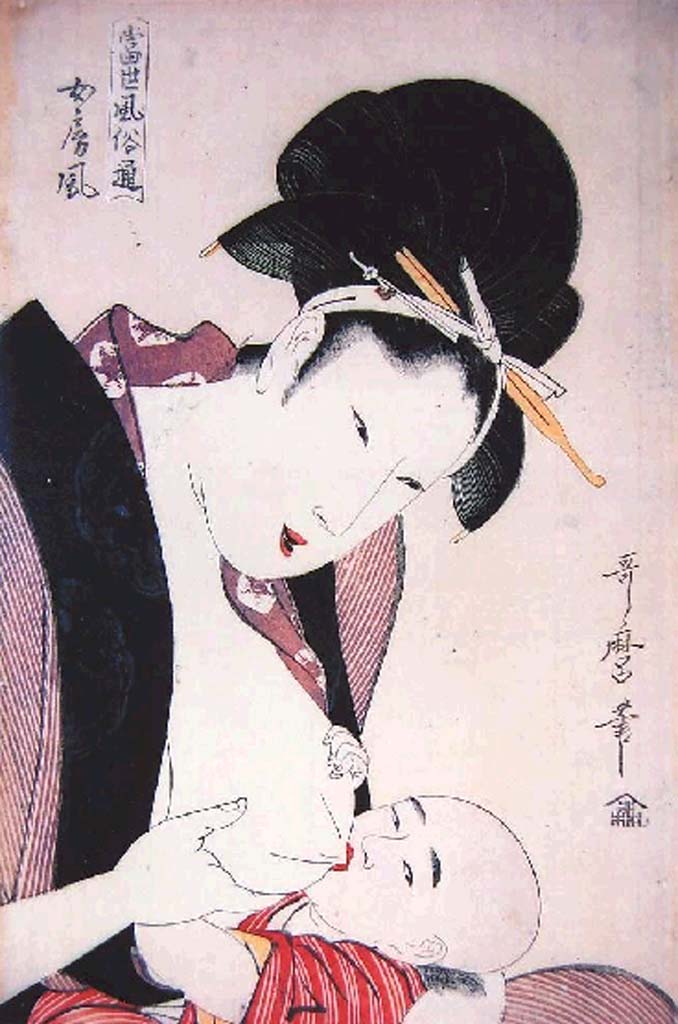 図7.喜多川歌麿「当世風俗通 女房風」 公文教育研究会蔵 |
|---|
歌麿亡き後も、浮世絵の母子絵は歌川国貞や歌川国芳などによって受け継がれ、子どもの遊び学ぶ日常生活を描いた子ども絵とともに、浮世絵風俗画の重要な分野になる。これは平和な時代になり、家の継続が重視され、子どもを大切にする子宝思想が広がるとともに、人々がこれらの浮世絵を競って購入した結果である。こうした背景を持つ歌麿の母子絵に感動し、追随したのは浮世絵師にとどまらない。
 図8.喜多川歌麿「行水」 MOA美術館蔵 |
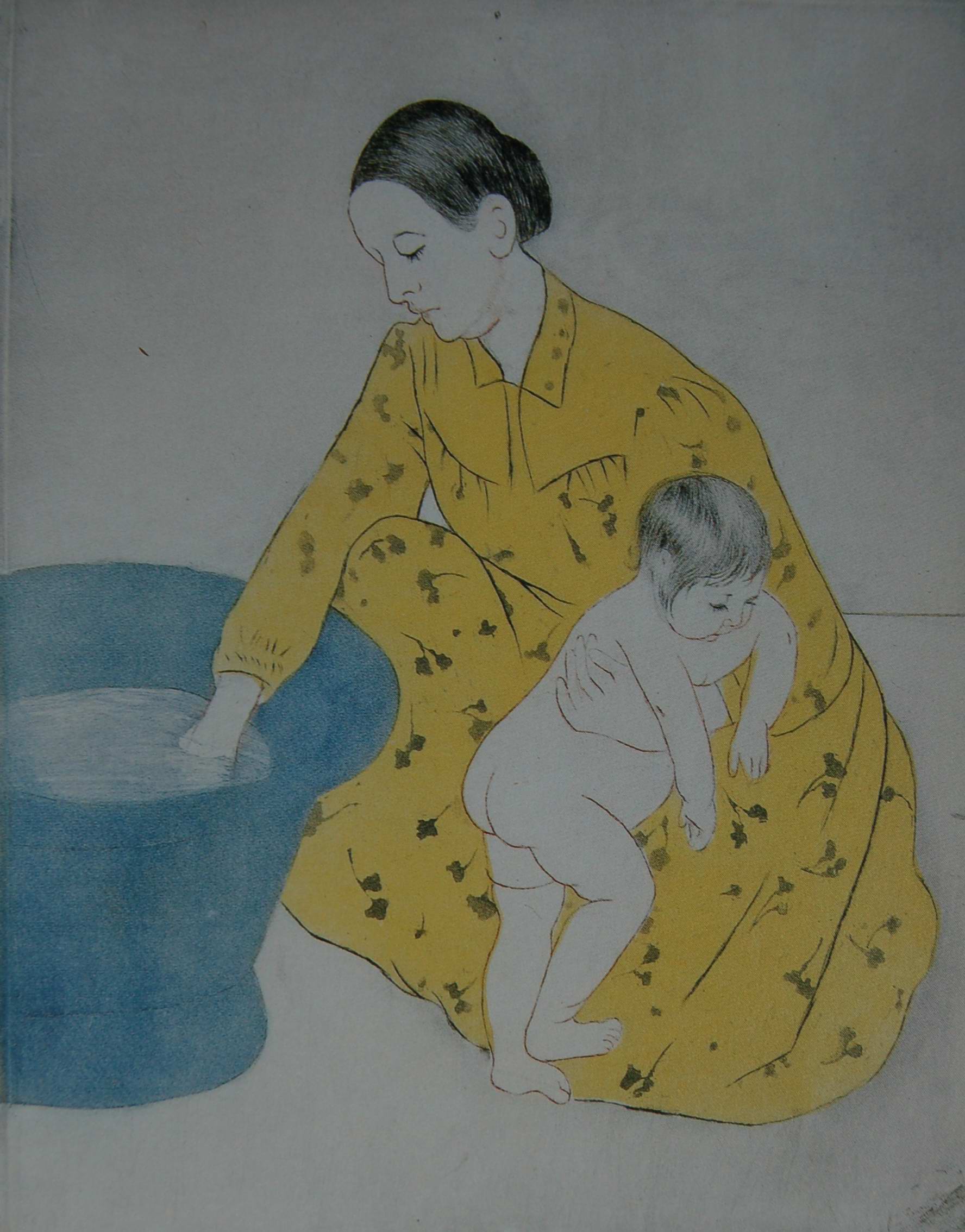 図9.M・カサット「湯あみ」 『メアリー・カサット展』横浜美術館より |
|---|
当時の女流画家は、裸体デッサン会には参加を許されず、キャバレーやカフェなどにも出入りできず、題材には大きな制約があった。また、子どもを里子に出す風習や、赤ん坊を布でぐるぐる巻きにするスワッドリングも見直され、家庭での新しい育児への移行期であった。アメリカ人のカサットは帰国後、母子がともに手鏡を見る姿や、歌麿の「行水」(図8)と同じ構図の「湯あみ」(図9)など、母子絵を多数描いて高い評価を得る。
江戸“おんぶ文化”のゆくへ
ネパールで、なぜ「布袋と美女の川渡り」のそっくりさんが版行されたか。まず、インドに接し、仏陀生誕国でもあり、ヒンドゥー教とともに仏教も信仰されてきた。中国生まれの布袋も、インドの弥勒菩薩の生まれ変わりとされ、違和感がなかったようだ。男女の合体神も、シヴァ・シャクティなど多々祀られていた。さらに、おんぶがネパールのみならず、ヒマラヤ南麓はじめアジア各国で広く見られる子育て風俗であることが大きい。
筆者が撮影した写真から、4点紹介しよう。ブータンの若い母子、シッキムの籠おんぶ、タイ北部のパラウン族(首長族)の横おんぶ、インドネシア・スマトラ島バタック族の姉弟(図10)である。おんぶ用具も、背負い方もさまざまであるが、家事や家業に従事しながらの育児に、また山道の移動に、おんぶが最適であったと思われる。
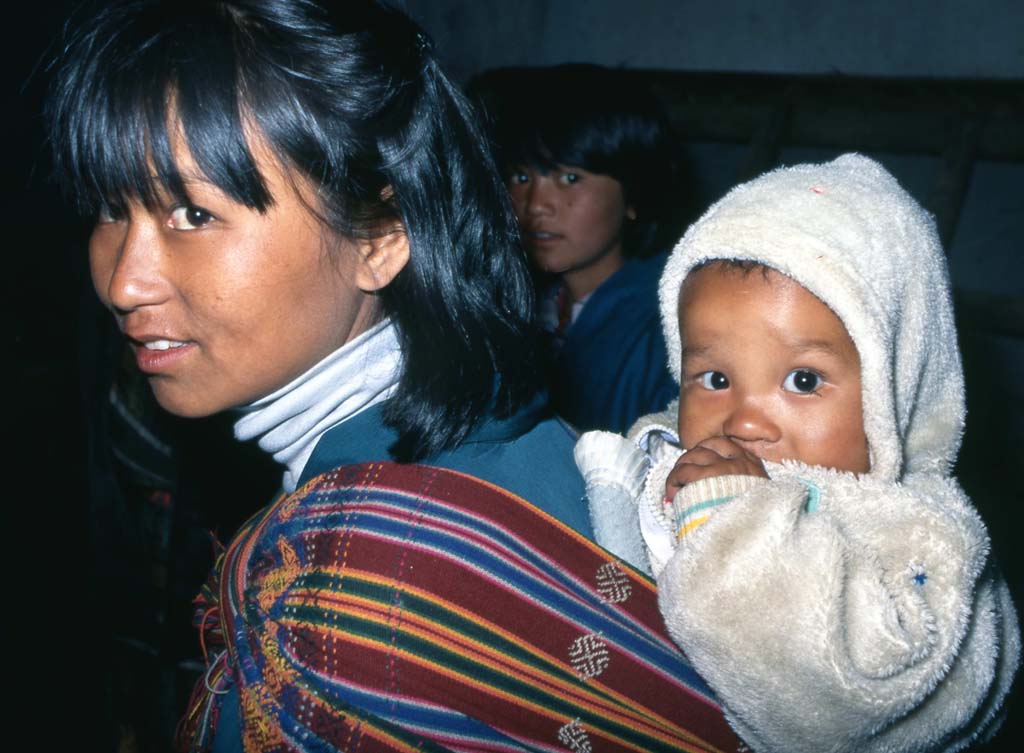 図10.アジアのおんぶ文化、筆者撮影。 ブータン |
 シッキム |
 タイ・パラウン族 |
 インドネシア バタック族 |
|---|
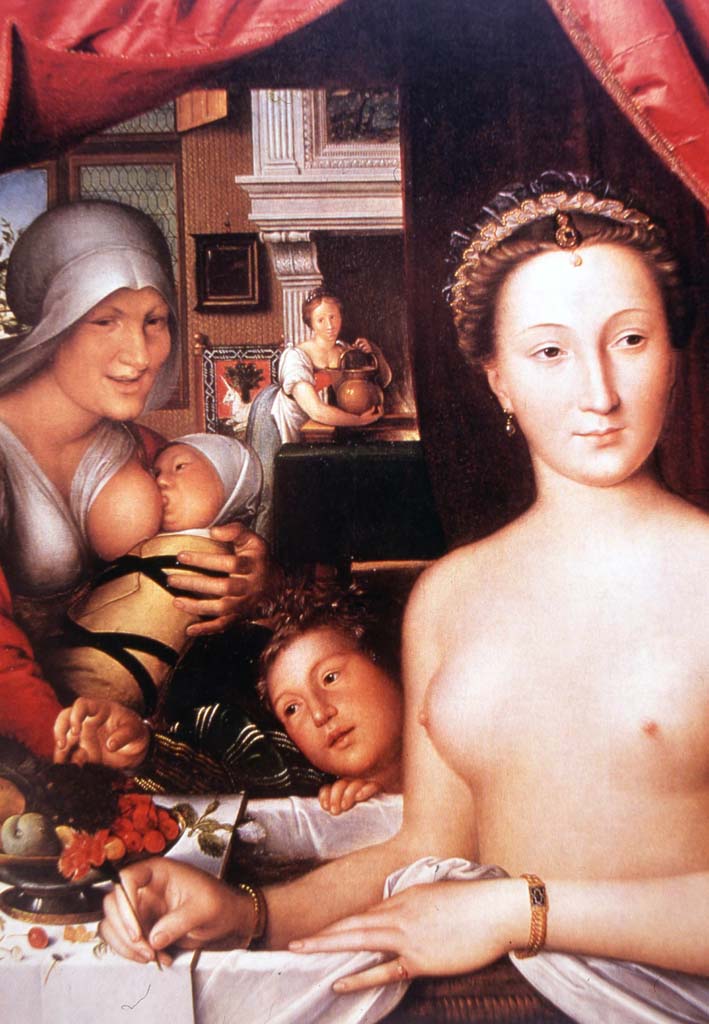 図11.F・クルーエ「浴槽のディアーヌ ・ド・ボワチエ」シャンティ城蔵 |
|---|
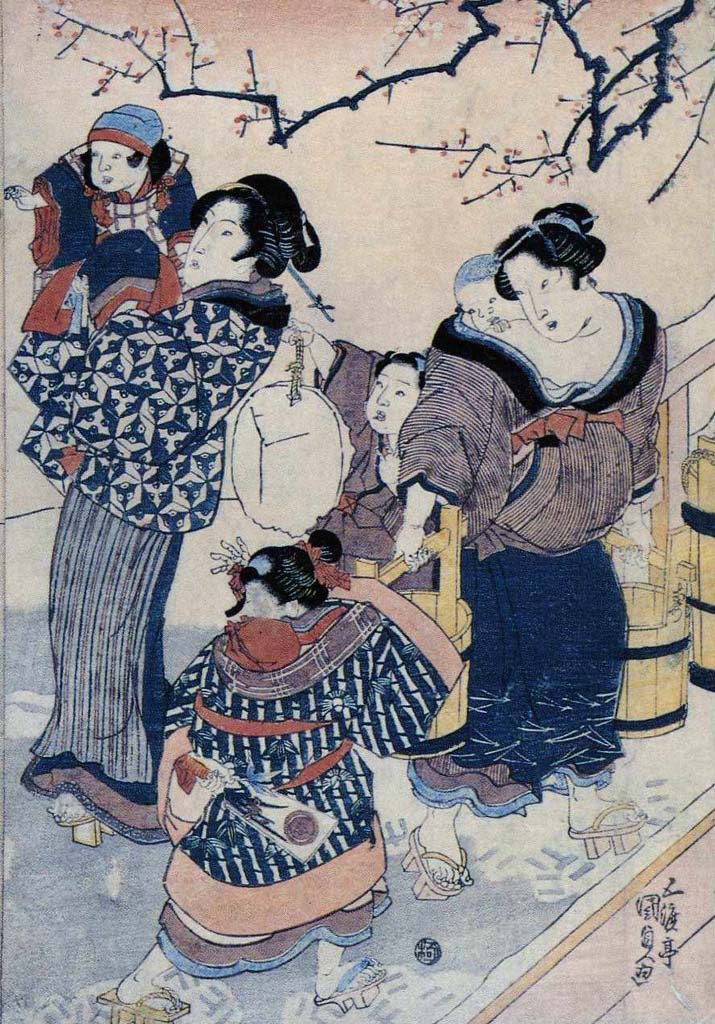 図12.歌川国貞「雪のあした」 公文教育研究会蔵 |
|---|
 図13.歌川豊国三代(国貞)「江戸名所 百人美女」 公文教育研究会蔵 |
|---|
 図14.現代イギリスのおんぶ エジンバラで筆者撮影 |
|---|
精神分析学の北山修九州大学名誉教授は、『浮世絵のなかの子どもたち』(1993年 くもん出版)で浮世絵の母子絵を見て以来、精力的に日欧の母子絵の画像を収集分析し、学会で発表してきた。そこで強調しているのは、浮世絵には「共に眺める〈共視〉」「みつめ合う〈対面〉」、そして「母子の身体的接触」が、西洋絵画よりはるかに多いことである。共視・対面・身体的接触、そして語り掛けからも、おんぶは乳幼児にとって最良の育児環境であっただろう。夫婦共稼ぎ、託児所保育の時代を迎え、これからの子育てをどう再構築するか、子ども好きだった布袋さんにチエを貸して欲しいものだ。 <版画万華鏡・5-2>
「布袋と美女、おんぶ文化」について
中城正堯(30回) 2019.03.31
見慣れぬ布袋様とおんぶ文化について、冨田さんはじめ何人かの方から、早速感想をいただき、感謝致します。浮世絵がヨーロッパのみならず、アシアでも模倣されたのは、浮世絵美術の素晴らしさとともに、江戸の町人文化の素晴らしさでもあります。
おんぶ及び子育てについて、図版での補足を少しさせていただきます。まず、ヨーロッパでのおんぶについてです。図1は、19世紀中頃のイギリス版画「山に住む人」(P・ポール画)で、スイス・アルプスの母子です。図2は、1884年頃のドイツ印象派F・ウーデの油彩画「姉妹」です。図3は、歌川広重の「木曽海道(ママ)六十九次之内 宮ノ越」(1837年頃・部分)で、祭りから夜道を帰る親子連れで、おんぶの父・だっこの母に姉が続き、名作とされています。広重は、風景画の中に子ども風俗を巧に織り込んでいます。
 図1.スイス・アルプスの母子 P・ポール画 |
 図2.「姉妹」 F・ウーデの油彩画 |
 図3.「木曽海道(ママ)六十九次之内 宮ノ越」歌川広重 |
|---|
 図4.育児書『やしなひ草』 『児童教訓伊呂波歌絵抄』 |
|---|
明治維新後は武家風の男尊女卑が強調され、女性は家庭に閉じ込められますが、江戸時代、町人の女性は多忙な家事家業に従事しながら、風流も楽しんだようです。 永森 裕子(44回)さん追悼文
惜しまれるフレスコ画研究の中断
中城正堯(30回) 2019.07.02
 2012年5月に加賀野井さんと 拙宅に来てくれた永森さん |
|---|
彼女がロンドンから帰国後、東京で国際児童図書文庫協会の活動を始めた時期に、新聞部OBOG会があり、再開してトータスにもお誘いしました。この頃、土佐高同窓会関東支部の会報「筆山」の編集長としても活躍しており、彼女の原稿依頼で駄文を提供したことでした。
 2010年Frankfrtにて (永森氏撮影) |
|---|
2006年秋から、1年半ほどイタリア・フィレンツェに滞在するので、しばらくトータスに出席できないとの話があり、それなら何かテーマを見付けて現地で調査し、帰国後に報告するようお願いしました。永森さんは、哲学美学修士を取得していただけに、イタリア各地のフレスコ画を探訪調査、2009年のトータスで見事な発表をしてくれました。これらの研究成果を論文にまとめる途中で発病したのは、大変悔やまれます。
心からご冥福をお祈り致します。 合田佐和子展 -友人とともに-
中城正堯(30回) 2019.07.15
合田さんの個展案内が届きました。
************************************************************
みうらじろうギャラリーより展覧会のご案内をさせていただきます。
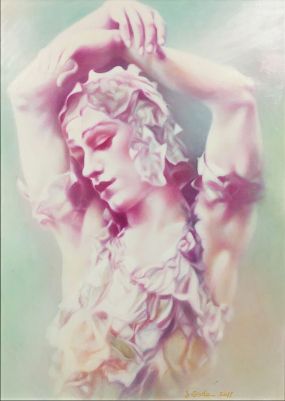 「ニジンスキー、バラの精」 合田佐和子 2011 |
|---|
会期:2019年7月13日(土)~28日(日)
12:00~19:00 月曜・火曜休(15日はオープン)
みうらじろうギャラリーでは8回目となります今回の個展では、合田佐和子と交流のあった作家の方々にご出品いただき、合田作品とともに展示いたします。この機会に、より広く多くの方に合田作品をご覧いただくとともに、その奥深い魅力を再発見していただければと存じます。
関連展示として、3階のみうらじろうギャラリーbisでは、1980年代のポラロイド作品を展示しております。
特別出品作家(五十音順、敬称略)
大西信之、桑原弘明、篠原勝之、建石修志、種田陽平、横山宏、四谷シモン
特別出品作品
それぞれの作家の皆さんが、合田さんとの思い出や合田さんへの想いを作品に込めてくださいました。
詳しくは右記サイトでご覧下さい。 http://jiromiuragallery.com
吉川 順三さん(34回)追悼文
ジャーナリスト魂を貫き新聞協会賞
中城正堯(30回) 2019.12.23
肺癌抱え田島兄弟の活躍を注目
 故 吉川 順三さん (毎日新聞大阪本社時代) |
|---|
 筆者近影 |
|---|
実は、昨年夏の終りに「土佐中高100年人物伝」の企画を相談したくて伊豆大室高原の自宅に電話すると、本人が出て明るい声で、「肺癌で検査入院からい今日帰ったところ」とのこと。「これからは療養に専念するので、申し訳ないが執筆などのお手伝いも、向陽プレスクラブ(KPC)への出席もできない」と言う。余命十か月と告げられていたとは、いつもどおりの口調から全く気付かず、また元気になったら頼むとお願いして電話を切った。
昨年5月には、KPCのHPで連載中だった「素顔のアーティスト」で田島征彦・征三兄弟を書くため、同級だった吉川君に情報提供をお願いした。メールでの返事には、「田島兄弟とはすぐ近くの隣り村で育ち、小学校のころから画の教室で一緒でした。中学・高校も同級、征三君は偶然にもまた伊豆で近くに住んでいます。私は閑居していますが、彼は痩身をものともせず、国内外を飛び回って大活躍です。特に今年は新しい分野の新聞広告デザイン(スポンサー伊藤忠)で日経賞大賞を受け、各紙の全面を飾ったことで注目されました。恒例になっている新潟十日町の地域を巻き込んだ国際芸術祭でも幹事役をつとめ・・・」とあった。この知らせのお陰で、6月に「大地のエネルギーを絵筆で歌う田島征彦・征三兄弟」をまとめることができた。
吉川君がマスコミ界から引退しても、同級生など仲間の活躍を暖かく追っていたことに気付かされた。小生の拙文も、よく読んでくれていた。『三根圓次郎校長とチャイコフスキー』もいち早く読み、「ケーべル博士のことなどよく調査取材して、知られてなかった校長の人物像を浮き上がらせている」と、言ってくれた。筆者は作家などに原稿を依頼する編集育ちで、取材執筆の訓練は新聞部以外では受けてないだけに、練達の取材記者からの反響は先輩へのお世辞混じりでもうれしかった。以後、「版画万華鏡シリーズ」でも、彼のような読者がいることを肝に銘じて執筆してきた。
リクルートで世紀のスクープ
 平成23年4月23日(土)八重洲パールホテルにて 左から故岡林、筆者、森田、故吉川の各氏 |
|---|
経済記者のみならず、新聞記者としての最高の栄誉の一つが、毎年日本新聞協会が発表する新聞協会賞である。これには第一部門(ニュース)、第二部門(連載企画)など六部門に分かれて授賞作品が選定される。なかでも、社会・政治・経済・学芸などの分野を超えて、過去一年間で最も価値ある報道ニュースとして選定される第一部門が、注目される。平成4(1992)年度、この賞に見事輝いたのは、毎日新聞大阪本社経済部長・吉川順三を代表とする<「リクルート ダイエーの傘下に」江副前会長の持ち株を譲渡のスクープと一連の続報>であった。
協会賞を発表した『新聞研究』1992年10月号には、「情報を棄てずに可能性を探る」と題して吉川部長の、大スクープの発端から綿密な裏付け取材、さらに記事掲載のタイミングまで、見事なチームプレーが明かされている。この記事が出た直後、ダイエー中内・リクルート江副の両トップが記者会見でこの報道を認め、各社が後追い記事を書く。しかし、長期間にわたって取材を重ね、この出来事の背景から両トップの関係、さらにはこの買収劇の経済史的意味付や、体質の異なる企業の合体が及ぼす影響などをしっかりおさえた毎日の記事は、他社の追従を許さない圧勝だった。まさに、経済界が迎える大型合併の時代と問題点を先取りした世紀のスクープであった。
 2010年、向陽プレスクラブ設立総会にて 左から横山、故吉川、故岡林の各氏 |
|---|
「見るべきものは見た」
 土佐高新聞部の種崎海水浴キャンプ。後列左から:3人目が故吉川、 麦わら帽が筆者、その右で顔を隠しておどける故秦洋一。 中列:故岡林、公文 前列:左端故合田、?人目が久永の各氏。 1956年 |
|---|
吉川君の長男が、ふと父に「マスコミに進みたい」と漏らしたとき、彼は「この世界で見るべきものは見た。別の道をめざせ」と、諭すのを奥様は耳にしている。厳しいマスコミの世界で、先頭を駆け抜けた彼ならではの想いだろう。長男は経済界で、次男は学界で活躍中と聞く。晩年の年賀状には、「伊豆閑居 妻の傍らで熱燗を飲む」と記してあった。ここで拙文は終え、奥様のお手紙の一端をご紹介しよう。
「お尋ねの〈新聞協会賞〉の頃は、順三の記者としての仕事の中でも最も充実していた時代だったと思います。・・・お電話でお話しました梅棹忠夫さん、小松左京さんを囲む国立民族学博物館の先生方との飲み会は、毎月一回何年か通い、楽しみにしておりました。社外に広くネットワークを持つことをこころがけ、大阪ジョン万の会を頼まれたのも、その人脈の延長上であったと思います。五十三歳で新聞社をやめたとき、驚くほど大勢の社外の皆様が会をして下さり、サントリーの佐治敬三さんがお得意の〈ローハイド〉を歌って下さったのも思い出となりました。高校時代の助走から本人が〈見るべきものは見た〉と言えるまで、志を実現できたのは本当に幸せだったと思います。」
合掌 花だより
中城正堯(30回) 2020.03.07
  |
|---|
 筆者近影 |
|---|
生まれ故郷の高知市種崎は、戦争までは桃の名所で、小学に入学しB25が姿を見せ始めた戦時下も、遊び仲間と実生の桃を拾ってきては育てていました。
狭い庭で我が物顔に咲き誇っている桃は、中国では邪気を払い、長寿のシンボルでもあります。同じく中国から渡来したコロナウイルスの邪気払いにつながることを願いつつ、眺めています。 <新刊『サハラの歳月』のご案内>妹尾加代(35回生)さんが翻訳出版
「破天荒・感涙のサハラ!」と話題
中城正堯(30回) 2020.03.22
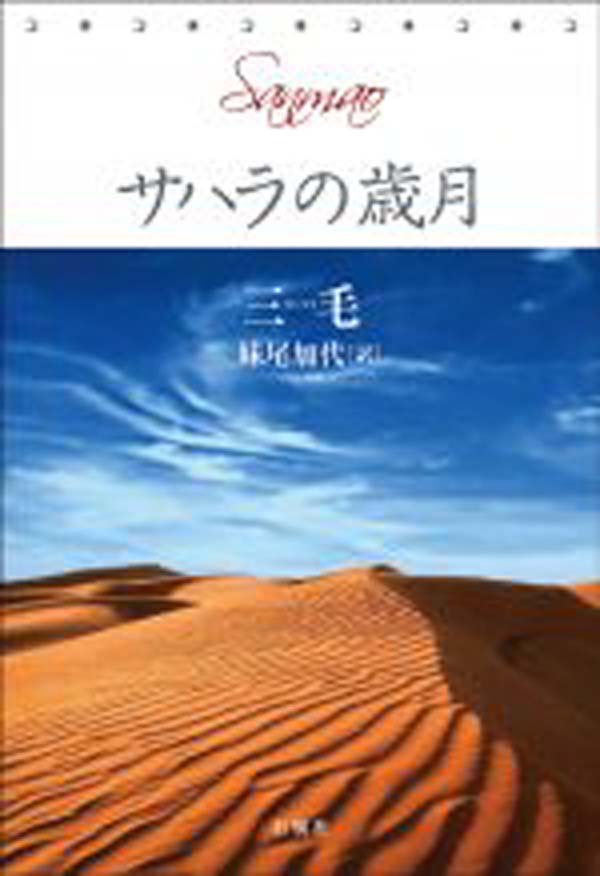 『サハラの歳月』 (三毛著・妹尾加代訳) |
|---|
やがて図書館から受け取ったのは、サハラ砂漠の写真で装丁された分厚い本で、そのボリュームにたじろいだが、読み始めると「数億の読者を熱狂させた破天荒・感涙のサハラの輝きと闇」という、キャッチフレーズ通りの面白さで、一気に読み終えた。訳者あとがきで妹尾さんは、「その途轍もない面白さと深い愛に感動し、台湾に住む作者・三毛に連絡を取り、翻訳にとりかかった」と記している。普通なら、海外の話題書は出版社や翻訳エージェントの人間が見付けて翻訳者に依頼するが、妹尾さんは自ら発掘翻訳したのだ。
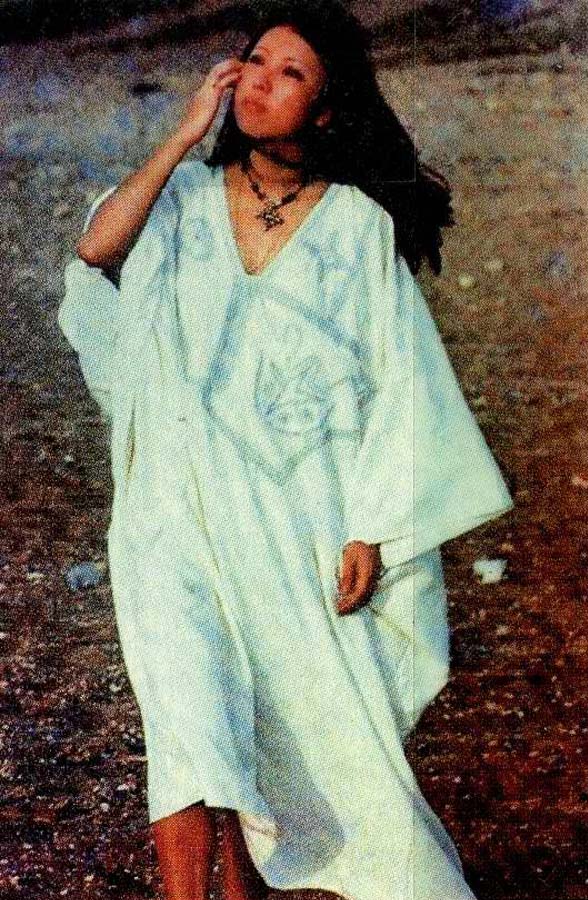 著者の三毛(同書より) |
|---|
妹尾さんの訳文は、中国の教養豊かな女性によるサハラの牧畜民探訪という、日本人読者にとっては二重に理解困難な世界へ、違和感なくいざなってくれる。20数年前に「中国年画と満州」という小論をまとめる際、小松さんに紹介いただいて中国文献の翻訳に大変御世話になった。これは『季刊民族学』に発表、お陰で好評だった。妹尾さんとはその後失礼していたが、同窓会広島支部幹事長として活躍とのことを洩れ聞いていた。この素晴らしい翻訳書を、皆さまにも楽しんでいただきたい。 <季節便り>
庭のエビネが咲きました
中城正堯(30回) 2020.04.14
 筆者近影 |
|---|
今では回りの雑木林もすっかり宅地化され、エビネも、アゲハチョウも、カブトムシも、シマヘビも、すっかり姿を消してしまいました。わずかに恩田川沿いにツクシやイタドリが春を告げ、口に含んでは少年時代の野生の味と香りを思い起こしています。もう一つアケビも、熟れた実を持ち帰って食べた種からいつのまにかツルが伸び、この時期に紫の花を咲かせます。秋には、今でも口に含んでは種を飛ばしつつ、甘い果肉を味わいます。
戦時下の少年時代は食糧難で、特に甘い物は欠乏、クワの実やアケビを見付けてはむさぼっていました。今や洋菓子店にはパティシエが腕を振るった豪華ケーキがならび、花屋には遺伝子操作で生まれたのか色鮮やかな大輪のランが妍を競っています。コロナ騒動で、近代文明が脆さを露呈しつつあるなか、素朴な地エビネに慰められるこの頃です。
 |
 |
|---|
中城正堯(30回) 2020.04.29
 筆者近影 |
|---|
リパブールに始まる奴隷産業の紹介、竹本さんの綿密でしつこい文献渉猟ぶりにただただ脱帽です。リパブール繁栄の裏事情から、奴隷貿易の過酷な実態まで教えられることばかりでした。あとは、KPCのメンバーが、読んでくれるのを願うばかりです。
私の海外探訪では、奴隷制度の残滓が目に触れることはあまり有りませんでしたが、奴隷貿易に続く植民地制度の末期はいくらか実見しました。
1965年に初めての海外訪問で訪ねたオーストラリアのアリス・スプリングスのアボリジニー保護区では、原住民の子どもを親から隔離しての教育が最盛期で、原野に住み、昔ながらの暮らしを続ける親と、分離されて施設で英語での近代的学校教育を受ける子どもが引き裂かれていました。後に、これでは親子の会話も、伝統文化の継承も出来ないとして、改められました。オーストラリアの保護領だったパプアニューギニアでは、戦前同様に原住民を使って大農園を経営する英国系オーストラリア人を訪ねました。ホテルのレストランもモーニングティーから、暑い中盛装しての夕食に閉口しました。このうち、アボリジニーの史料は、後に国立民族学博物館の小山教授に進呈しました。
インドネシアのニューギニアに近い香料列島バンダネイラでは、16世紀頃オランダとポルトガルとの争奪戦に使役されたサムライの絵にビックリでした。日本の戦国時代の敗残兵の中には、西欧諸国の奴隷となった日本人も居たのではないでしょうか。さらには、日本が統治した時代の台湾・韓国と、西欧による新大陸植民地との比較など、我が国の歴史認識にも引き戻されました。
せっかくの力作ですので、次回以降もぜひ挿図・写真を多用し、竹本さんの行動や感じたことを交え、親しみやすく読みやすい紙面・文章を期待します。 (2020/04/29)
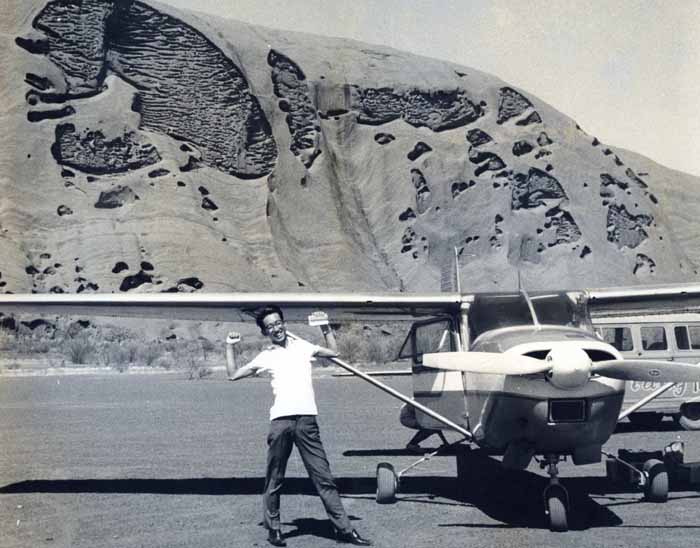 エアーズロックにセスナで到着 |
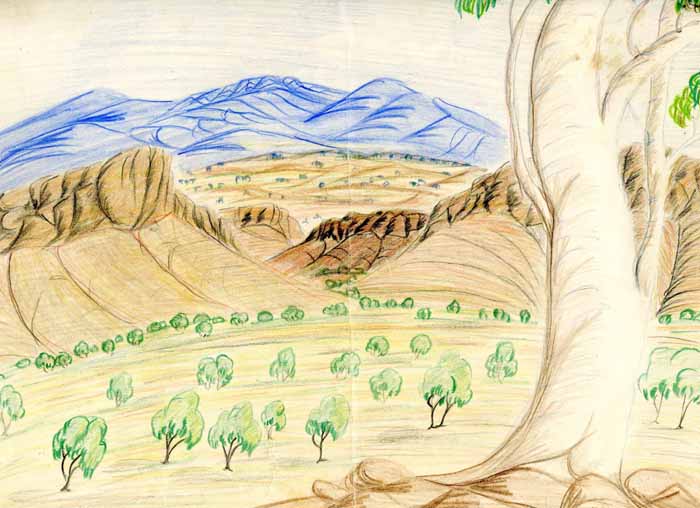 先住民の子どもが描いた風景画 |
 ニューギニアのコーヒー大農場 |
|---|
中城
竹本様
今朝、朝刊(朝日新聞)を開いて驚きました。「国際」面で「クック上陸250年豪 先住民と保守派 異なる歴史観」の見出しで、昨日紹介した先住民教育のことも、悲劇として紹介してあります。また、クック上陸後、英国の流刑地となった事から、先住民は「文化の消滅」が始まったのか、「科学と民主主義」を得たのか、と問いかけています。
なお、クックが1768年にエンデバ号で出航したのは、リパブール港ではなく、プリマス港で、オーストラリア到着は1770年、250年前のことでした。
私が訪ねた1965年は、中央部の先住民聖地ウルル(エアーズロック)訪問にはセスナをチャーターするしかなく、むろん飛行場もなく、乾燥した草原に着陸したことを思い出します。その写真と、先住民の子どもに描いてもらった風景画を添付します。先住民は、絵の才能が素晴らしく、ロックアート(岩面画)や樹皮画(カンガルーの骨格まで描くレントゲン画)が知られ、この風景画でも、うねるような独自のタッチで、岩山や巨木を表現しています。 (2020/04/30)
中城
中城さま
メールをありがとうございました。
1.ニュージーランドのマオリの事は早くから知っていたし、海洋民族で文化も進んでいたが、アボリジニの事はシドニーオリンピックの時の開会式に登場するまで知りませんでした。ウルル(Uluru)周辺のアボリジニの宗教上の聖地と言うことで、以前のような観光地でなくなった記事を見ました。
2.シドニーに滞在していた時に、支社に東京から鉱山の大型掘削システムの点検に来ていた技術者がいて、「東京から9時間で来たが、現場まで大型ジープで片道30時間・・・一泊二日とか言っていた事を思い出しました。
3.翌日、ジャカルタへ移動したのですが、クリントン大統領の特別機が来るので、いつもと違うコースで遠回りするとアナウンスがあり、メルボルンまで南下してから北北西に旋回しました。そうしたら、大分経ってからアナウンスがあり、ウルル(Uluru)が下に見えました。ウルル(Uluru)は最初で最後です。
4.将来、イギリスの城郭の投稿をする時に説明しようと思っていた事ですが。リバプールの時に、干満の差が大きくて、大型船が停泊するためにはドックが必要と言いました。西内さまにもCCで送ります。プリマスは古くからヨーロッパ大陸との交易の港で、自然の入り江があって、海賊ドレイクの拠点でした。地図を添付します。ロンドンは、イギリス一番の港ですが、テムズ川岸の陸地に沢山のドックがあるのが分かると思います。ユーロトンネルの開通で暇になりました。リバプールはアメリカ大陸が植民地になってからの港です。最大の港は、史上最大の作戦で連合軍艦隊が出撃した、ポーツマスです。巨大なドックが沢山あります。
 イギリス周辺地図 |
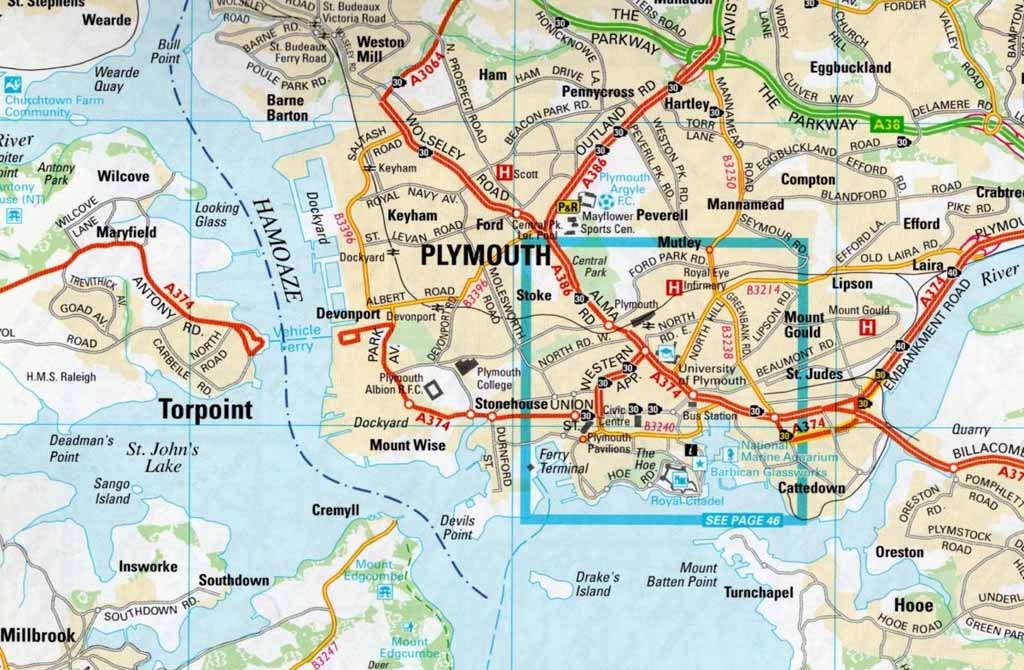 プリマス地図 |
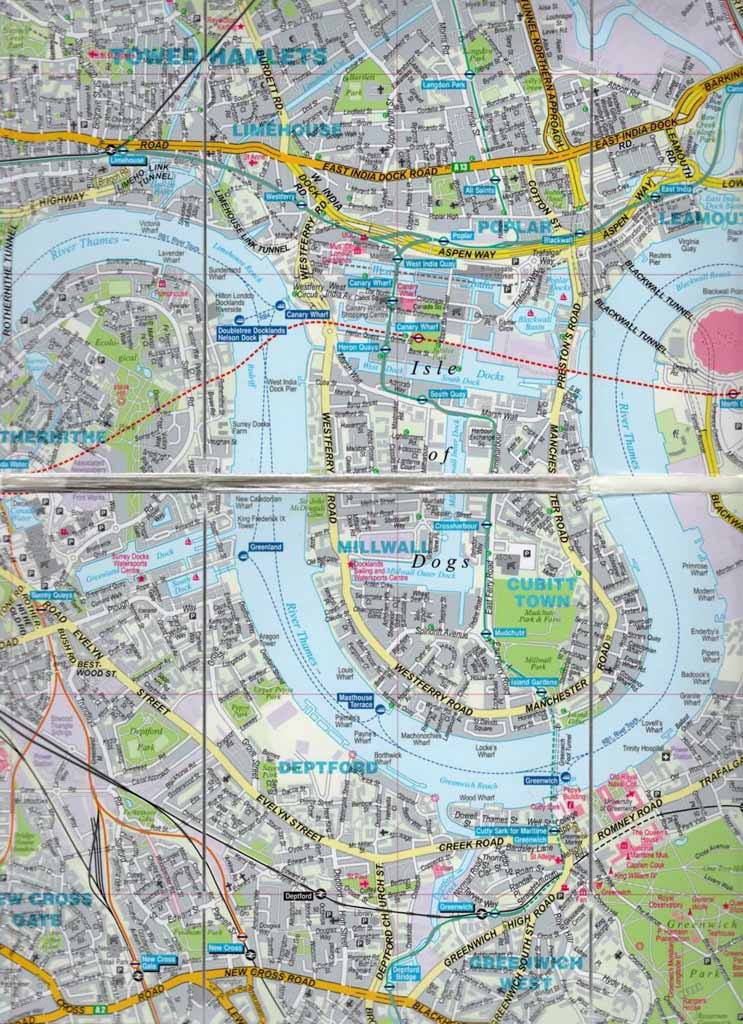 ロンドン港 |
|---|
失礼します。 (2020/04/30)
竹本 修文
竹本様
日本人は港と言えば海港を思い浮かべますが、ヨーロッパは河川港が古くから重要だったこと、ドックで干満差に備えたことなど、あらためて気付かされました。ロンドン港周辺がドックだらけの様子もはじめて知りました。
そういえば、知人のグリンデルワルト在住・中島正晃さんは20年ほど前にスイスからボートで地中海まで、河川と運河を漕ぎ下り、冒険家大賞を取りました。
イギリス人が大好きなボルドーワインも、ボルドーの河川港から、ロンドンに運ばれたわけですね。 (2020/04/30)
中城
中城さま
1.スイスのお話は日本では珍しいと思いますね~?.森健一先輩がお得意の30年戦争のあとのウエストファリア(独:ヴェストファーレン)条約で出来た国々の一つですが、正式名が「スイス連邦共和国」で30の国(カントン)で出来ていて、大統領は毎年交代するので覚える必要はない、何年か前に国連にやっと加盟したが190番目だったことだけ覚えています。
2.国連加盟前の独自防衛時代のスイスのチューリッヒの水道局の浄水場を見学しました。貯水池のチューリッヒ湖に毒薬をいれられた事を想定したリスク・マネージメント・システムとチュ-リッヒ上空で東西軍の核兵器がさく裂した場合を想定した、クライシス・マネージメントの概要を聞きました。
3.チューリッヒ湖から出た水は、オランダのロッテルダムに出ていくまでに、人間の体を4回通るといっていました。ライン川周辺のヨーロッパの国々では、常に戦争があり、子孫に土地などを残す習慣がないので、井戸を掘らないのです。ライン川の水を調理に使い、そこそこの処理をしょて、またライン川に戻す。秩序を守らないと戦争だった。「井戸を掘らない、植林をしない」・・・ヨーロッパ共通の常識でした。
4.ボルドーは今度投稿する積りのノルマン朝時代にフランス語しか話せないイギリス王の時代にボルドーなどの地域を領有し、ローマ軍が持ち込んだワインを育てて、自分たちの好きな味にしました。ワインの行き先は当時はブドーが育たなかったイギリス、そしてオランダで、濃厚なフル・ボデイーでした。そのうちに、フランスの親戚同士の戦い百年戦争でジャンヌダルクが出てきて、フランス王シャルル7世を助けて勝利し、イギリスはポルトガルのポルトでワインの生産を始めたのでした。百年戦争の後半、イギリス王ヘンリー五世がフランス王を継承する事になていたが急死した。その息子のイギリス王ヘンリー六世がパリでフランス王を継承宣言したが、ジャンヌダルクが現れてフランス軍を鼓舞してオルレアンでイギリス軍に勝利し、フランス王家のシャルルを連れてシャンパーニュのランス大聖堂でフランス王シャルル七世として戴冠した。イギリス王家は即位も葬式もウエストミンスター寺院で式を行うが、フランスは即位はランスで戴冠式を行い、葬式はパリの北側のサンドニ大聖堂と決まっていた。なお、ランスの綴りはReims またはRheimsだが、初めてだとランスとは読めない
5.ボルドーからパリへは、セーヌ川を遡りしねければならず、輸送しませんでした。ブルゴーニュ地方からは、運河・ヨンヌ川・セーヌ川で容易に運べました。今でも、フランス人はブルゴーニュ、イギリス人はボルドーと言われています。
6.太陽王ルイ14世の軍事技術者ヴォーバンがボルドーから地中海への世界遺産ミデイー運河を建設して、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルローなどのワインが地中海に入りました。
7.温暖化のお陰で、イギリス南部には800以上のワイナリーがあり、白ワインと発泡酒は90点です。イングランドは樺太、スコットランドはカムチャッカですからね~
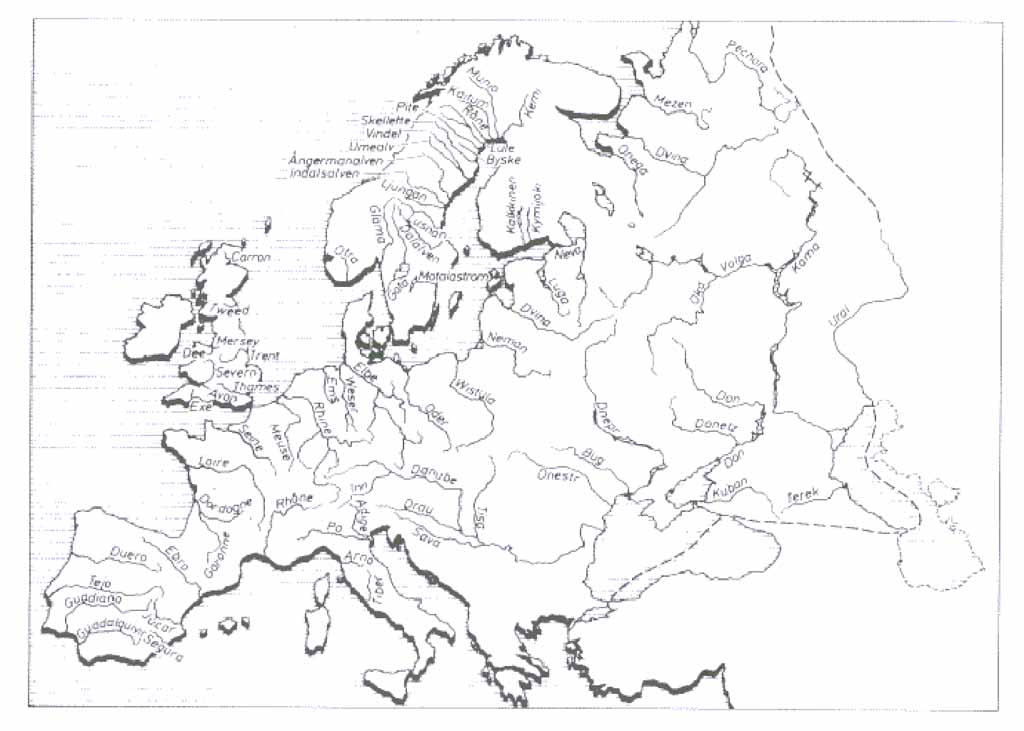 ヨーロッパの河川 |
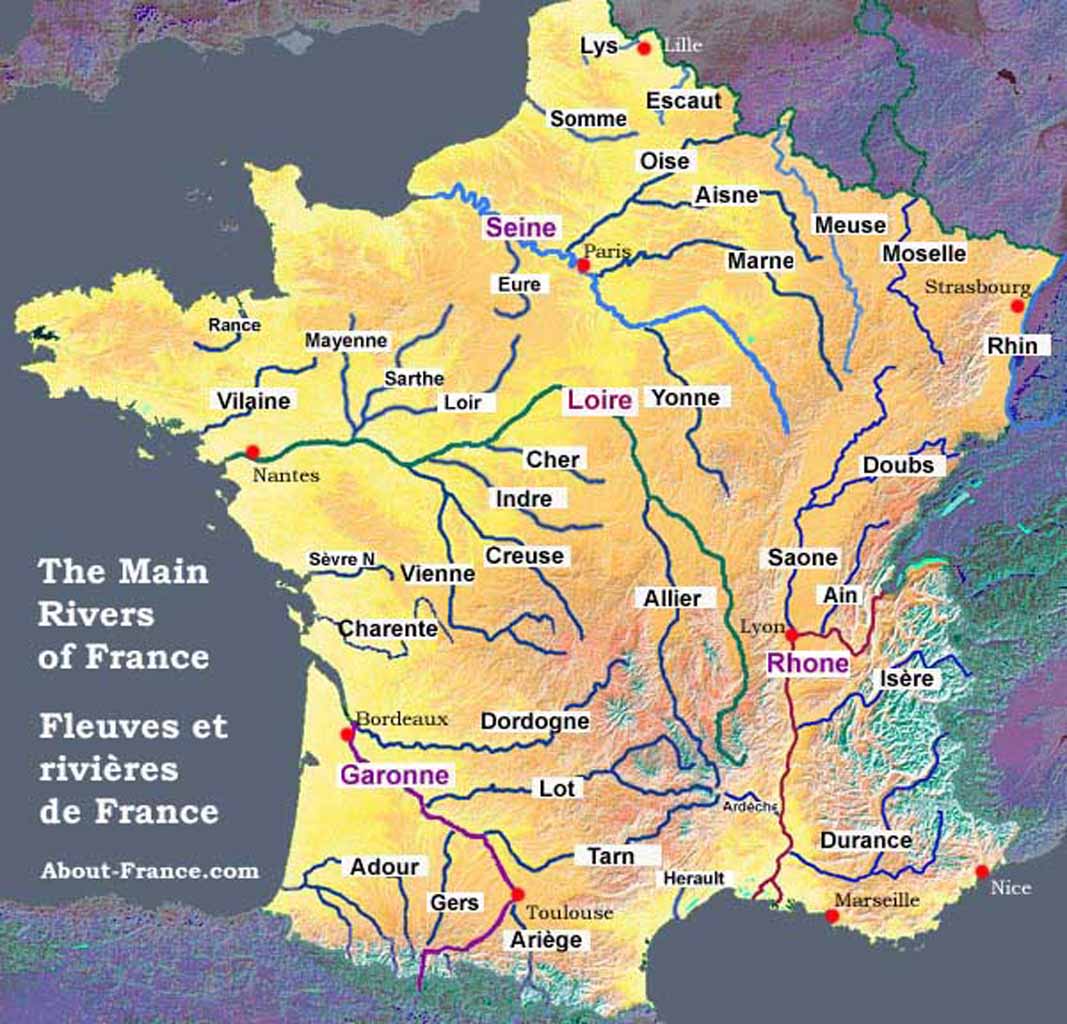 フランスの主要河川 |
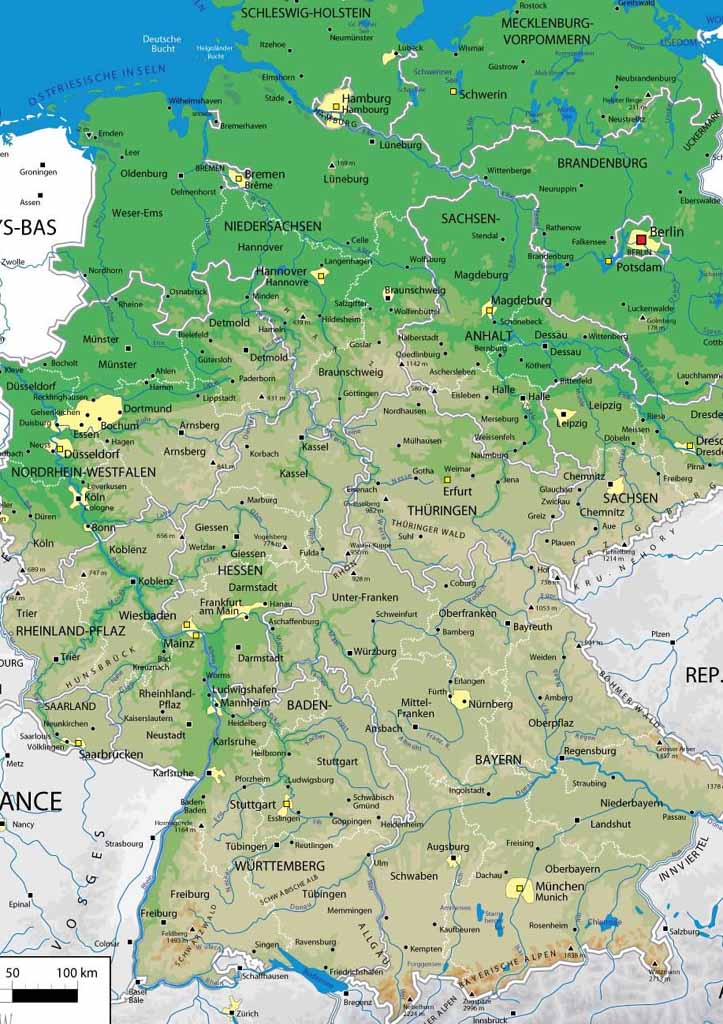 ドイツの河川 |
|---|
おやすみなさい (2020/05/01)
竹本 修文
竹本様
早速にヨーロッパの河川地図が各種添付され、感謝です。
昔読んだ「家なき子」で、舟で運河を行く旅芸人一行の姿を思い出しました。鉄道誕生までは、内陸の水運が輸送の大動脈だった様子が、よく分かります。
スイスでは、1971年の初訪問の際ジュネーブのホテルがどこも満杯、郊外の民宿を取りました。やっとたどり着き、玄関を開けると銃が立ててあるのにビックリでした。国連にも入らず、独立を守るため国民皆兵などと聞かされた事でした。現在は、どうでしょうか。
あと一つワイン・造船に詳しい竹本さんに、教えていただきたいのは、船台式進水式のシャンパン割りです。インターネットの情報では、生け贄→赤ワイン→白ワイン→シャンパンと、なっています。どこの国で始まり、シャンパンになったのは何時どこか、造船大国英国と、ワイン大国フランスがどう絡んでいるかなど、興味があります。
シャンパンは、ランスの蔵元を訪ね、地下の洞窟で瓶を回転させてはオリを抜く作業を見学、この酒の高価なわけを納得した次第でした。ボルドーでは、有名画家のラベルで知られるシャトー・ムートン・ロートシルトの博物館を訪ねました。残念ながら十五年前の発病で、禁酒生活です。
KPCホームページと竹本さんのお陰で、昔話が楽しめます。 (2020/05/01)
中城
中城さま
★スイスは技術交流だ何回も行きましたが、国連にはやっと加盟しても、EUは絶対に加盟しない、と言っていたのが、昨年から理解できました。ノルウェーも加盟しなくて良かった。
★スイス兵は自国とバチカンを護っていますね。私が付き合っていた技術者も数年おきに短期間兵役について国境を護っていました。銃を背負ってスキーで、オリンピックのノルデイックみたいな軍隊でした。
★ローマ帝国の北の国境であるライン川とドナウ川を船で短距離ですがロックを通りました。イギリスには小さなロックが5000か所もあり、内陸の水運が非常に発達しています。
ロック(Lock)とは「閘門(こうもん)」と訳されていますが余りなじみはないと思います。今上天皇がオックスフォード・マートンカレッジに留学されていた時に研究されたのが、イギリスの水運システムでご著書The Thames and Iが出版されています。イギリス中に5000もあるロックと書いたのはこの事で、写真を見ればよく分かるので、ウキペデイアを引用します。URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/閘門
★そうですか、ランスでシャンパン・・・いいですね~!私は、ランスの街はノートルダム大聖堂とサン・レミ聖堂をじっくり見ました。そして隣のエペルネでドン・ペリニヨンで有名なモエ・エ・シャンドンの地下セラーを見ました。
★進水式とシャンペイン(=英語、仏語では:地名も酒もシャンパーニュ)の事。知っているウンチクを以下に並べてみました。回答にはなっていませんが、なにかお役にたてれば幸いです。
1.進水式は建造した船を水面に移動する過程のセレモニーで、数千年前に遡る海軍の伝統行事で沢山の種類の文化が混じりあっている。例えば、古代バビロニアでは牡牛を生贄にして、儀式を行ったと言われている。古代ギリシア・ローマ・エジプトでは、新しい船と船員の安全を神々に祈願するためにワインを飲み、ある種の水を船体にかけたと伝えられている。
2.船に名前を付ける命名式はカトリックの国で始まり、それは司祭が子供の洗礼式を行うのと同じようであったとされている。聖餐に使うワインはイエスの血と言うことになっているので、かつて調べたら新約聖書作成時代の書物には何も書かれていない。初期のキリスト教の聖餐を色濃く残していると言われる東方正教では普通は赤ワインが使われている。西ヨーロッパのカトリックはギリシア語で書かれた新約聖書をラテン語に翻訳して使っているし、布教活動も気温の低い北ヨーロッパに向かったので、赤ワインの生産が困難なドイツでは白ワイン、ベルギーではビールも使われている。
3.プロテスタントでは進水式は宗教行事ではなく、俗社会の行事であり、沢山の記録が残っている。紹介するのは、1610年にイギリスのロンドン港東側のWoolwich(ウリッジ)の造船所での進水式である。船は64門の砲を装備したガンシップPrince Royal(何処かで聞いた名前ですね~?)で主教は出席せず、著名な造船技師、造船所長と共に皇太子が出席した。船尾のデッキには皇太子、海軍卿及び大勢の貴族が並び、そばにはワインがなみなみと注がれた金ぴかの大きなカップが立っていた。 船の誕生と幸運を祈る事はカトリックの場合と同じである。トランペットのファンファーレで皇太子がワインを船外に注ぎ、厳かに、船の名前を「プリンス・ロイヤル」と呼び、船が斜路を滑り降り始めたら担当役人がカップからワインを一口すすり、残りのワインを船の舳先から海に注ぐ。普通は、カップも海に投げ込まれ、拾い上げた人にあげていた。しかし、海軍が大きくなって建造が増えると、網でカップを拾い上げて次の浸水に再利用するようになった。
4.初期のアメリカの船はイギリス製だったので、宗教と無関係であり、自国で建造するようになっても、儀式の決め事はない。ポルトガルの強化ワインであるマデイラ酒が使われた例もある。ダイアナ妃が生前にイギリスの造船所で進水式に参加して、シャンペインをロープに付けた滑車にぶら下げて、合図で細い紐をナタでカットしてボトルを船の舳先に向けて滑らせたまでは良かったが、舳先に衝突してもボトルが割れなくて、係員が走って行って、ハンマーでたたき割ったテレビニュースを見ました。
★1995年5月、スコットランドのウイスキー街道を中心にドライブした。北端のインバネスにはカロードンの古戦場(1746年、スコットランドがイングランドに最終的に敗戦した戦い)の貴族の館跡のホテルを事前にインターネットで予約していた。12室だが豪華なホテルだったが、チェックインの時に「初めての日本からのお客様なのでCrown Prince (皇太子)がオックスフォード大学に在学中にお泊りになった部屋をお取りしておきました」との事でビックリしました。同じベッドとお風呂を使わせて頂きました。当時はデジカメはなくて、ビデオカメラの時代だったから撮りまくった事でした。
(2020/05/01)
2.船に名前を付ける命名式はカトリックの国で始まり、それは司祭が子供の洗礼式を行うのと同じようであったとされている。聖餐に使うワインはイエスの血と言うことになっているので、かつて調べたら新約聖書作成時代の書物には何も書かれていない。初期のキリスト教の聖餐を色濃く残していると言われる東方正教では普通は赤ワインが使われている。西ヨーロッパのカトリックはギリシア語で書かれた新約聖書をラテン語に翻訳して使っているし、布教活動も気温の低い北ヨーロッパに向かったので、赤ワインの生産が困難なドイツでは白ワイン、ベルギーではビールも使われている。
3.プロテスタントでは進水式は宗教行事ではなく、俗社会の行事であり、沢山の記録が残っている。紹介するのは、1610年にイギリスのロンドン港東側のWoolwich(ウリッジ)の造船所での進水式である。船は64門の砲を装備したガンシップPrince Royal(何処かで聞いた名前ですね~?)で主教は出席せず、著名な造船技師、造船所長と共に皇太子が出席した。船尾のデッキには皇太子、海軍卿及び大勢の貴族が並び、そばにはワインがなみなみと注がれた金ぴかの大きなカップが立っていた。 船の誕生と幸運を祈る事はカトリックの場合と同じである。トランペットのファンファーレで皇太子がワインを船外に注ぎ、厳かに、船の名前を「プリンス・ロイヤル」と呼び、船が斜路を滑り降り始めたら担当役人がカップからワインを一口すすり、残りのワインを船の舳先から海に注ぐ。普通は、カップも海に投げ込まれ、拾い上げた人にあげていた。しかし、海軍が大きくなって建造が増えると、網でカップを拾い上げて次の浸水に再利用するようになった。
4.初期のアメリカの船はイギリス製だったので、宗教と無関係であり、自国で建造するようになっても、儀式の決め事はない。ポルトガルの強化ワインであるマデイラ酒が使われた例もある。ダイアナ妃が生前にイギリスの造船所で進水式に参加して、シャンペインをロープに付けた滑車にぶら下げて、合図で細い紐をナタでカットしてボトルを船の舳先に向けて滑らせたまでは良かったが、舳先に衝突してもボトルが割れなくて、係員が走って行って、ハンマーでたたき割ったテレビニュースを見ました。
竹本 修文
≪編集人より≫
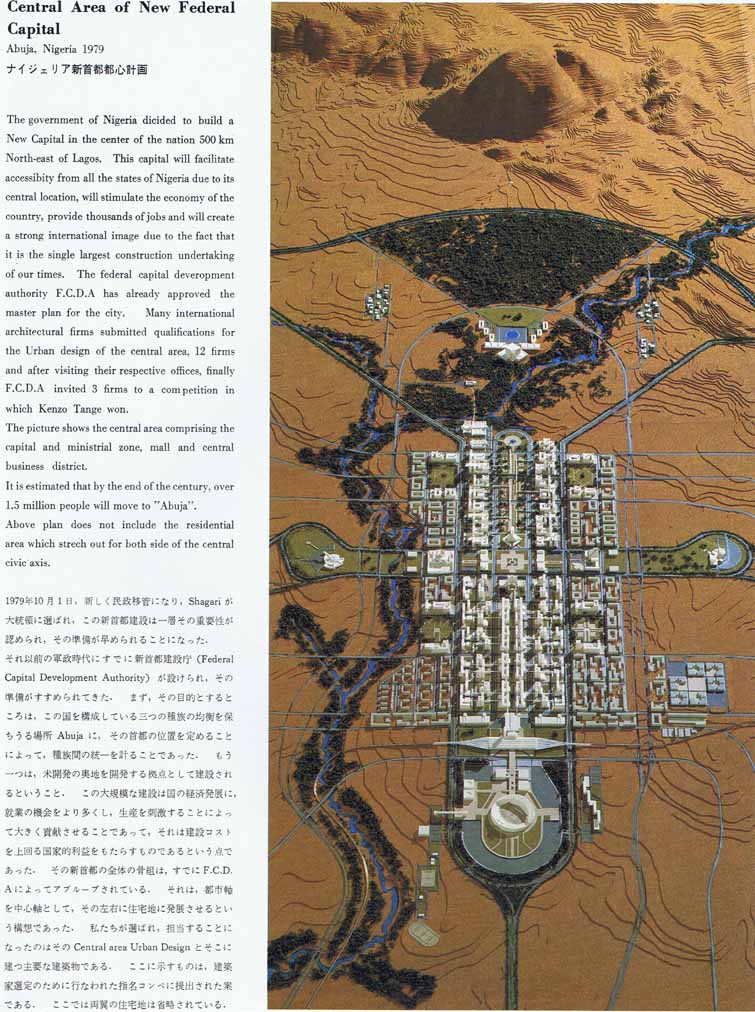 KENZO TANGE & URTEC 1981より |
|---|
尚、当時は奴隷海岸という地名は知っていましたが、ビアフラ戦争での「ハウサ族」「ヨルバ族」「イボ族」の対立が根本に奴隷貿易に起因しているとは知りませんでした。単に、民族間の融和を図るために3つの地域の中間に新しい首都を計画するという話を聞いていましたが……。 (2020/05/01) ―宮尾登美子・公文公・倉橋由美子たちの回想―
『綴る女』をめぐる変奏曲
中城正堯(30回) 2020.07.16
「宮尾ワールド」と倉橋との浅からぬ因縁
 筆者近影 |
|---|
一晩で一気に読んだ。林は宮尾の生前に評伝を書く許可を本人から得ていたものの、そのためのインタビュー前に宮尾が亡くなったとある。高知での取材も重ねての執筆とあるが、大筋はほとんど知っていたことだ。第一章で、「大御所女流作家宮尾登美子の盛大な誕生会が開催。朝日の中江や文春の田中に混じり小泉純一郎出席」(『噂の真相』1998年6月号)を引用、権力の象徴(大新聞・出版社の社長)から「有名政治家まで従える大振袖の老女」と紹介。「多くの読者にとっては、全く知らない宮尾登美子の一面であろう」とある。
 宮尾登美子 |
|---|
ここでは、宮尾と倉橋の「浅からぬ因縁」を中心に、『綴る女』では触れられていない公文先生と宮尾の交流、そして公文先生と倉橋たち教え子に迫りたい。なお、公文先生と書くのは、筆者が土佐中に入学した1949(昭24)年から中学時代の三年間、幸運にもずっと公文クラスだったからである。朝日の中江とのお付き合いも長い。筆者が学研でビジネス雑誌担当だった頃、経済関連の企画立案に毎月助言をいただいて以来で、ほぼ半世紀におよぶ。当時、中江は朝日の情報技術改革への遅れを嘆き、こちらは学研の保守的経営体質に辟易していた。やがて、中江は朝日の首脳となって飛躍させ、筆者は公文先生のお誘いで公文に移籍、先生の元でくもん出版を興す。(以下敬称省略)
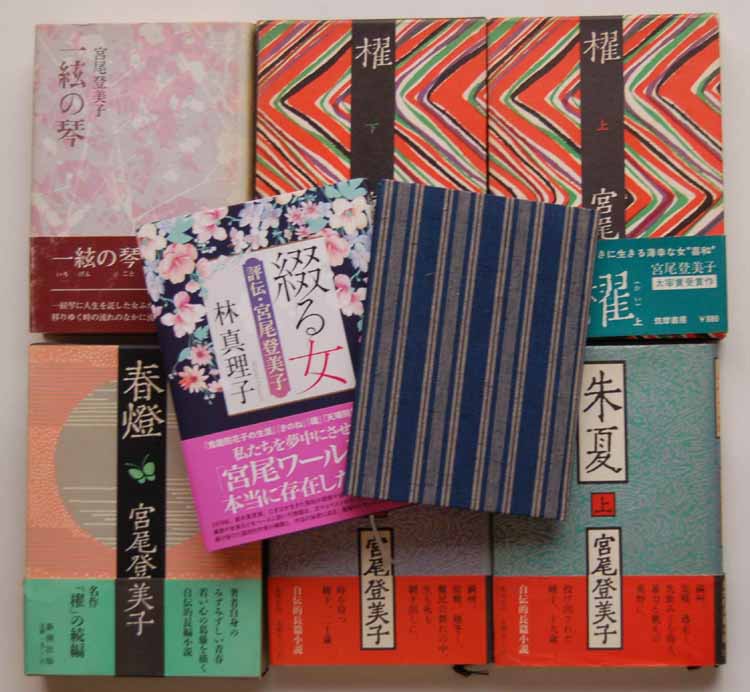 『綴る女』林真理子著と『櫂』 布装の自費出版本、および宮尾の著書。 |
|---|
「宮尾さんは約束を破った」倉橋の発言
林が『綴る女』で「かなり奇妙な文章」という、宮尾が前田とみ子の名前で書いた記事の掲載誌『新潮』(1965年4月号)を、早速取り寄せた。「倉橋由美子の結婚」は、<文壇>という純文学作家の動静を伝えるコラムにあり、ほかに阪田寛夫が高知高校・東大以来の友人・野島良治の死を悼む文などが並んでいる。野島は「新思潮」同人で、危篤の病床には瀬戸内晴美(寂聴)や曽根綾子などが駆けつけて再起を願ったがかなわなかった。坂田とは、かつて新宿ゴールデン街の「よさこい」で、飲んだことなどが思い出された。
 倉橋由美子 |
|---|
「皮肉なことに、式の準備が進むに従い、T・K君の過去の女性関係があばかれてきたことで彼の性格とその生活が次第に浮彫りされてきた。・・・・・・将来彼女の精神的なお荷物になるであろうことが疑えなくなったとき、式はもう明日・・・・・・この結婚を思いとどまるよういく度も彼女に懇願したが、気丈な彼女は・・・・・・ついに全部の予定を成しおおせた」
倉橋の結婚は1964年12月、仲人の内幕暴露の記事が『新潮』に掲載されたのは、それから半年も経たない翌春であった。いくら文芸雑誌とはいえ、仲人が書く内輪話ではない。後年、1987年に筆者が同窓会誌『筆山』で倉橋をインタビューした際、結婚につき「宮尾さんの紹介でお見合いをした。『ものを書くなら結婚した方がいい。食べさせてやる』という言葉に、あまりの感激で、ただ『はい』と言ってしまった」「結婚のいきさつは話さない約束だったのに、宮尾さんが破って書いた」など、あっけらかんと語ってくれた。今回『新潮』を取り寄せて読むまで、こんな内容とは思いもよらなかった。これでは、まるで「残酷童話」の世界で、魔女が若いお姫様に嫉妬、不幸な結婚を予言するかのようだ。
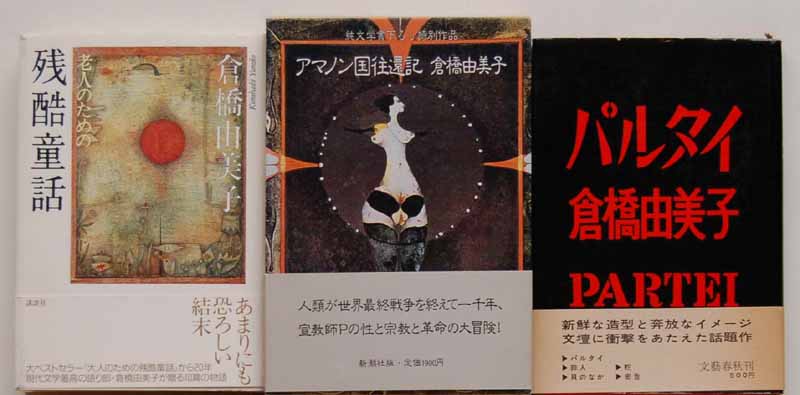 『パルタイ』初版と倉橋の著書 |
|---|
おそらく宮尾は、編集者にふと漏らした新人作家倉橋の秘話を書くように迫られ、とかく中央での文章発表の場を求めていた時期だけに、友情よりも仕事を選んだのだろう。
公文公先生と倉橋の再会、そして宮尾ブーム
1987年に筆者が倉橋にインタビューする際、彼女は娘の入学した玉川学園の学園誌に、「昔、土佐高校で公文公といふ、まことにユニークな先生に數学を教わった・・・・・プロに徹した教師であった」などと書いていたことを思い出した。そこで、大阪在住の公文が東京本部に上京する日を選び、師弟の対面もあわせて実現した。公文は倉橋の園芸部活動や片地の歯医者だった倉橋の父に触れ、倉橋は「今になり公文の授業こそ教師の原型」と思えることや、クマテン(吉本泰吉)の漢学への博識と大人(たいじん)ぶりに魅せられたと回想。また、自分が土佐中高で蓄えたものを執筆に使うだけでなく、娘の英語の先生も土佐高出身の谷敦雄(34回生)で、親子で縁が切れないとも語っていた。
公文は、1983年から高知新聞で始まった南風対談の第3回目に登場する。これは、評論家山田一郎が、高知出身の知名人を毎月一人ずつ選び「十二名家・巡礼の旅」を続ける連載対談だった。好評のため結局三年間に延長、36名が名を連ねる。この連載で、公文式が高知の公文先生創案と知れ渡り、かつての教え子たちから声が掛るようになる。ファッションデザイナー山本寛斎の父もその一人で、山田一郎と同時期の海南中学での教え子だったが、関西で洋装店を開き、服飾デザインも手がけながら、妻子を顧みず自由奔放な生活をおくる。晩年、息子が著名になるなか、東京でひっそりと暮らしていた。先生にお会いしたいとの電話があり、筆者も同席した。もう還暦は過ぎているのに、皮ジャン姿で大型バイクにまたがり、颯爽と市ヶ谷のビルにやって来た。しかし、先生の前では朴訥純真な中学時代にもどった表情になり、教室の座席の位置から、数学は成績順のクラス編成でビリのガンマー組だったこと、さらに戦死した同級生のことなど、話は尽きなかった。後に、NHKファミリーヒストリーで山本寛斎が取り上げられ、既に逝去された公文に代わって、その師弟対面の場をお話しした。
公文は、教え子の学校での様子だけでなく、家庭の事情までよくご存知で、記憶していた。それを、嫌みのない表現で語りかける。今は初老となってなにかと悩みを抱える教え子たちも、いつしか純朴な中学時代にもどり、偉大な老師の優しい懐に癒やされ、元気を取りもどして帰っていった。
教え子ではないが、公文から「お会いしたい。出来れば公文の新年研究大会の講師をお願いしたい」と話があった相手は、宮尾登美子である。宮尾は、1964年に高知新聞記者だった宮尾雅夫と再婚、2年後には土佐を脱出、上京する。生活苦の中で、自らの出自を丹念に綴った『櫂』を、縞織物の装丁で自費出版する。これが筑摩書房の編集者の目にとまり、太宰治文学賞を受賞する。さらに書き足して同社から上下2巻で刊行、ここから、宮尾文学の破竹の勢いでの創作が始まり、1979年には『一絃の琴』で直木賞を受賞する。『鬼龍院花子の生涯』は夏目雅子主演で映画化、「なめたらいかんぜよ」の名台詞が話題になって大ヒット、映画・舞台もからめて「宮尾ブーム」が巻き起こっていた。
造酒屋の息子と娼妓紹介業の娘
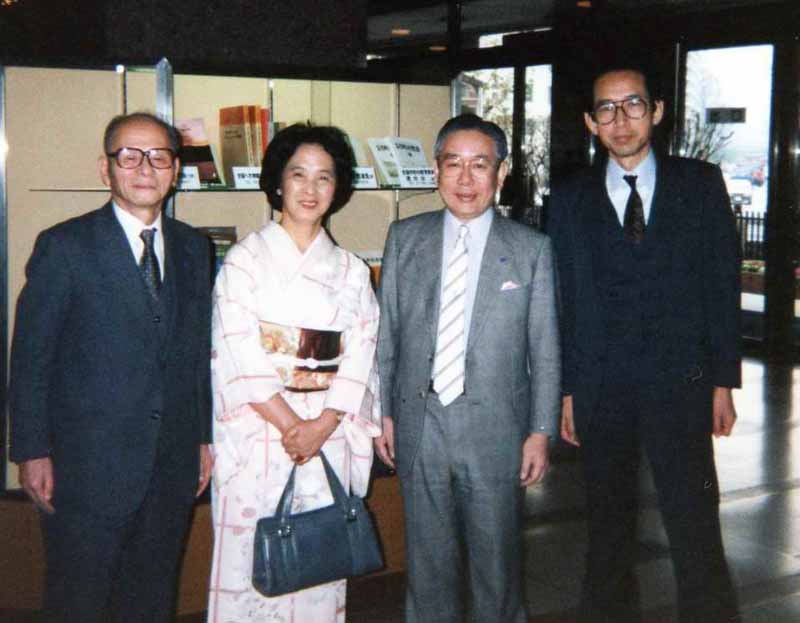 公文の新年研究大会で講師の宮尾を囲む 左から公文・岩谷・筆者、1990年 |
|---|
最初の講演後、そのお礼を兼ねての食事会を4月に開くことになった。その段取りで、場所を吉兆か辻留・・・と問うと、「吉兆」と即答であった。こうして、公文、宮尾、それに、朝日の中江専務(当時)、岩谷清水(公文の役員・27回生)、筆者の5人での会食となった。この席で印象に残っているのは、まず中江が座に着くと、公文は初対面の挨拶もそこそこに早速公文式教育の説明を始めたことだ。次ぎに公文と二度目の宮尾が来場、軽く会釈を交わすと床の間に向って正座、丁寧に掛け軸や花入れを鑑賞、作法通りの「床の拝見」を行なったことだ。両者の話題はもっぱら高知市緑町の戦前のたたずまいで、宮尾は白壁造りの公文の酒蔵をよく覚えていた。公文は宮尾の兄・岸田英太郎と同じ小学校の下級生で、岸田のかけっこの速かったことを鮮明に記憶していた。
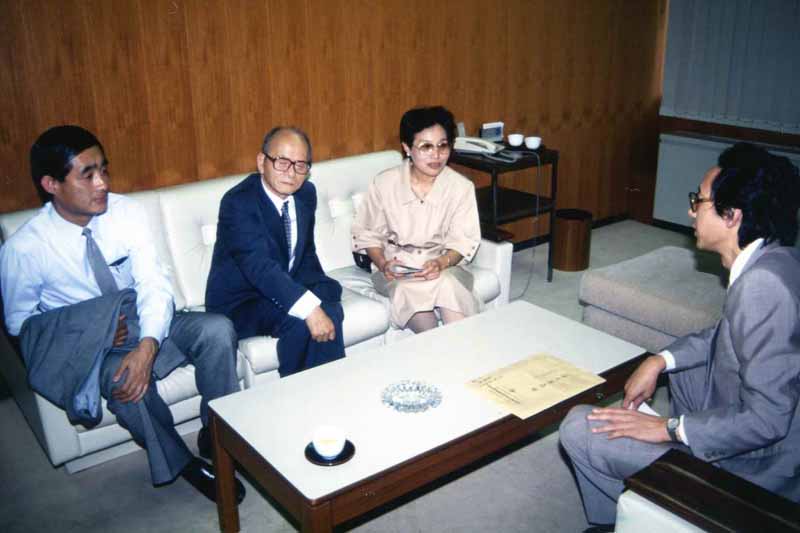 公文公を訪ねた倉橋(中央)と、 浅井伴泰(左30回生)、筆者(右)、1987年。 |
|---|
一方、倉橋からは『大人のための残酷童話』『アマノン国往還記』『交歓』など毎年新著をいただき、電話でおしゃべりをしていた。宮尾と吉兆で食事会をした報告の直後には、下重曉子の話になり、ともに作品のファンで紙上では互いにラブコールを贈ってきた仲だが、まだ会ってないという。下重もぜひ会いたいとのことで、1989年6月に神楽坂の「おく瀬」に設営した。会うと互いに意気投合、ともに連れ合いがテレビマンであり、体験的結婚談義・男性論も出た。途中から、ちょうど上京中だった倉橋と同級の福島清三(29回生)も加わり、一段とにぎやかになった。
 赤岡の「絵金祭り」を取材する下重曉子、1999年。 |
|---|
それぞれの終曲、歓喜か悲愴か
振り返れば、1995年に公文が、2005年に倉橋が、2014年に宮尾が、次ぎ次ぎと去って行った。この秋に刊行される『筆山の麓-土佐中高100年人物伝』に、公文と倉橋の略伝を担当執筆したので、いずれ併せてお読みいただきたい。また、宮尾や倉橋の代表作の背景には、宮尾のリアリズム、倉橋の反リアリズムと真逆ながら、若き日の高知でのさまざまな体験が自ずと反映されており、改めてこれらをさぐるのも再読の楽しみだ。
公文は、奈良で出会った禎子夫人に支えられ、世界的な教育事業を大成した。禎子夫人は奈良女子師範附属出身で、「のびてゆく教育」で知られる木下竹次の教え子であり、安部忠三(NHK高知放送局長)や前川佐美雄に学んだ歌人であったことは、数学者公文公の教育を英語・国語へと発展拡大させる上でも、主婦を教室の指導者に活用する上でも、大きな力となった。
 名城見学会で高知城を訪ねた下重曉子と 公文敏雄などスタッフ、2009年。 |
|---|
下重も、かつてパートナーの海外支局駐在に同行、ベイルートで暮らしたり、急病の知らせでハワイまで看護に駆けつけたり、互いに自立しつつも助け合って暮らし、話題作を生み続けている。新春には「木枯にミイラの夢の覚めにけり」の賀状が届いた。
『綴る女』たちの、パートナー(夫・妻)とのあり方もさまざまだ。それにしても残念なのは倉橋である。創造力を駆使して虚構の世界を構築し続けてきたが、前衛的な作品に似合わず、我々の前では平凡な主婦にしか見えない穏やかな家庭的女性だった。パートナーは結婚後にNHKから独立、映像プロデューサーになっていた。晩年の倉橋は、難病と闘いつつ、つれあいの仕事ぶりも心配だったようで、密かに四国遍路を始めていたが、69歳で亡くなった。結婚式直後に、仲人宮尾が新郎について語った「将来彼女の精神的なお荷物になるであろう」の言葉が、なぜか魔女の予言のように甦り、耳に残っている。ただただ、安眠を願っている。(写真は、筆者撮影及び提供) <NHKテレビの時代考証>
「大江戸もののけ物語」の不思議な寺子屋
中城正堯(30回) 2020.07.16
コロナ禍で、家に籠ってもっぱらテレビを見ていますが、再放送ばかりの中、時代劇の大型番組の予告があり、その寺子屋場面にビックリです。
よろしかったら、メンバーの方々にもお知らせください。
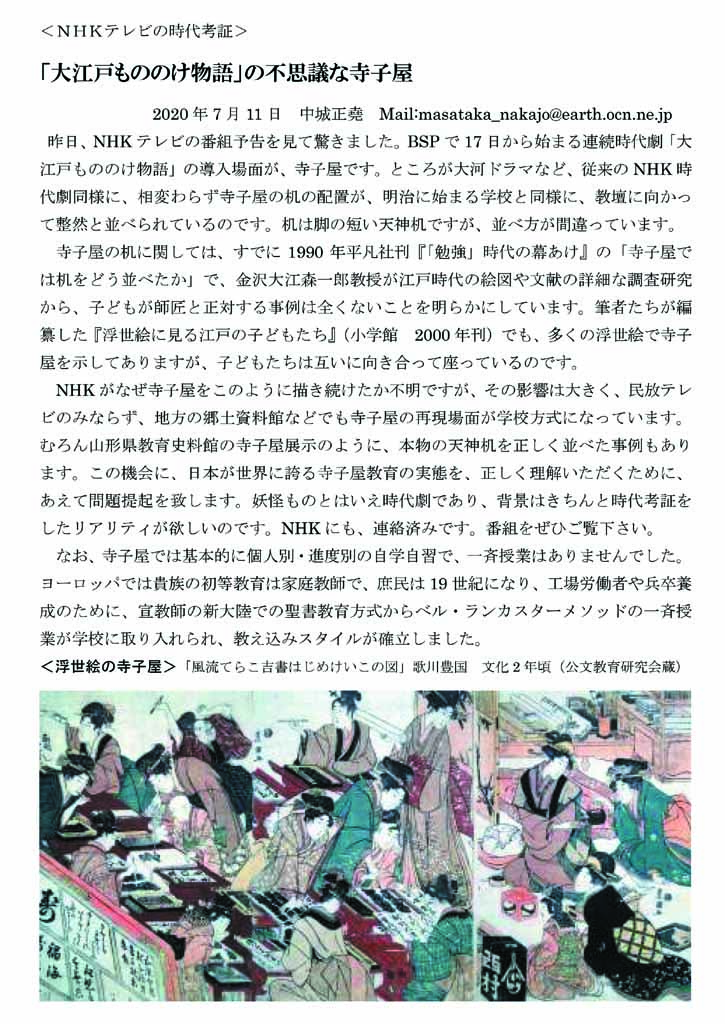 「大江戸もののけ物語」の不思議な寺子屋 |
|---|
 「大江戸もののけ物語」の不思議な寺子屋 PDF版(一括表示・保存・印刷・拡大)
オーテピア高知で「中城文庫展」
「大江戸もののけ物語」の不思議な寺子屋 PDF版(一括表示・保存・印刷・拡大)
オーテピア高知で「中城文庫展」土佐藩御船頭の資料を展示
中城正堯(30回) 2020.08.14
 筆者近影 |
|---|
送られてきた新聞には、「土佐藩船頭(ふながしら) 中城家資料70点・・・」とあり、記事には「坂本龍馬も暗殺される前に立ち寄った中城家は、土佐藩主らを乗せる船の運航を任された・・・今回は高知藩が発行した鯨の藩札や、本居宣長や鹿持雅澄の短冊など約70点を並べた」とある。全く狐につままれた様な話で、寄贈主には一切連絡なしだ。
2008年の寄贈当時から図書館長も担当学芸員も変わり、今も健在なのは岡﨑市長のみだ。市長室に電話すると、秘書は連絡不十分を平謝りで、すぐ案内書を送付するとのことだった。今日8月13日、ようやくオーテピア高知図書館の担当者からここに掲載のチラシ等が、送られてきた。同封の毎日新聞(8月1日)には、「時代伝える中城文庫 和歌・紙幣など40点」「コレラが明治期に流行した際に感染拡大防止策を議会に求めた嘆願書など」とあり、時代に合わせた展示を心がけてくれたようだ。
2000年から必死で資料整理を行ない、なんとか2008年に収め、企画展「海から世界へ~土佐・種崎浦一族の船出~」が開かれた。それ以来、種々活用されてきたようだが、こうして再度展示会が開かれたことには、大いに感謝したい。ただ、事前連絡がなかったことは「中城文庫」のみならず、さまざまな高知関連資料の県市施設への寄贈に協力してきただけに誠に残念だ。
筆者は呼吸器系の疾患を抱え、コロナ禍の移動は厳禁状態だ。9月22日まで開催なので、高知在住の方は、ご興味があればぜひ御覧いただきたい。
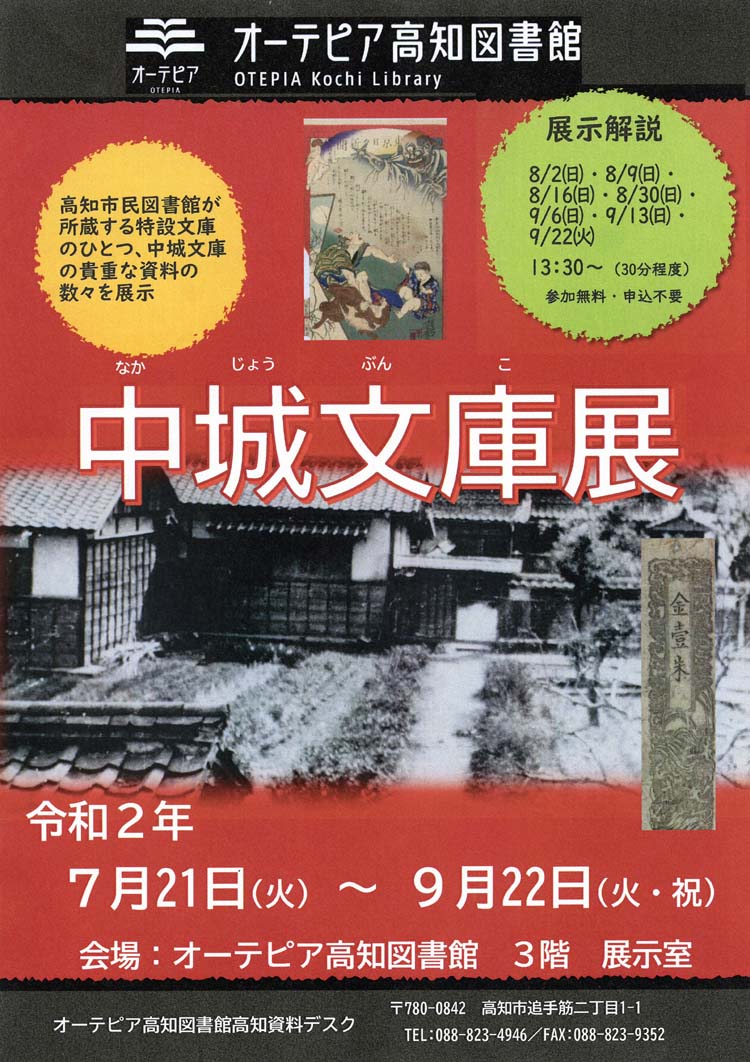 中城文庫展:9月22まで オーテピア高知図書館 |
|---|
「ジョニ黒」ことはじめ
中城正堯(30回) 2020.08.27
 筆者近影 |
|---|
「ジョニ黒」ことはじめ
竹本さんの「日本産ウイスキーの裏話」、私たちがウイスキーを飲み始めた昭和三十年代後半とは隔世の感があり、驚きつつ拝読しました。国産ウイスキーの国際的評価が上がっていることは聞いていましたが、それに便乗してスコットランドやカナダから樽を輸入、日本で瓶に詰めて日本産として輸出とは、ただただ絶句です。老人の「ジョニ黒ことはじめ」を記してみました。
私が初めて海外に出たのが1965(昭和40)年で、オーストラリアでした。シドニーの領事館で後に通産官僚として大活躍する天谷直弘さんからジョニ黒を1カートンもらい、同行のカメラマンと驚喜して車に積み込み、一月半の取材に出かけました。当時、日本ではもっぱらトリスの水割りで、ジョニ赤にも手が出ない時代です。取材で訪ねた戦前からのウールバイヤー・飯田さんからは、「スコッチはストレートで飲め。ただし水を飲みながら。炭酸割りなどとんでもない」と指導されました。当時、シドニーのレストランではワインを置いてなく、酒屋で買って持ち込まないと飲めない状況でした。海外旅行の土産では、ロイヤル・サルートやジョニ黒が人気でした。
その後、日本旅行作家協会や日本城郭協会に入りましたが、旅にも城にも酒はつきもので、ボルドーのワイナリーや、ランスのシャンパンの地下蔵はじめ、国内ではサントリーの山崎・白州などを訪ねました。サントリーでは私と同級の北岡明君が山崎の工場長、ニッカでは武田勝君(31回生)が副社長と、この世界でも同窓生の活躍が見られました。
都内での試飲会も、礼装で出席のブルゴーニュ騎士会などに呼ばれました。ただ酒音痴で、ウイスキー、ワインとも味や香りがよく分からず、がぶ飲みするのみです。バーボンだけはダメで、ウイスキーはもっぱら飲み慣れたスコッチ、ときどきシングルモルトを楽しんできました。
 「うすけぼー」に集まったメンバー |
|---|
中城正堯(30回) 2020.09.10
 筆者近影 |
|---|
「中城文庫」展に関連し、高知でのコレラに関する歴史を、手元史料でお知らせします。
「中城文庫」には、今回展示してある「虎列刺予防法ノ願」(1879年)の他にも、書簡「虎列刺予防、村界見張番所相廃」があります。村の予防委員が祖父宛に出したものです。
「土佐事物史」(土陽新聞 大正八年六月)には、「伝染病も随分多い、最も恐るべきは虎列刺、黒死病であるが、虎列刺は土佐では安政年間に大いに流行して、幾多の人を殺した・・・、次に大流行は明治十二年と十九年であらふ」とあります。
現代の文献では、『高知市史 中巻』(昭和四十六年刊 高知市)の、「伝染病と対策」に5ページにわたって記載してあります。
また、「土佐種痘の元祖」としては、豊永快蔵が知られ、嘉永二年に大坂に出て蘭学医から牛痘接種法を学び、帰国して高岡郡各地で種痘を行ない、効果を上げています。
どなたか、土佐医学史、特に伝染病との闘いを世界的視野で調べてくれると有難いです。高知県に医師・病院が多い事や、幕末の寺子屋師匠に土佐では医者が非常に多かった背景も解明できそうです。
土佐高からは、日本史や郷土史の学者が少なく、ぜひ呼びかけて下さい。 <テレビ番組のご案内>
「日曜美術館」 画家・田島征三さん
中城正堯(30回) 2020.09.24
 筆者近影 |
|---|
「筆山の麓 土佐中高人物伝」は、お陰様で、10月10日発刊されます。この表紙画家・田島征三さんが、10月4日(日)NHK Eテレ「日曜美術館」で特集されます。ちょうど発刊および、母校100周年記念日の直前で、大変タイミングのよい話題です。
「日曜美術館」で現代画家を取り上げることはまれで、どう紹介されるか見逃せない番組です。添付の<ご案内>では、番組紹介を兼ねて、人物伝表紙と本文での田島兄弟、さらにこの本に登場するアーティストにも触れておきました。同窓生・在学生にもぜひ番組を見ていただきたく、この情報の伝達へのご協力をお願い致します。添付の<ご案内>は、加工修正いただいても結構です。
なお、田島さんの新刊絵本原画を中心にした作品展、および高知での少年時代を映画化した『絵の中のぼくの村』(ベルリン映画祭銀熊賞)の上映も高知県立美術館に呼び掛けているそうです。昨年は瀬戸内海国際美術展2019の大島会場にも意欲作を出展、現在も展示されており、ぜひ見て欲しいとの事です。
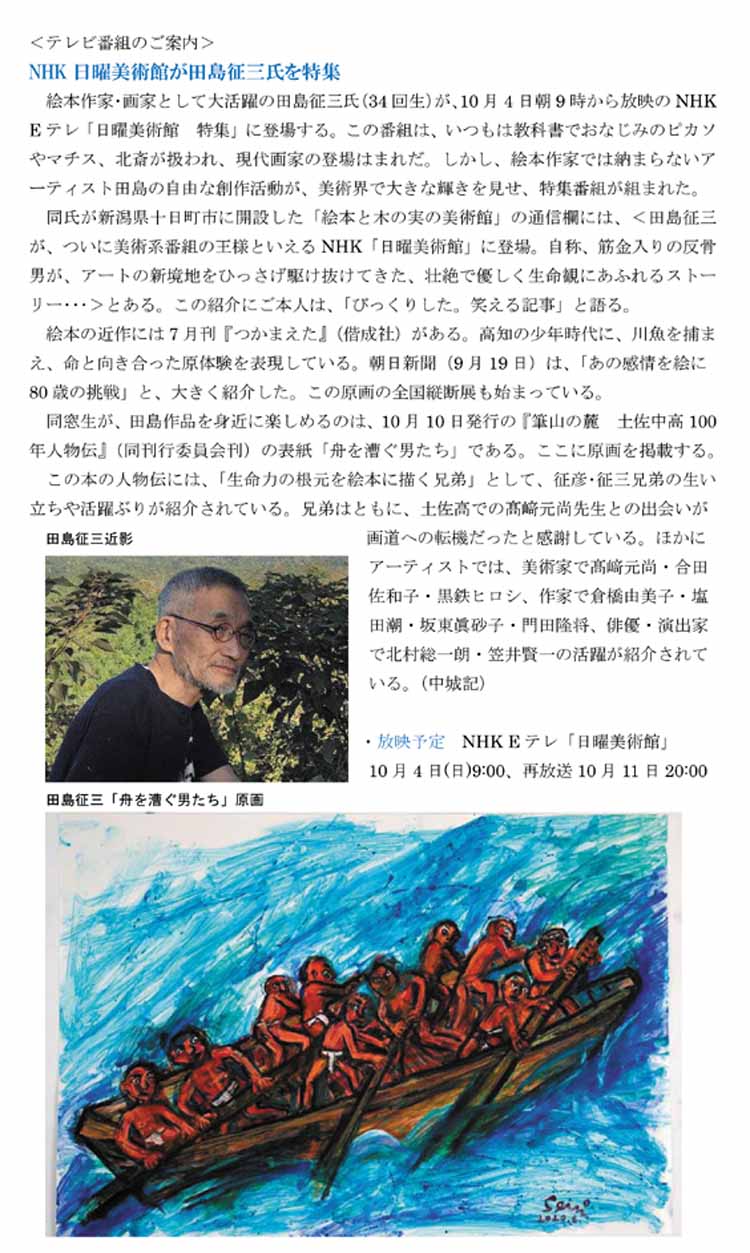 |
|---|
中城正堯(30回) 2020.10.08
 筆者近影 |
|---|
 丘の上にそびえるエディンバラ城。 |
|---|
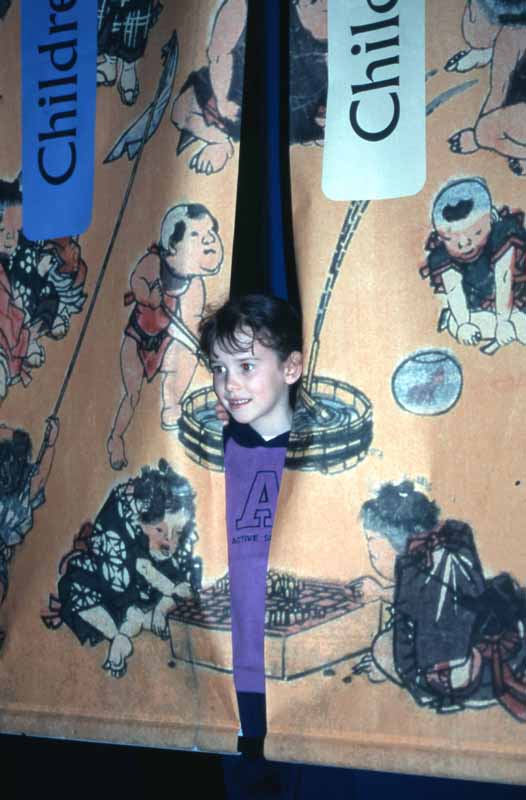 浮世絵展会場入口の “広重のれん”。 |
|---|
一週間ほどの滞在であったが、スコットランド人の自国への誇りと、日本への好意を強く感じた。展覧会オープニングの晩餐会は、マンモスなどの骨格標本がならぶ展示室に、特別に設営されていた。「江戸体験コーナー」は、大学生の日本文化研究会が運営してくれていた。併設された子ども博物館のコーナーには、スコットランド出身の偉人展示があり、蒸気機関のワット、電話のベル、文豪スティーヴンソンなど著名人物の肖像画が並び、最後は鏡だ。自分の顔が映る鏡の上には、「次は君だ!」とあり、子どもたち一人ひとりに奮起を呼び掛けている。イングランドへの対抗心が、展示からもうかがえた。
 3.忠犬ボビーを訪ねてきた少女。 |
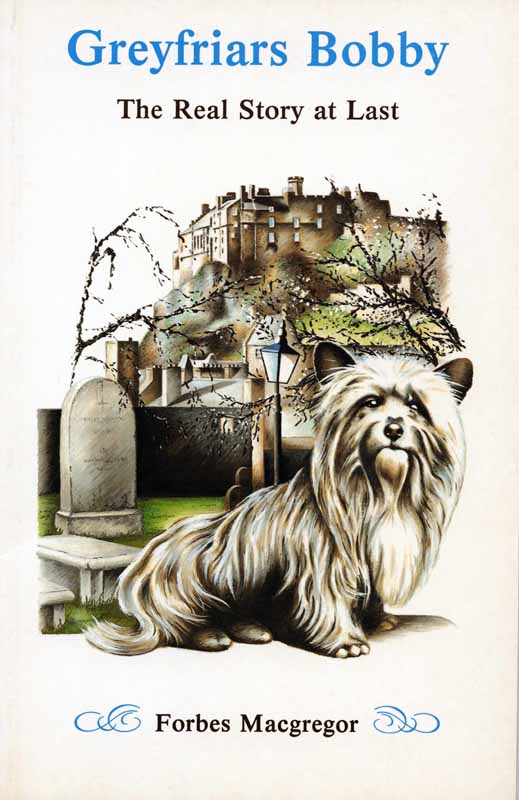 4.『Greyfriars Bobby』の表紙。ボビーとその記念碑(左)、 後方はエディンバラ城。 |
 5.渋谷ハチ公前での、メッセージ伝達式。 |
|---|
イギリス人女性作家ヴィーダの『フランダースの犬』にも触れておこう。日本では名作児童文学として知られ、アニメでも大人気だったが、物語の舞台であるフランドル(ベルギー)や、作者の出身地イングランドでは、忘れられた存在だった。しかし、その舞台を探して日本人観光客が押し寄せ、地元観光局は「ネロとパトラッシュの像」と風車小屋を建て、日本人の期待に応える。1988年にここを訪ねていたので、ボビーにも興味を持った。だが、アントワープ聖母大教会で、あこがれの名画ルーベンスの『キリスト降架』を仰ぎ見ながら、愛犬パトラッシュを抱いて凍死した薄幸の少年ネロは、銅像になっても安泰ではなかったようだ。今、この銅像は撤去され、後には中国人によって作られた石像が横たわっているとのことだ。(写真は全て筆者撮影)
 6.アントワープ郊外にあった「ネロとパトラッシュの像」。 |
 7.復元された風車小屋と子どもたち。 |
 8.ネロ少年あこがれの巨匠ルーベンスの「キリスト降架」。 |
|---|
コロナ禍乗り越えベストセラーに
中城正堯(30回) 2021.01.15
 筆者近影 |
|---|
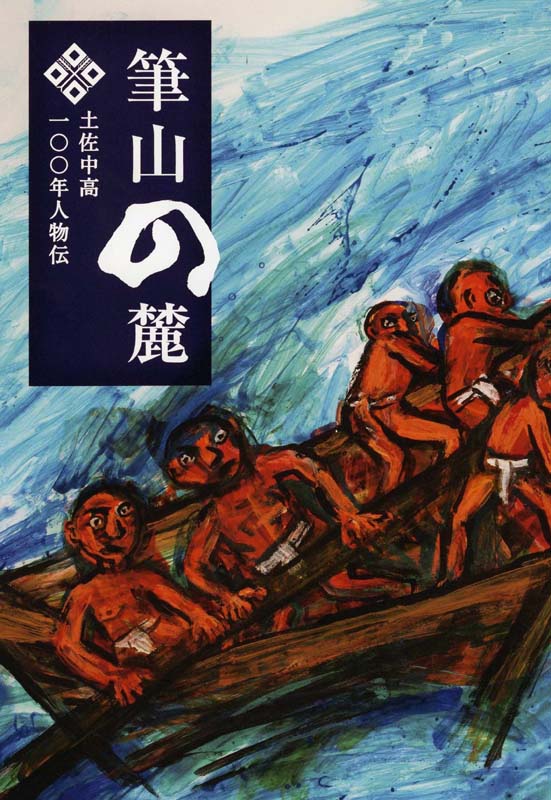 「筆山の麓」表紙。 |
|---|
新聞部出身者と7人のサムライ
この企画は、向陽プレスクラブ(KPC)で刊行した『土佐中學を創った人々-土佐中學校創立基本資料集』(2014年刊)、『三根圓次郎校長とチャイコフスキー』(2017年刊)の後続企画として、個人的にあたためていた。創立百周年が近づき、KPCでも同窓会本部でも検討いただいたが、「企画自体は評価するが、人選など内容に責任を負えない」とのことで、両者での制作・刊行は見送られた。しかし、創立記念の人物伝だけに個人で刊行できる本ではなく、残るは有志による刊行委員会形式しかなかった。これにいち早く賛意を表わしてくれたのが、KPCの公文敏雄(35回)、筆山会の佐々木泰子(33回)・前田憲一(37回)、前校長の山本芳夫(40回)、ジャーナリストの鍋島高明(30回)であった。年齢的には74~84歳の後期高齢者だが、いつまでも若々しい心の持ち主ばかりだった。
 刊行直後の2020年10月末に 集まった7人のサムライ(刊行委員)。 |
|---|
人物伝として取り上げたい候補は30人を超し、刊行委員だけではとても担当出来ず、さらに同窓生有志の協力を仰ぐことになった。ここでも新聞部出身者が競って執筆陣に加わってくれた。堀内稔久(32回)、冨田八千代(36回)、加賀野井秀一(44回)であり、公文敏雄と筆者を加えると、登場人物のほぼ半数ほどをこの5人が担当して、執筆や原稿依頼に当った。また、久永洋子(34回)、山本嘉博(51回)からも情報をいただいた。
 1958年の新聞部新年会 前列左から旧姓で森下(31回)早川(35回) 浜口(35回)大野(36回)合田山崎(34回)。 |
|---|
写真は1958(昭和33)年、これらの人物が在学中の新聞部新年会である。前列には左から、旧姓で森下睦美(31回・卒業生)、早川智子・浜口正子(35回)、大野令子(36回)、合田佐和子・山崎洋子(34回)が並び、後ろに刊行委員・公文敏雄のほか、卒業生の岩谷清水・横山禎夫・筆者・田内敏夫(31回)、岡林敏眞(32回)などもいる。
すごい先輩の息吹に触れて
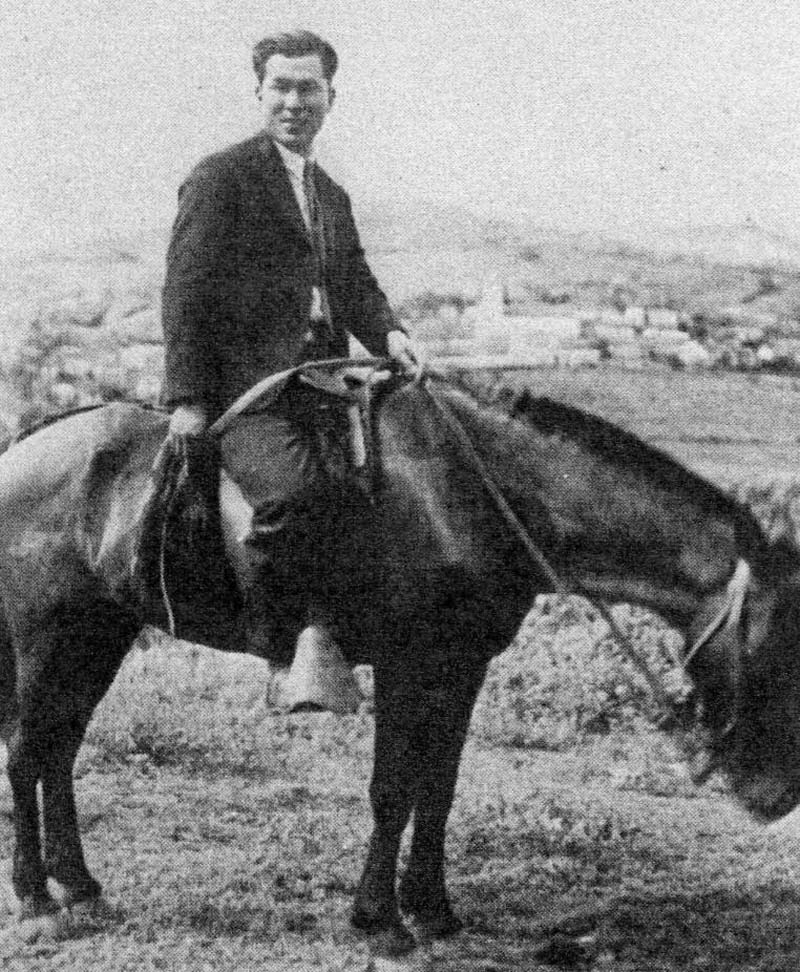 ブラジルで農業に取り組んだ 中沢源一郎(1回)。 |
|---|
このように隠れた存在の人物では、堀内稔久弁護士が発掘執筆してくれた下村幸雄(23回)もおり、下村の義弟に当る横山禎夫が取材に協力してくれた。また、公文公(7回生)の公文式が土佐中の個人別自学自習を元に生まれた学習法であり、初期には岩谷清水など多くの教え子たちがその事業を支えたことも明らかにできた。哲学者・加賀野井秀一は、異端の評論家・高山宏(42回)の百学連環ぶりを論じ、冨田八千代は世界最先端の宇宙物理学者・川村静児と須藤靖(52回)に体当たりで迫ってくれた。
むろん新聞部以外でも、元新聞記者の鍋島高明、鍋島康夫(40回)の両氏は、経済人やノンフィクション作家の活躍ぶりを見事な筆力で描写、元土佐中野球部監督の坂本隆(47回)は、大嶋光次校長、籠尾良雄監督(27回)、岡村甫投手(32回)、三者三様の野球への情熱ぶりを克明に再現、感激の場面を蘇らせてくれた。
刊行委員の佐々木泰子は、宮地貫一(21回)の文科省での業績につき、日本テレビ幹部だったご主人ともども同省の図書館へ行って調査くださった。ほかの委員にも、慣れぬ編集制作作業に、終盤はコロナ禍のなか家族ぐるみで協力いただいた。
本書誕生の背景には、母校ならではの師弟関係や同窓生の絆がある。筆者は上京以来、先輩たちが初代三根校長を敬愛してやまず、府中市多磨霊園に毎年墓参を続ける様子を見て過ごし、就職でも先輩に大変お世話になった。刊行委員には、それぞれ母校・先輩へのこうした思いがあり、手弁当での協力体制が出来あがった。
まだまだ多い隠れた人材
編集に当り最も苦労したのは、取り上げる人物の絞り込みであった。著名な科学者であるが、きちんと紹介出来なかった人物もいる。例えば木原博(4回)は東大で造船工学を確立、非破壊検査の先駆的研究で知られる。森下正明(6回)は京大での動物生態学の草分けで、梅棹忠夫などを育て、旧宅が森下正明研究記念館になっている。筆者のような文系には科学的業績がとてもとらえきれず、人物群像での紹介にとどまった。
新聞部員で残念だったのは、島崎(森下)睦美(31回)や、永森(松本)裕子(43回)だ。島崎は母校の国語教諭となり、新聞部顧問でもあった。結婚後はおもに横浜市に住み、子育てを終えると、保育士の資格を取った。保育園勤務後、横浜市の乳幼児子育て相談員になり、10年近く地域社会のためにボランティア活動を続けていた。永森はロンドン滞在の経験を生かし、海外からの帰国児童が日本でも各国の原書絵本を読み続け、言語も文化も忘れぬように国際児童図書文庫の運営に当った。またフィレンツエ滞在で出会ったフレスコ画研究に打ち込んで哲学美学修士を取得、研究や講演に活躍、『筆山』編集やKPCの活動再開にも先頭に立って貢献してくれていた。だが、お二人とも突然病に倒れ、多くの活動仲間に惜しまれつつ亡くなった。ほかに、埼玉県で社会活動家として奮闘していた山川(大野)令子もいた。
 1985年夏の三根校長墓参会 前列右から三人目が世話人の近藤久寿治(6回)。 |
|---|
編集が大詰めとなった昨年2月にコロナ禍が拡大、毎月の編集会議が出来なくなり、校正など仕上げの作業が全てメールでやらざるを得なくなった。しかし、比較的若い前田・山本のお二人が印刷所や同窓会などとの連絡を含めて、制作管理の面倒なとりまとめ役を買って出てくれた。昨年のメールを開くと、毎日のように校正紙をめぐるやりとりが続いている。一字一句疎かにせず、疑問点は指摘し合った。しかし、筆者のような老齢者はうっかりミスが多く、この校正でどれだけ救われたか分からない。こうして、何とか予定どおり2020年10月10日の発行にこぎ着けた。
むろん刊行後も、チラシ制作から同窓会誌での新刊紹介、さらに知人への購入呼びかけまで、コロナ禍のなかでも販促広報活動が続いた。高知での「土佐校百年展」(2020年11月10~15日)には、前田、公文、冨田などのみなさんが帰高して駆けつけ、本書とチラシを手に購読を呼びかけてくれた。高知新聞は11月12日に<「筆山の麓」出版 多くの出身者たちの紹介を通し、同校の教育をうかびあがらせている>と述べ、朝日新聞高知版は12月7日に<「卒業生の32人土佐中高語る」 有志が母校の人材育成の歴史を振り返ろうと企画・・・自主性を重んじる自由な校風を築いた初代校長らを紹介>と報じた。
どうかみなさんも、7人のサムライとその仲間が、せいいっぱい頑張って描いた母校の誇るべき人物たちの歩みに、ぜひ思いを寄せていただきたい。 念願の『創立百年史』を読んで
-親しめる『土佐中高100年の歩み』を創ろう-
中城正堯(30回) 2021.01.15
豪華な『創立百年史』に驚く
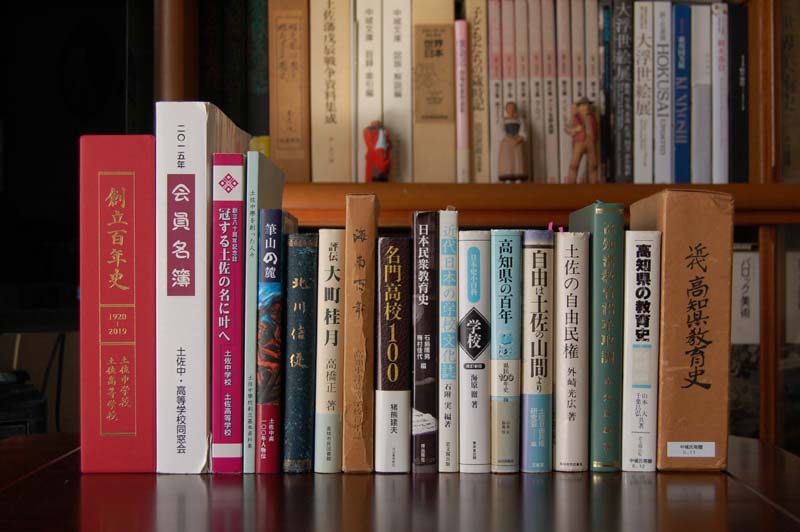 筆者所蔵の高知県教育史関連図書。左端が、 ようやく加わった土佐中高の『創立百年史』。 |
|---|
通史は、学校百年史の基本的な部分だが、導入の章では明治の自由民権運動がらみで「私学の黄金期」を、戦時中の章では「四国の学徒動員」を詳細に論じており、教育学・学校史の専門家ならではの斬新さを感じた。特に、「建学の精神」に関しては、土佐中の「設立趣意書」や「開校記念碑」から、それは「国家が望む人材の育成」であり、「報恩感謝」ではないことを明確に述べてあり、大いに評価できた。また、新制土佐中高になってからは『向陽新聞』の記事をよく活用、学校生活を分析してあるのもありがたかった。
なぜか無視された基本資料
いっぽう、明治黄金期の私学として海南中学や土佐女学校に紙数を割く一方、それらと土佐中誕生がつながらず、違和感も覚えた。向陽プレスクラブで平成26(2014)年に刊行した旧制土佐中学時代の基本資料『土佐中學を創った人々』も、ほとんど活用されてない。専門家ならではの特論とも言うべき個別テーマでの掘り下げは見られても、私立中高の100年史としての時代区分も、学校史としての柱である教育方針や教育内容、そして学校文化の変遷も、記述に基準や統一性がとれてなく、100年の曲折に富んだ歩みがよく読み取れない。学校文化とは、校舎・制服・校歌・運動会・自治会(向陽会)・部活などだ。制服・校歌を扱ったのはよいが、創立時の“制服は背広”という構想に触れてないなど、掘り下げが不足だ。
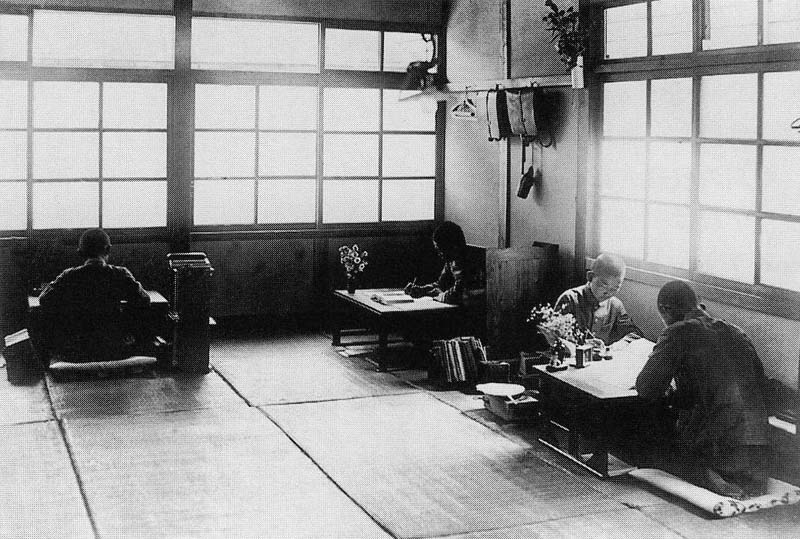 学内の寄宿舎にあった寮の学習室。 |
|---|
さらに、残念なのは誤植や引用ミスが研究書にしてはとても多いことで、執筆者や校閲者の『土佐中高学校史』というテーマへの強い意欲や愛着が感じられない。本書の筆者がよく引用している『近代高知県教育史』(高知県教育研究所 昭和39年刊)に、土佐中はわずか9行しか割かれていない。これは土佐中高の通史としての学校史が未刊のためでもあり、研究者から無視をされても文句が言えなかった。今後は是正を迫ることが出来ると考えたが、このような内容と表記ミスでは心許ない。
教員・同窓生一体で伝統に迫ろう!
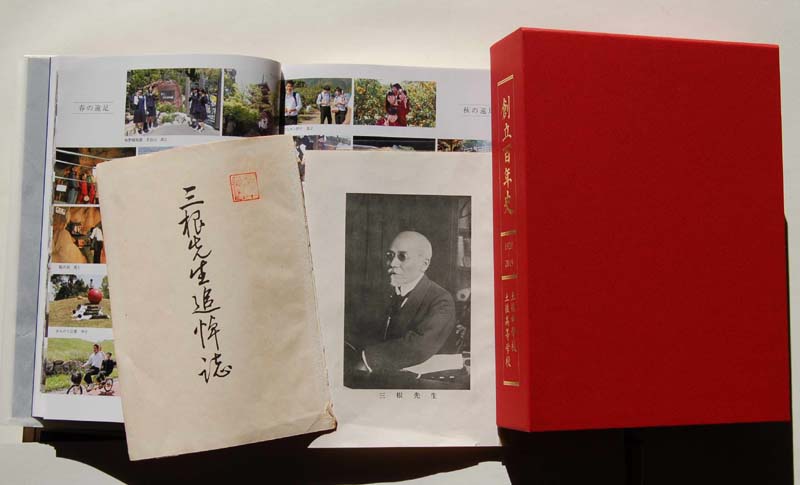 『創立百年史』と『三根先生追悼誌』。 後者は、1997年に宮地貫一同窓会関東支部長 が復刻した際に使用した原本の一部。 |
|---|
学校任せや研究者任せでなく、同窓会も乗り出すべきで、これを機会に一般卒業生や県民にも親しめるみんなの学校史『土佐中高100年の歩み』(仮題)を、別途学校と同窓会が共同で企画編集するのも一案だ。学校長だけでなく、各時代の名物教諭や学芸・スポーツで活躍した生徒など、人物を登場させるといった工夫もしたい。さらに、若い人々が自ら調査執筆することによって、教職員も卒業生も、母校の伝統をより会得することができ、伝承が可能となる。じつは『三根先生追悼誌』も、平成9(1997)年に「建学の精神」が忘れられつつあるのを憂い、宮地貫一同窓会関東支部長が自費での復刻を企画、筆者は印刷所の手配などそのお手伝いをした。この時、はじめて全文を読み、三根校長の人物とその教育姿勢に感服した。
『創立百年史』の配布は限られているようだが、手元に届いた新聞部出身者は、豪華な本書を書棚の飾りとせずに、ぜひ熟読して欲しい。そして対応策を協議・具体化し、学校の歴史を我々の手に取りもどしたい。母校・同窓会に、みんなで具体案を提案し、3年後をメドに「私たちの学校史」をまとめていただきたい。
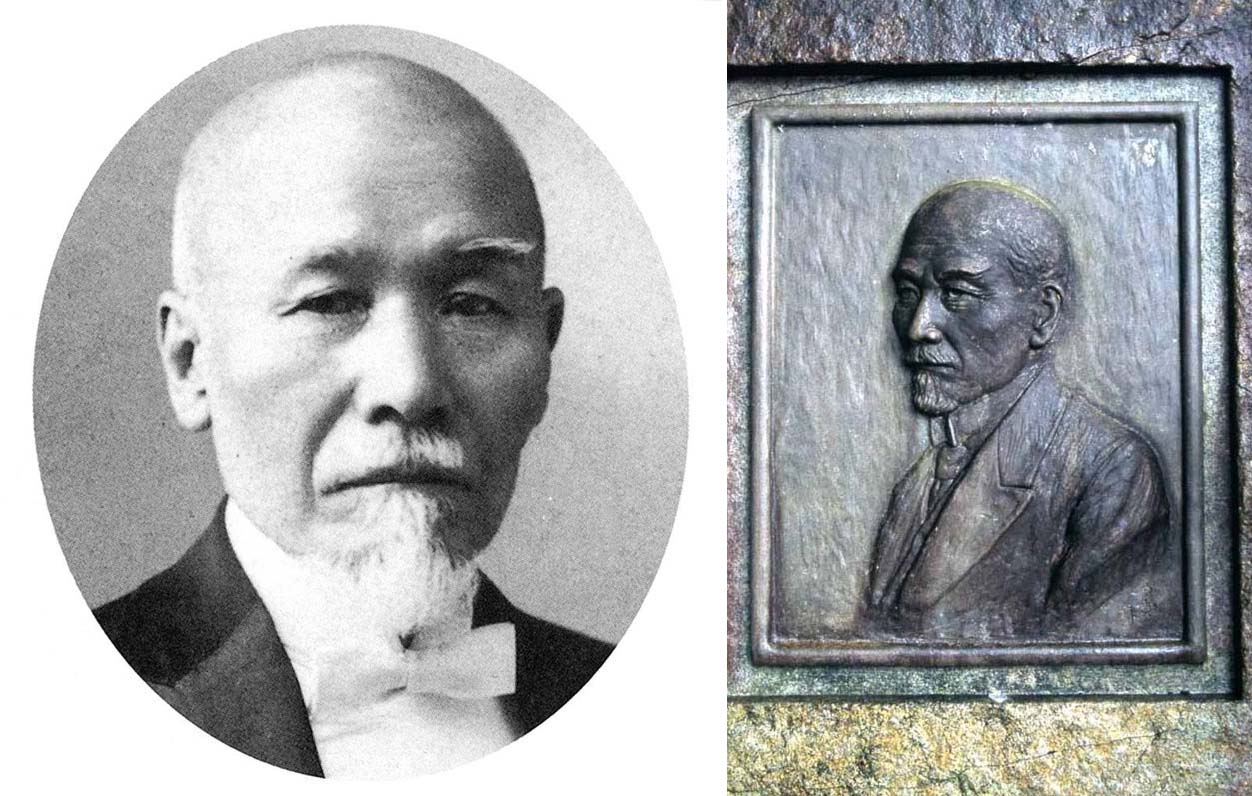 三根圓次郎初代校長の写真と同窓会が建設した胸像(本山白雲作)。 |
|---|
田島征彦展のお知らせ
中城正堯(30回) 2021.03.15
『筆山の麓』でも紹介した絵本作家・田島兄弟(34回生)の兄、田島征彦さん(淡路島在住)から2つの個展案内状が届きました。いずれも、関西での開催です。お近くの方は、ぜひご覧下さい。
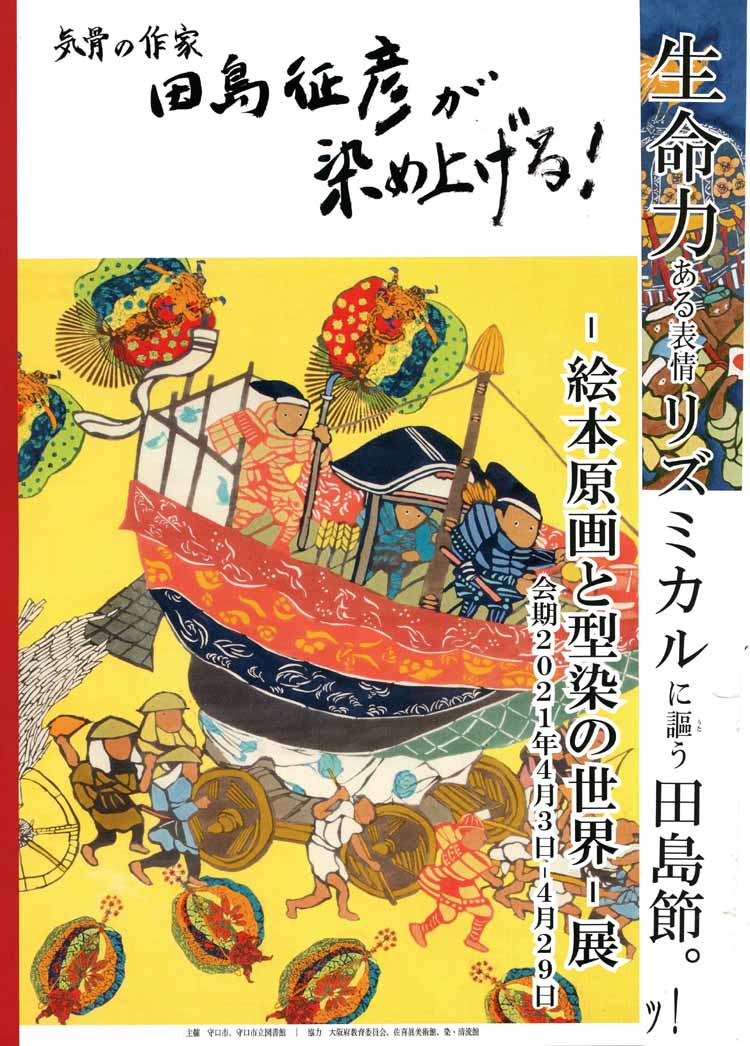 |
|---|
会場 大阪府守口市大日町2-14-10 守口市立図書館 ℡06-6115-5475
交通 地下鉄谷町線「大日駅」、大阪モノレール「大日駅」より徒歩5分
会期 4月3日~29日
・守口市立図書館一周年記念の記念行事としての展覧会で、4月24日(土)14時~15時30分には、田島さんの講演会(予約制・無料)も開かれます。
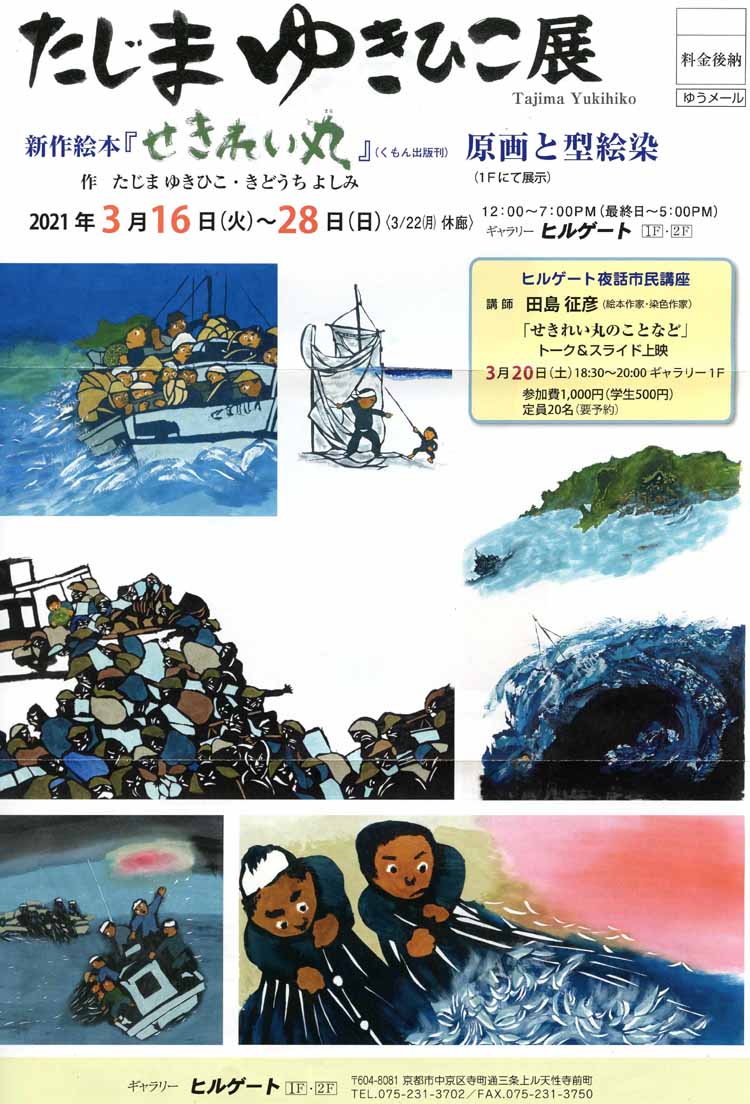 |
|---|
「たじまゆきひこ展」―新作絵本『せきれい丸』原画と型染め絵-
会場 ギャラリー ヒルゲート 京都市中京区寺町通三条上ル天性寺前町
交通 地下鉄東西線「市役所前」より徒歩3分 ℡075-231-3702
会期 3月16日~28日
・3月20日(土)18時30分~20時には田島さんによる講座「せきれい丸のことなど」が開催されます(要予約、参加費1.000円)。
浅井伴泰さん(30回)追悼文
母校を熱愛した新聞部の“野球記者”
中城正堯(30回) 2021.05.10
虫の知らせ
 筆者近影 |
|---|
そこで、和子夫人にメールで「松﨑や西内など級友がみんな心配している・・・」と送信して入院した。3日間のカテーテル検査などを終えて21日に帰宅すると、公文敏雄・KPC会長から「浅井さん逝去」の知らせが届いていた。虫の知らせが、当ってしまったのだ。西内君から22日葬儀との連絡をもらったが、検査づめで疲れ果てており、残念ながらお見送りできなかった。そこで「・・・阪神大躍進と賢夫人和子様に見送られての安らかな旅立ちを迎え 心からご冥福をお祈り申し上げます」と、弔電を供えた。
公文クラスの新聞部三人組
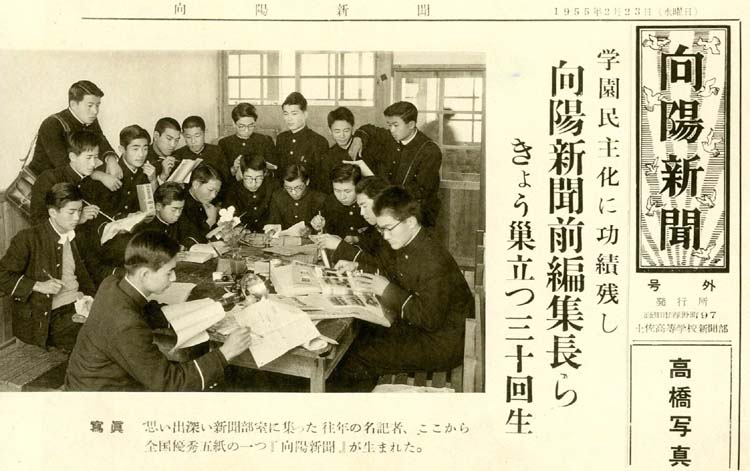 昭和30年の土佐高卒業アルバムに掲載の新聞部記念写真。 後列左から3人目が浅井君 |
|---|
B組の級長は大町玄君で、彼に浅井君、千原宏君が加わって中一から新聞部に入っていた。筆者も誘われて入部したのは、中2になってからだ。浅井君は全てに早熟で、野球は中学で卒業、新聞部も高1でさっさと卒業した。酒は早く、いつからかは判然としないが実家が酒屋だった谷岡先生から年末に一升瓶をせしめ、母親の留守をねらって浅井家に悪友が集まっては酒盛りを開いたりした。二学期の終業式で、生活指導のオンカンが「正月に酒を飲んだら街中を出歩くな」と、白線が目立つのを諫めるだけの時代であった。
 浅井記者によるセンバツ野球の記事。 クリックするとPDF版へ向陽新聞第18号昭和28年4月13日 |
|---|
記者としての名文は、翌28年春のセンバツ野球観戦記だ。筆者が編集長で、選抜の記事を売り物に新年度開始早々に発行すべく準備を整え、千原君を特派記者として派遣していた。初戦で早稲田実業に6-0と快勝したが、二回戦は銚子商業に0-3で敗れた。翌日、原稿到着を待つ部室に千原君から電報が届いた。「ネツアリ キジカケヌ」とある。そこで、選手とともに帰高したばかりの浅井君にピンチヒッターを依頼、一晩で書いてもらった。「向陽新聞」二面トップに「お嬢さんと記念撮影 センバツ野球裏話」の見出しが躍っている。ところが、この記事の活字が組み上がったところに、ひょっこり千原君が記事を持って現れた。熱が引き、なんとか書いて駆けつけたという。そこで急遽、部数を二分し、浅井記事を第1版、千原記事を第2版とすることを決断した。こうして昭和28(1953)年4月11日発行の「向陽新聞」第18号は、これまた高校新聞では初めての2版二種類が実現した。これら、「向陽スポーツ」「向陽新聞18号」とも、KPCホームページのバックナンバーに収録されているので、ぜひ浅井記者を偲んでご覧いただきたい。
クラス誌「うきぐも」に注力
 東京で公文先生(中央)と再会した浅井君(左)と、 倉橋由美子さん(29回生・右)。筆者撮影 |
|---|
しかし、大町・浅井・千原の三人組は、高二になると新聞部を辞める。やむなく、横山禎夫君と筆者がまとめ役を卒業まで続けることになる。この背景には、我々Oホームは“公文先生が主任”と信じて集まった者が中心で、高1になると若い新担任に落胆、以来主任との軋轢が絶えなかったことがある。そこで、この三人組を中心に文芸部の梶田広人君なども加わって、クラス誌として文芸色の強い「うきぐも」が創刊された。一般的に、文化部は高1で引退し、受験勉強に専念するならわしであったが、三人組はむしろクラス誌編集や、草野球など課外活動に熱中し、担任との抗争も続いた。「うきぐも」は卒業後も続き、平成23(2011)年に第20号を出したが、その企画・編集には、相変わらず三人組の名前が並んでいた。しかし、浅井君の逝去で、ついに三人とも消えてしまった。
高校時代の思い出で印象深いのは、昭和29年秋、高3の運動会での仮装行列である。Oホームのテーマは「吉田神社の夏まつり」で、写真前列右が葉巻を加えた吉田茂首相と、寄り添う娘の麻生和子巫女である。細面の浅井君は、いかにも清楚な巫女になりすまして大好評であった。小生は、その他大勢の汚れ役・進駐軍で、顔を黒く塗りパンパンたちに囲まれている。当時の政治情勢への批判を込めた仮装で、間もなく吉田は引退し鳩山内閣となる。翌30年の「卒業アルバム」の寄せ書きに、「天皇を葬れ!!これが民主化の第一歩だ」とか、「保守反動を打ち破れ!」とあり、前者が浅井君、後者が筆者であった。
 昭和29年の運動会Oホームの仮装行列 前列右端の美人巫女が浅井君 |
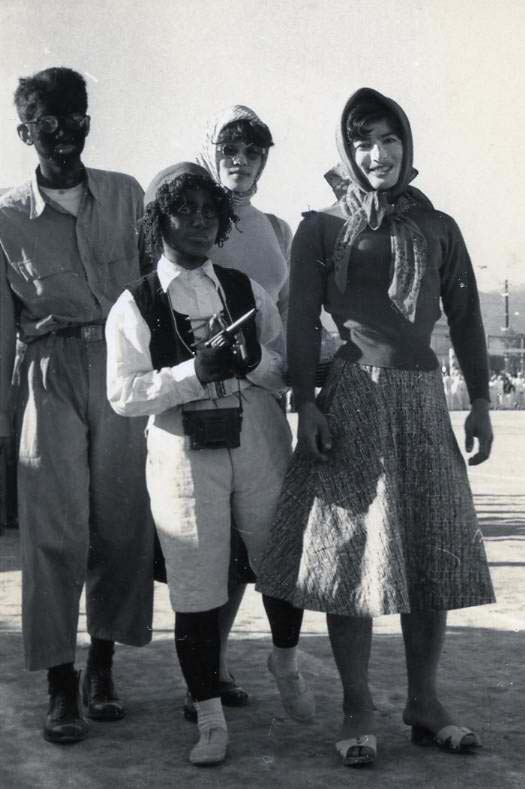 仮装行列での進駐軍 筆者(左端)と女性たち |
|---|
「土佐高野球が命」そして夫婦旅行
晩年の様子を簡単に報告しておこう。会社や同窓会の役員も勤め上げ、晩年はもっぱら趣味を楽しんでいたが、その熱中ぶりはやはり尋常でなかった。野球は、阪神ファンでいわゆるトラキチだが、それ以上に「土佐高野球が命」であった。春秋の県大会や四国大会が始まると、家業にかこつけて帰高しては観戦、戦績や有望選手情報を克明に知らせてくれた。たまに甲子園出場が決まると、現役のサラリーマン時代から級友は全試合応援に呼びつけられていたが、途中から筆者には声がかからなくなった。それは、高2の夏の決勝戦以来、連続4試合筆者が行く試合は、全て眼前で敗れたからだ。
野球だけではない。相撲も幕下から高知出身の力士情報を教えてくれた。さらに競馬にも通っていたようだが、これは高知競馬より中央競馬の大レースを好んだようで、大穴を当てたことはずっと後から聞かされた。「浅井金持ち、川﨑地持ち」と謳われた江戸以来の豪商の末裔だけに、力士や名馬のいわば「たにまち」のような存在に思えた。
仕事から身を引いた後、同窓会関東支部幹事長や筆山会会長も早めに身を引き、後任に一切を託していた。ただ、同窓会本部の役員若返りが進まないことだけは、気にしていた。
筆者が出版社を退いた際に、高知からも仕事の誘いがあったが、高知の情報に詳しいだけに、「それはやめたがよい」と賢明な助言をしてくれた。
 和子夫人のガーナ大使離任で、 大統領に挨拶。2006年の年賀状より。 |
|---|
こうして土佐高の同窓生同士の結婚でも、ともに独自の分野で働き、さらに夫妻助け合って日本ガーナの親善事業や、母校・同窓会の役員など社会的な活動を続け、模範的なカップルであった。最期も、珍しく阪神首位躍進のテレビを楽しみ、奥様に見守られての穏やかな旅立ちで、うらやましい限りである。ただ、松﨑君に限らず級友一同、「もう一度アザイに会いたかった」の思いが消えない。合掌
 夫妻が感動したという壮大な アブシンベル神殿。筆者撮影 |
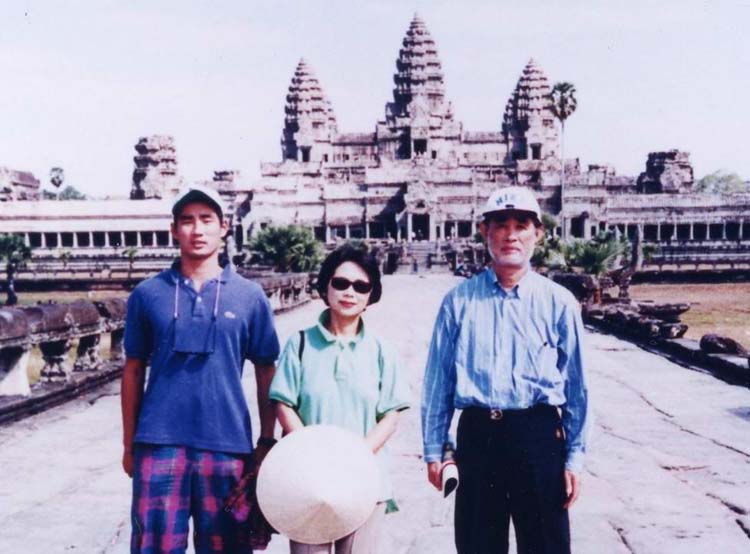 カンボジアのアンコールワットでの 夫妻と長男。1998年の年賀状より。 |
 世界自然遺産・白神山地の原生林を散策 2008年の年賀状より |
|---|
追記:浅井家の歴史に興味のある方は、『高知経済人列伝』(鍋島高明編 高知新聞社)や、『高知県人名事典 新版』(高知新聞社)の〈浅井藤右衛門〉の項目をご覧いただきたい。同様に、和子夫人の実家・中谷家も中谷貞頼などが出ている。 サンペイさん追憶!出会いと土佐の旅
中城正堯(30回) 2021.08.09
東京で初めての原稿依頼人
 筆者近影 |
|---|
 サンペイさんとファン。 檮原「雲の上のホテル」で。 |
|---|
那須さんは昨年春、筆者の「寺子屋と郷学が育てた佐川の人材」(佐川史談会誌掲載)を読んで、「寺子屋の話、興味深く拝読。(破門された子を諭して師匠に詫びる)あやまり役の老人が居たというのは面白いですね」と、感想を寄せてくれた。浮世絵に登場する江戸のいたずらっ子が、そのまま大人になったような作家で、作文審査や講演会で大変お世話になった。山口県防府市に住み続けていたが、肺気腫での急逝だった。サンペイさんも誤嚥性肺炎が原因で、筆者も肺の病気を抱えるだけに他人事ではない。
サンペイさんは、小生の編集稼業のなかでも特に印象深い一人で、高知も絡んでのさまざまな交流があった。その一端を紹介しよう。漫画家をめざし大阪大丸の宣伝部をやめた際、関西ジャーナリストのドン小谷正一氏から「漫画家になるなら、漫画界の王様、横山隆一氏に会っておくがよい」と言われ、鎌倉の横山邸に連れて行かれる。自作の四コマ漫画を差し出すと、王様から「案はいい。漫画を描くんだったら東京へこなくちゃダメだよ」と云われ、東京へ引っ越す。
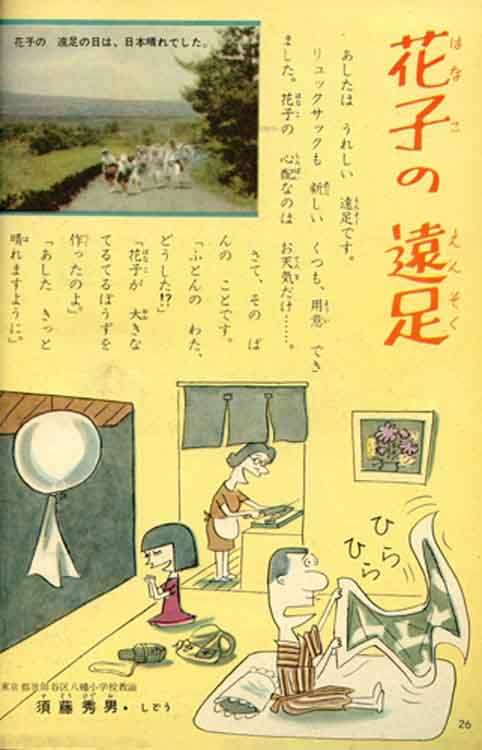 サンペイさんの挿絵。 『3年の学習』1962年10月号。 |
|---|
漫画の王様・横山さんの導き
サンペイさんを中央の漫画界に導いた横山隆一さんは、筆者にとっても編集者への道を開いて下さった恩人であった。1959年の中大卒業を間近にしながら、新聞社・出版社ともはねられ続け、やっと学習研究社の一次(筆記試験)に受かり、次は「出版企画を提出せよ」の課題が出た。当時、新しく小学校で道徳教育が登場するところで、横山さんの人気漫画「フクちゃん」を活用した道徳漫画の副読本を企画した。公立図書館の貸出しデータから、横山漫画が子どもにも人気なのを実証、さらに道徳の徳目ごとに適合した4コマ漫画を選んでページ見本も作成した。学力での劣勢を、企画力でカバーするのに必死だった。
この様子を知った土佐高東京同窓会のドン近藤久寿治先輩(6回生・同学社社長)が、岡﨑昌生先輩(24回生・外務省)を通して横山隆一氏を紹介して下さった。岡﨑先輩は、横山夫人のご親戚であった。こうして、鎌倉の横山邸を訪問し、サンペイさん同様に助言をいただいたが、内容は思い出せない。
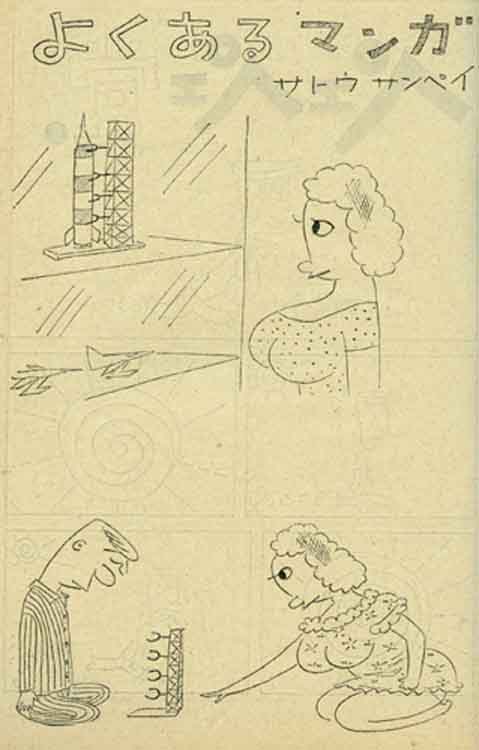 ビジネス雑誌『マイウェイ』 の漫画。1969年9月号。 |
|---|
サンペイさんは、筆者の次に人気週刊誌『漫画サンデー』の峯島正行編集長から声がかかり、出世作「アサカゼ君」が誕生、『暮らしの手帖』花森安治編集長にも認められる。朝日新聞の「フジ三太郎」は、ヒラ・サラリーマンの立場から、世相を風刺とユーモアを効かして切り取り、大人気を得て長期連載となる。筆者が学習雑誌からビジネス雑誌の部門に異動してからも、超多忙ななかで仕事を受けていただいた。ビジネス雑誌では、漫画以外にも、当時の人気芸能人との対談も始め、お好みに合わせて若手清純派歌手・森山良子から「恍惚のブルース」の青江三奈まで、毎月銀座の三笠会館に呼んでおしゃべりを楽しんだ。ビジネス雑誌の漫画では、ロケット発射台の模型を挟んで、元気な奥様としょんぼり亭主を描いている。
高知県の依頼で「雲の上のホテル」へ
 御畳瀬でコップ酒を手に立ち 食いするサンペイ・下重のお二人。 |
|---|
この記事の最初に掲載した写真は、隈研吾氏設計の名建築「雲の上のホテル」レストランで、大阪から来たファンの女性に見つかりご満悦のサンペイさんだ。もう一枚、御畳瀬の干物に舌鼓を打つサンペイさんと下重さんを紹介しておこう。やがてお二人の筆になる、高知の知られざる伝統文化や、最新のホテルなど観光情報が、新聞雑誌に次々と掲載された。その一つには、女性に代わって筆者らしき人物との食事場面が描かれていた。サンペイさんは、新聞連載から身を引いた後も、運転免許取得、パソコン習得、海外旅行などへのチャレンジを楽しんでは、その奮闘記を出版し、賀状でも知らせてくれた。これは1998年の年賀状。
 土佐の旅のエッセイ挿絵。 1979年3月「山陽新聞」他。 |
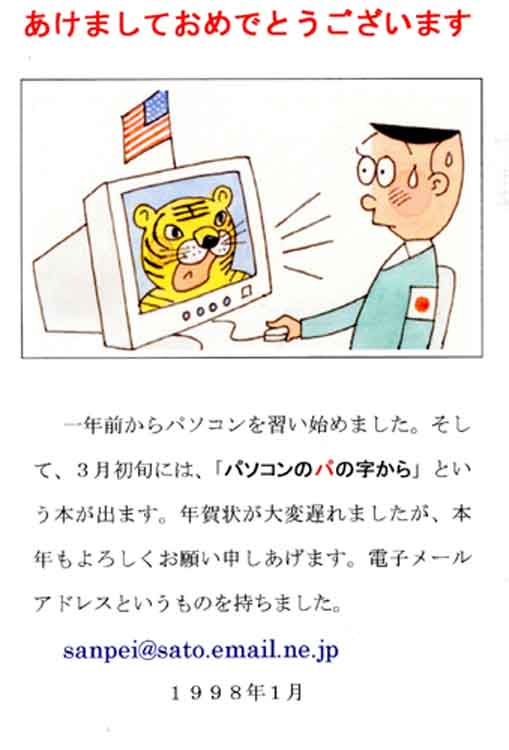 新聞連載を終えてからの パソコン年賀状。1998年。 |
|---|
『絵画史料による 江戸子ども文化論集』
江戸子ども文化論集への反響
中城正堯(30回) 2021.09.10
 筆者近影 |
|---|
・辻本雅史(京都大学名誉教授・教育思想史)
「子ども浮世絵」のコレクションは、比類なき素晴らしい限りで、ウェブ構築までまことに敬服するばかりです。公文の文化事業として社会的意義はとても大きいと存じます。その過程での論文の数々壮観です。「子ども浮世絵」「母子絵」と名付け分類した功績、西洋にない日本の特質で、学問的意義や大、ぜひ市販を期待しています。
・常光 徹(国立歴史民俗学博物館名誉教授・高知県出身)
ご研究のなかでも、「子どもの魔除けファッション―病魔と闘った母性愛の表象―」は、とても興味深く多くのことを勉強させていただきました。私も浙江省の民俗調査をしたときに、赤い腹かけをした子どもを見かけたことを思い出しました。また、カニに関する伝承が浮世絵に描かれていることを知り、中国との交流の歴史の深さを改めて感じました。
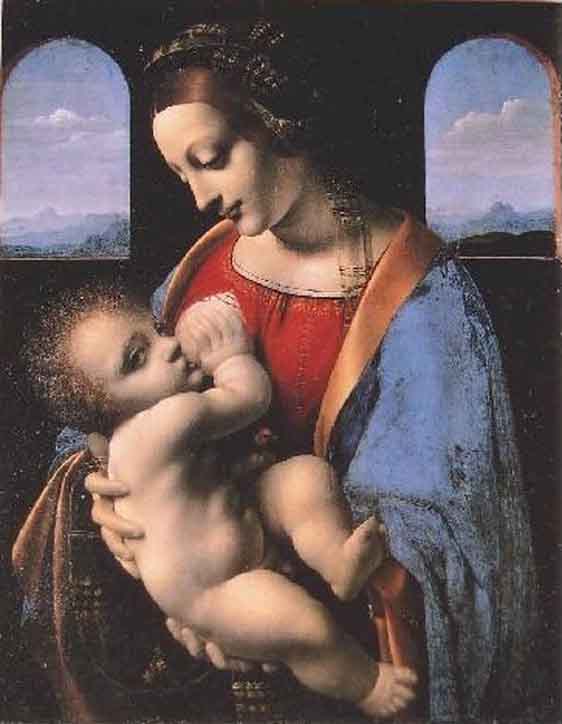 「リッタの聖母」レオナルド・ダ・ヴィンチ 1490年頃 エルミタージュ美術館蔵 |
|---|
<「もう一つの美人画“母子絵”-歌麿の母性愛浮世絵-」につき、>西洋絵画、例えばネーデルランドの風俗画など、子供のいる場面はありますが、そこに愛情あふれた育児の場面は見当りません。日本独自の文化として誇るべきテーマかと思いました。日本の近代化を語る際、明治維新があまりにも重視され、江戸中期・末期からの文化の連続性が無視・軽視されてきたきらいがあるように思います。この御研究は、歌麿といえば花魁美人図といった先入観から脱し、江戸後期の庶民文化の真の姿を解明し、西洋になかった独自な美点を明瞭に示された、素晴らしいご研究と思います。
・中江利忠(朝日新聞社元社長)
貴兄の数十年にわたる「子ども浮世絵」の発掘からスタートした日本と東洋・西欧の文化史論の集大成であり、画期的な大事業だと思います。特に最後に「日本にも『国際子ども博物館』を! 」と訴えられたことは極めて意義深いことであり、署名でしたら参加させて下さい。サンペイさんの追悼レターも記されていますが、付き合いの長さでは貴兄が十数年長く、あらためて見直しました。
 〈風俗美人時計 子ノ刻」歌麿 寛政11、12年頃 大英博物館蔵 |
|---|
永年の子ども文化研究の集大成として、大変参考になります。とりわけ「おんぶ文化再考」は、興味深く拝読。
・小林忠(学習院大学名誉教授・国際浮世絵学会名誉会長)
御著書、座右に置いて、種々学ばせていただきます。私の近刊(『光琳、冨士を描く! 』をお届けします。
・小和田哲男(静岡大学名誉教授・日本城郭協会理事長)
『江戸子ども文化論集』、後半の魔除けに関するあたりが、特に興味深かかったです。
・三山陵(中国民間美術研究家)
「上方わらべ歌絵本」を大変興味深く拝読。合羽摺も美しいし、素晴らしい資料です。やはり、資料は解る人、必要な人のところに来るのだということも納得です。江戸の教育・文化程度の高さにも一段と感じ入りました。続くポロの話も面白く、八戸に騎馬打毬があることに興味津々です。
 「当世風俗通 女房風」喜多川歌麿 享和頃 公文教育研究会蔵 |
|---|
ライフワークを淡々とこなしておられる、その熱意と好奇心の持続に心より敬意を表します。昨年1月にミャンマーに行ったのを最後に、海外への旅行は遠い昔の話になってしまいました。私がサハラに行き始めて来年でちょうど50年になります。当時の暮らしは歴史記録となっており、また戦乱により、もう何年も立ち入れぬことから、この半世紀間の記録をまとめてみようかと整理を始めたところです。
・大石芳野(写真家)
ご著書をお贈りくださいまして、誠にありがとございます。1986年からずっと〈子ども浮世絵〉の発掘研究をなされていらっしゃったとは・・・!さすが中城さんです。成果の程は、専門外ですがただただ唸らされる思いです。
・下村幸雄(裁判官・弁護士・23回生)
この度のご本、隅々まで神経の行き届いた見事な造本で、感服いたしました。中城さんの面目躍如です。歌麿のエロティックな母子像には以前から見慣れていますが、それが西洋の聖母子像と影響し合っていることなど、露知らず、子ども群像に至っては、その存在さえ知りませんでした。
 「浴槽のディアーヌ・ド・ヴワチエ」 フランソワ・クルーエ 16世紀 シャンティイ城美術館 筆者撮影 |
|---|
子ども浮世絵を読む楽しさを御紹介下さり、私も子どもの頃を思い出し、楽しいひとときを過ごさせていただきました。それにしましても、寺子屋では女の子も手習いをしていたことを知り、びっくりいしました。その自由な伸び伸びとした雰囲気に江戸町民の自由闊達な生活があり、300年続いた江戸の平和を改めて知ることが出来ました。子どもの姿、表情にその社会が顕れています。歌麿の母子絵と比べ、クルーエの「浴槽の・・・」のなんとつめたいことか。
・公文敏雄(NPO法人役員・KPC会長・35回生)
ご研究の成果がふんだんに盛り込まれて、長年のお働きが伺え、敬服いたしました。このごろ縄文文化が見直されていますが、江戸時代も、我々が教科書で読んだ階級差別、庶民の苦しみ、百姓一揆の頻発などの自虐的記述に虚偽・誇張が多いとの研究結果が発表されるようになりました。浮世絵は江戸の庶民の暮らしぶりの一端を伝えるアートかつ貴重な歴史資料でもありますね。
(以上いずれも私信の一部であるが、著者にとって嬉しい反響であり、紹介させていただいた。中城) オランダ黄金時代の跡
香料列島モルッカ諸島
中城正堯(30回) 2021.09.19
 筆者近影 |
|---|
なお、香料列島のバンダ諸島をめぐっては、16、17世紀に貿易の主要商品であった香料の丁字(クローブ)やナツメグの獲得をめざし、現地先住民・英・蘭で激戦が繰り広げられます。しかも、17世紀初頭には、関ヶ原で敗れた西軍の残党兵がオランダ軍の傭兵となって、この離島まで動員されています。近年、日本の歴史家も研究しているようです。現地の小さな郷土博物館で、日本刀を振りかざして戦うサムライの油絵を薄暗い壁面で見かけ、撮影しましたはずですが、残念ながら見当たりません。
手元にある、英・蘭・日・先住民4者入り乱れての強者たちの夢の跡をご覧いただきます。今は、真っ青な海に緑の小島が点在する別世界です。なお、バリ島から飛行機でモルッカの中心都市アンボンへ飛び、バンダ諸島へはここから客船で一泊の旅、もうニューギニア島に近いとびきりの離島でした。
 勇猛な海洋先住民の伝統的なボートレース |
 古舟の図を持つ村人。今はイスラム教徒だ。 |
|---|
 今も実るナツメグの実。 果肉のジャムも美味しかった。 |
 ナツメグの種。 これが香辛料になる。 |
 伝統的な武将の装束を付けた村人。 兜飾りに珍しい熱帯の鳥。 |
|---|
ヒマラヤ南麓の愛しき稲作民
中城正堯(30回) 2021.10.15
 筆者近影 |
|---|
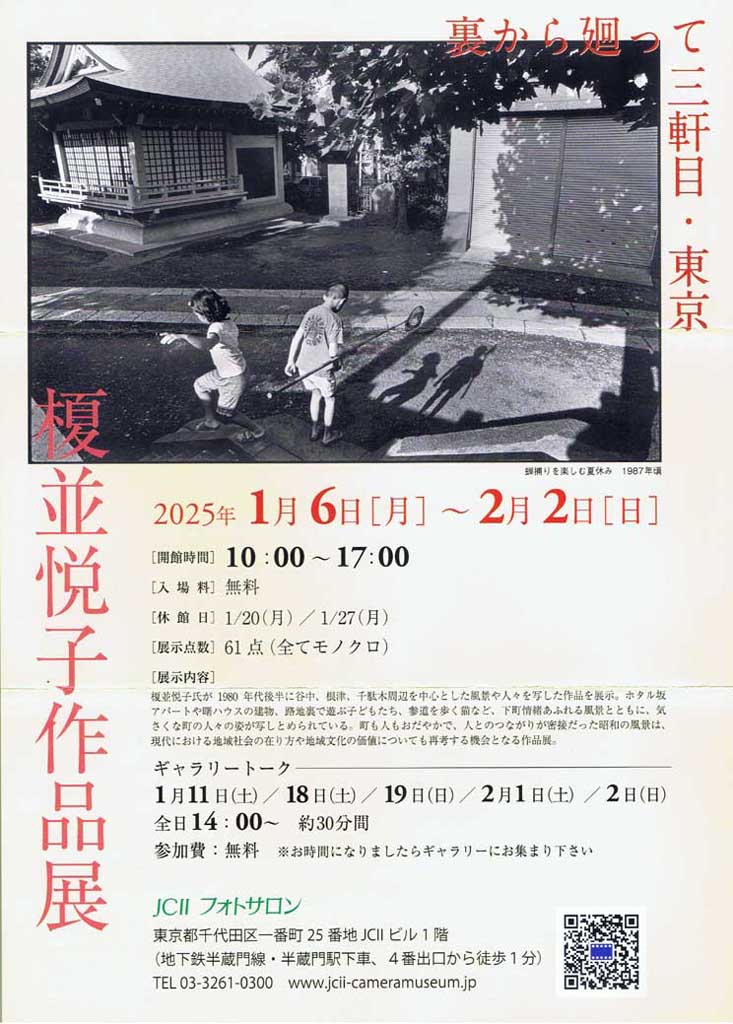 著者の榎並悦子氏と アパタニのNibu(Priest/shaman) |
|---|
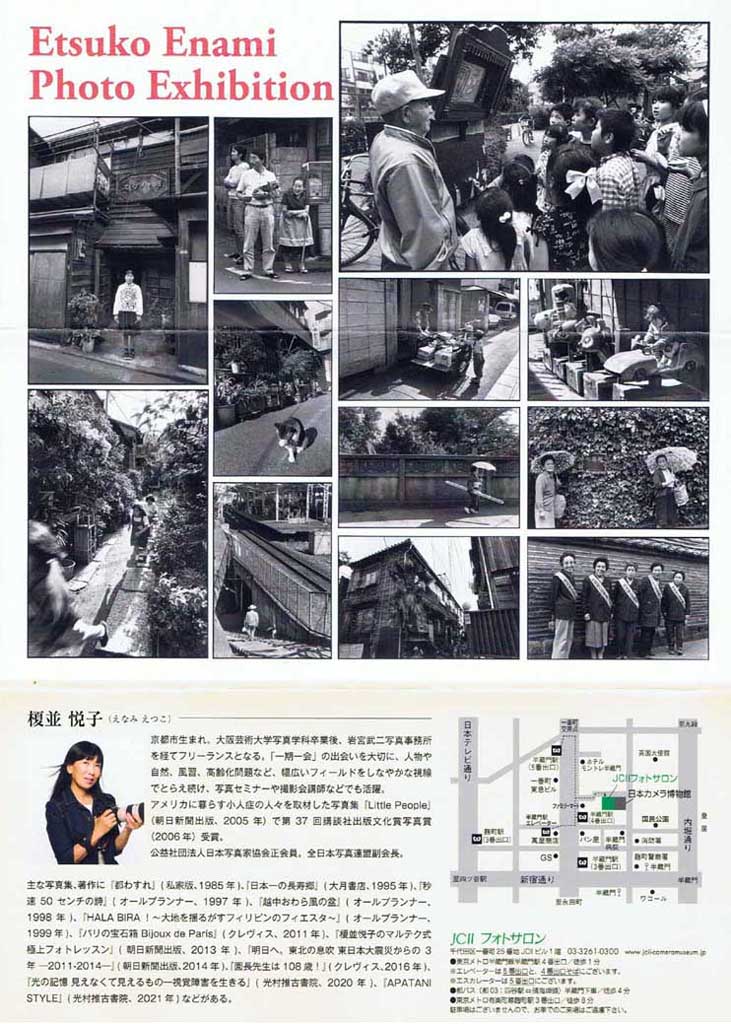 鼻栓・タトウー・首飾りの老女 |
|---|
 祭りで正装の女性 穏やかで優しげな表情だ |
|---|
 タイ北部のバダウン族。 少女 と |
 母子 ………… (中城撮影) |
|---|
 生後一週間の赤ちゃんを抱く、 アパタニ民族の若い夫婦 |
|---|
では、筆者の撮影したインパール近郊の浮島漁民などの様子が、1993年2月29日の『アサヒグラフ』に掲載されたので、その一部を紹介しよう。
<写真>(アパタニ民族の写真は、全て本書より)
≪注≫榎並さんは、高知出身の野町和嘉さん(世界的フォト・ジャーナリスト)と、写真家夫妻で、中城や藤宗もメンバーの、ジャーナリストや写真家による情報交換会「トータス(陸亀)21」の仲間です。
インパールの浮島漁民と山地民。(アサヒグラフ誌より)。
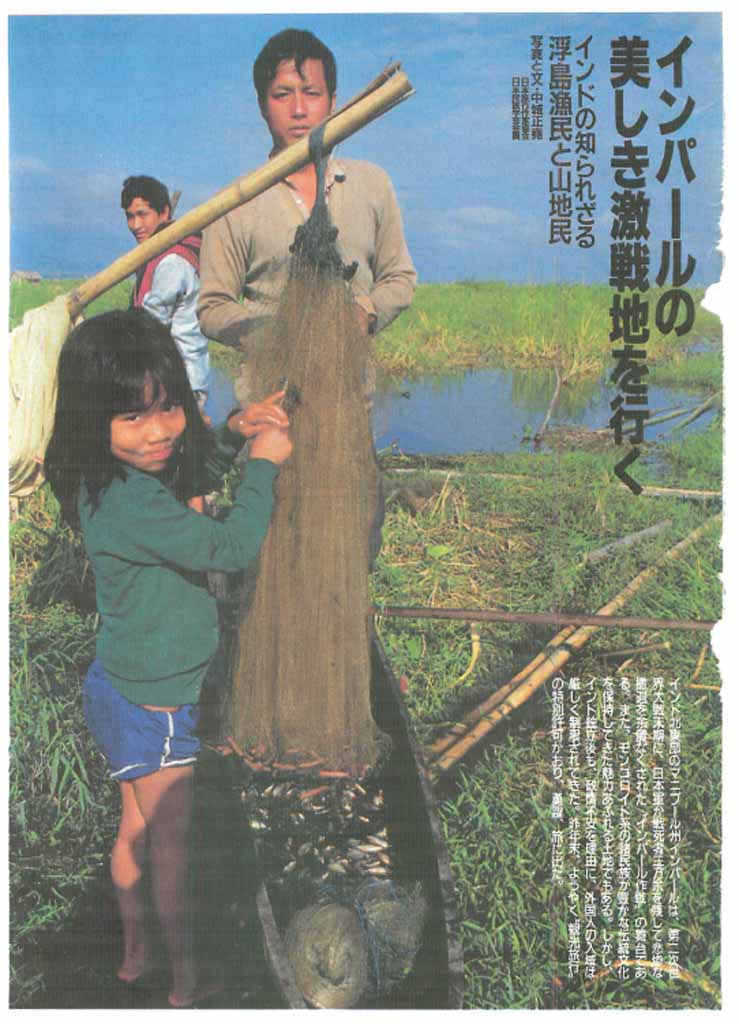 |
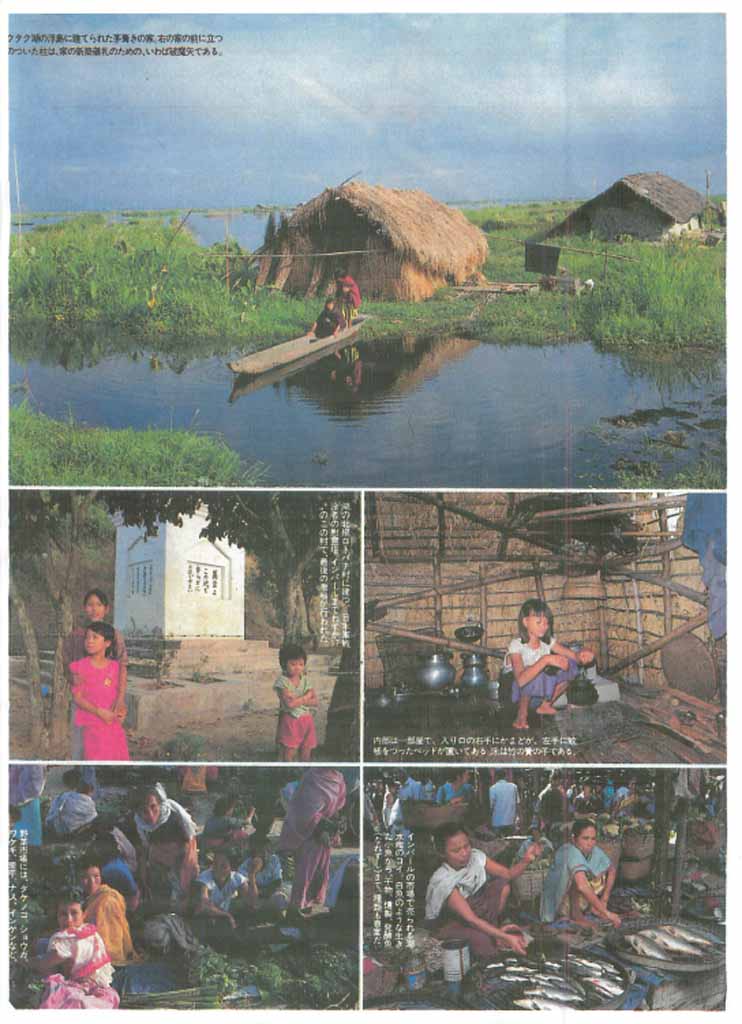 |
|---|---|
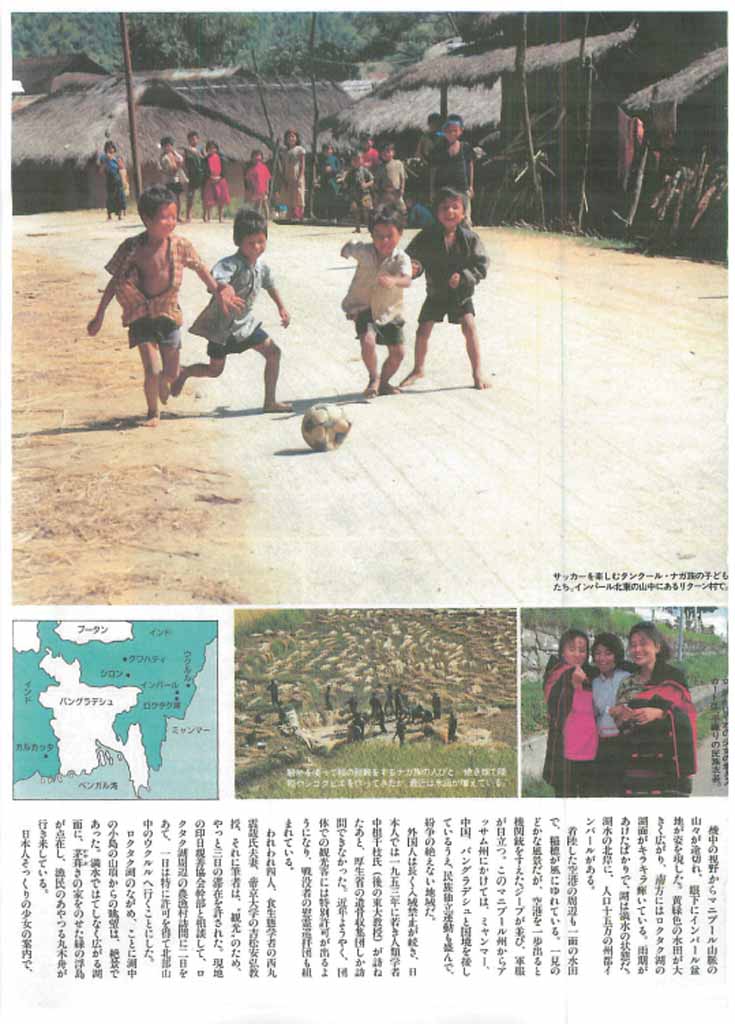 |
 |
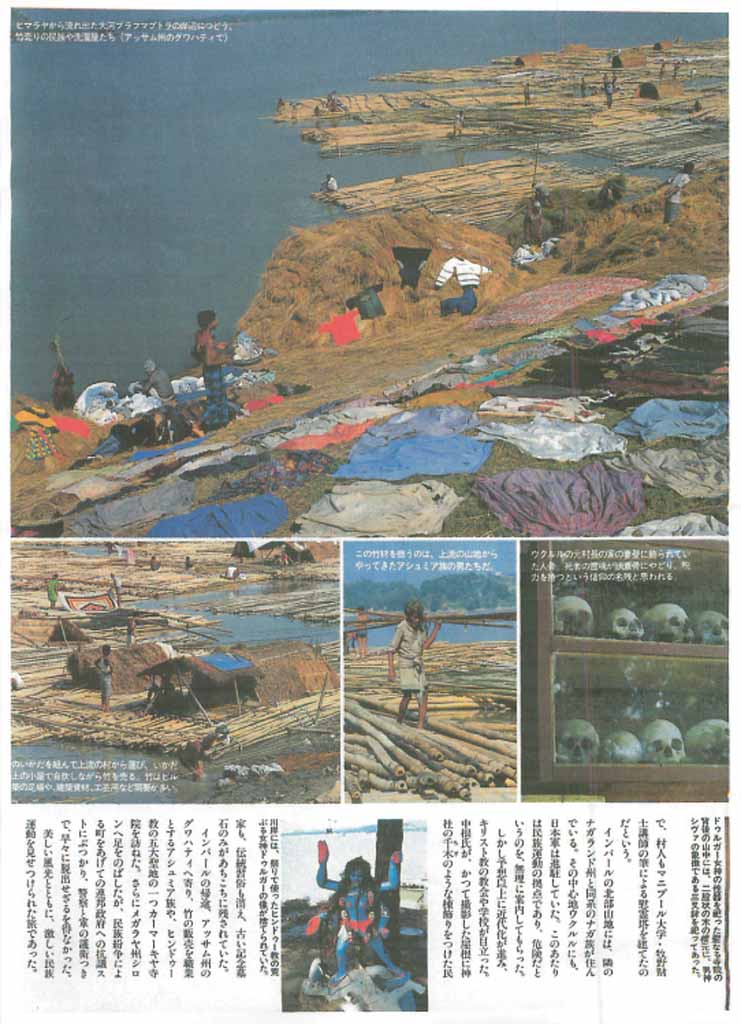 |
「ヨーロッパの木造建築」を楽しむ
中城正堯(30回) 2021.10.23
 筆者近影 |
|---|
 ルーマニア、マラムレシュ村の ルーマニア正教木造教会。 |
|---|
関さんの写真に興味があったのは、小生も学研の若き編集者時代に豪華写真集『日本の民家 全8巻』を担当し、文化庁建造物課の鈴木嘉吉さん(藤宗さんの大学先輩・後の奈良文化財研究所所長)にしごかれながら日本全国の重文民家を取材したからです。
これがキッカケでヨーロッパの木造建築にも興味を持ち、ルーマニア・ドイツ・スイスなどの木造民家や教会を訪ねました。要するに、伝統的な民家は土地に豊富にある建築資材を使って住居を建てており、アルプスなど森林地帯では木造家屋が多々見られ、日本と同様に炭焼き小屋もありました。
 木造教会の板壁に描かれた 村人への戒めの地獄絵。 作物泥棒や不倫人間が裁かれる。 |
 マラムレシュ村の 木造井戸小屋や穀物小屋。 |
 この村の民家。木彫をほどこした 立派な門と、板葺き屋根の母屋。 |
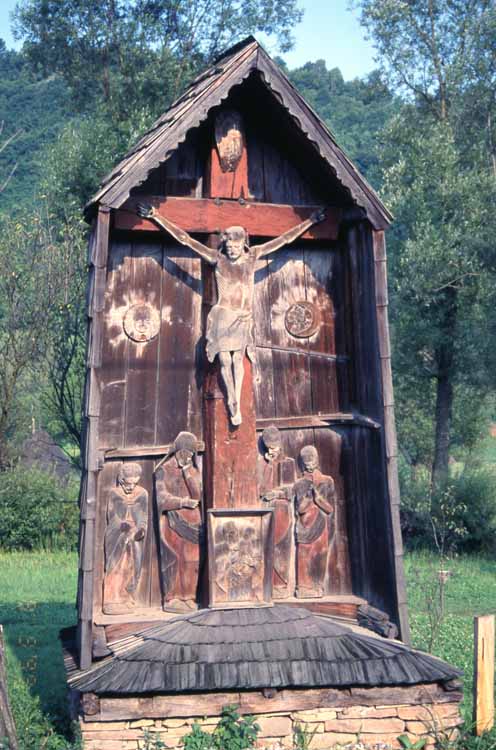 村の道ばたに立つ 木彫のキリスト像。 |
|---|
 ドイツ、ケルン郊外の民家園に 移築された茅葺き農家。壁は土壁。 |
 この土壁には、日本 の民家同様に木の 骨組みが入っている。 |
|---|
小生が撮影したヨーロッパの木造建築も、何点かお目に掛けます。まず、カルパチア山脈に近いルーマニア北部のマラムレシュ、次いでドイツのケルン郊外の民家園、そしてスイスの民家園で見かけたベルン州の山村農家です。
 スイスの民家園。ベルン州の山村農家。 左が住居、右は倉庫。屋根は板葺き。 |
 倉庫の屋根裏につるされた大量の 自家製ソーセージ。冬の保存食。 |
 ベルン州の18世紀末建築の大農家。 合掌作りを連想させられる切妻造りで、 大家族のほか農夫も同居、屋根裏は倉庫。 |
|---|
 四大天使(ロマネスク期) |
|---|
先生と呼ばれる程の……。ボソっとつぶやいたら、いつの間にか記事にされたので、あわてて確認しました(暇!)。左の画像はシチリアのチェファルー(Cefalu)の大聖堂の天井画で同じデザインの四大天使の画像ですので多分間違いないと思います。翼を持つ画像には、他に天子、四大福音者などがありよく間違えます。大天使の中で最も有名なのは受胎告知に登場するガブリエルです。ちなみに、天使、天子には性別はありません。
************************************************
藤宗さん
芸術の秋といいますが、お蔭様でこのところ見ごたえ読みごたえのある投稿が続いて目を離せません。
貴兄の大学写真部のご縁で目にすることができた、写真家?関健一さんの写真と記事「 カルパチア山脈の木造教会」はすごいですね。
中城さんご紹介の『APATANI STYLE』(榎並悦子氏)もそうですが、「プロだから当然」のを越えて、被写体に関わる民族・歴史・風俗文化への切込みが深いのに常人の及ばぬわざと感じ入りました。さすが貴兄のお仲間。
ヨーロッパの建築と聞いて石造りばかりを思い浮べてはだめで、木の建築は本家(らしき?)日本にひけをとらないことがよくわかります。歴史的建造物とはいえ、地域の風景と社会に溶け込んでいるのが写真から伺えてすばらしい。想えば、ドイツやオーストリアなども森林が豊かで、日本の林業、木造建築などの関係者が「先進国に学べ」と見学に行くといいます。
公文敏雄(35回)
-NHK「幕末・日本美術の至宝」を見て-
ナポレオン3世皇妃と幕末狩野派
中城正堯(30回) 2021.11.04
 筆者近影 |
|---|
皇妃ウージェニーの旧蔵品
 ナポレオン3世と皇妃ウージェニー (ホテル・デュ・パレ所蔵) |
|---|
 ホテル・デュ・パレの空撮全景 (同ホテル絵葉書より) |
|---|
 優雅なロビーで寛ぐ斎藤夫妻 (前列中央)、その左は筆者。 |
|---|
ビアリッツは、美しい海岸の景観だけでなく、新鮮な魚貝類の鉄板焼きやバスク風の肉料理も美味しく、バスクの民族衣装など独自のデザインや風俗も楽しめた。西に向かい、橋一つわたれば、スペインのサンセバスチャンで検問もなく自由に往き来できた。新発見の日本美術が、このホテルを生んだ皇妃の愛蔵品だったとは、実に意外な思いだった。
幕末狩野派の掛軸は日本の至宝か
 チュイルリー公園で遊ぶ小学生 遊びはコラン・マヤール。 |
|---|
 狩野房信の見事な 「佐野の渡図」 (NHK画面より) |
 狩野友信の「紅葉に青鳩図」 と、住吉弘貫の「山水画」 (NHK画面より) |
|---|
 中国、徽宋帝の「桃鳩図」 (『世界美術史』木村重信 朝日新聞社より) |
|---|
筆者は日本美術の素人だが、テレビ画面からの印象を述べよう。屏風は狩野派初期の狩野永徳「檜図屏風」の、金雲を背景に画面からはみ出す巨大な檜を描き、圧倒的な迫力で武家時代到来を象徴する作品群とは異なる。しかし、日本の王朝文化の雅な雰囲気を見事に表現している。一方、掛軸は将軍からの献上品らしく金箔をふんだんに使い、高価な顔料で色鮮やかに仕上げてあるが、その画面からは斬新な表現が感じられず、心に迫るものがない。先人の粉本模写に偏り、活力が失われ、また表装も西洋の宮殿にはそぐわない。
評価が高い暁斎・絵金・芳崖
それに引き替え、江戸時代に町民に好まれ、育てられた浮世絵師たちは、庶民が好んだ芝居役者や美人で評判の遊女・茶屋娘を、その生活空間とともに生き生きと描き、大人気を得た。独自の木版多色摺の技法を磨くとともに、次第に動植物や風景画にも画題を広げ、さらに西洋絵画の人体描法や遠近法も取り入れ、安価な庶民芸術を発達させた。フランス印象派の画家たちにも、大きな影響を与える。
無論、狩野派を学んだ絵師たちにも、中国絵画や狩野派先人の模写に飽き足らず、改革を志す絵師も現われた。辻惟雄(東大名誉教授)編『幕末・明治の画家たち』(ぺりかん社)の冒頭で紹介された三人の絵師、河鍋暁斎・絵金・狩野芳崖は、いずれも狩野派に学んでいる。暁斎は最初に浮世絵師・歌川国芳につくが、やがて狩野洞白に師事し、伝統的な狩野派の技法を身に付ける。辻によれば「粗野でいきいきとした時代の庶民の感情」を忠実に記録、「外国人にもてはやされた」とのべ、表現の活力と人間くささを高く評価している。
 赤岡絵金祭りのポスター (部分、絵は「蘆屋道満大内鑑 葛の葉子別れ」) |
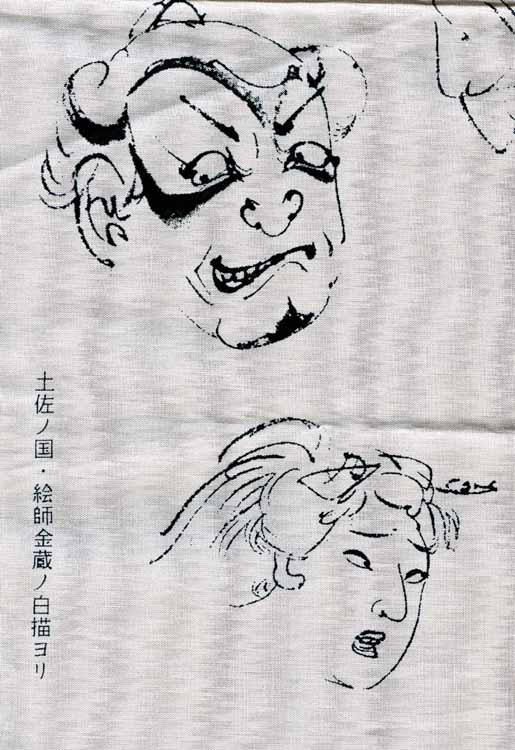 絵金の白描を印刷したハンカチ (部分、原画は吉川登志之所蔵) |
|---|
狩野芳崖はフェノロサに学び、西洋絵画の技法と狩野派の伝統的表現の折衷による明治日本画の改革をめざし「悲母観音」などの名作を残した。辻は、「東西美術のはざまに見出した安らぎの空間-静謐な象徴空間」を、高く評価している。
今回は、NHKが新発見「日本美術の至宝」の発掘調査を追い続け、見応えがあった。旧蔵者にも驚かされた。しかし、中国絵画に小手先の日本情緒を加え、きらびやかに飾り立てたに過ぎない作品への評価は、やや残念であった。
-知られざるインドネシア“もう一つの孤島”-
巨大な木造“王の家”そびえ立つニアス島
中城正堯(30回) 2021.11.26
 筆者近影 |
|---|
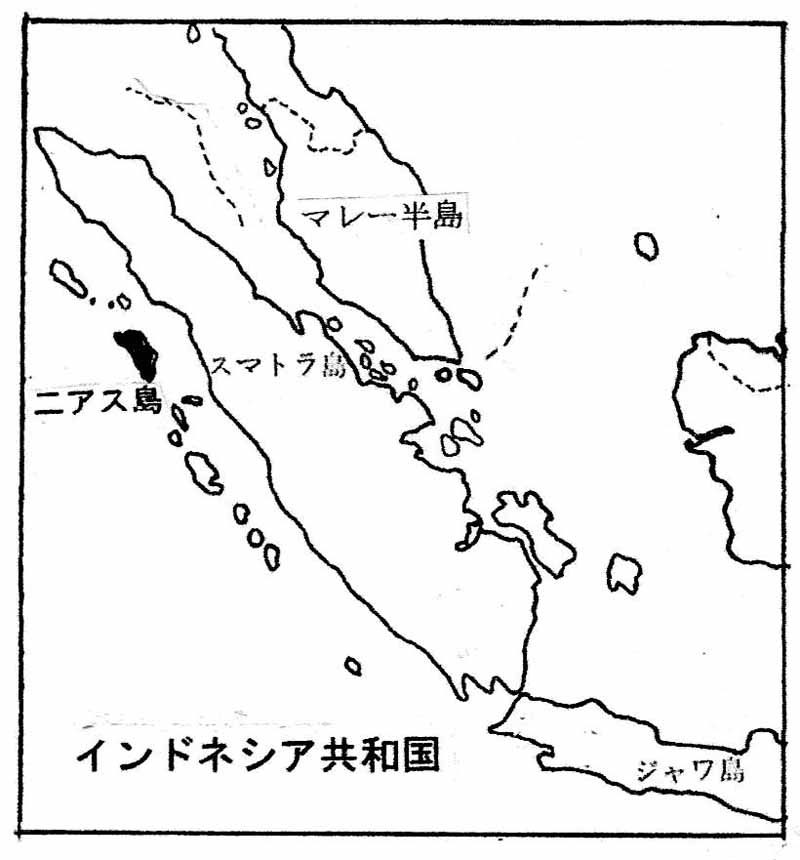 二アス島の位置図。 インドネシアの西端にある。 |
|---|
 大屋根・高床の王の家オモ・セプアの前で、槍と楯を手に踊る戦士。 |
 王の家の前に置かれたテーブル状の巨石。王の業績を称えて造られた勲功記念物。王の家屋を支える巨大な床柱も見事だ。 |
 テーブル状の巨石の浮彫り。人物が持つのは、嗜好品キンマ入れの袋と、砕く道具。 |
|---|
 王の家の部屋に飾られたブタの顎骨と、オランダの軍艦を描いた浮彫り。 |
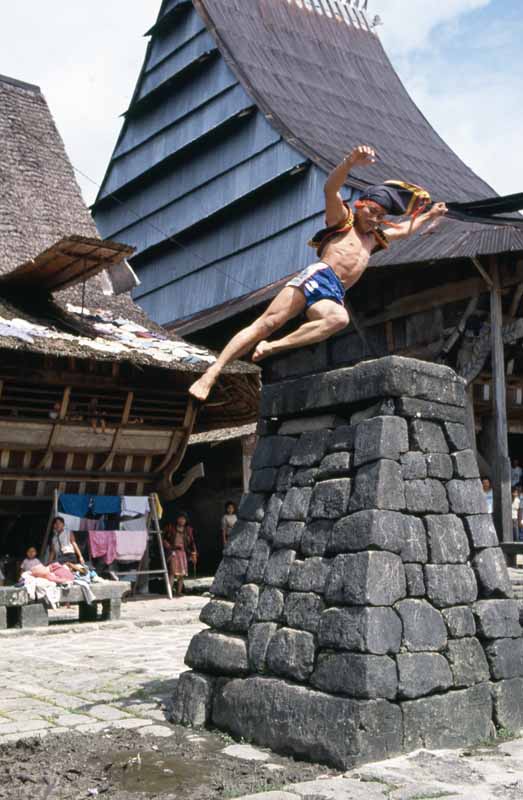 成人式の石飛び。 2メートルの石積み跳躍台を飛び越せないと、男として認められない。 |
 王の家の軒先正面に飾られた守護神ラサラ。古代中国南部の聖獣「辟邪(へきじゃ)」と類似している。 |
|---|
 守護神ラサラは、村の入口の 石造階段にも刻まれている。 背後には、戦士の槍と楯。 |
 村はずれの貴族の土葬新墓にも、 ラサラ像を祀ってあった。 |
|---|
では、島の魅力的な建築文化・巨石文化・浮き彫りといった伝統的な美術様式や、魔除けのシンボルなどを見ていただこう。バンダ諸島では、旅の半ばで初めての痛風を発病、右足の指に激痛が走って満足に歩けず、取材・撮影も途中であきらめたが、二アス島ではなんとかその見事な民族文化に迫ることが出来た。
 敷石の広場に立つ正装の女性。背後の左右に、大屋根・高床の木造家屋が整然と並ぶ。屋根は、ヤシの葉で葺いてある。 |
 広場は儀礼の場であり、農作物加工の作業場、そして子どもの遊び場でもある。女の子が騎馬戦のような遊びをしていた。 |
 ハイネゲルデンが同一の美術様式というトラジャ族の舟形住居。屋根の前後は船の舳先を模ったとされる。正面は水牛と鳥の頭部が守護し、朱色と白黒の幾何模様で装飾されていた。(写真は全て筆者撮影) |
|---|
<参考文献>
『東南アジア・太平洋の美術』R・ハイネゲルデン、M・バードナー著 弘文堂 1878年
『巨石人像を追って』木村重信著 日本放送協会 1986年
『民族探検の旅 第2集東南アジア』梅棹忠夫監修 学習研究社 1977年
お龍さんの実像に写真と史料で迫る
―“生意気な女”か“近代女性の先駆け”か―
中城正堯(30回) 2021.12.15
 お龍の墓にお参りする筆者。 横須賀市信楽寺で。 |
|---|
坂本龍馬も、その妻“おりょう”(お龍、お良)も、相変わらずテレビの人気者で、よく取り上げられる。先月(2021年11月)も、4日にNHK BSP 「ザ・プロファイラー」が「坂本龍馬の妻 お龍」をその流転の日々中心に「おもしろき女」として取り上げ、11日にBS11イレブン「偉人 素顔の履歴書」が「幕末を駆け抜けたヒーロー 坂本龍馬」を、その思想形成を軸に紹介していた。しかし、その内容は相変わらずで、ともに重要な視点を見落とし、また新史料の発掘活用も見られなかった。
ここでは、まずNHK「坂本龍馬の妻 お龍」の問題点を指摘しておきたい。この番組は、タイトルのみならず内容も、鈴木かほる著『史料が語る 坂本龍馬の妻 お龍』(新人物往来社 2007年)をほぼなぞったものだった。しかし、高知県和食村(わじき・現芸西村)千屋家や、横浜市の料亭田中家の時代にはあまり触れてなく、見るべき新史料もなかった。
確かに鈴木のこの本は史料をよく調査し、執筆・収集してある。しかし、NHKはこの旧著に寄りかかりすぎで、その検証や追加取材への意欲が感じられない。特にお龍の写真が問題で、相変わらず芸妓風の媚びを売るような写真を、異論があると断わりながらも、再三大きく登場させていた。鈴木自身が著書でこの写真に触れ、東京浅草・内田九一堂写真館の撮影であるが、京都国立博物館博・宮川禎一などの研究からも、真影とはほど遠いと述べている。まともな図書・番組では使わない写真である。
お龍さんの面影伝える二枚の写真
では、真実のお龍を伝える写真を二枚紹介しよう。まず、鈴木が著書に「たった一枚の真影」として掲載した晩年64歳の写真である。明治27年『東京二六新聞』の連載記事「阪本龍馬未亡人龍子」の第一回に添えられたもので、だれもが晩年のお龍と認めている。なお、この記事や横須賀市大津・信楽寺にある「阪本龍馬之妻龍子之墓」でも、「坂本」「阪本」は、混用されてきた。この墓石は、お龍(長女)の妹・起美(三女)が皇后からの龍馬への下賜金で大正3年に立てたが、背後には土佐出身の宮内大臣・田中光顕の働きがあった。
もう一枚は、龍馬と死別後にお龍が土佐・京都・東京を経て一時仲居として働いていた横浜駅に近い旧神奈川宿・料亭田中家時代の写真だ。しかし、なぜかこの写真はほとんど知られていない。筆者は、漫画『坂本龍馬』の作者・黒鉄ヒロシ(41回生)さんから数年前にコピーをいただいた。最近、田中家五代目の女将平塚あけみさんに確認の電話をすると、こう説明してくれた。
「この写真は、田中家にお龍さんがいた明治7年、大森海岸に従業員旅行で行った際に撮ったものです。お龍さんは、うちの制服は着ないでこんな着物で通し、目立つ存在でした。うちの仲居時代の写真に間違いありません」
 お龍の真影。明治27年、64歳、東京二六新聞掲載。『坂本龍馬全集』より。 |
 横浜の料亭田中家に埋もれていた写真。明治7年、44歳、田中家蔵。 |
 若き日のお龍とされてきた“ニセ写真”。明治6~8年頃、東京内田九一堂撮影。 |
|---|
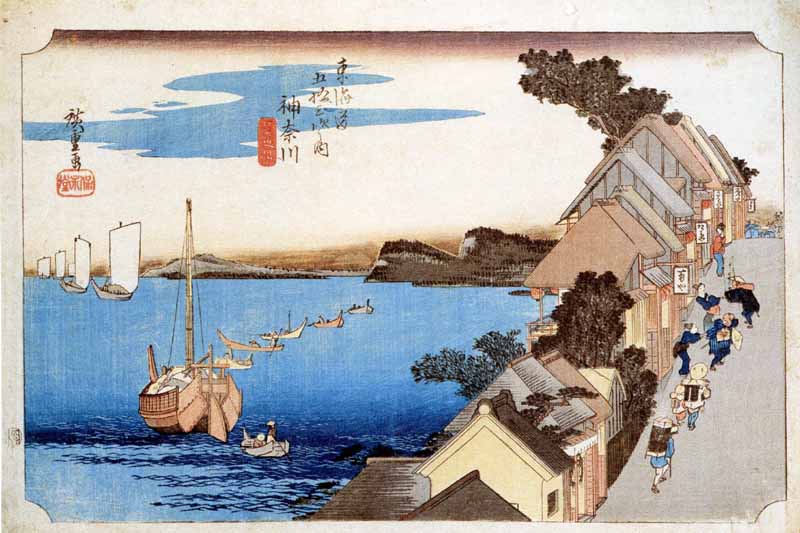 「東海道五拾三次之内 神奈川 台之景」歌川広重画 天保4年 川崎・砂子の里美術館蔵 『横浜錦絵 図録』より。 |
|---|
この仲居時代に、かつて京都の寺田屋の泊まり客で、旧知の西村松兵衛と再会、やがて妹光枝(次女)・海軍兵曹中沢助蔵夫妻が住む神奈川県三浦郡大津村(現横須賀市大津町)で同居する。明治8年7月に西村に入籍し、西村鶴(ツル)となって三浦郡豊島村に住み、再婚後も横浜田中家での仲居はしばらく続けたという。これらの経緯は、神奈川新聞刊『よみがえる老舗料亭田中家』に記されている。鈴木の著書にも、「神奈川の料亭」として、田中家での仲居時代が紹介されているが、文献からの記述のみで、仲居時代の写真には全く触れてない。NHKでも肖像写真取材の努力をせず、ニセ写真ですませている。
なお、鈴木からはこの著書出版前に取材依頼があった。当時、筆者は大病で一月半の入院生活を経てやっと退院したばかりで、とても史料を準備して対応出来る状態ではなかった。お龍と筆者の祖母・中城仲の交流を説明出来ず、残念だった。
お龍の武勇伝ばかり紹介
写真に続いて番組で気になったのは、お龍の人物像のとらえ方である。相変わらず、お龍の母がだまされて妹二人が遊郭などへ売り飛ばされようとした際、金を工面したお龍が単身乗り込んで男たちから妹を救った武勇伝。さらに寺田屋で入浴中に、伏見奉行配下の襲来を察知、袷一枚引っかけただけで階段を駆け上って龍馬の命を危機一髪で救った寺田屋事件。その後、西郷の世話による傷治療を兼ねた薩摩への新婚旅行で、神話にもとづく「天の逆鉾」を引っこ抜いて笑い飛ばしたエピソード。そして、ピストルを好んだことなどから、相変わらず“無鉄砲な女”の印象ばかりを強調している。
龍馬は、乙女への手紙で「まことにおもしろい女」と紹介、思うまま自由に発言・行動する個性的なお龍の人間性に惹かれたのであろう。だが、裁縫、料理などは得意でなく、良妻賢母・夫唱婦随を理想とする海援隊の若者はじめ龍馬の同志たちからも理解されず、“生意気な女”として嫌われたと伝わる。同志だった佐々木高行は、維新後に侯爵になったが、回顧談に「龍馬夫人は美人で有名だが、賢夫人かどうか知らない。善悪ともに為しかねないようだ」と記している。当時の男性の、一般的な女性観からの発言である。だが、現在も女性活動家へのこのような視線は、まだまだ残っているようだ。
番組では自由な発言と行動をするお龍を、もっぱら“生意気な女”としてとらえ、時代に先駆けた近代的女性としての存在にはほとんど触れてない。お龍の優しさや近代的な女性ぶりは、龍馬亡き後の高知在住時代でも、横浜の料亭田中家時代でも発揮され、鮮烈な記憶が残されているが取り上げてない。
お龍は龍馬の遺言で身を寄せた坂本家と不仲になり、実妹・起美のいた和食村の千屋家(起美の夫・菅野覚兵衛の実家)に転居する。その原因を、坂本家一族の弘松宣枝は著書『坂本龍馬』(明治29年 民友社)で、「彼の女、放恣にして土佐を出て、身を淫猥に沈む。乙女怒て彼の女を離姻す」と断じ、この説が広まる。しかし、全く別の思い出話も残っている。まず坂本家での様子を、龍馬の姉・乙女の長女・岡上菊枝は、幼い頃「母(乙女)はお龍さんが来ると、得意の一絃琴を教え・・・、お龍さんもとても優しい人で、母には姉さん姉さんとしきりに親しみ、うやまっていました」(貴司山治「妻お龍その後」『歴史読本』昭和42年1月号)。お龍自身も、「姉さんは親切にしてくれました。土佐を出るとき、船まで見送ってくれました」(「千里駒後日談」川田雪山聞書『土陽新聞』明治32年)と述べている。
洋書を抱える「高知城下のお龍」
 「高知城下のお龍」藤原信一画 『土陽新聞』明治16年8月30日高知県立図書館蔵。 |
|---|
高知時代のお龍の写真は見当たらないが、そのモダンな風貌を見事に描いた新聞連載「汗血千里駒」の挿絵が残されている。「高知城下のお龍」(藤原信一画『土陽新聞』明治16年8月30日)で、右手に洋傘、左手に洋書、腰にピストル、面立ちのきりっとした知的女性である。背後には、高知城天守もそびえている。この洋書だけは、お龍に似合わないと思っていたが、田中家・平塚女将の「英語もはなせた」をお聞きして納得した。高知でも、龍馬にもらった英会話入門書を持っていたのではないだろうか。龍馬と海援隊士はいち早く英語の習得に取り組み、『和英通韻伊呂波便覧』の編纂にも着手、龍馬亡き後の慶応4年に土佐海援隊蔵版で刊行される。さらに、明治2年には『いろは丸沈没事件』で紀州藩から得た賠償金を使い、海援隊幹部だった菅野覚兵衛は新妻を置いて、白峰駿馬とアメリカに留学する。ニュージャージー州立ラトガース大学で造船学を学ぶが、この留学にお龍を加え、龍馬との渡米という夢の一端を実現させてやりたかった。
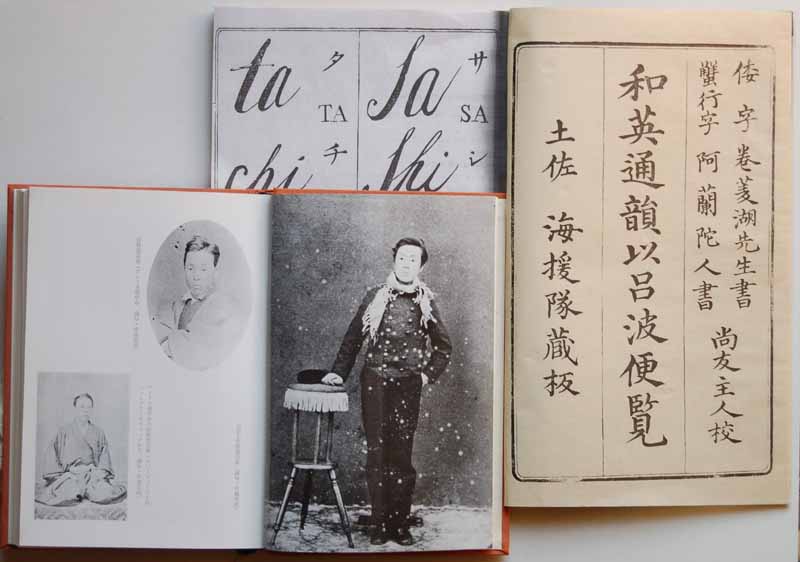 海援隊蔵版『和英通韻伊呂波便覧』(複刻版)と、 留学中の菅野(『ある海援隊士の生涯』口絵)。筆者蔵。 |
|---|
 中城仲が、お龍からもらった帯留。留具は龍馬の刀の目貫から。NHK『龍馬伝』図録より。 |
|---|
お龍の近代性に気付かぬマスコミ
 千屋家に来た菅野起美 (お龍の妹)高知市民図書館 『中城文庫』蔵。 |
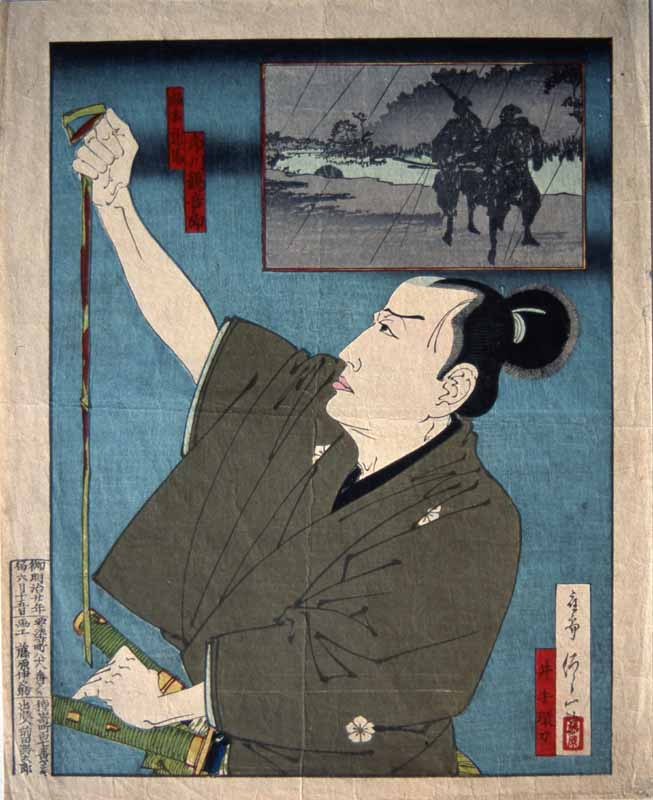 「坂本龍馬役者絵」明治20年高知座上演 高知城歴史博物館蔵(筆者より寄贈)。 |
|---|
お龍に直接接した高知坂本家や千屋家の女性の証言には注目せず、当時の封建的な男尊女卑の未亡人観を、いまだに脱皮できないのだ。龍馬暗殺を下関にいて知ったお龍へ、長府毛利家は扶助米を支給したが、土佐では坂本家への士族家禄だった。明治4年、明治政府太政官から高知県宛に、
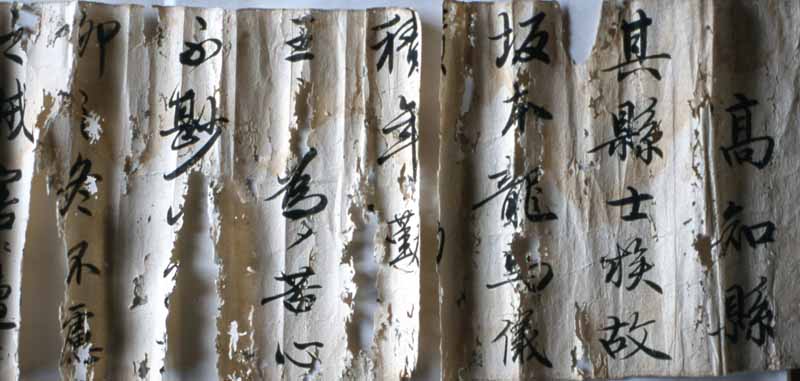 明治4年、政府太政官より小野淳輔を 坂本家継嗣とする通達の書き出し。『中城文庫』蔵。 |
|---|
三浦夏樹・高知県立龍馬記念館学芸担当は、坂本家の当主権平(龍馬の兄)の立場を、「土佐では天保期に奉行所が出した通達に、結婚は身分の低い者でも双方の親が納得した縁組みで、庄屋に届け出がないと認めないとの項目があった。権平は、当人同士で決めて乙女に知らせただけの、この型破りな結婚を認めたくなかったのでは」と、述べている。
 武市半平太の妻・冨、88歳。 大正6年逝去の3ヶ月前。『中城文庫』蔵。 |
|---|
明治の伝記作者は男性ばかりで、女性からの目で見た記録はほとんど伝わらない。その習わしが、現在の研究者・作家にも残存している。田中家の女将が、「お龍は当家の恩人。この写真がお龍本人」と言っても、証拠がないとして取り上げられない。貴重な史料が、調査も評価もされずに埋もれたままだ。幕末・明治の先駆的女性が自己主張をしながら、生きていくのは大変困難だった。現在それらの女性の生き方を実証するのにも、同様な困難が続いている。これが、最後の帰高で潜伏した龍馬を世話した女性や、お龍に遊んでもらった女性が語り継ぐ、龍馬・お龍の姿を聞いて育った筆者の実感である。
 慶應3年9月、龍馬が最後の帰郷で潜伏した中城家 「離れ」座敷。筆者撮影。 |
|---|
田中家でいえば、幕末からの横浜発展とともに歴史を刻んできた史跡であり、神奈川県立歴史博物館や、地元研究機関、マスコミが協力して、きちんと調査すべきであろう。
<参考文献>
宮地佐一郎編『坂本龍馬全集』光風社出版 増補三訂版 1980年
佐藤寿良『ある海援隊士の生涯』-菅野覚兵衛- 私家版 1984年
鈴木かほる『史料が語る 坂本龍馬の妻 お龍』新人物往来社 2007年
中城正堯『龍馬・元親に土佐人の原点をみる』高知新聞総合印刷 2017年
続「お龍さんの実像に写真と史料で迫る」
―写真と挿絵が語りかけるもの―
中城正堯(30回) 2022.02.22
 お龍の墓にお参りする筆者。 横須賀市信楽寺で。 |
|---|
ひときわ目立つ凜とした容姿
まず、前回紹介した横浜の料亭田中家時代の人物写真につき、平塚あけみ女将にその写真全景の提供を受け、内容についてもいくつかお尋ねして回答を得た。その写真からご覧いただきたい。
 1.田中家の従業員集合写真 |
|---|
 2.集合写真のお龍 |
|---|
では、この写真が明治7年頃の撮影と推定できるだろうか。人物の風俗に注目すると、男性はすでにすべて総髪かザンギリ頭である。ハンティングなど帽子姿も目立つ。明治4年に断髪令が出され、明治6年に天皇も断髪、一気にチョンマゲは消え、髷のない頭を寂しがって帽子を被る人が増えたという。さらに明るい色調の日傘“パラソル”も見える。幕末から英国商人によって洋傘の輸入が始まっているものの貴重品で、国産洋傘が誕生し、庶民にも普及し始めるのは明治16年鹿鳴館時代になってからだ。写真が明治7年撮影とすると、この持ち主は田中家の女将かお龍くらいだろう。明治7年頃に、100人もの従業員を抱える大旅館兼料亭になっていたのかや、幟の文字のさらなる解読も必要だ。
この大団体を受入れた施設は大森海岸のどこで、名称は何というかも確認したい。大森海岸がよく知られるのは、明治10年のモースによる大森貝塚発見だ。今後、品川区立品川歴史博物館はじめ、現地での調査も欠かせない。なお品川は、龍馬が剣術修業のため初めて江戸に出た際、黒船来航で品川台場建設に動員され、黒船に目覚めた土地である。
「田中家」繁昌支えたお龍の英語
 3.『金川砂子』に描かれた「さくらや」 |
|---|
神奈川宿が明治になって変貌する様子は、前回紹介した歌川広重「東海道五拾三次之内 神奈川 台之景」と、ほぼ同じアングルで描いた歌川国輝二代「神奈川蒸気車鉄道之全図」(部分 明治3年 川崎・砂子の里資料館蔵)にある。新橋からの鉄道が出来るのは明治5年だが、錦絵ではすでに走っている。この頃、神奈川宿の海辺でも埋め立てが始まる。ペリー上陸で知られる横浜村の浜辺では、安政5(1858)年の日米修好通商条約によって埋め立てによる居留地建設が始まっていた。幕末に「さくらや」は高島嘉右衛門(高島易断の創始者)が買い取り、旅籠「下田屋」になっていたが、それを晝間弥兵衛が買い受け、旅籠料理屋「田中家」となる。幕末から明治にかけて、この旅籠には江戸へ向かう西郷隆盛・高杉晋作・伊藤博文なども立ち寄ったとされる。
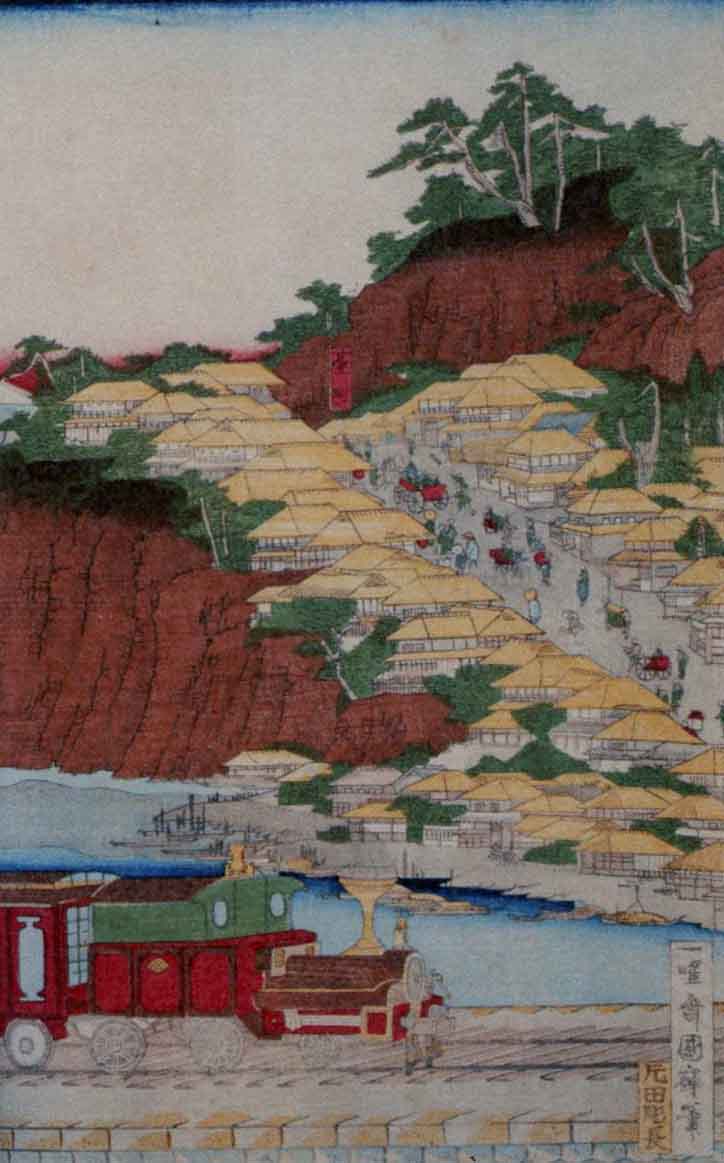 4.「神奈川蒸気車鉄道之全図」部分 |
 5.「増補再刻御開港横浜之全図」部分 左上部:横浜居留地、右:岬のあたりが神奈川宿 |
|---|
その後も、田中家は貿易港横浜とともに発展を続ける。特に明治29年に二代目当主となった晝間駒之助による和洋折衷料理や椅子席・英会話などが好評で、大正7年刊『横浜社会辞彙』には、料亭として唯一「田中家 青木町にあり名古家・丁子家と鼎立せる著名なる料理店にして、粋人間に知らるる主人(二代女将)を晝間ヌイ子という」とある。田中家の地名は、神奈川宿から横浜市神奈川区青木町、さらに同区台町となる。幕末以来の埋め立てで、周辺の山が削除され、地形・眺望も変貌するなか、関東大震災も乗り越え、昭和初期には3階建ての壮大な料亭に改築する。ただ、明治初期の従業員数は不明だ。
神奈川宿周辺が開港で横浜に大変貌する様子は、明治の横浜浮世絵に詳細に描かれている。その一つ「増補再刻御開港横浜之全図」(歌川貞秀 慶応2年)の、画面右は東海道神奈川宿(半島のあたり)、左上部は埋立て地にできた横浜居留地である。
洋書を持つお龍を読み解く
 6.挿絵「高知城下のお龍」 |
|---|
「・・・お龍はロンドン製の(なんと傘骨の中心部にローマ字でそう記されています)のパラソルをさしています。長崎で龍馬に買ってもらったものでしょうか。・・・袴の紐にはピストルを挿して、左手には洋書を抱えています」。
そして、龍馬の死を聞いたお龍は髪を自ら切ったが、その事情を知らないまま絵師は短髪で表現しており、これは高知の人々が鮮明に記憶していた姿で、絵の信頼性の高さを示すとする。なぜ洋書を抱えているかは、龍馬が乙女・おやべ宛の手紙で、「妻には時間があるようなら[本を読め]ともうしきかせています」とあることから、「左手の洋書は龍馬のいいつけを守っていると言うことなのでしょうか」と、推測している。
お龍の持つパラソルの中心部を確認すると、逆さ文字になっているが確かに〈LONDON〉の文字が読み取れる。パラソルは、田中家の集合写真にも登場しており、不思議な繋がりだ。龍馬は、慶応3年に最後の帰郷をした際には、川島家・中城家の女性に、〈PARIS〉の文字が入ったコンパクトを土産に渡しており、現物は見当たらないものの図面が『村のことども』(三里尋常高等小学校 昭和7年)に掲載してある。龍馬は世話になった女性に珍しい舶来品を贈っており、妻にはパラソルも与えたのだろう。左手で抱えた英国上製本の洋書も、腰のピストル(龍馬旧蔵品でスミス&ウエッソン製)も精密に描写してある。
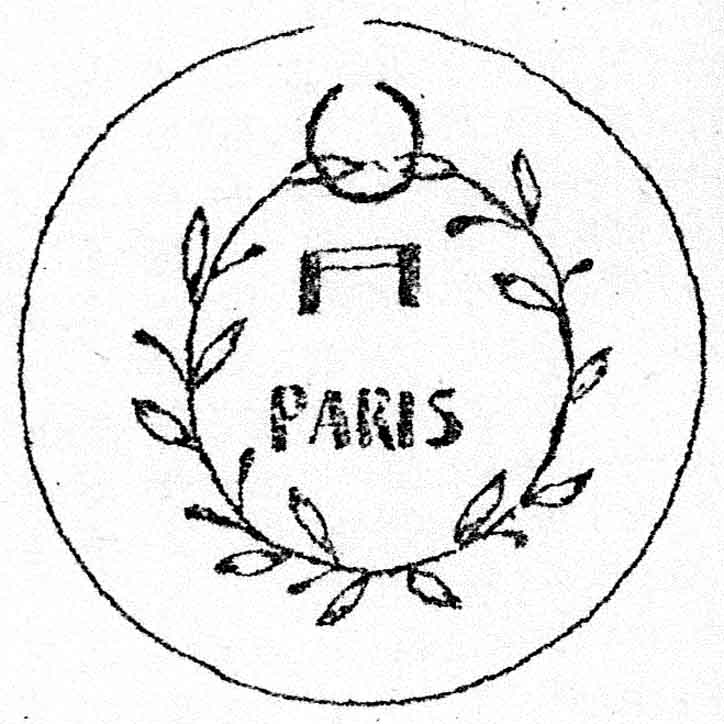 7.龍馬土産のコンパクト |
 8.龍馬旧蔵のピストル(複製) |
|---|
さらに、龍馬・お龍夫妻がともにこれらの英国製舶来品や英語に親しんだのは、おもに慶応2年6月から翌年2月までの8ヶ月間、長崎の豪商・小曽根英四郎宅に身を寄せた際と思われる。当時、龍馬は亀山社中を土佐藩の海援隊に発展させ、小曽根家にその事務所をおき、グラバーやオールトなどの英国貿易商と頻繁に交渉、船舶や武器の購入に当っていた。このため英語は欠かせず、「海援隊約規」5カ条の一つに隊員の修業すべき科目として「政法、火技、航海、汽機、語学」をあげてある。語学は、オランダ語でなく英語であり、そのために前回紹介した英語入門書『和英通韻伊呂波便覧』の編纂にも着手していた。
この長崎時代に、お龍は中国楽器の月琴を教わり、後に田中家でも客に披露して喜ばれたという。仲居名はツルを名乗ったが、これはグラバー夫人ツルから取ったという。おそらく、長崎時代に英語もある程度学び、龍馬とともに外国人に接することもあったと思われる。長崎での経験が、後に田中家での外国人接遇にも生きたのであろう。
なお、幕末維新期の高知は、米国帰りのジョン万次郎やフランス帰りの中江兆民のみならず、五台山吸江病院に招いた西洋人医師や帰国留学生などの活躍、立志学舎の設立もあって、自由民権思想のみならず洋学や英語教育でも先進県の一つであった。
お龍の人物像探求のさらなる課題
 9.坂本龍馬と海援隊士、中央龍馬、一人置いて右へ菅野・白峰 |
|---|
振り返れば江戸時代、女性には「三従の教え」(家にあっては父に従い、嫁しては夫に従い、夫亡き後は子に従い)が強調された。現実には、商家の女性は家事だけでなく店頭にも立って家業を支え、文芸音曲にも親しんだが、独立した人格など認められなかった。明治になっても、おしとやかな良妻賢母が理想とされた。お龍は医師の家に生まれたが、父を早く亡くし、充分な教育を受けないまま母子での自活を強いられた。龍馬は、この封建的な女性観にとらわれない「面白き女」を愛したのである。
龍馬を失ったお龍は、東京に出たもののどこからも援助がなく、再婚した西村も没落、酒に溺れたのも事実だ。しかし調査を重ねると、龍馬と出会って以来、死別・再婚までの生き方は、いわゆる優等生ではないが“近代女性の先駆け”というべき姿が強く感じられる。徒手空拳の身で、幕末維新の世に夢を懐いて駆け抜け、素晴らしい出会いと挫折を味わった女性だ。ただ実証的な史料が少なく、コロナ禍もあって関係先や歴史博物館へ出向いての取材調査も困難で、自宅・図書館の蔵書と通信手段のみが頼りだった。その中間報告である。ぜひ、若き研究者がこの人物研究に挑戦することを期待したい。
<付記>幕末・明治の横浜と土佐
お龍が田中家で働いた明治初期には、横浜開港で大発展をとげる横浜で土佐の人々も大きな貢献をしていた。その一端を付記しておきたい
*後藤象二郎 明治2年に横浜の下岡蓮杖が「成駒屋」を設立して東京と結ぶ鉄道馬車を始める際、後藤にも資金援助を仰いだと伝わる。鉄道馬車は鉄道開通の明治5年まで賑わう。
*山内侯爵家 横浜市神奈川区の山内町には、現在横浜市中央卸売市場があり、神奈川県民の台所をまかなっている。この町名は、明治2年に旧土佐藩主山内侯爵が認可を得て埋め立てを始めたことに由来する。
*白峰駿馬 越後生まれだが、勝海舟の神戸海軍操練所を経て海援隊幹部となり、維新後は菅野覚兵衛とともに渡米、ラトガ-ス大で造船学を学び、卒業後もニューヨーク海軍造船所で造船技術を習得して帰国。海軍省に勤務後、明治10年、神奈川区青木町に民間では日本初の西洋船専門の白峰造船所を設立。三菱・岩崎弥太郎の船舶修理も担当する。
<参考文献>『区政施行50周年記念神奈川区誌』編集発行・同誌編さん刊行委員会 昭和52年/『東海道と神奈川宿』横浜市歴史博物館 1996年/『よみがえった老舗料亭』編集発行・神奈川新聞社 2006年/『幕末・明治の写真』小沢健志 筑摩書房 1997年/『横浜浮世絵』川崎・砂子の里資料館 2009年
<図版出典>1.「田中家の従業員集合写真」田中家 2.「集合写真のお龍」田中家 3.『金川砂子』横浜市歴史博物館刊『東海道と神奈川宿』 4.「神奈川蒸気車鉄道之全図」川崎・砂子の里資料館刊『横浜浮世絵』 5.「増補再刻御開港横浜之全図」横浜市歴史博物館刊『東海道と神奈川宿』 6.「高知城下のお龍」高知県立図書館蔵 7.「龍馬土産のコンパクト」三里尋常高等小学校刊『村のことども』 8.「龍馬旧蔵のピストル」NHK刊『龍馬伝』図録 高知県立坂本龍馬記念館蔵 9.「龍馬と海援隊士」平尾道雄著 白竜社刊『坂本龍馬 海援隊始末記』
<訂正>前回の原稿で、導入部分の鈴木かほる著書からの引用「京都国立博物館・宮川禎一」は「京都・霊山歴史館・木村幸比古」に、また『お龍の写真』キャプション「明治7年、44歳、田中家蔵」は「明治7年、34歳、田中家蔵」に、お詫びして訂正致します。
<同窓生アーティストの近況>
中城正堯(30回) 2022.05.15
 筆者近影 |
|---|
田島征彦さんが沖縄戦の絵本
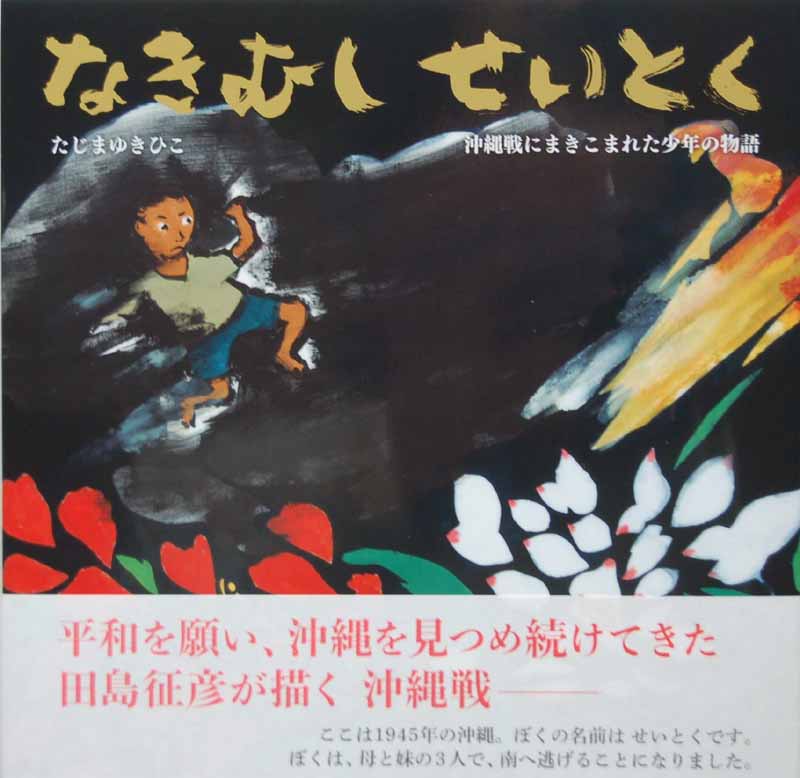 『なきむし せいとく』の表紙 |
|---|
筆者のような高知大空襲を知る世代は、空襲・艦砲射撃の場面からあの日の恐怖がよみがえり、大きなガマ(洞窟)に逃げ込んだ村人の姿から、ウクライナ戦争で製鉄所地下室にこもってロシア軍の卑劣な攻撃にさらされる現代の戦場を思い浮かべます。悲惨な戦場も、作者は穏やかな色調と柔らかいタッチで描いてあり、本を閉じたあとに現実の恐ろしい場面がじわっと胸に響きます。子どもや孫たちとともに、今に続く戦争を考える「現代の戦争絵本」です。(定価税込 1.760円)
 空襲と艦砲射撃から逃げまどう村人 |
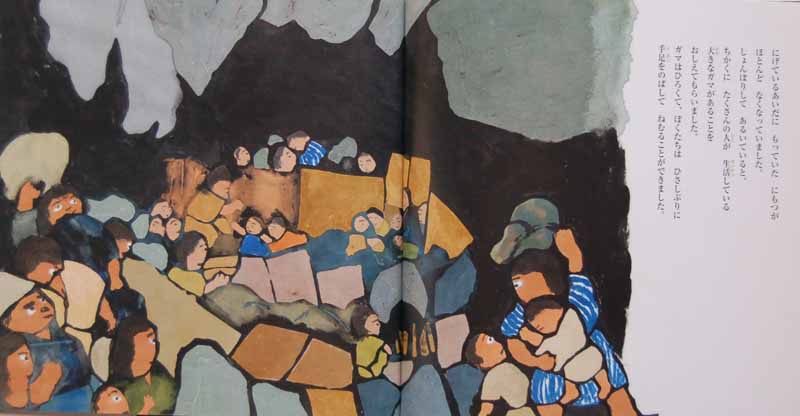 大きなガマに逃げ込んで、しばし安堵の人々 |
|---|
「合田佐和子展」を高知と三鷹で開催
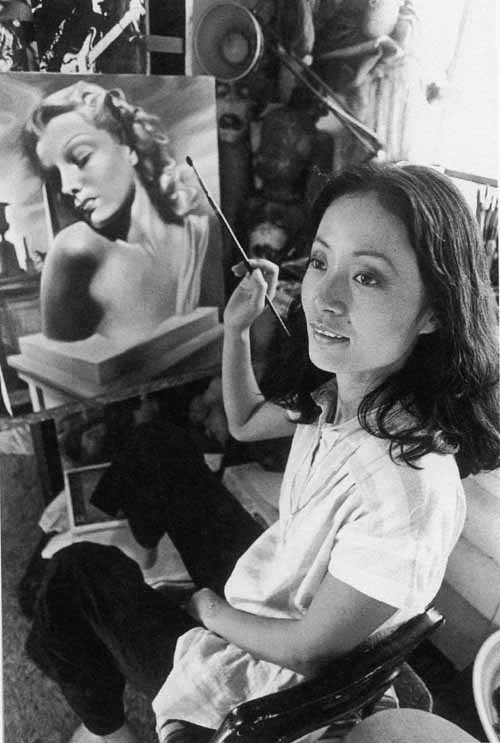 合田佐和子さん (『筆山の麓』より) |
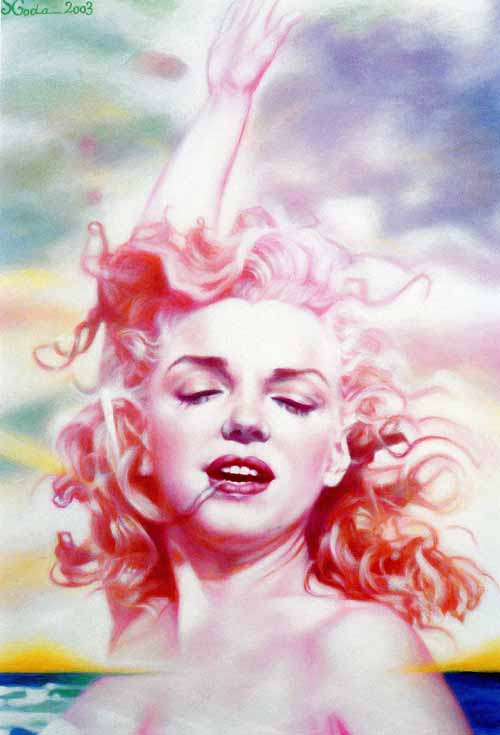 油彩画「マリリンの海」 (『合田佐和子 影像』より) |
|---|
パリ日本文化会館から
「文明開化の子どもたち」展
中城正堯(30回) 2022.07.05
 筆者近影 |
|---|
皆様へ
パリ日本文化会館から、「文明開化の子どもたち」展の報告書が届きましたので、ご参考までにその一部を添付します。コロナ禍下でしたが、40日で6.784人の入場者があったとのことで、そのアンケートの一端と、会場風景です。以下のメールは、この展覧会の責任者とのやりとりです。
お世話になっております。報告書と日本語抜き刷りが無事お手元に届いたとのこと、ご連絡をありがとうございました。温かいコメントも頂き、恐縮の限りです。
日本語版抜き刷りは当地での成果を日本の方に還元するという意味でも重要であると考え、完成は事後となってしまいましたが作成をいたしました。
展覧会を御覧頂いたお客様やメディアからは軒並み良い評価を得て、当地のお客様に「明治の子ども浮世絵」を知って頂く素晴らしい機会になり、当館としても誇りに思っております。先生のご研究があってこそのことであり、心から敬意と感謝を表明申し上げます。
日本は暑い日々が続いているのではないかと存じます。どうぞご自愛ください。
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
パリ日本文化会館 大角友子
昨日、報告書並びに日本語版抜刷りを拝受しました。パリ文化会館のご丁寧な対応に、いつもながら感謝申し上げます。特に、日本語版抜刷りは執筆者として大変有難いです。日本では、頻繁に海外美術展の日本展が開かれていますが、本国関係の鑑賞者や筆者には、一部論文の原文掲載のみで済ませています。コロナ禍での開催に、ご苦労も多かったと思いますが、鑑賞者・メディアともよい反響だったようでなによりです。
中城正堯
 |
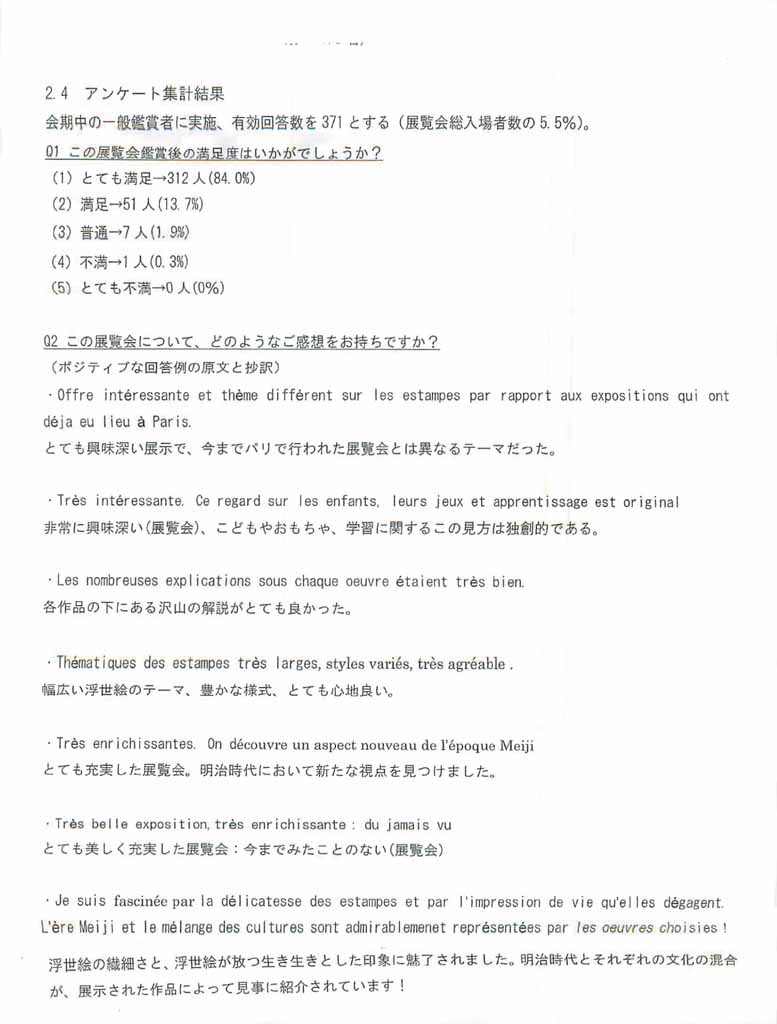 |
|---|---|
 「文明開化の子どもたち」展 PDF版(一括表示・保存・印刷・拡大) |
皆さまが読みやすいよう原文(WORD文)をpdf変換して添付しました。プラウザによっては開けない場合もありますが、その場合、画像の上にマウスポインターを置き、右(中指)クリックしてダイアログを開き『対象をファイルに保存』を選んで保存し、PDFViewerでご覧下さい(拡大閲覧、印刷できる上、ファイルも小さくて済む)。 |
<同窓生アーティストの近況>
「田島征三アートのぼうけん展」
「いのちのケハイ とわちゃんとシナイモツゴの物語」
「特別展アリス へんてこりん、へんてこりんな世界」
中城正堯(30回) 2022.09.05
 筆者近影 |
|---|
皆様へ
土佐校同窓生の美術・文芸などアーティストの活動を、折に触れてお知らせしてきましたが、その最終回です。田島征三さん(34回生)と、高山宏さん(42回生)関連の展覧会が、下記の通り開催中です。お二人とも『筆山の麓』に登場いただいており、それぞれの分野で日本を代表する人物として活躍中です。
 田島征三アートのぼうけん展 |
|---|
「いのちのケハイ とわちゃんとシナイモツゴの物語」 鉢&田島征三 絵本と木の実の美術館(新潟県十日町市)2022年11月13日まで ℡025ー752ー0066 越後妻有アート トリエンナーレ「大地の芸術祭」の参加作品。田島征三の構成で、鉄の作品による水中生物へのオマージュ。
「特別展アリス へんてこりん、へんてこりんな世界」翻訳監修・高山宏 森アーツセンターギャラリー(東京・六本木)2022年10月10日まで ℡050ー5541ー8600 アリスの世界に精通する高山宏が翻訳監修した<好奇心くすぐる大博覧会>。
小生は、同窓生アーティストの活躍ぶりを折に触れて紹介してきました。狭い知見からの発信でしたが、「こんな素晴らしい同窓生がいたとは」とか、「おかげであの作者のナマの作品に触れることができた」、といった感想をいただきました。しかし、体調に問題を抱え、終了させていただきます。できれば、向陽プレスクラブか筆山会(同窓会)で、どなたか自分なりの発信者が現われることを期待します。
訃報
武市功君(30回生)逝去のお知らせ
中城正堯(30回) 2022.09.30
 |
|---|
新聞部出身で同期の武市功君逝去の知らせが、このほど輝夫人から届きました。「1月29日に心不全で永眠」とのことです。
同君は、土佐中高時代に新聞部・放送部で活躍、社会に出てからはおもに大阪に住み、公文教育研究会副社長として同社を牽引、アメリカ進出などに大きな功績を挙げました。
一人旅を好み、引退後はもっぱら四国八十八か所巡りや、天然記念物巡りを楽しんでいました。
写真は高1時代の新聞部。中列左が武市功、その右・森下睦美(31回)、前列左松木鷹志(30回)、示野貞夫(32回)、後列中城、横山禎夫(30回)。
